
小説『エミリーキャット』第70章・サエリとキヨリ
店へ入ると同時に赤銅のカウベルが三段落ちの立体細工を施した、いかにも年代ものの扉の上でガランガランと大きな音を立てた。
『いらっしゃい』
歳の頃には80前後とおぼしき色ムラの無い、まるで雪のような白髪のマスターがカウンターキッチンの中で白いスープ皿をディッシュクロスで磨いていた。
カーディナル・レッドのエプロンを掛け、髪と同じく真っ白の口髭を生やした痩身のマスターの向かい側でカウンターの上を布巾で拭う70代の半ばほどのひじょうにふくよかな婦人が、客人の入ってきた扉を笑顔で振り返った。
彼女は1日のほぼ終わりで半ば褪せたような化粧の残るその顔に柔和な笑みを浮かべて、こう言った。
『あら、順子ちゃん、
いらっしゃい、久しぶりね、』
『お久しぶりです妙子さん、
今日は旦那と一緒じゃなくてちょっと…友達と一緒に来たんです。』
『あら、お友達?
可愛い人ね、
ここの店の者で私、妙子というの、
よろしくね、
奥に居るのは主人でここのマスターよ、
マスターの名前は……
別に必要ないわね、
ポチとでも呼んどけば』

するとカウンターの中のマスターは鼻先でふふっと笑っているのか笑っていないのか、どっちつかずな吐息混じりのその笑いを老いた咳のようにして漏らした。
『どうも、彩です初めまして』
『はい、マスターのポチです、
よろしく』
それを聴いて彩と順子は共に笑ったがふたりの花やいだ笑い声が店の空気を灯るませるのを感じて、マスターは顔をほころばせると小さく照れたように頭を下げた。

ふたりが店に来たからとヨンマルイチゴーシツは早々に店仕舞いをしてしまった。
妙子は褪せた化粧の名残の下から、いかにも、人の善い、深い笑窪のある笑顔を見せてこう言った。
『今日は貸し切りにしてあげるわ、
順子ちゃん
どうせ開けていたって平日でもあるし、誰も来ないのよ、
私達夫婦ももう歳だしこの頃じゃお店三時や三時半に閉めちゃうこともあるくらいだから』
『じゃあ今日はラッキーだったな』
『順子ちゃんが来ると解っていたら、そりゃあ5時でも開けときますよ、
貴女は私達にとっちゃなんだか娘みたいなものだから、どうせまたサエリンに逢いに来たんでしょう?』
『ええ、それはもちろんなんだけど…。ビリーさん夫妻が大好きだったというカフェ・ロワイヤルも飲みたくて…』
『それとサエリンが大好きだったタルト・タタンね?』
『そう!当たり!』

彩は順子と妙子のまるであらかじめ、決められた台詞のように流麗でスムースなひじょうに仲のよい疑似親子さながらのやりとりに思わず息を飲み、呆然と二人の様子をただ見守り続けた。
『サエリンはタルトタタンでキヨリンはおませだったのかしらね、
ピーチメルバがお気に入りだった…』
と妙子は還らぬ遠い日々を心の中で追うかの如く瞳を閉じ、陶然としてそう言った。

『あんな若くて愛くるしかった女の子達がこんなおばあさんよりずっと先に逝ってしまって…
一体もう何年経つのかしらね…
思い出せないくらいよ』
カウンターやその周囲の席はもう片付けるからこちらのほうがよりリラックス出来るだろうと妙子の気遣いで彩と順子は壁でブースのように仕切られ、奥まった部屋へと通された。
最初まだ店内の雰囲気に慣れない彩が奥の部屋を整える妙子の後ろ姿を遠めに見つめながら廊下の隅で順子に囁くようにこう問うた。
『ねぇサエリンって誰?
キヨリンってのも誰のことなの?』
そう言って怪訝な目つきをしながらも彩は何かを既に光の速度で感知していたが、その癖それが何なのかちゃんと知るのが怖いような想いの中に居た。
彩の中でその奇妙に確信めいた思いだけが、さながら透明なエレベーターの箱が上昇してくる時にその壁面で回るあの巨大な鉄のベアリングのように大きくクルクルと不安な主張をするかのように回り始めるのを彩はただ無力感と共に感じていた。
あるいは狂った操跎輪(そうだりん)のような、不可解な''何か''が彩の中で軸だけは決っしてぶれないものの、車輪だけ外れてどこかへその揺れの勢いで飛んでいってしまいそうなほど左右に狂おしく回り出すのを彼女はどうしても止めることが出来なかった。
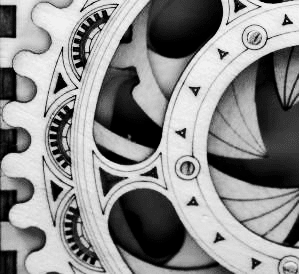
彩はそのいたたまれない不安の回転を打ち消そうとして自らの問いに覆い被せるようにして更に順子にこう問うた。
『ねえ順子さんっ!
サエリとキヨリって一体誰のこと?』
『後で』
と順子はそんな彩の心模様に全く気づかずにさながら節をつけるような愉しげな口調で云うと
『後でね』ともう一度念を押すように言って、にっこりと微笑んだ。
その日の順子は珊瑚朱いろの口紅を淡くつけ、若草いろのセーターとカーディガンのツインセットに紺のスカートと、やや肌色の浅黒くスポーティーな感じのする彼女にそれらはとても映りがよく、
如何にも清楚で春らしかった。
そしてその笑顔は以前逢った時よりずっと若々しく見えるように彩は感じた。

テーブルの用意が整えられ通されたブース状の室内の中央には木目のはっきりとした楕円形の大きなテーブルがあり、その両脇には椅子が6脚もあった。
簡素ではあるがシャンデリアが黄褐色の暖かみのある光を充満させ、クリームいろの壁には大きな刷毛でざっくりと掃いた跡のように見える柄があり、彩はそれを見て自分のマンションの寝室をふと想起した。
そして部屋へ入るとすぐ正面のそのクリームいろの壁の続きに少女時代のエミリーと少女というよりも童女のアデルとが抱き合う絵がシンプルな真珠いろの光沢を放つ白銀(しらがね)の塗装の額縁に入れられ、飾られてあるのを目の当たりにして彩は思わず呼吸を止めて絵の前で棒立ちとなった。
『…エミリー…!』
と彩は思わず小さく口の中で囁くように彼女を呼んだ。
父親の描いた絵としてではあるものの、彩はいきなり少女のエミリーと出逢った気がして胸の奥が熱く波立つのを感じた。
ひょろっと背の高い少女エミリーはダークで微かに波打つブルネットを片耳に掛け、ちょうどその耳の上に白い薔薇が一輪挿されている。
やや腺病質そうな蒼白い頬に砂糖菓子を思わせる食紅いろの頬紅がやや濃いめにひと刷毛刷かれていることは絵でも鮮やかにそうと判る。
その稚(いとけ)ない唇にも葡萄の古い貴酒を想わせる酷く大人びて、どこか黒薔薇や濃紫のチューリップにも似たダークなルージュがややぞんざいに引かれ、全体的にそれらはとても技巧的な化粧とはいえないものの、
かえってそのことが彼女の幼ない中にも内から滲み出る無自覚で未分化な色香を際立たせ凄艶にすら見せていた。
特に妹アデルの頭に隠れて遠く見えにくいほうの右の碧い瞳が、
鋭く陰の奥から揺れ動くような妖しい光を見せ、彩はその絵の中でまだ自分が知らないエミリーの断片を見たような気がした。
観る者によっては一抹の居心地の悪さや不穏さすら感じ兼ねない昏い臨場感にあふれたその絵の中のエミリーは彩をまるで
『あなた達なんかわたしは知らない』
といったような不敵な顏(かんばせ)で、その絵の中のエミリーのあまりにも強い射るような視線に彩は一瞬たじろぎ、思わずこの絵はビリー・ダルトンが描いたものなのであろうか?
と本気で疑った。
そんなエミリーの薄く、か細い胴体に抱きつく幼ない妹の小さな金髪の頭の上に彼女は頬を当て、顔を半分伏せている。
うっとりと瞳を閉じているどこか長閑(のどか)な様子の妹と違ってエミリーは鳶色のほうの左眼を薄くこちらに向け、
まるで何かを問うように一見鎮かな表情で弓を張るような強靭なその眼差しをひたすらに、
まるで永遠に思われるかのように投げかけてくる。
少女とはいえ、絵の中のエミリーはまるで見る者に挑むような視線を放つのを見て彩は何故か背中にじんわりと冷や汗が一条(ひとすじ)流れるのを感じた。
幼ない姉妹ふたりは共に華美な振り袖をゆるく纏(まと)うように酷くしどけない着付けをしており、
共に巻いた舞妓のようなだらりの帯も金糸が濡れたような光の滴をその輪郭に沿い滑らかに放って見える。
エミリーは少しだけ緩く巻いた髪ではあるものの薔薇を挿す以外髪にはなんら装飾は施されてはいないが、アデルは淡いブロンドをソワレに出る貴婦人のようにうなじ近くで髷結いにしてその豊かな明色の髪は薔薇の花芯のようにアデルの首筋で端正な渦を巻いて在る。

耳たぶには金色の房のついた長々しいイヤリングが花車(きゃしゃ)なその肩にまで垂れかかり、丹念に結われた髪には銀色の鏡の破片を繋ぎ合わせたようにヒラヒラ揺れるチリ髪(かん)挿しをつけ、更には藤の花がだらりと垂れ下がる舞妓が初夏につける髪挿しを挿し、
かなり凝った髪の容(かたち)となっていたが逆にアデルは化粧のほうは全くしていなかった。
ふたりの互いの躰に巻き付けられた小さな白い人形のような手にはおのおの、エミリーは白い桜草を、アデルは花でなく金赤に輝く舞い扇を握っている。
『…美しいでしょう?
少女像なのに余りにも妖艶過ぎて
こちらを見ているエミリーちゃんの眼差しが私達の何もかもを見透かしているようで…
少し怖い感じも否めないけれど…
でも美しいことに変わりはないわ』
と妙子はしみじみとその絵を見上げて何故か諦観するような口調となって言った。

『是非買わせて欲しいとこの絵を熱望する人もいるんだけど…
これだけは譲れませんとはっきり断言してあるの、
だってこれまで譲ってしまったら…
ダルトン・ファミリーとの大切な思い出が本当に…
薄くなってしまいそうで…』
『これ…ダルトンの作品ですよね?』と彩は怖々試問した。
『ええそう』
と妙子は絵を見たまま微動だにせず、そう答えたが彩にはふと何故か妙子が本当のことを言っていないような気がした。
『エミリーと…
妹のアデルですね?』
ともう一度彩は念を押すように訊ねた。
『そうサエリンとキヨリンよ』
と妙子は絵から視線を彩へ移すとどこか無感情にそう答えた。
『サエリンとキヨリンてこのふたりのことですか?』
と更に彩は試問に試問を重ねるように訊いた。
妙子は、何故か瞳を強く輝かせ、
意欲的な質問を次々投げかける彩を見て、ふと勘づいたような視線を順子に向かって目知らせするように滑らせるとこう問うた。
『順子ちゃん、彼女は…
もしかして…サエリちゃんと…
その…』
とその先の言葉を一瞬、発してよいものか逡巡していた妙子はとうとう覚悟を決めたかのようにこう言った。
『逢った人なの?』


順子は黙って妙子の眼を見つめたまま深く頷くと、彩に向かってこう言った。
『彩さん、サエリというのはね、
エミリーさんの日本名よ、
エミリー・サエリ・キーティング、
表向きはガートルード・ダルトンだったけど』
『じゃあ…アデルはキヨリ?』
『そう』
順子は鎮かに頷いた。
『ふたりともどういう字を書くの?』順子がバッグから手帖を取り出すと、ボールペンでその何も書いていない頁をめくるとこう書いて見せた。
冴琳(さえり)
聖琳(きより)

『これでサエリ・キヨリと読むの?
サエリン・キヨリンと読んでしまいそうね』
と彩が順子に云うと妙子が答えた。
『でしょう?
多分当て字なんでしょうけどね、
日本名の名づけ親は母親の美世子さんだと聴いているけどいい名前だと思うわ、』
『でもだから渾名でサエリンとかキヨリンとか呼ばれていたのよね?』
と順子。
『そうね、
だってそう読めちゃうもの、
とはいえふたりの日本名を知る人は少なかったからそう呼ぶ人達は私達を含め、ほんの一握りでしかなかったけど…』
と答えながら妙子はマスターが持ってきたふたりぶんのカフェロワイヤルのコーヒーカップを彩と順子の前のテーブルへと置いた。
カップの上へカフェロワイヤル専用の特別な黄金(きん)いろのスプーンが横一文字に橋渡された。
スプーンの先端に僅かに突き出した小さな長方型の部分がカップの覆輪の上に落下しないよう掛かっていた。
そしてそのスプーンの上には角砂糖が乗せられ、マスターの手によりブランデーがその上からほんのりとふりかけられ、そのブランデーに濡れた角砂糖の上にマスターはマッチを擦って、
火を点けた。

妙子がそれと同時に室の照明灯を落とし、暗闇の中で黄金(きん)のスプーンの上で燃える角砂糖の焔は一瞬、春雷の如く青い焔となって細長く揺らいで立ち上がったが、妙子に勧められて彩と順子は焔を乗せた角砂糖を珈琲の中へスプーンごとそっと沈めた。

室の照明はもとに戻り、彩はそのカフェロワイヤルをひとくち飲むとまだ胸騒ぎの収まらない気持ちを抑えてこう尋ねた。
『ダルトン一家…
いえ、キーティング一家と妙子さん達はどうして親しくなさっていたんですか?
何か特別な切っ掛けでも?』
『いいえ、
まぁ特別というか…
ビリーさんと美世子さんがお若い頃、通っていたテニスクラブでよく私達ふたりも時々ご一緒することがあってね、
一緒に夫婦でダブルスの試合をさせてもらうこともあったくらい、親しくなれたのはそれが切っ掛けかしらね、
そのうちおふたりはうちの店へも来てくれるようになって…』
『そうだったんですか…』
と彩は遠い過去とはいえ、そんな些細で日常的な話題に触れて波立つような不安な胸の中が次第に凪いでゆくのを感じて小さく隠すような吐息をついた。
『うちへ来てくれるようになってしばらくして私達はビリーさんがあのウィリアム・C・ダルトンだと知って酷く驚いたものよ、
当時はカフェ兼小さなギャラリーで…私達夫婦が趣味で蒐(あつ)めた様々な画家達の作品を飾っているだけの画廊とも云えぬ程度の画廊でしかなくて…』
と妙子は磨き立てたテーブルの上に映る絵の中の抱き合う幼い姉妹の面影に想いを馳せるように小声で呟くように話し始めた。
『でもビリーさん夫妻と親しくなるにつれビリーさんが友情の紋(しる)しにと幾つか初期の頃の油絵や版画を私達夫妻に贈ってくださるようになって…
私達はそれらを店内に展示することにしたの、
お茶を飲みながら沢山の人達が世界の画家のリトグラフやエッチングと共にビリー・ダルトンの絵を観れるだなんてこんな贅沢な空間は他には無いと私達はとても誇りに思っていたわ、』

『現にビリー・ダルトン自身も時々来るんだもの、ファンにしてみればここは憧れの場であり、絵も含めてすべてが垂涎ものであったんだと思うわ』
と順子が後づけた。
『ダルトン、いえキーティング夫妻がおふたりで時々訪れるようになって暫くすると店を夜、ディナーの為の貸し切りにして愛娘達ふたりを呼び寄せるようになったの、初めて逢ったエミリーちゃんはそりゃあ、神秘的な少女だったわ、話すと意外なほどお茶目で可愛らしいんだけど黙っていたら話しかけるのが躊躇われるような特有のミステリアスさがあって…
妹のアディちゃんはただただ明朗活発で愛らしくて人懐っこいんだけど…

エミリーちゃんは自分だけの世界を人知れず守っているように見えたの、話しかけるとまるでそれが壊れてしまいそうで…
ちょっと話しかけづらいような…ね…?』

ふたりの前に次いでタルト・タタンを乗せた皿が二つ運ばれ彩はブランデーに浸け込まれた半透明の林檎の薄切りが乗ったガーネットと琥珀の中間のような色味のタルトの表面にフォークを切るように差し入れた。
『子供の頃のエミリーを知っていらっしゃるんですね』
と彩は口の中でコニャックとダーク・ラムの香りが広がるタルトの風味が鼻から抜けてゆく感覚を楽しみながら、それでもどこか遠くで疼くような裏淋しい声を出して言った。
『…羨ましいわ…』
その頃のエミリーともし出逢えていたならもっと早くもっと長く親しくなれたであろうにと彩は切実に思った。

『でも彩さん、貴女も順子さんと同じでエミリーキャット族なんでしょう?』
とまるで今度は妙子が試問する口調となった。
『エミリーキャット族だなんて…
確かにエミリーとは出逢いましたけど…』
と言いつつ彩は順子に向かって目知らせで''妙子さんはあのことを知っているのか?”と問うた。
『妙子さんに二年前くらいについほろ酔いついでに私、あの森でのことを話してしまったの、
でも妙子さんは信じてくれたわ、
マスターもね』
と順子はさながらヨンマルイチゴーシツがフリーメイソンじみた場所でもあるかのような錯覚を彩に起こさせる妙に静かで慎重げな声を出して辺りに誰もその話を聴く者は居ないのにそっと周囲に一瞬眼を光らせるのを見て奇妙な心地がした。

その奇妙な心地とは、まるで何か犯罪か、あるいは秘密であることは間違いはないが何か特有の魔教のような学問をこの人達と共に分かち合い、同時に隠蔽しているかのようなそんな感覚だった。
その感覚は不条理であると共に彩にとって避け難い生理のような何かであり、彩もまた彼らと同じようにその対象の輪郭が曖昧なまま、隠したくなるような奇妙で説明のつかない焦燥感と同時に強い連帯感をも感じた。

『昔からエミリーちゃんやそのご家族が亡くなってからもああいったオカルトめいた噂がつきまとっていたから…まさかとは思っていたけど…順子ちゃんからその話を聴いて…私達はようやくそれが信じられたの、ああ、エミリーちゃんの魂はまだ今はもう無いあのビューティフル・ワールドの跡で迷って…残り続けているのかもしれないって』

『…迷って…』
と彩は思わず妙子の言ったことを口の中で小さく繰り返した。
そして心の中で小さく、しかし同時に大きく抗うようにこう叫んでいた。
『…みんなそう言うのね…
…でも違う!
そんなんじゃない!』


しかしながら『ねえ彩さん、彩さんの逢ったサエリちゃんは一体どんな様子だった?
元気にしてた?』
と問う妙子の口調はまるで長年出逢えていない親戚の姪か何かを気遣うような、あるいは懐かしむような、
それはさながら生きて現存する人に対するのと何ら変わらぬ然り気無い、
そして強い郷愁を含んだ口調だった。

エミリーキャットと呼ばれる世界に属する人々はこんな風に彼岸と此岸の境界線がどこか曖昧となってそのことを奇異とは感じずに時に忙殺され、時に急に空いた空隙を視るように閑居ともなり、かと思えばまた気ぜわしい社会生活を営み始める波の中に揺られながらその現実に眩惑されても決して酔わずに泳ぎ抜く魚のようにタフに秘密を共有して生きている人々なのかもしれないと彩は思った。
が、次の瞬間彩は気づいた。
自分も今や秘めたるその世界に属す、入り口の前に立っているのだということに…。

『まぁ…
そうなのかもしれませんね…』
と彩は言葉を選びながらも答えに少しばかり窮したせいもあり、
こんな風に答えてしまった。
『私は少ししか逢っていないので…
エミリーキャット族とは云えないかも』するとそのことにさして頓着しない様子の妙子が急に意外なことを語り始めた。
『エミリーキャット族ってね、
ファンの間で造語のようになって濫用されていた言葉だったけど…
本来はエミリーの亡霊に逢った人達という意味では最初は使われてなかったのよ、
もともとは彼女の愛猫のロイの血を引く猫達の血脈が連綿と受け継がれ、
その子孫の猫達が日本中へ貰われてゆき、養子のようにされていったことから出来た言葉だったの、
つまりエミリーの猫達という意味ね』
『ロイの子孫?』

『そうよ、ロイの血を絶やしたくないと思ったエミリーさんが他所から貰い受けた猫と掛け合わせてその血を引く子孫を飼い続けたのを、養子にして貰い受けた人々が当時はまるであの有名なアーネスト・ヘミングウェイのパパズ・キャットの如く日本中に沢山いたのよ、私達夫婦もそのうちの一人でロイによく似た…でもロイと違って短毛の仔猫を貰って大切に育てたのよ、
颯太(ふうた)といってね、
そりゃあ、子供のいない私達夫婦の可愛い子供代わりとなってくれたわ、
二十歳まで生きて老衰で亡くなるまで美しくて賢い彼は本当に私達の誇りだった…』
『そうなんですね』
と彩は羨望に堪えるような声を思わず出して言った。

『最初、ファンの間ではダルトン・キャットとかビリー・ザ・キャットとか巫山戯(ふざけ)て呼ばれていたものの…猫の繁殖はエミリーさんの発案であることとロイはエミリーさんの愛猫でもあったことからいつの間にかエミリーズ・キャットと呼ばれるようになり…そのうち英語のエミリーの、という意味のSがいつの間にやら取り去られ、日本人にとって呼び易くて発音のしやすい”エミリーキャット''へと変わっていったの』
『でもエミリーは本名をメディアには伏せていたはずなのに』
と彩が言うと妙子は深く頷くと、こう答えた。
『サエリちゃん達がまだ子供の頃やとても若かった時代はそうだったけどね、成長と共に本名を伏せ続けることがだんだん不自由になっていったんだと思うわ、
サエリちゃんはずっとではなかったけどお勤めもしていたことだしね、まさか偽名のガートルード・ダルトンで会社勤めは出来ないでしょう?』
『でも学校ですら偽名で通せたのに?』と彩が言うと『ダルトンという性はね、
ある意味偽名であってそうではなかったの、
ビリーさんは本当はアイルランド人で英国への養子だった、
ダルトンというのはその時の継父母のサー・ネームだったから…。
でも彼は自分が本当はアイルランド人だということを誇りに思っていてアメリカに住む頃には自らアイルランドの本名であるキーティングを私的には名乗っていたらしいの、でも戸籍上では彼はダルトンが本名だったのよ』
『……じゃあ…じゃあ、エミリーは本当はエミリー・ダルトン?ガートルードじゃないのにキーティングではなくエミリー・ダルトン?』彩は混乱して息切れする思いに思わず歯痛に耐える人のようにこめかみを押さえた。
『こんぐらがってしまうわよね』
と妙子がまるで芯から同情するような声を出して言った。
『でもサエリちゃんはいつもこう言っていたわ、
ビリーさんの想いを尊重してきっと敢えてそう言っていたんだと思うけど、”たとえ、戸籍がダルトンでも私の本名はパパの本当の故郷の名のキーティングよ、
だから私はガートルードと呼ばれようがなんと呼ばれようがエミリー・キーティングなのよ”ってね』

『じゃあ”エミリーキャット''って、
私や順子さんのようにエミリーとあの森で逢った人達の総称以外には、
ロイの子孫達である今や日本中に居る猫達のことを指していうんですね?』
と彩は混乱をふりほどいて自分の中の規律を正すために敢えて話頭を戻してそう妙子に問うた。
そうでもしないと頭が変になりそうだと彩は思った。
するとまだ同情を隠せない様子の妙子は彩を案ずるような眼の色を隠さずに頷いた。
『そうなの、
だからエミリーキャットとは厳密にはその猫達の名称ね、
でも今や彩さんの言う通りいろんな意味で使われているみたいで順子ちゃんや彩さんのように亡き後のエミリーちゃんと逢った人達のこともそう呼ぶみたい』
『…そうなんですね…』
と言いながら彩はすっかり冷えたカフェロワイヤルの残りに茫然と口をつけたが急に思い出したようにその唇にどこかなだらかさを含んだ春寒のような微笑みが浮かんだ。
『颯太くんに逢ってみたかったわ、
ロイの血を引く子なら…
さだめし美しい猫だったでしょうね』
『そうね、
とても賢くて愛らしい…
ロイを短毛にして…
もう少しとっつきやすく陽気で、フレンドリーな感じにした子だったわ、
とてもひょうきん者のお茶目さんでね、

残念ながら天に召されてそろそろ…10年にもなるけれど…
でも大往生だったわね、
雄なのに病気ひとつせず二十年生きたんですもの、
さすがはロイの子ね、
ロイもとても強くて長寿な猫だったから、』
『そうですか…』
『でも颯太はラグドールと日本猫のミックスの雌猫と晩年掛け合わせてね、最後の子孫を十八歳で9頭も残したわ、
そのもっと前も数回颯太は子孫を残してこの世に送り出したけど…
最後の子供達のうちのひとりは、
エミリーさんの最期を看取った美術評論家である鷹柳貞男さんが、絶対大切に育てるからといって貰い受けて行ったわ、
いずれはよその猫とかけて増やすんだと言ってね、
だから今もその子は鷹柳さんの家にはまだ元気で居るのよ、』

『えっ…!?鷹柳?鷹柳って…
あの…』
鷹柳教授??
と彩はその先の言葉が急にまるで忌諱に触れるかの如く言えなくなった。

すると背後でふいにあの赤銅のドアベルがガランゴロンと鳴り、
マスターがカウンターの中から客人に声をかけるその言葉が聴くとも無しに彩の耳に飛び込むようにして聴こえてきた。
『おや、鷹柳さん、
おひさしぶり、
エミリーちゃんのお墓参りの帰りですか?』



to be continued…
