
巫蠱(ふこ)第六巻【小説】
▼之墓簪③

自分は妹に「姉さん心配してたよ」とうそをついた。
妹たちは姉から大切に思われていないことを分かっていた。
なんとなく、その「姉さん」は一人称のつもりでもあった。
でも館(むろつみ)にとって自分はただの「お姉ちゃん」でしかない。
「わたしは長女になれない」
▼楼塔是と之墓簪①

簪(かんざし)は是(ぜ)とその門下生の稽古を見学しつつ考えていた。
自分と他人、どちらが装飾品なのだろうと。
その明るさは真実でも、かざりからでた光をこえない。
蓍(めどぎ)から家出をうたがわれ、離為火(りいか)にはさびしさを見抜かれた。
「武具じゃない、武具じゃない……」
▼之墓諱と簪①

案の定、是(ぜ)は館(むろつみ)の絵をあずかっていた。
簪(かんざし)はそれらを受け取り、赤泉院(せきせんいん)経由で之墓(のはか)にもどった。
おかえりなさいと諱(いみな)が言う。これまでに館からもらった絵、そのうちの数枚をかさね、つまぐりながら。
ぱらぱらと色がみえる。灰色ばかりを集めたようだ。
▼之墓諱②

之墓諱(のはかいみな)は、すわらない。
その地には、いすに似た形状の岩がひとつある。
灰色のまだら模様。ひじかけも備える。
台座に立ってみれば、うしろの背もたれがどんな人間よりも高いことが分かるだろう。
之墓の長女はそこに立つ。ひとりのときは、背もたれのほうを向いている。
▼之墓諱と簪②
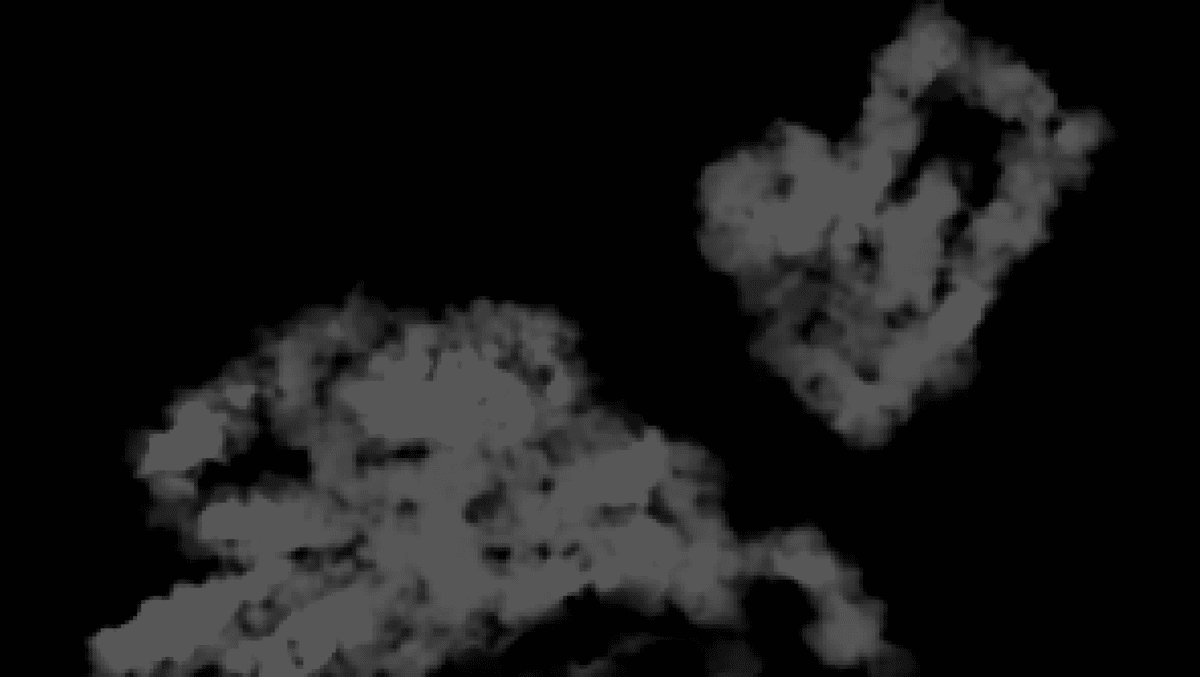
からだを回転させ、諱(いみな)は簪(かんざし)を目にいれる。
かかえている紙束に対して「それなに」と聞かれた簪だったが、妹にことわりもなく新しい絵を見せるわけにはいかないと彼女には思われたので、かるく笑ってごまかした。
「話さなくていいよ、なにもかも」
姉の声は重い。
▼之墓諱と後巫雨陣一媛①

「話しなさい、なにもかも」
そのときとつぜんひびいた言葉は、之墓(のはか)の姉妹のものではなかった。
諱(いみな)は自分の立っているいすのうしろをのぞきこむ。ちょうど背もたれのかげになっているところだ。
そこに後巫雨陣一媛(ごふうじんいちひめ)がよりかかっていた。
▼後巫雨陣一媛②

簪(かんざし)の案じていたとおり、一媛(いちひめ)は諱(いみな)を心配していた。
彼女が巫蠱(ふこ)をきらいなことも知っている。
ただ、ほころびの始まりを諱はよろこばないだろう。
なぜなら之墓(のはか)の長女は自分が受け皿であるとも分かっていたから。
そして一媛は、彼女のかくした優しさを、信じてもいた。
▼之墓簪と後巫雨陣一媛④

「お姉さん……」
之墓簪(のはかかんざし)は実の姉を「姉さん」と言う一方で、後巫雨陣(ごふうじん)の長女である一媛(いちひめ)を「お姉さん」と呼ぶ。
「離為火(りいか)たちは」
いすのかげからはみでた手に問う。
「まだ、なか。ワタシは諱(いみな)をなぐさめに」
「……うまく言うって言ったよね」
▼之墓諱と簪③

「わざわざ一媛(いちひめ)までくるとはね。なに? 世界でも終わるの?」
「姉さん、世界は終わらない。終わりうるのはわたしたち」
「えっ!」
諱(いみな)は露骨にせきこんで、ふたたび簪(かんざし)のほうを見つめる。
「……へえ、それは、おめでたい。まえから無意味と思ってたし。なくなれなくなれ」
▼之墓諱と後巫雨陣一媛②

「……なんかさあ」
いすのひじかけの片方を左足で踏みながら、けだるげに目をうえにやる諱(いみな)であった。
「みんな御天(みあめ)すごいって言ってるけど、実際そこまでたいしたやつじゃないでしょ、あれ」
「諱にとってはただの友達」
「……そとのやつらも」
「諱はそれでいい」
▼巫女と蠱女⑧

ふたりの会話を耳で追いつつ、やっぱりお姉さんがきてくれてよかったと安心している簪(かんざし)であった。
……そろそろ日がかたむく。
いすの影が伸びてきて、この場に加わる声ふたつ。
「一媛(いちひめ)もいるな」
「みたいですね」
「蓍(めどぎ)さん、げーちゃん」
「筆頭どうも」
「うわ」
▼之墓諱と赤泉院蓍①

「いや人の顔を見るなり『うわ』はない。『うわ』は」
「べつに蓍(めどぎ)に言ったわけじゃ……」
「気にしてないから気にするな」
「なんでここに」
「桃西社(ももにしゃ)にいく途中。あと館(むろつみ)は十我(とが)の家」
「ふーん……」
「絵をかいてる。おまえらマジで果報者だな」
▼之墓簪と赤泉院蓍③

……例のいすからちょっとはなれたところに之墓(のはか)の姉妹は居をかまえる。
立ったままねむる諱(いみな)を横目に簪(かんざし)がささやく。
「蓍(めどぎ)さんはわたしが姉さんから逃げると思ってたの」
「だから館(むろつみ)におまえへの礼をことづけた」
「そうだね。ほんとは逃げてたとこなのさ」
▼之墓簪と館③

六日目の朝。
目を覚ました簪(かんざし)は、そばに妹がいるのをみとめた。
「……むろつみが、ぜーちゃんにあずけてたやつ、回収したから」
「ありがとうお姉ちゃん。それと蓍(めどぎ)お姉ちゃんと鯨歯(げいは)お姉ちゃんからもありがとうって」
「ふたりは」
「もう、たったよ」
「早いね」
▼桃西社阿国①

……桃西社阿国(ももにしゃあぐに)は浮かんでいた。
立ち泳ぎに近い格好である。
ちょうど彼女のわきのあたりに水面がくる。水底に足はついていない。
赤泉院(せきせんいん)の泉よりも深く楼塔(ろうとう)の露天風呂よりも広く水をたたえた湖に、阿国はずっとつかっている。
▼桃西社①

桃西社(ももにしゃ)には陸地がない。とはいえ巫蠱(ふこ)はそこを土地とも地域とも言う。すなわち湖全体をひとつの地とみなす。
ちなみに刃域(じんいき)の巫女(ふじょ)がやってくるときは、氷の張った時期である。
そして実質的に桃西社をまもるのは、長女でも次女でもなく。
▼桃西社鯨歯と阿国①

……之墓(のはか)と桃西社(ももにしゃ)との境目、すなわち湖のなぎさにて鯨歯(げいは)はしゃがんだ。
両手の指で水面を三度つつく。
一回目はつよく、二回目三回目はよわく。
生まれた波紋は大きくなるとともにゆるやかさを増し、水面をゆっくりすべっていき、阿国(あぐに)のわきにふれた。
▼桃西社鯨歯と阿国②

身をふるわせたあと立ち泳ぎのまま波紋の発生源まで向かう阿国(あぐに)であった。
「聞いてっからね、くじら姉(ねえ)。きのう『あなた』がきたからね」
それぞれ鯨歯(げいは)と岐美(きみ)のことである。
「案の定やんね。で、ここに異変はあんの」
鯨歯は姉妹に対しては敬語ではない。
▼赤泉院蓍と桃西社阿国①

「なあんにも。かわらず波が立ってるだけ」
「阿国(あぐに)」
蓍(めどぎ)が姉妹の会話に加わる。
「なん、ぜーちくさん」
「最近、皇(すべら)見た?」
「……いや、見てはないやね」
「ふるえは?」
「どうなんやろ、それらしいのはあったような。とても繊細な波が……」
▼巫女たち②

阿国(あぐに)の返答にうなずいた蓍(めどぎ)は、話を切り替える。
「はいっていい?」
鯨歯(げいは)が苦笑いしている。それで阿国は察した。
「どぞ」
「ありがと。ここんとこずっと歩いて、しかも瞑想もろくにできず、こう息が続くとな、こうでもしなきゃやってらんない」
そして、あたまから湖に。
▼赤泉院蓍⑤

何人積み上がってもたりない深さ。
ましてや巫女(ふじょ)のひとりなど、かんたんに飲み込んでしまうだろう。
衣装に水をしみこませ、蓍(めどぎ)はそのまま落ちていく。
手足のみならず全身をせわしくうごかして、比較的浅い部分のそこに達する。
鼻を土にあて、瞑想に移る。
▼赤泉院蓍⑥

その瞑想は一瞬だった。だが筆頭巫女(ひっとうふじょ)には必要なものだった。
もう息が切れそうだ。今度は水上に向かって全身を泳がせる。
くちをつぐんだまま、光にもどる。
波紋はあった。あぶくはなかった。
あたまが湖から浮かぶ。
彼女はくちを天にやり、あらげた息を何度もはいた。
▼赤泉院蓍と桃西社阿国②
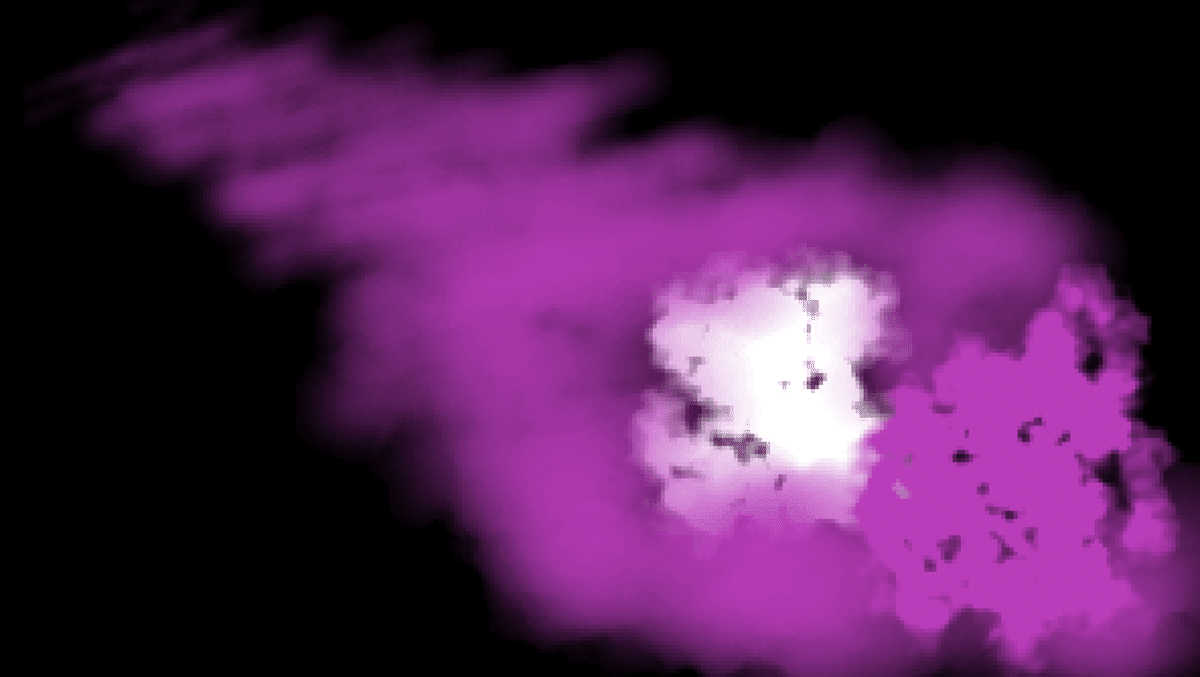
「ぜーちくさん、だいじょうぶなん」
近寄ってきた阿国(あぐに)へと、蓍(めどぎ)は首をややかたむける。
「思いっきりすっきりした」
「おつかれさまやんね」
彼女の息がやわらぐまで、しばらく時間をおく。
「……さて阿国。桃西社(ももにしゃ)でいちばん深い場所はどこ」
「西」
▼巫女たち③

「おまえその場所にもぐれる?」
「むりやけど、くじら姉なら」
「鯨歯(げいは)って、そこまでしずんだことあったのか」
蓍(めどぎ)が陸地の人影に向かって呼びかけると、之墓(のはか)の土に貼り付いたままの彼女から返事がきた。
「ないですよ、筆頭。でも、いけると思います」
▼桃西社鯨歯③

桃西社(ももにしゃ)の西端は楼塔(ろうとう)との境目である。
巫女(ふじょ)たち三人が泳ぎ着いたころには、夕方が終わりかけていた。
日没と同時に鯨歯(げいは)がもぐる。からだをまるめず、手足を伸ばし、無数の泡をたてながら。
身をうねらせ、ぐんぐんと、闇を深める。
(つづく)
▽次の話(第七巻)を読む
▽前の話(第五巻)を読む
▽小説「巫蠱」まとめ(随時更新)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
