
巫蠱(ふこ)第十六巻【小説】
▼そとの人間⑤
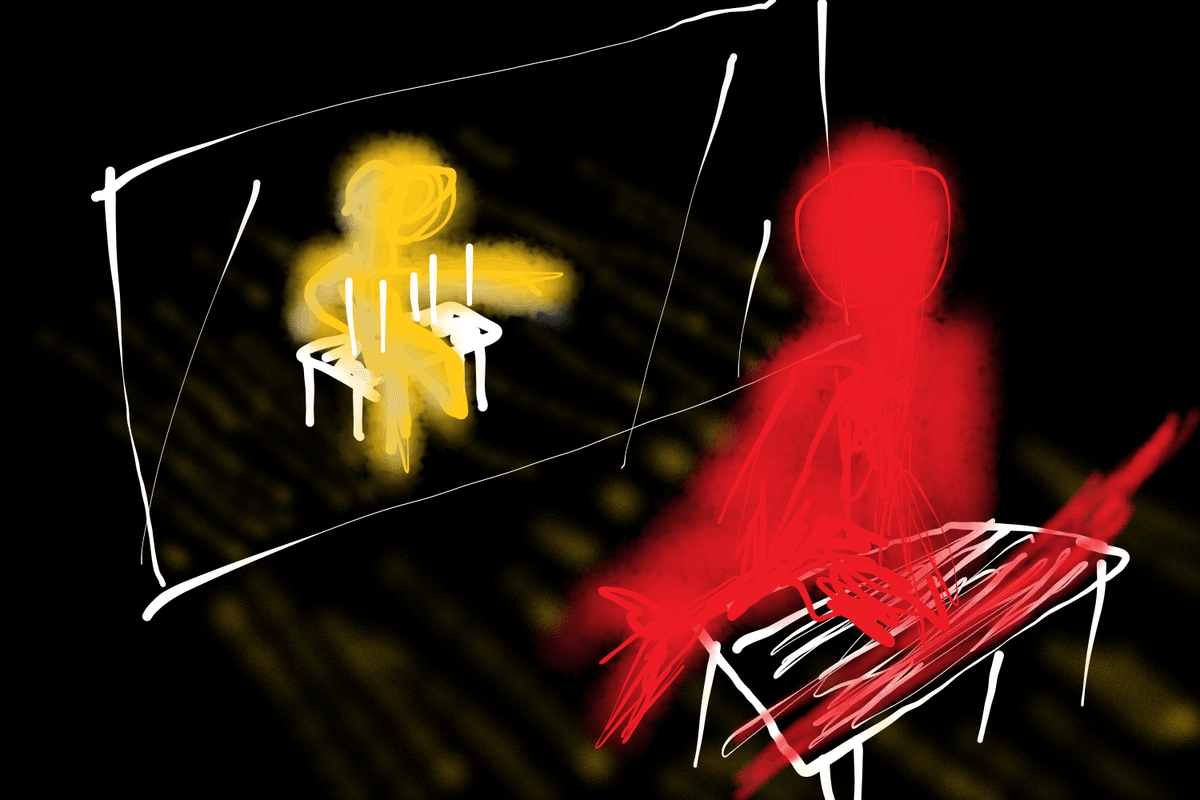
用意されていた椅子に旅人がすわると、壁の向こうにいる人も自分の席に着いた。
「まずコウさん、あなたは偽名を使っていますか」
「よく分かりましたね」
「全員に同じ質問をしているだけです」
透明な壁に細長いすきまが縦にいくつかあけられているので、声は伝わる。
▼そとの人間⑥

「越境の目的は」
「人さがしです」
「普段は、なにを」
「組織の代表を」
「生年月日は」
「わたしの故郷には誕生日の概念を捨てる風習があります」
「最近の国際間の緊張についてどう思います」
「なにも思いません」
「あなたの愛する国を教えてください」
「ありません」
▼そとの人間⑦

「最後の質問です。あなたが現在持っているものは、なんですか」
「かさです」
実際に旅人は待合所にいたときからずっとそれを自分の近くに置いていた。よごれも濡れもない状態でたたみ、いまは椅子の座面に寝かせている。
「いつ雨がふるかも分かりませんので」
▼そとの人間⑧
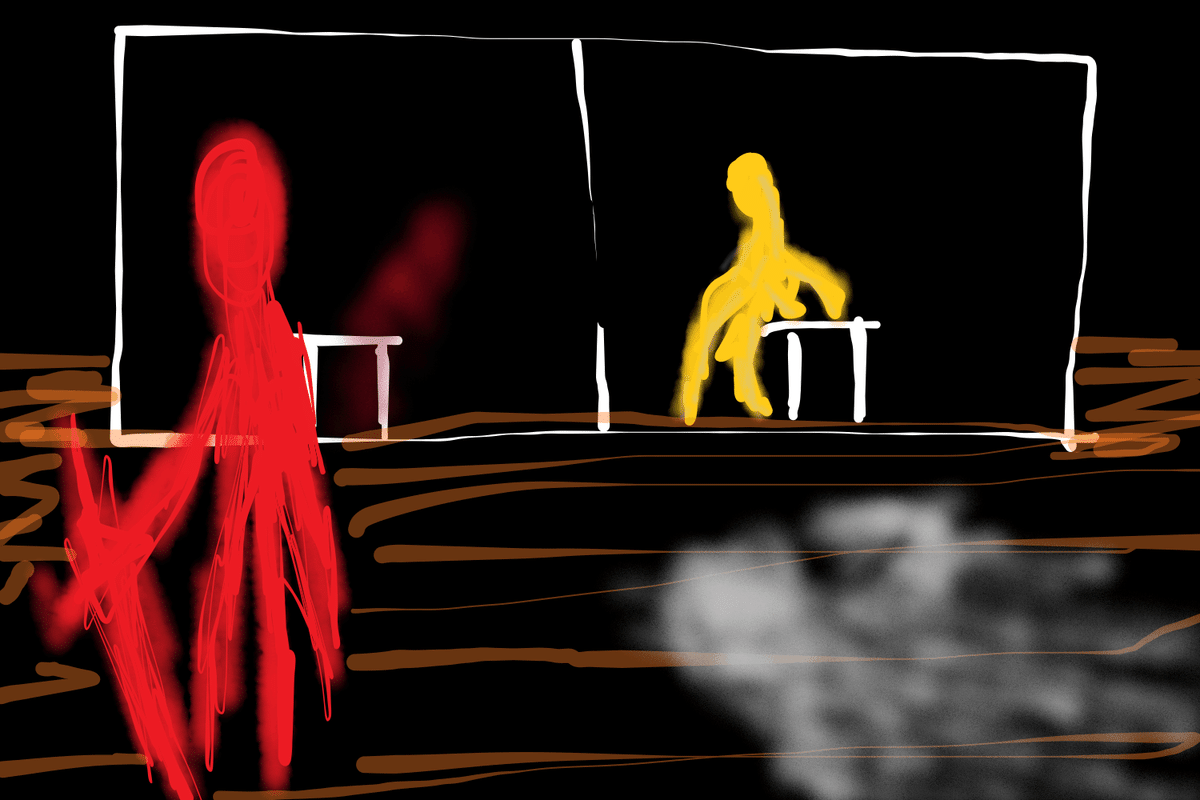
壁の向こうの質問者は表情を変えず、うなずいた。
「わたしからの検査は以上です。おつかれさまでした。偽名の件は追及しませんので、ご安心を」
対して旅人は立ち上がり、軽く礼をし、その部屋をあとにした。
そとに控えていた兵に案内され、次は所持品検査を受ける。
▼そとの人間⑨

旅人の荷物は少なかった。一本のかさのほかは、ほとんど着の身着のままであった。危険物を隠し持つ余地はないということで、所持品検査はすぐに終わった。
これで、国境通過の許可が出た。
「まあ向こうの国でも検査があると思いますが」
兵のひとりが申し訳なさそうに言う。
▼そとの世界⑥
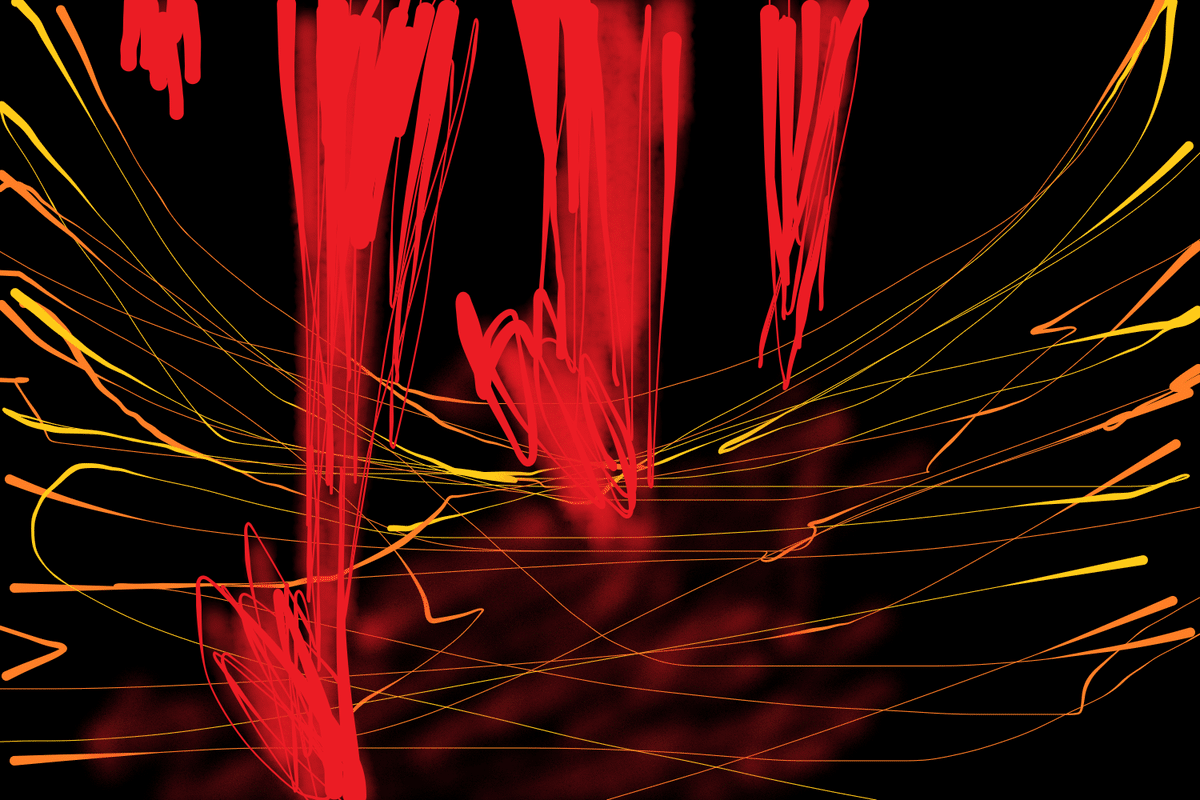
太陽の位置を見る限り、いまは正午過ぎのようだ。このあと類似の検査を受けても日暮れまでには間に合うだろう。
そう旅人は判断し、国境をまたいだ。
しかし国境線がどこに引かれているのか分からなかった。あるいはその線を踏んづけたのかもしれないが、とくになにも感じない。
▼そとの世界⑦

国境線上にあるのは小石と雑草。別の場所では街道の石畳も確認できるだろう。
最近まで両国の仲が良好であったせいか、壁はない。
緊張状態に入ってからも軽い柵さえ設けない。たがいに相手国を刺激したくないのだ。
一方で兵たちが肉眼でにらみ合う状況は続いている。
▼そとの世界⑧

そういった、なんとも言えない視線が多く交差するなかで、旅人は国境を越えなければならなかった。
ただ、彼女が次の足を踏み出そうとしたときだ。
前方にいたひとりの兵が、急に震えた。彼は自身の頭頂部をなでたあと、そらを見上げた。
雲ひとつない、快晴であった。
▼そとの人間⑩

どうやら晴れ渡った上空から雨粒が落ちてきたらしい。
旅人の前方にいる兵たちは、それを「天気雨」と言った。
一方、うしろからは「狐の嫁入り」という声があがった。
落ちたのは一粒だけではない。旅人のうなじにも当たった。二粒……三粒……まだまだ、ふってくる。
▼そとの世界⑨
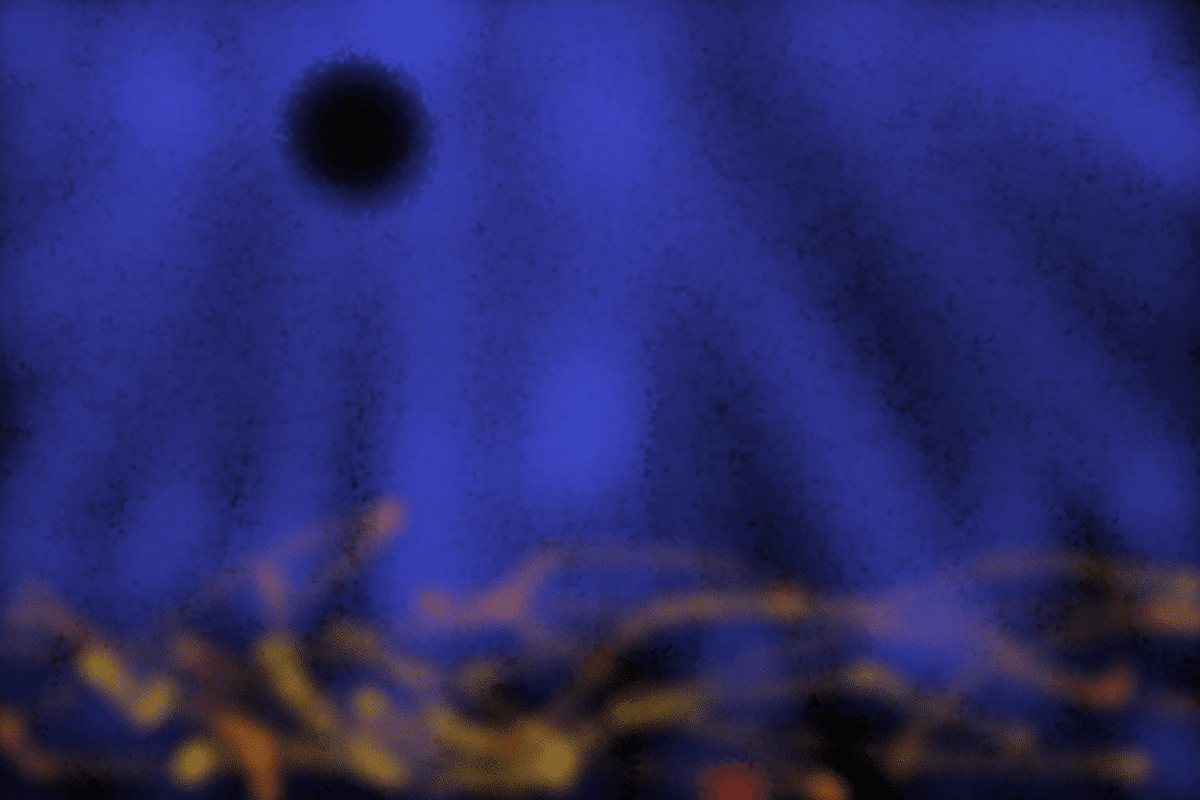
土砂降りになった。もはや「天気雨」ないしは「狐の嫁入り」の降水量ではない。
兵たちも、旅人以外に国境の通行を許可された者たちも、あわてふためく。
急に雨雲が発生したわけでもない。人々の頭上に浮かぶのは太陽のみ。まるで青天が、雨を落としているかのようだ。
▼そとの人間⑪

平静を取り戻した兵たちが、雨宿りできる場所に一般人を誘導する。旅人もそれに従う。
ここで誰かが叫んだ。
「御天(みあめ)さま!」
雨音にかき消されることなく、はっきり耳に届く声。その絶叫に、みなの表情が青ざめ、くもる。
「まさか『彼女』が本当に……」
▼宍中御天①
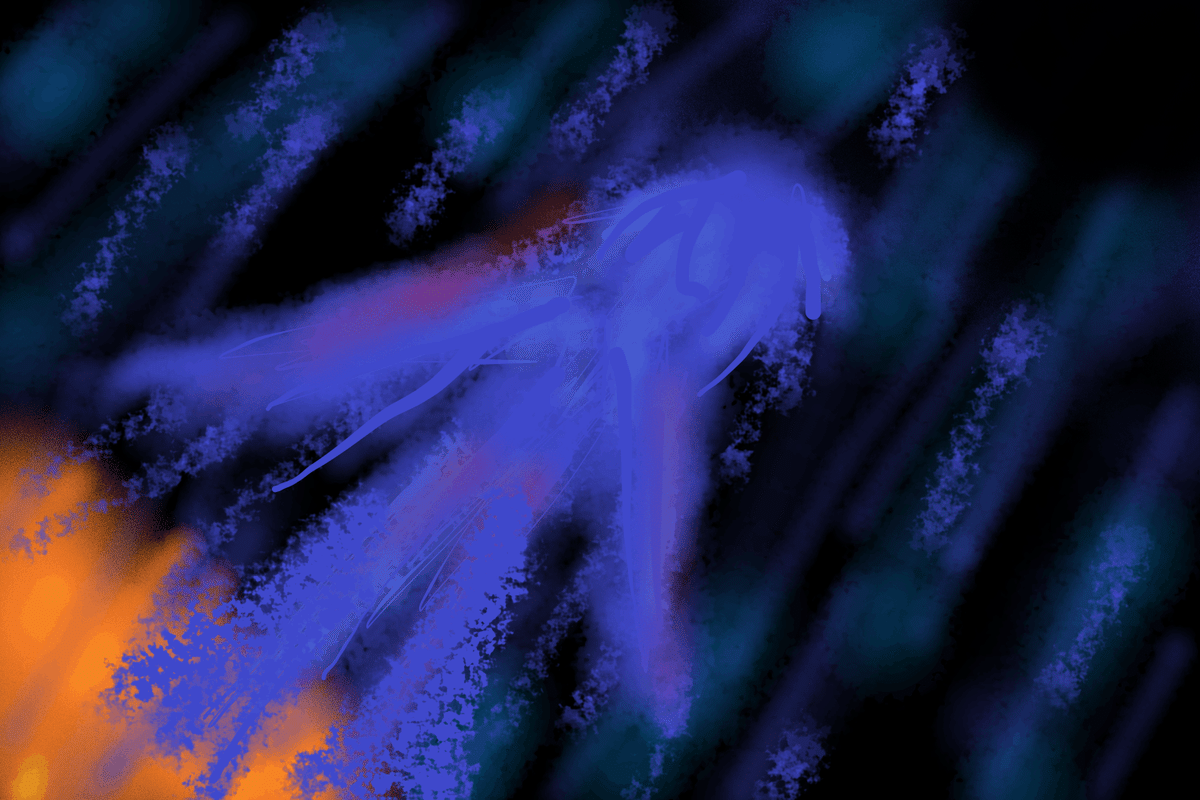
決まって彼女は戦争のまえに現れる。雲なき雨をふらせ、人々を惑わすという。存在自体が凶兆と思われている。
御天(みあめ)という名は昔から忌避されてきた。その世界で言う「狐の嫁入り」は彼女の影を隠すための言葉でもある。
なお当代の御天が何代目かは分からない。
▼そとの人間⑫

★分岐点⇒[ありえないと思われる選択]
……その忌むべき名を響かせる絶叫を聞いて、避難の列から外れる一般人がひとり。
かさを持った例の旅人である。
避難誘導する兵に謝ったかと思うと、みなの制止の言葉も聞かずに声の発生したほうに走りだした。
ひとり立ちつくしている叫び声のぬしに駆け寄り、かさを広げる。
▼そとの人間⑬

旅人は「だいじょうぶですか」とか「落ち着いてください」とか、そんな声かけをしなかった。かさを相手の頭上に突き出したまま、「商人さん」とぽつりと言った。そして続ける。
「彼女の顔でも見ましたか」
相手は一瞬だけ間を置いて言葉を返す。
「いいえ、旅人さん」
▼そとの人間⑭

棒立ちになっている彼を旅人は知っていた。きょうの午前に会話した商人だ。声を覚えていた。顔も記憶していた。名前は忘れたので、「商人さん」と呼びかけた。
彼も旅人のことを思い出したようで、やや表情を緩めてつぶやく。
「わたしは御天(みあめ)さまの顔を知りません」
▼そとの人間⑮

「彼女の名を叫んだ理由は単純です。『そこにいる』と思われたからです」
「なるほど、この天気ですからね」
澄みきった青空のもと、まだ土砂降りは、やみそうにない。
「旅人さん、あなたですか」
「はい、わたしは旅人です」
「……あなたが御天(みあめ)さまなんでしょう」
▼そとの人間⑯

「思い込みですよ、商人さん。わたしはあなたの呼びかけに応じてここに来たのではありません。聞き覚えのある声が耳に入ったから気になっただけです」
旅人は首をまわして、うしろを見る。
「ともあれ、雨宿りしましょうか」
人の影がふたつ、雨にまぎれて近づいてくる。
▼そとの人間⑰

人影の正体は、この天候のなか避難誘導をおこなっていた兵たちだった。
商人と旅人は彼等についていく。案内されたのは、やや大きめの頑丈そうな建物。兵の屯所のひとつを避難場所として開放したらしい。
その屋根のしたに入ったところで、迷惑をかけたと商人が詫びた。
▼そとの人間⑱

例の名を声高に叫んだこと。異常な土砂降りのもと避難もせず旅人と兵たちに余計な手間をかけさせたこと。
以上を謝罪したうえで商人は自分を探しに来てくれたことへの感謝の言葉も付け加えた。
兵たちは返答の代わりに微笑する。
「ずぶ濡れでしょう。手ぬぐい、貸しますよ」
▼そとの人間⑲

雨に濡れたからだをふいたあと、旅人と商人は屯所のなかの広間にとおされた。そこでは、ほかの避難者たちが大勢うずくまっていた。
そのあいだを縫って、あいている空間を探すふたり。
ちなみに旅人のかさは、屯所の玄関にあった「かさ立て」に置いてきている。
▼そとの人間⑳

すでに壁際は人でうまっていた。しかし広間のちょうど中央に位置する場所には誰もいなかった。
「ここで休みましょう」
そんな旅人の提案に商人は首肯する。
(きょう会ったばかりで、しかもさきほど問題を起こした自分に対して妙に優しい気もするけれど……)
▼そとの人間㉑

ふたりはその場に腰をおろす。おたがい、しばらく黙っていた。目を閉じる旅人。うつむく商人。
周囲の人々の会話が聞こえる。
「……もし『彼女』が現れたとしたら」
「……その名を叫んだやつがいたとか」
「……気がふれたのか」
「……もう兵隊に取り押さえられただろう」
▼そとの人間㉒

(兵隊に……?)
その言葉を耳にして商人は気付いた。さきほど自分を探しに来てくれた兵たちも、本来は自分を拘束しようとしていたのではないかと。だがそれは回避された。
なぜ。
はっとして目のまえの旅人に視線を移すと、そのまぶたがゆっくりとひらいた。
▼そとの人間㉓

「あなたが駆け付けてくれていなかったら、わたしは」
「声を抑えましょう」
旅人が商人の話をさえぎる。
「みんな聞いていないふりをしながら聞いているものです」
そう耳打ちし、まわりの者たちを見回す。
「聞かれてもいい話題はどうです。たとえば、たがいの名前とか」
▼そとの人間㉔

「なおわたしはコウと名乗っています」
「まあ、あなたとは奇妙な縁を感じますし、こちらも……あれ、でも旅人さん、待合所でわたしの名前が呼ばれるのを聞いてましたよね」
「忘れたもので」
「では『余分』の『余』と書いてアマリです」
「なるほど、今度は覚えられました」
(つづく)
▽次の話(第十七巻)を読む
▽前の話(第十五巻)を読む
▽小説「巫蠱」まとめ(随時更新)
★IF[ありえないと思われる選択]
「そとの人間⑫」より分岐の可能性【皆無】
旅人は動かなかった。土砂降りのなかでも雨にうたれるまま、持っているかさをひらきもしない。
避難誘導する兵たちが、なにやら話し合っているのが聞こえる。雨音のせいで、詳細までは分からない。
そのうちのふたりが雨の向こうに消えていく。さきほど絶叫が聞こえてきた方向である。
しばらくして、ふたたび「御天(みあめ)さま」という大音声が轟いた。今度は悲鳴のようにも思われた。
何回も連続してその名が叫ばれる。声のところどころに、すすり泣きのような音が混じる。
おそらくあの兵たちが、声の主を黙らせようとしているのだろう。当然だ。ただでさえ緊張の高まっている場所に、この不吉な異常気象。これ以上、現場を混乱させるわけにはいかない。へたすれば戦争にもなりかねない状況なのだ。
奇妙なのは兵たちの声が届かないこと。彼等は黙々と役目を遂行しているものと思われる。
そして、じきに例の声は途切れた。
兵ふたりが、「彼」を連れて来る。顔は布で隠され、みえない。いや、どちらにしても、この雨のなかでは近寄らない限り顔が分からずとも無理はない。
ただ、彼の口元の様子はみえた。手ぬぐいらしきもので、さるぐつわをかまされた格好だ。なぜ手ぬぐいが使用されているのか。それは拘束する相手を油断させるためだったと思われる。
彼は、避難している一般人のまえにわざわざ連れて来られた。「声の元凶は取り押さえた」と兵たちは誇示したかったのだろう。しかし、これについて歓声や安堵といった反応は得られなかった。
旅人も遠目にそれを見ていた。ここで、「早く屯所に入ってください」とほかの兵にせかされた。
彼女は、ひらきもしなかったかさを屯所の玄関の「かさ立て」に刺した。
奥に進もうとしたところで、そとから人の声が聞こえた。
「御天さま」「御天さま」……
声はひとりのものではなかった。何重にも積み重なっていた。
兵の声も加わり、どんどん大きくなり、そして。
雨がやんだ。
小石と雑草のうえにたくさんの人間が倒れている光景が白日のもとにさらされる。濡れている彼等のからだを、太陽が直接に焼いている。
どうやら戦争が始まったようだ。
旅人は屯所から出た。ほかの一般人のほとんどは、なかの広間でうずくまったままだったが。
かさ立てから、かさを抜く。ここでようやくそれを広げる。
なんの表情も作らず、彼女は足を踏み出す。そして戦場の隙間と轟音のなかに、消えていった。
(おわり)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
