
巫蠱(ふこ)第二十巻【小説】
▼草笠クシロ④

暗いなか、わずかな月光を頼りに三人は歩いた。
十我の家に着いたのは丑三つ時。
客人ふたりは家に招かれ、すぐに眠った。
――翌朝。客人のひとり、クシロが目を覚ます。
彼は体に毛布がかかっているのに気付いた。また、そばで誰かが自分の顔を見下ろしていることも。
▼草笠クシロと之墓館①

彼女はあどけない顔をしていた。
クシロはそれ以上の外見描写を心中で試みた。
しかし皇のときと同様、罪悪感に邪魔されて失敗した。
「この毛布は君が?」
「十我お姉ちゃんじゃないかな」
「君は」
「館です。お客さん来たって聞いて来ました。あなたを絵にしていいですか」
▼草笠クシロと之墓館②
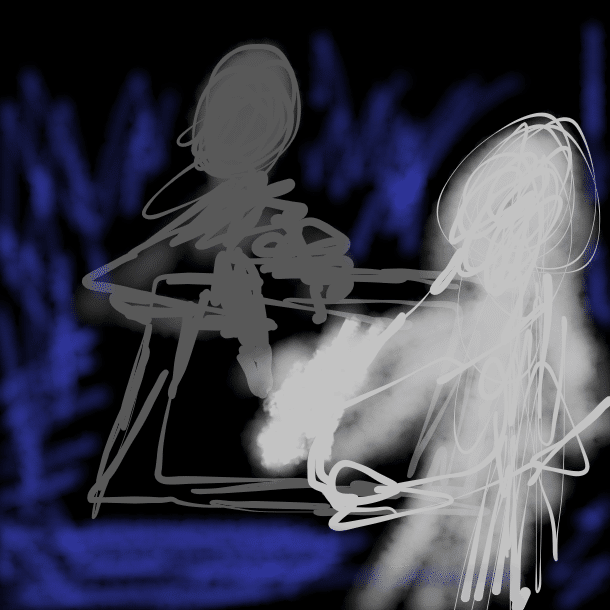
★分岐点⇒[ありえると思う選択]
「いいけど、絵になるかな」
クシロは身を起こし、之墓館に笑いかける。
館は板をかかえている。その上に黒い紙がある。
ぺこりとあたまをさげ、ほほえみを返した彼女は、筆のようなものを取り出し、紙に色を付け始めた。
「お兄さん、灰色でいい?」
「君の好きなように」
▼草笠クシロと之墓館③

紙に色を落としながら館は「見てていいよ」とつぶやいた。
見やすいよう、画板を少しかたむける。
彼女は影絵をかいているらしい。
輪郭内をぬりつぶす。
写実的ではない。
本物とは異なる体格。
服装の無視。
クシロはシズカの言ったことを思い出す。
(認識の再生産……)
▼宍中③

さてクシロが館と一緒にいるとき、当のシズカはそとに出ていた。
草むらにしゃがんで虫たちを観察している。
(宍中の虫。一見すると昆虫。
(しかし個体によって足の本数とその生えている箇所に差異がある)
そして観察の途中、彼は背後から質問を受けた。
「醜いですか」
▼茶々利シズカと宍中十我②

シズカは立って振り返った。
「めずらしいとは思います」
「茶々利さん」
そこにいた蠱女、十我は一歩だけ後ろにさがる。
「きのうは彼等をつぶしましたか」
「できる限りは気を付けました」
「あなたは虫をさげすみ、あわれみ、うらやみますか」
「全面的に『いいえ』です」
▼茶々利シズカと宍中十我③

「茶々利さんのご用件は我々の動向調査でしたね」
昨夜の自己紹介の際に確認していたことを、十我が繰り返す。
シズカは首肯した。宙宇の書いた紹介状もすでに渡してある。
「ご迷惑はおかけしません」
「足りませんよ。あなたは筆頭巫女を狙う刺客とも思われます」
▼茶々利シズカと宍中十我④

「ご安心を、十我さん。
「危険物は携帯していませんし、わたしも同行させた草笠も軍の人間としては貧弱で」
「丸腰で非力でも筆頭巫女をひとひねりにするのは簡単です。
「もちろん護衛はいますが、念のため人質を要求します」
「草笠を差し出せと」
「いえ、人質はあなたです」
▼宍中十我⑦
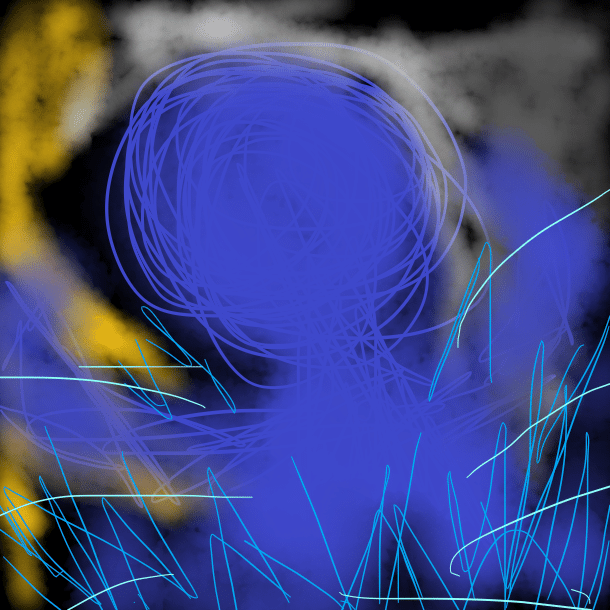
「必要なときに仲間や自分を切り捨てられるあなたに対して人質は無意味です。
「でも草笠さんは茶々利さんを見捨てないでしょう。なぜ分かるか?
「草笠さんはうちの館と仲良くできているから。
「あなたに関しては、善良な人間を道連れにこの地に踏み込んだ時点で」
▼宍中十我と桃西社鯨歯④

「では返答を。……あ」
そのとき十我は横を向いた。
やや遠くに誰か立っている。背の高い人物である。
十我は大声を出した。
「鯨歯」
すると向こうからそれ以上の声量が返ってきた。
「おふたりの話が聞こえないぎりぎりの間合いにいるのでわたしのことはお気になさらず」
▼茶々利シズカと宍中十我⑤

「いや、鯨歯にも聞いてほしい。様子を見てこいと蓍が指示したんだろ」
そう十我がさけぶと、鯨歯がこちらに向かってきた。
あらためて十我はシズカのほうを見て声を通常の大きさに戻す。
「彼女は桃西社鯨歯です」
「わたしを引き渡しますか」
「人質になってくださるなら」
▼宍中十我と桃西社鯨歯⑤

鯨歯はシズカに近寄り、あいさつを交わした。
十我から説明を受け、彼女は呆れた声を出す。
「事情は分かりましたけど要求が一方的ですよ。わたしたち悪者みたいじゃないですか」
「万が一にも蓍は失えない」
「お互いに人質を用意すれば公平です。こちらからはわたしが」
▼茶々利シズカと桃西社鯨歯①

シズカの目を見て鯨歯が提案する。
「そちらが巫蠱にひどいことをしようとしたらシズカさんを、逆に巫蠱がそちらに危害を加えようとしたらわたしを始末するというのはどうです」
「あなたの真意は」
「見知らぬ土地にたったふたりで来た不安を取り除いてあげたいんです」
▼茶々利シズカと草笠クシロ⑬

「草笠の意思も確認します」
シズカは十我の家に引き返す。
「草笠、筆頭巫女に会うために俺は人質になるが、いいか」
窓越しに声をかける。
なかから返事が来る。
「人質なら自分が」
「指名されたのは俺だ」
「シズカさんは納得を?」
「面白いと思った」
「なら、いいです」
▼茶々利シズカと之墓館①

その会話の直後、シズカの耳にクシロとは別の声が届いた。
「あなたも絵にしていいですか」
窓の向こうの家のなか。
クシロの近くに幼い顔がひとつある。
彼女は画板をひざに乗せ、紙に模様を付けていた。
構わないとシズカは答える。
(十我の話からすると彼女が之墓館か)
▼宍中十我⑧

「おなか、すきません?」
ここでシズカに背後から話しかけたのは、彼を追ってきた十我であった。
鯨歯も一緒である。
十我は自分の家にもう一度シズカを招き入れ、食事を出してくれた。
シズカたちの感謝に対して十我は「一日一回だけですよ」と申し訳なさそうに言った。
▼宍中十我⑨

それから十我はシズカたちを連れ、赤泉院の地に向かう。
途中、彼女は草むらから虫をすくいあげた。
「占いですよ。
「……結果は『損』と出ました。
「悪いものとは限りません。怒気や欲望が減損すべきであるように。
「ただし当たるも八卦当たらぬも八卦。無視しても結構」
▼草笠クシロと宍中十我①
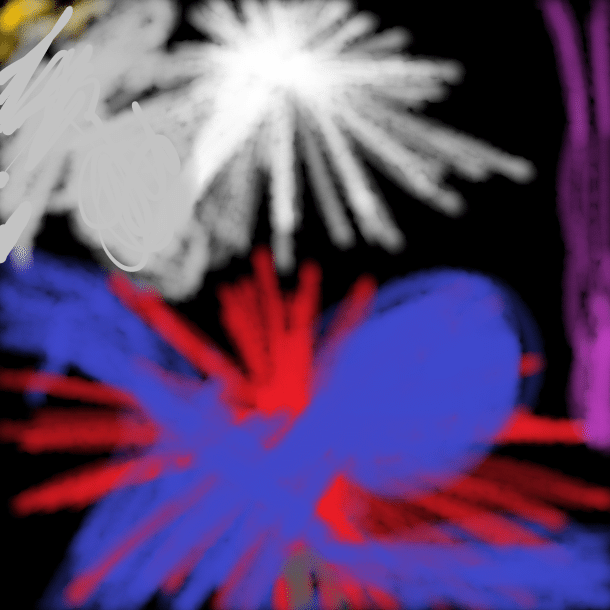
「さて蓍に会う流れですが、その前提でよかったですか」
そんな十我の疑問にシズカとクシロが同時に応じる。
巫蠱のことを知るには筆頭巫女に聞くのが一番だと思うと。
十我が問いを重ねる。
「筆頭蠱女は?」
「先日、仕事中に見かけました」
今度はクシロの口だけが動いた。
▼草笠クシロと宍中十我②
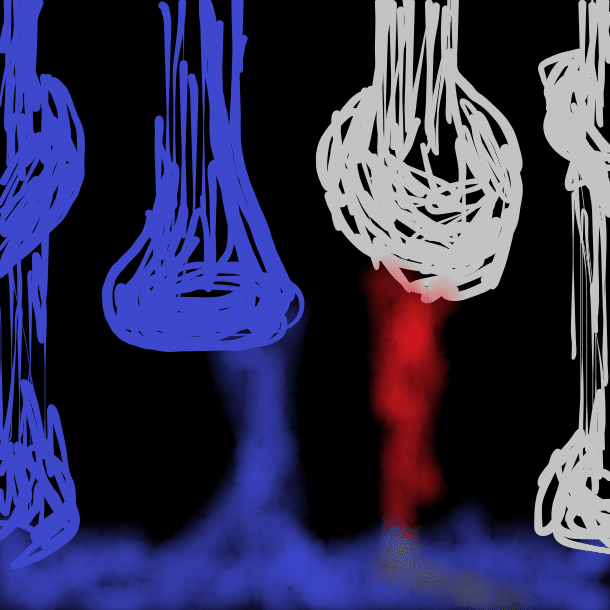
「本人が名乗ったんですか、草笠さん」
「いえ、絵にもかけない美しさで」
「でしたらうちの筆頭と思われます」
「国境を越えるところを見かけたのです。同日、雲なき雨がふりました」
「人々から凶兆と思われていますよね、戦争の」
「今回は、なにも起こりませんでした」
▼茶々利シズカと桃西社鯨歯②
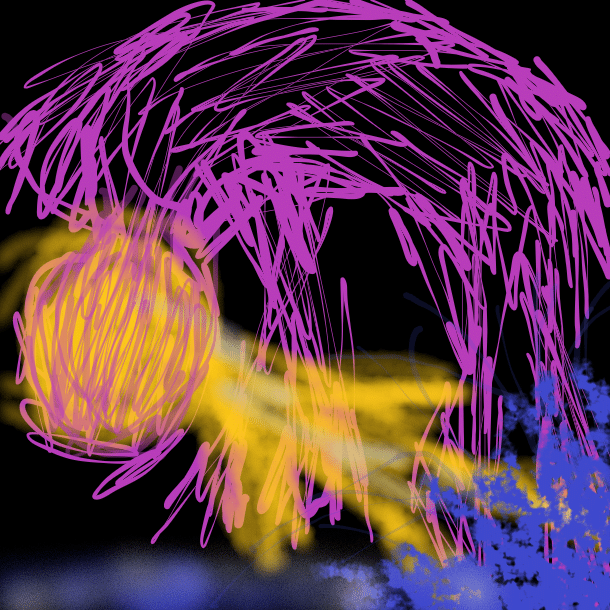
一方、黙ってしまったシズカの顔を同行していた鯨歯がのぞきこむ。
「クシロさんに託すために、あえて沈黙しましたね」
鯨歯は腰から首までを過度に湾曲させている。
「信じましょう。十我さんも筆頭と話すときの予行演習をしてくれているようですし」
「恐れ入ります」
▼茶々利シズカと桃西社鯨歯③

「いや恐れ入ることはないですよ」
鯨歯は首を回した。
「もっと馴れ馴れしくても全然。わたしの敬語も相手を敬ってのものじゃありませんし」
首を動かしながらも彼女の視線はシズカの顔から離れなかった。
(宙宇、説、葛湯香、鯨歯。全員巫女だが思いはそれぞれか)
▼桃西社鯨歯⑧

シズカと話すうち鯨歯は自身が巫女になった経緯にもふれた。
もともと彼女はさる富商の次女。
ある日、雨と共におりてきた思いに突き動かされ家出。
のち家族に探し出されたが「つらいときは必ず帰ること」を条件に和解。
「泣けるでしょ。とんだどら娘がいたもんです」
▼草笠クシロと宍中十我③
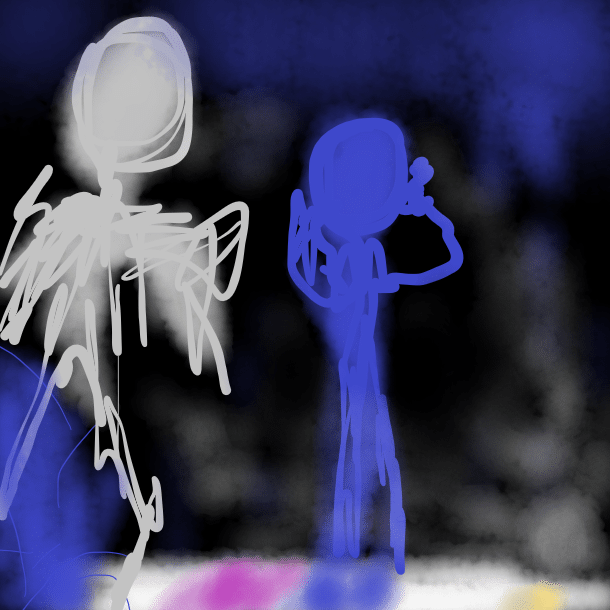
そろそろ赤泉院に入る。
草むらが途切れ、虫が減った。
十我は自分のほおを指の節目でさすりつつ「なぜ聞かないんです」とクシロに言った。
「雲なき雨の元凶、御天とわたしは姉妹です。せんさくの好機では」
「……話せることはありますか」
「わたしも御天が分からない」
▼宍中十我と桃西社睡眠①

赤泉院の屋敷には夕方前に到着した。
玄関近くで待っていた人物に状況を説明して客人たちを預けた十我は屋敷に背を向け宍中に戻る。
「館に留守番させていますので」
彼女は走ってすぐ消えた。
それを見届け、玄関近くに立つ人物が名乗った。
「こんにちは睡眠です」
▼赤泉院③

シズカとクシロは屋敷の一室に通された。
すでに置かれていた座布団の上に腰をおろす。
部屋の戸は開け放たれており、縁側の先の景色がよくみえる。
そとには小石が散らばる。
花を咲かせない植物があちこちに生えている。
この風景のやや奥に、ぽつんと水たまりがあった。
(つづく)
▽次の話(第二十一巻)を読む
▽前の話(第十九巻)を読む
▽小説「巫蠱」まとめ(随時更新)
★IF[ありえると思う選択]
「草笠クシロと之墓館②」より分岐の可能性【五割一分】
「あなたを絵にしていいですか」
そんな之墓館の言葉は、草笠クシロを戸惑わせた。
館は無邪気というか悪意のない顔をしていた。
彼女の希望に乗っても、問題はないと思われる。だが。
「いや、僕は絵にならないよ。ごめんね」
クシロは身を起こしながら謝った。
対して館は首を勢いよく振る。
「いえ、いえ。わたしが不躾に頼んだことです。お兄さんは気にしないで」
正直、クシロは後ろめたさを感じた。
(気を許すな)
さきほどから、そとの茶屋で聞いた刃域宙宇の忠告が脳に響いている。
いたいけな少女にもみえる館の提案をあっさり拒んだのは、その声に従ったからだろうか。
館も、この世界で異端視される巫蠱のひとり。
本当のところ実年齢がいくつかも分からない。
外見で判断すべきではない。
彼女は蠱女。思われる者。その特性は、おそらく「絵にすること」に集約されているはず。
世界にたった十二人しかいない蠱女。
そこには特別な意味合いが含まれていないとおかしい。
そう考えたとき、「絵にする」という行為が一種の呪術であるかのようにも思われた。
自分という存在が絵という枠に閉じ込められるような予感。
クシロ自身が皇の絵をかこうとしたとき紙を破ってしまったのは、筆頭蠱女である皇がその枠内に収まる存在ではなかったからではないだろうか。
だから怖くなった。絵にされるのをためらった。
しかしクシロは仕事でここに来ている。
巫蠱の動向を探るにあたって、彼女たちとはできるだけ友好的に接したほうがいいとも理解している。
このまま相手の希望を拒否した状態で終わるのは望ましくない。
とはいえ。
彼の気持ちは、それだけではなかった。
「君は普段、どんな絵をかいているの? 見てみたいな」
なだめるような口調と共に、クシロは館に笑顔を向ける。
すると館が、首を振り回すのをやめた。
彼女は画板を持っていた。
そこに置いた黒い紙に、絵をかきだした。
「鏡じゃない絵をかいてるよ。だからあなたではなく、わたしが想像したあなたの心を絵にします。これならいい?」
「君の想像なら絵になると思うよ」
それからクシロは黙って彼女の様子を見る。
館は筆のようなものを紙にこすりつけながら色を広げる。
使われているのは、灰色だ。
「お兄さんの心の色。でも嫌な色じゃないよ」
ここで同じ箇所へと執拗に、同色を重ねていく。
「だって之墓の色だから。あ、それよりちょっと薄いかも」
重ねた同色を乱暴に伸ばす。
その部分はあまり上手く色が広がらなかった。
「適当だけどね」
こうして、黒い紙の底のほうに灰色の「だま」が出来た。
ただし絵全体に流れはあるようだ。
灰は上へと散らばりのぼり、ひとつの先端に収束する。
……かと思いきや、上空付近で飛び散った。
その飛び散った残骸は再び「だま」に合流するでもなく、黒い紙の左右のはしに遊んだままである。
それは、クシロの心底に芽生えていた、もっと単純な。
白色よりも色のない感情。
明確なかたちのない感情。
なおかつ弾力のある感情。
そして指向性のある感情。
つまり感情の質量の「質」の部分が抜け落ちた、純粋な「量」としての気持ちであった。
大量にあるわけではないが、底にしっかり落ちている。
それが、クシロの心を完璧に描写している絵かは分からない。
なぜならあくまで館の想像したクシロの内面にすぎない。
そもそもクシロは自分の心にどのような色が住んでいるのかを知らない。
「これ、贈ります」
画板から紙を浮かせ、館が絵を差し出した。
「ありがとう」
クシロは館にお礼をしたくてたまらなかった。
その絵が嬉しかったというよりも、その絵をかいて渡してくれたことが嬉しかったのだ。
(手みやげを渡すな)
宙宇のこの忠告を思い出さなかったら、お返しとしてなんらかのものを彼女にあげたと思われる。
(ただ、宙宇は紹介状の代わりにたまごの殻を受け取っていた。
(手みやげではなく取引だったら別にいいのでは)
一瞬クシロはそう思ったが、あどけない雰囲気の館に対して取引という概念を持ち出すのはどこか嫌な感じがした。
結局、感謝の言葉で我慢した。
「草笠」
そのとき窓のそとから茶々利シズカの声がした。彼はクシロの上司のひとりである。
なんでも筆頭巫女に会うために人質になるらしい。
クシロとしては気が進まなかった。
しかしクシロはこの上司が自分より何倍も賢明であると知っている。
よって部下として無理に反対するわけにはいかなかった。
そして話が終わったとき、彼女の声が部屋のなかに広がった。
「あなたは絵にしていいですか」
低いような、高いような、その中間でもないような、形容しがたい音だった。
自分に聞いていると気付いたシズカは少し考えて答えた。
「遠慮する」
これに対して館は、聞き分けよくうなずいた。
そして新しい黒い紙を用意して、また色を広げ始めた。
今度は青だった。
(おわり)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
