
巫蠱(ふこ)第三巻【小説】
▼巫女と蠱女④

「まよいました」
「やっぱりか、おまえ何回ここきたことある?」
「数えてませんよ」
「わたしもだ」
そんな調子でさまよう巫女(ふじょ)ふたりのまえに、木陰よりあらわれる蠱女(こじょ)がひとり。
「げーちゃん、蓍(めどぎ)さん、やっときたね」
「あ、簪(かんざし)」
▼之墓簪と赤泉院蓍①

之墓簪(のはかかんざし)は髪を葉っぱでこすりつつ、蓍(めどぎ)へと目を向ける。
「なんでこいつがここにって顔だね、蓍さん。じつは、ぜーちゃんにたのまれたのさ。ま、道場も再開されたし、姉さんのところにもどるついでにね」
「え、その話からするとおまえ……」
▼之墓簪と赤泉院蓍②

「家出?」
「ちがうけど」
それから簪(かんざし)は、妹の館(むろつみ)にした話をくりかえす。
「ああ、ぜーちゃんが道場休んだから気になったと。だれから聞いたわけでもないだろうに。
「てかおまえと館がいたなんて知らなかったな。もしかしてわたしだけが?」
▼之墓簪と桃西社鯨歯①

簪(かんざし)は、そこらの樹木に貼り付いていた桃西社鯨歯(ももにしゃげいは)に向かって言う。
「げーちゃん気付いてた?」
「妹さんのほうなら。直接見たわけじゃありませんけど、紙をこする音が夢心地に聞こえたような気がしたので、もしかしたらと思ったんです」
▼後巫雨陣③
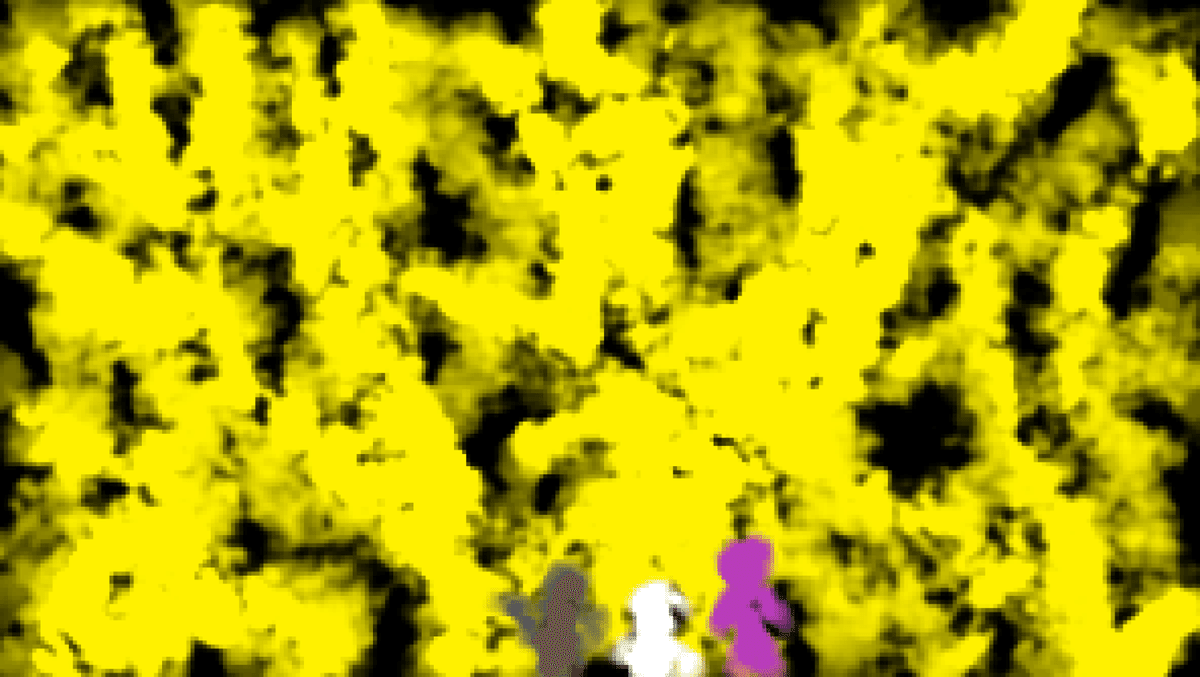
皇(すべら)をさがしつつ、三人は後巫雨陣(ごふうじん)をかきわけていく。
奥に進めば進むほど、しめりけの感覚が増す。植物たちのあふれさせる水気の量も多くなり、その肥大ぶりに拍車がかかる。
空気自体がべっとりしていて、肌に吹く汗と区別がつかない。
▼後巫雨陣④

しかし奥の奥まで踏み込んだとき、肌に貼り付いてくるようなしめりけが、さわやかな冷気に変わっている。
水滴をふきかけられる感覚は同様だが、もう方向がくるうことはない。そこに肥大した植物はなく、足下は河原のように小石だらけだ。
ここがこの地の最奥である。
▼後巫雨陣一媛①

後巫雨陣(ごふうじん)の地はどうしてしめっているのか。
その答えが、小石のすきまからふきだしている。
地下水がとぎれることなく天に向かってとびだしており、一本の柱のかたちをなしている。
そしてそのそばにたたずんでいるのが、後巫雨陣の長女、一媛(いちひめ)。
▼之墓簪と後巫雨陣一媛①

「お姉さーん」
之墓簪(のはかかんざし)が後巫雨陣一媛(ごふうじんいちひめ)に手をふって呼びかける。
ふきあげる水の柱から目をはなさずに一媛は応える。
「簪と鯨歯(げいは)ちゃんに、筆頭。ご無沙汰」
よく見ると柱の表面に巫蠱(ふこ)たちの顔が映っている。
▼赤泉院蓍と後巫雨陣一媛①

「……そう、御天(みあめ)ちゃんが」
三人の巫蠱(ふこ)から説明を受けた一媛(いちひめ)は、水の柱に手をつっこんで、なにかをつかむしぐさをした。
「筆頭」
「なに」
「ワタシは平和を信じていなかった」
「つまり」
「今回のことは、そとの者たちのおかげ」
「あっそ」
▼之墓簪と後巫雨陣一媛②
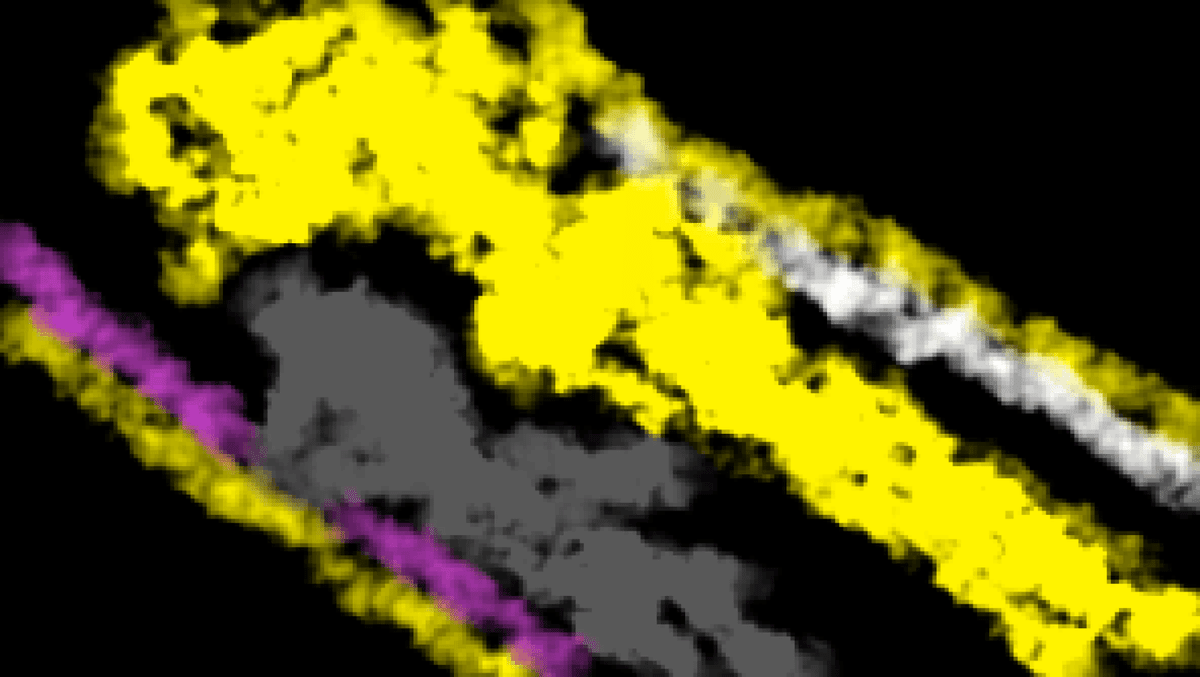
一媛(いちひめ)は蓍(めどぎ)から目をはなし、簪(かんざし)の顔を見つめる。
「簪はもう是(ぜ)から全部聞いたの」
「うん、全部かは知らないけど」
そのとき、水の柱に映り込んでいる一媛の表情がゆがんだ。
「……お姉さん、姉さんのこと心配してるでしょ」
▼之墓簪と後巫雨陣一媛③

「……じゃ、わたし帰るね。姉さんには、うまく言うつもり。それと蓍(めどぎ)さん。あした、むろつみがここにくるから道案内してもらって」
そう言って去りかけた簪(かんざし)を、一媛(いちひめ)が呼びとめる。
「待って。離為火(りいか)が話したいみたい」
▼後巫雨陣一媛と離為火①

水の柱に刺さっていた手が引き抜かれる。
濡れた彼女の二本の指には、べつの女の指がひっかかっていた。
手首、ひじ、肩が順にあらわれ、最後に足が小石におりる。背丈はある。なのに華奢。
姉の薬指と中指に、自分の人差し指と薬指をからませている。
▼之墓簪と後巫雨陣離為火①
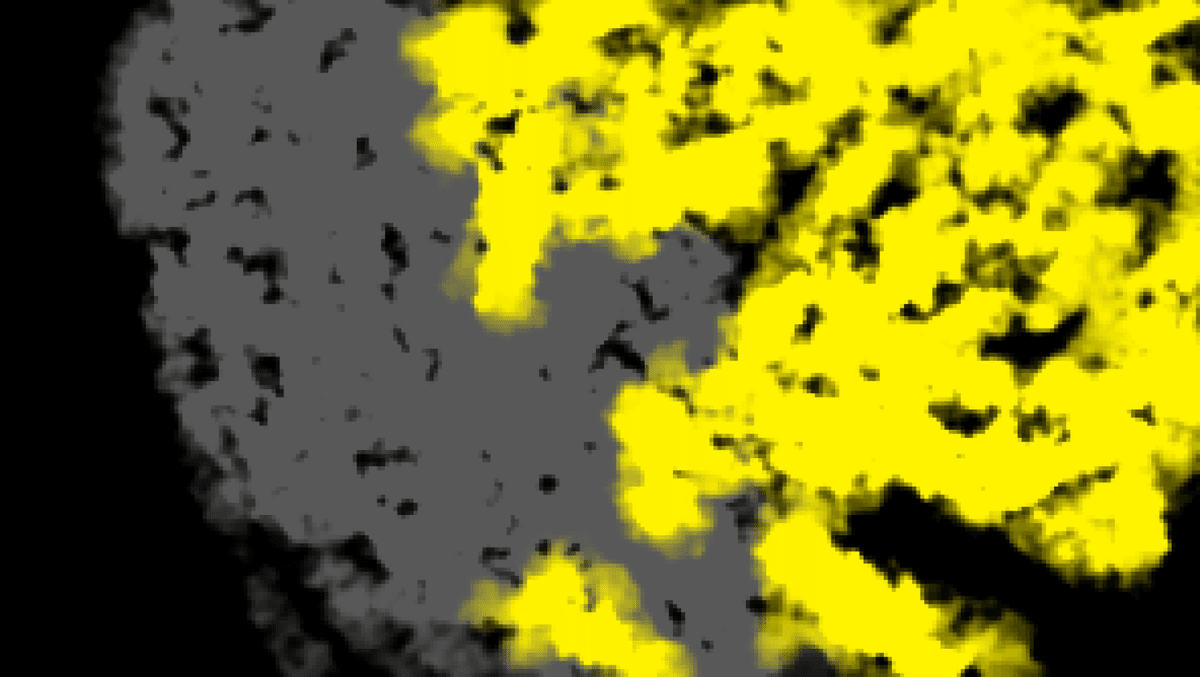
三人からはなれ、後巫雨陣離為火(ごふうじんりいか)が之墓簪(のはかかんざし)の耳元にくちを近づける。
「さびしい?」
うなずきがあった。離為火のくちびるに残っていた水滴が、その耳穴にしたたり落ちる。
簪は一回ふるえ吐き捨てた。
「かわかしてよ」
▼巫女たち①

「……鯨歯(げいは)ちゃん、筆頭がそっけないのなんで」
「話せるだけマシでしょうよ」
「半分瞑想しているようで、ここ居心地いいんだよな」
「だそうです、一媛(いちひめ)さん。道のりとしては楼塔(ろうとう)よりもつらいはずですけどね」
「……はぐらかしてない?」
▼後巫雨陣一媛と離為火②

「……簪(かんざし)はかえしたよ」
そう言って離為火(りいか)が一媛(いちひめ)のほうに歩いてくる。
「なにを話したの」
「かわかしたの」
一媛をとおりすぎ、地下水のふきだしている場所に足を付け、なかにもどる。
「筆頭、鯨歯(げいは)。簪、お礼は要らないって」
▼赤泉院蓍と桃西社鯨歯⑦

水の柱に離為火(りいか)が消えた。
蓍(めどぎ)はその場でひざをかかえ、ころがった。
鯨歯(げいは)は小石のうえに正座している。
「皇(すべら)さんにとって居心地がいい場所を考えますか」
「あいつ自分を追い込むからな。いままでも、どこいってたんだろ」
▼赤泉院蓍と後巫雨陣一媛②
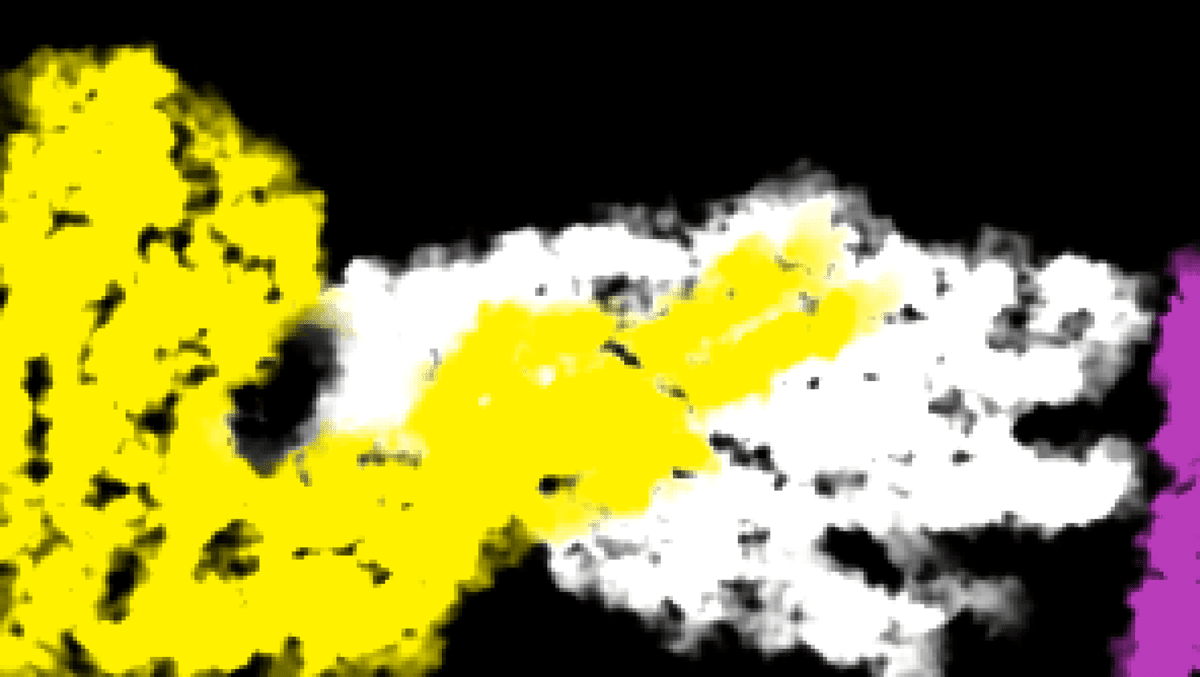
「一泊するつもり?」
一媛(いちひめ)の声はやわらかい。
「わるいね」
「かまわない。ときに皇(すべら)について。行き先を聞いても答えてくれたことはない」
「行き先というか消え先か」
「刃域(じんいき)にすらいないのかも」
「これを最後にしてほしいよな」
▼桃西社鯨歯と後巫雨陣説①

……いつのまに寝たのか、気付くと鯨歯(げいは)のほおをぐりぐりする手があった。人差し指と中指を立てている。
後巫雨陣(ごふうじん)の三女、説(えつ)の肩から伸びた手だ。
鯨歯が起きたのを確認してから、指をはなす。
代わりに、それら二本に葉っぱをはさむ。
▼後巫雨陣⑤

後巫雨陣(ごふうじん)の地に生えている植物から葉っぱをもいで、くちにふくむと存外の弾力におどろかされるだろう。
葉っぱは分厚く、歯をあてた瞬間に樹液のような水が口内を満たす。
あまさとからさが七と三。
葉脈をかみちぎれば、すっぱさがはじけとぶ。
▼巫女と蠱女⑤

葉っぱをかみつつ鯨歯(げいは)が礼をもごもご述べる。
説(えつ)は蓍(めどぎ)のよこに移動し、さきほどとおなじように、ほおをぐりぐりしはじめる。
一媛(いちひめ)は水の柱を見つめ立っている。小さな影がそばにある。
鯨歯は咀嚼したぶんを飲み込んだ。
▼之墓館②

小さな影は画板をかかえてしゃがんでいる。
絵はかいていない。ここでは紙がふやけてしまうからだろう。
その視線が巫女(ふじょ)たちを順に追う。水の柱にも目を移す。
画板をとんとんたたきつつ、姉のように髪をこする。
之墓館(のはかむろつみ)は、ねむそうだ。
▼之墓館と赤泉院蓍①

一媛(いちひめ)たちとわかれ、蓍(めどぎ)と鯨歯(げいは)は館(むろつみ)についていく。
べっとりした空気と肥大した植物を抜けるたび、その足運びがかるくなる。
「蓍お姉ちゃん、宍中(ししなか)でいいんだよね」
「ああ、いまはあいつら十我(とが)の家」
▼宍中①

最初からまよわずに進めたからだろう。
三人が後巫雨陣(ごふうじん)を突破したあとでも、日はほとんどかたむいていなかった。
しめりけが失せる。方向感覚がもどる。
ここからは宍中(ししなか)。
いわゆる木はない。生えているのは草ばかり。花がちらほら咲いている。
▼宍中②

巫蠱(ふこ)がまもる八つの地域のうちで、もっとも歩くのが楽なのは宍中(ししなか)であろう。
草ぼうぼうの平坦が広がっているだけだからだ。
ただ、虫が多い。
目のまえをちょっと蹴ってみれば、生き物たちがあたりにちらばる。
かれらは無害で、人を攻撃しない。
▼宍中十我①

一行は草を踏み踏み突き進む。
そんなおり、向こうから接近する人影がひとつ。
こぶしをほおにあてている。頬杖の格好だが、彼女のひじは浮いている。
宍中十我(ししなかとが)のくせなのだ。
そのひじを一行に向けながら、近づいてくる。
虫が散る。虫が散る。
(つづく)
▽次の話(第四巻)を読む
▽前の話(第二巻)を読む
▽小説「巫蠱」まとめ(随時更新)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
