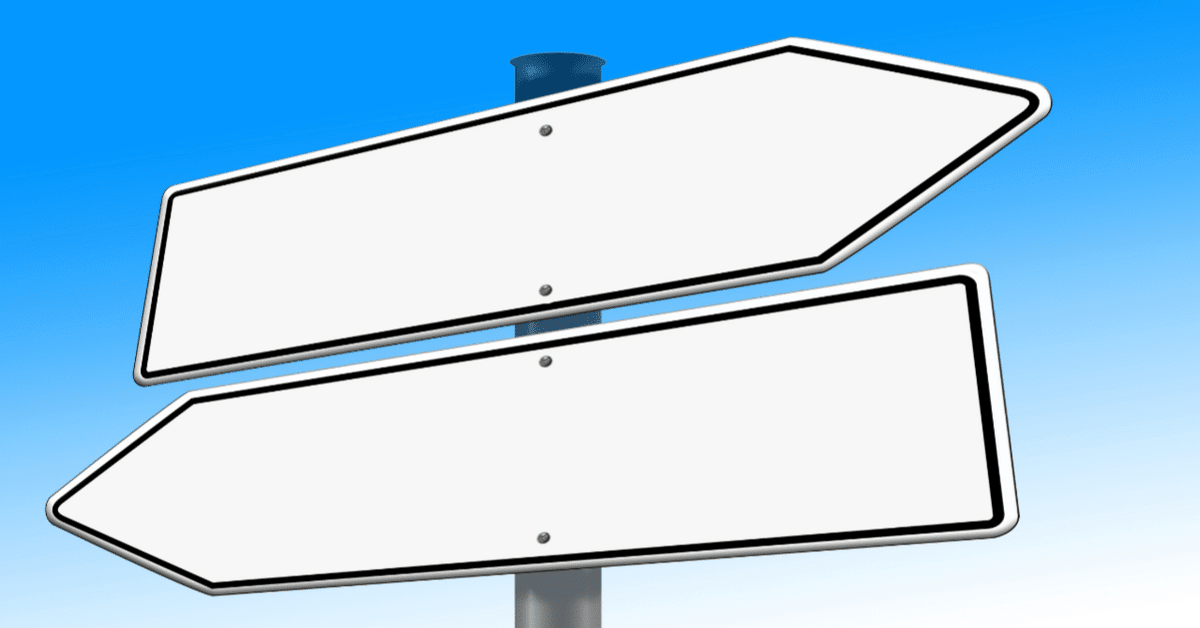
成長できる中小企業と成長できない中小企業は、何が違うのか?
こんにちは、お金が入るでかねいりです。
先日、ある会社に訪問をし、経営者の方に現状についてお話を聞くと、「売上が伸びていない」、「成長が鈍化している」ということを話していました。
実は、こういった話は、他の中堅・中小企業でも聞くことが多くあります。
今日は、どういった中堅・中小企業が成長できて、どういった中堅・中小企業が成長できないのかについて考えてみたことをお伝えできればと思います。
■中堅・中小企業が成長できない理由とは?
これまで多くの中堅・中小企業の経営の現場を見てきた中で、経営者を取り巻く環境から次の3つの状態になることが多いと感じています。
①目の前の風圧
中堅・中小企業の場合、社長の目の前では、いろんなことが起こります。大手企業とは違い、社長自身がそれに対応しなければなりません。現場のフォローをすることもあれば、会議やミーティングも多い。現場で起こる問題や課題への対応もある。目の前のことでいっぱいいっぱいになり、短期的なことに意識が偏りがちになります。
②コルセットがない
大手企業にはコルセットがあるのですが、中堅・中小企業にはコルセットがない。どういうことかというと、大手企業の場合、株主からの目線、金融商品取引法からの視線、社外取締役からの視線など外部からのプレッシャーにされされているため、経営をしていくにあたっての制約があり、緊張感があります。
一方で、中堅・中小企業の場合、圧力をかける存在がいなく、制約もありません。言い換えれば、怒られることがない。そのため、できない言い訳がしやすい状態であり、悪い意味での公私混同をしやすい状態になります。
③なりゆきの引力
これは、ある程度、会社が安定している時に起こりやすいケース。「うまくいっているんだから、このままでいいんじゃないか、そこまでがんばらなくてもいいんじゃないか」という気持ちになってしまう。そして、チャレンジすることに臆病な状態になる。この状態のことを書籍ビジョナリーカンパニー2で「GoodはGreatの敵」と表現していて、偉大な会社(Great)になる一番の敵は、良い会社(Good)にとどまってしまうことと言っています。
これらのことをまとめると、中堅・中小企業の経営者は、「経営」に集中できていないということ。
ここが成長できない、次のステージに行けない最大の要因だと考えます。
■経営と執行の違い
ここで言っている「経営」とは、何のことを言っているのかと言うと、まず下記の画像を見て頂ければと思います。

「経営」は、影響の範囲が広く、時間軸も長い。一方で、
「執行」は、影響の範囲が狭く、時間軸が短い。
もう少し具体的に言うと、「経営」は中長期が大前提。中長期を考えると、今の事業が存続していけるかは、絶対とは言えない。安泰とは言えない。それは、外部環境が変化するから。お客様が求めるものが変わるかもしれない。競合が新たな打ち手で巻き返してくるかもしれない。そうしたことを予想しながら、既存事業の更なる深掘りをしたり、新規事業領域の検討をしたりしていくことが経営。
一方で、「執行」は、目の前のことをより良くしていくことが求められる。ゆえに執行は、目の前のことに意識が偏りがちになる。そうすると、変化への対応が遅くなったり、変化を感じづらくなり、対応できなかったり、という体質になりやすい傾向にあります。
社長や幹部がプレイングマネージャーになっているケースが多い中堅・中小企業の場合は、この目の前(執行)の風圧にさらされます。
経営者が中長期のことに何も意識ができていなければ、当然ながら、この風圧に飲み込まれてしまいます。一方で、意識ができていたとしても、その風圧にあらがうことは簡単ではありません。
ここに中堅・中小企業の経営の難しさがあると考えています。
■うまくいっている中小企業は何をやっているのか?
うまくいっている中堅・中小企業が、「経営」の時間をつくるためにやっていることが「経営計画書をつくり、実行し続ける」ということです。
経営計画書とは、以下のようなことが整理されたものになります。
・使命・存在意義(理念)
・ビジョン(中長期の事業構想)
・今期の重点施策と目標
・実行計画と実行体制
これらのことを整理していくことには時間がかかります。なので、1カ月1~2回、3時間ほど時間を確保し、それを半年くらいかけて少しずつ進めています。
また、経営計画書をつくっただけで実行されなければ意味がないため、実行体制も決めています。具体的には、会議体をつくり、アジェンダを決め、成果物を決め、参加メンバーを決め、開催頻度・開催日を決めます。
さらには、経営計画書は初年度につくって終わりではなく、毎年作り直しています。正確に言えば、前年の経営計画書を見直し、バージョンアップさせます。この時に注意しなければならないのは、前年踏襲の考え方で見なすのではなく、使命・存在意義に沿って見直すということです。前年踏襲では、執行と変わらないものになってしまいます。
このようにして、経営計画書を活用している中堅・中小企業は、強制的に「経営」をする時間を確保していました。
一方で、「経営」の時間を確保するかどうかを決めるのは、経営者の意思。
最終的に中堅・中小企業を成長させられるかどうかは、経営者の意思にかかっていると言えそうです。
