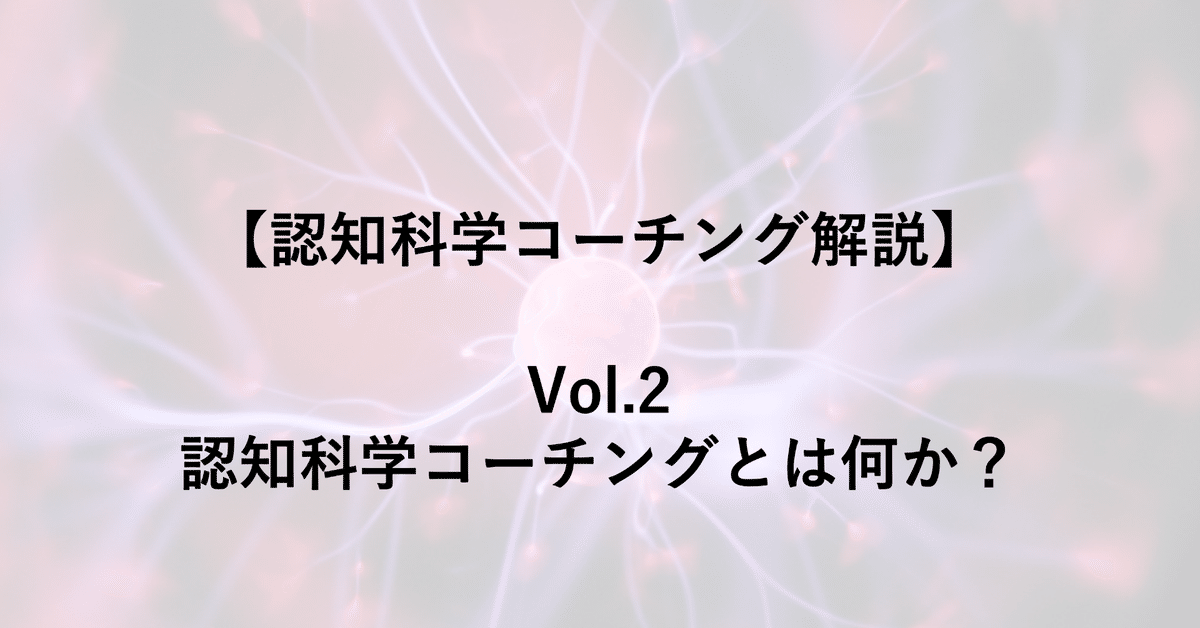
【認知科学コーチング解説】vol.2認知科学コーチングとは何か?
こんにちは!かねコーチです。
❶次世代リーダーが自分らしく仲間と共に歩み出すプログラム「NewType」の運営
❷コーチ/コンサル/士業などのプロフェッショナル業の売上アップに貢献する「マーケティング戦略コーチ」
の2つの仕事をしています。
詳しい情報については、下記の別記事をご覧ください。
【自己紹介】かねコーチとは何者か?
次世代リーダーのためキャリアプログラム「Newtype」
さて、ここから本題に入ります!
認知科学コーチング解説シリーズ
最近よく
・認知科学って何?
・コーチングって何?
とよく質問を受けます。
そこで!!!!
・認知科学流派のコーチングスクール「mindset coaching school」を卒業
・すでに500名以上をコーチングしてきた
私が徹底的に解説してしまおうというのが、このnoteを目的です。
シリーズ企画として、9本のnoteに分けて【認知科学コーチング解説】をしていきます!
9本の内容は以下↓
vol.1 認知科学とは何か?
vol.2 認知科学コーチングとは何か?
vol.3 コンフォートゾーンとホメオスタシス
vol.4 ゴールと臨場感
vol.5 want to
vol.6 現状の外
vol.7 バランスホイール
vol.8 エフィカシー
vol.9 RASとスコトーマ
さて、今回は
「Vol.2 認知科学コーチングとは何か?」
という内容です。
前回の内容がそもそもわからない!という方は、まず下記の記事からキャッチアップしてください。
では、今回の内容に入っていきましょう!!
認知科学コーチングとは、内部モデルを書き換えるもの
認知科学コーチングは、一言でいうと何なのか?
「内部モデル(ビリーフシステム)を書き換えることにより、人生を劇的に変化させる対話手法」
これが認知科学コーチングの本質です。

「Vol.1 認知科学とは何か?」でお話したように、人には外部刺激の受け取り方と行動ともに影響する、「内部モデル」、別名「ビリーフシステム」が存在します。
人を変化させるためには、外部刺激を変えるだけでも足りないし、行動を無理やり変えようとしてもあまり変化がみられない。
逆に「内部モデル」を変えることで、外部刺激への捉え方も、行動の選び方も劇的に変わります!
そして、認知科学コーチングはこの内部モデルを変化させるために、コーチがコミュニケーションをしていく必要があります。
多くのコーチングが実は間違っている?!

よくあるコーチングの失敗例ですが、内部モデルではなく、行動のみに焦点をあて、「どうすればうまくいくか?」という会話のみが行われることがあります。
どの行動が最適か?、どの解決策がいいのか?
という話は、課題解決が目的のコンサルティング的な関わり方であり、厳密にいうとコーチングではありません。
また、行動だけを変化させても、根っこにある「内部モデル」から変えない限り、クライアントは気分良く行動ができません。
「内部モデル」の中、いわゆる心の奥底ではその行動はやりたくないと思っている。
でも理屈でいうと、その行動を取ることは正しい。
クライアント本人も当然その行動を取るべきであるとわかっている。
しかし、人間は論理よりも感情の生き物。
最適な行動がわかっても、いざ行動しようと思うと、心が邪魔して行動する気になれないのです。
そして、次回セッションで、
コーチ:「前回決めたのに、どうしてやってないの?」
クライアント:「やるべきとはわかっていたけど、時間を取れなかった。」
というような会話が繰り返され行動が進まず、コーチングは泥沼へハマっていきます。
内部モデルを関係する2つのキーワード
それでは、内部モデルを変えるためには、どうすればいいのか?
気になるとは思うのですが、その前に関係する2つのキーワードを理解する必要があります。

1つは「セルフイメージ」
これまでの経験から、自分はこんな存在だ、こんな人間であるという風に、普段言葉にはしないけど、無意識的に自覚している自分像のことを指します。
もう1つは「ブリーフシステム」
これは「内部モデル」とほぼ同じ意味にはなるのですが、過去の経験によって蓄積された、「これが好き/これは嫌い、これが正しい/これは間違い、これが重要/これは微妙」などと思う価値観の集合体のことです。
数学でいう関数とも言える「ブリーフシステム」があるからこそ、受け取るべき情報についても、取るべき行動についても、人は無意識的に選んでいるとう話です。
アインシュタインの名言に、
「常識とは、18歳までに身に付けた偏見のコレクションである。」
という言葉があります。
まさに18歳までの様々な経験からできた価値観の塊が「ブリーフシステム」である、と理解するといいでしょう。
また、「セルフイメージ」と「ブリーフシステム」には相互関係があります。
・こんな自分だからこそ、こんな価値観だ
・こんな価値観を持つ、こんな自分だ
というように、セットで存在するものだと解釈していただければ良いです。
内部モデルを変える方法
改めて、どうすれば内部モデルが鮮やかに変わり、認知科学コーチングが成功するのか?
察しの良い方であれば、お分かりではないでしょうか?
それは、
「本当にそうでありたいけど、現状では無理だと思える新しいセルフイメージを脳の中に作ること」
これにより、セルフイメージが置き換わり、セットであるブリーフシステム(内部モデル)が変わる。
ブリーフシステムが変わることで、情報入力と情報出力にまで変化が及ぶ。
という流れになります。

そして、この新しいセルフイメージを脳の中に作ることを、
「ゴール設定」
といいます。
つまり、コーチは「ゴール設定」によりクライアントの内部モデルに変容をもたらし、さらに行動をもたらす存在であるということです。
もう少し補足します。
認知科学コーチングを成功させるには、
「本当にそうでありたいけど、現状では無理だと思える新しいセルフイメージを脳の中に作ること」
が大事だといいましたが、
なぜ「本当にそうでありたいけど、現状では無理だと思える」ようなセルフイメージでないといけないのか?
それは、現状できるものであれば、セルフイメージが変わらない。
ということは、ブリーフシステムにも変化が起こらないからです。
そして、現状では無理そうなセルフイメージをおくのであれば、そうありたい!やりたい!と思えるものを設定しないと、新しいセルフイメージに引っ越そうと心が思えないからです。
おわりに
今回はいかがでしたでしょうか?
要点を一言でまとめるとすれば、
「ゴール設定で、内部モデルと人生を変えるのが認知科学コーチング」
です。
ゴール設定の詳細はVol.4
の投稿をお待ちください。
今後も認知科学コーチングについて、解説していきます。
ぜひフォローいただけると、今後の情報をご覧いただきやすいです。
数日おきに更新していきますので、今後もお楽しみにお待ちください!
また、この認知科学コーチングのによる変化にご興味のある方は、下記のnoteも合わせてご覧ください。
