
『春いちばん』再読 ③
賀川豊彦(1888-1960)の妻・ハル(1888-1982)を主人公にした小説『春いちばん』(玉岡かおる、家の光協会、2022年)を読み直し違和感をおぼえたのは、賀川の偉人ぶりやハルの夫に対する従属性だけではない。彼女の容貌に対するコンプレックスの記述が異様に多いのだ。
賀川は明治の末期、神戸・新川のスラムで、キリスト教の伝道と救貧活動を始めた。それらの体験を含めた自伝的小説『死線を越えて』(改造社、1920年)で、自らの恋愛・結婚観や、ハルとのなれそめを詳しく書いている。『春いちばん』は『死線を越えて』をベースにして書かれているので、賀川の価値観が色濃く出ている。
独身時代に賀川が悩んでいたのは大雑把に言うと、結婚する女性は容貌か性格かという二択問題だった。『死線を越えて』には、見た目に関する記述が頻繁に出てくる。ハルについては、<その婦人は一寸見れば、どこかの細君のようである>と描かれ、容貌は微に入り細を穿つ。ハルは、樋口喜恵子、賀川は新見栄一として登場する。小秀は顔見知りの芸妓である。
ちなみに『死線を越えて』は、ハルと結婚して7年後に刊行されている。
(樋口喜恵子=ハルの)その顔は丸顔で色の白いことは西洋人の肌そつくりで、小秀よりか遥かに白いもので、混血児で無いかと思はれる程である。髪は波形に縮れて居るが漆のやうに真黒で、皮膚の色によく配合して居る。美人と云ふのでは無いが、凛々としたしつかりした顔で、貧民窟の人々がよく『おかみさん』と云ふ位だけあつて、更けて見えるのである。
樋口さんも親切である。然し栄一は樋口さんと自分がとても夫婦になるとは思へ無い。それは教育も違ふし、身分も違ふやうに思ふし、樋口さんがなんだかあまりふけて見えるので、人の細君であるやうな気がしてならないのである。
賀川には、ハルがよほどふけて見えたのだろうか。仮にそうであっても、そんなことを書くか、という話である。これら容貌に関する記述について玉岡は、『春いちばん』の中で以下のように憤っている。
何よりハルは「年齢より老けてみえる女工」と表現され、いたわりのなさに傷ついた。自覚はしていても、世間はきっと嗤っているだろう。ペンはやはり武器なのだ。
非難はしたものの、このすぐあとに、『死線を越えて』がミリオンセラーとなり、莫大な印税が入ったことで辛抱できた、と書いている。金銭で相殺される問題なのだろうか、という話は前回に書いた。

「先生は、私みたいに貧しくても美しくなくても、そして無学で愚図でも、へだてなく神様は愛してくださるとおっしゃった」
『春いちばん』での、ハルの台詞である。「先生」は、キリストの教えを乞う賀川のことで、ハルは家の中でも夫をこう呼んだ。このすぐ前にも、美人に対する敵意をあらわにしている。
<正直、ハルは美しい女が苦手なのだ。美鶴をはじめ、女学校のいじめっ娘たちはみんな美しく、それに比例するように残忍だったから>
すべての美人が意地悪であるかのような書き方である。『春いちばん』の中で、ハルは次第に賀川に惹かれていくが、恋敵があらわれる。( )内は角岡の註である。
<そうだ、自分は(信徒として)賀川についていくと決めたではないか。たとえ彼が、自分ではない美しい妻を娶り、その人に微笑む姿を見守られなければならないつらい日々が課せられようとも>
しつこいくらいに、自分と他の女性を比較している。
やがてハルに、父親から縁談が持ち込まれる。ハルは独身を通してでも伝道に尽くしたいと考えていたので、賀川に相談する。これも『死線を越えて』に出てくるエピソードである。
賀川は「それはよかったですね。おめでとう」「女の人はちゃんと配偶者がいてこそ法的に守られる」と祝福する。独身女性が伝道を続けるのは難しい、というのがその理由らしい。ハルの縁談を聞いた賀川は焦る。この人を逃していいのだろうか――。
彼が出した結論は、ハルとの結婚であった。以下は『春いちばん』で、ハルが賀川のプロポーズを受け入れる場面である。
「先生、本当に私でいいのでしょうか」
賀川は神様のための用をなす人だ。なのに自分には学もない。貧しくて、神の教えもまだ浅い。何よりも、賀川の妻と言われるのに、美しくもなく学歴もなく、賀川が嗤われることがないだろうか。
牧師の妻になる条件に、信仰歴はともかく、学歴や経済力、ましてや美しい容姿は必要なのだろうか?
賀川はハルの手を取ると「あなたには、働き者のこの手がある。そんな宝を、私と一緒に神様のために役立ててくれますか」と懇願する。引き算のハルに対して、足し算の賀川。だが、賀川のその算術は、ただ彼女を労働力とみなしている節がある。
というのは『春いちばん』の中で、結婚後にスラムで救貧活動に邁進しつつも苦悩するハルが描かれているのだ。
これまで一度だって賀川に反論したことはない。結婚式の日、彼がハルを女中だと紹介した時も、傷つきはしたが打ち消さなかった。彼がハルを気にもかけずに一人渡米を決めた時も、泣きはしたが止めなかった。結局は彼がすべて正しかったのだし、それでよかったと思っている。大人気の『死線を越えて』にしたって同じこと。彼が結婚を決めるのに、自分の活動を手伝うには地味な女工の方がよかろうと思って妻にした、という表現があった。そう、ハルはその程度の選ばれ方で妻になったと、あの小説は彼の本音を世間に公表したも同然なのだ。
賀川が『死線を越えて』で、それをどのように書いていたのか。彼は神戸女子神学校で教会史を教えていた。以下『死線を越えて』から引用する。もう一度確認するが、文中の新見栄一は賀川、樋口はハル、玉枝は樋口の下で働く十代半ばの女工である。
女生徒を教へる時に、新見はいつも柔らかい異性の温かい血を感じた。そしてもしも与へられるなら、自分の女生徒の中から、彼の妻として終身彼と共に貧民窟の犠牲になってくれる人を探しても善いと思うた。
(中略)
それで、栄一は、それ等の女学生と、樋口さんや玉枝さんなどと比較して見た。そして驚いたことは女学生に生気の無いことであつた。勿論女学生の中には玉枝さんのやうな美しい女は一人も居らなかつた。またそれと同時に樋口さんのやうに元気のあるハキハキした女も居らなかつた。女学生はみな箱詰の人形のやうに、栄一に見えた。それに反して女工は自分の生活を自ら支へて居るだけ、それだけ凛々しく見えた。
それで新見は変則な学問した女より人間らしく生々して居る女工の中から、一生の好伴侶を選ぼうと決心した。
賀川が女学生に教えていたのは20代半ば。まだ幼い女学生よりも、奉公を経て女工頭を務め、スラムの救貧活動にいそしむ同年齢の樋口(ハル)が<元気でハキハキ><人間らしく生々して居る>ように見えるのは当然だ。何よりも、芸妓の玉枝のような美しい女は一人もいなかった。かくしてハルは<貧民窟の犠牲>になったのであった。
玉岡は『春いちばん』の中で、<小説(『死線を越えて』)では、読者たちは(賀川の結婚相手に)選ばれなかった美しい女に同情した。だが賀川の価値観は女の美醜にはない。彼にはただ、彼とともに前進できる女が必要なのだ>と書いている。
読者が美人に同情したかどうかはともかく、賀川の価値観は、間違いなく女性の美醜にもあった。最終的にハルを選んだものの、『死線を越えて』では、美人か性格かという二択問題に多くのページが費やされている。


『春いちばん』の主人公・ハルが、自らの容貌に強いコンプレックスを持っているように描かれたのは、賀川が外見至上主義にとらわれていたからに他ならない。
ただし、ハル自身が著した著書や記事には、私が見た限り、そのような記述は見当たらない。果たして、夫のルッキズムを反映した描写は必要だったのだろうか。仮に書くとすれば、もっと批判的に描くべきではないのか。
明治・大正・昭和を生きた男が、現在から見れば保守的であるのは当たり前かもしれない。だが、男の妻を描くにあたって、夫の価値観や美意識をそのまま書いてしまうのは、いかがなものか。
すぐ前に私は、牧師の妻になる条件に、信仰歴はともかく、学歴や経済力、ましてや美しい容姿は必要なのだろうか、と書いた。賀川は恋愛・結婚において美醜のほかにも、相手の身分や階級、職業も気にしていた。やはり『死線を越えて』から引用する。
栄一はまだ恋の根本要求は美であると考へた。それでもし鶴子や小秀のやうな、美しい女に恋が出来ないならば、恋などはしないとも考へてみた。それに矢張り身分を考へてゐた。自分は樋口さんよりは一種上の階級の人間であるかのやうに考へることが、貧民窟に来てゐても退かないのである。
世話女房としては樋口さんのような間違ひのない女も珍しかろうと思つた。それで、自ら進んで何人かに仲介の労を取つて、結婚をさせてあげやうかとも考えたこともあつた。然し飛び切りの美人と云ふのではないし、身分としては印刷会社の女工である関係上、巡査以上には紹介は出来ぬと考へたこともあつた。
明治中期の生まれで身分意識が抜けきれない時世に育ったとはいえ、神の愛を説く牧師が、それに抗えなかったのだろうか。
1922年に結成された被差別部落の運動団体・全国水平社の創設メンバーたちは、初代委員長の候補として賀川の名前を挙げたようだが、このような堅固な身分意識を持つ者であれば、仮に就いたところで務まらなかっただろう。
賀川の身分意識を反映したのか、玉岡は『春いちばん』の中で、賀川への恋心に揺れるハルの心中を<自分には学歴もよき出自もない>と記している。出自によいも悪いもあるのだろうか。
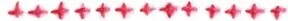
賀川豊彦やその妻・ハルの社会的弱者に向ける冷たい視線は、現代の作家・玉岡かおるにも感じる。賀川やハルが偉人であることを際立たせたいのか、神戸のスラム・新川の描き方が一面的である。以下、『春いちばん』から抜粋する。
二人で歩むはるかな旅路の起点は、以前と変わらぬどんづまり。社会からはじき出された弱者たちが打ち寄せられ、もう後がない水際だ。それでもハルにとっては、賀川と夫婦で生活できる唯一の場所。もう離れなくていい。それだけで、暗くすさんだスラムが楽園に思えた。
五十近くもの子会社を率いる鈴木商店には十万人規模の雇用がある。特に鈴木の樟脳工場は新川から遠くなく、ハルなど、スラムに落ちてくる人たちに仕事を与えてくれればいいのにと願っていた。
暗くすさんだスラム、スラムに落ちてくる人たち…。著者の表現と視点が、いかにもステレオタイプである。医師が新川で医療活動を始めるにあたっては、賀川に「祈りが届いた。こんなところに来ていただいて、なんとお礼を言ってよいのやら」と言わせている。社会の差別意識やマイナスイメージをそのまま投影した文章・台詞である。
賀川が粗食であったことを記した文章は、次のように描かれている。
賀川はほとんど菜食主義で、肉は食べないと決めている。新川の住人が食べられないのに自分が口にすることはできないというのが理由であった。
賀川が菜食主義者だったのは、敬愛する作家のトルストイに倣ったのであって、新川の住人が肉を食べられなかったからではない。そもそも新川の住民がそれを食べていなかったかのような記述は、かなりあやしい。
というのも新川は、屠場(食肉センター)が市街地から移転してきたこともあって形成されたスラムだからである。新川の少なくない住民が屠場で働いていたことは想像に難くない。彼らにとって肉の入手は容易すかったはずである。
新川にあった屠場は再移転し、今はもうないが、その名残で、旧新川周辺には今も精肉店が、びっくりするほど多い。屠場の近くにそれがあるのは全国共通で、前者が移転しても後者は残る。つまり新川の住民は、日常的に肉を食べていた。
贅沢品のイメージがあるから、玉岡はスラムの人々は肉を食べることができなかった、賀川はそれに準じたと考えたのであろう。新川の歴史を知らずに書いているとしか思えない。
日本(内地)に関してだけではない。1922年、賀川夫妻は台湾に伝道に赴く。玉岡は『春いちばん』で、<日清戦争後、台湾は清国から割譲されて日本の領土になっている。かつてアイヌの土地だった蝦夷地を北海道として開拓したように、台湾にも血税を投入してインフラ整備がなされ、政商はもちろん鈴木商店のような民間企業や、大久の久伍のような一般人も多数移住し、新しい土地作りが進められていた>と述べた上で、こう続けている。
しかしこの地には生蕃と呼ばれる土着民がおり、もとの宗主国の清国もその反抗に手を焼いていた。
「長年、軍隊を投入してもまだ統一できないとは、政府はいったい何をやってるんだ。人を統べるのは力じゃないよ、愛だというのに」
それこそ賀川の信条が活かされる場であろう。となると、今回の旅は長くなる。
これでは賀川は、まるで為政者ではないか。満洲で基督教村事業を推し進めた賀川にとっては不思議ではないかもしれないが、アジアへの侵略を<インフラ整備><新しい土地作り>と言ってのけ、<土着民>の弾圧を当然のように書く作家には疑問を抱かざるを得ない。

賀川夫妻の軌跡とその評伝文学を追った私の旅も長くなった。私が言いたいことはこれまでに何度も述べてきたが、あらためて記しておきたい。
現在の視点から、過去の人物や事象を安易に批判してはならない。また、過去の人物や事象を描く際は、当時の価値観や美意識を相対化する必要がある。安易に人を貶めても、持ち上げてもならない。
玉岡は『春いちばん』の刊行後、講演会やインタビューで、賀川がノーベル平和・文学賞に何度も候補になった偉人であったと繰り返し述べている。
だが、彼の著作をひもとくと、スラムの救貧運動や農民・労働運動などに手を尽くしたとしても、黒人・部落民・女性・障害者・ハンセン病者への差別や優生学的思考、戦争責任などの面において、問題が多すぎる。ノーベル賞にふさわしい人物とは、とうてい思えない。唯々諾々と彼に付き従ったハルも、同じ穴の貉である。
彼らを必要とする時代が、再び来ることがあってはならない。また、彼らを賞賛する文学も、あってはならない。(終わり)<2023・11・30>
いいなと思ったら応援しよう!

