
ドラゴンクエスト10 全職業クエスト面白さランキング
「ドラクエ10はストーリーが面白い。ネトゲだからと食わず嫌いせずにやってみろ」
そうして勧める声を、かつては結構見かけていた。
実際、これが言われていたのはバージョン2くらいの時期で、その頃は確かに本編ストーリーが面白かった。
それから月日が経ち、本記事の執筆時点ではバージョン7.2まで存続している本作だが、ストーリーに関しては度々不満の声が上がっており、公式の感想コーナーに強い不満意見を見かけることも珍しくない。
まあ、バージョン3以降のシナリオをほとんど全部ボロクソに言っているのは俺くらいだと思うが、安定して好評と言い難くなっているのは確かだ。
そんな中、どういうわけか一貫して高品質なストーリーが揃っているのが職業クエストだ。職業ごとに個別で存在する専用クエストで、ボリュームとしては長くて1時間程度の短編ばかりではあるが、文字通り笑いあり涙ありの傑作シナリオが揃っている。
それで、せっかく各シナリオが独立しているのだから感想を書くついでにランキング形式で発表しよう、というのが今回の記事だ。
今回の記事は詳細に書きたいのでネタバレに関しては一切配慮していない。
その点は理解して読み進めていただけると幸いだ。もしも未プレイで、途中で興味が湧いた場合は途中で読むのを止め、是非とも自分の手でプレイしてほしい。
ランクE:職業クエスト唯一の汚点
23位 スーパースター
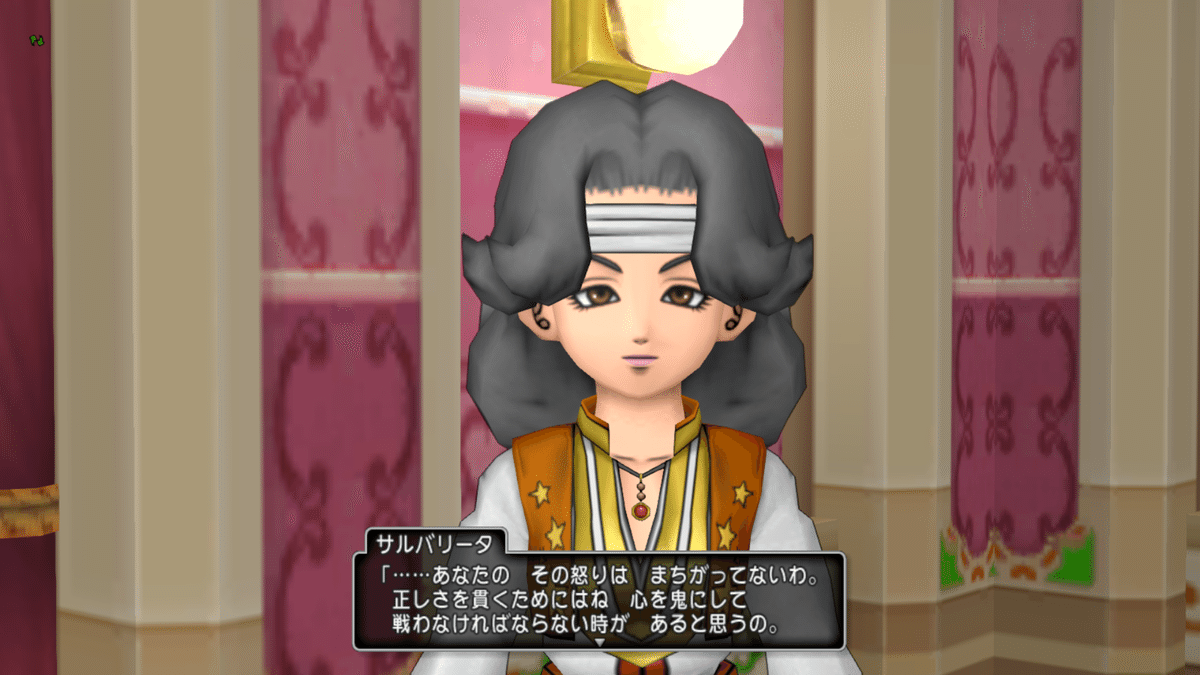
俺が珍しく絶賛している職業クエストのうち、唯一擁護不能だと思っているのが本クエスト、スーパースターだ。
このシナリオの何がダメかを端的に言うなら「スターの世界の厳しさ」の描写にひたすら失敗している、という点に尽きる。
物語の流れは、主人公が画像の人物サルバリータの弟子となり、トップスターを目指していく内容だ。そして、その過程で出会った天才ダンサー、プレシアンナを超えることが目標となる。
問題なのが中盤からの展開で、主人公はサルバリータに「スターの世界は厳しい。ライバルを蹴落とすことだって必要」と言われ、姉弟子であるクリスレイを潰すことを要求される。これが意味不明だ。

サルバリータ曰く、このクリスレイ潰しは「主人公に自信を付けさせるため」らしいのだが、そんな事をする必要が全く無いのだ。
この指示をされる時点で主人公は「才能がない相手とは話さない」と言われているプレシアンナから明確に才能を認められた一方で、クリスレイは認められなかった。既に主人公がクリスレイよりも格上なのは明らかだ。
と言うか勝利経験を与えることで自信を付けさせたいなら、その目的を本人に堂々と伝えるなよ。その時点で台無しだろ。
それで、この計画の内容を以下に記すが、これがまた無茶苦茶だ。
まずクリスレイに「あなたにはプレシアンナをも超える才能がある、だから今回の修行もクリアできる」と嘘を吹き込み、明らかに勝てない魔物と戦わせる
敗北したクリスレイが意気消沈している前で、その魔物を主人公が倒す
クリスレイに実力の差を見せつけることで主人公に自信が付く(?)
明らかに「主人公に自信を付けさせる」よりも「クリスレイの心を完膚なきまでに叩き折る」ことに特化している。オルゴ・デミーラが考えたのか?
こんな事を断行させられるので、俺は結構本気で「サルバリータの正体はスーパースターを絶望させ、その魂を食らう悪魔」みたいなオチでもあるんじゃないかと疑っていたんだが、別にそんなことはなく単にサルバリータが凄まじく無能だっただけだ。余計にタチが悪いだろ。

そして、クリスレイの受難は終わらない。
無能師匠の言いなりになった主人公に意味もなく心を折られた彼女は焦ってプレシアンナに挑み敗北、能力を奪われて二度と踊れない体にされる。
能力を奪われるって何だよと思うかもしれないが、俺が知りてえよ。
「スーパースターはダンスバトルで勝った相手の能力を吸収できる」なんて設定は本シナリオ中のどこにも出てこない。プレシアンナが本当に唐突に「能力を吸収する」と言い出し、当然のようにクリスレイの能力を奪う。
一応言っておくが、この時点のプレシアンナは普通の人間だ。
本シナリオの最後では、道を誤って魔物と化したプレシアンナとの決戦になるが、あくまで最終的に魔物になるだけだ。「プレシアンナは元々魔物だった」なんて描写はどこにもない。
なので「魔物としての邪悪な力でクリスレイの力を奪った」わけでもない。唐突に出てきた謎の設定によってクリスレイは再起不能にされた。

その後、クリスレイが再起不能にされたのを見た主人公が怒りの力で覚醒、スーパースターの最終奥義を習得する。シナリオ的にはクリスレイの能力を奪ったプレシアンナへの怒りのはずなのだが、多分大体のプレイヤーはこんな事態を招いた元凶のサルバリータに対して怒っていると思う。
何とも悲しいのが、クリスレイは普通に好人物であることだ。
まあ彼女が嫌われキャラだったら、この「クリスレイが潰された怒りで覚醒」が成り立たなくなってしまうから仕方ないのだろう。
それに、「トップを目指すためには、良き友ですら潰す必要がある」という葛藤のある展開を表現するためにも、彼女を好人物として描いた事自体は間違っていない。
ただ、その過程が本当にグチャグチャなせいで、サルバリータ・主人公・プレシアンナの三匹の魔物からクリスレイがひたすらボコボコにされるだけの、悲惨で胸クソの悪い物語にしかなっていないのだ。
一応、シナリオ終了時のエピローグではリハビリに励んでいる彼女の姿が描かれているので後に復帰した可能性もあるように描写されてはいるのだが、だったら「一生踊れない体になった」と言われていたのが何だったのか分からなくなるし、どっちみち物語としては詰んでいる。
これが本シナリオで表現したかった「スターの世界の厳しさ」なのか?
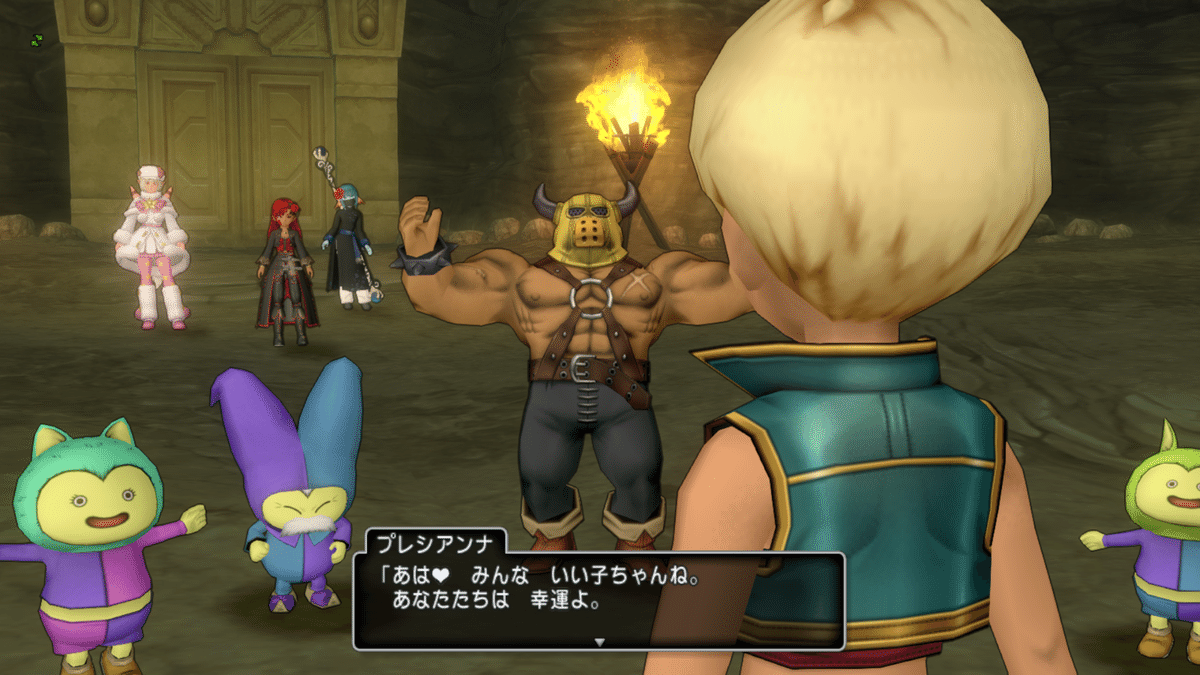
そもそもの話、このクエストではスーパースターをどういった存在として描きたいのか分からない。
主人公にとってのスーパースターは「戦うための職の一つ」のはずだが、本シナリオ中ではダンサーとしてステージで喝采を浴びる存在を目指すのが目的のように扱われている。
そのくせ実際にはダンスによって他のスーパースターと直接対決することはなく、ダンスの修行と称してモンスターとの戦闘を繰り返すだけだ。
そして結局、本シナリオは魔物化したプレシアンナを主人公が退治したことでハッピーエンドのような形で終わるのだが、その後に主人公がステージで喝采を浴びるような姿は描かれない。じゃあ何のためにプレシアンナを越えたんだよ。何のためにクリスレイは潰されたんだよ。
いわゆる芸能界の厳しさ的な物語を表現したかったのだろうとは思うが、それをドラクエの世界観と調和させることに完全に失敗し、どちらの方向から見ても何がしたかったのか分からなくなっている。それがスーパースターだ。
初っ端からボロクソに書いているが、明確にダメなのはこれ一つだけだ。信じてくれ。
ランクD:やや欠点の目立つ佳作
22位 魔法戦士

22位、職業クエストのブービー賞にしてDランク最下位は魔法戦士だ。
主人公はヴェリナード魔法戦士団の一員となり、不可解な魔物の出現から始まる事件の謎を追うこととなる。
国内を守るヴェリナードの衛士と、国際的な問題に対応する魔法戦士の関係を描く様子はヴェリナード国の解説としても機能しているし、本クエストで登場する「魔物商人」は まもの使いの職業クエストとも繋がってくる内容だ。本作の世界観を味わうにあたって、本クエストは重要な位置にあると言えるだろう。「面白そうな要素」自体は決して少なくない。
しかし、その内容は実際のところ今一つ盛り上がりに欠けたり、大きめのツッコミどころがあったりして、他の職業クエストと比較するとクオリティには難がある方だと感じた。
「その地域に居るはずのない魔物が現れた」との事件は、何か生態系が崩壊するような異常事態の発生を予感してワクワクしたが、実際には「悪人が外部から魔物を連れ込んだから」というだけで、まあ妥当ではあるが盛り上がりに欠けるオチだ。
魔物商人との対決に関しても、本クエストで出てくるのはザルギス一人だけだ。犯罪組織との全面戦争になるような大規模な話ではない。
ヴェリナード国全体が関わってくる物語でありながら、どうにも尻すぼみな展開になっている感が否めない。

魔法戦士団の副団長ユナティと、その義兄である衛士ノーランの関係性もまた本クエストの大きな要素だが、これが最大のツッコミどころだ。
本クエストの最後では、裏切りを行ったノーランの沙汰をユナティが任される。
ユナティは兄が相手でも私情を挟むことなく、ヴェリナードを支える魔法戦士としての誇りを守り、ノーランに対して重い国外追放の刑を言い渡す。そして、この物語は幕を閉じる。
ここまでは良いのだが、このクエスト終了後にユナティに話しかけると彼女は「罪を償ったノーランと、いつか魔法戦士として共に戦える日が来ると信じている」と口にする。
ノーランに対して「生涯、ウェナ諸島に足を踏み入れることは許さぬ」と宣言したのは彼女なのだが、その一分後にはこれだ。
まあ、おそらくは模範囚として過ごしていれば減刑されるような制度があって、ノーランに言い渡したのは「刑を終えない限りは」足を踏み入れさせない、という意図だったのだろうと解釈はできなくもないが、明らかに説明が足りていないせいでユナティが記憶障害を起こしたようにしか見えなくなっている。
プライベート時にノーランに対して「すごいよノーラン兄ちゃん!」と話すような萌え要素作りに力を入れる暇があったら、もっとやるべき事があっただろ。

それからノーランが魔法戦士を憎み、裏切りへと走った理由は「自分たちの町が襲われたとき、魔法戦士だった父は国外に遠征していて自分たちを守ってくれなかったから」と語っている。
この話の際、ノーランは始めのうちは「父が助けに来てくれると信じていたのに来てくれなかった」と残された側の辛さを語っていたはずなのだが、いつの間にかその話は「父が幸せだったのか分からない」との内容にシフトする。
そして、ユナティが「父は誇りを持って戦っていた。幸せだったはずだ」と語ることで話が終わり、最初に語っていた問題点が無視されたまま終わってしまう。
確かに国際的な問題に対処するのも重要なのは分かるが、「魔法戦士である父は肝心なときに自分たちを守ってくれなかった」との過去がトラウマになったノーランの気持ちは普通に理解できるし、だから国内を守る衛士になった彼の志は立派だったと思う。
「本来は誇り高い人物が闇落ちしてしまった、同情できる悪役」として彼は普通に納得できるキャラクター付けになっており、この点をもっと綺麗に解決してくれれば本当に良い話になれたと思うんだよ。
それが、ただ彼が魔法戦士に対する理解が浅かったかのような話で終わってしまうのはモヤモヤする点だった。
何だかこのクエストに関しても結構ボロクソに書いている気がするが、話の流れ自体はおおむね王道の内容として起承転結はあるし、ワクワクする要素もあったのは事実だ。
それから、最終的にノーランを無罪にして「罪を許す心が大切!」みたいな方向性に持っていかなかったのは本当に良かった点だと思っている。本作の本編ストーリーは大罪人が野放しにされ過ぎなんだよ。
色々と問題点は多かったが、根本的に話として成立していないスーパースターとは明らかに違う。
そのためスーパースターは単独Eランク、魔法戦士はDランクの最下位と表現している。
点数を付けるならスーパースターは3点、魔法戦士は40点くらいの差だ。
21位 盗賊

とりあえず、本クエストに「なんだって そんなに盗みを嫌うんだ?」とかほざいてくる狂人は登場しない。
主人公は盗賊ダルルの率いる義賊団の一員となり、トレジャーハント、あるいは魔物に奪われたアイテムを奪い返すなどの活動に参加する。
そして、義賊を憎む強盗団「つむじ風の旅団」との戦いにも身を投じてゆく……といった内容だ。
主人公たちを「義賊」としたのは妥当と言える。流石にドラクエ世界でも窃盗は犯罪なので、そこを平然と正当化しないのは当然だ。その当然ができていない作品があった気もするが、気のせいだろう。

意味不明な展開、唐突な設定などは無く、起承転結はしっかりしている。それなりに惹きつけられる演出はあったし、大きな不満は無い。
ただ、本クエストはとにかく地味だ。物語は中心人物となるブデチョの家庭の問題で完結しており、話の規模があまりにも小さい。
先述した「つむじ風の旅団」の首領はブデチョの息子チャムールで、彼は「母が病気になった時、薬を買う金は持っていたのに父は見殺しにした」との理由からブデチョを憎み、事件を起こしていた。
この「ブデチョが母(妻)を見殺しにした理由」が話の中核となるのだが、結局この答えは「盗んだ金を私的に使ったら義賊ではなくただの泥棒になるから使うなと妻に止められた」というものだ。
納得できない理由ではないが、普通に妥当すぎて何の驚きもなかった。
あと、主人公は一応ダルル盗賊団の一員となるのだが、作中では最初から最後まで単独行動だ。設定上は仲間も別の場所で活動しているらしいが、仲間たちで協力して悪と戦うような場面が無いため印象が薄い。
これも、盗賊という立場を考えたら大人数で動かないのは妥当ではあるのだが、物語として盛り上がらないのは分かるだろう。
盗賊クエストに限らず、ver1時代のシナリオは全体的に大きな問題点が無い代わりに強烈に惹き付けられる要素も少なく、淡々と進んで淡々と終わるものが多い。
逆に言うなら、大きな問題点の無いこのクエストが下から3番目である点からも、職業クエスト全体のレベルの高さを感じてほしい。
この盗賊クエストも、悪くはなかったんだよ。
20位 僧侶
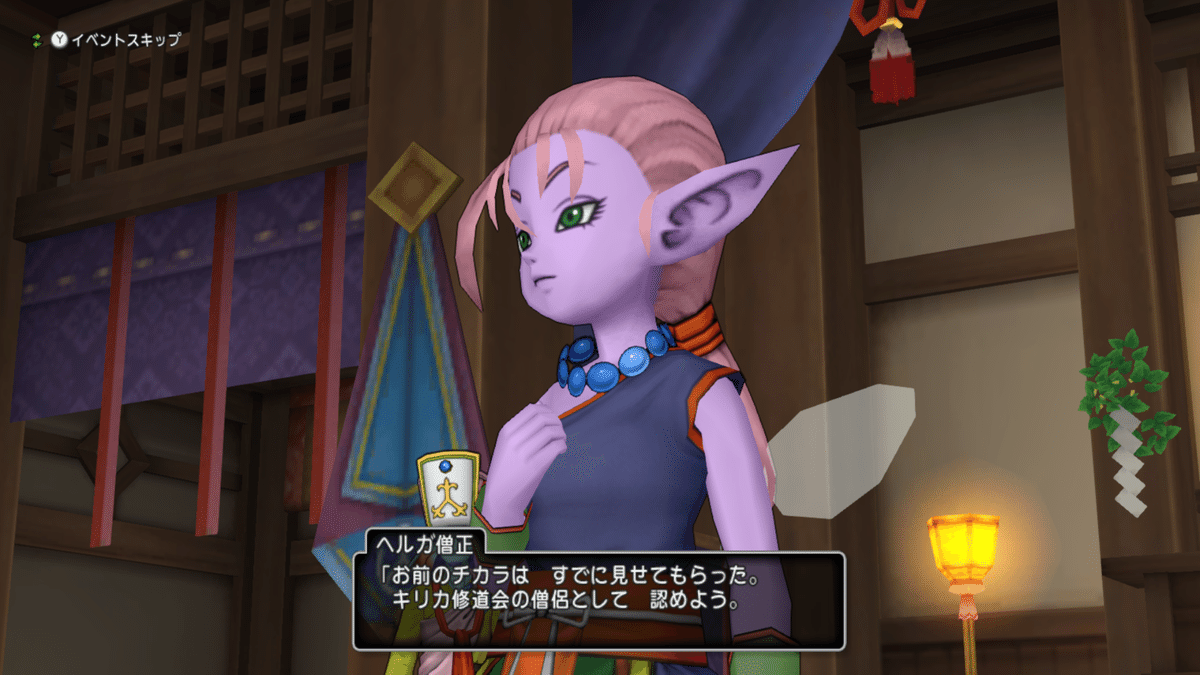
20位は僧侶だ。本クエストも盗賊と同じく「話の流れが妥当すぎて盛り上がらない」が欠点と言える。
この物語で主人公はキリカ修道会に入門し、「死神の息吹」と呼ばれる伝染病に抗うために奔走する。
そして、閃香樹なる香木が特効薬となることを知るも、これは300年も前に絶滅しており、唯一現存しているのはエルドナ神の宿る木彫りの神像のみ。
病から人々を救うため、この神像を砕いて火に焚べるか?焚べないか?
……というのが、本クエストの物語だ。
普通に考えて、焚べない選択肢は無いだろ。
死神の息吹は一度広まれば世界中を巻き込んで大量の死者を出す病と語られており、明らかにキリカ修道会が「神像は大切なものだから嫌」と拒否していいような規模の話ではない。
これが仮に、身内の一人や二人を見捨てれば解決する問題だったなら「私情で神像を破壊するか、信仰を優先して彼を見捨てるか」の葛藤を描けたのだろうが、死神の息吹の規模が大きすぎるせいで「私情と関係なく、普通に使命としても神像を焚かなきゃダメでしょ」と感じる展開になっており、プレイヤーが葛藤する余地がほとんど無いのだ。
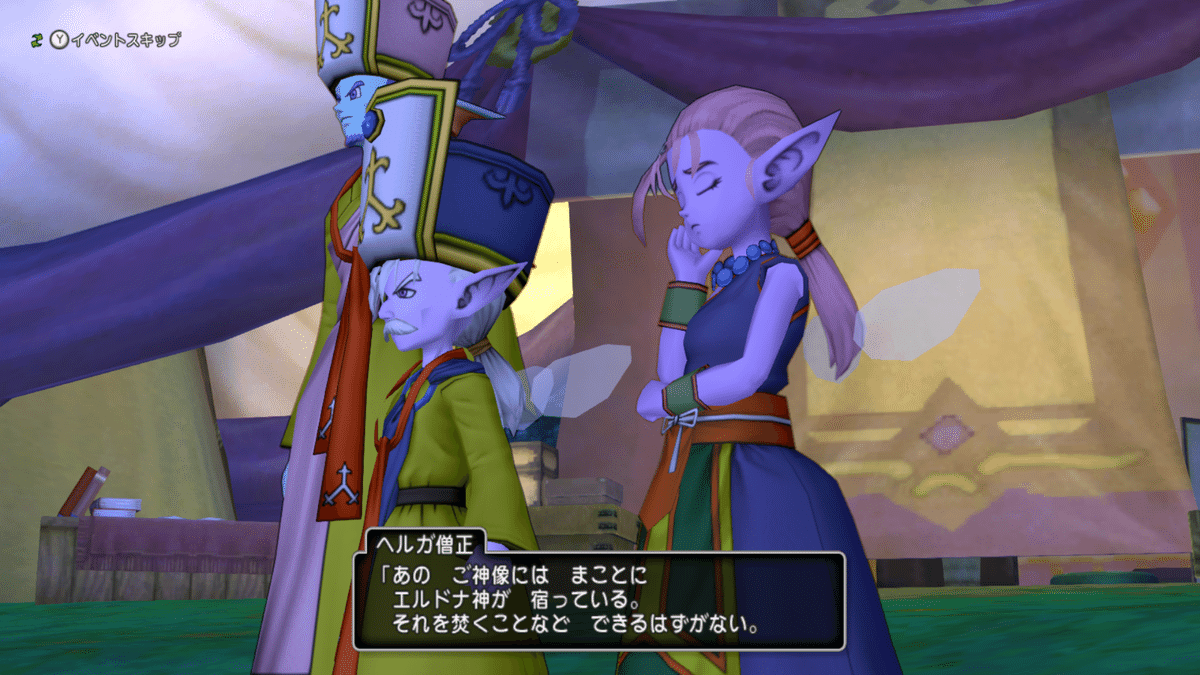
結局、主人公が独断で像を焚いた事で病は根絶されるのだが、この件を知った大僧正は「この大罪人を捕えよ!」と口にする。
ヘルガ僧正たちの説得によりこの発言はすぐに撤回され、大僧正も考えを改めるのだが、これじゃ大僧正がただのアホじゃねえか。
と言うか、神像が疫病に効く希少な香木で作られているなんて「いざとなったらこの像を焚け」と最初から意図されているようにしか考えられない。書物とかで目的・用途が伝わっていてもおかしくない話だが、そんなものは出てこない。この修道会、もうダメなんじゃないか?
まあ、そうしたキリカ修道会の杜撰な体制や、融通の利かない考えを主人公の行動が正した……という物語なのは分かるし、おそらく彼らにとって神像が本当に大切な物だったのだろうとも思うのだが、キリカ修道会の側がひたすら無能になっているのが何だかスッキリしない話だった。
あと、これは本シナリオと直接関係ない部分だが、本作ではver4シナリオで主人公がエテーネルキューブを入手して以降結構気軽に時間跳躍が可能になっており、実際に「現代では残っていない物だけど、お前なら過去に行けるから平気だろ。取ってきてくれ」と、コンビニにでも行くような感覚でタイムリープさせてくるクエストも登場している。
(何ならver1時点でも過去に戻る前提のクエストはあった)
なので、今になって本クエストを見ると「過去世界で閃香樹取ってくれば数分で解決するな…」と思えてしまうのが虚しい話だ。
19位 バトルマスター

主人公は飲んだくれのろくでなしバトルマスター、ジェイコフに弟子入りする。そして彼の借金の返済を手伝わされたり、依頼された仕事をこなすうち、コロシアムに渦巻く陰謀に巻き込まれていく…といった物語だ。
ライバルとなる先輩の闘士セインズの登場、危機に陥った主人公のもとに現れる謎の仮面闘士など、ワクワクさせる要素はそれなりにある。仮面闘士の正体は割とバレバレだが、そこまで含めて楽しめると言っていいだろう。
ただ、このシナリオには一つ大きな問題がある。
本クエストの終盤では主人公とセインズが決闘し、主人公が勝利する。そして、ジェイコフはセインズが負けた理由として「真のバトルマスターとは他の誰かのために戦う者。自分の強さしか見ていないお前では主人公に勝てないのも必然」と語る。
これ自体は少年漫画でよくある内容だと思うが、何が問題かと言うと本クエストにおける主人公は基本的に自分の身に振りかかった火の粉をひたすら払っていただけで、言うほど他の誰かのために戦っていないのだ。
そのせいで、シナリオの最大のテーマらしき部分に疑問符が付く内容になってしまっている。
せっかく物語にテーマを掲げているのに、実際の内容がそれに即していないのは大きな残念ポイントだった。
18位 海賊

主人公はマドロック船長率いる正義の海賊団の仲間となり、伝説の海賊が遺したとされる宝の地図を、そして記された海神の秘宝を探して駆けずり回ったり、無法なハルバルド海賊団と対決したりする物語となっている。
このクエスト最大の問題点は、何と言っても主人公が一度として海に出ないことだ。
「以前の戦いで船が破損して海に出られない」との理由で、本クエストの舞台は最初から最後まで地上で完結しており、大海原を冒険することは一切無い。これじゃただの探検家だ。
一度も航海していないのに「お前は海賊に収まるような奴じゃない」と言われたって困るんだよ。まず収まる機会が来ていない。
一応、先述のように「宝の地図」「悪の海賊との抗争」といったポイントで海賊らしい雰囲気を出そうと頑張っているのは感じられるし、終盤には中々大掛かりな疑似航海ギミックも登場する。なので竜骨が折れている割には案外海賊の物語としての体は保っている。
マドロック船長は普通に頼れる人物だし、「不確かな物を探すのにうってつけの存在が海賊」として、彼らの旅がこの先も続いて行くのを示して終わるのは中々良い締め方だった。
それでも、根本的な物足りなさを払拭するには至らなかった感がある。

それから、本クエストの主要人物となる魔法戦士のゲーダムに関わる描写については、色々とスッキリしない点が多かった。
彼は「海賊の抗争に巻き込まれて弟が死んだ」との理由から海賊を憎んでいる。なので海賊の一員となった主人公に当たりが強いのは仕方がないとしても、無関係な人物にまで横柄な態度なのは普通に心象が悪い。こいつのせいでヴェリナード魔法戦士団の品格まで下がってるんじゃないか?
そして物語の終盤では、実はゲーダムの弟は死んでおらず、マドロックたちに救助されて海賊の仲間に加わっていたことが判明。これで彼らは和解するのだが、本当にこれで良かったのか?
弟が海賊生活をエンジョイしていたとは言え、海賊の抗争が原因で彼らの人生が狂わされたこと自体は事実だ。一歩間違えば普通に死んでいてもおかしくなかっただろう。
なのに結果的に弟が助かっていたからめでたしめでたし、で終わらせるのは根本的な問題を有耶無耶にされた感がある。
まあ、海賊の抗争とは言っても吹っかけているのはハルバルドのような無法な海賊たちで、マドロックたちが周辺被害上等で戦っていたわけではないと思うが。「結果的にとは言え、無関係な人々を巻き込んだこと」自体には、もう少し向き合ってほしかった気がする。

それから、これも本クエストが悪いわけではないのだが、マドロックが一般人間男性キャラの体型そのまんまのせいで中途半端にしょぼくれた外見になっているのは地味な不満点だ。
もっとガタイの良い男のモデル用意してやれよ。
17位 踊り子

主人公はカリスマ踊り子ラスターシャの合方となり、二人で踊り子の伝説を築く……はずだったが、ラスターシャは除霊踊りにより悪霊と戦う使命を背負っていることが発覚。
主人公はラスターシャと共に除霊踊りを極め、悪霊の王である黒怨王との戦いに挑んでゆく。
本クエストにおいて最大の長所であり、同時に最大の短所でもあるのが、この除霊踊りだ。
一体どうやって踊りで戦っているのか不明瞭だったスーパースターと違い、こちらでは「踊りによる除霊」との形にすることで、比較的違和感なく踊り子の戦いを描いている。これ自体は良い設定だ。
最初は踊り子としての修行から始まりつつ、ラスターシャの使命の判明を経て巨悪との決戦に向かってゆくストーリーの展開も違和感はない。単品のストーリーとしては十分に楽しめる内容だった。
それから主人公たちのプロデューサーとなるナッチョスがひたすらに良い男で、舞台に立ちもせずに悪霊との戦いに明け暮れる主人公に嫌な顔一つせず応援してくれるのが非常に温かい。
そういった点から「悪と戦う」ドラクエとしての楽しさは十分あったが、踊り子のクエストとしては色々と不満があった。
明らかにシナリオの内容が除霊に寄りすぎて、踊り子要素が置いてけぼりになっているのだ。このクエストでも主人公が舞台に立つことは一度もない。
一応ラスターシャが「踊り子として舞台に立つ喜び」を語ってくれはするが、俺はその喜びを味わってないんだよ。スーパースターに引き続き一回も舞台に立たせてもらえないまま終わったからな。
特に、本作は「踊り子」という職業のコンセプトが大きく変わった作品だ。
過去のドラクエにおける踊り子は、直接戦闘が苦手な代わりに踊りで敵を妨害するサポーター的な職業だった。
対する本作の踊り子は、補助能力を持ちつつも二刀流による物理攻撃と炎系呪文を使いこなすアタッカーとしての側面が強くなっている。過去作のイメージで転職すると、その攻撃性能の高さに驚かされるだろう。
後に紹介する賢者や遊び人などはこの新しくなった職業イメージを職業クエストで描いており、物語を楽しみつつ「過去作とは違う性能になっている」ことを学べたのだが、踊り子ではそれがない。
特に本作の踊り子は踊りだけでなく歌唱もこなす職となったのに、職業クエスト内で歌が話題になることが一切無いのは残念な点だ。
この頃の本作にはボイスも無かったし、アクションを見せることもできない歌はムービーでの描写が面倒だから省かれたのだと思うが、少しくらいは焦点を当ててほしかったと思う。
ランクC:安心して楽しめる良作
16位 レンジャー

主人公は自然保護団体のような立場となり、森の平和を守るために戦う。
本クエストで印象的なのは、何と言っても主人公に宿る精霊スピルだ。
「森の精霊」のイメージにそぐわない真っ直ぐな熱血漢で、主人公の相棒として活躍してくれる。
メタ的に言ってしまえば彼は「主人公の代わりに喋ってくれるキャラ」だが、一貫して主人公を相棒として信頼しているのが伝わるし、必要以上に出しゃばって主人公のお株を奪うこともないので本当に印象が良い。
主人公を徹底して空気化させて新キャラだけで勝手に会話を進めるver4以降の本編シナリオとは大違いだ。
しかし、わざわざランクを一つ上げておきながら似たような批判をするが、本クエストにも問題点が2つある。
一つは中盤に敵対する伐採同盟だ。
当初、主人公たちは違法な伐採を行う彼らと敵対するのだが、後に彼らは「仲間たちを守るために仕方なく伐採をしているだけで、実は悪い人たちではない」と判明する展開になる。
しかし、事情はあれど彼らが違法な伐採を行っていたのは事実だし、何より最初に主人公たちに伐採を目撃された同盟員は伐採マシンに主人公を襲わせてきた。脅かして追い払う程度のつもりだったのかもしれないが、もし主人公が弱かったら普通に死んでいてもおかしくない。
そんな凶悪犯を抱えている団体を「実はいい人たちでした」で済ませるのは、いくら何でも無理がある。
そして、もう一つの問題は非常にシンプルだ。
本クエストの終盤では、暴走した伐採マシンが出火して森が火の海となり、怒った森の精霊たちと争う展開になる……のだが。
もう、「人間の愚かな行いに偉大な自然が怒る!」なんて展開はいくら何でも使い古されすぎていて、根本的にワクワクしないんだよ。
とは言え最終的に、スピルがその身を呈して森の精霊たちを鎮める展開は決して悪くなかったし、最後の台詞の演出には素直に感動できた。
それに、結果的に解決するのがスピルとは言え、そこにはスピルが「人間たちは愚かな者だけじゃない」と信じるに至った、主人公たちレンジャーの活躍が確かにあったのを感じさせる展開になっていた。
だから物語としては十分に楽しめた一方で、どうしても若干の説教臭さと飽きを感じずにはいられなかったのも事実だ。この手の「自然の怒り」的なストーリーに初めて出会った子供なら心から感動できるのかもしれない。
とにかく、伐採同盟に関する描写だけはもう少し何とかしてほしかった。そうして考えると、本当に色々と惜しい話だったと感じる。
15位 戦士
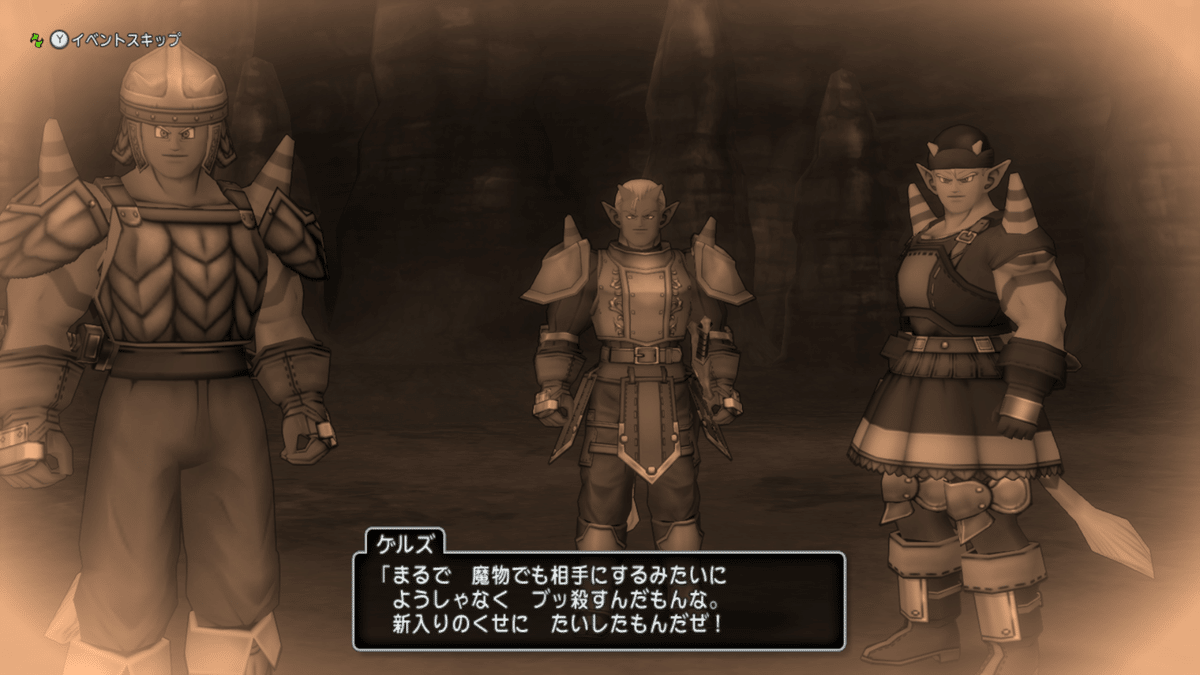
主人公は謎の老人アガペイの弟子となり、「ある戦士の記憶」を辿りながら戦士としての修行を積んでゆく。
ただ魔物を倒すだけの内容かと思えば、初っ端から「この戦士には魔物と同じに見えていただけで、実は違った」と明かされる演出には多くのプレイヤーが驚かされるだろう。
かと言ってそのオチだけに頼った一発屋的な内容のクエストではなく、起承転結のしっかりした堅実な物語だ。
修行を積み、師となったアガペイの過去を打ち破り、最後には自分自身の闇をも超える。
良くも悪くも「アガペイによるプレイヤーの修行」に終止しているため物語の規模としては最小クラスだが、決して浅くはない。戦士という無骨な職業のクエストとしてしっかり完成された、必要十分な物語だ。
ただ、クエストの進行が「指定の場所に移動して戦闘したら終わり」ばかりで、いくら何でも単調すぎるのはもう少し何とかならなかったのかと思う。
それから「違う運命を選ぶ」場面で、同じムービーを頭からもう一度スキップ不可で見せられるのは流石に手抜きを感じた。
何でもかんでも派手に盛り上げれば良いとは思わないが、ローコスト感があまりにも浮き彫りなのは放置しないでほしい。そんなことを感じる内容だった。
14位 まもの使い

主人公は「亡き夫に代わり、魔物使いという職業を広めたい」と願う未亡人クラハの願いを叶えるため、魔物使いとして仕事をこなしてゆく。
そして、クラハの息子ファーベルや、その周囲に渦巻く大きな陰謀との戦いに巻き込まれていく。
DQM3の記事でも書いたが、ドラクエには「魔物は悪いやつなので、躊躇なくやっつけて良い」という価値観が前提として存在する。
しかし、昨今ではモンスターの人気上昇もあって「魔物にだって良い奴はいるし、普通に人間と同じように生きている」描写が増加してきた。
この相反する価値観の問題が放置されているせいで、DQM3では「人間たちに虐げられ、魔族の王子ピサロや魔物の友人たちと共に過ごしているロザリーが、魔物はどれだけ殺されても眉一つ動かさないのに人間が傷付けられると嘆く」という、とんでもないサイコパスと化す事態が発生していた。
本クエストは流石にここまで酷くはないが、この「魔物という存在をどう扱うか」について歪さが残る状況を解決しきれていなかった感が拭えない。
最も気になったのが、シナリオ中盤で「トガスのぬし」の退治を依頼される場面だ。
このトガスのぬしが、人を傷つけている等の悪行は語られない。ただ、「採取をするのに邪魔だから退治してくれ」と依頼され、そのまま主人公が退治して終わる。
仲間にするとか、せめて追い払うだけに留めるとか、そういった方法はなかったのか?
本ストーリー中では「モンスターとの絆」を描いているが、結局のところ人間にとって邪魔な魔物は機械的に処理されるのかと思うとスッキリしない話だ。

それから、第一話の「もんもん モーモン訪問」の内容も非常に惜しいと言うか、ドラクエにおける魔物という存在の扱いの難しさを感じた。
このクエストでは病床の女の子を元気付けるため、その女の子が好きな魔物であるモーモンをプレイヤーがスカウトし、連れて行く。
結果、女の子は喜んでくれるが、帰ってきた母親から「魔物を連れ込むなんてどういうつもり!?」と激怒され、追い出されてしまう。
「前提として、魔物は多くの人にとって恐ろしい存在である」と描写するのは魔物使いのクエストとして間違いなく必要な描写だったと思うし、それ自体は良い点だ。
ただ、このモンスターがマスコット的な外見であるモーモンとなっているせいで、どうも「たかがモーモンごときで大騒ぎする母親」だけが悪者のような形で目立ってしまっている感が否めない。
実際のところプレイヤーだって低レベルでモーモンの群れに襲われたら死にかねないし、モーモンと言えど野犬くらいの危険性はあるのだろう。だが、この画面を見てくれよ。このモーモンを見て震え上がる母親に心から感情移入できるか?
例えばこれが、キラーパンサーとかバトルレックスのような見るからに強そうな魔物だったら、母親の側にも十分共感できたと思う。
まあ、このクエストは仲間モンスターをスカウトする事のチュートリアルも兼ねているし、高レベルのモンスターを対象にはできなかったのだろう。
だから色々と仕方ないとは思うのだが、今一つ物語に入り込みにくくなっている感は否めない。

そうしたモンスターの扱いに関する難点を背負わされているのが困ったクエストではあるが、ストーリーの内容そのものは良好だ。
師匠とも言えるメドウに認められたり、ファーベルが段々と主人公に心を開き「自分はどんな道を選ぶべきか」と苦悩し、答えを出してゆく様子は素直に応援したくなる。
特に話の構成として上手いと感じたのが、ファーベルの相棒であるキッズを第2話でプレイヤーが借りる展開だ。
キッズの潜在能力を描写しつつ、プレイヤーもキッズと共に仕事をした仲になることで、その後ファーベルが「キッズと別れるか否か」で悩んだり、絆を取り戻す展開が他人事ではなくなり、感情移入しやすくなっている。
あと、最後にメドウが出てきて敵の主犯格を捕まえてくれるのは本当にスッキリした。本作は悪党が野放しにされるパターンが非常に多いので、俺は「まさか結局ここで敵を逃して終わらないよな…?頼む!ババア来てくれ!!」と思っていたら本当に来てくれたのが嬉しかった。
登場人物はしっかり魅力的に描かれているし、プレイヤーを違和感なく物語に入り込ませるような工夫もされている。
それだけに、根底に存在する「魔物の扱い」を解決しきれていなかったのが惜しい内容だった。
13位 どうぐ使い

主人公は、新たなる職業「どうぐ使い」を生み出したと言う人物デルクロアの弟子となり、最強のどうぐ使いを目指してゆく。
本クエストだが、上のあらすじのアッサリ感からも分かるように話の規模は非常に小さい。
登場人物はデルクロアと、その相棒のタンス、そしてデルクロアと敵対している魔界の貴族の使いゴルゴンザの3人だけで、残りは名無しの魔物くらいしか登場しない。
クエストの進行も、「魔物が襲ってきたので倒しました」くらいで、物語としては地味極まりない。
ただ、その中でも登場人物は魅力的に描かれている。
デルクロアの「元から強い奴を強くしても面白くない。弱い奴でも戦えるから道具は面白い」との主張はダイの大冒険のロン・ベルクを彷彿とさせる信念を感じるし、ゴルゴンザとの決着後の彼の台詞は一般的な価値観であれば失礼な表現でありながら、デルクロアにとっては最大の褒め言葉であることがよく分かる。

それから敵となるゴルゴンザも、少ない出番ながらその人格がしっかりと描かれている。
彼は「どうぐ使いの研究なんて無駄だ」とデルクロアに否定的だったが、無意味にデルクロアを痛めつけるような事はしていない。
そして、どうぐ使いの研究成果をしっかりと確かめた上で、その価値を最終的には認めている。
結局デルクロアと彼が和解することはないが、あくまでゴルゴンザは「自分たちの軍事力を強化する」任務に忠実なだけで、ただの乱暴な石頭ではない人格が伝わってくる描写だった。
せっかくキャラクターは魅力的なのだし、二人とも魔界絡みのシナリオに大きく関わらせてくれても良かったんじゃないかと思う。
色々あって雇い主の貴族と敵対したゴルゴンザが、デルクロアに頭を下げて共闘する展開とかあれば絶対面白いと思うんだが。
12位 賢者

賢者となった主人公は、落第寸前の新米賢者アーニアの手助けをすることになる。彼女にはシェリルという優秀な友人がいるようだが、ここ最近は酷く荒れているらしく、シェリルのことが心配でアーニアは自分の研究も手につかない状態らしい。
主人公はそんな彼女を手助けするうち、彼女の友人シェリルとの間に起こった事件、そして賢者たちに迫り来る邪悪な存在と相対することになる。
踊り子クエストの際に言及したが、まず本クエストの良い点は「刷新された賢者」のイメージに言及している点だ。
賢者という職はDQ9で職業が再デザインされ、光と闇の魔法を専門に扱う職となった。本作でもその設定が引き継がれている。
本クエストではその設定に言及があり、「宇宙の理の深淵に横たわるのが闇。それを知らなければ賢者として大成できない」と語られている。
こうした、新しい職業の設定をしっかりと掘り下げてくれるのは嬉しい点だ。「光と闇を理解する」という設定も、ただの魔法使いとは違う賢者の特別さを感じさせてくれる。

それから、本クエストのボスは「魔賢者アクバー」だが、この配役は中々面白い。
アクバーと言えばDQ6で登場したボスだが、お供のガーディアンをザオリクで復活させてくるのが厄介な相手だった。「アクバーと言えばザオリク」と覚えているプレイヤーも多いだろう。
このザオリクだが、DQ9及びDQ10では僧侶が習得できなくなり、賢者の専用呪文のような扱いとなった。
(10では武器スキルとして天地雷鳴士も習得可能になったが、レベルアップの基本呪文として覚えるのは賢者のみ)
「ザオリクと言えば賢者」とした上で、元々ザオリクの使い手であるアクバーを「魔賢者」として登場させたのは、新しい賢者の設定を上手く組み込んだ面白い演出だ。

そしてストーリー面だが、主役であるアーニアとシェリルの魅力はしっかり伝わる内容だ。
落ちこぼれだが素直に他人を頼ることができるアーニアと、優秀であるが故に一人で全てを背負い込んで追い詰められてしまうシェリルは分かりやすく対照的で、二人が互いにとって無くてはならない存在であることがよく分かる。
また、終盤ではアーニアもそれなりに頼れる姿を見せてくれるようになり、「あくまでシェリルが心配で自分の研究も手につかない状態だったから落第寸前だっただけで、アーニアも(あまり優秀ではないにせよ)賢者として足るだけの実力はある」ことが感じられるようになっている。
アクバーを倒し、彼女たちが再び親友として歩み出す結末は素直に喜びを感じられる、良い話だった。
ただ唯一スッキリしないと言うか、肩透かしに感じる部分もあった。先述の、アーニアが「心に闇を持たないから大賢者になるのは不可能」と言われた件だ。
心に闇を持たないと言うのは、つまり「悪い心を持たない」ような意味に思える。実際、アーニアは素直で元気な子なので、そう考えて納得できた。
だから、俺はここから「賢者を極めるために闇(悪い心)を持つべきなのか?」と葛藤するような展開が来るのかと期待していたんだが、実際はそうした精神的な話ではなく、「心の闇」というのは単なる闇のエネルギーのような扱いで終わってしまった。
この辺りの掘り下げもしっかり行ってくれていれば最高だったと思うと、ちょっと惜しく感じる気持ちがある。
11位 天地雷鳴士

主人公はカミハルムイの天地雷鳴士アサヒのスカウトを受け、天地雷鳴士の陽衆として仕事をこなしてゆく。
その中で、彼女の友人だった陰衆のヨイ、そして天地雷鳴士という組織の過去と向き合い、カミハルムイに迫る危機に立ち向かってゆく。
中心人物となるアサヒ、ヨイの二人はどちらもクセが無く可愛い・美人なデザインになっているし、深夜アニメ的なキャラクター付けもあって公式がかなり「オタクを狙ってきた」感の強いクエストだ。
ver4以降のドラクエ10において、露骨に男性オタク向けを感じさせるストーリーはオオクワガタくらい珍しいので、どうにも異質さを感じる。
とは言え決して雑にキャラクターの可愛さを見せるだけの内容ではなく、アサヒとヨイを通じて描かれる陽衆と陰衆の関係や、大幻魔テンオツキジンの設定などはしっかり作り込まれているのを感じた。要所の演出も全体的に気合が入っており、本気で当てに来ているのは伝わってくる内容だ。
ちゃんとアサヒは可愛いし、ヨイとの複雑なトラブルを乗り越えて和解、力を合わせて大災害を打ち払う展開はしっかりと熱かった。
物語の主役は明らかにこの二人だが、アサヒが主人公によく懐いていることと、主人公を「陰と陽を併せ持った存在」とすることで一定の存在感は保たせている。
本クエストの実装時期はver4らしいが、ちゃんと最後の大災害を払うシーンで主人公も手を貸しているのは本当に好印象だ。この頃の本編ストーリーだったら確実にラストはアサヒとヨイの二人だけ映して主人公は棒立ちだったからな。

不満点としては……何度も似たようなことを書いているが、ゲーム上の職業要素がやや置いてけぼりになっている点だ。具体的に言うとカカロンやドメディなどの、実際に主人公がゲーム上で使役する幻魔は本クエストに一切登場しない。
これらの幻魔が主役になっていればクエストを通じてプレイヤーに幻魔への思い入れを持たせることもできたと思うし、ひっそりとキャラバンハートのプレイヤーに対するファンサービスにもなったと思うので、この点は本当に勿体なく思う。
あと、ヨイが主人公を襲撃した件について結局最後まで一言も謝らなかった件については地味ながら根に持っている。
これはもう本編シナリオなど全てに言えることだが、近年のドラクエでは犯人が悪事を反省したらその時点で罪が精算された扱いになり、迷惑をかけた相手に謝罪しなくても大団円扱いになる傾向がある。
酷い場合だと反省すらしていなくても大団円になるので(例:ムニエカの町)それと比べたらマシではあるが、これは本当に全然直らないのが悲しい点だ。
ランクB:自信を持って勧められる傑作
10位 旅芸人

主人公は旅芸人ポルファンの弟子となり、笑いの道を極めるために修行をしてゆく。その最中、旅芸人が次々に行方不明となる事件を知らされ、主人公自身もその事件に巻き込まれてゆく。
とりあえず、本クエストでも主人公が人々を笑わせて喝采を浴びるようなシーンは無い。たかが脇道に過ぎないクエストでモブを大量に並べたムービーシーンを作るのが面倒だからなのだと思うが、芸人系のクエストで主人公が全くお客さんの相手をしないことが一貫しているのは残念な部分だ。
ただ、本クエストは敵との戦いにおいて一応「芸で笑わせ、人を救う」ことを描いており、その点では不満が最も少なかった。
主な登場人物は先述のポルファンと、敵となる悪魔道化師ゲイザー、闇芸人ルルルリーチの三人だが、寂しげな様子で過去を語るポルファンに加え、敵側の人物もしっかり魅力的に描かれている。
ゲイザーは、師であるポルファンが病気の母を救えなかったことから「芸で人は救えない」との考えに陥り主人公と敵対するが、その中でも真面目に修行をして正々堂々と主人公に勝とうとしており、元は真っ直ぐな奴だったのがしっかりと伝わってくる。
最終的に、味方だった魔物から切り捨てられて致命傷を負ったゲイザーを、主人公が笑わせて「芸で人は救える」と伝える場面は、相変わらずムービーにおける主人公の棒立ち問題が発生している以外は感動的だった。

そして、最後の敵となるルルルリーチとの戦いが、本シナリオを特に深みのあるものにしている。
彼は「自分の方がセンスは有ったのに、魔物だから評価されなかった」との理由で他の旅芸人たちを憎んでいる。何だか無能な奴の嫉妬みたいな理由だが、実際に彼はポルファンからも才能があったと認められているので、種族による差別が原因というのは本当なのだろう。
戦いの決着後、ルルルリーチは主人公に対し、「あなたは自分の才能が認められなくても、笑いの道を極められるのか?」と問いを残してゆく。結局彼は「無理に決まっている」との考えを曲げないまま散ってゆき、救われることはない。
ゲイザーは笑いによって救われた。笑いによって人が救われる例がある、というのは確かに間違いない。だが、もしも本シナリオがそれだけを理由に「笑いは人を救います!笑い最高!」と短絡的なハッピーエンドに持ち込んでいたら、どうしても薄っぺらな印象になってしまっていたと思う。
そこで救われたゲイザーと対比して救われないルルルリーチを描き、最後に「本当に笑いで人を救えると信じ続けられるのか?」の回答をプレイヤー自身に委ねて終わる。これが本クエストの、本当に味わい深い点だと思う。
初期のサブクエスト故の規模の小ささや演出のショボさ等の問題はあるが、安直なハッピーエンドでもなく、かと言ってただの救われないバッドエンドでもない、深みのある物語だった。
しかし、俺にとってこの話が刺さるのは単に俺自身が売れない芸人やってるせいのような気もするが、深く気にしないようにしよう。
9位 パラディン

この物語はドラクエ10という作品の、良い所も悪い所も詰まったストーリーだと感じる。
まず、これはシリーズ全般に言えることだが、ドラクエは可愛げのあるデザインに反して割と普通に死人が出るのが特徴の一つだ。
グロテスクな描写があるわけではないが、「戦いは遊びじゃない」ことを誤魔化さない。そんな一定の厳しさがあるのがドラクエの世界観だ。
本クエストは主要人物となるズーボーがツボの運搬作業から帰還したところから始まり、次は主人公とズーボーに犬の散歩の仕事が任される。
ズーボーの「なのだ」口調や純朴な人物像も相まって、最初はこうした「小さいけれど大切な仕事」をこなしていく、ほのぼの系のシナリオのように見える。
だが、その次の任務から露骨に不穏な空気が漂い始め、少女一人の対価として動く大金、何か隠し事をしている様子のジェニャ、ジェニャを心配しつつも深入りできないズーボー……といった描写は、何となく先の展開の予想が付きつつも退屈さを感じさせない。
そして、ジェニャは大地の竜に捧げる生贄だと明かされる。
その事実が判明してからの展開は決して派手で重厚な演出があるわけではないが、各キャラクターの言葉の節々から葛藤が伝わってくる。
そこから結末への流れもドラマチックで、決してハッピーエンドではないが未来への希望を感じさせる締めは良い意味でドラクエらしい、厳しくも優しい物語に仕上がっている。

じゃあ、このクエストの何が悪いのかと言うと肝心な場面で演出が全く足りていないことだ。
本クエストの終盤では、いざ生贄となる時に「もっと生きたかった」とジェニャが溢す。そして、それを聞いたズーボーが大地の竜と戦う決断をする。そして、主人公が戦闘を終えると……これだ。
これはジェニャを庇ってズーボーが大地の竜の呪いを受けたことで石化したらしいのだが、その間の描写が一切ない。戦闘が終わったらいきなり謎の石柱の前でジェニャが嘆いており、この石柱がズーボーの変わり果てた姿だと言われる。
これでは今一つ盛り上がらない……どころか初見ではそもそも何が起こったのかが分からず、肝心なシーンで困惑が先に立ってしまった。
例えばこれが、「戦闘中、ズーボーの体が徐々に石化していくことに周囲が気付き、皆が『もういい、逃げろ』と彼を止めようとするが、ズーボーは頑なにジェニャを守り続ける」……なんて描写があれば熱かったと思うし、あるいは「無事に戦闘が終わり、大団円かと思われたところでズーボーが突然石化」なんて形でもショッキングなシーンとして印象付いたと思う。
この、本クエストで一番と言っていいくらい重要なシーンの演出がおかしいせいで色々と台無しになっているのが本当に悔やまれる点だ。

あと、以前の記事でも書いたがシリアスな場面に余計な茶化し要素を入れてくるのは本当にやめてほしい。笑えねえんだよ。
8位 魔剣士

主人公は「つるぎの酒場」の店員アガサの依頼を受け、心の闇から生まれる魔物「ダークネス」との戦いに身を投じてゆく。
そして酒場で最も腕利きと言われる魔剣士ディゼルの因縁の相手、邪毒のウィーヌムとの争いに巻き込まれてゆく。
まず本クエストの良い点として、主人公の過去が物語に関わってくる点だ。この物語では「魔剣士とは心に大きな痛み、闇を抱えた者」とされており、序盤のイベントで本編ストーリーの開幕で主人公の村が滅ぼされた悲痛な経験のトラウマを描写している。
そして、そんな心の痛みを知る者だからこそ主人公は強い魔剣士になれる、との理由付けにも活用している。
ちゃんと物語上における主人公の設定を活用しているのは素晴らしい。本編ストーリーも見習ってくれ。

心の痛みなんてものを題材にしているだけあって本クエストのシナリオは全体的に陰惨で、その元凶であるウィーヌムはドラクエシリーズ全体で見ても相当上位に入るであろう邪悪だ。
こいつは人を絶望させ、そこから生まれる魔の波動を好物として食らうのだが、その最高の魔の波動を得るためにディゼルの両親を殺害し、彼が自分への仇討ちに来るように仕向けた。だが、彼はそこにもう一つ仕込んでいた。
いざディゼルとの戦いになった際、彼は「自分は両親と喧嘩していたディゼルの負の感情を増幅させただけで、実際に両親を殺害したのはディゼル本人」と明かす。そうして、罪悪感により心の底から絶望したディゼルの絶望を食らった。
人を絶望させるためだけにここまで手の込んだことをやったのは、他だとDQ7のボトクくらいだろう。ひたすらに邪悪ながらも、人間の行動を読んだ上で意のままに操る周到な計画を練っている点には感心すら覚える。
そして結局こいつはディゼルの絶望が予想以上だったことで魔の波動を食いすぎて自爆する最期を迎えるのだが、この末路は少々スッキリしないと言うか、もっと思いっきりコイツを倒したかった感もある。
確かに策士が最も重要な部分を読み違えて自滅するのは無様ではあるのだが、爆散する直前までウィーヌムは至上の絶望をたらふく食って幸せそうな様子であり、どうにも勝ち逃げされたような気持ちも残る。
先述の通りこいつは本当に邪悪の中の邪悪みたいな奴なので、ディゼルにバラバラに切り刻まれるくらいの悲惨な末路を辿ってほしかったとも思うのだが……そうすると残虐な表現とかに引っかかって対象年齢が上がりかねなかったのか?

そして、主人公たちが絶望の底からディゼルを救い出して物語は決着。彼は魔剣士として人々のため戦うことで、この先の生涯を通じて罪を償っていくことを誓う。この結末は、本当に綺麗に着地している。
少し別の作品の話をすると、DQ11のデルカダール王は魔王ウルノーガに肉体を乗っ取られ、世界を滅ぼすほどの悪事を働いた。
このデルカダール王は、ウルノーガに乗っ取られていた自分が犯した罪を重く捉えていたのだが、俺はこれに対してどうにも理不尽さが拭えなかった。肉体を乗っ取られていたんじゃ本人にはどうしようもないし、別に彼自身は何も悪くないからだ。かと言って乗っ取られた当人が「自分は操られただけだから悪くない」なんて言い出したらそれはそれで嫌なので、どう転んでもスッキリしない。
この魔剣士クエストの物語において、事件の元凶は間違いなくウィーヌムだ。しかし、両親を殺害した憎悪の大本は確かにディゼル自身のものであり、彼はそれを抑えられなかったから両親を手にかけてしまった。その点ではディゼルに一切の責任が無いとも言い切れないだろう。
だからこそ彼が自身の罪に自覚的で、それと向き合い、贖罪のために生きていこうと決断することに納得できた。この罪と罰のバランスが、このストーリーは絶妙に作られている。
加害者側に同情を引いて、開き直りを正当化することが常態化している本編ストーリーは魔剣士クエストを見習ってくれ。
7位 魔法使い

主人公は、「魔法使いが泊まると謎の声が聞こえる」と噂の宿に宿泊する。すると噂通りに謎の声が聞こえてきた。
姿は見えないが、その声の主リュナンと交流するうちに主人公は徐々に打ち解け、直接会ってみる約束をする。
しかし実際に会おうとすると約束の場所にリュナンは訪れず、主人公は危機に巻き込まれる。そして、リュナンの背負っているものと、その身に迫る危機との戦いに巻き込まれることとなる。
このクエストに関しては以前の記事や過去の雑談配信等でも言及しているが、オンラインゲームとなった本作の舞台を上手く活かした内容だ。
そして本クエストの何が良いのかって「姿の見えない相手と会うのはこんなに危険!君もオフ会なんてやっちゃダメだよ!」と雑に説教をするだけの内容に陥らず、ちゃんとミステリー的な面白さと王道の勧善懲悪展開をもってリュナンという人物、そして魔法使いという職業自体にも愛着を持たせてくれる物語に仕上がっている点だ。
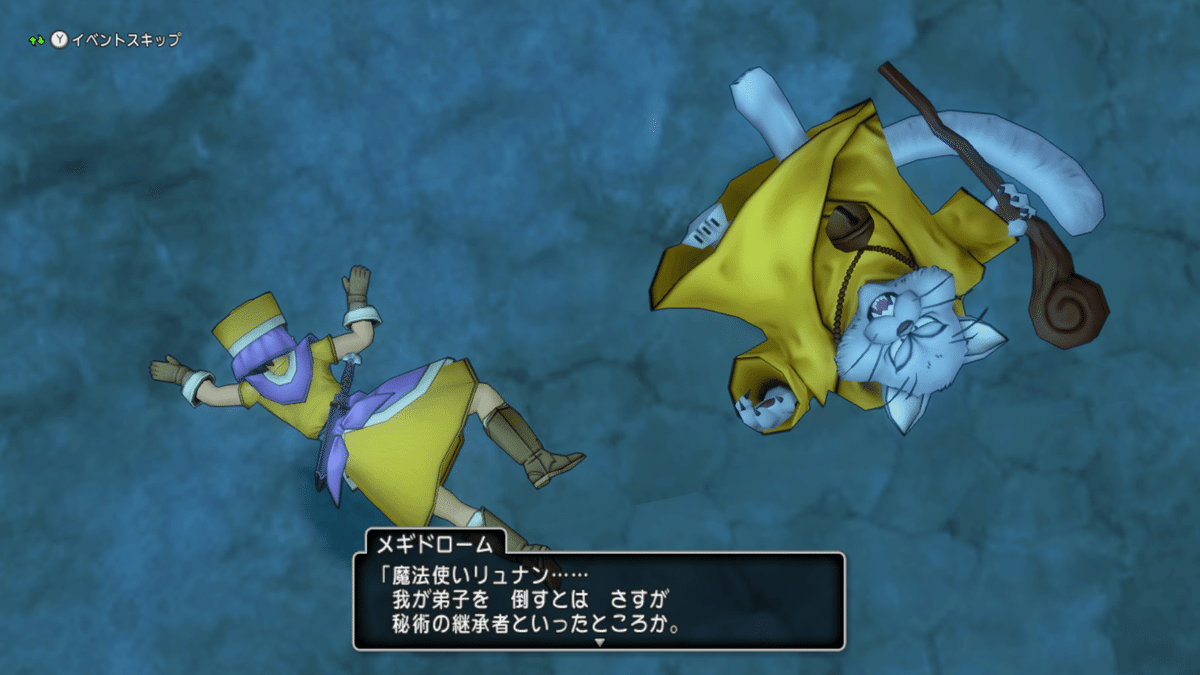
流石にもうバラすが、リュナンの正体は魔物だった。
まあ創作のセオリー的に考えれば、わざわざ「姿が見えない相手の正体」を長々と引っ張っておきながらただの人間でした、で終わらないことは大抵の人が察するだろう。
だが、例えば上の画像の場面ではご丁寧にも以前リュナンが「目印として同じ帽子を被ろう」と言っていたサフランハットを装備した人間が顔を隠して登場しており、いかにもこちらがリュナンであるかのように演出している。
この手の創作のセオリーを知らない子供であれば、普通に騙されそうな程度には手が込んでいる。
本クエストのボスであるメギドロームとの戦闘後、背後から主人公を襲おうとした偽リュナンをリュナンが倒し、その正体を明かす展開はオチの予想が付いていたとしても茶番臭さを感じさせないよう上手く演出されている。

本クエストの良い点として更に挙げられるのが、敵がリュナンを狙っていた動機として「魔法使いの必殺技、ミラクルゾーンを伝授できる存在だから」という理由が用意されているところだ。
他のクエストでは報酬として流れ作業的に必殺技を伝授されることが多いのだが、本クエストではそれが物語の軸となっている。だからこそ主人公がこの必殺技を習得すること自体がドラマとなっているし、クエストが終わってからもミラクルゾーンを使う度にリュナンとの絆を思い出せるようになっている。
先述したように、本クエストは割とオチの予想は付いてしまうし、昔の職業クエストの例に漏れず話の規模が小さい。
だが、この「オンラインゲームとなった舞台を活かした内容」「ゲームのシステム自体を物語に組み込んでいる」といった盛り上げ方が本当に巧みで、しっかりと一つの物語として楽しめるように仕上がっているし、魔法使いという職業に愛着を持たせる内容になっている。職業のクエストとして、非常に理想的な内容に仕上がっていると言えるだろう。
それでも本クエストが7位と微妙な順位なのは、ここから上が強すぎるだけだ。
6位 占い師

主人公は「占いの館」の新人占い師として、人々のお悩みを解決してゆくこととなる。主人公は、かつて封印されていた占いの秘術アルカナ・セラピアを用いて、悩める人々のお悩みを解決してゆくが……?
まず本クエストで面白いのは、ファンタジーの占い師にありがちな「水晶玉で未来を全部お見通し」な予知能力者ではなく、人々のお悩み相談室として働く、割と現実志向での占い師という職業を描いている点だ。
ならば地味な会話が中心の話かと言えばそうではなく、主人公はアルカナ・セラピアの力により相談者の心の中に入り、モンスターとして具象化された悩みの心を直接叩きのめすことで相談者の心を救う、凄まじい力業でのお悩み解決を行うことにる。何でもデュエルで解決する世界じゃねえんだぞ。

だが、そんなおバカな設定に反して物語の内容は非常にシリアスで、相談者たちのお悩みの内容に加え、占いの館の仲間たちユノ、ソーン、エゼルの悩みも中々リアルな様子で描かれている。
本クエストは人物の描写が見事で、この物語の黒幕とも言えるマルグリットは最初から絶妙な胡散臭さが漂う。
それからマルグリットと上記のユノたち三人は家族との設定だが、彼女たちの会話は遠慮なく素の自分で接している感じの距離感がクエスト内で非常に良く伝わってくる描写となっていて、これが微笑ましく心地よい。
これはドラクエ10の本編ストーリーにも存在するんだが、ダメなストーリーは大体こうした自然に家族らしさを感じさせてくれる描写がちっとも無いまま「自分たちは家族だ!誰よりも大切な相手だ!」みたいな露骨な絆アピールを入れて強引にお涙頂戴をして滑る傾向がある。
このクエストは本編よりもずっとボリュームが小さいのに、家族の空気感をしっかり描いてるのが見事な部分だ。

もう上で書いてしまったが、本クエストにおける敵、黒幕となるのはマルグリットだ。彼女は過去に、自分の娘を病で亡くしている。
そして、その時に娘から「母さんみたいな占い師になって、全ての人々を悩み苦しみから救いたかった」と言われたことが、彼女が凶行に走ったきっかけとして描かれている。
この場面の描写もなかなか見事で、娘が最期に残した言葉が突き刺さり、その言葉に縋ろうとして彼女が徐々に狂っていったことが伝わってくる。
最終的に本クエストは、彼女の心に住み着いた魔物を倒すことで決着する。
これは見ようによっては魔物に責任を押し付けたようにも思えなくはないが、ドラクエという作品において「人を追い詰める魔物の邪悪さ」「魔物に追い詰められて凶行に走る人間の弱さ」はそれぞれ別の悪事として扱われる傾向が強いので、ドラクエらしさという点では違和感はなかった。
マルグリットは弱かった。だから現実を受け入れられずに狂ってしまった。そこから目を逸らすことはなかったので、ちゃんと最後まで「心の闇と向き合う物語」として筋の通った内容に仕上がっている。
これだけちゃんとした職業クエスト作るほど気合いを入れているなら、占い師がサポート仲間として機能しない欠陥を放置するのをいい加減やめてもらっていいか?
ランクA:文句の付けようがない大傑作
5位 武闘家

主人公は武闘家ヤーンから、伝説の武闘家超天道士の修行を行うことを提案される。彼は、自分が修行をするのが面倒だから主人公に押し付けているような口ぶりだったが、そこには別の思惑があった。
このクエストも、魔法使いと同等以上に思い出深い話だ。
俺は元々オフライン版からドラクエ10に入ったんだが、本編ストーリーについては特段面白いと感じていなかった。
だから職業クエストに関しても最初はあまり興味を持っていなくて、当時メインでやっていた職業が武闘家だったので一応触ってみた、くらいの感覚だった。その結果、これが信じられないくらい面白かったので驚愕し、他の職業クエストもプレイして「職業クエストは面白い」と確信するに至ったのだ。
クエストの基本的な流れは単調で、ただヤーンに言われた通りに一人で修行をこなし、先に進むだけだ。しかし、序盤からヤーンには何か企みがある様子が描かれているし、彼の世話役であるガウラドの登場もあって、この先一体どうなるのかが気になるよう絶妙な「引き」が用意されている。

そして、中盤以降は物語が怒涛の展開を見せる。
ヤーンの計算違いで結局彼自身が超天道士の名を継ぐと、ガウラドが「自分は超天道士を倒すために魔界からやって来た」との正体を明かし、戦闘になる。
本クエストはそんなに文量が多いわけではなく、ヤーンもガウラドもそんなにベラベラと自分の心情を話すことはない。
だが、ここまでの展開でも一見やる気が無さそうに見えて、実は色々と計画を練って行動しているヤーンと、そんなヤーンに振り回され、手を焼いているガウラドの様子はシンプルな構図で分かりやすく描かれており、彼らの別れのシーンではそれぞれの心情がしっかりと伝わってくる描写になっている。
格好を付けたのか、あるいは見限ったつもりだったのか、一度はガウラドに背を向けたヤーンが、ガウラドの最期の言葉に思わず振り向く場面は彼らの長い付き合いと複雑な感情がひしひしと伝わる描写で、演出もバッチリ決まっている。
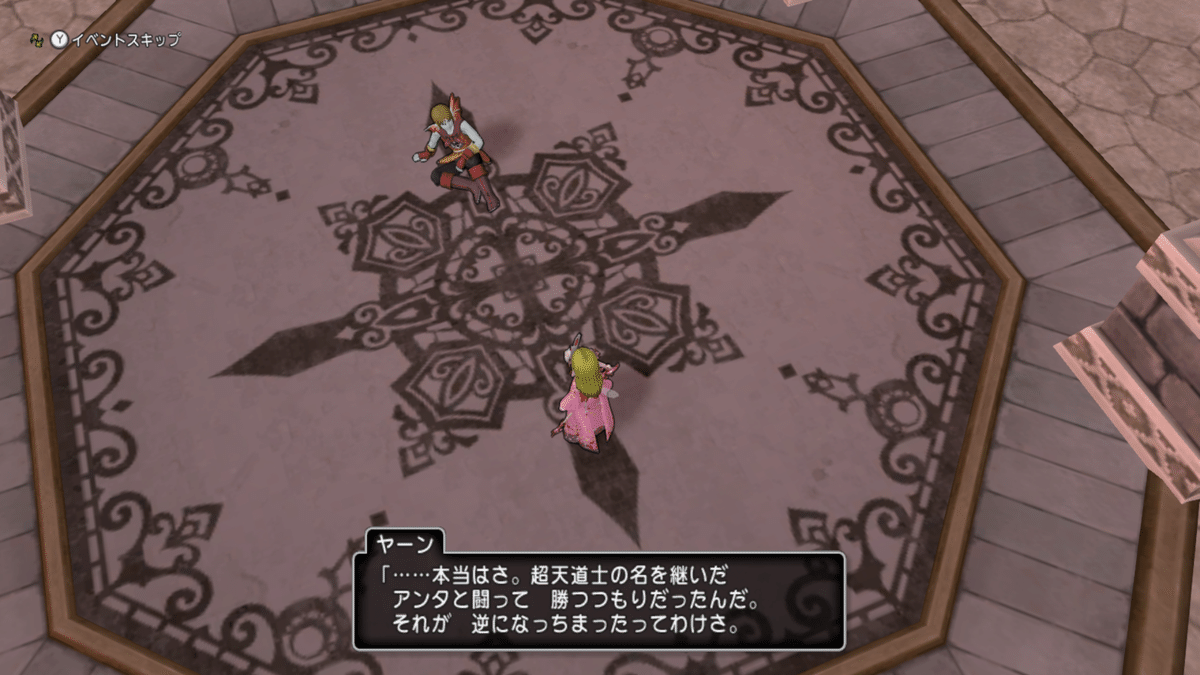
ヤーンの目的は主人公に超天道士の名を継がせた上で、その主人公と戦って自分が勝つことだった。そうして、「名に強さが宿るわけではない、肩書きなんてどうでもいい」ことを証明したかったのだ。
だが結局その計算は狂い、超天道士の名はヤーン自身が継いでしまった。
本クエストの最後では、その超天道士ヤーンと無名の武闘家である主人公が決闘し、主人公が勝利する。
ヤーンの想定とは逆の構図になってしまったが、「超天道士の名を持つ者を、その名を持たない者が倒す」ことは達成され、結果としてヤーンの願いは叶うことになった。
拳を交え、これまでの心中を吐露するヤーンの様子は本当に爽やかだ。そして「次に戦うときは俺が勝つ」と、主人公と良きライバルとしての関係を築き、物語は幕を下ろす。
この紆余曲折を経て、しっかりと王道に締められる結末が本当に見事だ。
決して長大なボリュームがあるわけでも、美麗で豪華な演出があるわけでも、有名な声優が声を当てているわけでもない。それでも、完璧と言えるくらいに完成された物語が心を満たしてくれる。
そんな職業クエストの魅力がぎっしりと詰まっているのが本クエストだ。
4位 遊び人

主人公は「遊びクラブ」の一員となり、仲間たちと一緒に遊びながら掲示板で映える(イタ映え)写真を撮影して過ごす。
そんな中、遊び人をを強制的に労働に目覚めさせる魔物、労魔デスワークが現れ、楽しい日々が脅かされ始める。
このクエストは、何となく遊ぶ前から「面白そうだ」と感じていた。
これは再三言っているが、ドラクエはシリアスな場面の真っ最中にもギャグシーンを入れて茶化さないと死んでしまう病気を患っているため、正統派ストーリーを意識していそうなものほど危険なのだ。
逆に、最初からおバカなストーリーの場合「下らなく見えて、どこか考えさせられる部分がある」感じの良質なストーリーに仕上がっている事がある。
本クエストは、その良い例での代表格と言える物語だ。

まず、本クエストは本作で刷新された遊び人のイメージをクエスト中でしっかりと描いている。ドラクエ3で初登場した頃の遊び人は、形容するなら「不真面目で身勝手な旅芸人」といった感じだったが、本作における遊び人は楽しく遊び、映える写真を撮影し、それを掲示板に貼っておひねりを貰うことで生計を立てている人となっている。要は現代におけるインフルエンサーのような職業となったわけだ。
これがクエスト内でもしっかり描かれており、遊びクラブのリーダーであるルッチーは、両親から度々「遊び人なんかやめろ」と言われては、「今時の遊び人は違う」と答えている。
事実として彼らは穀潰しではなく遊びで収益を得て生活しているので、ただの役立たずだった過去の遊び人とは違う存在だ。
だが、現実で見てもインスタグラマーとかYouTuberとか、そういった職業は「真面目に働かず、わけわからん事をやって生活してる犯罪者まがいの連中」のような目を向けられていた期間が長かった。VTuberに対しても未だにバーチャルキャバクラとか言ってる奴がいるよな。
本クエスト内でも、遊び人について「くさった死体にたかるハエのような存在」という罵倒が使われているが、これは一時期のインスタグラマーが流行りの飲食店に押し寄せては写真だけ撮ってロクに食べもせずにポイ捨てしていくような迷惑行為を行っており、「インスタ蝿」と揶揄されていたことが元ネタだろう。
本クエスト内でルッチーたちは「ハチミツの池を温めて、入浴しながらパンケーキを食べる」遊びを行うが、これがリアルに考えたら衛生面や倫理面で微妙に問題があるのも多分、そうしたインフルエンサーの微妙な迷惑さの表現の一つじゃないかと思っている。

そういったリアルな要素を取り入れつつも、本クエストはそれを「ドラクエ版」としてアレンジし、違和感なく描いている。
例えば上記の「くさった死体にたかるハエ」発言をするのは現在賢者をしているルッチーの父なのだが、ストーリーの終盤で実は二人は元遊び人だったことが明かされる。
これは間違いなくドラクエ3において遊び人は悟りの書無しで賢者に転職できる能力があったことが元ネタだろう。
ファンサービス要素としてしっかり機能しつつも、初見ではルッチーの両親が賢者である点について「両親はお堅い職業だから遊び人に否定的なのだな」と違和感なくミスリードさせる要素にもなっており、上手い設定だ。

本クエストで敵となる労魔デスワークだが、こいつに襲われると遊びをやめて働きたくなってしまう……とまあ、何ともシュールと言うか悪事でも何でもなさそうな事をやっているが、こいつに関わる描写は意外とシリアスだ。
本クエスト終盤では、デスワークに襲われた遊びクラブの仲間ゴランゾが別人のようになってしまう。
そして、それを見た仲間ピンキーが「デスワークに襲われたら自分が自分でなくなる。それは怖い」と言って遊びクラブから抜けてしまう。
人格を変えられてしまうというのは考えてみれば中々ホラー感のあることで、「働きたくなってしまう」というのが意外と笑えた話ではないことが伝わってくるだろう。

その後、デスワークは強制的に人格を書き換えているわけではなく、その人の「働かないことへの後ろめたさ」を呼び起こしているのだと明かされる。
だが、これは主人公には一切通用しなかった。
これがまた面白いシーンで、パッと見では「主人公がとてつもないアホだから」に見えるが、冷静に考えてみると違う解釈もできる。
主人公およびプレイヤーにとって、遊び人というのは戦うために就く職の一つだ。遊び人として戦う、経験を積むことに意味があるからやっているのであって、別に労働からの逃避で遊び人をやっているわけじゃない。だから遊び人として生きることへの後ろめたさも、あるはずがないのだ。
もしかしたら本当にただ主人公がドアホであるとの意図だけで描かれている可能性も否定できないが、先述のファンサービスなどを見ても、本クエストはおバカなノリで描かれた物語の割には各要素が非常に論理的に仕組まれている。だから俺は主人公は真面目に遊び人の道を選んでいるから効かない説を推したい。

時々真面目なところもありつつ、基本的におバカなノリが本クエストの最大の長所で、ひたすらシリアスではないからこそ、最終的に「壊れたロボットがいいねの力で復活!」なんて馬鹿げたハッピーエンドも笑って受け入れられる。何だかんだ楽しかったからだ。
面白ければいい。そんなシンプルな気持ちで終わらせてくれる一方で、所々にシリアスな方面で唸らされる部分もある。
遊び人の物語として、これ以上の内容はそうそう無いだろう。
3位 竜術士

主人公は竜術士ランジェの弟子となり、最強の魔法使いを目指して修行をしてゆく。その最中に現れた謎の怪物について探るうち、竜術士の背負う業、そしていずれ復活する虚竜王との戦いを知らされる。
バージョン7.0で実装、執筆時点での最新職である竜術士だ。
最初の方に書いた通り、近年のドラクエ10のストーリーは決してクオリティが高いと言えないものが増えているのだが、なぜか職業クエストの品質は高いまま保たれている。それどころか演出・ボリューム不足が改善し、普通に重厚で良質な物語として進化しているとすら言える。
本作の主要人物は師となる竜術士ランジェ、主人公と同じく弟子となるアスパとルーイン、そして竜のバウギスだ。
バウギスはパラディンのクエストで登場した大地の竜バウギアの対となる竜として以前から名前は登場していた。バウギス自身の具体的な実力は未知数だが、対となるバウギアが「大陸一つをたやすく沈めるほどの力を持つ」と語られているため、それと同格と考えれば魔王にも劣らない実力と考えられるだろう。
竜術士は竜と契約して力を得る職業という設定だが、主人公と契約する竜が半端な存在だったらそれだけで残念要素になりかねなかった。かと言って作中最強クラスの竜がいきなり新登場しても違和感は拭えなかったと思うので、このバウギスを契約の竜として登場させたのは非常に良い設定だ。
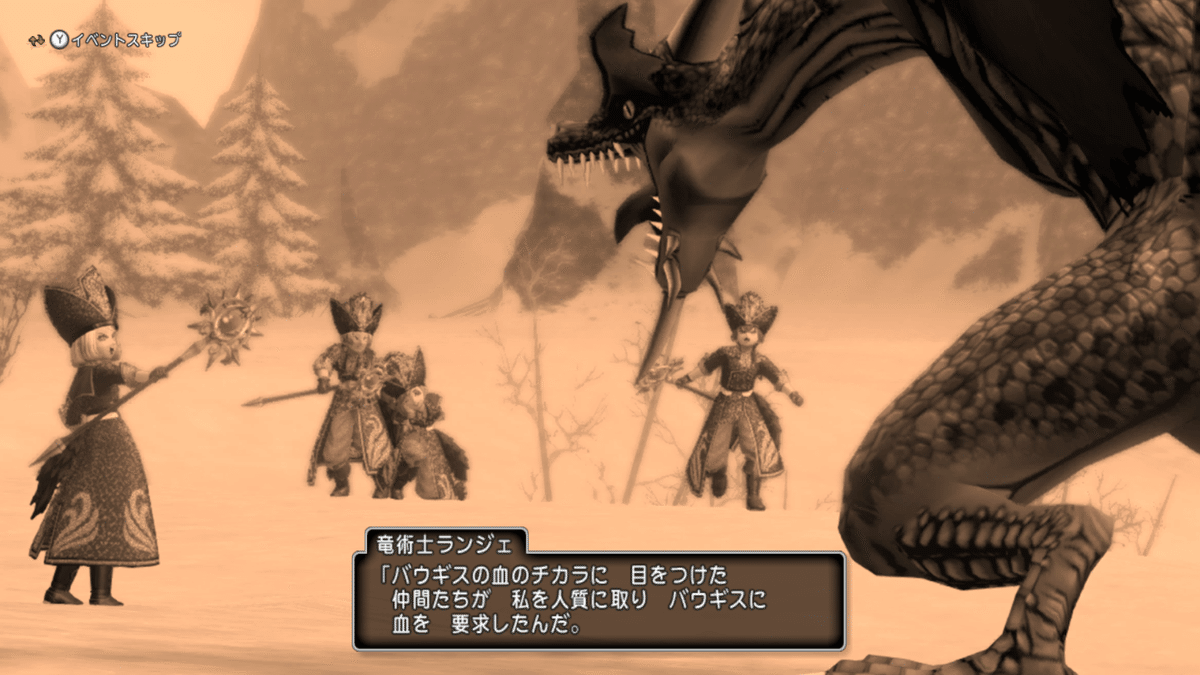
作中で「竜術士は呪われた職業」と言われている通り、その成り立ちは決して良いものではない……と言うか、以下に流れを書くが、割としょうもない理由だ。
事故でランジェが重傷を負ったとき、それを見かけたバウギスが戯れに血を与えた
ランジェはその血に適合し、大きな力を持つ竜術士となった
かつてのランジェの仲間(と言うかいじめっ子)だった魔法使いたちがランジェの力に嫉妬し、彼女を人質にバウギスに血を要求した
彼らは血に適合できず、竜術士ではなく虚竜と呼ばれる怪物になる
虚竜たちが力を求めて共食いし、虚竜王が生まれた
……とまあ、明らかにランジェをいじめていた魔法使いがひたすらカス、と言う話になってしまうのだが、一応は当事者であるランジェが「自分は悪くない」と知らん顔をできないのはまあ分かるし、虚竜王を倒そうとする彼女に協力してやりたいとは無理なく思える。

特に印象的なのが、ランジェが口調の割に全然師匠キャラらしくないことだ。
それが一番分かりやすいのが竜術士の奥義ドラゴラムを伝授されるシーンで、これは力に耐えられないと暴走したり、死ぬこともあると説明される。
最初はアスパにドラゴラムを伝授するのだが、この時のランジェの表情がものすごく嫌そうなのだ。
普通の師匠キャラだったらキリッとした表情で「お前ならできる!頑張れ!」と喝を入れるか、「ここで死ぬならお前はその程度ということだ」と厳しい言葉をかけたりするのが一般的だと思うが、ランジェからはただ「死ぬなよ…死ぬなよ……」と、ひたすらに不安と心配しか伝わってこない。
そして、この後にアスパは暴走しそうになる。
その際ランジェは「チカラに取り込まれるな!」と声をかけて彼を引き戻すのだが、この時も喝を入れていると言うより、ただ慌てて心配している様子だった。
上記の竜術士の成り立ちを見てもらえば分かるように、ランジェはそもそも別に強くなりたくてなったわけでもないし、竜術士の師となっているのも虚竜王と戦うために仕方なくやっているだけで、元は大したことのない魔法使いの少女でしかなかった。
ただの無力な少女が、背負わなくてもいいものを背負わされて、増やしたくもない竜術士を増やしてでも過去の責任を取ろうとしている。
それを考えると、彼女が「最強の魔法使い」と言われる竜術士の師という立場に対して、ひどく不釣り合いな人格なのも頷けるだろう。
だが、彼女はそうした自身の境遇について責任を感じている発言はしても、特に被害者アピールをしたり同情を引こうとしたりすることがない。だから彼女に協力したいと自然に思えるのだ。

それから、主人公と共にランジェの弟子となるアスパ・ルーインの二人はどちらも一癖ある人物だが、この二人が最終的に結構いいコンビになるのは心温まるものがある。
アスパはクエスト内の行動を見ていても全体的に浅慮な判断が目立つ上、デリカシーのない発言が非常に多い。だが根は悪い奴ではなく、過去の因縁から一度はランジェの元を離れたルーインを最後まで心配していた。
アスパがそんなちょっと放っておけないガキだからこそ、ルーインは彼の真っ直ぐな想いに心を開いたのだと思う。
最終決戦で過去の因縁を吹っ切ったルーインが駆けつけるシーンは熱かったし、そこで「俺も大切な人を守るために戦う」と口にしたルーインに対し、「それって僕たちのことですかっ?」とデリカシー0の質問をするアスパ、「ゴチャゴチャ言ってる場合かよ」と誤魔化すルーインの掛け合いは、緊迫した場面にもかかわらず顔がほころびそうになった。

この竜術士クエストは全体的に一癖ある人物が揃っており、しっかりと個性的でありつつもちゃんと全員に愛着が持てるようになっているのが非常に良い。
あと虚竜王との決戦では最後に全員でドラゴラムを使ってトドメをさすのだが、ちゃんと主人公も参加しているのが好印象だ。
何度でも言うが、ver4以降のドラクエ10本編ストーリーではこうした「みんなで力を合わせて強敵と戦う!」場面でも、主人公は当たり前のように棒立ちで何もしないからな。逆にどうしてver7実装の本クエストでは主人公がしっかり戦いに参加してるんだ?俺には分からない。
2位 デスマスター

デスマスターのデズリンの招待を受け、主人公はデスマスターとなる。
同じくデズリンから招待されたのに霊感が皆無なネリムを連れて事件を解決するうち、主人公たちは大きな事件に巻き込まれてゆく。
この話はできればネタバレをしたくないのだが、しなきゃ魅力を語れないので全部書く。まだ本クエストをプレイせずにここまで記事を読んでいる人は、できれば先に自分でこのクエストをプレイするか、YouTube辺りに投稿されているプレイ動画でも見ておいてほしい。

まず、このクエストで印象的なのは物語で足を踏み入れる黄昏の園の美しさだろう。本作の背景グラフィックは要求スペックの割に綺麗なものが多いが、その中でも黄昏の園のマップは非常に美しくも死後の世界らしい寂しさを感じさせる、見事な表現がされている。
ずっとここに居て景色を眺めていたい気もするが、あまり長居してはいけないような気もする。そんな気持ちを呼び起こされる。
ネリムは基本的におバカで天真爛漫な感じのキャラだが、エンディングで一人佇んでいる様子は普段の彼女からは想像できないくらいに映えている。

本クエストのストーリーだが、最初のうちはデズリンの依頼を受け、成仏できない幽霊たちの頼み事を解決していく。この時点では特に変わったことはなく、普通に生きている人間の頼み事を聞くのと変わらない。
だが、二度目の依頼の完了後、謎の霊魂がネリムに対し「継承者発見」と騒ぎ立てた辺りから、凄まじい勢いで物語が展開を始める。
本シナリオの黒幕の登場、継承者の意味、デズリンが主人公たちを招待した意図、ネリムに霊感がなかった理由など、重要な要素が次々と種明かしをされてゆくのだが、特に衝撃的なのは黒幕の指示で死霊の書の封印を解いたネリムが死亡する展開だろう。

ただ、これは魂が抜けただけで完全な死亡をしたわけではなかったらしく、デスマスターである主人公が彼女の魂を呼び戻すことでネリムは蘇生に成功する。
とは言え、普段は元気だった彼女が何の前触れもなくパタリと倒れ、「死んだ」と言われるのはかなりショッキングな場面だ。
そこからデズリンに「まだ蘇生できる可能性がある」と言われ、彼女を助けるために奔走する間は、先の展開が気になって仕方がなかった。
まあ結局、先述した通り彼女は無事に蘇生に成功するし、彼女は自分が死にかけたことにも気付いておらず、いつもの明るい調子のままだった。
そうしてプレイヤーが安心したところで、最大の仕掛けが来る。

デズリンは黒幕ギスマイヤーに殺害されて現在は幽霊となっており、霊感がないネリムには今まで彼女を認識できていなかったことが明かされる。
ここで、ご丁寧に回想を入れてくれるのだが、確かに「言われてみれば」と思う要素はあちこちに存在した。
例えばネリムは最初に主人公に会った時、「一人で不安だった」と言っていた。これはプレイヤー目線なら自然と「弟子は」一人だった、という意味で解釈するだろうが、彼女の視点では本当に一人だったのだ。
思えばネリムが主人公に対して割とベッタリだったのも、単に彼女が人懐っこいだけではなく、自分を招待した師匠すら一向に姿を見せない中、唯一出会った相手だったからという理由があったのだろう。
それから、デズリンは主人公に何かを教える時に毎回「本に書いてあるから読んで」と言っていたが、これも彼女が幽霊だから、直接手取り足取り教えることができなかった、というわけだ。
本クエストはこうした仕掛けが、至るところに自然に張り巡らされていた。

もっと遡って言うなら、最初に主人公がネリム・デズリンと顔を合わせたシーンにも意味があったのだろう。
ここでは主人公がネリム及びデズリンと3人で会話をした後、デズリンから改めて自分に話しかけるように言われる。
ドラクエ10において、こういった会話の流れは別に珍しくない。
おそらくはシステム的な処理の都合だと思うが、ムービーシーンで「もう一度話しかけて」と言われて会話が一旦終了、改めてフィールドで会話をして話を進行することは、他のストーリーでも散々あった。
だから何の疑問も持たずにこの場面も読んでいたが、後で確認するとこの発言も「ネリムと並んで喋り続けていたら会話の不自然さで自分が幽霊だとバレる危険性があったから、一度会話を打ち切って自分と1対1で会話するように持ち込む」意図があったと考えられる。
プレイヤーが「そういうものだ」と素通りする部分に、さり気なく仕掛けを置いておく。この、ドラクエであるからこそ違和感なく成立する叙述トリックが極めて巧みだ。

以前の記事で言及した点だが、デズリンは身長が2メートルくらいある。
何故か一般の人間女性の体型ではなく、人間より大柄なオーガ女性の体格がベースになっているからだ。
俺は多分これも演出の仕込みの一つだと考えていて、事情としてはこういった流れだと思っている。
「死」が題材となるストーリーだが、あまり重苦しい雰囲気にしたくないのでネリムを元気なキャラクターにしたい
だが、ネリムを本当に人生経験の浅い子供にしてしまうと死を扱う物語として薄っぺらになりかねない
だからネリムは「言動や服装が子供っぽい大人」になった
師匠であるデズリンは包容力のある大人にしたいし、体格としてもネリムより大きくしたい
だが、上記の理由からネリムを子供にするわけにはいかない
なので、デズリンの方を巨人にするしかなかった
こうして書くとトンデモ論っぽく見えるかもしれないが、上の画像を見てもらえば分かる通り、このストーリーのクライマックスではデズリンがネリムの頬に手を添えるようなシーンがある。この場面で二人が同じくらいの体格だったら明らかに格好が付かない。
だが、ただ体格差を作るだけならネリムを子供にするのが普通だろう。なのに、わざわざデズリンを特殊な大型体格にしてまでネリムを大人にした辺り、やはりネリムを子供にしたくない理由があったのは確かだと思う。
付け加えて言うなら、本クエスト内でネリムはソファに座っているか、もしくは寝ていることが多いのだが、これも彼女が普通に大人の体格をしていることをプレイヤーに気付かせないために、座らせることで身長を誤魔化していたんじゃないかと思う。
普段のシナリオだったら作者がそこまで計算しているとは思わないが、本クエストは叙述トリックのために色々と仕込まれているので、彼女たちのデザインにもそういった理由があるのではないかと思う。

一つツッコミどころを挙げるとすれば、デズリンが少々万能すぎる点だ。
作中の回想で、彼女は過去にネリムの霊感を封じた上、その記憶も封じていたことが明かされる。これは本作に限らないが、創作物での「記憶操作」は割と禁じ手に近いと思っているので、やり過ぎ感はある。
デズリンは死霊の書の継承者一族を守る家系と語られているので、その関係で色々と秘術のようなものを見に付けているのだろうと考えられはするが、それにしても便利キャラ化しすぎているのは否めない。
そして、それだけ万能な割に作中で彼女がやったことは大体裏目にしか出ていないのが何とも虚しい点だ。
ネリムの霊感や記憶を封じたせいで彼女が何も知らないまま事件に巻き込まれたことがまず一つ。そしてデズリンが主人公に正体を隠していたのは「幽霊からの依頼なんて信じてもらえないと思ったから」とのことだが、主人公からしたらそんなもん珍しくも何ともないわけで、最初から事情を説明して貰えた方が動きやすかっただろう。
とは言え、デズリンの側も信用できるか分からない相手に重大な使命を託すわけにはいかなかっただろうし、自分が主人公を見極める意味でも正体を隠していた部分はあったのだろう、と推測できる。(と言うか彼女の性格を考えると実際はそっちの方がメインで、「主人公に信用してもらえないと思ったから」と語ったのは建前上の理由のような気がする)

トリックの話ばかり続けたが、ストーリーの方に話を戻そう。
主人公は復活したネリムと共にギスマイヤーとの決戦に挑む。そして主人公たちが勝利し、死霊の書を奪回する。
それでもなお抵抗しようとするギスマイヤーだが、死霊たちの制御権は死霊の書を手にした正統後継者のネリムに移っており、逆に死霊を操られてギスマイヤーは沼の底へ沈んでいった。
このシーンも中々演出が面白い場面だ。
最初はギスマイヤーが死霊を操ってくると思ってネリムは縮こまるが、死霊は襲ってこない。どうも自分の動きを真似しているように見える。
そこで試しに手を振ってみたり、敬礼みたいなポーズをしてみたりして、死霊を操れることを確信した彼女は、上の画像のように命令を下す。
このシーンを見ても思うんだが、ネリムは言動がアホっぽい割に行動は結構頭が良いのが好きなポイントだ。この場面に限らず、思いついた仮説を一つ一つ順番に試してトライ&エラーで行動する、かなり合理的な思考をしている。
なお、ここで結局ギスマイヤーは沼の底に沈められているので、まず間違いなく死亡している。魔物以外が死亡するケースは非常に珍しい。
まあギスマイヤーはデズリンを殺害した前科持ちの上、ネリムが「大人しく死霊の書を渡せば全治二ヶ月くらいで勘弁する」と譲歩したのを一笑に付しているので、まあ死ぬのが妥当だろうと思う。
もしもネリムが譲歩する姿勢すら見せずに彼を殺害していたら若干の倫理的な問題が残りそうだったが、そういった物言いが付く可能性も本シナリオは考慮している節がある。

ギスマイヤーとの決戦を終え、思い残すことが無くなったデズリンを主人公とネリムで成仏させ、物語は幕を下ろす。
……と思わせて、死後の世界のデズリンから通信機を通して「あの世で元気にやってる」と連絡が入る。呆れたようにネリムが笑うカットを映して、今度こそ終幕だ。
この、ドラゴンボール的なお気楽な死後の世界の描写は全面肯定してよいか微妙なところだが、今まで散々な目に遭ってきた彼女たちが報われないまま終わるよりは、このくらいハッピーエンドで終わってくれても良いだろう。
ただ「叙述トリックが凄いです」だけじゃない。最後までデズリンとネリム、二人の「らしさ」を感じさせて、気持ちの良い読了感を得られる。
そんな満足感のある物語だった。
ランクS:ドラクエシリーズで一番面白い
1位 ガーディアン

長々と書いてきた職業クエストランキング1位はガーディアンだ。
本作で初登場した職業であり、後に竜術士が加わるマスタークラスの開祖でもある。
先に書いておくと、俺はこのガーディアンという職に対する事前の印象は最悪だった。そもそも戦士系の最上級職ならDQ7で登場したゴッドハンドがあったし、ガーディアンの肩書き「光の守護者」とやらも、聖騎士と呼ばれるパラディンとモロ被りだ。
更に言うならドラクエの代表である勇者だって光属性要素はあるし、わざわざ後から似たような光属性・戦士族の職を追加する意味が全く分からない。
この職業クエストを終えた今では、ガーディアンという職に対する愛着・思い入れは本当に強くなったが、そもそもの職業コンセプトが魅力的に見えない点はどうにもならないと思っている。
そして印象が悪かった理由のもう一つが、本クエストの実装時期がバージョン6.4だったことだ。
一般に、ドラクエ10のver6は最も本編ストーリーの評判が悪い。まあ俺はver5の方が明らかに酷かったと思うが、ver6が良かったとは全く思わない。
なので、その時期に実装されたクエストが面白いとは到底思えなかったのだが、後になって思えば俺が絶賛している遊び人はver4.3、デスマスターは5.0、魔剣士は5.4実装なので、やはり本編の品質と職業クエストの品質には全く因果関係がないことが分かる。
何故こんな事になっているのかと言うと、おそらく職業クエストは制作スタッフが正直どうでもいいと思っているのでシナリオを外注しているのだと思う。
ドラクエ10のver4以降の本編シナリオは主人公を物語から消滅させて制作陣の激萌えキャラクターをひたすら押し付けてくるだけの内容だが、職業クエストは主人公が守りたい相手や頼れる仲間と出会い、共に巨悪へと立ち向かう内容で一貫しており、明らかに毛色が違う。
実際、このガーディアンクエストは特に台詞の一つ一つにまで情報がぎっしり詰まっており、全体のテキストのレベルが異様に高いのだ。

さらに言うと、このガーディアンクエストはイベント戦闘すら職業のチュートリアルとして上手く作られている。
これは今まで書いていなかったが、職業クエストでは時々「◯◯の技を使って敵を倒せ」といった指示をされることがある。
職業の特技を使ってもらうための要素なのは分かるが、実態は指定された技を機械的に使わされるだけで、職業の性能を把握するために有効に作用しているとは言い難いものが多い。魔法使いのクエストには「マホトラで累計100のMPを吸収しろ」なんて指示もあったが、ただ純粋に面倒なだけだった。
このガーディアンのクエストは「邪悪な魔神族ストレザーテが生み出した、地獄の門から生まれ出る多数の魔物たちと戦う」ことがストーリーの主軸となっている。
その物語の通り、クエスト内では大量に出現する魔物を倒し続ける耐久戦タイプのイベントバトルがあるのだが、このような乱戦はガーディアンのスキル「天光の護り」と非常に相性が良いのだ。
それから本クエストのボスは強力な呪文攻撃を使ってくるが、これは退魔の鏡で対応が可能であることが登場人物から教えてもらえる。
ただクエストの達成条件として無理矢理に技を使わせるのではなく、プレイヤー自身が「この技が有効なんだな」と気付けるようなバトルを用意したり、「先輩からのアドバイス」として教えてもらえることで登場人物への親しみを持てるように設計されている。
そして「なるほど、この職業はこうやって戦えばよいのだな」と自然に理解できるようになっている。こんなところまで細かく丁寧に作られているのはガーディアンだけだ。

光の守護者なんて堅苦しい肩書に反して、騎士団員たちは家族のような温かみのある雰囲気を持った人物が揃っている。かと言って単にお気楽なわけではなく、オンとオフの使い分けがしっかりできる優秀な人物なのが分かる。
団員だけで6種族それぞれのキャラクターが登場し、職業クエストとしてはトップクラスに主要人物が多くありつつも、それぞれしっかりとキャラが立っており魅力的だ。
力強くも非常に知的な団長ダンディオ、団長と昔馴染なだけあって縁の下の力持ちとしてみんなを支えてくれるトオチャ、頼れる先輩ながらも所々で可愛さが溢れているプリゼーラ、彼氏に浮気された腹いせに修行をしていたらガーディアンにまで上り詰めていたルーヤ、比較的主人公に近い立ち位置から冷静に団員を見ているアビゲイル、やや未熟な一面を見せつつも、本来は優秀で人当たりも良いことが分かるセツラン……と、正統派からネタキャラ気味な人物まで、色とりどりのキャラクターが揃っている。
彼らの会話はクエスト進行の度に細かく変化するし、その内容もしみじみと感動するような言葉だったり、思わず笑っちゃいそうなコミカルな発言だったりと本当によく作り込まれている。

守護騎士団の団長であり、特にシナリオの中心となるダンディオは落ち着いていながらも非常に気さくで、気の利いた言い回しが多い。
例えばクエストの序盤、セツランが任務で失敗し「団長にお詫びの品を送りたいから、団長にはバレないように彼の好みを調べてほしい」と依頼された時だ。
この際、ダンディオ自身に話しかけると「何かコソコソと動き回っているが、悪だくみでもしているのか?」と問われる。
それに「はい」と答えた場合の返答が上の画像だ。
彼は主人公が本当に悪いことをするはずがないと分かった上で、「ここで堂々と肯定するからには、何か楽しいサプライズでも考えてくれているのだろう」と即座に察している。
だから余計な詮索はせずに、あえて主人公を笑って見逃しているわけだ。
単に人が良くて真面目なだけではなく、意外と冗談も結構通じるのが彼だ。

実際にセツランがお詫びの品を渡した際には「反省しているのならもう十分」と前置きをした上で、彼の気持ちを反故にすることもなく、「セツラン君の気持ちと僕の大好物はしかと受け取りました」との台詞と共にお詫びの品を受け取る。そして、その桜餅をみんなで一緒に食べることを提案する。
彼はとにかく利きすぎなくらいに気が利く人物なのだが、シナリオ全体が彼一人を持ち上げるような描写にはなっていないため、決して嫌味さはない。
団員全員の温かい雰囲気を作ることに貢献し、他の団員たちの魅力も引き出している。それが、このダンディオという人物だ。

クエスト全体を通して感じるのが、「プレイヤーが今どんな気持ちか」を本クエストは考慮している点だ。
先述したセツランがお詫びの品を団長に贈るイベントは、実際のところクエストとしては調査から物品の購入まで全部主人公がやることになる。これをセツランが当たり前のように主人公に要求していたら色々と不快な描写になっていたと思うが、依頼時にセツランは上の画像の台詞を言っている。
この言葉があるおかげで、セツランが単に図々しい奴ではなく相手の気持ちを思いやれる人物であることが表現されている。そして、ガーディアンという職業が背負う責務の重さと、そのせいでお詫びの品を自分で買いに行けないセツランの姿に哀愁と親しみを感じられる。
セツランは当初、主人公への嫉妬から敵対的な態度を取ってくる人物なのだが、その後にはしっかり謝罪をした上で、こうして本来は良いやつであることが伝わるように、とても丁寧に描かれている。
本編シナリオでは謝罪も反省もしなくても無罪放免になるのが常態化しているので、そうした点から考えても本編シナリオと職業クエストで担当者が異なるのはまず確実だと思う。本編の担当者がこんな丁寧な人物描写できるわけねえよ。

何ならメインキャラクターどころか、モブまで気持ちの良い人物だ。
本クエストの序盤では、守護騎士団のための保存食の調達を任されるのだが、この保存食屋のおっさんは「自分はパラディンのファンだが、ガーディアンも好きだ。だってみんな元パラディンだろ?あんたのことも応援してるぜ!」と言ってくれる。
こんな描写は本編だったら絶対無い。
ver4辺りからの本編シナリオ担当者は「あの人のことが大切すぎて、それ以外の人に攻撃的な態度を取ってしまう」みたいな描写が大好きだからだ。クオードとかリンカとかグレインとかヴァレリアとかリンベリィとかアリアとか天星郷の天使とかな。
もしも本編の担当者が書いていたら、このおっさんは確実に「ガーディアンん!?パラディンを裏切ったあのクソどもか!てめぇらに食わせるメシなんか無えよ!!」とか言ってるぞ。
別に登場人物をみんな超善人ばかりにすれば良いと言いたいわけではないが、ドラクエ10の本編はとりあえず性格の悪い人間を出せばリアルで面白いと思っているし、何ならその方が魅力的な人物だと認識している節があり、その結果不快な人物だけがひたすらに幅を利かせる地獄が完成している。
本クエストは、そういう余計なことを一切やらないのだ。
主人公は人々を護るガーディアンだ。ならば、その護るべき人々は当然プレイヤーが「この人たちを守りたい」と感じるような人物にしておくべきだ。
大切な人々を守るため、巨悪と戦う。
本クエストはその要点を外していない。と言うかこんな基礎の基礎を外してる本編シナリオがおかしいんだが。

そして、保存食を持ち帰った時のプリゼーラの言葉がこれだ。
ただ褒めてくれるだけじゃなく、「プリゼーラの胃袋の平和を守った」なんて可愛らしい言い回しをしてくれるので、彼女自身の可愛らしい外見も相まって思わず微笑みたくなる。
彼女は真面目でしっかり頼れる人物でありながらも、コロコロ表情が変わったり飛び跳ねたりするので見ていて飽きない。食いしん坊キャラ要素も可愛さのアピールとして機能しすぎるくらいに機能していて、中盤からものすごく重苦しい要素が登場する本クエストにおける癒しとして完璧な存在だ。

その重苦しい要素について言及しよう。
セツランから受け取った桜餅をみんなで食べている最中に、「若い頃の過ちは自分にもある」として、ダンディオは自身の過去の罪を告白する。
かつて彼には妻と娘がいたが、当時のダンディオは自分が強い戦士だと調子に乗っていた部分があった。そのため、「魔物が出るから危険だ」と言われていた地域に妻子を連れてピクニックに行ってしまった。
その結果、繁殖期か何かで想像以上に襲いかかってきた魔物たちに対処できなくなり、妻が犠牲となってしまう。完全に彼の過失であったため、家族からは絶縁され、娘とも引き離された……という話だ。
個人的には、このダンディオの失敗は本当に彼が100%悪い点が本シナリオの良い要素の一つだと思う。この物語では「罪を背負い、向き合い、償うこと」が中心的な要素となっているが、この「罪」がダンディオの責任と言い切れないものだったなら、スッキリしない話になってしまっていたと思う。
確かにダンディオは取り返しのつかない愚行をしてしまった。だが、それを心から反省し、彼は20年にも渡って孤独なまま、人々を守り続けてきた。
そんな彼に対して、「昔にバカな失敗をしたから」と死ぬまで石を投げ続けるのが正しいのか?と問うからこそ、このクエストの物語は深みのあるものになっている。
あと、このダンディオが罪を告白する場面でトオチャは離席している。
これはイベントシーンの時点では言及されず、その後のフィールド会話でトオチャ自身がサラッと「休憩中の見張りは俺がやっていた」と言うのみなのだが、これは彼の渋い魅力が本当によく出ている。
彼はダンディオと昔からの付き合いがあり、過去の事情も知っていた。だから何となく、この場面でダンディオが自身の過去を話すであろうことも察していたのだろう。
そこで当然のように見張りの代理を引き受けていた彼の優秀さが凄まじい。彼はダンディオと並んで団長候補に挙げられていた人物らしいのだが、そう言われるだけの人格者であることが、脇道のちょっとした会話で表現されている。こういう事があるほど情報の密度が非常に高いから、このクエストは小さな台詞の一つ一つも見逃せないのだ。

そして、本クエストにおける大きな事件が発生する。
ガーディアンの戦いにキリカ聖堂の優秀な僧侶を派遣してもらえる……との話で、やって来たのが他でもないダンディオの娘、サンだった。
この場面でダンディオに過去の記憶がフラッシュバックする演出も見事に決まっている。
プレイヤーは以前に彼女と一度会っているのだが、後になって思い返せばサンはダンディオと会話の雰囲気が非常によく似ていた。
だが、その頃はまだダンディオが「自分は天涯孤独の身」と言い張っていたし、サンも重要キャラらしい雰囲気を出していたわけではなかった。
だから何かダンディオと関係がある可能性を少し思い浮かべはしても、後でダンディオが「娘がいた」と語った際、即座にあの時の僧侶が彼の娘だと見抜いた人はそれほど多くなかったんじゃないかと思う。
俺はサンの初登場時にダンディオと何か似ているとは思ったが、その後は存在を完全に忘れてしまっていた。そして彼女が再登場した瞬間に全てを理解して息を呑んだのを覚えている。
サンは確かに優秀で、ただ強い聖なる力を持つだけでなく「ストレザーテの魔力は莫大なだけで、無限ではない」事を見抜き、それが勝利の鍵となる。その行動の優秀さを見ても、確かにダンディオの血を引いていることがよく伝わってくる。

そして、サンを加えてストレザーテとの決戦となるが、このシーンではまたダンディオの魅力が恐ろしいほどに描写されている。
守護騎士団たちを「踏み潰したところで意にも介さぬアリども」と形容したストレザーテに対し、「魔神族は記憶力に問題を抱えているようですね。1000年前そのアリに敗れたことをお忘れですか?」と毅然と煽り返す場面は、彼がただ清いだけでなく、邪悪に対しては鋭い敵意を向けることもできることがはっきりと描かれている。
そして、敵に襲われそうになったサンを守りに入った際、咄嗟に「ケガはないか!?」と父親モードで話してしまった後、改めて仕事モードで「僕が絶対に君を守ります」と口にするのが本当に彼らしい。
そこから「戦えっ!!世界を 人々を 共に戦う仲間を……すべてを!守り抜いてみせよ ガーディアン!」と団員たちを鼓舞する台詞は最高に熱い。
この辺りの場面で、俺は一つ心の底から警戒していたことがあった。
ダンディオが「"今度こそは"守ってみせる!」みたいな父親匂わせを自分から始めて、それを名台詞みたいに描いてこないかどうかだ。もしもそんな台詞があったら、完全に台無しだったと思う。
だが、このシナリオは違った。

サンは自分を守ってくれた背中が間違いなく父のものだったと確信し、決着後、彼をパパと呼ぶ。
対するダンディオは、自分に娘はいないと言い張る。彼は「自分が父であっていいはずがない、それを知られてはいけない」と今でも思い続けている。
それでサンはどうするのかと言えば、あっけらかんとした様子で「忘れちゃった?」とダンディオに問いかけ、過去の想いや、「父がケガをしていたら治してあげたい」との思いから僧侶になったことまで語る。
彼を父だと確信していることを改めて伝えた上で、確実にダンディオの逃げ道を奪う一手だ。
こんな言い方をされたら、ダンディオはこれ以上「自分は父ではない」なんて言い訳はできないし、もちろん「忘れた」なんて言えるわけもない。
ひたすらに知的だったダンディオに負けず劣らず、サンも同じくらいに賢い立ち回りを心得ているのが本クエストのキャラクター造形の完成度の高さだ。台詞を見ているだけでも、間違いなく二人が親子であることが伝わってくる描写になっている。

ついに観念したダンディオは、全ての心中を吐露する。お互いの想いをぶつけ合い、20年を隔てて二人は家族へと戻る。
そんな様子を満足気に眺めて、他の団員たちは無言で席を外す。
「自分を倒したことを誇れ」と堂々と消えていったストレザーテを含め、全ての戦いが清々しく決着して、物語は大団円を迎える。

エンディングで仲間たちが楽しそうに過ごしている光景や、その後の会話で彼らが活躍を続けている様子が窺い知れたりと、最後の最後まで胸が温まる内容だった。文句無しで最高のストーリーだ。
最初の方に書いた通り、俺はバージョン3以降の本編シナリオを基本的に全部ボロクソに言っているのだが、このクエストに会えただけでもドラクエ10を遊び続けた価値はあった。そう思っている。
今後、確かver7.5辺りで新規マスタークラスを実装予定と公式放送で言っていたような覚えがあるが、きっとその職業のクエストも素晴らしいものになるだろう。俺はそう信じている。
長々と書いたが、職業クエストは本当に面白い。
この点に関しては俺も「ネトゲだからと食わず嫌いせずにやってみろ」と勧めたい気持ちだ。やってない奴がここまで読んでたら全部ネタバレされてるが、多分それでも楽しめる。
やってみろ。面白さは俺が保証する。
このページで利用している株式会社スクウェア・エニックスを代表とする共同著作者が権利を所有する画像の転載・配布は禁止いたします。
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
