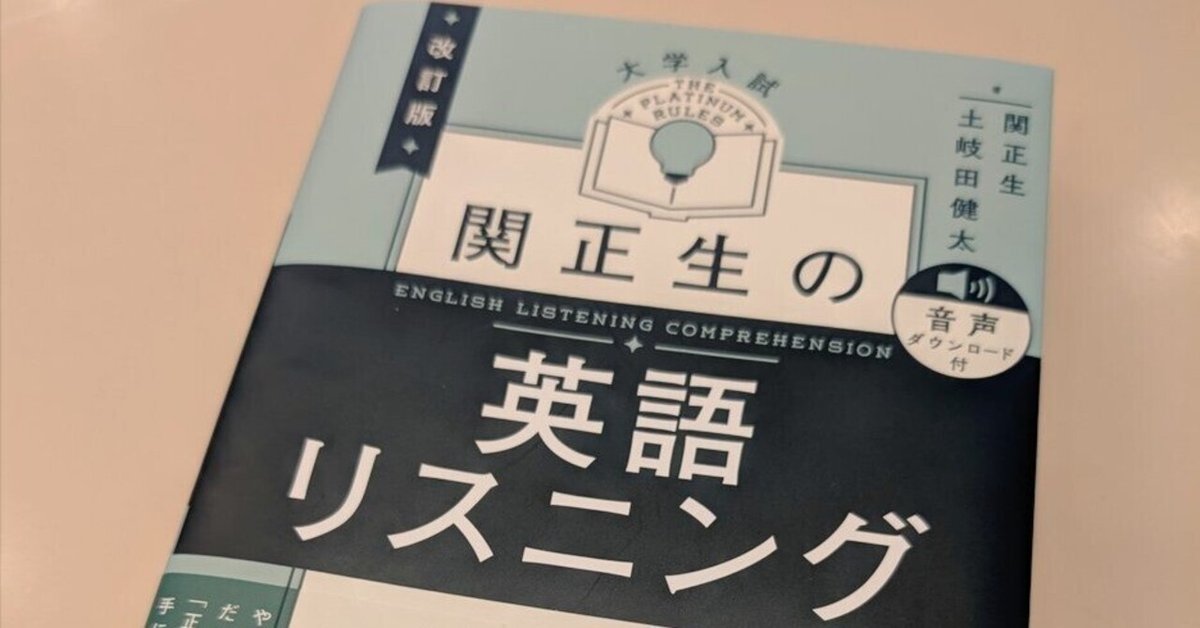
2025年にデビュー作の改訂版が出ます!~『改訂版 関正生の英語リスニング プラチナルール』(KADOKAWA)の出版~
『改訂版 大学入試 関正生の英語リスニング プラチナルール』(KADOKAWA)が2025年の最初の出版です。
この本は関正生先生と共著で書いた僕の2016年出版のデビュー作の改訂版(実に9年ぶりのリニューアル)です。
同時に関先生の4冊(リスニングも含む)のプラチナルールシリーズが改訂されています。関先生の単著として『改訂版 関正生の英語長文プラチナルール』、『改訂版 関正生の英作文プラチナルール』と関先生と斉藤健一先生の共著で『改訂版 関正生の英語発音・アクセントプラチナルール』がリニューアルしています。

1. リスニングのプラチナルールの主な変更点
さっそく、関先生と共著で書いた『改訂版 関正生の英語リスニング プラチナルール』に絞って説明していきます。
主な変更点として、改訂版ではセンター試験の問題をほとんど共通テストの新傾向の問題にしました。また、一部センター試験の問題でも、今でも通用する普遍的な良問は残してあります。共通テスト特有の短い対話問題、長い対話問題、イラスト問題、複数人のディスカッション問題などの対策も万全です。
共通テスト対策、英検®やTOEIC®対策の授業を各地で担当し、よりリスニングの解説力をブラッシュアップさせました。プラチナルールの出版以降リスニング対策で学校講演や集中講義も担当することが増えましたので、実際の現場での指導の知見も生かしています。2016年から2025年現在まで合計7カ所(3カ所の高等学校、3カ所の予備校、1カ所の経営したスクール)でのリスニング講座を担当しました。特に生徒が苦手としやすい問題形式やポイントをマスターできるように問題選定&解説をしたので、今回の改訂版ではまさに最新のリスニング対策にアップデートしました。
また、改訂版ではCDではなく、音声ダウンロード形式に変えています。便利なスマホアプリabceedにも対応しており、読者がより学習しやすくなりました。レイアウトもカバーは緑ベース、中身は目に優しい青を基調にした色に変わっており、学習の快適さが増しています。
2. 変わらない信念と新たな見所
①変わらない信念
最初に書いた時から、難関校のリスニング対策まで想定していたため、共通テスト対策から難関私大・国立の二次のリスニング問題対策にも幅広く使ってもらえます。最後の問題も長文リスニングを出題する青山学院大学の問題ですから、実は以前から英語難関校のリスニング試験対策、英検®準1級対策にも活用いただいていました。
元々リスニングのプラチナルールには2次試験や各大学のリスニング問題も多く採用していたこともあり、共通テストになってからもプラチナルールで解ける問題ばかりが出題されていました。計算問題のひっかけパターン、位置関係問題の重要ポイント、ディスカッション・講義形式のリスニングのアプローチ法など、あらゆる場面を想定して問題を選んでいたため、結果的に共通テストや新傾向にも十分応用が利く本になっていました。
それには関先生と土岐田のリスニング試験での経験や分析も活かされています。この話の理解を深めるために、リスニング試験導入の歴史や発展を紐解いてみるのも有益です。
僕が受験した当時(2006年)はセンター試験にリスニングが導入された最初の年であり、同学年の皆も慌てていました。ただ、リスニングはリーディングのサブ的位置付けで、配点は50点です。対策もやってみればリーディングに比べてもはるかに簡単な印象でした。僕はこのリスニング音声自体は「音声が遅いし、ものすごく簡単」と感じ、事実余裕で満点が取れるレベルまで行けました。
しかし、リスニングは実はスピード感、話者の癖や問題形式によって難易度が変わります。
海外のニュースやドラマはやはり難しかったですし、当時留学生や選択授業で取った映画のナチュラルスピードの会話はついていくのが大変でした。高3時に英検準1級を取得した時も「本当にこの教材や試験のスピードのリスニングができれば、将来リアルな会話についていけるのか」と疑問にも思っていました。
その懸念は見事2次試験のリスニングで的中してしまいます。英文科や外国語学部などの2次試験では特別にリスニング試験が課されることが一般的でした。特に2次試験のリスニングはブラックボックスで、非公表の大学も多かったです。情報が今のように手に入れにくく、効果的なリスニング対策はあまりなされていませんでした。また、実際に手に入る限り音源も活用しましたが、本番のナレーターは必ずしもプロのナレーターではない(自前の音声なので、もしかしたら在籍するネイティブの先生が吹き込んだものかも)点も本番の試験時の難易度を高めていました。これこそ生徒が「本番は難しく感じた」と感想を述べる理由なのです。
これはコラムに詳しくエピソードを書いたのですが、僕が上智大学を受験した時は2次試験にリスニングと面接の試験がありました。(今はTEAPでリスニングが必要な人も)リスニングがその場で読み上げられるイギリス人ネイティブの先生の英語には不慣れなこともあり、やや聴き取りづらく感じました。2次試験では当時自分の意見や考えを求められる英語面接もあり、「リスニング力」こそ、受験生が鍛えておくべき重要な技能であるということを痛感したのです。無事合格したものの、リスニング力の向上に対する興味・関心は入学後も深まりました。モデル通訳や音声のルールの研究も深め、その後予備校でも毎年指導しています。
②新たな見所
リスニングは学参市場が狭いようでもありますが、必要な受験生にどうしても届けたいコンテンツです。時間が限られた受験生がきちんと間に合うリスニング対策こそ、リスニングのプラチナルールにおいて関先生と僕が最優先に考えたことでした。抽象的な対策法とやみくもな数をこなす練習の奨励ではなく、具体的な対策法を音のルール、英文のルール、解法のルールでまとめることを本の指針にしていきました。
現在はプラチナルールが受験生へ定番書として浸透しつつあり、共通テストで多くの受験生がリスニングの必要に迫られている(難易度が上がり、かつ100点分の比重を占める)ため、大学入試におけるリスニング市場も拡大しました。
つまり、集中的に「本番以上の負荷をかけたリスニング力の向上」ができる本こそが受験生の求める本になったのです。まさに、時代がプラチナルールにようやく追いついてきたわけで、そのタイミングでの改訂版の出版とはありがたいことです。
見所として、新しいプラチナルールやリスニングの知識のまとめも増えています。その中には共通テストとTOEIC®の比較研究で培った見解もあります。その上で、TOEIC®と共通テストではそのテスト理念が大きく違いますから、どういった点をひっかけパターンにするのか、共通テストの新傾向でどのようなことが想定できるかも新しく採用したルールとまとめには反映しています。
関先生はTOEIC® L&Rテスト対策の著作も多く書かれており、共通テストへの影響についても人一倍分析なさっています。僕もTOEIC®を受験・研究する中で得た知見を本書の共通テスト対策の解説でも活かしています。今は出ていなくても、「これから出そう」というポイントとして解説に盛り込みました。そういった点も改訂版では妥協なく加えており、これはこの本の著者が二人ともTOEIC®990点満点講師であることが活かされた点であると考えます。
3. デビュー作の改訂への感謝
受験生の頃から2次試験でも使えるリスニング本の出版を目指してきました。
現在の入試ではリスニングが共通テストでリーディングと同じ比重の点数になり、受験生の優先順位が上がりました。その反面、共通テストのリスニングが難しいと感じる受験生も多くいます。この本では「共通テストのリスニングは余裕」と言えるレベルを目指せる本になったと自負しています。
音声には英米の音声スピードが2レベルで学習できます。これはリスニングの難易度を上げる方法がスピードとスピーカーの発音の多様性に影響を受けることが理由です。関先生と僕が現在もTOEIC®の分析を重ね、過去にも日常会話(ビジネス英語)の英語の分析も一緒に取り組んだことがあるからこそ、難易度が高い練習も必要だと考えました。練習と本番の微妙な差、そして目の前のリスニング試験で成果を出すだけではなく、最も難しいスキルの一つであるリスニングの速さや発音の多様性の現実を知って欲しいという想いもあります。関正生先生のプラチナルールシリーズでの共著という形で、この僕たちの理想が実現できました。
デビュー作を書かせていただいた関正生先生とKADOKAWAの皆さまにいつも感謝しております。関先生は僕がまだ大学院生の頃、教師セミナーでもお世話になり、その時のご縁から仕事につながりました。その時に学んだことが今僕が仕事をする上での宝物です。YouTubeでもほぼすべてのセミナーに来ていた話を関先生がしてくださっていますが、おそらく当時のセミナーでは全部吸収しようと全ての回に参加していたと思います!

また、発音・アクセントのプラチナルールを関先生と共著で書いた斉藤健一先生には出版当時からずっと公私ともによくしていただいている先生です。

関先生がYouTube内で「関ファミリー」というフレーズを使ってくださっており、僕たちは今回の改訂でも密にミーティングを行い、シリーズ著者のメールでの情報共有もしながら進めました。特に最初の集まりの時は関先生に出版の想いを色々話していただき、僕たちはそのあともカフェで話し込みました。もっと向上したいという集まりがプラチナルールシリーズの著者の共通点ですね。関先生がそのような著者の集いになるように、リーダーシップを発揮してくださったと言えます!
※これは関先生が一番下のYouTubeのリンクで具体的なエピソードを話してくださっています!
最後に、改訂版になる前に70,000部(26刷)を突破した本書リスニングのプラチナルールは多くの読者に愛された本でもあります。改訂版になると、累計で80,000部も突破します!関先生、編集者の皆さま、何より読者の皆さまにご縁をいただき、この本は改訂版の出版の日を迎えます。普段の受講生や生徒の皆さんも僕の著者デビューを後押ししてくれました。この場を借りてお礼申し上げます。
リスニングのプラチナルールは皆さんのさらなる目標達成を後押しできる本にリニューアルしました。新たなプラチナルールシリーズの誕生で、この本を使って目標大学への合格や将来の目標へのプラチナチケットにしてもらえたら著者冥利に尽きます。
【関正生先生のYouTubeチャンネルリンク】
改訂に関する解説で、ぜひそれぞれの改訂の特徴を把握するのにご覧になることをオススメします。製作にかける想いや想定読者層を著者本人から聞けるので、必見です!
関先生の単著と斉藤先生との共著、発音アクセントもおすすめです!
