
ダニエル ・ラノワ「Player, Piano」と幻想のケベック
2010年代からのラノワ
ダニエル ・ラノワの『ソウル・マイニング』(2013年、みすず書房刊。原著は2010年)は、文章が描き出す世界は詩的で美しく、奔放な構成は散文的で、まさに「ラノワの本」という感じだった。刊行時の初読からそう何度も読んでいるわけではないが、折に触れてパラパラ飛ばし読みしたり、彼の音楽を聴きながら該当箇所を読んだりしている。
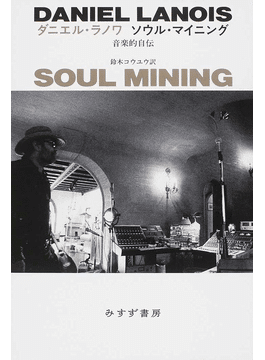
もちろん名盤・名録音の誕生秘話として、ラノワの頭の中、創造の源泉を辿るような内容は読み応えがある。しかし、それ以上に、幼少期のカナダの話、北米放浪の旅、ホーボーのようなミュージシャン生活……その中で見聞きした事柄や風景の描写に魅了された。
そして9月に出たラノワの新作「Player, Piano」はこの本のサウンドトラックのようだと感じた。
2010年代に入ってラノワは「Flesh and Maschine」「Goodbye to Language」「Venetian Snares x Daniel Lanois」とエレクトロ〜アンビエント作品を連続して出していた。彼のバンドプロジェクトだった「ブラック・ダブ」の反動のようなサウンドで、それはそれで嫌いではないのだが、個人的には「アカディ」的な歌ものが聞きたいという気持ちもあった(だが『アポロ』をCDとLPで2枚持ちする程度には、ラノワのアンビエントも好き)。
それが単独名義としては数年のインターバルを経た昨2021年に「Heavy Sun」をリリース。「アカディ」〜「イエロー・ムーン」につらなる、マジカルでソウルフルなラノワがまた戻ってきたと喜び、繰り返し聴いている。トロトロとしたグルーヴとたっぷりとしたエコー、そこに絡まるパワフルなヴォーカル。しかし細部の緩みなくきっちり締められたサウンドには、80年代懐古的な要素はなく、まさに「現代の」ラノワの音だった。たとえば思い切って装飾を排した『Please Don't Try』の美しさよ。
「Heavy Sun」は直接的にソウル〜ゴスペル的であり、それをエレクトロな側面とも拮抗させた構成が好きで、近頃はラノワが聴きたくなると同作に手が伸びている。
ピアノを軸にした新作の意外性
だから、「Heavy Sun」の流れから「Player, Piano」にもその路線(私の好み)を期待したのだが、それは大きく外された。だが、結果として外れてよかったのかもしれない。「Player, Piano」は素晴らしい作品だ。「アカディ」とは異なる意味でラノワを代表する1枚になるのではないか。それは作品の美しさと同時に、意外性も備えているからだ。

ラノワは1951年生まれなので、今年で71歳。57年7月の日付がついた幼少期のポートレートを採用したジャケットから想像できるような、人生振り返りモードの時期であり、その心象を反映した繊細な作品として聴くこともできるだろう。
だが……『ソウル・マイニング』を読む限り、彼の幼少期にピアノとの接点は見出せない。教会でピアノの音に親しんでいたかもしれないが、家系からの影響を含めてラノワは明らかに弦楽器から出発していたし、紛れもない「ギターの人」だ。
その意味ではラノワのドキュメンタリー映画であり『ソウル・マイニング』の実演版ともいえる『Here is What is』とそのサウンドトラックのほうが音楽的な自伝に近い。あるいは「Goodbye to Language」のようにラノワの手足の延長たるペダル・スティールで作り上げたアンビンエント作品は、ある種の集大成といえるだろう。90年代以降、ペダル・スティールの可能性を押し広げた立役者がラノワであることに異論はないはずだ。
ラノワはなぜ、こういう象徴的なジャケットを用いた作品でギターではなく「ピアノ」を主題にしたのだろうか。それが本作の意外性なのだが、聴き進めてしばらくしてはたと気が付いた。そのヒントも『ソウル・マイニング』あったのだ(そして『Here is What is』にはない)。
「Player, Piano」に収められた多くの曲は、そのアルバムタイトル通り、シンプルなピアノの旋律を軸にしている。「Player」と「Piano」をカンマで並べているそのニュアンスのまま、ラノワが一人ゆったりと朴訥とピアノをつまびく姿が思い浮かんでくる。
右手で弾いた単音のメロディーに左手を重ねて複雑にするのではなく、シンプルな右手のラインはそのままに、電子音がメロディに絡まって重奏される。ピアノがプリペアドされていたり、曲によってはリズムトラックの下支えもあるので、厳かさはたたえつつも、単純にクラシック的ではない。ピアノに寄り添いながらも、音素材として面白く響かせてもいる。
たとえば美しいメロディが耳を引く『Inverness』はピアノソロなのかと思いきや、途中途中で音像がベンドされたり残響を電子音と馴染ませてみたり、エレクトロっぽいフックが用意されている。また『Clinch』や『Lighthouse』といったエレクトロのアンビエント曲をそのまま生ピアノで弾き替えたような曲もある。
私がもっとも心奪われたのはフランス語で水を意味する『Eau』だ。フォークっぽいメロディを右手で奏で、左手はほぼルートだけ。その出だしでもっていかれた。それが40秒を過ぎたあたりから、水面の輝きのようにベルがきらきらと鳴らされ、オルガンの高音域やメロトロンっぽい持続音で一気に視界が開けていく。
水とラノワも不可分なモチーフだった。
これもまた水に関係する『Cascade』(滝の意)は純正ピアノソロ。しかし、一発録りではなく、1分22、3杪と1分32、3杪などでつんのめるような瞬間があるので、あえての編集点を「しかけ」として残しているのかもしれない。その通過時間あたりから、ペダル音か何かの動作音がずっと聞こえている。2分45、6杪の境目もカクっとくる。綺麗な曲だが完璧に流麗でない。そのためか、ナイアガラのような瀑布ではなく、落差の低い滝を思わせる。
幼少期の記憶と音楽
水とラノワとの関係といえば、「アカディ」の1曲目は『スティル・ウォーター』であるし、または代表曲『ザ・メイカー』の出だしの歌詞も印象深い。深い水底……その一言でこの曲の神性が担保されているかのようだ。
水はまた『ソウル・マイニング』の冒頭の描写にも現れていて、ケベックを流れるオタワ川、2つの世界を隔てる境界線として印象的な役割を果たしていた(そしてそれは豊かな自然としての景色よりも、みすぼらしい汚濁にまみれた景色だった)。だから、彼の中には原初の記憶の音として、水の音や律動がつねに息づいていたに違いない。
同時に、身近にあった音楽にはフレンチ・カナディアンとして受け継いできた民謡的な旋律があったことを同書でも触れている。
『Eau』を聴いてまっさきに思い浮かべたのが、アイルランドの民謡「サリーガーデン」だった(ドレミ始まりなのもあるが)。ケイト&アンナ・マッガリグルが歌うフレンチ・カナディアンの民謡、またはケイジャンなどを聴いてもわかるようにフレンチ・トラッドとブリティッシュ・トラッドは決して遠い存在ではない。旋律も用いる楽器も似ている。
何より、ダニエル ・ラノワが最初に手にした楽器がペニーホイッスル(ティンホイッスル)だったと『ソウル・マイニング』を飛ばし再読して思い出し、「サリーガーデン」を連想したことも間違いではなかった、と合点したのだった。
きっとラノワは、ホイッスルでなぐさみに奏でたかのようなメロディラインを、ポロポロと鍵盤に置き換えたのに違いない。『Eau』ばかりでなく、ピアノの単線的なメロディを主軸にしていうのもそんな理由なのではないだろうか。ジャケットに記された57年といえばラノワは6歳。幼児期最後の幸福さを、楽曲の中に落とし込んだのではないかと考えると、ほかには代えがたい価値を「Player, Piano」は放つようになる。
常に新しい音楽をクリエイトし続けてきたラノワは、こうした「意外」な「新しい形」で自らの記憶を表出したのではないか。だからこそ、本作は自身の幼少期を振り返った『ソウル・マイニング』のサウンドトラックであり、ラノワの心の中だけにある幻の「ケベック」を立ち上がらせる、音の幻灯機なのだ。
もちろん、録音のよさは言うまでもない。幻想的で、はかない夢のような音像が広がっている。
(了)
*素晴らしいトリオによる「The Maker」を。ブライアン・ブレイドのシンバルレガートは、こんな動画で聴いても美しい。さざなみのようだ。ラノワのレスポールの歪みの粒がきれいすぎる。
写真はSongfactsより。
