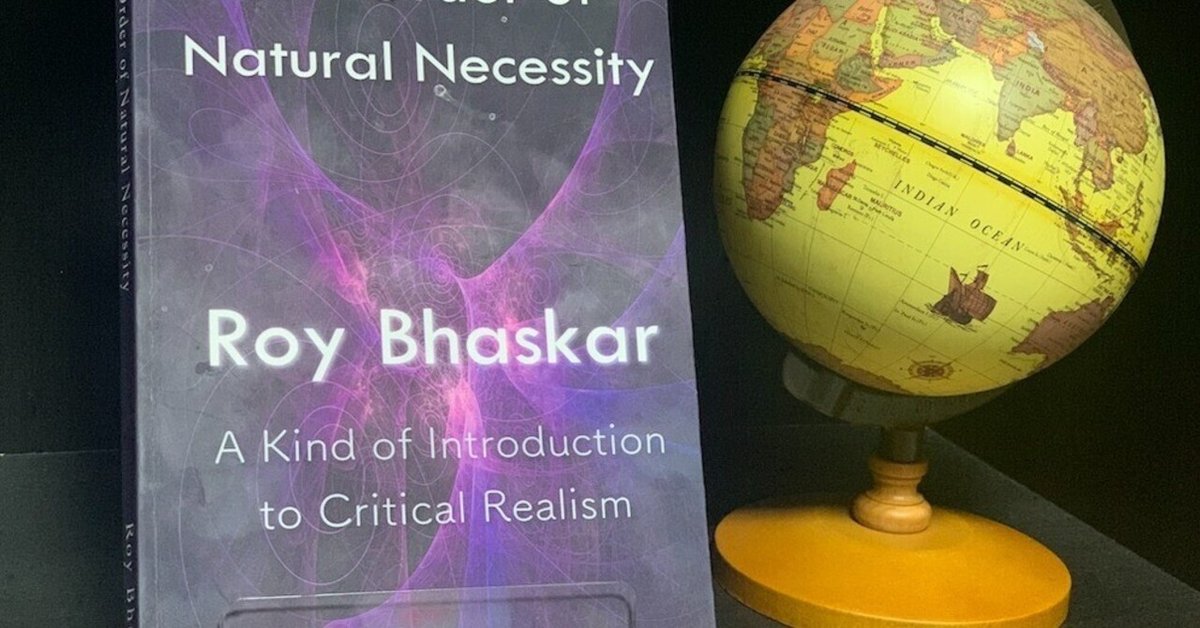
批判的実在論の意義とは何であるのか#437
わたしにとって、批判的実在論とは何だったのであろうか。
僅かながらも、いただいた貴重な命を使って探究したわけであるから、命はここで私に、1つの言語化を促してくるのである。
知的理解がそこまで得意ではない私にとって、それが哲学において、存在論や認識論において、あるいは実在論においてどう位置づけられるのかは、わたしのような人間の本分ではないであろう。
もっと素朴で、もっと日常的な何かで、もっといえば、今のわたしにとって意味を掬い上げるが重要なのである。
して、それを言葉にするならば、何であろうか。
それは「不在に目をやること」ではないだろうか。
不在にまなざしを向け、不在を不在化させることは、兎にも角にも価値があることであり、最早価値どころか貴い次元にまで逢着する。
思えば私たちの生活は、不在でできあがっていることをわきまえなくてはならなかった。
たとえば、人間の歴史というものは、学校の教科書みたいなものを思い浮かべるが、そこにあるのは言葉に過ぎず、歴史一般に過ぎず、あまりに時代観の違いから、そこにある実在に触れることは容易くない。
そのため、偉人の類は映画なりドキュメンタリーなりで我々に少しでも実在との距離を縮めてくれるわけで、それは大変有難いことである。
しかし歴史において、不在を不在化するというのは、真に歴史を形作っているのは、偉人のみならず、そこに眠るあまたの無名の命があることに照明することに他ならない。
目に見えるものの引力は凄まじい。我々は、人の目にうつり、語られるような仕事だけを仕事と言わんばかりの様相を醸し出すが、人々に語れるようなものと勝るとも劣らない千万無量の仕事が、私たちの意識の彼方に眠っている。瞬間瞬間に消えてゆき、報いを知らぬ仕事が。
そうやって不在へと意識を向けて見徹してゆけば、万感の思いに浸り、決して名状し難い深遠秘妙なるとてつもない何かに私たちは支えられ、生かされていることを観ずるようになってゆく。
かの有名なウィトゲンシュタインの奥深き言葉
「神秘とは、世界がいかにあるかではなく、世界があるというそのことである。」
というのは、不在に目を向けることによって、驚嘆と畏怖をもって世界と出会い直せるのである。
ここでいう目は、単に人間に肉眼をいうのみならず、時に目を閉じ心の瞳で観ていくような存在を含むことは言うまでもない。
そしてこのことは、何も世界の神秘に触れるのみならず、翻ってみれば、いつの日か名も忘れ去られる小さき自分をも慰藉することに還り、大いなる何かに連なる誇りを我々に与えてくれると思うのだ。
