
文字版 No2 銀座三丁目 カナエル通りの夢 第2話「カナエル通りの命の火」
「いらっしゃいませ」
薄暗い地下1階。
アーチ形のドアは開かれていて、足元はいくつもの照明で優しく照らされていた。階段を下りてくる足音が聞こえていたのだろうか。縁のない薄い眼鏡にさらりとした前髪の若い男性が、ゆみこを出迎えてくれた。黒いベストの胸元のソムリエバッジが、控えめで品のよい光沢を放っている。
「あの、一人なんです」
ゆみこは気後れしながら男性を見た。男性は優しく頷いた。
「お席をご用意できます。どうぞ」
ゆみこを招き入れた男性は、邪魔にならないようにゆみこの斜め前に立つと、こちらです、と歩き出した。
そんなに広くはない店内は、洞窟をすっぽりとくり抜いたような内装で、ところどころに置かれた間接照明やキャンドルが、薄暗い室内をあたたかく照らしていた。ゆみこのほかには誰もいない。
男性は壁側の奥まった4人がけのテーブルにゆみこを案内した。
「コートをお預かりしましょう」
そう言いながら、床に置かれた形のよい籠を取りだす。
「お荷物は、よろしければこちらに」
そして、ごく自然な仕草でゆみこがコートを脱ぐのを手伝ってくれた。男性の物腰はさりげなく、それでいてとても行き届いたホテルのサービスのようだった。若い男性にそんなに大切に接してもらったことのないゆみこは、かえって緊張しながら腰を下ろした。
知らない土地のレストランに一人で入るのは、それがはじめてだった。生まれて以来、ずっと両親と三人で暮らしてきたゆみこは、外で食事をすることがあまりなかった。
職場の忘年会や送別会、短大時代の数少ない友達からの誘い。両親以外で一緒に出かけるといえば、それくらいだった。そんなに気のすすまない場合でも、誘われれば、よほどのことがない限り断らないようにした。お洒落なレストランや行ったことのないカフェに行くのが楽しかったからだ。
学生時代の友人たちは、みんな結婚して子どももいて、会っても彼女たちの家庭や子どもの話なんかを聞いていることのほうが多く、正直にいうとどこか取り残されたような寂しさを感じることもあった。それでも、家や職場では見ない器や、手の込んだ盛りつけの料理を目にすると、不思議なくらい心が躍った。食べることも好きだけど、それ以上に、綺麗な食器や彩りの鮮やかな料理を見ることのほうが好きだった。
ただ、こんなふうに一人で、しかも夜に、きちんとしたレストランに出かけたことはなかった。
「先にお飲み物のメニューをご覧になりますか?ワインもソフトドリンクも、豊富にご用意していますよ」
男性が広げたドリンクメニューには、たしかにたくさんの飲み物の名前が並んでいた。イタリアンのレストランだけあって、やっぱりワインの品数がすごい。
普段は飲むことが滅多になかったけれど、ゆみこはアルコールが嫌いなわけではなかった。ゆみこの父の実家は造り酒屋で、祖父母の家を訪れる時には、その年の新酒の利き酒をすることもあった。お酒はゆみこにとって身近で、そして心をこめて接するものの象徴だった。酒造りの苦労を身近に知っていたからこそ、過度に飲みすぎることもなかったのかもしれない。
父の誕生日には、祖父から送られてくる上等の日本酒を一緒に飲むことが、二十歳を過ぎてからの楽しみの一つになっていた。
「グラスでのワインもいくつかご用意していますよ。お料理に合わせて、その都度頼まれてもよろしいかと」
男性の口調には押しつけがましさがまったくなかった。こんな店に一人で入るのが初めてなことも、財布の事情も察した上で、それでもとても大切に扱ってくれていることがよくわかった。体を強く縛っていた緊張が、するするとほどけていくような安心感があった。
「それでは、白ワインのグラスを頂けますか?」
ゆみこは肩の力をぬいて、そう言うことができた。言ったあとで、小さな嬉しさがこみ上げてきた。
「かしこまりました。ご用意いたしますので、よろしければお食事のメニューをご覧になっていてください。軽めのコース料理もございますし、もちろん一品物のお料理も取り揃えていますので」
男性に渡されたメニューは分厚く、まるで外国の古い本のような重厚感があった。値段のことを考えて、やっぱり少し不安になる。
いくらくらいするんだろう……。
、恐々とした気持ちでページを開くと、古風で見やすいフォントで印刷された、いくつもの料理の名前がずらりと並んでいた。
コース料理が4種類。アラカルトやデザートもたくさんある。聞きなれない名前の料理もあったけれど、そばには小さな文字で説明書きが添えられていた。値段も思っていたよりも全然高くなかった。場所が場所で、しかもソムリエの男性に迎えられ・・・。だから、メニューに書かれている値段の2倍くらいで済めばいいけれど、と身構えていたのだ。
でも、意外にも職場の近くの気の利いたレストランと変わらない金額に、ゆみこはほっと胸をなでおろした。安心すると、途端にメニューを読むのが楽しくなってきた。ゆみこはいつの間にか、一つ一つの料理の説明書きを熱心に読み始めていた。
「お好みのものは見つかりましたか?」
真新しいワインボトルをソムリエナイフで開けながら、男性はゆみこに微笑んだ。
「どれもおいしそうで。でも、食べたことのないものも多くて」
ゆみこは正直にそう言った。「わからない」ということを、初対面の人にこんなにも素直に言えたのは、もしかしたら初めてだったかもしれない。

「そうですよね。シェフはイタリア人で、あちらのレストランでの経験が長かったので、イタリアの地元の料理などものっていて。もしもお時間にゆとりがありましたら、シンプルなAコースはいかがでしょう? 女性の方でも食べられる分量に抑えていますし、今日は実は貸し切りに近い状態でして、ゆっくりとお食事を楽しむことができると思います」
「A 貴女のためのイタリアの風を楽しむコース」
そう書かれたコース料理は、確かにとてもおいしそうだった。
前菜 ホワイトアスパラとそら豆のサラダ トマトのカプレーゼ添え
3種のチーズの盛り合わせ
窯焼きの黒パンと白パン
海藻と水菜のコンソメスープ
小人のピザ
本日の魚料理または肉料理
ドルチェ
飲み物
小人のピザ?
にわかにお腹がすいてくる。ゆみこはささやくように音を立てた下腹部をそっとおさえた。
「そのコースをお願いします」
「かしこまりました」
お辞儀をして立ち去る男性の後ろ姿を見ていたゆみこは、キッチンと客席を隔てるように作られた、窯式のオーブンに気づいて目を留めた。古い映画や絵本に出てくるような大きなオーブンだった。中では本物の薪が燃えている。
ゆらゆらとゆれるオレンジ色の炎が、懐かしい何かを呼び寄せていいるような気がした。
「いらっしゃいませ」
薄暗い地下1階。
アーチ形のドアは開かれていて、足元はいくつもの照明で優しく照らされていた。階段を下りてくる足音が聞こえていたのだろうか。縁のない薄い眼鏡にさらりとした前髪の若い男性が、ゆみこを出迎えてくれた。黒いベストの胸元のソムリエバッジが、控えめで品のよい光沢を放っている。
「あの、一人なんです」
ゆみこは気後れしながら男性を見た。男性は優しく頷いた。
「お席をご用意できます。どうぞ」
ゆみこを招き入れた男性は、邪魔にならないようにゆみこの斜め前に立つと、こちらです、と歩き出した。
そんなに広くはない店内は、洞窟をすっぽりとくり抜いたような内装で、ところどころに置かれた間接照明やキャンドルが、薄暗い室内をあたたかく照らしていた。ゆみこのほかには誰もいない。
男性は壁側の奥まった4人がけのテーブルにゆみこを案内した。
「コートをお預かりしましょう」
そう言いながら、床に置かれた形のよい籠を取りだす。
「お荷物は、よろしければこちらに」
そして、ごく自然な仕草でゆみこがコートを脱ぐのを手伝ってくれた。男性の物腰はさりげなく、それでいてとても行き届いたホテルのサービスのようだった。若い男性にそんなに大切に接してもらったことのないゆみこは、かえって緊張しながら腰を下ろした。
知らない土地のレストランに一人で入るのは、それがはじめてだった。生まれて以来、ずっと両親と三人で暮らしてきたゆみこは、外で食事をすることがあまりなかった。
職場の忘年会や送別会、短大時代の数少ない友達からの誘い。両親以外で一緒に出かけるといえば、それくらいだった。そんなに気のすすまない場合でも、誘われれば、よほどのことがない限り断らないようにした。お洒落なレストランや行ったことのないカフェに行くのが楽しかったからだ。
学生時代の友人たちは、みんな結婚して子どももいて、会っても彼女たちの家庭や子どもの話なんかを聞いていることのほうが多く、正直にいうとどこか取り残されたような寂しさを感じることもあった。それでも、家や職場では見ない器や、手の込んだ盛りつけの料理を目にすると、不思議なくらい心が躍った。食べることも好きだけど、それ以上に、綺麗な食器や彩りの鮮やかな料理を見ることのほうが好きだった。
ただ、こんなふうに一人で、しかも夜に、きちんとしたレストランに出かけたことはなかった。
「先にお飲み物のメニューをご覧になりますか?ワインもソフトドリンクも、豊富にご用意していますよ」
男性が広げたドリンクメニューには、たしかにたくさんの飲み物の名前が並んでいた。イタリアンのレストランだけあって、やっぱりワインの品数がすごい。
普段は飲むことが滅多になかったけれど、ゆみこはアルコールが嫌いなわけではなかった。ゆみこの父の実家は造り酒屋で、祖父母の家を訪れる時には、その年の新酒の利き酒をすることもあった。お酒はゆみこにとって身近で、そして心をこめて接するものの象徴だった。酒造りの苦労を身近に知っていたからこそ、過度に飲みすぎることもなかったのかもしれない。
父の誕生日には、祖父から送られてくる上等の日本酒を一緒に飲むことが、二十歳を過ぎてからの楽しみの一つになっていた。
「グラスでのワインもいくつかご用意していますよ。お料理に合わせて、その都度頼まれてもよろしいかと」
男性の口調には押しつけがましさがまったくなかった。こんな店に一人で入るのが初めてなことも、財布の事情も察した上で、それでもとても大切に扱ってくれていることがよくわかった。体を強く縛っていた緊張が、するするとほどけていくような安心感があった。
「それでは、白ワインのグラスを頂けますか?」
ゆみこは肩の力をぬいて、そう言うことができた。言ったあとで、小さな嬉しさがこみ上げてきた。
「かしこまりました。ご用意いたしますので、よろしければお食事のメニューをご覧になっていてください。軽めのコース料理もございますし、もちろん一品物のお料理も取り揃えていますので」
男性に渡されたメニューは分厚く、まるで外国の古い本のような重厚感があった。値段のことを考えて、やっぱり少し不安になる。
いくらくらいするんだろう……。
、
恐々とした気持ちでページを開くと、古風で見やすいフォントで印刷された、いくつもの料理の名前がずらりと並んでいた。
コース料理が4種類。アラカルトやデザートもたくさんある。聞きなれない名前の料理もあったけれど、そばには小さな文字で説明書きが添えられていた。値段も思っていたよりも全然高くなかった。場所が場所で、しかもソムリエの男性に迎えられ・・・。だから、メニューに書かれている値段の2倍くらいで済めばいいけれど、と身構えていたのだ。
でも、意外にも職場の近くの気の利いたレストランと変わらない金額に、ゆみこはほっと胸をなでおろした。安心すると、途端にメニューを読むのが楽しくなってきた。ゆみこはいつの間にか、一つ一つの料理の説明書きを熱心に読み始めていた。
「お好みのものは見つかりましたか?」
真新しいワインボトルをソムリエナイフで開けながら、男性はゆみこに微笑んだ。
「どれもおいしそうで。でも、食べたことのないものも多くて」
ゆみこは正直にそう言った。「わからない」ということを、初対面の人にこんなにも素直に言えたのは、もしかしたら初めてだったかもしれない。

「そうですよね。シェフはイタリア人で、あちらのレストランでの経験が長かったので、イタリアの地元の料理などものっていて。もしもお時間にゆとりがありましたら、シンプルなAコースはいかがでしょう? 女性の方でも食べられる分量に抑えていますし、今日は実は貸し切りに近い状態でして、ゆっくりとお食事を楽しむことができると思います」
「A 貴女のためのイタリアの風を楽しむコース」
そう書かれたコース料理は、確かにとてもおいしそうだった。
前菜 ホワイトアスパラとそら豆のサラダ トマトのカプレーゼ添え
3種のチーズの盛り合わせ
窯焼きの黒パンと白パン
海藻と水菜のコンソメスープ
小人のピザ
本日の魚料理または肉料理
ドルチェ
飲み物
小人のピザ?
にわかにお腹がすいてくる。ゆみこはささやくように音を立てた下腹部をそっとおさえた。
「そのコースをお願いします」
「かしこまりました」
お辞儀をして立ち去る男性の後ろ姿を見ていたゆみこは、キッチンと客席を隔てるように作られた、窯式のオーブンに気づいて目を留めた。古い映画や絵本に出てくるような大きなオーブンだった。中では本物の薪が燃えている。

ゆらゆらとゆれるオレンジ色の炎が、懐かしい何かを呼び寄せていいるような気がした。
店の中では小さな音量でオペラが流れていた。曲に合わせて、キッチンの方からよく通る男性の歌い声が聞こえてくる。口ずさむ、という生易しいものではなく、舞台でしっかりと歌声を轟かせているテノール歌手のように朗々とした歌い声だ。
笑っては失礼だと思いながらも、あまりにも情感のこもった歌声で、なんだかおかしくて吹き出しそうなってしまう。あれが、男性の話していたシェフなのだろうか?
「遠慮なさらなくて大丈夫ですよ。向かいのバーから、よく苦情がくるくらいですから。店で流しているジャズよりもうるさく歌われたら、営業妨害だって」
いつの間にか前菜を並べてくれていた男性が、困ったように小さく笑った。

「シェフは気にも留めません。トゥーランドットの調べを理解しないやつなんか、ほうっておけって。シェフは、もともとオペラ歌手を目指していたんです。でも競争の激しいイタリアの音楽界では、なかなか現実は厳しかったようで。母親に説得されて料理人になったそうです」
男性の説明にかぶさるように、シェフの歌声が最高潮に達した。ゆみこは思わず声を立てて笑った。
「なんて楽しそうなのかしら」
聞きなれた声に驚いて顔を上げると、さっき別れたばかりの宝石店のオーナーの女性が立っていた。なめらかな白髪を上品にまとめ、深い藍色のロングコートを身にまとった姿は、宝石店で見たときとはまた違った雰囲気を漂わせていた。気品のある佇まいは変わらないが、うちとけた様子で笑顔を浮かべている様子が、どこか新鮮で親しみに満ちている。この店の常連なのかもしれない。
「ゆみこさん、またお会いできてうれしいわ。おひとり?」
「あ、はい。そのまま帰ろうと思っていたのですが、偶然看板を見て、それで急にお腹がすいてきて」
子どものように不格好に説明するゆみこに、女性は楽しそうに頷いた。
「ええ、わかるわ。オーブンから漂う燻製の香りがなかなかに強くて、私も仕事帰りによく寄るのよ。今夜はここは貸し切りなの。明日からシェフが急にイタリアに帰ることになってしまって。今日はうちの職人と佐伯君と4人で、当面のことを話しあうことになっていたのよ。よければこのテーブルにご一緒してもいいかしら」
女性の言葉に、ゆみこは慌てて立ち上がった。
「ええ、もちろんです。どうぞ」
「ありがとう。佐伯君。私にもゆみこさんと同じアスティをちょうだい」「かしこまりました、和美様」
和美、と呼ばれた女性はゆみこの向かいに腰を下ろすと、ゆみこにも座るように声をかけた
「年の瀬に困っていたところなの。でも、ゆみこさんとお食事ができるのならよかった。せっかくのご縁ですものね、シェフのお母様がご病気でね。明日にはイタリアに立つんだけど、いつ戻ってくるのか目途が立たなくて。かといって、このお店を閉めるわけにもいかない事情でね」
「それで、表にアシスタントシェフ募集の張り紙が」
「ええ、そうなの。ご覧になった? この店はどうしても開け続ける必要があるの。カナエル通りの命の火が消えると、通りの店が立ち行かなくなる。そんなジンクスがあって」
「カナエル通りの命の火?」
和美はうなずくと、ゆみこが見ていた大きな竈を指さした。ゆらゆらと炎の燃える昔ながらのオーブン。中には、さっきまではなかった鉄板が見えた。チーズの香ばしい匂いが漂ってくる。
小人のピザ?
「あのオーブンの火には、あるいわれがあって、どうしても絶やすわけにはいかないの。どんなに小さくてもいいから、毎日あのオーブンで料理を作ることが必要なのよ。急なことだったから、シェフが帰ってくるまで火の面倒を見てくれる料理人が見つからなくて、それで明日からどうするか話し合うことになっていたの」
和美の話に、ゆみこの息がほんの少し止まった。
5年務めてきた給食センター。
つい先々週、辞表を出したばかりの記憶が、ゆみこの脳裏によみがえっていた。
《第3話に続く》
~物語作家 ピカードいづみ~
《書籍》 ルディのダイヤモンド :
Amazon 電子書籍&ペーパーバック(紙の本)
世界で初めてダイヤモンドを研磨した、中世の宝石職人ベルケムとダイヤモンドの精霊の物語。この物語を出版した後、実在する銀座のジュエリーアーティスト、田村有弘氏が私の目の前に現れ、物語をイメージしたダイヤモンドのリングを制作してくれることになりました。(そのことを書いた記事は、こちらから)
不可能を可能に変える奥義、ダイヤモンドの精霊からのメッセージをぜひ、受け取ってください。
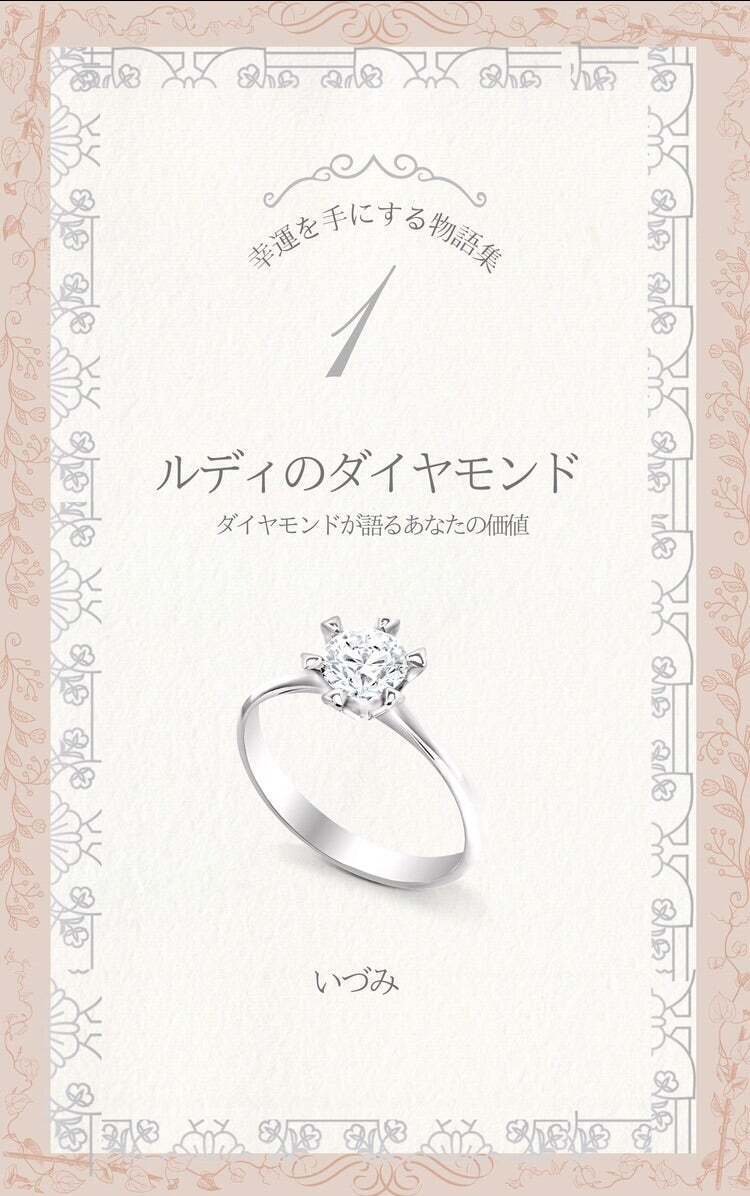
《書籍》 貴婦人の予祝 : Amazon 電子書籍&ペーパーバック(紙の本)

※ヒーリングセラピーについてのお問い合わせは、公式ラインで適宜お知らせしています。
#アラフィフ女子#エッセイ#銀座#ヒーリング#絵本#読書#錬金術#イタリアン#料理人#転職
店の中では小さな音量でオペラが流れていた。曲に合わせて、キッチンの方からよく通る男性の歌い声が聞こえてくる。口ずさむ、という生易しいものではなく、舞台でしっかりと歌声を轟かせているテノール歌手のように朗々とした歌い声だ。
笑っては失礼だと思いながらも、あまりにも情感のこもった歌声で、なんだかおかしくて吹き出しそうなってしまう。あれが、男性の話していたシェフなのだろうか?
「遠慮なさらなくて大丈夫ですよ。向かいのバーから、よく苦情がくるくらいですから。店で流しているジャズよりもうるさく歌われたら、営業妨害だって」
いつの間にか前菜を並べてくれていた男性が、困ったように小さく笑った。

「シェフは気にも留めません。トゥーランドットの調べを理解しないやつなんか、ほうっておけって。シェフは、もともとオペラ歌手を目指していたんです。でも競争の激しいイタリアの音楽界では、なかなか現実は厳しかったようで。母親に説得されて料理人になったそうです」
男性の説明にかぶさるように、シェフの歌声が最高潮に達した。ゆみこは思わず声を立てて笑った。
「なんて楽しそうなのかしら」
聞きなれた声に驚いて顔を上げると、さっき別れたばかりの宝石店のオーナーの女性が立っていた。なめらかな白髪を上品にまとめ、深い藍色のロングコートを身にまとった姿は、宝石店で見たときとはまた違った雰囲気を漂わせていた。気品のある佇まいは変わらないが、うちとけた様子で笑顔を浮かべている様子が、どこか新鮮で親しみに満ちている。この店の常連なのかもしれない。
「ゆみこさん、またお会いできてうれしいわ。おひとり?」
「あ、はい。そのまま帰ろうと思っていたのですが、偶然看板を見て、それで急にお腹がすいてきて」
子どものように不格好に説明するゆみこに、女性は楽しそうに頷いた。
「ええ、わかるわ。オーブンから漂う燻製の香りがなかなかに強くて、私も仕事帰りによく寄るのよ。今夜はここは貸し切りなの。明日からシェフが急にイタリアに帰ることになってしまって。今日はうちの職人と佐伯君と4人で、当面のことを話しあうことになっていたのよ。よければこのテーブルにご一緒してもいいかしら」
女性の言葉に、ゆみこは慌てて立ち上がった。
「ええ、もちろんです。どうぞ」
「ありがとう。佐伯君。私にもゆみこさんと同じアスティをちょうだい」
「かしこまりました、和美様」
和美、と呼ばれた女性はゆみこの向かいに腰を下ろすと、ゆみこにも座るように声をかけた。
「年の瀬に困っていたところなの。でも、ゆみこさんとお食事ができるのならよかった。せっかくのご縁ですものね、シェフのお母様がご病気でね。明日にはイタリアに立つんだけど、いつ戻ってくるのか目途が立たなくて。かといって、このお店を閉めるわけにもいかない事情でね」
「それで、表にアシスタントシェフ募集の張り紙が」
「ええ、そうなの。ご覧になった? この店はどうしても開け続ける必要があるの。カナエル通りの命の火が消えると、通りの店が立ち行かなくなる。そんなジンクスがあって」
「カナエル通りの命の火?」
和美はうなずくと、ゆみこが見ていた大きな竈を指さした。ゆらゆらと炎の燃える昔ながらのオーブン。中には、さっきまではなかった鉄板が見えた。チーズの香ばしい匂いが漂ってくる。
小人のピザ?
「あのオーブンの火には、あるいわれがあって、どうしても絶やすわけにはいかないの。どんなに小さくてもいいから、毎日あのオーブンで料理を作ることが必要なのよ。急なことだったから、シェフが帰ってくるまで火の面倒を見てくれる料理人が見つからなくて、それで明日からどうするか話し合うことになっていたの」
和美の話に、ゆみこの息がほんの少し止まった。
25年務めてきた給食センター。
つい先週、辞表を出したばかりの記憶が、ゆみこの脳裏によみがえっていた。
《第3話に続く》
~物語作家 ピカードいづみ~
《書籍》 ルディのダイヤモンド :
Amazon 電子書籍&ペーパーバック(紙の本)
世界で初めてダイヤモンドを研磨した、中世の宝石職人ベルケムとダイヤモンドの精霊の物語。この物語を出版した後、実在する銀座のジュエリーアーティスト、田村有弘氏が私の目の前に現れ、物語をイメージしたダイヤモンドのリングを制作してくれることになりました。(そのことを書いた記事は、こちらから)
不可能を可能に変える奥義、ダイヤモンドの精霊からのメッセージをぜひ、受け取ってください。

《書籍》 貴婦人の予祝 : Amazon 電子書籍&ペーパーバック(紙の本)

※ヒーリングセラピーについてのお問い合わせは、公式ラインで適宜お知らせしています。
いいなと思ったら応援しよう!

