
medu4やMedilinkなどの動画授業は医学生の学習習慣の基盤づくりになるか
国家試験対策と銘打ってる予備校に「卒後学習の足がかり」とか「土台作り」まで求めるのは少し無理がある気がする。
と考えるものの、実際にそれぞれの予備校はどんな理念で教材を提供しているのだろうか。
medilink
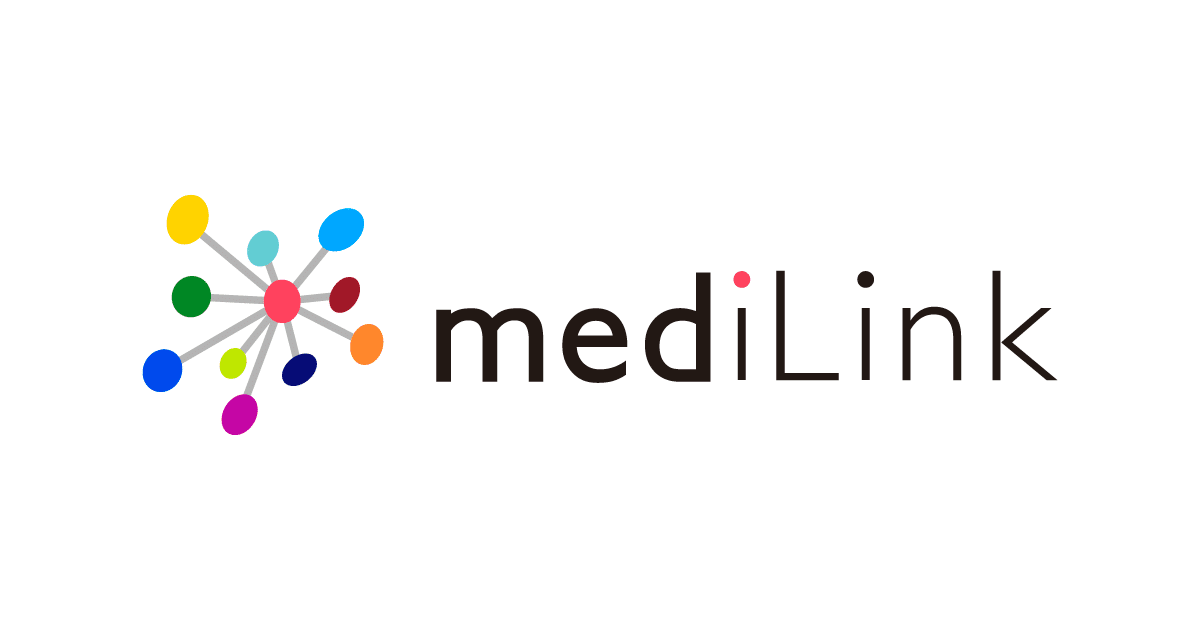
医学生の “学び” を、より楽しく、smart に。学ぶ人と教える人をともに支える e-school をつくりたい。そのような思いで、私たちは mediLink をつくりました。 第 1 段階として、理解・演習・補強、この 3 つの学びの流れを 1 つのアプリで一体化し、 スムーズに学習できるようにしました。
(中略)
・「イヤーノート」は,臨床実習・国試対策はもちろん,卒後臨床研修や専門医試験でも役立つ
・さらに,鑑別診断や手技,検査など臨床実習や初期研修など臨床現場で役立つコンテンツが段階的に充実
また、穂澄先生率いるmedu4の理念はこちら。

【medu4の5大ミッション】
1. 難解な医学的事象を分かりやすく多くの方に届ける
2. 必要な情報を、必要なタイミングで、具体的に提示する
3. 過不足のない100%を提示する
4. もう一度、ワクワクを取り戻す
5. 卒後も役立つ力を育成する
んーーー、これを見る限り、どちらの予備校も「卒業後に使い物にならない知識の提供」はしていないように見える。
でも、予備校におんぶにだっこで勉強する姿勢は、たしかに危険な香りがする。
そうか、ここか。
つまり、予備校主体で学習することに危機感を抱かれる時、というのは
「目標を達成したいと思った時、自分の力で何が必要なのかを理解し、それに向かって正しい方向性で努力をする」
そんな能力が身につかないことが危惧されているのではないだろうか。
ここで、医学部の特殊性について言及しよう。
医学部の特徴として
「所属した学部で学習する専門的職種に従事する割合が高い」
があると思っています。
つまり、医学部を卒業した人はほぼほぼ医者なる、ということです。
平成15,16年度の医学部卒業生の進路についての報告を見ると、卒業生6733人中、臨床研修に進む人は6598人(約97.9%)とのことです。
, 医学部医学科卒業者の進路状況調査 調査結果 より
同じ年の京都大学の産業別就職状況調査を見てみると、総合人間学部、文学部、教育学部など医学部以外の大学生の就職先は建設業、製造業、金融・保険業など多種多様でした。
これらは20年近く前のデータであることや、京都大学だけの状況であり単純に比較することは難しいです。また今の状況を反映しているとは言えません。
あくまでも、医学部を卒業して医師になる人の割合は高いのではないかと「示唆される」レベルです(もっと低いかもしれません)
正確さについてはさておき、ここでは
「〇〇学部を卒業して、〇〇に従事する人の割合は、医学部でめっぽう高い」
という前提で話を進めます。
この状況では、医学部に所属している間に学ぶ知識が卒後にも良い影響を与える可能性は高くなります。
では卒業して働く時に必要な知識というのは、在学中に学ぶ知識と全く違うものなのでしょうか??
答えはNo だと思います。
最も臨床実習にしか出ていないので、実際に現場に出た時にどうなるかは分かりません。臨床実習に出ている限り、座学で学ぶ内容は現場に近いものだと感じています。
話を戻します。今回の話は、
予備校で学習することで
「必要な情報は外部から与えてもらえる、後はそれを従順に熟すだけ」
という状況になり、
「目標を達成したいと思った時、自分の力で何が必要なのかを理解し、それに向かって正しい方向性で努力をする」
力が身につかないのではないか、ということが危惧されている。
そして、その力が必要になる理由を説明する際の根拠として
「卒業後に、在学中の学習が活きてくる環境で働く人の割合が高い医学部」
という環境の特殊性がある、という話をしました。
■ では、
「卒後に医者として働く人が多い」
医学部という場所で、
「自分で必要となるものを理解して正しい(目標達成に必要な)努力」
が出来る能力が必要とされるのは、何故でしょうか?
自論としては、
「いつまでも先生がいるわけじゃないから」
ということがあると思っています。
医学部在学中、予備校に方針を仰ぎ、勉強すれば良い。初期研修、上級医に指導を仰げば良い。後期研修、専攻医に指導を仰げば良い。
ではその後は‥?
そのうち「先生」がいなくなるときが来るのではないでしょうか。
その時に、自分で目標を設定して、自分の力で切り開いていく力が必要となる。
アンチ予備校の人は、こんな理由で「予備校に頼る学習」に警鐘を鳴らし(Tweet するだけですが)ているのではないでしょうか。
因みに、自分に必要な課題を自ら環境から見つけ出して学習していく姿勢のことを「自己調整学習」と呼びます。
学習者が〈動機づけ〉〈学習方略〉〈メタ認知〉の3要素に
おいて自分自身の学習過程に能動的に関与していること

医学部における自己調整学習。
これに関しては「医学部教育における自己調整学習力の育成」という本も出ていますので、興味のある方は是非手にとって見て下さい。
今日のNoteを通して、
「予備校はだめだ!!ガーーガーーー!!」
から、
「予備校を主体にした学習で自己調整学習力は身につくのか?」
という問いへと転換させることが出来たと思っています。
今後も考えていきましょう。
では。
あ、私はmedu4やMedilinkの授業は大好きですし、臨床医学の理解において自分の根底を成していると思っています。
その節は、大変お世話になっております。
