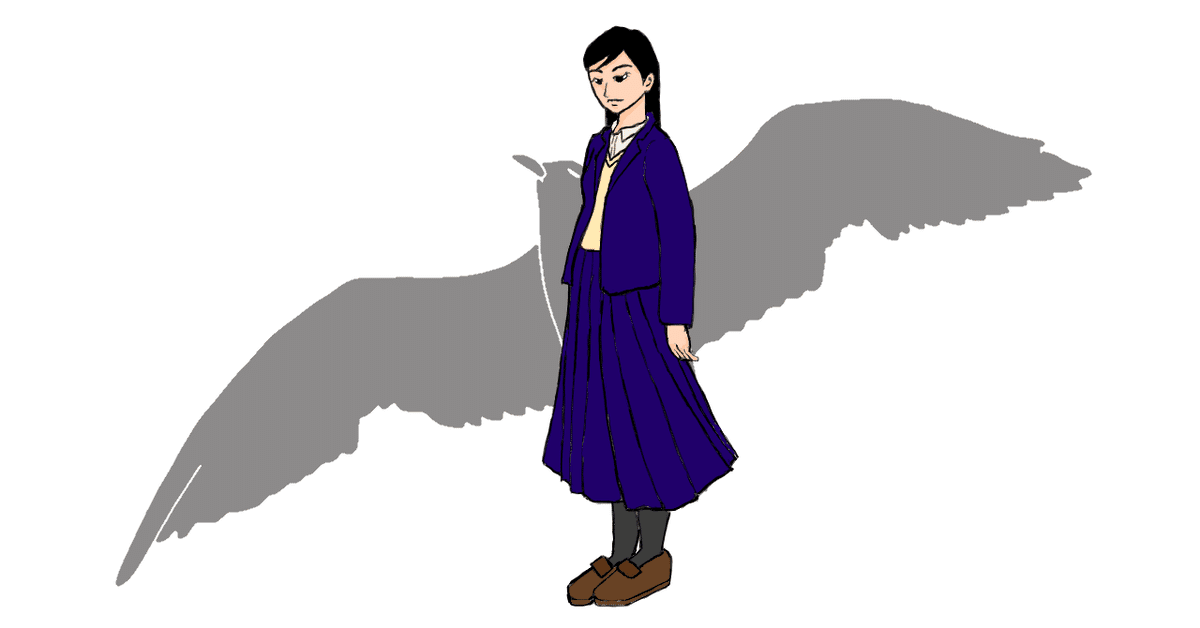
鳥【掌編小説】
黒髪は腰のあたりまでまっすぐ流れ、肌の白さを際立たせる。
切れ長の目は聡明な光を湛え、唇はほんのり紅い。頬は柔らかな曲線を描き、うなじは折れそうに細い。
だれが見てもうなずける美少女だった。
彼女の家は「鳥やしき」といわれている。
往来から見通せる広い庭に大小さまざまの籠があり、無数の鳥が入れられているのだ。
ハトだけでも20羽はいようか。小さいものはスズメに始まり、大きなものはなんとダチョウだ。
その異様さに恐れをなして、近辺の男たちも彼女には近づかなかった。
偶然である。
私は彼女がハトを捕獲するのを見ていた。
公園にいた、羽の傷ついた鳩だ。猫に襲われでもしたのか、血を流し、よたよたと歩いていた。
彼女がスカートのすそを翻し、背を丸めて走り寄り(その姿は大型の獣のようだった。少女の外観からは考えられないような身のこなしなのだ)、両手で鳩をすくいとって、学校の制服のブレザーに包み込んだ。
私は好奇心を抑えきれず聞いた。
「どうするの、それ」
彼女はこちらを見もせずに言った。
「飼います」
「あんなに飼っているのに?」
「ええ。まだ足りないんです」
数え切れないほどの鳥を集めて、まだ足りないなんて。
「なぜ? なにかに使うの?」
彼女ははじめてこちらを見た。
花の唇がほころぶ。
「ええ。大喰らいなんです」
黒い目がまばたきもせず私をとらえた。
あなたが深淵をのぞこうとするとき、深淵もまた、あなたをのぞきこんでいる。
このごろでは、珍しがってわざわざあの家を見に行く者も多いと聞いた。
謎は常に魅力的だが、リスクをともなうことを忘れてはならない。
