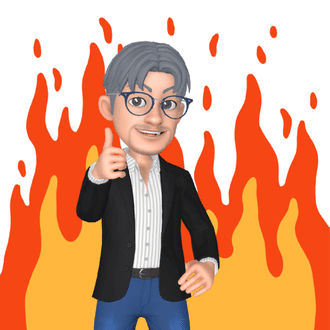ロボットがロボットを修復する時
先週の記事になりますが、ちょっと気になる記事を読んだので、今回はそのことについて書いていきましょう。
気になる記事はロボットの全自動ラインですが、まあここまではすでにあるんじゃないのかと持っていましたが、ロボットがロボットを修復や保守をするってことに目が行きました。
レベルにもよりますが、これってすごいことですよね。
最初の全自動ラインは既に2年前に見学した
ロボットが組み立て検査をするラインというのは既に2年前に見学したことが有る。
自動車の部品を作るような工場では、比較的珍しくないのではないかなと思う。
自分も自動車のダイナモを作成するラインを見たことが有るが、超長いラインで、1工程にロボットが3〜4台で構成されていた。
これはロボットの特性に合わせている内容で、部品を保持したり部品トレーから取り出してセットするのは多軸ロボットで、部品を組み合わせるとか挿入する作業はスカラーロボットが担当していた。
このラインで使用する板金部品などは、別の工程でロボットが作っておりある意味部品から組み立てまでを一つの工場内でロボット化している感じだった。
但し、そのロボットを管理したりするのは数名のサポーターがラインについてフォローをしていた。当然、超長いラインなので1工程が停止するとその後ろが全て止まってしまうので、復旧に緊急性を要していた。
しかし、その工程にまでいかないと、なぜ停止したががよくわからない工程となっており、IoTによる見えるかが急務だとそのときは感じていた。
電子部品を作るラインは更に進化していた
東北にある電子部品を作成する工場を見学したときには、自動車部品のロボットラインよりもっと進化していた。
一番驚いたのは、ロボットラインと自動機がうまく連携しているということだ。ロボットが自動機をうまく使っており、その自動機が安定して動くように、IoTにより状態監視が徹底されているということですね。
例えば、エアーを使って接着剤を塗布するような工程の場合、エアー圧をセンシングしている事はもちろんですが、塗布した接着剤の重量を測ることにより接着剤の使用量を管理し、押し出すエアー圧もコントロールしているということ。
そして、それらの機器は自製している場合が多いので、日常点検もタブレットを所定の位置にかざすだけで、各種の条件がBluetoothを経由して送られてくるので、人による書き写しエラーが回避されている。
したがって、可視化されている部分が多いので、フロア全体で設備をフォローする人材は極限にまで絞られており、生産エリアに2名程度しかおらず、その人達は通常は製品の修理作業をしており、設備不良が発生した場合には作業者のタブレットに故障した設備位置と停止内容が送られてくるようになっている。
エラー内容により過去の対処状況がリストアップされるので、その内容でチェックし設備を復旧させるようになっている。
最先端を行く自動車業界がすごいと思っていたが、それ以上の内容で構築されていたラインには驚いたものだ。
当然、ライン直行率も管理されておりロボットラインなのに直行率は90%以上を確保しているのには驚かされた。
これは設計と生産が一体になり、高生産ラインを構築するためにそのような設計にしている事が挙げられる。
更にはロボットがロボットをメンテナンスする
今回、京セラが日本全国16工場で無人のロボットラインを構築するということをニュース発表した。
先に書いたように、ロボットによる無人化ラインは既に多くの工場で投入されてきているのだが、それに加えてロボット同士の連携や自動メンテナンスによる完全無人化ラインを検討となっている。
もし、ロボットのトラブルやメンテナンスについて、ロボットが自己診断で解決することができたり、自動修復ができたりすれば驚くべきことになるが、そうでなくてもメンテナンスロボットが調子の悪いロボットを調整してくれるようになるだけでも驚きものですね。
これを実現するには、過去の同系列のメンテナンスデータを蓄積することは大前提とし、ロボットがメンテナンスや修理ができるように、事前にロボットをティーチングしなければならないからです。
今の所、ティーチング無しで自分で勝手に動くロボットは見たことも聞いたこともないので、実現にはかなりの知識と努力が必要になるかと思います。
物をセットするだけなら、始点と終点を設定して後はロボットに勝手にやらせることはできるかもしれませんが、部品を交換したり調整したりは難易度MAXですから同実現するのかが見ものです。
それこそターミネーターのスカイネットのようなシステムが無いと無理だと思いますが、現在の技術力では本当にできるのでしょうか。ボストンダイナミクス社の例もありますので、もしかしたら世界中のどこかで既に50%くらい実現しているベンチャーが有るのかもしれません。
いいなと思ったら応援しよう!