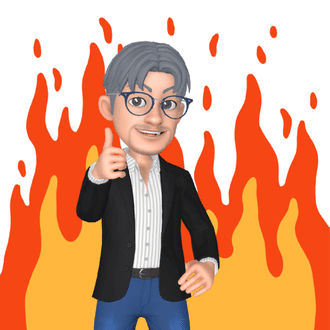本を読まなくなると考えなくなる
どうも、じぇいかわさきです。
みなさは本📕好きですか?よく読みますか?
今回は読書に関わる話です。
自分は読書が好きで、多い時は年間100冊以上読みましたが、最近は30冊くらいにまで落ちてるかなぁ。
最初にチョッとだけ、なんで本を読むようになったかの走りだけ書きますね。
高校も卒業間近、進学先も決まって余った時間に、たまたまテレビでやっていた映画が面白く、その原作を読んでみたのが始まりです。
そう、金田一耕助シリーズを書いた横溝正史の作品です。その後は大衆剣豪娯楽小説にハマり、新田次郎、池波正太郎、司馬遼太郎を貪るように読みました。
時代は流れ、社会人になってからは、専門職や自己啓発本をいっぱい読みましたね。
活字が好きで読んでると主人公になれたりする。でも社会人になって困った事も発生しました。
1番の問題は、本を読む事で理解して実践できるようになったと勘違いしてしまう事。
仕事に関係ある本を読んで、すでにその技術を取得し何でもできると思ってしまうことです。
これって多分専門書を読む人のアルアルネタじゃないかなぁ。
で、今回書きたかったのは、このアルアルネタではなくて、もっと別の事。
娘が高校時代の時、消費税制度が始まった。娘の宿題で、消費税制度に関するレポートを書けと言う宿題が出された。
そもそも、娘は本を読まず当時はガラケーばかりやってるタイプ。嫁さんも同じで、ガラケーでがなくテレビっ子タイプ。
そこにこんな宿題が出されたので、二人では何も分からずに四苦八苦しており、自分に救いの手を認めてきた。
結果、代わりに消費税の必要性や世界的に見たときの消費税の導入などを織り交ぜてレポートの下書きを作った。
これもビジネス書を読んだり、当時は海外出張が多く日本以外では消費税が導入されていたので、実際の買い物などの実体験を混ぜて書いたんです。
少なくとも、新聞を読んだりしていれば、もう少し自分なりにの考えを纏められたんじゃないかと思う。
またこんな事もあった。
算数などで、問題の考え方と言う算数の文章問題があるが、これが解けないのだ。
問題の考え方は、読解力が必要だと思う。すごく簡単な問題ですが、最近読んだニュースに書かれた問題にひかれた。
それは
A子さんのグループは10人で構成されています。今、背の小さい順に並んだ時、A子さんの前には4人います。それではA子さんの後ろには何人いますか?
この問題で、多くの子は6人と答えたそうだ。3児の母になった娘に、この問題を出したら、やはり6人と答えた。
そう、みんな単純に10人ー4人で6人と答えるみたいだ。
しかし、5番目がA子さんになるので、A子さんの後ろには残り5人なのだが、残りの中にA子さんが含まれてしまっているのだ。
すごく単純だが、問題をよく読めば間違えない。
文章、ここで言う問題の言わんとしている意図を理解できない証拠だ。
これは、普段から本を読んで著作が何を言おうとしているのかを、考える癖がついていれば間違わない。
小説でも同じで、読んだ文章のシーンをイメージできると、更に本は楽しいものになる。
昔言われた事が有り、子供達に勉強を教える時に言っていた言葉がある。
「正しい問いには答えが書いてある」と
「読書百遍自ずから通ず」です。
子供達に言いたかったのは、正しく問われている問題には答えが書いてあるから、分かるまで問題を読み直すといいよと。
問題を100回とは言わないが、何遍も読んでいると、なんだって気がつく事があるんですよね。
このように、読書をよくする人は、問題もよく読むので直ぐに理解し回答が出せる。
しかし、普段読書をしない人は、考えることがクセにならないので、解けないのだ。
だから読書は大事なんだよね。
読書は、別に本でなくてもニュースだってかまわない。noteの記事だっていいと思うよ。
活字を目から入れ、脳で意味を考える。これが1番重要な事なんじゃないかなぁ。
だから今日も自分は、いろんなニュースとnoteの記事を読むよ。そして、たまに本を読むんだ。
読書は楽しいぜ👍
いいなと思ったら応援しよう!