
東京学生映画祭史 1988-2021
1988年、昭和最後の秋に始まった東京学生映画祭(東学祭)は、2021年時点で32回目を迎えました。東学祭は文字通り都内で開催される、学生が作った映画(=学生映画)だけを対象にした映画祭です。

映画祭といっても、企画・運営まで学生が行なっているので、サークルの自主上映会に近いものがあります。ただ、過去には青山真治や園子温、井土紀州、熊澤尚人、中村義洋、月川翔、小泉徳宏、奥山由之、中川龍太郎、山戸結希、見里朝希といった歴々たる方々の初期作を紹介するなど、インディーズ映画界でちょっとした話題を呼んだこともありました。
私は2020年の秋から1年間、東学祭の代表をつとめました。この記事では、映画祭の過去33年の歴史を私なりに分析し、概観的な通史のようなものを練り上げてみたいと思います。
過去の出来事を機械的に要約するだけではなく、あえて映画祭とは直接関係のない時代のトレンドや、私個人の視点を踏襲しながら、積極的に迂回することに注力しました。そのため、少々周りくどい読み味になってしまいましたし、私の未熟な知識と文章の展開が、あるいは恣意的な印象を抱かせてしまうかもしれません。
ただ、私が今後も含め、しっかりとこの映画祭と向き合い、思いの丈を消化するためには、一定以上の手前勝手な文量が必要でした。

事前に強調しておきたいのは、あくまでこの記事は既に代表を退いた私による、趣味記事とも呼べる何かであるということです。
掲載することが憚られる内容は特にありませんが、映画祭の面子とは関わりのない一個人としての見解が強いので、独自の取材記事(あるいはしがないOBの心疾しい後日談!)くらいに認識していただきたいと思っています。もっとも東学祭は、ただのサークルで、基本的には代表であった私が思いの丈を述べることに躊躇する理由はあまりないと思いますが、例え大袈裟に思われようと、お世話になってきた委員や先輩、関係者との間に不用意なトラブルを招きたくはなかったので、そう書かずにはいられませんでした。
……という仰々しい前置きを挟んでも尚、このような記事を書かなければならなかった理由について、先に簡単に記しておきます。それはざっくり言うと、私が東学祭で得た、普段は中々知ることができない、かといって活用する術もない、だからこそ重要な知識や経験を、しっかりと自分の中で体系化しておきたいという気持ちが強くなったからです。そして一度アーカイブ化してしまえば、過去の関係者が当時を振り返る、あるいは現役世代が資料として参照する契機を作れるのではないか、とも考えたからです。
これだけの過去がありながら(そして私自身も多くの学びを得ながら)、特にその歴史が体系化されることなく、放置されてしまっている事態には、どこか勿体無さがありました。あくまで私個人の興味本意として、何とか現役の学生という立場でいられるうちに、これまで社会のスポットライトが当てられることのなかった学生映画、そして何より映画祭そのものの歴史を、概観的に振り返ってみたいという気持ちが強くなったのです。
もちろん、終わってみれば約100,000字(薄めな新書程度?)にまで膨らんでしまった私のパーソナルな分析も、一部の専門的に詳しい方から見れば、荒唐無稽に映るのかもしれません。私が生まれていない時期も長いので、知識不足は免れませんし、それを補う文章力もありません。だからこそ本来であれば、もっと映画祭の歴史に造詣が深いOB・OGの方が書くべきだったのかもしれません。
ただ私は、既に社会的立場のある方には書くことのできない、現役の学生としての視点を大切にしたいと考えました。さらに言えば、東学祭について口を開くことができるのは、現役の学生だけなのだとも考えました。今の東学祭をある程度は理解し、その過去を分析的に概観した上で、それを個人の記事としてアーカイブ化しようなど考える委員は、今のところ私ひとりしかいませんでした。
詳しくは、記事全般に渡って紹介していきますが、この誰も知らない小さな映画祭史にも、当事者である学生の人生を変えてしまうだけの希望と、同時に絶望が存在しています。映画を嫌いになってしまった誰かにも、エゴイスティックな成功ばかりに固執した誰かにも、物珍しそうに側から見ていただけの誰かにも、それぞれ別個の物語が存在しています。
それら物語の多層を、私一人の視点で無造作にまとめてしまう危険性については承知しているつもりです。ただ少なくともこの記事は、私の記憶が途切れてしまう前に、しかるべき手順で過去を振り返りつつ、時間を掛けて納得した史観ではあるので、自信を持って公開することに決めました。例え誰かから反感を買ってしまっても、長きに渡ってアーカイブ化する意義はあると踏みました。
ただ、そうは言っても——諄いかもしれませんが——たかだか私個人の拙い史観に、一読の価値があるかは分かりません。正直、私個人の想いよりも、全く学生映画に関心がない方に向けて「軽い読み物の一つとして楽しく読んでいただきたい」という気持ちの方が優っています。それでいて、こんなニッチな世界があるのか、と興味を持っていただいた方が、東学祭のHPや各種SNSに目を通し、次年度の映画祭に足を運んでいただける、ということが一番の本望です。
過去の入選作品は、U-NEXTやAmazon Primeなど各種配信サービスで、手軽に観られるようになっています(こんな時代は、今までにありませんでした!)。仮に一度でもご覧いただければ、学生ならではの青臭くも強かな雰囲気と、巷に溢れる映画と負けずとも劣らない独創性を垣間見ることができるでしょう。
あくまでこの記事はざっくりとした通史であり、私個人の恣意的な史観であり、この試みは、次の未来へ映画祭を伝承する誰かの意思によって、初めて完成されるべきものです。終盤では、学生向けに実施したアンケート結果などを踏まえ、2年半に渡って学生映画を定点観測してきた私が、学生が映画をどう捉えているか、もといこれからの学生映画はどうあるべきか、という私なりの現在地を提示してみるつもりです。私たちは、過去を踏まえ、そして現在地を認識できた時、初めて未来の地平線を歩むことができるのだと思います。(そういう希望的な言い回しも、学生故の青臭さなのかもしれません。)
前置きが長くなってしまいましたが、いよいよ次から、33年の歴史を紐解いていきます。記事を幾つかに分けて投稿することも考えましたが、長々しい時の流れを、ありのまま1ページで体感していただきたいという思いがあったので、あえてこのような形式を取りました。話が余談めいている時は網掛けのブロックで区切るので、場合によっては読み飛ばして貰って構いません。
(補足)
……と言っても、世の中の大半の方は、学生映画に触れたことすらないと思うので、実際の歴史に入る前に、前提の補足をする必要があると思います。
今の東学祭は、学生映画の定義を「撮影時に学生であること」としています。年齢に関わらず、どこかの学校に在学している者が撮った映画は、学生映画としてカテゴライズしています。近年は映画学校が増加しているので、そうした層もインディーズ映画全般の大きなボリュームゾーンを占めるようになりました。
少なくとも学生映画は、日本で年間1000本近くは撮られていると思います。正確な数値が分からないのは、大半の学生映画は公にすらならず、一部の映画祭やサークル、映画学校を除き、日常的にお目に掛かれるものでもないアングラ文化だからです。そもそも「映画とは何か」の定義すら曖昧で、専門家でも意見が分かれる、といった事情も考慮する必要があります。例えば、YouTubeに溢れている有象無象の動画でも、本人が「映画だ!」と言えば、実際の映画としてカテゴライズされてしまうケースも往々にしてあるのです。
実際に学生映画の上映会が開かれても、観客の大半は作品関係者で埋まっていて、それ以外も一部のコアなインディーズ映画好き、という程度です。近年はDOKUSO映画館等での配信も始まり、全国的に視聴できるエコシステムが整ってきてはいますが、学生映画が同人誌と似た、極めて小規模なサブカルであるという本質は変わりません(こちらの経緯は、後に詳しく説明します)。
そのため学生映画には、普段から私たちが親しんでいる映画とも異なる、独特の内輪臭が漂っています。国立美術館の企画展ではなく、小さなギャラリーで催されるグループ展、のような趣でしょうか(一部では「シネクラブ」と呼ばれるそうです)。集客は、作品の質より、監督や主要スタッフ、映画祭のブランド力に根ざしており、メジャー監督の過去作を除き、新作のプレミア以外にあまり上映価値はありません。そのため、あまりにも観客が少なく、そうした空気感の中では「誰のためにやってるんだ」と思われても仕方がないほど、観客が少なく、外部との関わりが希薄なケースも頻繁に発生しています。
他方で強調しておきたいのは、学生映画のほとんどは、本気で映画業界を志し、将来の邦画界を担いたい若者の結晶である、という点です。斎藤工は「学生という環境こそ、最も”今”に敏感に生活していると思います。」と、黒沢清は「いま世界の映画関係者で、学生映画出身でない人を探すのは難しいでしょう。それぐらい学生映画は定着し、商業映画を根底から支える豊かな土壌となっています。」と指摘しています。学生の間しか味わえない高揚感、あるいは行き場のない緊張感は、時に自由で、爆発的な発想を生み出し、やがて商業映画の鉱脈に連なっていきます。中には、後に語り継がれる伝説の学生映画も存在しますが、それも数年に1本程度の割合で、映画好き界隈でちょっとした話題に上るのが関の山です。ただ、学生映画は、その99.9%が徹底的に(あるいは即物的に)消費されているからこそ、余計に「”今”に敏感」にならざるを得ないのであり、一回性を尊ぶ古典的な映画ファン層(あるいはシネフィル)にとって、最もあらまほしい映画体験の一つということもできます。
東学祭は、自らも学生によって運営されているからこそ、どこよりも力を入れて学生映画を扱い、その魅力を雄弁に語ってきました。コンペティションの一部で学生映画を扱う映画祭は無数にありますが、学生映画のみに特化し、学生のみによって自主運営されながら、しかも30年以上も続いている映画祭は、日本中どこを探しても東学祭くらいしかありません(真偽は定かではありませんが、早稲田ウィークリーによると、ヨーロッパでも2010年の「カ・フォスカリショートフィルムフェスティバル(CFSFF)」が初めてだそうです)。
そのような視点に立った上でぜひ、この映画祭のポテンシャル(と同時にそのナンセンス)を読み解いていただきたいと思っています。
また、記事を進めるにあたって、どうしても特定の映画祭や映画監督、会場、企業の固有名詞を出さない訳にはいきませんでした。多くの記述は、現在の東学祭に辛うじて受け継がれてきた資料に拠っていますが、それでも主たるものは紛失していますし、多少なりとも委員間で慣習的に引き継がれた情報も存在します。不特定な情報や、扱い方に困っている情報に関しては、必要に応じて匿名化していますが、それでも事実誤認は免れないと思っています。もちろん、特定の団体や個人を中傷する意図は全くなく、全体に渡って然るべき引用の手続き、正誤性の判断を行っていくつもりです。
ちなみに余談ではありますが、私は性格的に、物事をさも意義深く素晴らしいものであったか、あるいは没意義で虚無的であったかを、いくらか誇大化させて表現してしまう嫌いがあるようです。今回の記事では立場を弁え、抑制の効いた物言いを心掛けますが、それでも「学園祭の機運」や「まったりとした意識改革」など、印象的なフレーズを、あえて恣意的に多用しています。これは全く私個人の志向という他ありませんが、ここには言葉遊びを通して映画祭の実像を浮かび上がらせたいという、私なりの意図があったりもします。
あまり言葉の表面に囚われず皆さんなりに、この映画祭の歴史や雰囲気を知っていただければ幸甚です。冒頭に示したように、この記事は一見すると本筋とは関係ない議論へ、積極的に迂回しているかのように見えます。周りくどいのは承知ですが、学生・学生映画としての第一歩は、いかに受験的で無機質な要件事実から抜け出し、一筋縄ではいかない世の中の命題に立ち向かってゆくか、だとも思うのです。
第1回(1988)〜第4回(1991)

会場:スタジオams(三軒茶屋)
<ゲスト>
渡辺文樹、山川直人、黒沢清、小中和哉
原一男、佐野和宏、かながわのぶひろ
相米慎二、石井隆、根本敬、金子修介、万田邦敏
東学祭には元々、早稲田合体映画祭という前身組織が存在していました。合体映画祭は、第1回東学祭の前年(1987)に始まり、恐らく現在も続いている早稲田映画まつりの前身(あるいは同一組織)でもあります。
合体映画祭は名の通り、早稲田大学内だけで成り立つ内向きの映画祭でした。当時の早稲田大学に何個の映画サークルがあったかは分かりませんが、現在の早稲田には、公認されているだけで8つもの映画サークルがあります。公認されていないものを含めるともっと多いと思われますが、少なくとも学内だけで映画祭の番組が組めるほど、今も昔も大きな規模を誇っています。
インカレ映画祭へ

ある時期を過ぎると、合体映画祭のメンバー数人は、他大学との交流が促されていない、いわば内輪盛り上がりの形態に不全感を抱き始めます。
早稲田大学は一般大(=非映画学校)だったので、特に芸術系の大学との関わりが希薄でした。映画祭をより充実したものにするには、どうにかして芸術系の大学との交流を深めてコミュニティを形成し、扱う学生映画の範囲を広げなければなりませんでした。特にこの時期は、映画学校が乱立する前で、一般大の映画カリキュラムも整っていなかった頃なので、いかにして一般大の学生が芸術系の学生と交流し、刺激し合うか、といった視座はとても重要だったと思います。
じきに彼らは、合体映画祭と分化し、都内全域を包括するような「東京学生映画祭」なる上映会の形態を模索し始めます。
ちなみに、同時期に早稲田大学に存在していた、かのイベントサークル「スーパーフリー」は、1982年に設立されたそうです。スーパーフリーは、1998年4月頃から常習的に極悪非道な事件を起こし、後に法律を変える程の社会的波紋を巻き起こしましたが、極めて猥雑なインカレサークルのノリは、80年代に生み出されたものだったのかもしれません。もしかすると東学祭にも似たような阿漕な精神が存在した可能性も、否定できない程度にはあります。
また、スーパーフリーが常習的に事件を起こし始める1ヶ月前、映画評論家・蓮實重彦は東大総長として初めて卒業式を迎え、「ノーパンしゃぶしゃぶ事件」はじめキャリア官僚の猥雑な不祥事を引き合いに警鐘を鳴らす、異例の祝辞を述べました。同じ年のアメリカでは、後に度重なるスキャンダルによって「#MeToo」運動の引き金となったハーヴェイ・ワインスタインが『恋におちたシェイクスピア』(1998年)でアカデミー作品賞を受賞し、ハリウッドで最も権威のある映画プロデューサーに登り詰めていました。
……ただ、こういった歴史的な視点も、私個人が過去をある特定の偏った色眼鏡で眺めて抱いたに過ぎない、時代錯誤のようなものかもしれませんね。

1988年、ams西武三軒茶屋店の5階にあったスタジオams。
まるで昭和最後に盛大な花火が打ち上げられたかのように、東学祭は幕を開けました。スタジオamsは同年に開館したばかり、日活ロマンポルノが終わりを迎え——昭和天皇の重体で自粛ムードが漂っていたものの——まさに新しさを希求していた時代の空気を象徴する何かが、そこには存在していました。
当時のフライヤーには、「都内近郊17キャンパスから33サークルが参加する一大イベント!」と記されており、11月18日~11月30日の13日間にも及ぶ長期間の映画祭になっています。チケットも「前売り:300円」「当日:500円」と極めて安く、招待ゲストには、黒沢清、原一男、相米慎二、石井隆、万田邦敏といった名だたる重鎮の監督が揃っていました。今振り返ってみても、第1回の景気付けには相応しい、華々しい内容です。
セゾン系列の劇場であるスタジオamsは、第12回まで継続して使用された会場です。当時の情報は少ないのですが、どうやら1950年代前後の東宝・松竹を中心に、小津や溝口などの巨匠作品とも異なる、巷にはあまり出ない希少な旧作ばかり上映していたようです。そのため、当時でもかなりのシネフィル(映画狂)が集まる場所になっていました。
東学祭はそれ以後、新宿文化センター、青山ウィメンズプラザ、お台場フィルムセンター、北沢タウンホールといった公営施設や大学のホールを転々とすることになりますが、設立当初は民営の小スタジオだったのです。当時はバブル期で、「学生がイベントを開く」といったらすぐにスポンサーが付いてしまう時代でした。東学祭も、セゾンカードに就職したOBの仲介で、スタジオamsを無償で借り入れることに成功しました(その委員は知り合いに尋ね回り、セゾンカードの入会を促したそうです)。
ちなみに、amsは元々、緑屋という百貨店の系統でした。しかし、当時は押しも押されぬ資本力を持っていたセゾングループと提携を組んでからは、西武の名を冠して店舗が運営されていました。写真にもある通り、三軒茶屋にあるams西武の運営母体は西友ですが、当時は系列店のほとんどに西武という枕詞が付いていたほど、その名が飛ぶ鳥を落とす勢いだった時代です。今でこそ西友、LIVIN、LOFT、無印良品といった各店舗はそれぞれ独立した趣向を感じさせますが、バブル期にはセゾン、西武といった名が絶大な影響力を誇っていたのです。
スタジオamsの延長線にあるセゾン文化の中でも、とりわけ象徴的なのは、西武渋谷店シード館の最上階にあったシードホール(THE SEED HALL)でしょう。そこは、ミニシアターや劇場、ライブスペースやインスタレーションなどを兼ねた多目的ホールとなっており、ミュージシャンの福富幸宏や小山田圭吾、小説家の阿部和重などがアルバイトをしていたことでも有名です。
その他、後に「J文学」なる潮流を産み出す中原昌也や保坂和志、佐々木敦などの映画と近接した文化人も、セゾンの現場にいました。
セゾン文化、ミニシアターブーム、立教ヌーベルバーグ

さらに、1988年について詳しく調べてみると、その年は東京テアトルがセゾングループの子会社となった年でもありました(後に撤退)。
当時のセゾングループは、百貨店を起点に「時代精神の根據地」を掲げ、美術館、書店、劇場、FMラジオ、ホテル・リゾートといった一連の文化戦略を繰り広げていました。先鋭的な映画興行もその一環で、東京ではシネ・ヴィヴァン・六本木、シネセゾン渋谷 、キネカ大森、キネカ錦糸町、パルコスペースPART3といった映画館がセゾン系列だったそうですし、『人間の約束』(吉田喜重)『千利休 本覺坊遺文』(熊井啓)『Focus』(井坂聡)『友達』(堤清二)といった傑作群も、セゾンの映画事業の一環でした。中でも、前述したシードホール(THE SEED HALL)やセゾン美術館などは、様々なカルチャーを多義的に融合する、80年代的な時代精神を体現していたように思えます。
以上の背景から、セゾン系列のスタジオamsで開催された東学祭はいわば、——もちろん一義的に、ということですが——セゾン文化の末端と呼ぶことができそうです。
また、同じ1988年に公開された『ベルリン 天使の詩』や、翌年の『ニュー・シネマ・パラダイス』といった作品が、単館上映で歴史的なヒットを飛ばした事実は、いわゆる80年代ミニシアターブームがピークを迎えていた事実を指し示しているように思えます。
当時の東京では、大使館経由のアート映画や、欧米の優れたインディーズ映画など、これまで観ることが叶わなかった良質映画を、至る所で鑑賞することができました。蓮實重彦も、『映画狂人日記』(1992)にて「どうやら東京は、ここ10年ほどの間に、パリにも匹敵する映画都市になってしまったらしい」「質と量において、ニューヨークを遥かに凌いでいる」と明言しているくらいです。
ちなみに当時、立教大学で教鞭を取っていた蓮實の「映画表現論」の講義には、黒沢清、森達也、万田邦敏、周防正行、青山真治、塩田明彦、篠崎誠といった名だたる立教出身の映画監督が出席していました。80年代は学生映画のレベルも総じて高く、自主制作の第1次ブームとも呼べる時期に相当するそうですが、一般大である立教大学から生まれたこの稀な潮流は、立教ヌーベルバーグとも呼ばれています。特に黒沢清、万田邦敏の2人は初期の東学祭に度々審査員として登壇していますし、青山真治も第2回東学祭の入選監督であることを考えると、東学祭と立教ヌーベルバーグは極めて近接した関係にあったといえるでしょう。
自主制作の第1次ブームを下支えした80年代ミニシアターブームは、例えば堀越謙三が1982年に桜丘町(現在は円山町)で開館したユーロスペースをメルクマールに、ヴィム・ヴェンダース、クローネンバーグ、張芸謀、ラース・フォン・トリアーら名だたる監督の作品をいち早く日本に紹介し、「先取り」「封切り」といった、ミニシアターの役割を固定化しました。ユーロスペースは、立教ヌーベルバーグの面々に加え原一男 、瀬々敬久ら名匠の初期作も上映し、「インディーズ映画がユーロスペースから旅立つ」という1つの流れは、今なお残っています。ちなみに第30〜32回の東学祭も、ユーロスペースが入館する同じキノハウスのユーロライブで開催されています。
さらにこの時期は、ミニシアターブームに加え、国際映画祭ブームも重なっています。
東京国際映画祭('85〜)、広島国際アニメーションフェスティバル('85〜)、イメージフォーラム・フェスティバル('87〜)、山形国際ドキュメンタリー映画祭('89〜)、ゆうばり国際ファンタスティック映画祭('90〜)、アジアフォーカス・福岡国際映画祭('91〜)と例を挙げていくと枚挙に暇がありませんが、特に80年代半ば以降から、国際的な映画交流の機運が全国的に高まっていたのです。その背景には、バブル経済下のふるさと創生事業('88〜89)に象徴される、公的資金の地方分配があって、多くの自治体は村おこしの一環として、映画祭を好んで採用したのです。
映画祭は他のイベントと比べ、世代を超えて娯楽性も高く、低予算で実現できます。その点において、各地で積極的に採用されやすい因子が揃っていたのですね。
【拙記事紹介】
80年代ミニシアターブームや、セゾン文化について興味がある方は、以下の拙記事を参照してみてください。UPLINKが閉館した渋谷を起点に、60年代以降のミニシアター文化を私なりにまとめています。
ちなみに、セゾン隆盛やミニシアターブームの背景にあったのは、ある一面ではポストモダンの文化潮流でした。私が論うのは身に余りますが、特に日本におけるポストモダンとは、「政治の季節」を終えた人々が安定的な消費社会に生きるにつれて、近代(モダン)の問題意識を脱却し、芸術、哲学、建築といった各分野で高級性を追求し始めた時代のことで、日本では一般的に浅田彰の晦渋な『構造と力』や中沢新一の『チベットのモーツァルト』などの上級者向け図書がベストセラーを記録し、彼らに加え蓮實重彦や柄谷行人らを筆頭にした評論家のニュー・アカデミズムが流行したり、建築では東京都庁舎などのポストモダン建築が相次いだり、一見すると「鼻持ちならない高学歴インテリがエスプリを利かせていた」とも捉えかられない、経済的に悠然としていたバブル時代です。そんな中、セゾン(とりわけ時代の寵児となった堤清二)は渋谷を拠点に、「百貨店」や「広告」といったものを武器に一時代を築いたのでした。
また、バブルを象徴する映画祭とでも呼べる東京国際ファンタスティック映画祭は、東学祭が始まる3年前(1985)に渋谷の東急文化会館で始まりました。「東京ファンタ」とも呼ばれたこの映画祭は、香港、韓国、インドといった国のインパクトが強い映画や、欧米の一部で流行っていたカルト映画を先駆けて紹介し、ジャンル映画のブームを牽引しました。
そして何より、自主映画という営みそれ自体がポストモダン的と言って然るべきだと思っています。自主映画を可能にした8mmフィルムが一般化したのは70年代前半で——『スパイの妻』(2020)にある通り、1920年代には一部の上流階級で既に自主映画9.5mmフィルムが流通していた事実には驚くべきものがありますが——一連のヌーベルバーグ運動を経ています。つまり始まりの時点から自主映画の作り手は、自分達が撮っている作品があくまで既存作品に影響され尽くしたパッチワークでしかない、というメタ的な認識を持っていたのだと思います。言い換えれば、自主映画はそれが「自主」である時点で、既存の「商業」と比べられる宿命にある、ということもできると思います。いずれにせよ、自主映画は、その概念から具体的な成り立ちまで、十把一絡げにポストモダン的な批評の振るいに掛けられてしまう性質を持っているのかもしれません。
以上をまとめると、華々しい(ある一面ではポストモダンの)セゾン文化やミニシアターブーム、第1次自主制作ブーム(立教ヌーベルバーグ)、国際映画祭ブームの陰で——ある意味、それらを総合的に象徴するように——産声を上げたのが、東学祭だったといえるかもしれません。
スタジオamsで開催されていた頃の記録はほとんど残っていませんし、セゾン文化やミニシアターブームと絡めた過去の言及も見当たりません。果たして、東学祭がポストモダン的な意識高さを持っていたのか、第1次自主制作ブームの延長にあるのか、東京ファンタ的バブリーな多幸感を持っていたのか、はたまたインカレのスーパーフリー的阿漕な精神に満ち満ちていたのかは、定かではありません。
いずれにしても、こうした図式的な時代性に東学祭を落とし込もうとし過ぎるのも、我田引水の嫌いがあるのだと思います。
あくまでも持論の域を出ませんが、当時の学生映画を紐解くのに必要になるかもしれない複数のセクションは、今後とも似たような道筋・立論で追っていきたいと考えています。
8mmフィルムと初期衝動
第1回の会期は13日間にも渡りましたが、当初は任意の17大学から33サークルが参加する「参加団体制」が採用されました。先に記しておくと、全国の学生であれば誰でも応募できる「公募」の仕組みを採用するようになったのは、第27回(2015)以降のことです。
設立されてしばらくは応募数も少なかったため、「グランプリ」「観客賞」などを決める一般的なコンペティションではなく、可能な限り全ての応募作が上映されました。後にコンペティションが導入されるのは、第5回を待たなければなりませんが、まずは映画祭の趣旨を理解してもらい、学生映画の間口を広げたい、といった意味合いが強かったのだと思われます。もっとも当時の委員は、それらのアジェンダがその後30年以上にも渡って継続されることになるとは、夢にも思わなかったでしょう。

会場:スタジオams(三軒茶屋)
出身:青山真治
<ゲスト>
万田邦敏、伊藤智生、山田太一、小松隆志
金子修介、山川直人、かわなかのぶひろ、 渡辺えり子
崔洋一、小中和哉、黒沢清、楳図かずお
手塚真、 長崎俊一、若松孝二、渡辺文樹
第2回になると、参加団体は22大学43サークルへと拡大し、ゲストにも山田太一、楳図かずお、手塚真といった、バリエーションに富んだ方々が招待されるようになります。山田太一は、脚本家の「四天王」とも呼ばれたテレビドラマのヒットメイカーで、楳図かずおは当時 『週刊少年サンデー』で「平成版まことちゃん」を連載していた日本を代表する漫画家でした。手塚治虫を父にもつ手塚真も、Vシネマの草分け的な存在となる『妖怪天国』(1986)を監督し、手塚治虫、水木しげる、楳図かずおといった漫画家たちを登場させて話題を呼んでいました。
以下の産経新聞の記事は、第2回の入選監督である青山真治に関する記述です。
蓮實の授業に触発され、ゴダールやヴェンダースといったさまざまな名匠の映画を見まくり、どうしたらああいう
映像が撮れるのかを実験するという意味合いで8ミリを撮るようになる。やがて、学生映画祭などの上映会で触
れた黒沢と万田邦敏(四七)の作品に感動。卒業するころには、自分の作品を大学の偉大な先輩に見てもらいた
いという欲求が強くなっていった。
【競う ライバル物語】(126)世界を翔ける日本映画の精鋭(4)
産経新聞 2003-10-09・東京朝刊・オピニオン 黒沢清と万田邦敏の名前が一致しているので、ここに書いている学生映画祭とは、東学祭のことで間違いないでしょう。青山真治は3〜5つあった立教大学の映画サークルの中で映画研究会に所属していて、黒沢清や万田邦敏率いるユニットパロディアス・ユニティには所属していませんでした。青山真治は、後に黒沢清、万田邦敏の助監督を務めることになるので、あるいは東学祭が彼らを「運命的に引き合わせた」、と解釈することはできないでしょうか。(*2022年3月21日追記 あまりに電撃的で、早すぎるご逝去に驚きを隠せません。ご冥福をお祈りしております。)
ちなみに同年、スタジオamsにて東学祭の「番外編」なる上映会も行われています。上映後の討論会で司会を務めていたのは、当時成城大学に在籍し、東学祭の委員でもあった熊沢尚人です。熊沢尚人は、『ニライカナイからの手紙』『君に届け』といった有名作品に加え、近年では『ごっこ』『おもいで写眞』といった作品を監督し、今も現役で活躍しています。
第1回、第2回と、押しも押されぬ勢いで規模を広げた東学祭ですが、当時は今と比べ、学生が活動的に集会しやすい機運があったのだと推測できます。近年は学生がネットを介して他大のコミュニティに参加することは容易ですし、東学祭も時代に合わせて、ブログ、ホムペ、mixi、Twitter、サークル情報サイト、アプリ、Instagram等を使って、都内近郊の学生を呼び込んできました。
ただ、時代が進むにつれて、オウム真理教の事件('95)、早稲田祭の中止('97〜01)、SEALDsの反政府デモ('15〜16)などに象徴される、学生の活動的な勧誘の機運は、ますます鈍化していったように思います。特にIT化が進んだ2010年代以降、(『絶望の国の幸福な若者たち』(2011)に登場するような)災害ボランティアやイノベーティブな学生ビジネス、SDGs的な社会貢献の精神が勢いを増し、芸術にうつつを抜かして非社会的な振る舞いをする学生が、時代の外に追い遣られた印象があります(ポストモダニズム的に言えば「大きな物語」が終焉し、芸術のサブカル化が進んだことの証左でしょうか)。私の勝手な考えだと、オンライン化が図られた2020年代以後の「Z世代」は、政治や芸術の活動的な集会が制限され、大学や国の体制に不満を抱きながらも、決して抗議の声を上げない無頓着な自己観が芽生えてしまい、益々の投票不振、芸術不振すらも招いてしまっているのだと思います。
私は個人的に、東学祭が容易にコミュニティを拡大することができた背景に、前述したような若者の機運があったのではないかと推測していますが、もっと単純にそれらを、学生の草の根にある情熱に見出した方が、遥かに簡単なような気もします。
当時はDVDが流通する10年も前で、学生は最も手軽に映画を撮ることが可能だった8mmフィルムで映画を制作していました。先行世代は高価で手が届かなかった8mmフィルムは、その頃から安価になり、かつその片手で持てる利便性が、裕福さに裏打ちされた崇高さとも異なった、ある種ノリで映画を撮ってしまえる初期衝動を象徴しています。例えば青山真治は、8mmフィルムについて、以下のコメントを東学祭に寄せました。
私たちの大半は8mmフィルムで撮影し、編集し、上映していて、いまとなっては信じ難い困難と
ともにあったはずですが、それでも易々とその障碍を乗り越えて脆弱な夢にしがみついていた、
まさに驚くべき若さの暴走と申せましょう。打倒PFF・打倒保守の気分だけはいまも大いなる
幻影として心の片隅に残っています。いまの皆さんは何を考えて作っているのか、一度訊いてみ
たいものです。
(25周年記念冊子) まさに、青山真治らしいエスプリの効いたコメントですが、やはり当時は8mmフィルムが自主映画の象徴だったことが伺えます。「脆弱な夢」と表現されているものは、モラトリアムである学生の不安定な初期衝動を指しているように思えますし、もしかすると、そこには当時から打倒PFFが半ば密かに意識されていた、ある種の対抗文化にも似た欲望があったのかもしれません。
PFFは、明くる第38回で「8ミリマッドネス!!~自主映画パンク時代~」と題された世界巡礼企画を開催し、石井岳龍(特に『狂い咲きサンダーロード』1980)、塚本晋也、園子温、矢口史靖といった監督らの、まさに「自主映画パンク時代」とでも呼ぶに相応しい8mmフィルムを特集しました。同じ第1次ブームの中でも、ゴダールや小津安二郎と比較されがちだった立教ヌーベルバーグとは異なった毛色の作品群です。ちなみに、東京2020五輪の記録映画を担当した河瀨直美も、自分の若かりし頃の衝動に回帰するために、競技会場へ8mmフィルムを持ち込みました。(NHKの字幕問題は残念でした。)
ただ、当時の8mmフィルムは、必ずしもPFFに入選するようなハイクオリティな作品ばかりだった訳ではありません。むしろ東学祭に入選した作品は、クオリティや洗練性を度外視した、極めて短絡的な作品が大半を占めていたのだとも推測されます。以下に引用する城定秀夫、石川北二のコメントは、まさにそういった短絡性を象徴しています。
僕も大学生のころ自主映画をやっていたのですが、まわりがビデオ撮りに移行する中
「映画はフィルムで撮らなきゃ映画じゃない!」という拘りのもと8mmフィルムで撮っ
ていました。現像が上がってくるまでどんな風に撮れているのか分からず、頑張って撮っ
たものが暗かったり、ボケてたりしたときの失望感はフィルム撮りでしか味わえないもの
ですし、バイト代がすべてフィルム代と現像代に消えてゆく絶望感もフィルム撮りでしか
味わえないものです。どっちも二度と味わいたくないですね。デジタル世代のみなさんは
幸せ者です!
因みに、そんな苦労をして作った映画を当時の東京学生映画祭に出すチャンスがあった
のですが、サークル代表を決めるジャンケンで負けたため出せませんでした。出品してい
るみなさんは幸せ者です!
(城定秀夫:第32回パンフレット) 当時の東京学生映画祭は、おバカ系特撮モノから鬱屈としたロードムービーまで…洗練された、
とは言い難い多彩な作品が上映され、ある意味、「自分が好きなら、なんでもあり!」という
自主映画ならではの魅力と熱気に溢れていたように思います。
(石川北二:25周年記念冊子) とてもフランクで、おどけた印象のある二人の口調ですが、つまり当時はこういった8mmフィルムの短絡性こそが、ある面の東学祭を形作っていたのです。
映画の体を成しているか分からない、そもそも現像されるかすらもわからない緊張感、現像費やフィルム費にバイト代が溶ける博打の軽々しさ。そこでは、石川北二の言う「自分が好きなら、なんでもあり!」といった半ば利己的な価値判断まで採用されていて、それが若者の草の根にある情熱として称揚されるムードが、学生映画を量産していたのです。
それに加えて私は、当時の東学祭をもっと分かりやすく、学園祭の機運が存在した、と表現してみたいと思います。これは映画秘宝の「中学生男子」感と通ずるものがあると思いますが、学生は社会的な立場がないからこそ、学園祭のような場所で羽目を外し、映画にうつつを抜かしていたのです。そして博打のように軽々しい感覚で青春を投げ出しながら、役者もスタッフ友人や知人で等身大だからこそ、自分たちを取り巻く何らかの規範に抗うように、およそアメリカン・ニュー・シネマで描かれたような「性」や「暴力」といった主題を好んで採用し、初期騒動を満たしていったのです。
少し話が逸れすぎるので、形式的にでも網掛けで区切っておきますが、一般的に学園祭に参加する学生には、良識の範囲内で楽しむ者、目先の享楽だけに興じてトチ狂う者、やる気を出すことを恥じて冷笑的に取り組む者、訳もなくエゴイスティックに成功に固執する者、様々いると思います。東学祭もそれは然りで、20年以上の前の資料にも、委員同士が深刻に揉めていた経緯が記されていましたし、基本的にトラブルのほとんどは、「〇〇が真剣に取り組んでいない」だの、「〇〇が不義理を犯した」だの、「〇〇は映画の見識がない」だのといった、極めて至らない若気の内輪揉めです。
学生であることは、——と書いている私も、ますます遣瀬なくなっているのですが——自由と引き換えに、ともすれば恩を仇で返しかねない、無責任の障壁が立ち塞がっているということだと思います。歴代の委員たちも、学生というモラトリアムに甘んじながら、時には他の委員の無作法な振る舞いに激怒し、時には朝まで呑み交わし、映画の希望と絶望を語る、といった具合に活動を続けてきたのでしょう。仲間たちの絆に嬉しくなる時もあれば、映画好きの若者を応援してくれる方々に胸が熱くなった時もあったでしょう。反面、損得ばかりを想定している企業、過剰な正義に駆られて生産的に運営できていない組織、その何処にも属さずに放浪を続けるエゴイスティックな個人、といった風に負の社会の縮図をも目の当たりにし、モラトリアムを脱することになるのです。それでモラトリアムを脱することができなかった一部の委員が、未だに偏狭であると言わざるを得ない映画業界へ旅立ち、今はその偏狭を維持するサイドに回っているのかもしれません。
私が代表をしていた第32回がどういう組織であったか、という内輪の話をするのは差し障りがあるので避けますが、恐らく、
映画に熱心ではない学生でも、やりがいを持って取り組める民主的な活動を目指すか。
といった点は、今も昔も通底している現実的な葛藤だと思います。もちろんそれがサークルである限り、「やりたい人がやったらいい」が原則ではありますが、かといってやる気のない委員を冷遇するといった振る舞いは大人気なく、サークルである以前に良心を疑ってしまいます。
また、上記の葛藤に加え、上級生が威力あるリーダーシップを発揮するべきか、マナーの悪い学生をどう対応したら良いか、恋愛を中心とした心理的トラブルはどう解消したら良いか、といった一般的な組織課題からは、どうしても免れなかったと思います。実際に私も、2年半を通じて大変多くの苦労した覚えがありますし、終わった今に至っても、全てが全てが解消された訳でもありません。
特に、東学祭のOB・OGなら理解していただけるかもしれませんが、学生映画にまつわる事務的かつマニアックな活動は、割りに映画に熱心でない学生にとって、遣り甲斐を感じにくい領域が多分を占めています。サークルの形態に、少しでも不全感を抱いた経験のある方は多いと思いますし、サークルが目的と意識の異なった、しかも金銭の絡まない身勝手な学生の集まりである以上、そのような組織課題は、構造的に解決不可能です。
おまけに、映画はある意味、宮崎駿と鈴木敏夫のコンビに象徴されるように、クリエイティビティと実運営をいかに折衷するか、という点でも最も難儀な芸術の1つであり、時には特定のオーソリティの意向を汲むため、下部の者が精神を擦り減らし続けなければなりません。オーソリティ側に天才的な説得力を持つ素材と、多少ブラックなりとも人に生業を提供するスタジオがあれば話は別ですが、いわんや学生サークルなどといった任意の形態においては、大体のケースで説得力のない素材を、半ば中途半端なモチベーションで実運営してゆくしかありません。インセンティブは、学生一人ひとりの仁義に依存していて、仁義なきサークルなどといったものに存在価値があるとは、私には思えません。仮にそんなものが存在するとしたら、大体はモラトリアムな学生故の惰性の産物でしょうし、行き過ぎれば非行・犯罪の臭いすら漂い始めるのかもしれません。

会場:スタジオams(三軒茶屋)
<ゲスト>
岡田裕、園子温、寺脇研、 手塚真
山川直人、利重剛、黒沢清、崔洋一
林海象、楳図かずお、今関あきよし、中原俊
押井守、若松孝二
東学祭が容易にコミュニティを拡大することができた背景には、前述した学園祭の機運の他に、「持ち込み」というアナログな形式で作品募集を行ってきた経緯もあったのだと思います。
フィルムは一般的に表面に傷が付きやすく、扱いが難しいとされています。そのため、原則として学生監督は東学祭委員の元へ足を運び、作品を手渡さなければなりませんでした。第5回までは応募作全てを上映していたので、もしかすると事前のやり取りは無く、ぶっつけ本番で上映をしていた可能性はあります。ただ、基本的には持ち込みによって「ちょっとあの大学へ足を運んでみよう」といった具合で、半自動的に学生間の繋がりが生まれたのだと思います。ちなみに、応募料は映画の尺を基準にしており、1分あたり100円だったそうです。今でこそ長編作品は多いものの、当時は短編作品が主の応募対象だったが故の料金設定です。
第4回は、1991年11月25日~12月7日の18日間に渡って開催されました(第3回の詳細は不明)。ゲストには園子温、山川直人、利重剛、今関あきよしといった、自主制作の第一次ブームを担った当時の若手が目立ちますが、当時『ケルベロス・サーガ』の実写を撮っていた、押井守の名前も挙がっています。
石川北二のコメントにあった、8mmフィルムのおバカ系特撮モノと聞いて、まず私が思い浮かべたのは——押井守がらみではありますが——『帰ってきたウルトラマン マットアロー1号発進命令』(庵野秀明)でした。この作品は、大阪芸大主体の「DAICON FILM」制作で、当時の主要メンバーであった庵野秀明(当時2回生)が監督とウルトラマン役を務め、評論家の岡田斗司夫が脚本を努めた、野心に満ちた8mmフィルムです。果たしてこれが「おバカ系」かは分かりませんが、「ウルトラマンをパロディする」といった内容自体はどこか青々しく、学生的ではあります。(他にもDAICON FILMは、作中にドラえもんやダースベイダーを登場させるなど、大々的に版権を無視した若々しい作品を作っています。)
今の東学祭は、「撮影時に学生であること」を学生映画の定義としているので、タイミングがタイミングなら、この『帰ってきた……』は紛れもなく東学祭の応募対象に成り得た学生映画です。第27回のTIFFで、「庵野秀明の世界」という特集上映が行われたのは記憶に新しいですが、庵野秀明の初期作はほとんど8mmフィルムで制作されていて、特撮それ自体の魅力のみならず、自主で特撮を試みようとする初期衝動のようなものには感銘を受けます。近々には、『シン・ウルトラマン』『シン・仮面ライダー』が公開されるみたいですし、果たして現代の庵野秀明が、どのように特撮という表現形態を捉え直し、社会にメッセージを発するかは、個人的に楽しみとするところです。
『帰ってきた……』は、日本SF大会で大評判を呼びましたが、当時は今よりも「自分が好きなら、なんでもあり!」的な二次創作の類が称賛されやすい土壌があったのだと思います。そもそも、それが自主映画である以上、自分の好きなように撮るに越したことはありませんが、同じように東学祭にも、上映作品や会場、審査員に至るまで、時には業界の不文律をも無視した恣意的な運営が可能になってきます。もっとも、恣意的だからといってエゴイスティックに開き直るのはナンセンスで、委員は自分たちが無知な学生であることを自覚し、「うまい」映画よりも「おもしろい」映画を、制作者と同じ目線で謙虚に語らう姿勢が必要なのだと思います。その上で、これぞという自分たちのパッションを大事にし、若々しい感性を世に問うてゆく姿勢を大事にしなければならないのだと思います。
ちなみに、「自分が好きなら、なんでもあり!」の自主上映は、ジプシー上映などとも呼ばれるそうですが、利益が見込まれる一般的な商業映画、ないし既に多くの劇場でかかっている映画とは異なり、その地域に未出な、とりわけメンバーが本当に世に問いかけたいと考えるマイナー映画を、赤字前提で上映することに意義があるといえます。70年代にジプシー上映を繰り返した名古屋シネマテークは、1986年から毎年恒例の「自主製作映画フェスティバル」を開催するようになりますが、中でも好評だった「何でも持ってこい!」企画は、「自分が好きなら、なんでもあり!」と全く同じ、時代的なノリを感じさせる内容でした。
当時は、名古屋シネマテークや東学祭以外にも、似たようなジプシー上映のイベントが無数に存在していたようです。中でも、東学祭は一貫して「学生映画の祭典」であることを強調し、むしろそれ以外にアイデンティティのない、世界的に見ても稀な老舗映画祭になっていったのです。
【拙記事紹介】
「自主製作映画フェスティバル」については、以下の拙記事でも詳しく取り上げています。名古屋は、東京に次ぐニホンの”第二映画都市”なのではないかと考えた私が、その根拠を、様々な資料を用いて展開した記事になっています。
第5回(1992)-第12回(2000)
コンペティションの導入

会場:スタジオams(三軒茶屋)
<ゲスト>
今関あきよし、山川直人、崔洋一
第5回は、いよいよコンペティション形式を導入します。
部門は、「コンペティション部門」の1つのみで、優れた作品にグランプリが与えられました。その頃になると東学祭は、22大学39サークルもの参加団体に恵まれ、105本もの作品が集まる規模にまで膨れ上がっていました。開催期間も3日に短縮し、上映作品を10本程度に絞り込んだ上で、ゲスト審査員という名目で今関あきよし、山川直人、崔洋一監督らが招待されました。
ちなみに、国際映画製作者連盟(FIAPF)が公認する映画祭のほとんどがコンペティション形式を導入しています。例えば、カンヌ国際映画祭であればパルムドール、ヴェネチア国際映画祭であれば金熊賞、といった具合に、各作品に箔を付けてプロモートするのが映画祭の定石です。
ただOBによると、こと自主映画祭においては、別の利点も挙げられるそうです。例えばそれは、学生のモチベーションが維持される、といった利点や、ゲストを招待する口実が得られる、といった利点です。コンペティションの副賞として、賞金や映画招待券を設ければ、学生のモチベーション維持に繋がりますし、それを目的とした学生の応募作の増加も見込まれます。また、コンペティション形式にすると、上映作の審査という段階が必然的に生まれ、ゲストを招待する口実にもなります。

会場:スタジオams(三軒茶屋)
出身:中村義洋
<ゲスト>
今関あきよし、矢口史靖、崔洋一
そこから東学祭は、第5回、第6回、第7回…とコンペティションを継続していきますが、その頃の部門や規約、賞に歴史的な一貫性はなく、資料も不足しています。
私は映画祭一般の事柄についてあまり詳しくないので、再度OBの意見を援用させていただくと、過去の東学祭は部門や規約を決める上で、例えば短編部門の一般的なレギュレーションである「30分未満」と「30分以上」で分けなくても良いのか、アニメーション作品を同一基準で審査しても良いのか、といった点が大きな争点となっていたそうです。また、学生でも60分以上の映画を監督してしまうと、海外では長編デビュー作としてカウントされてしまい、知らぬ間に国際映画祭、例えば新人に手厚いことで知られているロッテルダムや佂山映画祭へのエントリー権を失いかねない、といった別の側面もあるそうです。ちなみに、学生映画の長編デビュー目標としては、ロッテルダム、サンセバスチャン、テッサロニキといった映画祭が新人監督の発掘に長けているそうで、国際デビューを果たした後はカンヌ批評家週間部門、ヴェネチア映画祭オリゾンティ部門などに選出、最終的には三大映画祭のメインコンペで晴れ晴れ入賞、といったステップアップを希望する映画監督が多いのだそうです。
現在の映画学校では、3年次の実習で15分程度の作品、4年次の卒業制作で40〜60分程度の作品を製作することが多くなっています。ただ、8mmフィルムでは長尺の作品を撮ることは難しいですし、21世紀(特に東京芸大でアニメーション専攻が設置された2008年)以前は、アニメーション作品が決して多いわけではありませんでした。時代を追うごとに、学生映画の製作状況は刻一刻と変わり、それに伴って東学祭も、部門や規約、時期、ゲストといった各セクションを変えていかなければなりませんでした。その点、東学祭はインカレという特性を生かし、定期的にアンケートを取るなどして他大学との情報共有を欠かさず、映画祭をその時代に最適な形へブラッシュアップさせていくことができました。
ちなみに、過去の部門には「コンペティション部門」「長編部門」「短編部門」「アニメーション部門」、各賞には「グランプリ」「準グランプリ」「審査員特別賞」「主演男優賞」「主演女優賞」「監督賞」「名脇役賞」「(企業・団体名)賞」といったものが存在していました。恐らく、各部門・賞は、全く委員の一存で決定されていたものではなく、その時の企業・団体の関係者やOB・OGの意向が、一定数は反映されていたのだと推測されます。

会場:スタジオams(三軒茶屋)
出身:井土紀州・吉岡文平
<ゲスト>
今関あきよし、山川直人、山本政志
吉原健一、利重剛、ケラリーノ・サンドロヴィッチ
第7回の東学祭は、30大学45サークルもの参加団体が集まりました。しかし、応募作全てを上映することは叶わないので、少なくとも一定以上のクオリティを備えた10〜15本程度の作品に絞り込む必要がありました。
そこで始まったのが、当日の上映に先駆けて行われる予備審査です。

予備審査は、長期休業中の大学で行われることが大抵でした。
第7回は1995年1月31~2月5日の18日間に渡って行われ、市川崑、岩崎三郎、熊沢尚人、千明茂雄、矢口静雄といった監督らの在宅審査員といった枠がありました。詳細は明らかではありませんが、恐らくフィルムをVHSやDVDに変換したテレシネを配ったのだと思います。もしくは、自宅に8mmフィルム映写機があるプロの監督は在宅で審査し、映写機がないほとんどの学生は大学で審査に参加する、といった形式だったのかもしれません。
その後も、東学祭は一定数以上の応募作品に恵まれ、予備審査の仕組み自体は、今なお時期や会場、形式を変えながら継続しています。30年近く前の予備審査の詳細は残っていませんが、現在の東学祭では、多くの映画祭と同様に「1次セレクション」「2次セレクション」といった区分けを採用し、メンバーと人数を入れ替えながら予備審査を行っています。審査会の形態は、その時々の映像規格に依存する側面が大きく、これまで東学祭は時代を経るごとに8mmフィルムからVHS、DVD、Blu-rayといった家庭用の映像規格で作品を募るようになりましたが、私が代表を務めた第32回では完全なオンラインスクリーナー化を進め、リモート審査が主になりました。ディスクでの応募が主だった第28回までは、対面形式の審査会が必須で、OB・OGや出身学生監督らの意見を募る場、交流を促進する場としての機能も果たしていました。
映画100歳と才能
発展途上だった東学祭も、いよいよコンペティションを導入し、映画祭として着実に歩み続けていました。
そんななか第7回、山田洋次から以下のようなコメントを寄せられます。

「いいかい、映画監督は教養じゃないだよ、才能なんだよ」
ぼくがまだ新米の助監督だった頃、当時映画界きっての知性派といわれた
大庭秀雄監督に言われた言葉が、いまだに耳にやきついく(*ママ)ように残っている。
才能というのは自分では発見できな(*ママ)ものである。また、かなり頭のいい、
教養豊かな人でも、自分に才能があると錯覚しているケースが、別ないい方を
すれば、自分に才能がない事に気付かないケースが、実に沢山あるものだ。
才能は、他人によって見出され、他人に教えてやって始めて自覚できるもの
なのだ。
そこに、映画祭のような催しの、コンペティションの意義がある。
ましてや今日ほど、若い才能が真剣に求められている時はない。日本映画の
運命は、映画を目指す若者たちの中に、新しい才能を発見できるかどうかに
かかっている。
学生映画祭の、実り豊かな成功を、祈ってやまない。 なぜ、ここまで安直な誤字が散見されるのかは分かりませんが、上記のコメントにもある通り、山田洋次は執拗に才能、才能と声を上げていることがわかります(ちなみにコメントに登場する大庭秀雄は『君の名は』で有名な映画監督です)。
その当時、山田洋次は『男はつらいよ 寅次郎紅の花』(シリーズ48作)の撮影期間で、ロケ中に阪神淡路大震災を経験しています。それに加え、寅さん役の渥美清の癌が進行していて、「もしかしたらシリーズ最後になるかもしれない」という思いも残しています。つまりこの時期の山田洋次は、今後の進退について強く思い及ばせ、身を焦がしていたのです。

私は特に、山田洋次の「ましてや今日ほど、若い才能が真剣に求められている時はない」という発言に着目しました。とりわけ映画業界において、1995年頃に今日ほどと断言できる時代的な危機感は、一体どこから芽生えてくるのでしょうか?
それは、恐らく第一に1995年という、映画史にとっては節目の年に見出せるのではないでしょうか。映画史では基本的な事柄ですが、1995年は一般的に「映画の誕生」とされる、シネマトグラフの上映(1895年)から、ちょうど100年が経った年です。ちなみに別の側面では、黄金期ハリウッドを支えたスタジオシステムが崩壊したと一般的に言われる頃から、約50年経った年でもあります。
当時、世界中で「映画誕生100周年」ムードが漂っていて、至る所でシンポジウムが開催されました。ただ、その盛り上がりとは裏腹に、前年の1994年は「ハリウッド映画史上最も不作だった年」とまで呼ばれた有様で、映画界は才能不足に嘆いていました。それに加え、黒澤明、キューブリック、フェリーニといったレジェンドたちも象徴的に他界し、特に日本では淀川長治、渥美清、木下恵介といった精神的支柱も失いました。19世紀末に彗星の如く誕生し、瞬く間に20世紀を代表する一大娯楽メディアとして拡散したはずだった映画も、戦後民主主義の中心であるテレビに取って代わられ、ネットメディアが台頭し始めた100年目頃には、既にその革新性は失われ、錆の浮いたレトロなメディアとして目に映るようになっていたのです。
だからこそ日本の映画業界にとって90年代は——東京が世界でも有数な映画都市であるなら尚更——山田洋次が強調したように、既存の映画業界を塗り替える圧倒的な才能を渇望していたディケイドである、と一義的には解釈できると思います。ハリウッドでは、ミラマックスのハーヴェイ・ワインスタインの存在は既に触れた通りで、タランティーノ、リンチ、フィンチャー、ガス・ヴァン・サント、ソダーバーグ、コーエン兄弟といった、ある種の禍々しさを伴った監督が目覚ましい活躍を遂げ、日本でも立教ヌーベルバーグの面々に加え、北野武、諏訪敦彦、岩井俊二、庵野秀明、河瀨直美といった新しいタイプの監督が次々に頭角を現したのが90年代でした。彼らの影響圏は未だに——もはや映画の枠すらも超えて——凄まじいものがありますが、そのような反伝統的ともいえる新人監督の登場は、むしろバブル経済の崩壊以降、彼らがメジャースタジオで雇用を得る機会に恵まれなかった、時代的な閉塞感の裏返しともいえるかもしれません。
私も詳しく知りませんでしたが、同じ才能発掘という文脈で、国際学生映画祭('91〜93)なるコンペティションが日本でも誕生していました。朝日新聞(1991年5月9日夕刊)によると、国際学生映画祭は「資金や発表の場に恵まれず、映像表現の才能を発揮できないでいる若者のギャップを埋める試み」であり、欧米からアジア、アフリカも含む約40カ国、200の大学、専門学校から作品が集められました。次期の映画祭招待作品の製作費に充てられる賞金は、なんとグランプリで2500万円、ドラマ、アニメーション、ドキュメンタリーの各部門賞で500万円といった破格の金額で、バブル崩壊の始まりを感じさせない景気の良さでした。審査員の1人だった佐藤忠男も「学生の映画も水準は低くない。全世界的に募れば、傑作が集まるだろう。特にアジアでは、賞金が貴重な製作費となって貢献すると思う」と期待を寄せていました。
ただ結果的に、国際学生映画祭はたった3回で終わりを迎えてしまいます。当時、国際学生映画祭で通訳をしていた関山さんは、以下のような辛辣な考察を朝日新聞(1991年11月28日 朝刊)に寄せています。日本の映画業界の才能をめぐる、特に学生の問題意識が、歯に衣着せぬ語気で提示されています。
なぜ振るわぬ日本学生映画(声)
東京でこのほど開かれた第1回国際学生映画祭に通訳としてお手伝いした。世界の若い映像作家
からの応募作品が二百数十点、そのうち30点を選んで審査し、4点に賞金が贈られた。
日本の作品は応募数の1割を占めていたのに、1点も審査の対象にさえならなかった。これには審
査委員長である英国の映画プロデューサー、ブラボーン卿も首をかしげていた。経済大国日本、過
去には輝かしい名作の数々が海外にとどろいているのに。
主催者側の説明では、日本の応募作品がお話にならぬほどレベルが低かったという。国の補助が
ないからだというが、それなら英国でも事情は同じだと、同卿は反論した。欧米では学生の作品に
有名スターが友情出演するのが習わしだが、日本ではそれもない。
受賞者たちの話を聞いて、原因はもっと深いところにあると思った。彼らは一様に独創的な発想
力を持っている。そして明確な問題意識、討論でねり上げたテーマを映像で表現しようとする執念
のようなものを持っていた。
日本の学生たちは、平和で安易な生活になれ切ってしまって、問題意識を持つことができないの
ではないか。たとえ持っても、ヤボなこととして退けてしまう風潮があるのではないか。テレビ番
組や、電車の中で交わされる学生たちの会話はそれを物語っている。
(1991年11月28日 朝日新聞 朝刊) 確かに、関山さんの「テレビ番組や、電車の中で交わされる学生たちの会話はそれを物語っている」といった一方通行な主張は、「今の若者は……」といった——およそパピルスにも記されていたらしい——齢を経た物言いであることは間違いありません。ただ、数1000万、数100万単位の賞金がほとんど海外の学生に与えられ、「映像表現の才能を発揮できないでいる」若者を支援する骨子ができないまま、ドメスティックな才能を育てあげることができなかった事実には大きなインパクトがあります。
そもそも、PFFなどの自主映画のコンペティションは、「まずスタジオの門を叩き、アシスタントや助監督などの下積みを経てから、その中でも一部の優秀な者だけが監督に上りつめることができる」といった旧来のキャリアパスへの、アンチテーゼ的な側面も大きかったと思います。特にこの頃は、OV(オリジナルビデオ)と呼ばれる、予めレンタルビデオ用に量産される低予算映画が登場し、BS(衛星放送)が市場拡大を始めた頃で、例えば青山真治はじめ多くのメジャースタジオに入れなかった新人監督が、立教ヌーベルヴァーグの系譜ともまた異なる新しい環境下でキャリアをスタートさせています。
フランス・ヌーベルヴァーグの面々とリアルタイムで交流を重ねた山田宏一は、この時代に新たに普及したDVDの視聴環境を、映画起源を巡ってシネマトグラフ(リュミエール)と対極をなすキネトスコープに準え、エジソン的回帰と呼びました。21世紀が間近に迫り、映画そのものの定義が曖昧になりつつあった時代だからこそ、いかにして旧来の方法論を踏襲せず、新しい才気を発揮することができるのか、といった尺度は、頻繁に持ち出されたのかもしれません。
映画祭の意義とは?
これまで東学祭は、都内の学生映画を集め、それを一挙に紹介する、という活動を一環して行ってきました。
ただ、「自分が好きなら、なんでもあり!」といった言葉に象徴されるように、あくまで東学祭は、自主上映会という形式を借りた学園祭的なイベントに留まっていました。山田洋次も「才能は、他人によって見出され、他人に教えてやって始めて自覚できるもの」と述べていますが、他人の中でも、同レベルの学生が互いの才能を規定し、世にその真意を問おうとする姿勢には、極めて自己完結的な側面があります。実際、いくら適正なコンペティションを心掛けようと、優秀なゲスト審査員を招待したところで、才能が眠っているかもしれない100本程度の作品は、大学生による恣意的な予備審査によって、無慈悲にも振るい落とされているのが現状でした。もっとも、多かれ少なかれ、映画祭の魅力はその恣意的な変化にこそ潜んでいるという意見もありますし、あまり権威性に縛られ過ぎず、一つのアート・イベントとして自立性を重んじても良いのではないか、とも個人的には考えます。
ただここでは一旦、整理するために、改めて東学祭の意義を確認してみたいと思います。これまでの東学祭が達成目標としてきたことは、ごく簡単に図式化してしまうと、以下の2点に整理されるのでしょう。
学生映画の「紹介」
学生監督の「交流」
「紹介」「交流」の表現が的を射ているかは分かりませんが、この2点に東学祭の基本的な役割が存在していると、とりあえず私は解釈しています。
東学祭は、キャリアの浅い学生映画が公に晒され、トークショーで合評するある意味で実験的な「紹介」の場であり、上映機会や懇親会(レセプション)を通じて、学生や審査員、関係者、観客との間に図られる「交流」の場でもあります。第5回以降の東学祭は、会期が2〜3日と短く、十分な「紹介」「交流」の機会を設けることができているかは分かりませんし、映画祭を盛り上げようとすると、どうしてもトークショーや監督個人の発信が偏重になってしまい、映画それ自体のテキスト論的な魅力より、ファン・イベントとしての側面が強まってしまいます。逆に言えば、学生が何かしら学びを得、自身の仕事やクリエイティビティに繋げることができるかもしれない娯楽的な好機を提供することぐらいしか東学祭にできることはない、と開き直ることもできるかと思います。
ただ、いずれにせよ、そういった「紹介」も「交流」も、学生によるサークル活動という能動性のみに依存して成立しているのでは、あまりにも不健全でした。水物である映画は、一朝一夕で作れない苦労と、いつ運転資金が底を尽きるか分からないリスクに塗れているからこそ、安定的に守られるべきであり、そのために東学祭も、何か社会的に意義のある活動ができるのではないか———そう背伸びした発想をしてしまうのも、無理はなかったと思います。
そこで東学祭が取り入れたのが「育成」という観点でした。「紹介」でも「交流」でも不十分で、その先に「育成」する実利的な枠組みを設けることができれば、確かに本来的な意味で学生映画の未来に資することができます。実際に活躍した映画監督が、東学祭によって見出され、さらに東学祭によって育て上げられたという事実には、映画全体の利益と切っても切り離せない、社会的意義があります。
次の章からは、21世紀を迎えた東学祭がいかに立派な映画祭たろうともがき、様々な挑戦を試みては、その都度大きな挫折を余儀なくされたか、その不遇の歴史について掘り下げていきます。
* 第8〜12回の資料は、開催時期やゲスト含め、どういうわけか全く見当たりませんでした。
第13回(2001)-第16回(2004)

会場:新宿文化センター
出身:小泉徳宏
<ゲスト>
売野雅勇 三池崇史
*当日は会場でラジオドラマも披露された。
ミニシアター凋落、映画学校乱立
21世紀を迎えた第13回(2001)は、これまで使用していた三軒茶屋のスタジオamsではなく、新宿文化センター(小ホール)で開催されました。

やはり、ともいうべきか、東学祭のクレジットに「セゾンカード」の協賛は無くなっていました。セゾングループはバブル崩壊から世紀末にかけて力を失っていき、2001年には事実上の解散を迎えます。1996年にスタジオamsは閉館してしまいますが、東学祭が何らかの事情でスタジオamsが使用できなくなったのも、セゾン崩壊と無関係ではないでしょう。
通常、映画館の席数では収まらない規模の映画祭は、スタジオやミニシアターではなく、巨大なホール(近年はシネコン)を使用して開催されます。ちなみに、東京国際ファンタスティック映画祭は、東急文化会館にある渋谷パンテオンで開催されましたが、そこは定員1119人(!)のモンスター級のホールでした。東学祭は規模も小さく、スタジオamsやミニシアターのキャパで相応でしたが、新宿文化センターへ場所を移しました。
この事実の背後から読み取れるのは、ミニシアター文化の衰退です。世紀末には、池袋文芸坐(〜'97)、銀座並木座(〜'98)に、大井武蔵野館(〜'99)、亀有名画座(〜'99)などの名画座が次々に閉館し、ミニシアターブームを担った渋谷も21世紀以降、ヒューマントラストシネマ文化村通り(〜'09)、シネセゾン渋谷(〜'09)、シネフロント(〜'10)、渋谷シアターTSUTAYA(〜'11)、シネセゾン(〜'11)などが立て続けに閉館しました。その潮流は、近年のコロナ禍と配信(SVOD)によって拍車が掛かった形で、UPLINK渋谷(〜'21)や岩波ホール(〜'22)まで連綿と続いているといえるでしょう。
そこで渋谷のミニシアター文化に取って替わったのが、新宿のシネコン文化だったのです。新宿バルト9('03〜)、新宿ピカデリー('08〜)、TOHOシネマズ新宿('15〜)といったシネコンが勢いを増すにつれて、新宿全体の映画興行は年率10%で拡大しました(逆に渋谷は10%の縮小)。2021年現在、全国のスクリーン数はシネコンが8割以上を占めていて、特に地方では生活を支える巨大ショッピングモールと併設される形で浸透し、もはやミニシアターに行ったことがない若者が大半を占めています。
シネコン文化が台頭した理由として挙げられるのが、映画インフラ全体のデジタル化です。その頃、DVDは「史上最も早く普及した記録媒体」として一般家庭にまで普及し、撮影、編集、映写に至るまでデジタルで行うデジタルシネマが主流となりつつありました。シネコンは逸早くデジタルシネマを取り入れ、フィルムの焼き増し(プリント)費、修繕費、配達費、映写費といった物的コストを統一的に削減しました。それに加え、大手映画会社と紐づいたVPF(Virtual Plint Fee)という配給制度を駆使し、優先的に映画を買い付けることができました。その結果、市場に出回るほとんどの映画を大手映画会社が管理し、その傘下にあるシネコンが圧倒的なシェアを誇る、今日的な映画文化が根付いたのです。(デジタルシネマとシネコンの関係については、後ほども触れます)。
結果的に映画のデジタル化は、学生映画を劇的に(あるいはいたずらに)増加させる要因となりました。扱いが難しく、値段も高い映画用フィルムを使っていた学生が、一眼レフやビデオカメラ(近年であればスマホ)などで撮影した映画を、安価なパソコンとソフトウェアで編集し、それをminiDVなどの平易な規格で量産することが可能になったからです。初期投資もほとんど無く、撮影に掛かるや予算も数万円〜とコンパクトになり、長尺作品を撮影するのも容易となりました。年々増加した学生映画の数は、恐らく現在も短編・長編含めて年間1000本にも上ると推測されます。
もっとも、映画の増加自体は世界的な潮流で、デジタル化以後はアフリカやアジア含む様々な国・地域で映画が製作されるようになりました。一般に公開される商業映画だけで年間数千本、自主映画まで含めるとその数は計り知れません。それは映画配給のグローバル化を意味し、映画祭への応募も簡易的になったので、日本含めアジア諸国のインディーズが映画が、毎年のように主要な海外映画祭に正式出品されるケースが増えてきました。
また、映画に掛かる予算規模が縮小するということは、必然的に映画教育に掛かる予算も縮小することを意味しました。結果的に映画学校は、武蔵美映像学科('90〜)、UTB映像アカデミー(`95〜)映画美学校('97〜)、ニューシネマワークショップ('98〜)、東京芸大院映像研究科('05〜)、ENBUゼミナール('09〜)といった具合で、もはや乱立の様相を呈しています。映画学校は、北野武、黒沢清、諏訪敦彦、青山真治、塩田昭彦、篠崎誠、森達也といった一級の映画人を呼び込む形でカリキュラムを充実させ、あっという間にインディーズ映画界を席巻しました。ゼロ年代以降のインディーズシーンを彩った映画監督のほとんどは映画学校の出身で、一般大学との温度差は、ますます顕著になっている印象です。特に今、日本で最もヒーロー視されている濱口竜介はその最たる事例で、彼は2005年に設立された東京芸大院映像研究科の2期生でした。修了制作で撮られた『PASSION』は学生映画でありながら、既に現在の活躍を予見させる確固たる作家性、クオリティがあったと思います。
(*2022年3月28日追記 『ドライブ・マイ・カー』は、既にカンヌ映画祭やゴールデン・グローブ賞で国際的な地位を確立していましたが、日本国内の風向きは明らかにアカデミー賞の受賞を機に変わりました。それ位、日本におけるアカデミー賞の立ち位置が大きいことを再認識しましたし、濱口竜介や『ハッピー・アワー』の名が新聞の社説に載る日が来るとは、夢にも思っていませんでした。一部で出た「『ドライブ・マイ・カー』を大手映画会社が製作・配給していなかった現実は、邦画の暗い現状を露呈させている」といった意見は、産業全体で見れば正しいものの、濱口竜介に関して言えばその限りではないと思います。何故なら、初期濱口の『PASSION』『親密さ』『ハッピー・アワー』などの傑作から、『ドライブ・マイ・カー』に確実に引き継がれている彼の作家性は、明らかに日本の映画学校やインディーズの風土が生み出した固有のものであり、そこでしか醸成され得なかったものだからです。ちなみに私は、活動を通じて「濱口竜介に次ぐ才能を東学祭から輩出したい」などと意気込んでいた時期もありました。)
ものの10年で進んだ未曾有のシネコン化とデジタル化は、学生映画を巡る状況を劇的に、決定的に変えてしまいました。特に映画学校の乱立は、委員の大半が一般大の学生で成り立っていた東学祭にとって、自らのアイデンティティを失いかねないクリティカルな問題にもなり得ました。
映画学校があるなら、東学祭はいらないのではないか?
東学祭が、こういった自己言及に陥ってしまうのも無理はなかったと思います。才能を「育成」するという観点において、映画教育に勝るものはありませんし、果たして東学祭が見せていた一過的な盛り上がりが、山田洋次のいう才能を「育成」することに一役買っていたかは、大いに疑問でした。むしろ私なんかは、自分たちの意義を声高に吹聴するよりも、前章で記したような学園祭の機運を、自己目的として開き直ってしまうくらいの方が潔いのではないか、くらいに思えます。
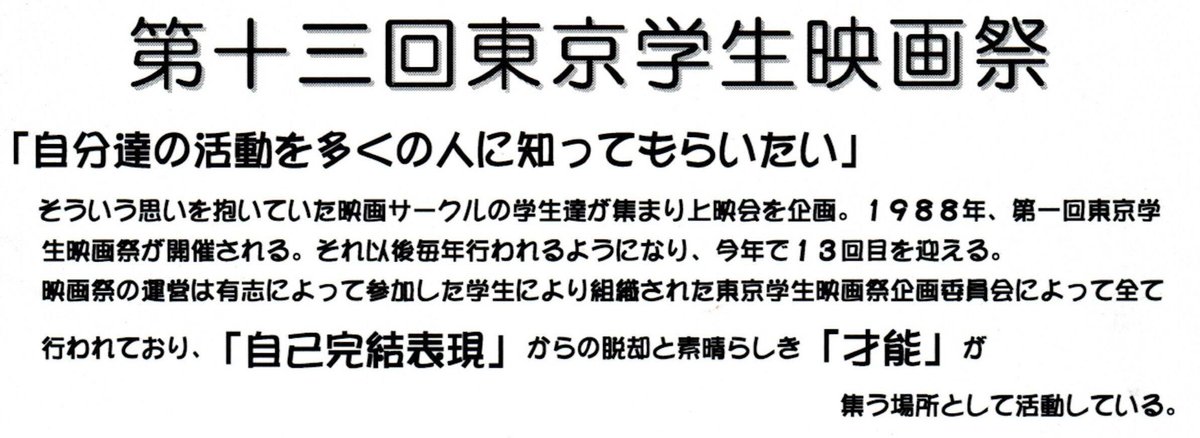
しかし21世紀の東学祭は、才能を「育成」する立派な映画祭としての展望を捨てることはありませんでした。むしろ、「自己完結表現」からの脱却を目指し、様々な活動を展開していきました。
当時の「開催概要」を紐解いてみると、第13回は<今後の展開>として、大きく3つ事業目標を立てていることがわかります。
《今後の展開 ① 映画祭》
今後の映画祭としては、参加団体(海外含む)の増加、作品数の増加、企画内容の充実、
作品数の増加、企画内容の充実、イベント規模の拡大、アジア各地をはじめとする海外応
募者の招聘、日本の学生との交流、作品や製作者の将来に焦点をあてる方向で推進してい
こうと考えています。
また上映作品は国内にとどまらず、広く海外の作品も上映できる体制を整える事を考え
ております。
《今後の展開 ② 映画製作》
学生の製作する映画のクオリティー向上の為、サポート体制を整えます。映画製作に対
する考え方や製作過程等を学ぶ環境の提供、現役の製作スタッフによる実技指導等を考え
ています。
《今後の展開 ③ 支援目的》
彼等の活動を支援する目的としては、映画制作をとおして、社会への意識を育て、学生
間の異文化理解を促進し、技術を学ぶ環境を与えること、そこから新しい才能が生まれる
可能性を追求します。そして、映像を表現媒体とする方向性への意識の改革を求め、やが
て社会との接点となる場所の創造を考えます。
(第13回開催概要)①〜③の事業目標それぞれにおいて、学生映画の「紹介」と「交流」の役割を補完する作用が見込まれます。ただここでは何より、東学祭が才能を「育成」することに比重を置くようになった、幾つかの重要なアジェンダを読み解くことができる点に着目するべきでしょう。そのアジェンダとは、私なりの表現で、以下の3つに分類できると思います。
① 国際交流
② 製作支援(スカラシップ)
③ マスタークラス
①〜③のいずれも<今後の展開 ①〜③>に呼応した形で、一部私が相応しいと判断した専門用語へ便宜的に置き換えています。厳密に言えば誤った用法かもしれませんが、説明しやすいように当て嵌めただけなので、その点はご容赦いただきたいと思います。
まず、①国際交流については、《今後の展開 ① 映画祭》で言及されていた通りで、その頃から徐々に存在感を強めていた、とりわけ近隣のアジア諸国との交流機会を作り、学生のグローバルな視点を養うことは、喫緊の課題でした。またPFFのように、入選した作品の海外進出を支援する(例えば海外セールスへ持ち込み、ディレクターを介して海外配給を目指す)枠組みも必要でした。恐らくこういった問題意識の背景には、1997年に設立された京都国際学生映画祭(初回ゲストは北野武!)の存在があるのではないかと、勝手に私は想像しています。
次に、②製作支援(スカラシップ)について、そもそもスカラシップとは、ある特定の技能(ここでは映画製作のノウハウ)を習得したい有志に与えられる、奨学支援の枠組みのことです。撮影や脚本執筆の期間へ充てられる援助や、省庁や財団などの助成金へのマッチングサービスもこれに該当します。これは明らかに、1984年かPFFが先駆けて実施し、園子温、橋口亮輔、矢口史靖といった監督を育て上げた「16ミリ映画制作援助企画(現・PFFスカラシップ)」を踏襲しています。複数の映画会社が共同でVIPO(映像産業振興機構)を設立し、2006年には若手映画作家育成プロジェクト(ndjc)を開始したのも、似たような動機があったのだと推測されます。
最後に、③マスタークラスについて、マスタークラスとは特定分野(とりわけ職業的訓練)を専攻したい者向けに開講される、専任クラスのことです。マスタークラスは、ほとんどの主要な映画祭で実施されていて、入賞者や関係者だけでクローズドに開講される、実用的な知見を共有するネットワークとして機能しています。もっとも、スカラシップとマスタークラスは相互に補完し合っている側面があり、厳密に区別する必要はありません。
ここで注目するべきなのは、①国際交流も、②製作支援(スカラシップ)も、③マスタークラスも、映画学校ではカバーできていない領域の試みであったという点です。
映画学校に在籍していたOBによると、今も昔も映画学校では「何が良い映画か」「どうすれば良い作品が作れるか」といった理論系のことを学ぶことは可能ですが、それ以外の——2017年に廃校したUTB映像アカデミーは「映画監督というフリーターにさせない学校」「4年連続就職率100%!!」を謳い文句に広告を出していましたが——例えば海外の映画祭文化やお金の集め方、保険の入り方、広報のやり方といった実用的な知見を教えられる機会は少ないそうです。①国際交流、②製作支援(スカラシップ)、③マスタークラスといった事業は、まさにそれらを補うための枠組みであり、東学祭が映画学校との差別化を図り、才能を「育成」する場所を目指す上で重要なスキームでした。
一見すると①〜③は、いかにも立派で、社会的意義があるようにも思えます。ただ、果たして当時の東学祭のポテンシャルで、そこまで大それた事業を実現することは可能だったのでしょうか?
ここで必要となってくるのは、海外の学生映画事情やスカラシップの財源、プラクティカルなマスタークラスの仕組み、といった高度の知見のみならず、それを果たそうと思える強いモチベーションでした。その点、何度も指摘しているように、東学祭に在籍していたのは映画祭や映画学校に所属している訳でもない、ましてや映画を作ったこともない、無責任な18〜21歳の学生ばかりでした。そもそも自分たちの経験やモチベーションですら足りていない学生が、どうしてをそれを「育成」する側に回れたでしょうか?
それに加え当時、東学祭は深刻な委員不足にも悩まされていたそうです。東学祭は、原則として3年で引退するサークルでしかないので、良好な組織運営と、下の代への適切な引き継ぎが必要になってきます。それは、必ずしも東学祭に限った話ではないと思いますが、少しでも上の代が日和見し、無責任なポジションを取ってしまえば、あっという間にサークルは空中分解してしまいます。そのため、東学祭が才能の「育成」を実現するためには、いつ計画が頓挫するかも分からない無責任なサークル体制から脱却し、安定的な組織運営を志さなければなりませんでした。

NPO法人を目指して
東学祭は第12回を迎えた時に存続の危機を迎え、これからの運営やあり方を見直す
機会を得ました。そして続く第13回より「映画製作を目指す若い創り手の発掘・育成
を支援し、同時に映画に関わる人たちの交流と理解を促進する」という理念を確立。
—中略—
学生映画の発展を目指し活動しており、来年度からNPO化を予定しております。それ
に伴い、活動の駅も東京近郊の大学生のみならず、海外や高校生にも広げています。映
画祭をゴールとするのではなく、より良い製作のきっかけとしてもらうために、優秀者
には製作支援を行っております。
(第13回パンフレット) こうして東学祭は、2001年に運営母体を「東京学生映画祭企画委員会」と正式に命名し、NPO法人を目指す運びとなりました。それに加え、企業の社員数名とフリーランスが名乗りを上げ、全面的なバックアップ体制が設けられました。
東学祭はサークルという体制から脱却し、決して無責任な学生に依存しない、安定的な運営への一歩を踏み出したのです。週に一回の会議も、これまでの貸し会議室や大学の教室ではなく、渋谷宇多川にあった某協賛企業のワンルームで行われました。月5万で間借りし、そこを事務所として構えるほど本格的な腰の入れようでした。
NPO法人を目指した背景には、予算の都合もありましたが、何よりも毎年メンバーが入れ替わり、その都度方針も変わってしまう行き当たりばったりな組織課題を解決するのが第一だったでしょう。例えばPFFであれば荒木啓子、TIFFであれば市山尚三といったディレクター職が全体を統括をするのと同様に、——建前として学生幹事の名義が変わろうと——特定のNPO職員がオーガナイザーを引き受けるようにして、映画祭の一環した方針を貫こうと考えたのです。
細々とした内容になるので再び区切りますが、当時の資料によると東学祭がNPO法人として実現しようと提示していたアジェンダは、以下の2つになります。
・新しい学生エンターテイメントの追求
・学生映画市場の開拓
新しい学生エンターテイメントというのは、当時は黎明期だった配信企画や専門サイトの運営など、21世紀型の新しい学生向けイベントを仮称したものだと思われます。他方で学生映画市場は、まだ学生映画において開拓されていない、マスタークラスやスカラシップといった専門領域の市場を指しているのだと思われます。
ちなみに、上記のような文言に、あたかも学生映画にビジネスチャンスがあるかのようなニュアンスを感じ取れなくもありませんが、今も昔も少なくとも「商売」という文脈に乗せてみた時に、学生映画はどう希望的に捉えても斜陽であることは疑う余地がありません。
「学生映画」=「学生が作った自主映画」で、小説や漫画で定義するところの同人誌のようなものに該当されます。しかし、大体の同人誌が二次創作的な趣味によって、例えばコミケのような大規模な市場が形成されているのとは異なり、映写機と上映会場を要する自主映画の市場は、基本的に「映画祭」と「自主上映会」の2つが占めています。近年は「配信」の事業も進んできていますが、まだまだ未開拓な領域です。
大前提として、映画産業のボリュームゾーンには、商業/自主に極めて拭い難い市場の格差が存在しています。それでも自主映画の一部がミニシアターの、例えばレイトショー枠の興行が掛かるケースはありますが、こと学生映画は、質的にも量的にも商品価値が低い作品に溢れ返っていて、基本的にサークル内の自主上映や映画学校の一般公開以外、上映機会に恵まれません。そして趣味の一環というより、映画祭のような実力試しの「コンペティション」の文脈、ワークショップのような「教育」の文脈に乗せられるケースがほとんどなので、同人ファンイベントのような規模のビジネスとして拡大することは、原理的にあり得ないのです。
NPO法人を目指し始めた東学祭は、引き続き新しく立派な学生映画祭としての形を模索していきます。特に第13回では、本祭(メインコンペ)とは別に、2つの新しいイベントが立ち上げられていました。
・学生向けセミナー
・サマー・フェスティバル
学生向けセミナーは、おそらく③ マスタークラスの設営から着想を得た企画でしょう。
ただ、残念ながら当時の資料は残っていません。それどころか開催されたかどうかすらも定かではないのですが、事前計画には以下のタイム・スケジュールが記されています。
名 称:東京学生映画祭セミナー(仮)
日 時:2001年7月末・12月末(予定)
場 所:株式会社〇〇本社地下プレゼンルーム(キャパ400人)
内 容:
1. ゲスト講演・シンポジウム
2. スポンサー講演・プレゼンテーション
3. 関係者講演
4. パネルディスカッション
5. 就職セミナー
6. 発表会(参加団体)
7. ネット配信
ねらい:活動を通じて、学生と社会の接点を生み出す。
(第13回「開催概要」) 一体、400人にも及ぶ巨大な会場で、どんなセミナーが行われたのかは想像に及びません。ただ、パネルディスカッションや就職セミナー、参加団体の発表会といった企画を見る限り、必ずしもゲストが一方向に講演するだけではない、インタラクティブな形態だったことが伺えます。
そして、資料の「ねらい」にある通り、そこには「学生と社会の接点を生み出す」という大義名分が存在していて、映画学校にはない実用的な知見を共有する場、具体的な就職を支援する場としてのセミナーを目指していたことも分かります。

サマー・フェスティバルは実際に開催されたので、過去の資料も残っていました。上記は当時のパンフレットですが、どことなく『2001年宇宙の旅』のイメージを喚起させます。
ここでは、サマー・フェスティバルで代表を務めていた方の「ご挨拶」を引用させていただきます。当時の委員が抱えていた、様々な問題意識を垣間見ることができるので、少々長めに引用させていただきます。
ご挨拶
本日は東京学生映画祭SUMMER FESTIVAL2001にご来場頂き誠にありがとうございます。
今年は東京学生映画祭は年2回の上映会を開催することに成りました。今日、行われるSUMMER FESTIVALは、
今年初めての試みになります。このSUMMER FESTIVALは従来の3月の本選とは異なり、テーマを「交流」と題し、
日本の学生以外の作品、CG作品、学生と社会人との共同制作作品の上映、参加団体からの推薦作品を企画委員が
テーマにあった作品を厳選し上映致します。(中略)
SUMMER FESTIVALの開催に至った経緯も、もともと、この学生の皆様に他のジャンルの映像作品などを見て
頂いて様々な刺激を感じてもらい、より素晴らしい作品を作ってもらいたいと考えていたからです。 日本におけ
る、自主映画というものは、将来、映像業界に行く為の手段であったり、趣味であったり様々です。しかし、アメ
リカなどでは、ショートフィルム自体に多大な価値があり、完成度も恐ろしく高いです。われわれ東京学生映画祭
企画委員会といたしましては、もっともっと日本の自主映画、ショートフィルムのクオリティーや価値を上げてい
きたいと考えています。ですから自主映画制作にあたっている皆様方の力になれるように全力を尽くしたいと思い
ます。(以下、省略)
(「SUMMER FESTIVAL 2001」パンフレット)
まず、「日本の学生以外の作品」「アメリカのショートフィルムは完成度も恐ろしく高い」といった記述には、国際水準では劣っている日本の学生映画に、国を跨いだ交流が図られていない現状認識が提示されています。そして、「より素晴らしい作品を作ってもらいたい」「もっと日本の自主映画、ショートフィルムのクオリティーや価値を上げていきたい」といった記述にも、東学祭が才能を「育成」する実利的な場所を目指していた、強い意思を汲み取ることができます。
パンフレットには代表の「ご挨拶」のほかに、委員としての全体コメントも掲載されていました。
現在、日本全国では映画祭と名の冠する上映会は大小合わせて200近くあります。しかし、その映画祭は
本来の目的とはかけ離れ、単に作品を上映する場所としてしか機能していません。 そのため映画祭において
授賞される各賞は名前だけになり、賞自体の重みや次への機会を与えてられる道標としての役割を持たなくな
り、また出品する立場からも賞へのこだわりや意欲が薄れてきたように感じます。
そういった現状を変えるべく、去年11月から東京学生映画祭では、本映画祭において優秀と認めた出品者の
方が次の機会へとつながる支援をコンセプトに外部との活動を行ってきました。そして、小さいながらも一つ
の挑戦が行われました。 “まず一緒に作品を創ろうと……”新しい環境 で行われた作品製作は、作品自体のクオ
リティーや撮影に参加したスタッフのコミュニケーション、製作時間や予算等、これからまだまだ山のように問
題はありますが、こういった活動が定期的に行われ、学生の皆様及び社会の方々に認知され、より多くの人が集
まり協力していければと思います。(以下省略)
(「SUMMER FESTIVAL 2001」パンフレット)ここでも注目すべきなのは、「次への機会を与えられる道標としての役割を持たなくなり—中略—賞へのこだわりや意欲が薄れてきた」といった、学生映画に対する悲観的な現状認識です。
確かに当時、映画祭の名を冠する上映会は200個近くありました。ただ国際映画祭に象徴されるように、そのほとんどが次へと繋がらない一過的なイベントに終わってしまっているのが現状でした。そしてそれは、東学祭も然りで、東学祭が自己目的から脱却し、才能を「育成」する継続的、かつ立派な学生映画祭へ変わらなければならないことは、当時の委員も強く自覚するところだったのです。

上記は、無事に成功した(?)学生向けセミナーやサマー・フェスティバルの経験を基に作成された、第13回の本祭(メインコンペ)イメージ図です。
些か簡略化されすぎている図式ではありますが、第13回はメインコンペ(上映会)を軸に、学生映画を「④独自サイト」や「⑦各メディア」、「⑤著名人」などにプロモートし、追々は「⑥次回作」へと繋ぐ算段だったことが分かります。また、当時はインターネット黎明期だったので、「④独自サイト」にはある種、新しさへのトレンドを感じさせます。同じ資料には「優秀作品はCSやビデオ化、地上波といった他メディアへ繋ぎ、チャンスの場を広げる」といった記載もあり、マルチメディア化への発展性も言及されています。
結果的に、第13回の本祭(メインコンペ)は——上記のイメージ図と重なるかは分かりませんが——後にも先にも繰り返されることのない、さらに4つの特別企画が立ち上がることなります。詳細な話になりますが、ご紹介します。
1つ目が、シナリオ部門の創設です。
当時の広報資料には、「B5 400字詰め原稿用紙50枚」という規定が記されていますが、応募された映画シナリオの優秀作品には各賞が授与され、原作を欲している学生監督へ斡旋されました。真偽の程は定かではありませんが、HPでの公開やラジオドラマ化の副賞もあったそうです。
2つ目が、写真・美術作品合同展示会です。
この展示会は「(映画以外の)あらゆる表現手段が交流する場を増やす」といった趣旨によるもので、会場のエントランスで開催されました。展示には、各大学の写真サークルや美術サークルといった、映画以外の芸術諸ジャンルのサークル複数が参加し、メディアミックスが図られました。
3つ目が、東学祭製作部の発足です。
そこでは主に、かつて東学祭に関わりのあった過去の委員を中心に、大学・サークルの枠を超えた映画製作が行われました。最小(minimum)単位から最大(maximum)の魅力を引き出す、というコンセプトでMiximum(ミキシマム)と名付けられた製作集団には、その年のグランプリ監督小泉徳宏も参加しました。映画祭によって生まれた他大学とのコネクションを活かし、実際の映画制作に役立てる、といったことは東学祭ならではの試みであると同時に、立派な映画祭としての理想でもありました。そして何より、映画を「上映」するだけではなく、その経験を活かして実際に「撮影」したいと考えていた委員の念願でもありました(実際、映画監督の多くは「上映」のセクションに関わりつつ「撮影」を行なっています)。
そして最も特筆すべき4つ目が、学生の座談会です。
東学祭は、以前から著名な映画人から頂いたコメントや、出身監督による座談会の内容を、パンフレットや広報紙に掲載していました。ただ、第13回に行われた、現役の学生監督3人(Y監督、S監督、M監督)による座談会は前例がありませんでした。
座談会といっても、内容の大概が学生らしく取り留めのない、半ば雑談のような代物です。ただ21世紀の学生たちが抱いていた、等身大の感覚が現れているので、以下に長々と引用させていただきます。
Y「やっぱり8mmがなくなってかなり減りましたよね」
S「うーん、卒業する身としては、もう最後まで8mmで、と思って」
Y「ほお」
S「だからYさんはDVにしちゃったよー、って(笑)」
Y「私が1年生の時とかはDV作品とかって本当になかったですよ。ここ何年かですよね」
S「でも画質ってそこまで向上してないような気がする」
Y「してない、してない。多分まだ8mmの方が良い」
M「ちょっと違いますけど、画のレベルが下がってきてません? 画面の撮り方というか」
Y「結構チャーッ、と撮っちゃいますよね」
M「そう、チャーッと」
—中略—
Y「まあ8mmは8mmで、白黒も同録もなくなっちゃってますけどね」
S「Yさんは今回DVですよね。」
Y「いやー、本当は16mmまで行きたかったんですよ。でもお金がなくなったっていうのがあって。
あと、私結構暗めに撮るので—中略—私の好きな画面だと、テレシネするとほとんど見えなくな
ったりするんですよね。それならDVの方がマシかなと思ったんですけど、やっぱ8mmの方がキレ
イですね。」
S「僕は今回、DVで出しますよ」
Y「業者に頼んだの?」
S「いや、自分でやりましたよ。シネプロの8mmが壊れちゃって、音が入れらんない、とかなって。
まあ、それでなんですけど。」 ここで気になるのが、冒頭の「8mmがなくなってから」という発言です。
果たしてその頃(2001年)には、既に8mmフィルムが無くなっていたのでしょうか? ちなみに、DVという言葉はあまり一般的ではありませんが、デジタル制作のビデオ全般を差す「Desital Video」の略で、「DVD(=Digital Versatile Disc)」とは異なります。
その点、8mmフィルムの概要については、第4回が開催された際に朝日新聞(1991年11月03日 朝刊)に掲載された「キャンパスで健在、8ミリ映画 東京学生映画祭に100本近い作品」という記事が参考になったので、それを参照したいと思います。
(ちなみに記事を書くにあたって、主要な新聞社のデータベースは全てさらいましたが、どういう訳か朝日新聞の掲載数が多かったようです。各メディアにどのような特性があるか、どのように東学祭と繋がっていたかは私の与り知るところではありませんが、いずれにしても東学祭内部に残っている情報以外に、参考となるような記事はあまり多くありませんでした。)
大手フィルムメーカーの富士写真フイルムによると、同社製造の8ミリフィルムは、ピーク時の76年に
2500万本だったが、10年後には1割以下の190万本に激減した。8ミリ愛好家で作る同社の「シングル8
友の会」の会員も、1万5000人から2000人に減った。上田裕一事務局長は、「新規入会も少なく、高齢
化が進んでいる」という。
1990年には、日本コダック社が8ミリ映画の高感度フィルムの販売をやめた。国内でのフィルム現像も
中止、愛好家に打撃を与えた。今、国内でフィルムを製造するのは富士フイルムだけ。「富士も製造中止」
のうわさが流れる度に、学生たちは、祈るような気持ちで真偽の確認に走るという。
カメラなどの8ミリ機材は、もう新製品が出ない。個人やサークルが持っている機材を、修理しながら
使うしかないが、修理できる人も場所も次第に少なくなっている。ビデオなら「1分間10円」ですむコス
トが、8ミリ映画では「1分間1000円」といわれる。
(1991年11月03日朝日新聞 朝刊) 記事にもある通り、大手フィルムメーカーの多くは、90年代後半には8mmカメラや映写機の製造を終了しています。ただ、映画フィルムで世界第2位のシェアを誇っていた富士フイルムに限って、2007年3月まで生産を続けています。
つまり「8mmがなくなってから」という発言は、第13回(2001)時点で8mmフィルムそれ自体がなくなっていたことを指し示しているわけではありません。むしろ東学祭が様々な状況を鑑みながら、意図的に8mmフィルムを排除した事実を指し示しているのです。

会場:新宿文化センター
出身:小泉徳宏
<ゲスト>
青木基晃、西村大志、赤羽根敏男、渡辺崇
第14回の応募規約にも「VHS、S-VHS、DVに限る」と明記されています。そこにはフィルムの文字が見当たりません。
結果として東学祭は、自主映画の象徴だった8mmフィルムをいとも簡単に時代の外へ追い遣り、デジタル化に対応してしまったことになります。もちろん作品そのものがフィルム撮影の場合、それをデジタルに焼き直したテレシネでの上映、ということになりますが、どうしてもフィルムの質感は損なわれてしまいます。
もちろんこれは、フィルムを取り扱う難しさや映写機の費用など、様々な事情を総合的に勘案した結果だとは思います。ただ、いくらなんでも2000年代初等で「フィルム不可」としてしまうのは、些か先回りし過ぎている嫌いがある気がします。
東学祭はその後も、時代と合わせてminiDV、DVD、Blu-ray、オンラインスクリーナーといった形で応募規定を変更していきます。ある意味でそれが時代の要件だったといえば、そこまでなのかもしれません。しかし、『ニュー・シネマ・パラダイス』で描かれたような原初的なフィルムへの未練がましさが、あまりにも感じらない冷然としたスタンスには、「自主映画パンク!」などと呼ばれていた時代と比べ、些か隔世的なうら寂しさを感じざるを得ません。(あるいは応募・審査はテレシネを、映写はフィルムのマスターテープを、ということなのでしょうか。当時の資料が少ない上に、上映に関する私の知識も不足しているので、よくわかっていませんが)。
Y「結構オリジナルで作ってますよね」
S「うん、映画そのものに絡めることが多いんです。でもそれは、学生映画でも監督が音楽まで作るっていうのあまりないじゃないですか。
だから逆にその特権を利用しようかな、ていう。—中略—学生映画全体を考えると『学生映画』と名の付くものはあまり著作権とかって
ことまで行かない方が良いと思うんです。PFFの本選出すとかだと勿論許されない訳ですけど。実際音楽を作りたくても作れない、って
人の方が圧倒的に多いと思うし、幅広く作品を募集するんだったらやはり少し厳しいかなと思いますね」
—中略—
M「実際、発案の場としてはどんなものが理想的なのでしょうか。」
S「学生の段階だと、多分大雑把に二通りの作り方があって、 大学生活の中で映画製作を楽しもうって人と職業として将来つなげていこう
という人では考え方も違って、その二つのカテゴリーの人々が同時に参加できる発表の場が東学祭とかだったら良いんじゃないですかね」
M「その部分、さっきの話じゃないですけど、筋道の問題があると思います。上映する時、お金取って見せるんだったら著作権とかちゃんと
やるのが当たり前ですよね。だから逆に言えばそこだけ筋通しておけばいいというか、Sさんが言ってた楽しんでやってる人っていう
のが実際ほとんどじゃないですか。それだったらもう、ハッキリ言うと研修期間みたいな感じで、映画っていうものをつついて遊んでま
す、っていうのも提示の仕方としてアリだと思いますね」
Y「学生映画の大規模な映画祭ってすごく少ないですよね。だから例えば東学祭が規模を大きくして、とかいうのはすごく良いと思いますけ
どーでもそこで音楽とかが厳しくなると出品本数自体にブレーキが……。」
S「かかるでしょうね」 そして、著作権を巡る上記の発言から覗いているのは、ともすれば映画の表現を縛りかねないポリコレへの意識です。
ポリコレ(英: political correctness)とは、広義で「特定の集団に不利益を与えないような配慮」のことを指しています。日本では、特にゼロ年代以降に頻繁に持ち出されるようになった考え方で、例えば「看護婦→看護師」「障害者→障がい者」「スチュワーデス→キャビンアテンダント」といった表記の変容や、差別用語の撤廃に一役買いました。
近年の「#Me Too」運動や「#Black Lives Matter」運動もポリコレの延長ですし、東京2020五輪のジェンダーレス化や度重なる不祥事の背景にも、ポリコレが渦巻いています。映画界では、カンヌ映画祭で「クィア・パルム」が創設されましたし、アカデミー賞でも、審査における性差と国籍差が意識的に取り払われるようになってきました。最近ではインティマシー・コーディネーターの登場や、スーパーマンのカミングアウトも取り沙汰されるようになりました。(*2022年3月30日追記 日本でも、某映画監督と俳優による「立場を乱用した」性行為強要が発覚し、映画監督有志の会は文化庁にハラスメント防止の要望書を提出しました。2020年6月にも、映画配給会社アップリンクのパワハラ問題が表沙汰になりました。私自身は、映画業界にあまり深く身を投じているわけではありませんが、知り合いから聞く限りでも、未だに日本の映画界には醜聞が尽きません。)
確かに、あまりにも過剰に人道的公正を求めてしまうと、ある種の文化は後退し、物事を強く主張できる人間の「ゴネ得」になってしまう現実はあるのかもしれません。その意味であまりポリコレを過剰に適応するべきではない、とする考え方も理解はできますし、あくまで虚構を論じる際の一つの批評戦略でしかないと私も思います。
ただ、あくまで映画は集団で作るものなので、少なくとも製作の過程においては、特に若者含め表現者は、常に誰かを傷つけてしまう事態を想定し、時代を睨み続けなければならないと思います。90年代を駆け抜けた学生の一部には、きっとデイヴィット・リンチを始めするサイコサスペンスや、人体の破壊のみを目的としたような犯罪映画、電波系や鬼畜系などのサブカルに傾倒した者もいたでしょう。いくら学生がモラトリアムだからといって、彼らが一端の人間である限り、芸術であることを免罪符にした暴力的な初期衝動は抑えなくてはなりませんし、特にゼロ年代以後はそうした理性的で強かな作風が評価されていったように思います。事実、とりわけ自主映画パンク!に見られた、ポリコレを鼻で笑い、むしろそれに積極的に抗うようなラディカルさは、確実に威力を失っていると思います。
日本では、NPO法人独立映画鍋や表現の自由調査団などが、多様で平等に開かれた映画文化を推進しています。彼らは国に対して積極的に政策提言を行っていますが、どこまで政府や業界の雰囲気が変わっているのかは、未知数な所があります。側から見ていても近年は、明らかに旧態依然を保っていた以前と比べ、他の産業と共々確実に前進しつつあるようには見えますが、特に雇用契約や労働環境の曖昧な映画業界は、未だに十分とは言えないレベルが現状だと思います。表現の現場は、ポリコレ含め全体的な社会規範を介して、トップダウン的に監視しなければならないと同時に、必ずしも国を信用せずにその緊張関係において、業界の内側から改革しなければならないのでしょう。
ちなみに、映画のフィルムとDVの関係について補足すると、これまでフィルム上映が主だった映画館が、(DCIやDCPなどの)デジタルシネマの規格に揃えなければならなかった21世紀の要請は、極めてクリティカルでした。ひとえにデジタル化といっても、映写機、投影スクリーン、ドルビー音響、高速通信ユニット、といった最新機器を、一斉に揃えなければならなかったので、1スクリーンにつき1000万円程ともいわれている補修費は、低資本のミニシアターや名画座にとって、規格外の投資となりました。
一方で、デジタルシネマは、とりわけシネコンにとって大きなメリットがあったといえます。映画の規格をデジタルに統一することで、これまで掛かっていたフィルムの焼き増し費や修繕費、配達費、映写費といった物的コストを統一的に削減することができました。特にシネコンは、全国的なシェアを誇るからこそ、効率的な配達網、汎用性の高い映写マニュアルを構築することが可能だったのです。また、シネコンを後押しするような形で、大手映画会社と連携したVPF(Virtual Plint Fee)といった配給方式も推し進められる結果となりました。
こうして21世紀は、数多くのミニシアターが閉館する代わりに、シネコンが圧倒的なシェアを占めるようになりました。映画インフラのデジタル化にあたって、一スクリーンあたりに掛かる機材費とフィルムの輸送費、現像費は量的に変わらないので、客単価とキャパが小さく、上映本数や作品のクオリティ、利率にムラがあるミニシアターの負担が大きいのは、火を見るより明らかでした。
デジタルシネマへの移行が遅れたミニシアターの多くは、わざわざデジタルシネマをフィルムに焼き直して上映を行いました。ただ、2011年にテレビのアナログ放送が終わりを告げたのと同様、デジタルシネマの波を食い止めることはできず、『アバター』(2009年)が3D映画として公開された頃には、その潮流は決定的になっていました。東映系のティ・ジョイは2011年、TOHOシネマズも2012年には、全スクリーンのデジタル化を完了し、2013年には富士フィルムが撮影・上映用のフィルムを販売終了しました。
フィルムの扱いに慣れていない今日の学生は、映写の仕組みや素材について無知であるという傾向が強まっていると思います。特に一般大の学生が多い東学祭委員にとってそれは、今後も頭を悩ませる種となるでしょう。
やっぱ祭り(人生)は楽しまなきゃ損ですぜ
以上のように、NPO法人を目指していた東学祭は早々とフィルムを取り止め、新時代の学生映画祭として才能を「育成」する継続的な場所を目指すべく、試行錯誤を繰り返していました。
ただ、折に触れて、三池崇史は以下のようなコメントを寄せています。以下の抜粋は、「SUMMER FESTIVAL 2001」のパンフレットからです。

学生映画祭に・・・
第十四回東京学生映画祭SUMMER FESTIVAL2001の開催、心からお祝い申し上げます。
若き映画作家と若き映画フリークの集うお祭りに、オジさんながら心踊る思いであります。
殊に映画祭に於いては劇場はライブ空間となり、観客の熱気と作者の心臓のバクバクとが入り混じり、
その正体をグロテスクなまでさらけ出すものでございます。あぁ、一期一会。いつ果てるとも知れぬ
あなたの人生なんて、お祭りみたいなもんじゃあ〜りませんか。
「創るアホウに観るアホウ・・・。やっぱ祭り(人生)は楽しまなきゃ損ですぜ」
甚だ勝手ながら、この祭典から強烈な映画作家が生まれることを期待しています。 三池崇史の調子付いた軽快な言葉は、一見すると監督らしい無鉄砲さを表現しているようにも思えます。
しかし、その後の東学祭の展開を知っている私は、むしろ痛い所を突かれ、目が覚める思いがしました。単に三池崇史は無鉄砲なのではなく、むしろそのアイロニックな視線をもって、東学祭の問題を浮き彫りにしたのだと思えたからです。
これはもちろん、私の勝手な拡大解釈でしかありません。ただ三池崇史の言葉の裏に、「国際交流」「マスタークラス」「スカラシップ」等々、意地悪く言えば頭でっかちな学生を、「祭り(人生)は楽しまなきゃ損ですぜ」と一笑に付し、その上で、映画本来の魅力を忘れてはいけない、という教訓を説いているかのような声音を感じたのです。
たかだが学生の集まりに、何ができるだろう?
改めて私は、そう卑下しました。
何度も指摘している通り、東学祭は無責任な学生の集まりに過ぎません。例えNPO法人化し、社会人やフリーランスを迎え入れたところで、才能を「育成」する高度な枠組みを設営するには、極めて高いハードルがあります。
だとすれば東学祭は、あれこれと難しいことを考え、自分たちの意義を声高に吹聴する以前に、設立当初の「自分が好きなら、なんでもあり!」の機運に回帰するべきだったのかもしれません。そして、ただ学生らしく祭り(人生)を楽しむことだけを想定し、「自己完結表現」に居座るべきだったのでしょう。
仮に歴史を遡ってみるならば、ハリウッドのメジャースタジオが崩壊した後に頭角を現したのは、映画小僧(film brats)と俗称された、コッポラ、スピルバーグ、ウディ・アレン、スコセッシ、デ・パルマ、キャメロンらの映画監督でした。多くはロジャー・コーマンによって見出された彼らは、60年代後半から急速にカリキュラムが整備された大学の映画学科出身で、業界に入る以前から実用的な映画製作のノウハウを携えていました。彼らの成果は、「まずスタジオの門を叩き、アシスタントや助監督などの下積みを経た上で、その中でも一部の優秀な者だけが監督に上りつめることができる」といった業界の慣習をすり抜け、ハリウッド第二黄金期を築き上げたことです。
歴史から学ぶところがあるとすれば、日本でもハリウッドと同様、映画小僧(film brats)が映画業界を支配するようになる、ということです。21世紀のデジタル化に伴って映画学校は乱立し、活躍している若手監督のほとんどは映画学校の出となりました。彼らの多くは製作スタジオに入る以前に見出され、そのまま商業デビューを果たしています。同様に、全国各地にフィルム・コミッションが設立されてからは、豊かな映画教育を受けた人が——一部はネットメディアやデジタル技術にもフォーカスを当てた——田辺・弁慶映画祭、なら国際映画祭、ゆうばり国際ファンタスティック映画祭、カナザワ映画祭、SKIPシティ国際映画祭、TAMA NEW WAVEといった映画祭を立ち上げました。誰でも簡単に映画を撮れるデジタルシネマは、映画祭にアマチュア向けの文脈を与え、少なからず学生映画の露出機会も増えてきました。
改めて書くと、早稲田大学から分化した東学祭は、今も昔も委員の大半が一般大学出身でした。つまり、映画に関しては中途半端な経験と知識しか携えていないケースが大半で、映画小僧(film brats)ではありません。そういう学生の集まりが、優れた映画学校や映画祭のコンセプトを模倣し、才能を「育成」などという発想を持つこと自体に、極めて差し出がましい意味合いがあった、ともいえるのです。

結果的に21世紀の映画教育は、映画学校とそうでない一般大とのクリエイティビティの差を、量的にも質的にも開いていきました。
曲がりなりにも一定数以上の学生映画を観てきた私の主観からしても、一般大は役者や機材の面で劣ってしまうのは仕方がないにせよ、着眼点や演出1つで見応えのある作品になる、といった期待も大体のケースで裏切られるようになってきているようにも勝手ながら思います。
映画学校が乱立する昨今、一般大はどのようにして復権してゆくべきでしょうか?
特に、一般大の早稲田大学は以前、「石を投げれば早稲田出身者に当たる」といったくらい、映画業界の人材が多い大学でした。例えば今村昌平、神代辰巳、石井隆、是枝裕和、吉田大八、瀧本智行、西川美和、といった監督も、早稲田出身です。ただ、一般大ゆえに映画教育のカリキュラムが乏しく、近年は8つもの映画製作サークルを抱えていながら、映画学校と比べたら見劣りしている印象が拭えません。
現に第32回では、応募があった15本の早稲田作品のうち——強い問題意識があるのであえて断言すると——有無も言わせぬほど際立った才能を感じた作品は、間違いなくありませんでした。才能、という言い方をすると偉そうなので、情熱、と言い換えてもいいかと思います。コロナ禍によるサークル活動の自粛が、映画学校と一般大の差を、さらに大きく広げてしまったのだと思いますし、内々に話を聞いてみると、早稲田にある8つの映画サークル全てにおいて活動がまばらで、上級生の引き継ぎも疎かになっていたそうです。その結果、下級生同士で固まった制作集団が、漠然としたイメージだけでカメラを握り、初歩的な演出・技術上のミスですら繰り返すようになってしまったそうです。
コロナ禍におけるサークル文化の衰退は、必ずしも学生側の問題だけとは思いません。ただそれでも、学生時代を共にした同窓が「バイト代がなくならない程度に」しか映画を撮れなくなった現状に、遣瀬ない想いは募ります。一昔前の早稲田は、授業で松岡茉優が登壇したり、小川紗良や岩切一空といった耳目を集める学生監督が居たり、少なくとも今よりは華々しい印象があったからです。それ以前にも、早稲田大学は他大学に先駆けてPFFとコラボし、入選者には国際情報通信研究科・映画研究室(2005-2014)への推薦制度を設けた経緯があります。映画研究室は21世紀のデジタルシネマ普及に伴い、産学官連携の映画制作システム(ブロードバンドネットワーク)や高速通信技術、CGIの特殊映像などの研究成果を上げ、エドモンド楊や丸山健志といった新人監督の育成にも力を入れました。
国際情報通信研究科が廃止された後、全学共通(3年生以上)の映像制作実習(2016〜)が始まりました。通年に渡って本格的に劇映画を撮る授業は、早稲田の中ではこの授業しかありません。前任・安藤紘平からの誘いで教授職を引き受けた是枝裕和や篠崎誠らが指導に当たっています。パルムドール監督と映画を撮るという贅沢な内容に在学生たちは色めき立っていて、他大生からも羨ましがられることが多いそうです。
実習で制作された数本の短編映画は、学内の大隈講堂や早稲田松竹で上映されます。私も何度か足を運び、東学祭にも応募があったのですが、やはり講師陣の指向が反映されているのか、ドキュメンタリーチックかつ自然主義調、とでもいえる映画が多い印象を受けました。立教ヌーベルバーグや自主映画パンク、デジタルシネマ路線とも毛色が異なる、新しい学生映画の潮流といえるのかもしれません。
実は私も、この映像制作実習に申し込んでいたのですが、(映画祭の活動も紹介した)書類選考で落とされてしまいました。ある教授から聞く所、
「人気な授業で定員がオーバーしている。だから理工系の学生が優先的に履修できるような形にはなってしまう。申し訳ないとは思うが、これはあくまで授業でしかない。本当に映画を撮りたければ、自分で仲間を集めて撮れば良い」、といった趣旨のことを言われました。全学共通なのに何故理工系の学生が優先されるのか、なぜその旨をシラバスに書かなかったのか、色々と怪訝に思う点はありましたが、毎度のごとく大学の履修制度はかくも曖昧なものかと——今年はモグリもできないそうで——諦めました。むしろ理工系の学生は、研究分野である技術面を担当し、監督や脚本はその筋に熱意があって第一線で研究している文系の学生が担った方が、カリキュラムとしては筋が通っていますし、そもそも「あくまで授業でしかない」という発言には、「大学は研究機関」だという、ある種の開き直りのようなニュアンスにも感じ取れて、どこか釈然としません。もちろんその理解にも正しいものがありますが、逆を言い張れば「大学は教育機関」ですし、大学教育が変われば、連鎖的に産業構造も変わるのではないかとも思うのです。コロナ禍の大学で「8単位分を通信教材で済ませる」「同じ講義動画を使い回す」「音声や映像の乱れに対処しない」「メールなどの連絡に応じない」といった教授側の不手際が、多くの学生の意欲を削いでしまったトラウマ的な事実もありましたし、それでいて学費を「変えない」「返さない」大学側の理屈に失望し、中退・留年を余儀なくされた学生も数知れません。
確かに映画の理論面は重要ですが、「出版産業論」の講義はあるのに「映画産業論」がないのはどこか不思議ですし、仮にその文化の表層が先行し、学生にとって実学的な知見が得られなければ、少なくとも教育機関としての大学の枠割は、画餅に帰すのかもしれません。私は以前の章で、映画学校の問題点を挙げました。それは、お金の集め方、保険の入り方、広報のやり方、といった実用的な知見を教わる機会が少ないという点でした。あくまで個人の意見に留まりますが、早稲田大学には改めてこういったコンサル的な問題点を認識してもらい、決して理屈で封じ込めず、むしろ一般大である鉱脈を生かした、学生に寄り添った教育改革を行って欲しい、と勝手ながら願っています。そうすれば、本気で映画を学びたい学生が「映画にバイト代を捧げる」ことに言い淀むこともなく、実用的な知見を持って「映画業界の石橋を叩いて渡る」必要のない、健全な映画文化の発信地となるはずだからです。
ところで、なぜ私はここまで一般大に拘っているのでしょうか?
確かに、活躍できる人材は個人単位で、一般大or芸術大の別を気にしすぎること自体に、学歴社会を助長してしまう側面はあると思います。実際、多くの監督の出身校はバラバラで、受けてきた教育や影響を受けた映画も異なります。
しかし、映画の問題は、端的にいえば資本主義社会に組み込まれている、という根も葉もない現状にあるのだと思います。ご存じの通り、資本は学歴に群がり、高水準の映画は資本なくして成り立たないので、大体のケースで論理的に資本=映画が成立してしまいます。
実際、多くの美術展覧会の協賛にはオールドマスメディアが付いているように、多くの映画祭・映画も、文化庁の支援がなければ成立しません。必然的に映画監督たちは、いかにして自らのクリエイティビティを出すかを考えるのと同時に、いかにしてそれが能うる資本主義の土壌を手に入れるかに懊悩します。
資本主義の担い手、少なくとも映画と関わりが強いのは、大手映画会社であり、テレビ局やNetflixなどのプラットフォームであり、力ある官庁です。そこには間違いなく、もはや言い逃れのできない学歴社会が存在しています。官僚試験に合格できるのは東大出身(その他一部の旧帝大や早慶)のみであり、就活で大人気な大手映画会社(東宝、東映、松竹、KADOKAWA)やテレビ局(キー局+NHK)も然りです。私も就活をしてつくづく感じるのは、良くも悪くも彼らは、芸術の水準を保つ美的インフラ作りではなく、あくまで最大多数を喜ばせるビジネスに奔走している、という明快な傾向です。社会貢献的な欲よりも、テーマパーク的な楽しさや、収益の安定性が、あくまでも優先される事項として上げられるのです。
身も蓋もなく言えば、そういった態度には、資本主義社会としては説得的で、一定の正しさが認められますし、むしろ映画がビジネスとして成り立つ時代に生まれたこと自体、幸福に感じるべきなのかもしれません。ただ、そもそも芸術という営みは、およそ国家やビジネスという概念が生まれる以前から、そこに価値があるの/ないのか、ある意味で宙ぶらりにされたまま、何だかんだで必然として継続されてきた遺産であり、そこに映画を含めるにせよ含めないにせよ、人類の豊かさを保つ美的インフラとして、先行投資し続けるべきだと私は思います。もちろん全体の資本は限られているので、どの程度まで再分配するかは議論の余地がありますが、少なくとも現状で映画に割り当てられている予算は、決して十分とはいえないでしょう。
後ほども少し言及しますが、そういった問題は、官庁や大手企業がお粗末なクールジャパン戦略しか取れていない点や、『ドライブ・マイ・カー』を配給できなかった点にこそ、顕著だと思います。個人的には——ここであえて名前をあげておくと——川村元気のような、支配的なオールドマスメディアとも適切な距離感を保ちながら——結果的に多少の美的ファクターを削ることになろうと——まとまった資本をもって、日本のサブカルを大舞台に押し上げるプロデューサーがもっと増えても良いと思います。例えば「ハリウッドの大物プロデューサー」が夢見られる海外と比べ、日本ではプロデューサー職の人気がありません。私も大学生活を通じて、「将来の夢は映画プロデューサー!」と声高らかに宣言している映画好きに会った試しがありません。
日本映画を底上げするためには、まずは一般大(特に難関大)が変わること。
学生である私個人に、何ら資本主義的な発言力がないこと、この記事で何かを主張しようと影響力がないことは自覚しています。ただ私はこれまで、学歴的には多少有意なポジショニングをしてきたからこそ——結果的に、むしろそのことで苦しんだことの方が多かったように思いますが——ミニシアターや学生映画のように枯渇しつつある文化を、直接的であれ間接的であれ、守っていけるような立場を目指したいと考えています。

会場:青山・ウィメンズプラザ
<ゲスト>
篠原哲雄
三池崇史の天声虚しく、東学祭は少なくとも第15、第16回と、学生にそぐわない意識高いアジェンダを掲げて活動を続けました。
第15回の後援に、日本ユネスコ協会連盟があったことが、その最たる象徴だと個人的には思います。国連の関連組織が、どうして東学祭と絡んでいたのかは定かではありませんが、もしかするとその背景には、国連広報センターや国連大学の近くにある青山ウィメンズプラザが会場として使用されていた経緯や、予選会場として青山学院大学が使用されていた経緯があったのかもしれません。
また、関連性があるのかは分かりませんが、その年は副賞としてPISTOL projectというニューヨーク・フィルム・アカデミー(以下 NYFA)の交換留学の権利が与えられていました。国際色が強い交換留学の仕組みは、恐らく「国際交流」「スカラシップ」の各セクションを克服する狙いがあったのだと思われます。

NYFAはどうやら「USC、AFI、UCLAと並ぶ世界最大規模の映画学校」らしいのですが、海外の映画教育事情に一切の門外漢である私は、この重要度の高さ、影響力の強さが良く分かっていません。
少なくとも2000年代前半、NYFAに所属する教員は世界中で講義を展開していて、その実践集中プログラムの幾つかは、日本人向けにも開講されていたそうです。真偽の程は定かではありませんが、スピルバーグの息子マックス・スピルバーグや、 マーレー・エイブラハムの息子、リュック・ベッソンの妹など、数多くのハリウッド・ ファミリーが NYFA で学んでいました。ハリウッドの第二黄金期を支えた映画小僧は、やはり自分たちの小僧にも上質な映画教育を施そうとしていた、ということなのでしょうか。

会場:パナソニックセンター東京
<ゲスト>
古厩智之
第16回が、有明のパナソニックセンターで開催されたという事実も、学生にそぐわない意識高さがあったという意味では、どこか象徴的です。
パナソニックセンターは、映画館というよりオリンピックやSDGs関連の展示を行うショールームのような施設です。2019年には、LGBTを題材とした映画『カランコエの花』の上映会、2021年には大阪で社会課題やSDGsをテーマにした「カエテクシネマ」が催されました。第16回の協賛先であったGAGA!の招待上映が行われた『白いカラス』(2004)も、人種差別を扱った内容でしたし、少なくともサークルのイベントを開催するのには不釣り合いな格調高さが存在しているように思えます。
第16回も引き続きNYFAとも提携し、「学生映画の黒船来襲!!」と題された、海外の学生映画の上映が行われました。上映後は、「Made in U.S.A 〜アメリカで活躍している日本人たち〜」と題されたトークショーが執り行われ、日本とアメリカの映画教育について議論が交わされました。
上映後の懇親会(レセプション)も「センター内のオシャレなカフェ」で行われたみたいですし、払ったチケット料が製作者に還元される西欧的な「チップ制」も採用されています。開催期間の二日目には、第16回東学祭のためだけに結成された東京藝大の映画音楽ユニット「Tokyo Lip Punchers」が余興演奏を行っています。
そういった、端的に言えばグローバルだとか、ダーバーシティだとかいったイメージが付き纏っているこの時期は、むしろ2021年現在よりも「現在的」といえるのかもしれません。例えばあいち国際女性映画祭は1996年から、学生を対象にした国際平和映画祭は2011年から始まっていますが、ここ十数年の東学祭に一貫した政治性はなく、あえて言えばノンポリ的といってもよいでしょう。社会批評的な側面から映画を捉え、それを何かの主張に繋げたい、というタイプの委員が、今も昔も少なかったのだと思います。もしくは何か問題意識を抱えてはいても、それを映画祭の空間で具現化する必要はない、と捉える委員が多かったのでしょうか。
もちろん、映画祭が明確なテーマを掲げ、政治的な主張をする(あるいは結果的にしてしまう)事が悪いとは思いません。むしろある程度の客観的な信頼を保った上で、自らが考える理想の映画(ひいては社会!)を主張することなしに、映画祭のどんな存在意義があり得るでしょう?
先ほどもポリコレと関連させて触れましたが、製作の過程におけるパワハラはご法度ですし、表現者は、常に時代を睨み続けなければならないと思います。ただ、主張が明確な(ともすればプロパガンダになりかねない)作品から、美質だけを追い求める作品まで——どれだけの極端さが許容されるかは議論を重ねるとしても——映画には、映画それ自体の限界を超え、常にその先にある普遍性に触れようと試み続けている、そういった毅然性があるとも思うのです。
だからこそ、映画に限らずあらゆる芸術の、あらゆる種類の挑戦は、包括的に可能であれねばならない、とも思います。そういった環境整備が自立的に進めば、ポリコレともまた異なる、芸術そのものの水準を保つ真の意味でのグローバリズム、ダイバーシティが達成できるのかもしれません。
第17回(2005)-第28回(2016)
結果としてやはり、というべきか、東学祭のNPO法人化計画は頓挫してしまいます。
原因となるようなエッセンスはこれまで提示してきたので、改めて詳細をグドく説明する必要もないかと思います。東学祭が社会的意義を提示するに至らなかったのは、ある意味で必然でした。新時代の学生映画祭のあり方として提示された学生向けワークショップや、サマー・フェスティバルの企画も形骸化してしまい、製作部(Miximum)の活動もまばらになった結果、東学祭は才能を「育成」する継続的な場所としての理想から、ますます遠ざかっていくことになります。
第17回の議事録に面白い内容があったので、以下に引用させていただきます。ここでは、どのように会議を行えば良いか、といったシミュレーションを行っているそうですが、扱っている内容はどこか当時の逼迫感を示しているようにも思えます。
「活動資金が底をつく」という事象に対しどうするかという流れ。
一. 昨日東学祭の活動資金が残り 五万円であることが判明した。
二. そのため、十万円かかるフライヤーの印刷が行えなくなる。
三. フライヤーの作成はどうしても必要なことで中止することはできない。
四. 財務部は打開策を考えることにした。
(中略)
部署会で考えた結果、打開策は大きく三つになった。
a. 全員で短期のバイトをする
b. 全員土下座でSさんに出してもらう
c. アコムで借りる
(第17回議事録) 開催資金が足りない打開策が、バイト、土下座、消費者金融の三択しか提案できないこの状況は、些か滑稽です。
現在では、企業協賛、OB・OGのカンパ、助成金、クラウドファンディングといった方法を提案できるのかもしれませんが、当時の委員にはそういった柔軟さがなかったのでしょうか。東学祭の運営規模は、前年度の繰越金と当該年度の収益によって変わってきますが、過去には委員がバイト代を献上したり、パチンコの一本釣りを狙ったり、といった形で開催費が賄われたという逸話も残されているくらいです。財源がなかった年の東学祭は、ゲストを減らすなり規模を縮小するなり、その時々に捻出されたアイデアを駆使して開催されてきました。
ちなみに引用中のSさんは、恐らくフリーの社会人として東学祭の運営に関わっていた方です。社員数名やフリーランスが東学祭をバックアップしてきた経緯は前記しましたが、第16、第17回の学生委員との深刻なコミュニケーション不足に悩まされていて、切実な不満を洩らしている内部文書も見つかりました。
こうして東学祭は、NPO法人化に失敗した挙句、大きな内輪揉めも経験し、実務的にバックアップしていた企業も次々と撤退していくことになります。第17回の概要資料にも、「協賛企業に頼った時期もあったが『やりたいことが制約される』」と後ろ向きな記述も散見されます。
21世紀に入ってから5年余り、ついに東学祭は外部組織を運営から切り離し、学生のみの運営に戻りました。東学祭が設立された当初のコンセプトを忘れ、一度は学生にそぐわない意識高さを掲げていた委員たちも、自らの矛盾に気づき、ここから徐々に当初の学園祭の機運を取り戻していくことになります。
学生の、学生による、学生のための映画祭

会場:新宿文化センター
<ゲスト>
松浦雅子、仲倉重郎、宮崎晃
第17回を迎えた東学祭は、後にも先にもなく公益性を度外視した、学生の、学生による、学生のための特別企画を立ち上げることになります。企業や社会人からの制約がなくなった結果として、必然的な流れといえるでしょう。(なぜかその年の協力団体に、草津温泉観光協会が入っています。草津温泉は、サークルやゼミの合宿を行う定番です……)。
To-1 GRANDPRIXと題された企画は、参加団体をA-Fまでの6つのブロックに分け、その後トーナメント形式でグランプリ(東京No.1映像団体)を決める、といった異例の内容でした。「To」は「Togakusai」の「To」ですが、「○ー1」というワードが頻繁に使われ出したのは「M-1」や「R-1」、「B-1」('06〜)の流れでしょうか。


会場:世田谷区 北沢タウンホール
<ゲスト>
降旗康男、渡邊孝好、滝田洋二郎
上図が、To-1グランプリの詳細です。
映画祭は映画を部門ごとに区切り、審査員を立てるのが常です。あろうことかTo-1グランプリは、参加団体を各ブロックへ恣意的に振り分け、それぞれ異なった相対の評価基準で予選を行っています。その後も、トーナメントに上がった団体同士による対決(VS)形式で審査が行われ、順位が決定されています。
これらは明らかに、映画を評価する映画祭としての平等なスタンスを欠いています。ただ、作品ではなく参加団体のNo.1を決めようとする発想には、どこか一般大サークルとしての「楽しまなきゃ損ですぜ」の矜持にも捉えられます。つまり、映画学校の乱立によって衰退していく一般大サークル(である東学祭)を、個人としてではなく、団体としていかにして盛り上げるか、といった従来の学園祭的な発想が、ここで改めて顕在化し始めるのです。
第18回になると、東学祭は下北沢の北沢タウンホールという大きな施設を借り入れることに成功します。
会場の変遷については、第29回以降の章でまとめて記述しますが、北沢タウンホールは第18回から第28回の11年間に渡って使用された、お得意の会場でした。東学祭はそこから、「下北沢で5・6月に開催される、毎年恒例の学生映画祭」としての、統一されたイメージを確立していきます。
下記は、当時の議事録に残っていた幹部の言葉です。
東京学生映画祭とは、本来学生たちがいて、自分たちのコミュニティを作り、
そこから自らや参加団体が成長し、共栄していくための組織であったはず。確かに、元を辿れば東学祭は、学生の、学生による、学生のための映画祭として設立されたはずで、1つの大学だけに留まらない新しいコミュニティを目指し、様々な大学、映画人との関わりを増やすための場所でした。名目的にでもPFFに対抗し、「自分が好きだったら何でもあり!」という若々しい学園祭の機運が、委員のインセンティブを保ってきたのです。
その意味で第17、第18回と、そういった原点に回帰した東学祭は——あえて時代的な言葉を使うと——まったりとした意識改革を達成した、ともいえると思います。
このフレーズは、映画評論家でもある宮台真司の「まったり革命」に拠っています。特に第17回の委員は、決して頭でっかちになることなく、「そこに意義はあるのか」「むしろそれは、没意義ではないのか?」などといった議論を宙吊りにしたまま、ただ「まったりと」脱力し、交流を深めていったのです。
そして何より、後にも先にもそのあり方こそ、東学祭本来の姿なのだと私自身も思っています。あくまでサークルとして、職業と趣味の間に存在するハードルを渡ってみせ、何かの主義に囚われて緊迫し続けている、といった状態は、あらまほしくありません。
コミュニティ拡大計画
このまま東学祭は第18回以降も、「まったりと」他大とのコミュニティを拡大をしてゆく、幾つかの意欲的な活動を展開することになります。
当時の代表は、委員向けに「第17回以降の東京学生映画祭の展望に関する報告」という資料を作りました。その中にある、「コミュニティの形成について」という項目を以下に引用します。
コミュニティの形成について
東学祭に期待されるのはコンペティションの他に、学生映画に関わる人々の「コミュニティ」の役割である。
■ 現状では交流会の出席の他には、特に交流は促進されていない。
■ 監督、脚本、役者、スタッフの共有が現実的に可能となるようなシステムの構築が不可欠である。
■ 現在は「参加団体制」であるため、個人がコミュニティに参加できない。ここでは、才能を「育成」するといった観点よりも、いかに学生間のコミュニティを拡大するか、といった点が強調されていることが分かります。また、これまで内輪の繋がりになってしまっていた「参加団体制」の問題点を指摘し、個人がコミュニティに参加できる枠組みを目指している点も分かります。
次に、同じ資料から、映画製作に必要な「監督、脚本、役者、スタッフ」といった人員をコミュニティ内で補い合う、SFM(Student Film Members)構想なる項目を引用させていただきます。
SFM構想
脚本、役者、スタッフの共有を実現するシステムとして、
SFM(Student Film Members)設立を提案する。
SFMとは東学祭とは別の、個人参加型データベースである。
会員には個人登録を行なっていただき、メンバーズカード、
ID、パスワードを交付する。これにより、HP上でメンバー
間での情報共有システムを創設し、登録された個人の情報を
検索、閲覧することができるようにする。
また、都内各地の映画館等と交渉し、会員にそこの情報を宣
伝する代わりに、学割以外の特典を会員に与えてもらうこと
も考えられる。
SFM構想実現のために、参加団体及び新規参入者に対する
構造的利益を想定する。
SFM会員の年会費を年1000円と設定する。ただし、東学祭に
参加している団体に所属する者はこの金額を免除とし、団体
での加入申請を可能とする。(個人の情報を団体でまとめ、
提出してもらう)
また、SFM会員は参加団体を介さずに東学祭への作品出品を
可能とする。
これにより、参加団体へは宣伝媒体等の無料提供が可能であ
利、団体に所属しない者、専門学校生等は東学祭への参加も
容易となる。(以下省略)SFM構想は上記に加え、メンバー対象のメーリングリスト、メールマガジンの運営を提案し、SFM委員同士の宣伝が可能となる施策も打ち出していました。
結果的にSFM構想は、年会費の仕組みや、「メンバーズカード・ID・パスワード」を基にした、会員向けデータベースを運営するハードルの高さから実現することはありませんでしたが、その発想を起点として、いわばコミュニティ拡大計画なる、幾つかの新たな活動を展開することに繋がりました。
それは、私が勝手に大別するところ以下の4つになります。次からは、それぞれについて、ごく簡単に概要をまとめていきます。
定例会
特別上映
パーソナルメディアの活用
日本学生映画祭
1. 定例会
まず1つ目が、定例会の推進です。
もともと定例会は、第15回から月に1回、映画祭の参加団体を対象に行われていました。第18回以降からはさらに活発な様相を呈することになります。

上記は第23回(2011)時の定例会の模様です。参宮橋にあるオリンピック記念館の一室を借りて執り行われていたようですが、かなりの人数が集まっています。
定例会では、東学祭のエントリー情報や、審査基準などの説明に加え、機関紙の配布、学生映画の上映会も行われました。定例会後には懇親会も行われ、各参加団体の取り組みやオススメ映画、行ってきた映画祭などの情報交換も行われました。雑誌の「ぴあ」が廃刊になり、映画をシェアできるFilmarksなどのプラットフォームがなかった頃、映画好きの学生たちは情報に飢えていたのかもしれません。
結果的に定例会によって促進された、普段は関わりのない学生たちとの交流やマメな情報収集は、部門や各賞など、しっかりと東学祭の運営方針にも反映されました。

上図は、第23回の全体フローです。
代表者一名はまず参加団体としてエントリーし、その後は定例会に参加を通して作品をエントリーする、という流れでした。
上記のリンクを貼った通り、定例会はブログやツイッターなどのパーソナルメディアによって、規模を拡大した経緯があります。Amebaブログに情報が記載されている通り、第24回の10月に開催された定例会の告知は、例えば以下のようなものでした。
みなさん、こんにちわっ♩
もうめっきり肌寒くて秋って感じですよね(^O^)/
夏休みボケと気温の変化で風邪ひかないようにしてくださいね🌷
さてさて今日は大事なお知らせがあります!!!!!!!!
第24回になって初めての「定例会」の日付が迫っています。
第1回 定例会は10月23日(日)18:00~、参宮橋のオリンピックセンターにて行います❗️❗️
第24回東学祭のご説明と23回の機関誌の配布などをさせていただきます!!
自分の作った作品を応募したい方はもちろんっ、映画制作に興味がある方や、
どんな映画祭なのかな?説明を聞くだけでも・・・って方も大歓迎です✌️
ぜひぜひ気軽に参加してください!!o(^▽^)o!!(中略)
Twitterのほうでも随時、最新情報を配信するので引き続きフォローお願いしますね('-^*)/ 公式ブログであると同時に、サークルらしい非常にパーソナルな文体であることが分かります。「(^O^)/」といった必要以上の顔文字や、「🌷」といった絵文字にも、今や隔世の感が漂っていますが、むしろ学生らしい親しみをもって読むことができます。

会場:世田谷区 北沢タウンホール
<ゲスト>
清水崇、津田寛治、柳ユーレイ、マギー
*副賞には「ホリプロ演技無料レッスン権」
定例会は、一つには第19回から作り始めた機関紙の配布を目的としていましたが、何よりも、作品の持ち込みを第一としていました。
以前の章でも触れましたが、第26回までの東学祭は、「定例会等での持ち込み」を応募の原則としていました。それは、郵送時にフィルムに傷がついてしまう時代の名残や、一時期を除いて東学祭に部室・事務所がなかったという背景もありましたが、一番の理由は、学生一人ひとりが別個に応募しなければならない煩雑な手続きを回避し、代表者がまとめて作品を応募することのできる参加団体制によるものでした。そのため、当時のエントリーには「 団体エントリー/5000円」「個人エントリー/1000円」といった、映画祭としては珍しいエントリーの区分けが存在していました。
以前の章でも、東学祭では基本的に作品の持ち込みによって、ちょっとあの大学へ足を運んでみよう、といった具合に学生間の繋がりが生まれた、と記しました。定例会でもそれは同じで、多くの学生が、何かしらの交流や出会いを求めて参加していたのです。
恐らく今も昔も、都内の映画サークルが一堂に会す、といった集会は、東学祭の定例会くらいしかなかったと思います。
後に詳しく説明しますが、定例会は2016年頃に廃止され、2020年に突如訪れたコロナ禍は、サークル文化を衰退させました。以前も書きましたが——それが、SEALDsの反政府デモをはじめとする「動員の革命」以後という言い方が正しいかは分かりませんが——学生が活動的に集会しようという機運は、ますます薄れてきているか、露悪へと向かってしまった実感があります。
こういった現状を、私個人はとても悲観的に眺めていました。
映画をはじめとする「文化系」サークルは、活動の達成度やフィロソフィーが共有されていないが故に、それでいて「何がいいか」の拘りの価値観が多様であるからこそ、むしろ所属する学生の多くが「目標を持って仲間を意識し、仲間の外を意識する」実感の掴めていない、閉鎖性を伴ってしまうことがただあります。そうした閉じられた社会関係の中では、ただ趣味や理屈の延長にある、一方的な価値観が蔓延しがちになります。偏った意見かもしれませんが、あくまで個人の実感として、そこには文化系サークルが宿命的に抱えている問題がある気がします。
私が見聞きする限り、ある種のサークルの揉め事は、特定のサークルクラッシャーがいて、その人が社交性を顧みず、自らの充足できない「非リア」的な不全感に、「こんなくだらないことやってられない!」というヒステリックな反動を起こしてしまったことに原因があります。彼らは、コミュニティ全体へのやっかみとして、「仲間」や「絆」ではなく、むしろ「損得」や「インセンティブ」といった精神性を、サークル内に振り撒くようになります。彼/彼女は、例えば「平気で活動をサボる」「飲み代に吝嗇になる」「会費を着服する」「性愛関係だけを求める」といった、他人への思いやりを欠いたアンモラルな行為に走ります。彼/彼女のようなサークルクラッシャーが一人でもいれば、複数人いれば尚更——そうした彼/彼女のアンモラルを抱える懐を持たない——コミュニティの新陳代謝は悪くなり、ますます島宇宙に閉ざされることになるのです。
そして何より、その傾向はコロナ禍で強まった実感があります。
極めて個人的な「サークル観」で、抽象的な言い回しばかりで申し訳ないと思いますが、あくまで上記の記述は、私個人が抱いた、文化系サークルにおける一極端な印象のスケッチでしかないので、あまり気に留めないでいただければとも思います。ただ私は、他の文化系サークルでも似たトラブルがあると耳に挟みましたし、実感としてあながち的外れでもないと思ったので、あえて記載しました。
これは「学園祭の機運」について記述した序盤とも通じてきます。改めて書くと、サークルとは元来、目的と仲間意識の異なった、しかも金銭の絡まない身勝手な学生の集まりです。そしてそういったサークルならではの身勝手さは、とりわけ文化系サークルに顕著で、だからこそその暴力的なまでの恣意性が、学生映画を学生映画たらしめているといえるのです。
2. 特別上映
年に1回のコンペティションだけでは、コミュニティ拡大に不十分だと判断した東学祭は、定期的に特別上映を行うことになります。
一括りに特別上映といっても、コンセプトや規模、雰囲気一つ取っても様々です。この記事では、特筆すべき上映会だけをピックアップし、系統化してまとめています。
まず、第20回以後から度々行われるようになったのは、本祭以外で入賞作品を上映する、展開上映なるものでした。先ほども触れた、「ショートムービー」や「アニメーション」といった短尺の作品専門の上映会や、グランプリ作品をミニシアター等で上映する、凱旋上映とでも呼ぶべき興行形態も含まれます。
映画祭の一環として上映されるのと、グランプリの名前を提げてミニシアターで公開されるのとでは、また違った重みがありました。例えば新宿テアトルでは毎年、和歌山で行われる田辺・弁慶映画祭のセレクション作品を劇場で掛けています。
上映される環境で作品の価値自体は変わらないと思いますが、それでも東学祭は、映画が常に異なるメディア空間・観客を行き来しているという現象と、それによって受容のされ方が異なる、という現実について、意識的に目を配ったのでした。そうしなければ、なぜ自分達がわざわざ映画をスクリーンに投映するのか、はたまた世界の至る所でその営みが継続しているのか、という根本的な疑問に対して、説得的な理由を提示できなかったのだと思います。
特に21世紀以後、私たちの多くは映画をテレビやネットなどのメディアに置き換えて視聴しています。委細を気にしなければ特に問題はないようにも思えますが、これまでの映画は、テレビやネット、ラジオ等とは異なり「映画館の暗闇で鑑賞する」というメディア環境に美徳が見出され、それゆえのダイナミズムが存在している、という考え方が支配的だった節があります。近年、配信サービスが益々発達してきているからこそ、なおさら映画祭はメディア環境に対して、これまで以上に問いを突き立てなければならないのでしょう。
配信に関する議論は、後程も触れたいと思います。ちなみに、こういったメディア環境を巡る議論について、少しでも映画をアカデミックに齧っている方ならば、マクルーハンの主著『メディア論―人間の拡張の諸相 』や、ベンヤミンの画期的な評論『複製技術時代の芸術』とその周辺の議論を思い起こすかもしれません。
何よりも東学祭の場合、ただでさえ公になる機会が少ない学生映画を、あらゆるメディア空間・観客に展開する、といった営為は正当化されるべきだと思っています。映画館であれ配信であれ、そもそも認知されていない以上、まずは多くの方の目に触れる機会を、街頭で宣伝するなり、フライヤーを刷るなり、映画サイトに掲載してもらうなりして、積極的に作らなければならないのですから。

会場:世田谷区 北沢タウンホール
<ゲスト>
澤井信一郎、清水崇、萩生田宏治
長澤雅彦、小林すすむ、緋田康人
川崎昌平、行定勲
第20回では、本祭の前日に「ショート!ショート!ショート!」と題された特別企画が開催されます。メインのコンペティションとは別枠で、まずは予選で「格差」というテーマのショートムービー(3分以内)で競い合い、決勝では自由なテーマによるショートムービーでグランプリが決定されました。3分以内、という尺の基準は後にも先にもありません。
ショートムービーといえば、当時はニコニコ動画の全盛期です。ただどうやら、学生映画の集会場にはなっていなかったようです。2021年時点で「自主映画」と調べてヒットするのは1389本、「学生映画」に至っては38本。しかも、それらのほとんどが東学祭の応募対象になりうる純粋な学生映画ではありません。
ジャンルとしてはホラーが多く、予想通り登場人物の挙動や、荒唐無稽な展開に目を光らせてはネタ化する、といった消費のされ方が大半でした。実際、巷の映画では見られない、あまりにもお粗末な学生映画(ふざけ過ぎている、真面目な演技が的外れかつ下手すぎる、話の展開が不自然すぎるetc……)はセレクションのネタになりますし、史上最低な映画監督エド・ウッド的な鑑賞法も、あるにはあって良いと思います。そのため、ニコニコ動画と学生映画の良さが融合されなかった過去には、少し寂しいものがあります。
ちなみに第20回の本祭では、同じ学生映画祭である夕張国際学生映画祭のグランプリ作品、フランスフレノワ国立近代アートスタジオ出身の瀬戸桃子の招待上映も行われました。副賞として、コンペティションでグランプリを受賞した作品が、協賛先の渋谷シネマGAGA!で展開上映されました。
ちなみに夕張国際学生映画祭は、ゆうばりファンタスティック映画祭10周年を記念して企画されたものですが、2008年に何らかの事情で閉幕してしまっています。夕張市は2006年に全国で唯一「財政再建団体」に指定された、財政破綻都市であることは有名ですが、少なくとも若者文化の後押しは、復興事業としての採算が見込めなかったのでしょうか。

会場:北沢タウンホール
出身:頃安裕良
<ゲスト>
山下敦弘、川原伸一、寺島進、大塚雅彦
アニメーション作品が増加したことを鑑み、第21回の東学祭は「実写部門」「アニメーション部門」の2部門の編成に変わりました。
この年から新たにホリプロが協賛に加わり、「オリジナル演技レッスン無料参加権」という副賞付きの「役者賞」が設置されました。前回に加え、同じ学生映画祭である京都国際学生映画祭と、フィルムスケッチ国際大学生映画祭(韓国)の招待上映も行われました。
京都国際学生映画祭は、現在も継続して協力関係にありますが、フィルムスケッチは「韓国の学生映画祭」という以外にはまさに藪の中で、その実態は分かっていません。ネットや新聞で検索を掛けても、ほとんど引っ掛かりませんでした。
そもそも、この社会には見たことも聞いたこともない映画祭が無数に存在していて、その多くが趣味の延長、あるいは主要な映画祭で評価されない製作陣の見栄張りの対象になっている——という言い方は、斜に構えたようで酷いでしょうか。ただでさえ映画祭はマイナー文化で、世の中の大半がパルムドール作品さえ追えていない現状下で、どうして無名の映画祭に応募し、格付け(と同時に格差下げ?)を行おうとするのかは、私の知識や理解が及ぶところではありません。
他方で、そもそも全ての情報にログが残っている、といった発想自体が、現代的なものなのかもしれません。かつては、多くの映画・映画祭の宣伝がフライヤー(チラシ)やポスターのみによって行われ、興行期間が終わった後はソフト化を待たなければなりませんでした。ソフト化がされないまま、フィルムのマスターテープを遺失してしまえば、永久にアーカイブは残りません。例えば戦争によって多くの映画フィルムが焼き払われ、名だたる巨匠の作品が遺失してしまった事態には、嘆かわしいものがありました。
現代、いかなる芸術も——特に最近は演劇部門が活発ですが——アーカイブ化できるテクノロジーの進化に、私たちは感謝するべきなのだと思いますし、この記事全体も、そうした資料の恩恵に与っています。一方でアーカイブ化が進むあまり、むしろ氾濫してしまう情報を、定期的にアップデートし、然るべき解釈を与えるということが、何よりも必要なのだと思います。

会場:北沢タウンホール
<ゲスト>
岡本大輔、井土紀州、小泉徳宏
第21回の直前には20周年を記念し、「誰も知らない映画史」と名付けられた特別シンポジウムが開催されました。会場のホワイエでは、20年分の年表や資料が展示され、数多くの関係者がお祝いコメントを寄せました。
上映会では、過去の入選作三本(下図を参照、8mmフィルム)が上映され、東学祭の出身である井土紀州、小泉徳宏の二人がトークショーのゲストとして迎えられました。
トークショーにて両監督は、東学祭の過去や学生映画にまつわる話を展開し、「若い頃に撮った作品を観るのは恥ずかしい。」と昔を回顧しました。一方で、自らが学生時代に持っていた、いや学生時代にしか持ち得なかった情熱について語り、映画を志す学生に向けて力強いメッセージを送りました。この点については岩井俊二も、「どう考えても情熱だけは大学時代がピークだった。あのゾーンには大人になるとなかなか辿り着けなくて悔しい。」と東学祭にコメントを寄せたことと通じます。

『第一アパート』(井土紀州)
『文金高島田二丁目』(小泉徳宏)
このシンポジウムは、小さいながらもコツコツ続いてきた東学祭が、当事者以外に、ほとんど誰も知らないサブカルとして続いてきた経緯を振り返り、次世代の想いを継承する、といった要素が大きかったと思います。当時の委員も、「当時と現在の映画の変貌、逆に変わらない部分などが見えてきて、なんとなくではあるけれど『学生映画とは何なのか』、そういったことが見えてきたように思えます。」と感想を述べています。
2021年から13年前、当時は10歳にも満たなかった私が第32回代表としてその襷を掛け、今こうして記事を書いているということに、どこか感慨深いものを感じざるを得ません。

ちなみに、現在の東学祭が使用している上記のロゴも、20周年を記念して作成されたものです(私自身も愛着が深いです)。レゴのように幾何学的でゴツゴツしていながら、どこか若々しいスマートさのあるこのロゴは、まさに東学祭のイメージを体現しているようにも思えます。

会場:渋谷HUMAXシネマ
<ゲスト>
三木聡
第21回もグランプリ作品の上映会が行われ、三木聡がゲストとして登壇しました。三木監督は学生に「どうせなら、滅茶苦茶なものを作って欲しい」と述べた他、自分が学生時代に映画を撮っていなった経緯について語りました。確かに、立教ヌーベルバーグはじめ多くの映画監督は学生から映画を撮っていますが、そうではない(例えば社会人になってから映画に目覚めた)方もたくさんいます。
その意味で、必ずしも映画に学校の教育やサークルの環境が整わなければならない、とまで言い切る必要もないのだと思います。本気で映画監督を目指してバイト代を捧げるも良し、フリーターとして趣味で続けるも良し……つまるところ「商業映画」「職業映画監督」という枠に囚われさえしなければ、「本当に映画を撮りたければ、自分で仲間を集めて撮れば良い」という指摘は尤もで、テクノロジーの進化と共に映画のみならず、映画製作自体が大衆化されることは、そして、何ら商業的なしがらみに囚われる必要も無くなったということは、むしろ尊いことだと思います。
ちなみに会場として使用された渋谷HUMAXは、前年まで使用されたシネマGAGA!の名称が変わったものです。翌年の第22回(2010)も、同会場のレイトショー枠にてグランプリ上映会が行われました。その時のゲストは、『愛のむきだし』『ヤンヤン〜夏の思い出〜』等をプロデュースした河合真也です。

会場:北沢タウンホール
<ゲスト>
崔洋一、中村義洋、伊藤さとり
境宗久、杉井ギサブロー、野村辰寿
第22回では、アニメーションだけに特化した「東京学生アニメフェス!!」が開催されました。当日は上映に加え、絵コンテや作中で使用されたオブジェ、「あなたにとって学生映画とは?」というパネル展示も行われました。元々は本祭の一部門だったアニメーションを、「学生アニメーションの可能性を発信する」という趣旨のもと、あえて別イベントとして拡充した形でした(翌年以降、元の編成に戻る)。
ちなみにアカデミー賞や主要の映画祭でも、メインコンペの一部にアニメーションを組み込んだり、あるいは専門の部門を設置したり、といった形で対応の仕方を変えています。他方で、実写/アニメーションを明確に区別し——ストップモーションなどの中間作品はその都度議論し——どちらかを専門的に扱っている、という方針を採用している映画祭もあります。

会場:北沢タウンホール
出身:奥山由之
<ゲスト>
大森立嗣、田口トモロヲ、矢田部吉彦
新海誠、ヤマサキオサム
第23回になると、「ショート!ショート!ショート!」や「東京学生アニメフェス!!」といった特別上映会が無くなった代わりに、本祭とは別枠で、前代未聞の学生映画のオールナイト上映会が開催されました。

第15回グランプリ『鳥籠』(木下雄介)
第19回準グランプリ『スーパー大学生 片岡次郎』
第21回グランプリ『シュナイダー』(頃安祐良)
第22回準グランプリ『エコーズ』(唐澤弦志)
新宿バルト9の24時15分〜翌5時30分に実施されたオールナイト上映は、学生映画の上映会としては稀代の、異様なまでの熱気に包まれることになりました。上記の写真に見て取れるように、250席が全て埋まる繁盛ぶりでした。途中からは急遽、補助席を出して座る方までいたそうで、学生映画では考えられない動員です。
シネコンが学生で埋まるといった現象も前代未聞でしょうし、シネコンを借りた学生映画だけのオールナイトは未だかつて聞いたことがありません。条件的には日本初なのではないかと思っています。
当日は、会場のカフェスペースにて、各大学のフリーペーパーサークルの冊子が展示されました。オールナイト上映の休憩時間は外食もできず、だからといって暇潰しもありません。そこでフリーペーパーとは、なかなか機転の効いた発想だったと思います。
ちなみにその年の本祭には、まだ自主映画界隈に顔を出していた新海誠がいました。
元々、新海誠の映画監督としてのキャリアは、『ほしのこえ』(2002)を初上映した下北沢トリウッドからスタートしています。来年(2022)で『ほしのこえ』の上映から20年が経つので、新海誠特集2022が開催されるそうです。
以前にも触れましたが、新海誠のようなサブカル文化が日本全体を巻き込むムーブメントになることは、個人的にはとても良い傾向だと思っています。(2022年3月25日追記 それにしても黒沢清が乃木坂46のMVを撮るとは意外でした。かなり以前にも塚本晋也が紅白に出ましたし……他の業界でも古市憲寿がワイドショーに引っ張りだこで、箕輪啓介は出版業界とネット社会を股にかけて、という具合で、芸術であれ、言論であれ、日本はテクノロジーの変化に過剰適応するより、既存の支配的メディアとの上手く折り合いをつけてゆく、というあり方も、良し悪しは別にしてあるのかもしれません)。
同じ下北沢では2022年初頭、K2という新しいミニシアターが開館しています。北沢タウンホールを使用し始めた2006年以降、東学祭は15年以上に渡って下北沢の貸し会議室を活動の拠点としてきました。やはり下北沢は演劇・ライブハウスの印象が強いですが、ただでさえミニシアター文化が枯れつつある昨今、映画文化に寄り添う新たな発信地が生まれたことを、とても好ましく思います。
3.パーソナルメディアの活用
東学祭は、第18回(2006)頃から特に、ブログやツイッターなどの各種パーソナルメディアを積極的に活用するようになりました。
ちなみに、2006年という年は、ブログ媒体が最も円熟していた年だったといえるかもしれません。元を辿れば2004年は「ブログ元年」などとも呼ばれ、FC2ブログやAmebaブログなどがサービスを開始し、ブログの女王とも呼ばれた眞壁かをりさんや中川翔子さんがブームの火付け役となりました。さらに、2005年には「ブログ」が流行語大賞に選出され、国内だけで約1700万もの閲覧者で溢れました。日本は他国と比べてブログの「投稿数」が多い傾向にあり、2006年前半には日本語ブログの投稿数が世界最多に登ったそうです。
上記のような現状を加味して、総務省は2006年に「日本ブログ協会」を設立した訳ですが、少なくともホームページを見る限り、活動といった活動もないまま事業は終わっています。中途半端なクールジャパン戦略にも見て取れるように、官僚とパーソナルな文化との間には、大きな溝が存在してしまっているといえるでしょう。少し前には、あいちトリエンナーレ2019の「表現の不自由展・その後」中止騒動や、『宮本から君へ』(2019)助成金打ち切り騒動もありました。
これまで、日本はアニメ(ジャパニメーション)や漫画の分野で世界をリードし、映画文化でもアジアをリードする立場にありましたが、ヨーロッパを拠点とした近年の韓国映画、中国映画、香港映画の目覚ましい発展を目の当たりにすると、些か霞んで見えてきます。『パラサイト』『はちどり』といった国際的に評価を得た作品や、『愛の不時着』『イカゲーム』といった「Netflix」で大ブームを起こした作品が日本で生まれていない現状に対する国の認識には、甘いものがあると思います。
以前にも触れましたが、規模の大きい文化事業の財源の多くは、文化庁の助成金や公益財団の支援金によって賄われています。こと映画祭に関して言えば、応募料収入やチケット代収入がイベント規模と見合わず、何百にも及ぶ応募作品を審査するスタッフやゲスト、招待作品、審査員、会場などをブッキングするスタッフ、SNSやHP、プレスなどの広報戦略を行うスタッフ、といった具合で、膨大な人件費も掛かります。制作サイドもそれは然りで、監督、助監督、プロデューサー、カメラマン、編集、照明、録音、美術、装飾といったように、必要な人材には枚挙に暇がありません。
日本の映像産業を支える人材が、良い待遇に恵まれない中、近年ではアニメーション業界から優秀な人材が中国に流失しているといった現状もあります。また、世界で活躍する日本人監督の多くが、フランスなどの海外助成を頼りにしている現状もあります。以前も書いた通り、多くのケースで芸術=資本の図式が成り立ちます。一般的にアメリカは寄付が充実し、ヨーロッパでは公的援助の比重が大きいですが、日本の芸術分野はそのどちらも現状では不十分だと思います。三宅唱、山下敦弘、是枝裕和といった監督が外資系のNetflixと契約を結んだ事実にも大きなインパクトはありましたが、テレビ含む映像メディア全般は、SVODというグローバルな産業構造改革(イノベーション)の風に晒され、もはやその勢いを食い止めることができません。それはトヨタ然り、火力発電然り、マスコミ全般然り、昭和から日本文化の基幹を担ってきた産業全般に渡って、濃い暗雲が立ち込めています。
・独自ドメイン
2006年に東学祭が立ち上げた独自ドメインのブログは、以下のようなものでした。ドメイン名は、ずばり「blog.tougakusai.com」といったものですが、現在は偽サイトからファーミングされてしまっているので、閲覧することができません。

独自ドメインのブログで投稿された内容としては、映画祭の基本情報や定例会の告知、オススメ映画紹介や各種委員の活動日誌、といったものが主です。「FC2ブログ」や「Amebaブログ」といった、既存のブログではなく、独自ドメインに拘った理由は分かりません。
2009.11.13 Saturday
熱い思い
やっとこさ順番がまわってきました!
のわりには更新遅くなってごめんなさい!!
はじめましてこんにちは★
広報部のKと申します。(←なんか堅苦しい...
さてさて、機関紙も完成し、学園祭回りも佳境に入る今日この頃ですが、私のお仕事はひたーーすら
新人さん対応でございます。(←やっぱり堅苦しい...??
学園祭をめぐっているおかげか、このブログでのみんなの掛け声のおかげか、いろーーんな新人さん
から連絡が日々あり沢山の出逢いをさせていただいてます、感謝感謝です!(お、ちょっと柔和に!
気がつけば何でもありな大学生活が始まって早いもので7ヶ月ちょっと。
ほんっとーーーうに早いです。マッハで通り過ぎていった気がします。
堅苦しい校則と制服に縛り付けられた高校生活にお別れして飛びこんだキャンパスライフ、なんてフリ
ーダムなの大学生って!と思う同時に、下手したら空虚に過ぎてしまうんだなってすごく感じました
でも、
でも、
この東学祭で出会う人にからっぽな大学生活を送っている人はほとんどいないと思うんです。(これ過
言じゃないんですよ!?
参加団体の方々も、企画委員も、新人さんも、“映画”というひとつのロープにつながって、日々をきら
きらさせるべくも求め、考え、動いています。
今の自分達が生み出す映像、今の自分達でしか撮れない映像、
そんな大学生でしか撮れない作品を世に出していくお手伝いをさせていただけて、少なからずわたしは日
々を充実させて今を過ごしています
みんなもそうだよね
ねっ??
笑 上記は当時、新入生対応をしていたKさんによる活動日誌ですが、本人も書いている通り、極めて柔和な印象を受ける文体です。
「やっと回ってきた」という記述から、日誌を書くのは委員のローテーションだったことが分かります。さらに、「いろーーんな新人さんから連絡が日々あり沢山の出逢いをさせていただいてます」といったポジティブな記述からも、このブログ発信が新入生を歓迎する、イメージ戦略的な側面があったことも分かります。そして何より、「からっぽな大学生活を送っている人はほとんどいないと思うんです。(これ過言じゃないんですよ!?)」といった記述には、思わずやきもちを焼きたくなってしまうくらい、内輪関係に対する過剰な楽天性が伺えます。
つまり、その頃の東学祭には、平たく言えばキラキラした機運が存在していたのでしょう(田舎者の私も東学祭に入る前、「東京」「映画」「祭」と聞いただけで、忽ちそういったイメージを抱きました)。そのため当時のブログは、必ずしも「活動を紹介する」といった目的意識に留まず、今ではInstagramのストーリーを通じて仲間同士の絆を確かめ合うような、こう言って良ければ自助作用として働いていた節があるのだと思います。
・ホムペ
2008年になると、東学祭はケータイブログを始めます。
以下の画面を見て懐かしく思う人がいるかもしれませんが、これはゼロ年代後半に中高生で流行っていた、いわゆる「ホムペ」というやつです。

ホムペとは、一般的なホームページの中でも、誰でもガラケーを使って簡単に作成できる点に特徴があります。用途は、個人のブログや二次創作、友達との交流、といったように様々でした。
サイト内は「自己紹介」「リアルタイム」「日記」「写真ライブラリ」「BBS」「リンク」といった基本的な要素で構成されています。テンプレートさえあれば1時間程度で完成できたそうで、例えば「自己紹介」はサービス側の質問に答えるだけでしたし、当時流行していた前略プロフィールのリンクを貼る人も多かったそうです。ちなみに、「リアルタイム」とは、現在でいうツイートのようなシステムで「BBS(=Bulletin Board System)」は掲示板のようなシステムです。

当時は、nano-ナノ-やフォレストページ、@peps!といった様々ホムペ専用サイトがありましたが、東学祭はxmbs.jpといったドメインからも分かる通り、Mobile Space(モバスペ)というサイトを使用していました。
もっともホムペは、スマホの普及やSNSの進展と共に影を潜め、震災とアラブの春があった2011年には、ほとんどオワコン化します(モバスペのサービスは2020年に終了)。東学祭のホムペも、メインのブログと比べて投稿数は少なく、トピ(=トピック)も数件しかないことを考えると、あまり活発だった訳ではなかったみたいです。
・Amebaブログ
2006年から運営していた独自ドメインのブログは、2009年の12月20日をもって終了しています。最後の投稿は、「ブログお引っ越しのお知らせ」と題された内容ですが、コメント欄は猥褻なリプライで荒らされてしまっていたので、恐らくそれが原因だと思います。
東学祭のブログは2009年、Abemaブログに引っ越します。ちなみに私も、ある独自ドメインのHPを管理しているのですが、サーバー費用やWP(ワードプレス)の管理は一筋縄ではいきませんし、少しでも情報が漏れれば簡単に荒らされてしまう危険性があります。この記事を掲載しているnoteもそうですが、既存のWeb媒体は他の利用者との間口も広いですし、HTMLの入力やサーバー管理の手間も省けるので、無難に便利です。

上記に見て取れるように、Abemaブログではサイトの模様替えができたので、その年ごとにサイトカラーが異なっています。今もサイトは生々しく残っているので内容の細い言及は避けますが、とりわけ私が気になったのは「いつまでも笑顔で。」と題された記事でした。
いつでも笑顔で。
2011-03-12
テーマ:blog
こんばんは。
昨日はとても大きな地震がありましたね。皆さん、ご無事でしょうか??
関東はもとい、東北地方では想像を遥かに超える被害の大きさが出ていて、
ニュースを見るたびに心が沈んでいってしまいます。
これ以上の被害が出ないこと、心からただただ祈るばかりです。
私自身、地震により電車が動かないため出先から帰ることが出来ず、新宿の避難所で一晩を越しました。
何度も地震速報のアラームが鳴り不安でありながらも、助け合う人々の姿に勇気をもらいしっかりしなくては!!!
という気持ちになりました。
本当に今このときも、被災した誰かのために働いてくれているという人が沢山いること、
念頭に置いて過ごさなくてはいけないですね。
今日はMCオーディション、明日は会議も部署の会議も急遽中止となり、家にいる時間が長くなりました。
気分が沈みがちになりますが、こんな時こそ元気に笑顔でいなくては、と思います。
今、この時に載せるのも不謹慎になるかもしれないのですが、一本おすすめの映画を紹介します。
纐纈あや監督「祝の島」
山口県上関町祝島の原発をテーマにしたドキュメンタリー映画なんですが、人々の姿の撮り方が上手いなって思いました。
何より、「一方的な原発反対!」ではなく平等に原発側の人々も映しているため、とてもためになります。
特にひねりがある訳でもなく、はらはらどきどきする作品でもないですが、もっとも人にとっての特別な、
守らなくてはいけないものとは何かを考えさせられる一本です。
福島県の原子力発電所の被ばく情報が流れている今、無関心ではいられない現実だと受け止めて、
ぜひともオススメします。
(中略)
1人でも多くの命が救われますように
1日でも早く被災者の方々が安心して休めますように
心から祈ります。
広報部 S冒頭をお読みいただければ分かると思いますが、この記事は東日本大震災の翌日(2011年3月12日)に投稿されたものでした。
福島出身の私は被災当時、地元の小学校にいました。あの日が金曜日であったことを鮮明に覚えていますが、あの翌日には会議とMCオーディションが控えていたという事実は、10年後に代表となる私個人にとって、時間の重みを感じさせてくれる感慨深いものでした。
10年前から東学祭は、今と変わらず土曜に下北沢だったのです。

ちなみに東学祭は、2010年に12月からTwitterを始めています。
震災直前には、「予選が終わった」という内容のブログを投稿した旨がツイートされていました。恐らく東学祭は昔も、入選作品を決めるこの期間に最も時間を割いていたので、もしかすると震災時は一息ついていたタイミングだったのかもしれません。
東学祭は、かれこれ15年以上は下北沢の貸し会議室で会議を行なっています。委員の大半は都内在住なので、震災の実被害という意味ではそれほど甚大ではなかったのかもしれません。ただ、間接的な被害はあるにはあったそうで、第23回(2011)に上映素材として使う予定だったHDcamが、宮城県にあるソニーのテープ工場が被災したことによって入手困難になってしまったそうです。震災直後こそHDcamのラージテープを手に入れるのは難しかったそうですが、何とか本祭の5月には調達できたそうです。
ちなみに、HDcamの生産は2011年7月下旬に一部再開していますが、その後は需要の減退により、2014年10月に販売が終了しています。
「いつまでも笑顔で。」(2011年3月12日)の記事で紹介されていた『祝の島』で登場する、山口県上関町の「上関原発建設計画」を巡る村民と四国電力の睨み合いは、今なお続いています。1982年の計画発表から、来年(2022)で30年を迎えます。
「海と山さえあれば生きていける。」
といった祝島の人々の主張は、今の世の中でどこまで共鳴するでしょうか? 2015年にはサミットでSDGsが制定され、同年にはパリ協定が採択されています。2021年にアメリカがパリ協定に復帰して以降、火力発電中心の日本のエネルギー問題や、EVで遅れを取る自動車産業に度々視線が注がれるようになってきました。国内におけるカーボンニュートラルの実現には、「原発再稼働」が大きな焦点となっています。
【拙記事紹介】
再三、拙記事を紹介して申し訳ありませんが、以下は今年(2021)の年始に私が原発周辺を巡ったレポートです。南相馬市は日本で唯一、「脱原発都市宣言」をした自治体であるのと同時に、津波で流された荒涼とした大地には「太陽光」「(洋上)風力発電」「水素製造施設」といった新たなエネルギー拠点が生まれていました。
4.日本学生映画祭

会場:北沢タウンホール
出身:三原慧悟 、山戸結希、中川龍太郎
<ゲスト>
井土紀州、石井裕也、瀬々敬久
本郷みつる、山村浩二、神山健治
第24回になると、東学祭は中川龍太郎(『わたしは光をにぎっている』,『やがて海へと届く』)、三原慧悟(=三原JAPAN、台湾で人気を誇るYouTuber)といった、今も「若手」として活躍する先進的なクリエイターを輩出するようになります。第23回に入選した奥山由之も、つい先日に広瀬すず10周年の記念写真集を担当し、今や写真展があれば行列が生まれるほどの人気クリエイターです。
特に山戸結希(『溺れるナイフ』『ホットギミック』)が審査員特別賞を受賞した『あの娘が海辺で踊ってる』(2012)は、ほとんど事件とも呼べるセンセーショナルなものでした。
当日は審査員を務め、後に『溺れるナイフ』の脚本を手がける井土紀州は、上映後のトークで他の作品を扱う暇もなく作品を褒めちぎり、浴衣を着て登壇していた山戸監督は感極まって涙を流しました。『映画はどこにある インディペンデント映画の新しい波』(2014、フィルムアート社)によるインタビューで山戸監督は、当時のことを「後にも先にも、あんなに人に褒められることはない」と振り返っています。ちなみに東学祭と関わりが深い井土監督自身も、第5回『第一アパート』を崔洋一に激賞された過去を持ちます。
哲学科専攻の女子大生が見よう見まねで撮り上げた、撮影や音声のままならない処女作はその後、東学祭に来ていたポレポレ東中野の小原治からの誘いを受け、同館のレイトショーで上映されました。これが記録的なヒットを飛ばし、山戸監督は怒涛の勢いで自主映画街道を駆け抜けることになります。
映画を専門的に学び、技術力に自信のある一部の学生からは「なんであんなものが賞を取るんだ!」というリアクションもあったそうです。ただ、まさにこの作品にこそ、東学祭が探し求めていた脱映画的な初期衝動があり、東学祭が起こしたかったムーブメントがあるのだという論調は、今なお一つの伝説として語り継がれています。
ちなみにその後、山戸監督は自身がプロデュースした『21世紀の女の子』(2018)などで、「若い」「女性監督」のメルクマール的な存在になります。制服少女やダンスなどを扱うフェミニンなテーマ性のみならず、山戸監督自身から漂い、言葉として吐き出されるメランコリックかつ風変わりな知的ポップさとでも呼べるものには、確かな時代性が宿っていると思います。それは「時代的な」ものに最も敏感な評論家の1人ともいって良い中森明夫から見染められている事実や、逆にそうした商業的な新奇さを嫌う蓮實重彦からボロクソに批判されている事実からも象徴的です。

話を戻すと、第24回(2012)から東学祭は、東京国際映画祭(TIFF)を後援に迎えています。
TIFFは国内で唯一、国際映画製作者連盟の公認を受けている、いわば日本の顔を担っている国際映画祭です。2012年頃は「グリーンカーペットクラブ(GCC)」を創設し、地球のサステナビリティを推進するイベントしての方針を強めていました。実は1985年設立と歴史は浅く、隔年ではなく毎年開催となった1991年以降は、東学祭と同じ開催の回数を重ねていたのでした(2018年に東学祭が延期したことでズレる)。
TIFFには、学生応援団というオフィシャルサポーターがいます。学生応援団は今も、学生のフットワークを生かして映画祭や映画の魅力を発信していますが、元々は第24回の東学祭委員5人らが参加したことがきっかけで誕生した組織でした。
TIFFのサポートを得た東学祭は、満を辞して、学生映画イベントの集大成ともいえる、日本学生映画祭(日学祭)の開催にこぎつけました。

日時:2011年7月9日(土)
会場:新宿バルト9
第2回
日時:2012年8月26日(日)
会場:お台場シネマメディアージュ
日学祭とは、東京学生映画祭、京都国際学生映画祭、TOHOシネマズ学生映画祭の3つの映画祭(=三大学生映画祭)のグランプリ作品が一同に会した、いわば日本の学生映画を総合した一大映画祭でした。
京都国際学生映画祭、TOHOシネマズ学生映画祭はいずれも学生が運営している学生映画祭ですが、東学祭とは異なるのは、運営母体に企業が付いている点です。京都国際は「海外の学生映画」も募集対象としている点、TOHOはジャンル映画よりの「PV色の強い短編作品」を打ち出している点に特徴があります。

第1回日学祭は、新宿のバルト9にて再びオールナイトで開催されました。
オールナイトという形式は、会場費が抑えられる点、学生が深夜に集まりやすい点で大きなメリットがあるのだと思います。第1回では横浜聡子、瀬々敬久をゲストに迎え、各映画祭のグランプリ・準グランプリ作品が上映されました。

会場:北沢タウンホール
出身:三原慧悟、川和田恵真
<ゲスト>
君塚良一、瀧本智行、松江哲明
大山慶、高木淳、保田克史
松下洋子、熊澤尚人、斎藤工
東学祭の話に戻すと、第25回は再びTIFFとコラボを果たし、『学生×映画=∽ ~学生映画がつなぐ未来~』と題したイベントを開催しました。このイベントは、両映画祭の25周年を記念したもので、映画祭や学生映画の未来について考えるシンポジウムとなりました。

会場:六本木アカデミーヒルズ49
会場は、TIFF開催期間中の六本木アカデミーヒルズで、当日は第14回のグランプリ作品『文金高島田二丁目』の上映に加え、監督を務めた小泉徳宏も登壇しました。

当日は、歴代のチラシやポスター等のパネル展示が行われた他、来場者全員に「25周年記念冊子」が配られました。
冊子では、東学祭の「25年間の歩み」を振り返ると共に、創設時のOB・OGのインタビュー企画や、青山真治、中村義洋、井土紀州、小泉徳宏、石川北二、といった出身監督から寄せられたコメントの紹介もありました。学生向けのアンケート結果も盛り込まれ、「好きな映画・俳優」「映画を観る頻度」といった各項目のアンケートには、興味深いものがありました。
私はここにきて、初めて東学祭に歴史としての重みが宿ってきたような印象を受けました。
1988年に第1回が開催された当時の学生は、今や50代半ばです。出身監督も今やキャリアで中堅の位置を占め、TIFFに学生として関わる側ではなく、もはやゲストとして招待される側になっているのです。

第24回の話に戻りますが、東学祭はTIFFのみならず、東京フィルメックスとのコラボも果たしています。
東京フィルメックスは2000年に創立された、アジアを中心に独創的な新人作家の作品を紹介する国際映画祭です。近年はTIFFと近接している印象もありますが、TIFFと比べてエスニックな作家性が強いラインナップが多く、中国や台湾、韓国をはじめ、イラン・イスラエルなどの中東作品も多数紹介しています。過去には『ブリスフリー・ユアーズ』(アピチャッポン)、『息もできない』(ヤン・イクチュン)、『愛のむきだし』(園子温)、『ふたりの人魚』(ロゥ・イエ)、『嘆きのピエタ』(キム・ギドク)といった話題作を先駆けて紹介してきました。

東学祭と東京フィルメックスの主なコラボ内容は、東学祭の委員と学生監督が、1つの賞である「学生審査員賞」の選考を務めるというものです。
参考までに、歴代の学生審査員賞を以下に列挙させていただきます。学生審査員賞は、コンペティション部門の通常の審査とは別に、若い観客層からの視点を取り入れたい、といった趣旨で創設された賞でした。
第12回:『東京プレイボーイクラブ』奥田庸介
第13回:『あたしは世界なんかじゃないから』高橋泉
第14回:『トランジット』ハンナ・エスピア
第15回:『彼女のそばで』アサフ・コルマン
第16回:『タルロ』ペマツェテン
第17回:『普通の家族』エドゥアルド・ロイ・Jr
第18回:『泳ぎすぎた夜』 五十嵐耕平
第19回:『ロングデイズ ・ジャーニー この夜の涯てへ』 ビー・ガン
第20回:『昨夜、あなたが微笑んでいた』 ニアン・カヴィッチ
第21回:『由宇子の天秤』春本雄二郎
第22回:『見上げた空に何が見える?』アレクサンドレ・コべリゼ こうして見ると、日本人監督が多い印象を受けます。『ロングデイズ ・ジャーニー この夜の涯てへ』や『由宇子の天秤』といった、近年の話題作もありますね。
日本以外のアジア映画は、90年代以降から急速にクオリティーを上げている印象を受けます。最新鋭のアジア映画に触れる機会は、東学祭の委員や学生監督にとってグローバルな視野を養える、代え難い経験になったのだと思います。

日時:2013年10月25日
会場:TOHOシネマズ 六本木ヒルズ
日学祭の話に戻すと、第3回からはTIFFの全面的な協力を得て、TOHOシネマズ日比谷やTOHOシネマズ六本木ヒルズといったシネコンで、TIFFの特別上映枠として開催されるようになります。学生が運営する映画祭が、国際映画製作者連盟公認の映画祭の一環として、シネコンの大スクリーンで行われるのは、世界的に見ても稀な光景です。

日時:2014年10月26日
会場:TOHOシネマズ日本橋 スクリーン6
第5回
日時:2015年10月23日
会場:新宿バルト9 SCREEN 2
第4回もTIFFの一環として、新築されたばかりのTOHOシネマズ日本橋で開催されました。TOHOシネマズ日本橋は、プレミアボックスシートやドルビーアトモスなどを都内で始めて導入した、最新鋭のシネコンでした。
第5回では新宿バルト9での開催に加え、京都の京都文化博物館での追加上映も行われました。日学祭の上映作品には、もちろん東京以外の学生映画もあったので、関西圏に上映会の幅が広がったことは意義深かったと思います。
また、第5回の開催に際し、故・大林宣彦から素敵なメッセージも寄せられていました。
上記の動画をご覧いただければ分かると思いますが、やはり大林監督らしい老練な喋り口です。「すべての作品が印象に残っている」という言葉を、大林監督が亡くなった今になって振り返ってみると、どこか隔世の感が漂っています。
もし日学祭、ひいては東学祭のことを少しでも胸に留めて旅立たれたのであれば、非常に嬉しく思います。大林監督が残したインディーズ映画の精神は、他のどの監督よりも濃く、現在の学生映画に脈々と受け継がれていると思っています。

会場:TOHOシネマズ六本木ヒルズ
最後の開催となった第6回日学祭は、『PUI PUI モルカー』でもお馴染み見里朝希の『あたしだけをみて』含む、数本の学生映画が上映されました。当日はゲストとして大友啓史と、放送作家/映画活動家で東学祭OBでもある松崎まことを迎えし、トークショーが開催されました。

会場:北沢タウンホール
<ゲスト>
小林啓一、橋口亮輔、横浜聡子
FROGMAN、水江未来、赤尾でこ
東学祭に話を戻すと、第26回はさらに活動の幅を広げ、広告会社電通ともコラボしています。
当時、電通は大学サークル専用のコミュニケーションアプリ「CircleApp」をリリースし、全国の大学生とコラボしていました。東学祭とのコラボもその一環で、『予告編ムービーアワード』と題された実写部門8作品による、予告編映像のコンテストが行われました。コンテストでは、CircleAppのユーザーが「最も本編を観たくなったのはどれか?」という視点で投票を行い、最優秀賞が決定されました。
ちなみに、学生映画祭畑の人が必ずしも全員、実写映画やアニメーションの製作を希望している訳ではありません。アカデミカルではない広告映像やPVの製作が大学で行われることは少ないので、専門学校が多い印象ではありますが、それでもテレビ局や広告代理店の製作部門には、未だに根強い人気があります。
もっとも、そういった商業畑の業界人の中にも、優れた映画を世に送りたいと考えている人はたくさんいますが、以前にも書いたように、日本のメジャーは「芸術的価値のある映画作り」よりも「最大多数を喜ばせる映画作り」に勤しむ傾向が強くあります。そのため、実感として大抵の学生監督は過度な商業映画を毛嫌いし、インディーズに立て籠ってしまう傾向にあります。後にも詳しく書きますが、その産業構造の欠陥にこそ、学生映画ひいては自主映画全体の限界が存在していると思っています。

また同年、文化庁が主催しているndjc(若手映画作家育成プロジェクト)とのコラボも実現しました。
ndjcは、映像産業振興機構(VIPO)が文化庁から委託を受け、2006年度から開始された映像人材育成事業です。過去には中野量太、岨手由貴子、池田暁といった監督らが参加し、これからの映画界を担う若手育成に取り組んでいます。
第26回で入選を果たした監督には、ndjcへの参加推薦権が与えられました。ただでさえ自主映画の製作には、容易にはペイできない財源が必要なので、文化庁からの助成は大きなインセンティブになったと思います。

会場:新宿スタジオアルタ
第26回終了後は、シネ・フェスタ新宿2014とのコラボも実現し、その年の観客賞を受賞した『あがきのうた』が上映されました。当日は、監督を努めた中村有里と映画評論家・中井圭を交えたトークショーも行われました。
シネ・フェスタ新宿は、新宿区が毎年開催している新宿クリエイターズフェスタの一環として行われたイベントです。ただ、2013年から2015年までの短命で終わってしまったので、継続的なコラボとはなりませんでした。

会場:北沢タウンホール
<ゲスト>
大林宣彦、萩生田宏治、古館寛治
片渕須直、ひらのりょう、ヴィヴィアン佐藤
第27回になると、東学祭は映画レビューサイトFilmarksとコラボします。当日はFilmarks賞が設けられ、副賞としてオンライン上映会への出場券が付与されました。
運営会社つみきによると、Filmarksは2012年にサービスを開始し、2015年2月で累計レビュー数が500万件(1日平均約2万件)を突破しました。同年6月にはWebマガジンFILMAGAをリリースし、ますます勢いを強めていました。

このコラボにより、以降の東学祭作品はFilmarksに登録されるようになっています。Filmarksがメジャー映画だけではなく、東学祭のようなマイナー映画のレビューも可能にした点は、大変に意義深いと思います。
ちなみにその頃から、Filmarks以外にもAmazonレビューや映画.com、Yahoo!!といったサイトで映画レビューが活発になっていて、若者が「レビューで映画を観に行くか決める」といったことが常態化し始めました。それに伴いFilmarksは、2017年にドラマ、2020年にアニメーションのレビューも開始し、総合的な映像コンテンツレビューサイトへと変化しています。

会場:北沢タウンホール
<ゲスト>
池田史嗣、清水崇、山戸結希
新井陽次郎、植草航、 氷川竜介
第28回は、恐らく東学祭にとって初となる横浜(ブリリアショートショートシアター)、大阪(シアターセブン)といった場所での展開上映が行われました。
ほとんど都内の特権と化している映画祭が、いかにして地方を行脚するか、あるいは地方開催の映画祭がいかにして都市へ上るか、といった視点はとても重要だと思います。80年代の国際映画祭ブーム時には潤っていた地方自治体の多くは、今や深刻な過疎化によって財政危機に陥っています。自治体から十分な助成金を得られなくなった山形国際ドキュメンタリー映画祭やゆうばり国際ファンタスティック映画祭といった映画祭は、今や任意のNPO法人としての不安定な運営を続けています。(残念ながらアジアフォーカス・福岡国際映画祭は2020年に閉幕します)。
私はこういった課題を解決するのが、サブスクリプション(SVOD)における配信になってくると考えています。その点については、後ほど詳しく掘り下げます。
第29回(2015)-第32回(2021)
上記のように、コミュニティを拡大した第17回〜第28回の東学祭は、私が見る限り、東学祭の歴史で最も活発だった時期に該当すると思います。前述したようにキラキラした機運が存在していて、良好な運営がなされていました。
第27回の東学祭は、映画の応募対象を「都内の大学」から「全国の大学・専門学校」に拡大し、作品応募を「持ち込み」だけではなく「郵送」でも受け付けるようになります。最初こそ、内輪だけの参加団体制だった東学祭も、気づけば一定以上の知名度を得て、全国の学校を対象にした公募の映画祭になったのです。
以前の章で、東学祭は「下北沢で5・6月に開催される、毎年恒例の学生映画祭」としての統一されたイメージを確立した、と記しました。東学祭の規模がここまで大きくなった背景には、何よりも第18回以後、毎年、特定の期間、特定の場所(=ハコ)で行われた経緯があり、それはある意味、映画祭が発展するための初歩的なステップでした。

東学祭は、これまでams西武や大学のホール、渋谷の青山ウィメンズプラザやパナソニックホールなどの会場を転々としてきましたが、第18回から第28回までの約12年間に渡り、下北沢の北沢タウンホールで5・6月に開催されています。
5・6月であったタイミングの理由は様々ですが、例えばその時期に開催すると、募集作品の中核を占める大学の卒業制作を取り込める、といった点が一番大きいでしょう。また「夏休みは学生の駆動率が低い」「9月開催のPFFの先鞭を付けたい」といった、東学祭ならでは二次的な理由も存在してきます。
通常、区営ホールの貸し館は抽選になることが多く、一学生のサークルが継続して毎年、同じ時期(しかも土日連続で)に借りることは極めて困難でした。それに加え、北沢タウンホールは立地も良く、使用料も安価の人気の施設で、年間を通じてほとんど100%の稼働率を誇る「日本一忙しいホール」として知られていました。
ではなぜ、東学祭が北沢タウンホールを継続して借りることができたかというと、端的にいえば、指定管理会社A社の厚意によるものでした。
指定管理会社とは、国や自治体が保有する施設を、民間業者に委託する制度のことです(世田谷区では2006年から採用)。詳しい経緯は定かではありませんが、OBによるとA社は「毎年継続して開催できるイベント」を探していて、学生イベントとしては規模の大きく、社会との関わりも大きかった東学祭に声を掛けたそうです。細かい手続きの話をすると、会場費(通常であれば1日16万程)が全額免除となる代わりに、北沢タウンホールによる「共催」というクレジットが付されることになりました。
公的機関ではなく、一企業ないし個人間のやり取りおいて、大きな会場を無償で借り入れることができたという事実は、民営化における1つのパーソナルな恩恵を示しているようにも思えます。ただ、逆に捉えてみると、そこには「大学生の一サークルが公的施設を無償で借りられる」というアンフェアな図式があったことも事実です。

北沢タウンホールは、収容人数が456人と非常に多く、ロビーも広いため、交流スペースを確保することも可能でした。そして、会議室を借りれば同一施設内で懇親会(レセプション)を行うことができるという点も、通常の映画館や大学のホールにはない強みとなりました。
ただOBによると、ホールのプロジェクターは、映画上映に耐えうるクオリティとはとても言い難かったので、外部からプロジェクター(映写機)を持ち込む必要があったそうです。その上で、シネマカメラなどを扱っている某社に協賛という形で関わり、安価で機材を提供してもらうという方策が執られました。これまでの東学祭は映写を専門に扱う部署がなかったので、新たに上映部が設けられ、学生が機材オペレーションを統括するようになりました。
以上のような体制で東学祭は、その後10年に渡って「下北沢で5・6月に開催される、毎年恒例の学生映画祭」として運営を継続することができたのです。会場に伴って毎週の会議も下北沢で行われ、ブログでは「下北沢カレー巡り」といった下北沢関連記事も度々更新されるようになりました。それに加え「下北沢新聞」や「下北沢南口商店街」といった、地域的な団体との連携も強めました。
そもそも映画祭の多くは、開催される場所の名を冠することがほとんどです。例えば、カンヌ国際映画祭であれば「毎年カンヌで開催される恒例イベント」として世界的に根付いている節がありますし、スイスのロカルノ映画祭では、「ピアッツァ・グランデ」と呼ばれる場所での野外上映が、地域の醍醐味となっています。映画祭は、他の映画祭とのバッティングを避けて、毎年、特定の期間、特定の場所(=ハコ)で開催されることに大義があり、発展的な映画コミュニティを形成するための初歩ステップといえるのです。
つまり東学祭は、毎年特定の期間、下北沢の公営施設から共催クレジットを獲得し、しかも無償で使用することができたからこそ、東学祭=下北沢というイメージをもって、コミュニティを拡大することができたのでした。会場や資金面、そして何よりも信用の面で懸念がなくなった東学祭は、盤石の体制で運営を継続することができました。
つながり失い、延期へ

会場:品川区荏原文化センター
<ゲスト>
佐々部清、今泉力哉、山戸結希
鈴木伸一、水鳥精二、水江未来
しかし、第29回以降の東学祭は、映画祭としての基盤を揺るがしかねない、様々なつながりを失うことになります。
指定管理会社A社は、2017年に北沢タウンホールの担当を解かれ、代わりに「世田谷サービス公社」という会社が管理するようになりました。世田谷サービス公社は、今も「三茶しゃれなあどホール」「梅丘パークホール」「烏山区民会館」「成城ホール(砧区民会館)」「玉川せせらぎホール(玉川区民会館)」といった施設の指定管理会社になっています。
世田谷サービス公社は、元々世田谷区が設立した団体ですが、1985年からは株式会社になっています。設立から一貫して、世田谷区の「地域社会の発展と区民福祉の向上に寄与する」ことを目的に事業を行っている半公的機関で、現在も約9割の株と議決権を世田谷区が保有しています。
HPによると、現在の世田谷サービス公社は以下の事業を行っています。
拡大、多様化する行政ニーズへの対応や、行政コストの削減、規制緩和など社会経済環境が
激変し続ける中で、当社は世田谷という地域社会の発展と区民福祉の向上をめざし、公と民
の隙間を埋める企業として業務を展開しています。
(株式会社 世田谷サービス公社) 私は、特に「行政コストの削減」という部分に着目しました。
恐らく、世田谷サービス公社が、北沢タウンホールの指定管理会社となった2017年、世田谷区の財政は悪化していたのだと思われます。つまり、民間企業であるA社の代わりに、半民間企業である世田谷サービス公社が指定会社となった背景には、財政を立て直したい世田谷区の意向をできるだけ反映させるための施策があったのです。
一民営企業ないし個人間のパーソナルな厚意によって成り立っていた東学祭にとってそれは、——例え区全体の利益に資する目的であっても——クリティカルな問題でした。A社とのつながりを失った東学祭は、必然的に北沢タウンホールによる「無償貸出」と「共催クレジット」の特典が解消されることになってしまいました。
一面的に見ると、この悲劇は「東学祭が公的機関に見放された」ことになりますが、他方で「大学生の一サークルが公的施設を無償で借りられるアンフェアな図式」が解除されたとも捉えられます。
以上の経緯で、東学祭は別の会場を借りる必要がありました。会場費として数十万円を積み立てなければならず、おまけに一身上の事情によってシネマカメラを扱う某社からの協賛も失い、上映機材料十数万も新たに発生することになってしまいました。

第29回は、品川区荏原文化センターという品川の中心から離れた会場で開催されました。
当初は、例年と同じ北沢タウンホールでの開催を目指し、レンタル料を支払った上での「抽選」の手続きを踏んだそうです。北沢タウンホールは「日本一忙しい」とも言わしめるほど人気の施設であることは前記しましたが、特に東学祭が狙っていた土日連続の抽選倍率は相当に高く、見事にハズれました。ちなみに、東学祭は規模的に「土日開催」が望ましく、「平日午後開催」では大学の授業や集客の兼ね合いから、厳しいものがありました。
結果的に第29回の開催時期は、5・6月ではなく8月24(木)~26(土)にまでズレ込みました。多くの映画館、ホールの貸し館は「半年前の月始め」の予約が多く、複数の抽選を同時に申し込むとキャンセル料が発生してしまうので、開催時期をズラすしかなかったのです。
ただ、8月末ではお盆の時期とも近く、大抵の大学生は夏休み真っ只中でした。しかも、例年9月中旬から実施されるPFFのラインナップも既に公開されていて、「東学祭は別にいいや」といった事態を招きかねないPFFの前哨戦のようなテイストにもなりかねませんでした。さらに、これは内輪の反省点で、記事に書くのも褒められたことではないのですが、その年のPFF観客賞を受賞してスカラシップの挑戦権を獲得し、ベルリン国際映画祭・フォーラム部門でも史上最年少で招待された稀代の学生映画『あみこ』(山中瑶子)を一次セレクションで取り零してしまうという、極めてお粗末なセレクションの問題も露呈してしまいました。
以上の経緯から、第29回は組織内課題に加え、勝手の違う会場に翻弄される形で、内容的にも集客的にも半端に終わってしまいました。これまでの積立金をほとんど使い切った挙句、いつ会場や予算を確保できるか分からない、映画祭として有るまじき不安定な状態が続くようになりました。「毎年、特定の期間、特定の場所(=ハコ)で開催される」アイデンティティを失うだけで、こうも簡単に映画祭は露頭に迷うのです。
東学祭は会場以外にも、他の様々なつながりを矢継ぎ早に失います。
まずは、定例会の廃止です。東学祭は都内の大学から「全国の大学・専門学校」に募集規模を拡大したことで、私書箱などを活用した「郵送」で作品応募を受け付けるようになりました。その結果、作品の持ち込む場としての定例会の意義が無くなり、都内近郊の大学生しか参加できないアンフェアさが浮き立ってしまう事情からも、廃止を余儀なくされました。月に1回、都内の映画サークルが一堂に会し、情報を交換し合う学生のつながりがなくなったのです。
次に、セレクションのつながりも失いました。
その頃には東学祭は、VHS、DVD、Blu-rayといった家庭用の規格で作品を募るようになり、第29回以降はディスクでの応募が基本となったので、全ての作品をリッピング、データ化することができました。そのことによって、予備審査は上映会での視聴ではなく、オンラインスクリーナーを用いた在宅審査での視聴へ切り替わりました。OB・OG、出身監督からはテキストでコメントを貰うようになり、これまで直接的に意見を募る場、交流を促進する場として機能していたセレクションのつながりも、なくなってしまいました。

ちなみに東学祭は、第30回でDVD 、Blu-rayか、オンライン・スクリーナー(Vimeo、YouTube、Google Driveなど)での応募受付に変更し、コロナ禍の第31回では、オンライン・スクリーナーの比重が大きくなりました。私が代表を務めた第32回ではオンラインスクリーナーでの応募を原則とし、セレクションも加速度的にオンライン化が進みました。
まとめると東学祭は、第28回、第29回あたりの僅か一年至りで、これまでのコミュニティを形作ってきた「下北沢」「5・6月開催」「定例会」「セレクション」といった各つながりのファクターを、一斉に失ってしまったのです。
財源も底を尽きかけ、諸々が半端に終わってしまった第29回に希望を見出せなかった委員の多くは、続々と辞めていきました。気が付けばブログの更新も止まり、日学祭の運営や企業とのコラボも引き継がれなくなってしまいました。
そして迎える30周年、いよいよ東学祭は存亡の危機に立たされます。

平成 30 年 4 月 14 日
第30回東京学生映画祭の延期のお知らせとお詫び
私たち東京学生映画祭は皆様から多くのご協力を賜り、これまで29回の映画祭を開催し
て参りました。その中で、幸運にも学生の豊かな才能に巡り会えることもございました。
おこがましくも、「東学祭」の名で学生映画製作者たちの目標の1つになれているのでは
ないかと思っております。
しかしながら、第29回東学祭は前年度まで使用させていただいていた会場が変更になっ
たことも影響し、収益面で非常に苦労することとなりました。学生のみで運営を行ってい
る私たちにとって、現時点での資金では今年度中の第30回東学祭の開催が難しい状況で
ございます。そこで、年度内の第30回東京学生映画祭開催を見送らせていただく次第と
なりました。応募をお考えになっていた学生の皆様、開催を楽しみにしてくださっていた
皆様のご期待に応えられない形となってしまったこと、深くお詫び申し上げます。
近年、私たちは学生映画を取り巻く環境が大きく変わりつつあると強く感じております。
また、これまで長く東学祭を見守り続けてくださっている方々より運営について様々なご
助言を賜りました。その中で東学祭がどうあるべきか、これまで以上に東学祭を成長させ
るにはどうしたら良いかを私たちなりに考えた末の決断でございます。
第30回東京学生映画祭につきましては、来年度2019年 5 月頃の開催を予定しており
ます。それまでに、定期的な上映会などといった新たな企画に挑戦していきたいと考えて
おります。何卒ご理解、ご了承のほどお願い申し上げます。
東京学生映画祭企画委員会学生映画のハブを目指して
ついに延期の判断を下した東学祭は、30回目の節目を目指し、抜本的に組織を変えていきます。
ひとえに延期といっても、上級生にとって学生でいられる時間は有限です。残った委員は、何とか学生である内に映画祭を形にしようと奔走しました。
延期コメントにもある通り、学生映画を取り巻く環境は目まぐるしく変わっています。それには、映画インフラのデジタル化、映画学校の乱立、ミニシアターの衰退、シネコン化といった要因が絡んでくることは、これまでの章で説明してきた通りです。
そういった中で東学祭は、今一度学生映画のハブとしての役割を再定義し、前に進み始めます。
・ココガクナイト

第30回東学祭は与えられた1年の猶予を使って、2つ実験的な企画を立ち上げました。
まず1つ目が、ココガクナイトです。
ココガクナイトとは、吉祥寺で2017年10月に開館したミニシアター・ココマルシアター(ココロヲ・動かす・映画館◯)を拠点に東学祭の学生映画を紹介する、定期的な上映イベントでした。

「月に1度 学生映画を語り合う夜」と副題を付けられたこの企画の趣旨は、その名の通り月に1度、平日夜に東学祭の作品を紹介するというものでした。年に1回の映画祭ではなく、定期的な上映企画にすることで、学生が育ち、旅立ってゆく場所としての、学生映画のハブを目指したのです。

2018年8月3日に開催されたVol.01では、26回の入選作品『オールドフレンド』(内田裕基)が上映され、「物語を<語る>って?」と題された、ワークショップ企画が催されました。ただ学生映画を紹介するだけに留まらず、その映画について「語り合う」場としての意義がありました。
2018年9月28日に開催されたVol.02では、第25回の入選作品『薄いしきり』(須山拓真)と、第26回の入選作品『ひかりタイプ』(柴野太朗) が上映されました。上映後は、観客とディスカッション形式でトークが行われ、「ここはどういうこと?」「私ならこうする!」といった、自由な意見が交わされたそうです。

もちろんこのココガクナイトは、学生映画の小さなハブとして、定期的に学生映画を発信することを目的としていました。
ただ、より現実的には、安定的な収益源を得たいという組織としての狙いもあったと思います。当時の議事録を見てみると、ゆくゆくは作品を公募し、映画祭とは別企画として学生映画を紹介する枠組みを作ろうとしていたことも分かります。

ちなみに、ココマルシアターは記憶に新しい人もいるかもしれませんが、2017年10月のオープンから2年も経たず、2019年9月には閉館しました。
ココマルシアターは、設立当初から映画に限らない文化の発信地としての挑戦的なコンセプトや、特徴的な電飾やインテリアを用いた空間作りへの取り組みを掲げていました。2014年5月には、同じ吉祥寺内の老舗バウスシアターが閉館し、2016年1月には渋谷を代表するミニシアターシネマライズも閉館していたので、吉祥寺に誕生する挑戦的なミニシアターには、多くの期待が寄せられました。クラウドファンディングでも600万円にも及ぶ支援金と、多くの限定会員を集めることに成功し、順調な滑り出しでした。
しかし結果的にココマルシアターは、度重なるトラブルによって、映画ファンの失望を買ってしまうことになります。
2017年4月には工事が未完了のままプレオープンが始まりましたが、それも僅か1日で終了してしまいました。そこから、計10回に及ぶオープン延期を発表し、映画館として営業するために必要な審査をパスするのに半年を要しました。一部のネットでは、「吉祥寺のサクラダファミリア」とまで揶揄されてしまう有様で、SNSでも度々炎上を繰り返していました。正式にオープンした初日にも機材トラブルが発生し、上映中止に追い込まれてしまうなど、まさに踏んだり蹴ったりの状態でした。
ただ、今になって振り返ってみると、ココマルシアターが目指していたインディーズの映画館像なるものには、ある程度の需要とシンパシーがあったように思えます。
確かに、各所で指摘されているような映画館としての経営体制には些か問題はありますし、今もネットの記事では酷評の嵐です。ただそれでも、HPに記されている以下のような文言に、私は惹かれてしまうのです。
映画を観終わったあとの感想会や、新鋭映画監督を支援する自主映画企画発掘イベントなど、
様々な試みに挑戦していきます。上映ラインナップは、ココロヲ・動かす・映画社〇配給作や
話題のロードショー作品。さらに企画特集上映なども行います。
「映画作品」「感動」「人」との「出会い」をコンセプトに、感動を共有しあえる、そんな場
所になれば幸いです。ご来館をお待ちしております。
(ココマルシアターHP)特に惹かれたのは「感想会」「出会い」「新鋭映画監督」「自主映画企画発掘」といった、インディーズの精神です。これはまさに、この記事でも度々言及している東学祭の精神とも合致するのではないでしょうか。
結果的にココガクナイトは、僅か2回で終了してしまいます。映画祭側の熱量や財源、映画館側の経営体力不足は、とても採算に見合いませんでした。
ただ、ココマルシアターとのコラボは、学生映画のハブとしての東学祭の役割を考える上で、必ずしも無意味ではなかったと思います。
・『カメラを止めるな!』学生限定試写会

会場:VANADLISM渋谷
実験的な企画の2つ目が、『カメラを止めるな!』学生限定試写会です。
インディーズ映画の『カメラを止めるな!』(2018)が日本を席巻し、世界を股にかけてヒットしたことは記憶に新しいですが、実はあの映画を製作したENBUゼミナールと東学祭がコラボし、学生限定の試写会が行われていたのです。
学生限定試写会は、『カメラを止めるな!』が本公開された2018年6月23の1週間前、6月17日に開催されました。『カメラを止めるな!』はENBUゼミナール主催のシネマプロジェクトという「劇場公開映画製作・俳優ワークショップ」で製作された作品で、以前にも『あの女はやめとけ』(市井昌秀)、『サッドティー』(今泉力哉)といった作品が話題を呼んでいました。シネマプロジェクトの中でも『カメラを止めるな!』は、新宿K’sシネマの先行上映チケットが僅か5分で即完し、その後も破竹の勢いで全国区に拡大するなど、際立ってセンセーショナルな作品でした。
『カメラを止めるな!』学生限定特別先行試写会、無事に終了致しました👏
— 東京学生映画祭 (@tougakusai) June 17, 2018
上映後にみんなでゾンビポーズ🧟♀️🧟♂️#カメラを止めるな #東京学生映画祭 #試写会 pic.twitter.com/RWclwJukts
上記は、会場が一丸となって「ゾンビポーズ」をとっている当時の写真です。上映中は笑いが絶えなかったそうで、上映後のティーチンでは植田慎一郎はじめ製作陣が壇上に上がり、これからのインディーズ映画を担う学生たちに檄を飛ばしました。
植田慎一郎は、以下のコメントを東学祭に残しています。
僕は中学生の頃から仲間とハンディカムで自主映画を大量に撮ってきました。
お金のためでもない。名誉のためでもない。出口があるわけでもない。
映画づくりが何の「ため」でもなかった学生時代。
ただ「撮りたいから撮っていた」学生時代。
大人になるにつれ、それはだんだんと難しくなってきます。
でも、結局はその気持ちが一番大事なんだと思います。
「カメラを止めるな!」はもう一度中学生に戻って創った映画です。
ただただ、自分の「撮りたいもの」を信じて撮りました。
まずは自分の「撮りたいもの」を信じてあげてください。
信じれたら、後は映画づくりを思いっきり楽しむだけです。 まさにインディーズ映画、学生映画の畑で名を上げた植田監督だからこそ生み出せる言葉には、大きな説得力があります。「お金のためでもない。名誉のためでもない。出口があるわけでもない」からこそ価値がある。それこそが、学生映画なのです。
インディーズ映画である『カメラを止めるな!』が前例のないムーブメントを生み出した事実は、学生にとって大きな刺激になったのではないでしょうか。
ちなみに今回の試写会は、EUBUゼミナールとのコラボ企画でしたが、東学祭が映画学校との結びつきを強めることは、学生映画のハブを目指す上で必要なことなのだと思います。そして、必ずしも学生映画だけに留まらず、その延長上にあるインディーズ映画全般へ目配せし、関心を持っていることを世間に提示する必要もあったのだと思います。
SVODで配信へ〜渋谷の街から〜

会場:渋谷 ユーロライブ
<ゲスト>
熊澤尚人、入江悠、三島有紀子
平林 勇、大槻 貴宏
延期のコメントでは、2019年5月頃開催を目標としていた第30回ですが、またもや会場の抽選に外れ、8月6、7日の開催となりました。それは令和元年の夏のことで、当時大学1年生だった私は、まだ学生映画について右も左も分からない状態で入会しました。

会場はユーロスペースが入館している渋谷のキノハウス2階、ユーロライブでした。席数(キャパ)が程良いこと、アクセスが良いこと、会場費の支払いに融通が効くことなどが選定理由でした。北沢タウンホールと比べて会場が狭いため、全回入替、自由席制が採用されました。
第30回は、延期しているぶん200本以上の作品が集まり、部門も第21回から用いられていた「実写部門」「アニメーション部門」から、「東学祭コンペティション部門(16分以上)」「 短編コンペティション部門(16分未満)」に変更されました。応募数が少ない短編アニメーションの入選が多い割に、短編実写作品の入選が少なくなっている現状を加味した結果でした。招待上映では、第13回東京フィルメックスで学生審査員賞を受賞した『あたしは世界なんかじゃないから』が上映され、高橋泉と、高橋監督とゆかりの深い白石和彌のアフタートークも行われました。

また、渋谷スクランブル交差点の目の前にあるSHIBUYA TSUTYAとのコラボも実現し、東学祭専用ブースが設けられました。ここでは、東学祭の過去作が無料でレンタル可能だった他、ゲストや出身監督の作品、委員や学生監督のオススメ作品のレンタルも可能でした。
さらに、映画監督とミュージシャンがコラボする祭典MOOSIC LABと、「クリエイターズ プログラム」の一環でドキュメンタリー制作を支援する「Yahoo! JAPAN CREATERS Program」との協力も実現しました。1年間の猶予を与えられたからこそ、多方面で新たな学生映画の可能性を模索する、新しい形のイベントを提示できたのではないでしょうか?

会場:渋谷 ユーロライブ
<ゲスト>
大九明子、井口奈己、深田晃司
岩井澤健二、佐々木敦
第31回も引き続きユーロライブで行われ、部門は「東学祭コンペティション(15分以上)」「短編コンペティション(15分未満)」と尺に若干の変更が加えられました。
当初は6月中旬の開催を目指し、会場(ユーロライブ )の予約も済ませ、日時の公表も終えていました。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、再び延期を余儀なくされました。昨年から十分に確保できなかった財源は会場のキャンセル料によってさらに逼迫し、再び東学祭は継続の危機に晒されました。

そんな中、多くの方から応援の声をいただき、クラウドファンディングで80万円もの支援を獲得することに成功しました。ちなみに、私はクラウドファンディングの運用を担当したひとりだったのですが、最終日に50万円を支援した方がいて、目が覚める思いがしたのを覚えています。(投資家のマネーロンダリングに使われたのかもしれないなどとも噂しました。)
TIFFや東京フィルメックスとの会期が被らない10月中旬に会期を設定し直した東学祭は、多くの映画祭が「オンライン開催」or「中止」に転換する中、スクリーンに投影し、学生たちが交流するフィジカルな場に拘りました。座席も前後左右1席ずつ間隔を空け、会場の消毒、舞台上のパーテーション設置、マスク着用も徹底した上で、例年通りのトークセッションも実現させました。
予想外のコロナ禍は、限りある私たちの学生生活の自由を蝕みました。ただ、むしろ東学祭にとっては躍進の契機にもなったといえます。
というのも、東学祭はいわゆるサブスクリプション(SVOD)にて、全国規模の配信を実現させることができたからです。サブスク元年と言われた2019年以降、Netflix、AmazonPrime等は、おうち時間に決定的な娯楽として普及しましたが、そういった流れによって「学生映画を配信で」といった幸甚な機運が生まれたのです。
東学祭は、これまで作品の上映だけを行なってきたので、配信は未開拓な領域でした。そもそも東学祭は、作品を募集する時点で「上映」だけを前提とした権利処理が成されていて、「放映」「配信」といったマルチメディアへの展開は想定されていませんでした。
・U-NEXT

第31、第32回と、具体的にご協力いただいたのが、U-NEXTとDOKUSO映画館の2社です。他にも複数の配信サービスの協力を得ていますが、スタートアップから関わりのある2社に絞って紹介したいと思います。
まずは、U-NEXTです。
U-NEXTは、国内3位のシェアを誇る配信サービスです。独占の最新作から雑誌に至るまで、国内最大級のコンテンツ量を誇ります。一部、ポイントを活用できる点に特徴があり、個人的にはSVODで最も充実したサービスを展開していると感じています。
U-NEXTは、新型コロナウイルスの影響を受けて各地の映画祭が縮小・中止を強いられている状況を
鑑みて、東京国際映画祭(TIFF)、下北沢映画祭、東京学生映画祭の3つの映画祭との連携を発表。
各映画祭の方針を尊重しつつ——中略——全国の映画ファンと作品とのハブになれるような連携を決定。
東京国際映画祭では、初めてメディアパートナーとして参画。また下北沢映画祭、東京学生映画祭では、
今年の上映作品をU-NEXTでいち早く配信いたします。
(U-NEXT ニュースリリース) U-NEXTは2020年10月5日、上記のリリースを発表しました。東学祭では以後、第31、第32回の作品を主に、2021年時点で約60作品のタイトルの配信が実現しています。
コロナ禍によって、映画祭が「オンライン開催」or「中止」に転換したことは既に触れましたが、元来から地方の映画祭は直接足を運べないという問題を抱えていました。実際、東学祭と同時期に始まった山形国際ドキュメンタリー映画祭やゆうばり国際ファンタスティック映画祭も、コロナ禍ではオンライン開催が余儀なくされています。前述したように、アジアフォーカス・福岡国際映画祭に至っては、来場者や協賛金の減退によって、遂に解散を迎えてしまいました。
U-NEXTのような大手サービスでの配信は、認知度の低い映画祭が全国区に広まることが見込まれる上、作品を介した映画業界との接点の増加にも寄与します。これらは、地方開催の映画祭がいかにして都市に上るか、あるいは都内の特権と化している映画祭がいかにして地方を行脚するか、といった課題を解決する革新的な事業でした。
ただ配信は、およそ映画祭の役割を根本から揺るがしかねない危険性を孕んでいると個人的には思います。地域密着の映画祭が全国区に広がることは、作品にとっては良いことですが、「交流」や「村おこし」といった点に関しては、ネガティブな影響も大きいと思います。映画祭において、いかに交流が大切かは散々説いてきたと思いますし、そもそも日本を代表する映画祭である山形国際ドキュメンタリー映画祭は山形市政100周年で始まり、ゆうばり国際ファンタスティック映画祭も夕張市の「炭鉱から観光へ」の一大事業でした。ましてや、過疎化によって自治体の財政が引き締められているからこそ、いかにして映画祭側に資金を還元していくかは、今後の課題となってくるでしょう。

2020年10月からU-NEXTでの配信が始まったラインナップが、東京国際映画祭(TIFF)、下北沢映画祭、東京学生映画祭といった並びであることは、些か恐れ多い気もします。
この2020年を、映画祭配信元年などと呼んでいる関係者の方もいました。
この小さな映画祭を最初にピックアップしていただけたことは、自主映画に垣根はない、といったある種のメッセージとも受け取れました。
以後もU-NEXTはラインナップを増やし続け、2021年末時点で以下の21映画祭との連携が実現しています。
2020年10月
・東京国際映画祭
・東京学生映画祭
・下北沢映画祭
2021年2月
・未体験ゾーンの映画たち
・茅ヶ崎映画祭
・SKIPシティ国際Dシネマ映画祭
・広島こわい映画祭
2021年4月
・TOKYO青春映画祭
・NASU SHORT FILM FESTIVAL
・なら国際映画祭
・あわら湯けむり映画祭
2021年6月
・music lab.
・うえだ城下町映画祭
・関西クイア映画祭
・TOKYO青春映画祭
2021年8月
・ぴあフィルムフェスティバル
・おおぶ映画祭
・ながおか映画祭
・バウムちゃんねる映画祭
2021年9月
・夏のホラー秘宝まつり
・小布施短編映画祭
・あいち国際女性映画祭ちなみに第32回の作品も、2021年10月末から配信が開始されています。興味がある方は、ぜひご鑑賞いただければ幸いです。以下は、配信に先だった映画ナタリーのリリース記事です。第32回の開催に寄せられた斎藤工、毎熊克哉からのコメントも掲載されています。
・DOKUSO映画館
次に、DOKUSO映画館とコラボ内容について説明します。

DOKUSO映画館(ドクソーエイガカン)とは、2020年1月23に立ち上げられたインディーズ映画に特化した配信サービスです。
DOKUSO映画館 が目指すもの
次々と単館映画館がなくなり、想いとお金をかけて製作した映画が、たった数館、たった2週間
程度の上映しかできないようなことも増えてきました。
—中略—
『DOKUSO映画館』では、眠っている良作を発掘し、インディーズ映画を愛するお客様に届けるこ
と、そしてクリエイターに正当な対価をお渡しし、次の映画製作へと繋げていただける場所をご提
供したいと考えています。
(DOKUSO映画館:2020年1月リリース) サービスがローンチした当初のコンセプトは、上記のようなものでした。
DOKUSO映画館は、ミニシアター(単館映画館)が減少したことで埋もれてしまっているインディーズ映画を、配信を通して全国に広める事業を展開しています。U-NEXTの場合は映画祭にフォーカスが当てられていますが、DOKUSO映画館はありとあらゆるインディーズ映画を包括的に紹介している点に、大きな特徴があるといえるでしょう。
また、DOKUSO映画館は新たに、配信に関わるクリエイター側の負担が0円、そこに視聴売り上げの35%が支払われる仕組みを考案しました。コロナ禍では、想田監督の仮説の映画館の事業も始まりましたが、必ずしも劇場の興行収入だけに頼らない、新しいクリエイターファーストのエコシステムだといえるでしょう。
DOKUSO映画館でもU-NEXTと同様、第31、第32回の作品を主に約60作品のタイトルの配信が実現しています。
特に第31回では、当日のトークショー含むディレイ配信(直後配信)も実施されました。新型コロナの影響で県を跨いだ移動ができない方や、平日午後に予定が入っている方にとって、とても大きな訴求力になったと思います。
上記が、第32回の配信ラインナップです。こちらも興味があれば、ぜひご鑑賞いただければ幸いです。
ちなみにDOKUSO映画館は、2021年1月に1周年を迎えた時点で、約500本ものインディーズ映画を抱える規模にまで成長しています。同年9月には配信事業だけではないインディーズ映画応援コミュニティとしてのコンセプトを掲げ、映画祭まとめ情報サイトやワークショップのマッチングといった各種機能を追加しています。今後も、映画系の仕事マッチングサイトDOKUSO WANTEDを展開する予定で、ますますの飛躍が期待されています。
U-NEXTやDOKUSO映画館の他、東学祭の作品はAmazon Prime、GYAO!、CINEMA DISCOVERIES、ビデオマーケットといった各種動画配信サービスにも展開されています。今後も配信されるプラットフォーム数は増え、さらに多くの作品が展開されていくと思います。
こういった配信事業で、何が達成できたでしょうか?
もちろん、配信視聴料が製作者にバックされる仕組みは、必ずしも劇場公開に縛られない、新しい映画祭・インディーズ映画の興行形態です。ただ、『カメラを止めるな!』といった例外作品はあるものの、インディーズ映画それ自体の認知度はまだまだ低く、ほとんどのケースで製作費は還元されていないのが現状です。それに加え、YouTube、TikTok、Netflixといった巨大な動画サービスを前に、ことさらインディーズ映画を見ようなどといった人も稀です。
恐らくここで大事なのは、資金面ではありません。自分が心を込めて作った映画が、どこかの誰かに観られ、応援してくれているかもしれないという期待を、抱かせてくれる点にあるだと思います。
テレビのリモコンに、サブスクリプション(SVOD)のロゴが入るようになって久しくなりました。今や生活の一部と化した動画配信サービス上に、一般公開されている映画と並んで自分の「監督作」が表示されるのです。その光景に、憧れを抱く人は多いのではないでしょうか?
特に最近は、サブスクリプション(SVOD)とアート映画・インディーズ映画の垣根が取り払われてきているように感じます。Netflixでは、是枝裕和、山下敦弘、三宅唱といった監督らが起用されていますし、Huluオリジナルドラマでも東学祭出身の中川龍太郎が起用されています。同じく東学祭出身の見里朝希の『PUI PUI モルカー』も、YouTubeやサブスクリプション(SVOD)を通じて拡散し、社会現象を巻き起こしました。
スクリーンでの鑑賞体験に拘るのは、もはや時代遅れなのでしょうか?
確かにミニシアター文化が衰退することは名残惜しいですし、シネコン化によって映画がイベントの側面を強め、作品と深く向き合い、製作者や観客と対話を重ねる場として機能が無くなってゆくことは、どこか嘆かわしい気もします。また配信化によって、スクリーンならではのアトラクション性が希薄となり、旧来から観客を魅了してきた映画本来のダイナミズムが損なわれる、という意見も頻繁に耳にします。
そういう意味で、コロナ禍は一つの分岐点だったのでしょう。配信を嫌う映画祭、映画館、重鎮監督の存在、むしろ配信を活用して名を成してゆくベンチャー企業や若手……。
私は、映画の破壊的イノーベーションは恐れるに足らない、と個人的には思います。なぜなら、そもそも映画とは、あらゆる新しさを獲得しては、その都度これまでの古さを刷新してきた歴史を持っているからです。
活動写真とも言われるように、映画の原点にあるのは写真技術でした。それがやがて「動き」を手に入れ、後に「音」や「色」を手に入れました。その後、映画は「CGI」によって非現実のイメージを生成することが可能となり、近年では立体的な視覚を齎す「VR」まで台頭し始めています。
一体、映画が誕生した1895年の人類に、そして東学祭が誕生した1988年の学生たちに、それらの技術を予想した者はいたでしょうか?
新しい技術の誕生は、往々にして旧世代との対立を生みます。ただ、いずれはその記憶も薄らいでいき、当たり前のように技術を駆使する、私たちの新しい時代が幕を開けるのです。
変わりゆく学生映画、想いの継承
いよいよ、私が代表を務めた第32回の話に入ります。

もっとも、東学祭への思い入れが強くなったのは、私が第32回の代表を務め、様々な業務を行うようになってからです。OB・OGとの関わりも大きくなり、関係者との様々な交流を通じて、少しずつ東学祭の過去や、学生映画のあり方について興味を抱くようになりました。
もちろん私は、第30回以前の東学祭を知りません。委員として参加した第30、第31回でさえも、映画祭の方針に大きく関わっていたわけではありませんでした。ですから、本来であればこういった記事も、私より東学祭の歴史や映画祭について造詣の深い方が書くべきだったのだと思います。
ただむしろ、こういった記事に必要なのは、既に社会的立場のある方には書くことのできない、現役の学生としての視点なのだと思っています。さらに言えば、東学祭について口を開くことができるのは、現役の学生だけなのだと思っています。冒頭にも書きましたが、今の東学祭をある程度は理解し、分析的に過去を外観した上で、それを自分の記事としてアーカイブを残しておこうなど考える現役の学生は、今のところ私ひとりしかいませんでした。
私も私なりに、第32回の代表として、活動を全うしてきたつもりです。もちろん、全てが全て満足いくクオリティだったとは言いませんが、それでも半ば無為に学生の時間を捧げ続けたひとりの学生、ひいてはひとりの人間として、口を開くことを許してほしいと思っています。そして私が今後も含め、しっかりと映画祭と向き合い、思いの丈を消化するためには、記事を公開するという選択肢しかありませんでした。例え知識と経験が浅かろうと、一部の方から反感を買ってしまおうと、私の中で納得するためには、そうしない訳にはいかなかったのです。
ここからは、これまで以上に手前勝手で、個人的な記述が続くと思います。アンケートの結果などを踏まえ、学生が映画についてどう捉えているか、もといこれからの学生映画はどうあるべきか、といった私個人の視点も提示してみるつもりです。感情的な部分も多分に含まれるので、あるいは偏見じみているかもしれません。ただ少なくとも、そういった記述は、私の記憶が途切れてしまう前に、しかるべき手順で過去を振り返りつつ、時間を掛けて納得した結果です。

会場:渋谷 ユーロライブ
<ゲスト>
イシグロキョウヘイ、川添彩、今泉力哉、中野量太
小田香、小路紘史、池田千尋、坂本安美
柴崎友香、城定秀夫、山内菜々子
毎熊克哉、しんのすけ、キミシマユウキ
この記事を書き進めるほどに、ますます思います。
1つのサークルの歴史を振り返ることに、どれほどの意味があるだろうか?
よくよく考えてみれば、私はある特定のサークルにおける凡そ100,000字にも上る詳細な歴史など見たこともありませんでしたし、日本でも有数のサークルを抱えている早稲田大学(公認約500サークル、非公認推定3000サークル)で、今も活動的かつ際立って長い歴史と、ネームバリューを持つサークルを調べても、その歴史をかなりの文量を割いて、分析的に概観できるような資料を公開しているサークルは、1つも存在しませんでした。あるいは何らかの形で存在していても、それが外向きに公開されているといった現状はなかったと思います。
そのため、この記事は、少なくとも学生のサークルという数少ないベクトルにおける——コロナ禍で衰退しているからこそ尚更——些か挑戦的なの試みである気がしましたし、どこまで私が持つ情報と表現力でそれが可能かは、未知数でした。私は映画を専門的に学んでいるという程ではありませんし、特に映画理論の分野は不勉強です。ただ「書き残したい」という欲望自体は、それを果たせられるだけの立場・条件が揃っている限り、何とかして消化したいと考えていました。
ただ、いくらそう仰々しく言ってみたところで、この記事にそれほどのインパクトはないでしょう。
記事全般に渡って使用された、半ば家宝のように学生間で引き継がれてきた資料は、「へえ、昔はこんな感じだったのか」「懐かしいなあ」といったノスタルジーに浸る以外の何にも寄与しないでしょうし、またそれを誰へ宛てるともなく外部に公開すること自体も、ある意味では不毛です。そして恐らく、どれだけ私一人が思いを書き連ねたところで、「何を言ってんだコイツ(笑)偉そうに。」位に笑い飛ばされるのがオチですし、私はそれを自覚しながら、自分の道理に叶う大切な人たちに向けて言葉を差し出したいと、常日頃から考えていました。
そもそも東学祭は、どこかの大学の公認でもなければ、企業の意向で成り立っている訳でもありません。どこまでも身勝手な学生が自主的に集まった人的ネットワーク、という体を成しているのです。その限りにおいて、この映画祭史が継承され、活動が継続される必要性はありません。
つまり東学祭は、いつ、誰が解散したって良かったのです。

ただ、奇跡的に33年続いた映画祭の歴史も、私含め、ある種の人生を変えるだけのポテンシャルはありました。
東学祭はこれまで、「日本一の学生映画を決める」「映画の未来のために」「才能を発掘する」などと嘯きながら、これまで数百人もの学生監督を紹介し、彼らに「あなたこそ才能がある! 引き続き頑張って欲しい!」などと浮ついた語気で、半ば自己完結的に下駄を履かせてきたようなものでした。他方で冷静になって振り返ってみると、東学祭が実際に活躍している映画監督を輩出できているのは、5年に1、2人くらいのペースです。毎年応募される150作品の中から15作品を上映してきたとすると、700人〜800人に1人か2人程度の割合です。
つまり、端的に言ってしまうと、東学祭で紹介された映画監督の大抵は映画監督になれません。
東学祭で紹介されて以降、大学を卒業してからもフリーターを続けながら、何とか2、300万位の資金をかき集め、何本かの長編自主映画を撮り上げた方々も多くいます。ただそれも、結局はミニシアターでの自主配給(1週間のレイトショー)で止まり、製作費すら回収できないケースが大半になっています。
もっとも、それは委員も然りです。商業映画は嫌いだと経済的な物差しを外し、いつまでも自主映画の世界へ拘泥し、それと知りながらも居場所を探し、いつまでもバイト漬けの沼から抜け出せないまま、中には映画への情熱を失ってしまったOB・OGも多いことでしょう。
こういった現実がありながら、だからこそ、と私は思うのです。
この記事は、映画が大好きなあの誰かに向けた、祈りのようなものです。私も就職以降のことは分かりませんが、少なくとも学生の間は、映画に固執していたいと思っています。私にできることは、例え知識や経験が少なくとも、このサークルの歴史を分析的に振り返り、それを外向きに発信しつつ、長きに渡ってアーカイブを残す事ぐらいです。この記事に大したインパクトがなかろうと、最低限は現役委員に託す内向きの引継ぎ資料として機能さえしてくれれば万々歳です。
いや……それもきっと、建前なのかもしれません。
私はきっと、私が少なからず知ることができた学生映画の手触りと、いわば映画の精神世界に居場所を求めていたい拘泥感を、誰かに知って欲しいのです。そして私という人間が、確かに映画を夢見ていた現実が、大切な誰かの記憶に留まって欲しいと、ただ切に願っているのです。
私がこの映画祭の活動に費やした時間は、必ずしも全てが全て、有意義だったというわけではありません。そして、再三言及している通り、「日本一の学生映画を決める」云々といった大義名分以前に、もっと個人的な意味合いで不毛かつ、没意義に終わってしまったことが大半だったと思います。そもそも映画鑑賞という営み自体が個人主義的ですし、上映会に向けた運営も地道なメール打ち、書類作り、契約、お金のやりくり等々、事務的な作業(しかもほとんどがボランティア)が大半でした。活動を通じて抱かざるを得なかった、感傷的で、やりきれない精神の凝りは、映画祭が無事にトラブルもなく終わり、お世話になった方々や委員にお礼の連絡を入れてみたところで、決して取れるような類のものでもありません。
ただ、集まった224本(過去最大)の学生映画の、計6000分という時間は私に大きな、決して無視のできない魅惑を与えてくれたこともまた、事実なのです。コロナ映画、リモート映画、VR映画なる新しい映画様式は、私がこの時代に学生であった幾つかの同時代性を象徴しているようにも思えますし、映画の夢に駆られた高校生の作品と、むしろそこから逃れられずにいる30、40代の方々の作品、あるいは来年から社会人で物理的に映画が撮れなくなる学生の最後の作品には、決して軽く言い表せない儚い人生の繁栄、同時に衰退の所在がありました。
私自身もクリエイターを目指していた時期があるので、半ば矜持として告白しておくと、224本に及ぶ第32回の応募作全てにおいて、際立った才気に打ちのめされるといった鑑賞体験には至ることは——「濱口竜介に次ぐ人材を」などと意気込み過ぎていた節もありますが——一度もありませんでした。ただ、だからこそ、むしろ私自身の未熟さと照らし合わし、半ば同調しながら、それでいてある種の不憫さのようなものに、思い及ばせてしまうのです。

上記は、第32回の応募状況をまとめた円グラフです。
募集対象となった作品は、主に新型コロナの煽りを受けた学生映画でした。対面での授業が滞り(それでいて、どこの大学も学費を下げない!)、作品が集まるかどうかが懸念事項だったので、2020年末から年始に掛けて、全国の大学を対象にちょっとした製作状況調査なるものを行いました。
すると、多くの映画学校から「制限は設けるが、実習は例年通り行う予定」との回答が得られました。ただ、一部で「卒業制作の期限が遅れる可能性がある」といった回答もあったので、例年と違う対応が迫られました。
映画学校のほとんどは、9月~12月あたりまでに卒業制作の撮影を終え、1月~2月末までには完成版がパッケージ化されます。ただ、2021年は卒業制作の期限が遅れる可能性を鑑みて、応募時期を先行エントリー(2021年3月6日〜3月31日)、二次エントリー(4月1日〜5月9日)と幅を持たせることにしました。先行と二次に分けたのには、会場へ支払う資金の早期確保と、200本以上の作品を鑑賞する委員のリソース獲得の目的がありました。

ただ、こういった委員側の対応もよそに、いざ蓋を開けてみると過去最大224本もの作品を集めることに成功しました。
詳しい理由は分かっていませんが、エントリー時のアンケートによると、東学祭はほとんどSNSやホームページ(一部、劇場フライヤーやメディア掲載)から認知を得ているので、日頃の地道な宣伝や連絡が、功を奏したのかもしれません。あるいは、第31回から始めていたU-NEXTやDOKUSO映画館等での配信が訴求効果を生んだのかもしれません。いずれにせよ、数ある映画祭の中でも、かなり多い水準の作品に恵まれたことは喜ばしく思っています。
今年は、やはりコロナ禍で制作が滞った影響で、長尺の作品(61分〜91分)が10%と少なく、短尺の作品(〜30分)が70%と多くなりました。実写とアニメーションの比率に大きな変化はありませんでしたが、どういう訳かストップモーション作品が多かった印象があります。
作品のモチーフとしては、オンライン化した大学生の鬱屈、ウィルスが蔓延したディストピア世界、といったものが必然的に多くなっていました。私たちは、それらの作品をコロナものなどと呼んでいましたが、いくらその題材を扱わない訳にはいかない何らかの理由があったにせよ、「コロナ=孤独」「オンライン授業=不満」といった単純な図式だけが浮かび上がってしまった作品も多く、食傷気味になってしまいました。逆にいえば、単純な図式だからこそひっくり返すことも容易く、時代性と閉塞感が奇妙な具合に絡まった新しい味わいの映画もありました。ただ、映画というメディアや、時代そのものをメタ的に言及し、鋭い批評を展開するような挑戦作や、極端に過ぎるほど政治的な主張を行うイデオロギッシュな作品は少なめでした。
そしてやはり園子温、塚本晋也、石井岳龍、三池崇史あたりの「自主映画パンク!」の雰囲気は確実に薄れ、台湾映画や黒沢清っぽい作品、あるいはマイノリティや災害などを扱ったシリアスな作品が増加した印象です。そしておそらく、今泉力哉や山下敦弘などに影響されたナチュラルで緩い若者を描いたオフビート作品も、益々増えている印象です。また先ほども言及した「リモート映画」や「VR映画」といったテクノロジーに裏打ちされた新しい映画様式は、コロナ時代だからこそ芽吹いたものであるようにも思えた一方、自分達がいかにしてスマホやPCで日常的にカメラと接し、撮り/撮られ、見る/見られの認知構造それ自体が変わっているか、やはり鋭く批評的に切り込んだ作品があってもよかったとも思います。
エントリーをした学生監督203名(224作品)に対してアンケートを送付したら、104名の方々から回答を得られました。アンケートが得られた大学群は、以下のようになっています。
<芸術系大学>(*順不同)
日本映画大学、京都芸術大学、大阪芸術大学
東京藝術大学、東京藝術大学大学院
武蔵野美術大学、東放学園映画専門学校
名古屋ビジュアルアーツ、東京ビジュアルアーツ
日本大学芸術学部、HAL名古屋、HAL大阪
ENBUゼミナール、映画美学校、
東北芸術工科大学、有明教育芸術短期大学
成安造形大学、静岡文化芸術大学
<一般大学>(*順不同)
早稲田大学、東洋大学、目白大学
立教大学、横浜国立大学、東北大学大学院
東京造形大学、東京農業大学、慶應義塾大学
桜美林大学、九州産業大学、佐賀大学
名古屋学芸大学、立命館大学、成蹊大学
北海道大学大学院、順天堂大学
東京大学、東京大学大学院、国士舘大学
関西学院大学、法政大学、京都精華大学
アメリカンスクール イン ジャパン
Loyola Marymount University
104名のうち70名が映画学校(芸術系大学)出身でした。量的にも質的にも、ますます「映画学校の乱立」際立った印象です。
特に上記のアンケート結果には驚かされました。東学祭に応募した学生のなかで、仕事として「映画製作」ないし「アニメーション製作」を希望している方は何と95%にも上り、またそのうち82%が監督志望でした。基本的にアンケート回答は、応募された作品の監督なので、高い数値が出るのは必然です。ただ狭き門である監督希望がこれだけ多いという事実には、単純に驚かされました。
東学祭は700〜800人(5年間)に1人か2人のペースで映画監督を輩出しているということは既に触れました。ただ、どれだけ監督を志す学生が多かろうと、日本にある既存の映画マーケットは、それに見合う成長を見せていません。映画がデジタル化されたことで、誰でも低予算で映画を撮れるようになり、他方で文学賞の応募数も増え、自らのアートワークをInstagramで投稿することができるようになりました。ただ、そういった芸術全般の民主化は、アーティストの枠を縛り上げ、不用意に倍率を上げている印象が付き纏っています。
【第32回東京学生映画祭授賞式】
— 東京学生映画祭 (@tougakusai) October 23, 2021
速報✨
グランプリ👑
「大鹿村から吹くパラム」金明允
準グランプリ🎞
「夏だまりの家」 石井梨帆
審査員特別賞📽
「トエユモイ」福岡佐和子 はまださつき
「素敵なあなたに」染谷夏海
「また春が来やがって」堀内友貴
観客賞🎬
「また春が来やがって」堀内友貴 pic.twitter.com/nDu5OjRCnK
第32回は、2021年10月19〜22日(ユーロライブ)、23日(LOFT9 )の5日間に渡って開催されました。
この年も土日の枠が外れてしまったので、平日午後の開催となってしまいましたが、5日間に渡って18本の学生映画、14本の招待作品を上映する、例年にない規模感の映画祭となりました。前年度のクラウドファンディングが成功し、配信事業も始まったので、今年は豪華にしようといって始まった映画祭でした。
当日の雰囲気は、CUT TOKYOさんに取材いただいた上記のダイジェスト動画をご覧いただければ分かると思います。私も代表として口を開いていますが、委員含めゲストの方や入選監督の声に耳を澄ましていただければ幸いです。「社会人として映画を撮りたい人が減っている」という私の発言はこと一般大が顕著で、フリーターとして自主映画を撮り続けている人も数知れない、といった趣旨です。
東学祭の基本的な役割は、この記事や動画内でも言及している通り、立場の弱い学生映画を世に「紹介」し、観客やゲストの方々と「交流」を促すことにあります。
そのため、是が非でもフィジカルの上映形式に拘りました。ただでさえ上映機会の少ない学生映画が、スクリーンに映写され、観客に観られるといった夢の体験にこそ東学祭の核があり、普段は話せないゲストや同年代の仲間、観客の方々と言葉を交わし合う体験にこそに、東学祭の核がある、と強く考えたからです。

当日のプログラムは、上記のスケジュールで進行しました。
今、振り返ってみると、初日は225分(4時間弱)のプログラムから始まり、ほとんどのプログラムで150分(2時間半)を超え、22時過ぎまで漏れなく使い切るこの番組編成には、学園祭らしい訳の分からない凄みがあったと思います。それでいて、学生500円という設定も破格で、元を取ろうなどといった発想も、毛頭ありませんでした。
もっとも、そういった価格設定にしなければ、学生の重い腰を上げさせることはできなかった訳ですが、平日午後という時間帯でありながら、結果的にメインプログラムだけで500人強の動員に恵まれました。席は少なくとも半数以上、多い時は7割以上埋まった回もあったので、集客という意味では成功を収めた年となりました。
当日はスタンプラリーも行い、副賞としてオリジナルステッカーと授賞式への招待を設け、継続的な動員の確保を目指しました。全体を通して、前半の口コミやゲストの発信で、芋づる式にお客さんが増えていった実感があります。特にCプログラム今泉監督の回でSNSが盛り上がり、翌日のDプログラムで毎熊克哉さんの登壇が決まってからは、木曜の16:30〜の回で7割近く席が埋まりました。

これまでの東学祭は基本的に、学生映画だけでプログラムを組み、上映後は審査員とトークセッションを行う、といった番組内容でした。もっとも、予算的にはそれがオーソドックスな編成なのですが、そこには2点ほど課題がありました。
それは、
・学生映画だけでは動員が上手くいかない
・トークショーが審査員の講評になってしまう
といった課題です。
営利目的ではない東学祭は、学生映画を紹介し、交流の機会を生み出すことに基本的な役割があるので、必ずしも動員が必要な訳ではありません。ただ動員を増やし、異なる映画ファン層との接点を増さないことには、なかなか展開していかないことも事実です。さらに、立場に上下間の差がある学生と審査員のトークショーは、往々にして一方的な講評で終わってしまい、学校の講義と変わり映えがしなくなってしまいます。
そこで第32回は、東学祭でしか為し得ない新鮮なプログラム、トーク空間を目指しました。具体的には、学生映画を紹介する各プログラムで、現役で活躍しているゲストの作品を併映し、必ずしも審査の形式に縛られないフラットな視点でのトーク空間を目指しました。
招待するゲスト、併映する作品の方向性はあえて統一せず、担当する委員個々の発想を優先しました。その結果、イシグロキョウヘイ、川添彩、今泉力哉、中野量太、小田香、小路紘史、池田千尋といった、バリエーションに富んだ監督方の、多くは学生ないしインディーズ時代の作品の併映が実現し、異なる映画ファン層も呼び込むことができました。トークショーの時間も例年より長めの35分〜45分に設定し、既存の枠に囚われない談義となりました。

学生映画全体の印象としては、やはり女性監督が目立ったという点でしょうか。今回の入選作の男女比は、結果として男性3:女性14となり、女性監督が多くなりました。
そもそも女性監督という呼び方自体、極めて図式的ではありますが、全くもって女性を偏重した訳ではなく、少なくとも今年全体の応募作に渡って——あくまで1つのサンプルでしかありませんが——質的にも量的にも純粋な視点で見て、女性側に優れていた傾向が認められたと思います。
私個人の恣意的な価値観で、包括的なジェンダー差を提示するのはフェアではありませんが、そもそも現在の美大の男女比が男性2~3:女性が7~8となっている反面、日本の映画業界は極端に男性偏重になっています。表現の現場調査団によると、主要な映画賞審査員の男女比は平均男性8:女性2で、邦画大手4社が20年間製作・配給した実写映画のうち、女性監督作の割合は僅か3%です。こういった極めておろし難いジェンダーギャップの根本には、単純な比率の問題より、映画産業ひいては日本社会全体の問題を読み解かなければなりませんが、むしろ東学祭のようなフラットな低層から、ボトムアップ的に是正するのが望ましいのだと思います。

今回はトークライブハウスLOFT9(10月23日)を借りることもできたので、これまでにない新しい2つの上映会イベントを企画しました。
1つ目は、「映画とファンを繋ぐ、新しい出会い」をモットーにSNSやTikTokで映画の魅力を発信し、若者に支持を得ているuniとのコラボ企画です。東学祭はこれまで、シルバー層の観客が主だったので、10代・20代への訴求効果を狙いました。当日はuniメンバーである、キミシマユウキさんとしんのすけさんをお呼びし、第30回の入選作品『Female』(常間地裕)『Fiction』(北川未来)を観ていただいた上で、学生映画をどうPRするべきか、若者に向けてどういう映画を作るべきか、といった視点でトークショーを行いました。
2つ目は、業界最年少の活動写真弁士である山内菜々子さんによる、活弁上映です。名作『東京行進曲』(溝口健二)と『漕艇王』(内田吐夢)の2作に加え、今回は第31回の準グランプリ作品である『こちら放送室よりトム少佐へ』(千阪拓也)を活弁していただきました。学生映画の活弁は、私の知る限り前例がありませんし、それどころか世界初の企画だったのではないかと勝手に思っています……

LOFT9では上記の坂本安美、柴崎友香、城定秀夫のお三方をゲスト審査員としてお呼びした上で、関係者だけのクローズドで授賞式と合評を行いました。
坂本さんにはパンフレットに、「映画を見る体験とは、私にとってそうして「世界」を発見、再発見しに行くことであり、東京学生映画祭で出会う作品とともにそうした旅に出ることを心から楽しみにしています。」と素敵なコメントを寄せていだきました。そうした学生映画の発見、再発見の先に、審査員のお三方に共通していたのは、究極的には映画に優劣は付けられない、ということだったと思います。開催の直前にTIFF学生応援団との合同インスタライブでは、僅か数人のスペースに何と斎藤工さんが入室してくださり、「頑張ってください(絵文字)」とのメッセージを寄せていただきました。
もちろん学生映画は、質的にも量的にも、未熟なところが目立ちます。そして誰しも、その存在そのものに、疑問を投げかけたくなる瞬間があったでしょう。
学生映画はどこから来たのか。
学生映画は何者か。
学生映画はどこへ行くのか。
答えはありません。ただ恐らく、学生映画は、世の中で数多存在する映画の中で、最も「〜のために」という目的意識や、「〜の達成」という進歩史観、あるいは「全ては『最後の審判』に向かう」時間感覚から遠く離れた、ひたすら無常に散在する作品群なのだと思います。つまり、映画祭での受賞や批評的な評価、社会的意義、メッセージ性など、あらゆる意味性に先んじて、ただそこに単一的なミラクルが存在するだけなのです。そして映画祭が映画祭である所以の先で、若者が映画に情熱を捧げ、時間が過ぎる、ただその事実が重要であるというお告げを聞くだけなのです。
第32回の結果について詳しくは、こちらをご覧いただければと思います。もちろん、どの作品がどうだったか、どのプログラムが充実していたか、といった私見は幾らでもあります。ただ、この記事で特定の事象を論うのは止めておこうと思います。東学祭はこれまで、何かにつけて出身監督の名を借りて宣伝し、学生監督の言葉をそのまま援用してきましたが、実際、委員自身が映画の中身を語ることは少なく、ある批評精神に基づいたテクストとしての映画の<内側>への関心よりも、イベント的な映画の<外側>への関心が強い傾向があるのです。その意味で、映画そのものの作品論的な意義を軽視してきた、といえると思いますし、だからこの記事でも、映画の<内側>について分析するということを——私にその批評眼がないという現実的な理由もありますが——努めて避けてきました。
ただ第32回のプログラムに関して確実に言えるのは、例え統一的な判断基準はなかろうと、今回の映画祭で紹介した学生映画は、委員が自信を持って選定した作品群であるということです。それでいて自らが無知な学生であることを自覚し、決して傲ることなく、これぞという若々しいパッションを世に問うてゆく姿勢のある、映画進化の現在地を指し示す作品群です。
いくら映画祭で紹介した作品が優れていようと、映画祭それ自体が称賛されるべきものではありません。ただ、結果的に多くの動員に恵まれ、関係者、ゲスト、OB・OGの各所からも素敵なリアクションをいただけたのは、番組が魅力的だったから、そして何より、委員自身が情熱を持って取り組んだからに他ならないと思っています。
1年間に渡って代表として取り組んできた映画祭に、1つの結果、結末が齎されたという感覚には、不思議なものがありました。そして私は、およそ達成感よりも先んじて、寂寥感を抱いてしまいました。
学生、サークル、仲間、映画 etc……
青年の私を取り巻いている物たちは確実に終わりを告げ、人生の新たなステップに進まねばならないという現実が、まざまざと実感されたのです。

結果的に第32回の東学祭は、世界的に見ても珍妙な映画祭になったと、今になって振り返っています。
グッズ等の製作物や、企業との関わり、他サークルとのコラボ企画に至っても、委員は各々の能う限りの立場を利用しながら、取り組んでいたと思います。ただ、半ば五里霧中になって作り上げたこの映画祭も、冷静になってから俯瞰してみると、体感的に相当ヤバいプログラムであったことは間違いないでしょう。
18本の学生映画から14本の招待作品、芥川賞作家、最年少活動弁士、著名なTikToker、ドキュメンタリー冒険家、Filmark人気ランキング1位の監督。二枚目の俳優、『カイエ・デュ・シネマ』元編集委員、エロVシネマの名手 500人以上の観客 etc……
少々失礼かもしれませんが、こういった字面だけ見ると、ありとあらゆる可能性が交差した、闇鍋とまでいえそうな凄みを感じさせる番組内容です。必ずしも学生映画に留まらず、ありとあらゆる映画の可能性について目配せしていたら、かえって一貫性のない混沌さが際立ってしまったのかもしれません。

しかも場所は、東京の異境とも呼ばれる渋谷のラブホテル街です。
少し足下の悪い平日の午後、4時間近くのプログラムから始まり、平均150分超えのプログラムは22時過ぎまで続きます。
私たちの夜の営みは金曜を超え、土曜も終わりません。
この空間は、もちろん私含む委員や、学生監督だけで作り上げたものではなかったのです。500人以上の観客やゲスト、関係者やクラウドファンディングの支援者、OB・OG、その他、予想だにしない記憶の連続。
ここには学生映画に捧げられた、情熱の時間が凝縮されていました。
33年の想いの歴史を超え、私たちの映画祭は終わったのです。
終わりに、映画祭全体を振り返ってみます。
確かに運営には、云百万の予算と時間、そして何より精神力を要しましたが、その主体は大学生という身勝手なノマドで、必ずしも映画業界に入る必要もなければ、誰もバイト代を貰う訳でもありませんでした。そして最もらしく映画の選評をする義務もなければ、業界の不文律を守る義務もありませんでした。
東学祭は、映画を好きなように評価する民主的なあり方が許されながら、実際の映画業界とも関わりが持てる魅力的な空間でした。そして普段から学生の日常を送っていても、決して巡り合うことのない新しい表現の可能性に触れ合える空間でした。
考えてみれば、私は大学生活を通じて、6、7個もの緩いサークルに籍を残していた気がします。そのどれもが気軽に入会でき、決して村八分に合うことなく退会できるリセット可能性なるものに、魅力がありました。
実際、コロナ禍によって夥しい数のサークルが散り散りになりました。そういった現状を、私は幾度となく気に病みそうになりましたが、必ずしも悲観するべきものでもないと思います。
緊張感がない飲み会に価値があれば、自我を深く沈潜させる鑑賞体験にも価値はあります。凡そ学生に限定された賞味期限の短い活動の記憶は、その多くが瞬間的に忘れ去られる宿命に曝されています。
そして社会的な意義もなければ反復不可能な、誰も知らない想いの歴史を形作ります。
私が東学祭に参加したのは、2019年5月のことでした。
通常であれば即決で辞めるであろう幾つもの面倒に遭ってもなお、私は東学祭に何かを感じ、その何かが目に見えることを期待し続けているようなものでした。そしてその期待が、掌で掴めそうな感覚を伴っている時もあれば、最も嬉々たる瞬間ですら、まるで砂のように指の隙間から零れ落ちてしまう感覚もありました。
私は、その期待を明確に掴めていない間中は、例え代表を務めていたとしても、決してモラルに反さない程度に、自らやる気を削ぎ落とすようにして取り組んでいた節もあったりします。一社会人の面をし、責任を肩代わりする恣意的な役割を全うしようといった義務感に燃えたこともありません。改めて言うと、そこには常に学生ならではのリセット可能性が横たわっていて、無責任な振る舞いが許容されていたのです。
他方で、そういった不義理を「まあ大学生だから」「若気の至り」と一笑に付してくれた方々の後押しによって映画祭が成り立ってきた経緯もあるので、感謝を尽くさなければならないと思っています。デモもヤンキー文化も時代遅れで、私はメタバースやYouTube、Instagaramで内面を迷走させている、うぶなZ世代のひとりです。仮に旧来的な大人たちが、私たちをむしろ時代を担うものとしての威勢に欠けているな! と一方的に懲戒するようなことがあれば、映画業界ひいては日本社会は自ずから優秀な若者を失い、尻すぼみに向かっていくだろう、などと悲観的に開き直ることもあります。
私は少なくとも大学生でいられるうちは、この青臭いスタンスを保っていたいと思います。自分の創作意欲や熱意を、前時代的で枝葉末節な規範で削いでくる大人より、若気の無秩序な初期衝動を大切にしている大人を慕おうと思います。彼らは出る杭を迎え入れて、自分と相対した激情的な若者を、むしろ昔の自分自身に投影して許容してくれるのです。
東学祭はこれまで、大学生どうしの至らぬ小競り合いを繰り返しつつも、学生映画の灯火を絶やしたくないという各代の想いを引継ぎながら、今日も稀に長い映画祭史を紡いできました。学生映画を取り扱う映画祭は無数にありますが、学生映画だけを専任とした、学生だけが自主的に運営し、30年以上も続いている映画祭は、日本中どこを探しても東学祭しかありません。
この記事で提示してきたように、これまで東学祭(特に21世紀以降)は次々に新しい方針を打ち立てては体力切れに陥り、先代が荒野に残した(あるいは残さなかった)多くの可能性と禍根をマイルストーンに、次代の学生たちが駆け巡ってきたようなものでした。
ただ、まさにその点にこそ本質があります。上映作品や会場、時期に至るまで、毎年違う恣意的なメンバーが、約1年間かけて自由に作り替えていく、その一過的なダイナミズム、あるいは不憫さにこそ、東学祭の価値があります。
結果的にこの記事は、概観的な通史とは程遠い、雑然とした出来事と文脈の連続になってしまったかもしれません。それでも私は、この物語の希望と絶望の多層を、例え無造作であっても系統化し、通史を練り上げてみたいという欲望に抗えませんでした。正直、書く過程で幾度となく食傷気味になりましたし、人の生き方や考え方にラベルを付け、批評を加えてしまう歴史には、多くの危険性が伴っています。ただ、筋を通すことで引き裂かれるニュアンスもあれば、むしろ筋を通すことによってしか得られない想いの歴史もあるのではないか、とも思うのです。
ただ……結局のところ、私ひとりがこういった映画祭史の大風呂敷を広げ、さも意味ありげに口を開いてみたところで、大きなインパクトにはなり得ないのでしょう。
次はこの想いを、学生映画の未来を担う学生に引き継がなければなりません。私個人がエゴの史観を提示するより、全く東学祭を知らない方が関心を寄せてくれることの方が、よっぽど尊いことです。もしこの長々しい記事に目を通していただいた上で、今も尚この文面を読んでいる方がいらっしゃれば、ぜひ次回以降の映画祭に足を運んでいただければ幸いです。
私は個人的な動機から、映画祭の想いの歴史を知るために、約33年に渡る通史を掘り起こしました。少なくとも私に可能だったのは、この映画祭史に、私個人のパーソナルな発想や言葉を乗せて、叙情的な舟で運ばせてみることでした。
そして海先の靄が晴れて辿り着く岬に、もしかすると打ち上げられているかもしれない誰かの想いに期待しながら、いずれ学生を卒業し、大人になるために、前に進み続けることでした。
遅かれ早かれ、私が生きている間には、この映画祭は終わりを迎えるでしょう。
そして1つの青春と、1つの時代は、幕を閉じるのです。

最後に、1つのアンケート結果をご紹介します。
改めて説明すると、このグラフは、エントリーをした学生監督203名(224作品)の内、回答をいただいた104名の方のアンケート結果を基にしたものです。
自分の将来は不安ですか?
自分の将来に不安が「ない」「あまりない」と答えた人は、僅かに11% 。そして「どちらでもない」と答えた人は26%、「ある」「少しある」と答えた人に至っては66%にも上ります。
つまり、過半数を超える学生監督が、大なり小なりの不安を抱えているのです。そして残りの大抵も、ただぼんやりと将来の幸福な自分像を見定めることができていないのです。
若者の自尊心の低下には、惨憺たるものがあります。ただどんな不安も、孤独も、喪失感も、絶望も、永遠には続きません。むしろ日常を生きる私たちへ宿命的に掛けられた、アサインメントのようなものだと考えた方が良いように思えます。
例え意識で変わらずとも、自分の感情はいずれ別の何かへと転回しているものです。どうしてこんな日常を繰り返しているんだろう? とまた映画を観ても、それもまた、いずれは過ぎ去っているのです。
そう信じながら、私はこの映画祭の想いの歴史を、引き受けてみたいと思います。
まだ、知らない可能性の存在を追い求めて、今この瞬間の幸せ、愛の事実を手放さないようにしたいと思います。その意志こそが、この世界の事実を越えた、真実であるはずだからです。
映画に居場所を求めていたい、あの誰かへ。
今、この時に映画を夢見ていた、あの誰かへ。

