
絶対に所属するな!「悪いコミュニティ」の怖さと見抜き方
こんにちは! かけだしコミュニティアシスタントの若林です。
今回は、JINEN株式会社のコミュニティディレクターである藤田に、「悪いコミュニティ」について話を聞きました。
「悪いコミュニティをつくらないためにはどうしたら良いのか?」・「悪いコミュニティが個人に与える影響」など、さまざまな角度から深掘りしているので、コミュニティ運営に関わる方はもちろん、あらゆるコミュニティに所属する方にもぜひ読んでいただきたい内容です!
悪いコミュニティの定義
若林:今日のテーマは「悪いコミュニティ」です。まず、「悪いコミュニティとは何か」について教えていただけますか?
藤田:悪いコミュニティを定義するうえで、まず重要なのは個人のウェルビーイング(well-being)にどう関わるかという点です。
ウェルビーイングとは、「身体的、精神的、そして社会的に良好で、すべてが満たされた状態」を指します。安心感や役割実感を得られるコミュニティに所属することで、ウェルビーイングのうち社会的健康を満たすことができます。このようなコミュニティは「良いコミュニティ」と言えます。
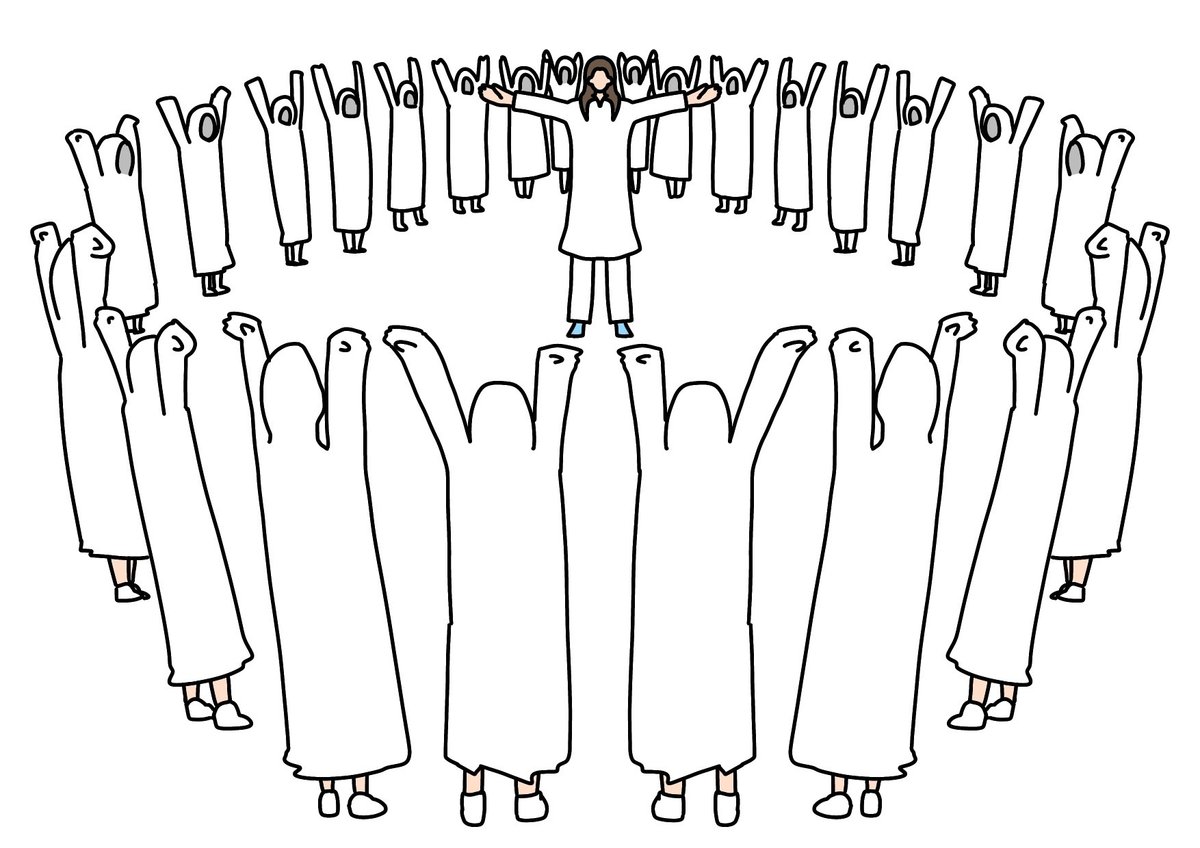
藤田:しかし、個人のウェルビーイングが満たされていても、社会的価値を欠く場合もあります。たとえば、カルト宗教は一部の人々のウェルビーイングに寄与することがありますが、社会的にはクーデターやテロなどを引き起こすリスクがあり、社会的価値は非常に低いと言えます。したがって、良いコミュニティであるためには、社会的価値があるかどうかも重要です。
さらに、事業の観点で、短期的な貢献と長期的な貢献のバランスも重要です。たとえば、軍隊のように厳格に統制して利益を追求するコミュニティを作れば、短期的には成果を上げることができるかもしれません。しかし、持続可能性がなければ、長期的には成り立ちません。このような場合、コミュニティとして良いとは言えませんよね。
この短期・長期の視点は、事業だけでなく、個人や社会全体の観点でも重要です。まとめると、「悪いコミュニティ」とは、個人のウェルビーイング・社会的価値・事業への貢献という3つの要素において、短期的にも長期的にも寄与しないコミュニティだと定義できます。
若林:個人、社会、事業の3つの軸があるんですね。
藤田:その通りです。そして、すべての要素を満たしていない場合はもちろん「悪いコミュニティ」ですが、たとえばカルトのように、1つの要素だけを満たしていて他の要素を満たせていない場合も、やはり「悪いコミュニティ」になってしまいます。
企業や個人への影響

若林:悪いコミュニティを運営してしまうことで、企業にはどのようなデメリットがありますか? また、そういったコミュニティに所属してしまった場合の個人への影響について教えてください。
藤田:まず、悪いコミュニティを運営してしまった場合、企業にとってのデメリットについてお話しします。
たとえば、企業がファンコミュニティを作ったとします。本来であれば、そのコミュニティを通じてファンが増えることを期待しているはずですが、逆にその場が企業の悪評や悪口を言い合う場になってしまうことがあります。「この企業ひどいからAmazonレビューに低評価をつけよう」なんて流れができてしまうことや、X(旧:Twitter)などでネガティブな発言が拡散されて炎上するリスクも考えられます。こうなれば、間違いなく企業の評判や事業に悪影響を与えることになります。
また、オンラインサロンのように収益化を目指したコミュニティを運営する場合も注意が必要です。オンラインサロンは「共感」を重視する仕組みですが、運営者自身がその共感を維持し続けることで疲弊してしまう可能性があります。たとえ収益が上がったとしても、運営側のウェルビーイングが低下してしまうんです。
さらに、場合によっては「怪しいコミュニティを運営している」と見られてしまい、企業のブランドイメージに悪影響を及ぼすこともあります。結果的に、運営者自身も「怪しい人」というレッテルを貼られてしまうリスクがあります。
次に、悪いコミュニティに所属してしまった場合のデメリットについてお話しします。まず、個人のウェルビーイング、つまり幸福度が下がるのは間違いありません。
また、コミュニティに所属していることで年収が下がったり、そもそも仕事がもらえなくなったりする可能性もあります。とくに業務委託やフリーランスのような働き方の場合、「この人なんか違うな」と思われるだけで仕事のチャンスを失ってしまうことがあります。これは最近、とくに顕著な傾向だと思います。
さらに、このような問題はスキルの有無とは関係がありません。むしろ、「コミュニティの雰囲気に合わない」という感覚的な理由で敬遠されることが多いんです。
たとえば、傲慢な態度や話し方がその人の印象として残ってしまうと、周囲から「この人とは一緒に働きたくない」と思われる可能性があります。そうなると、いくら能力が高くても仕事を得るのは難しくなりますよね。
正社員の場合は少し状況が異なりますが、それでも悪いコミュニティに所属していたことが原因で、不利な部署に異動させられることがあります。そうなると、当然ながら年収やキャリアの成長も期待できなくなります。とくに大企業では、リストラ候補が集められる部署に異動させられることもあります。このような環境に置かれると、どれだけスキルが高くても、それを発揮する場が与えられなくなってしまいます。
さらに厄介なのは、悪いコミュニティに所属していたことが原因でこうした影響が出ても、本人がその理由に気付くことが難しいという点です。スキル不足であればフィードバックを受けられる可能性がありますが、「コミュニティに合わない」という問題は暗黙の了解として扱われることが多いですからね。結果として、悪いコミュニティに所属していた期間が、その後のキャリアに大きな影響を与えてしまいます。
こうした理由から、悪いコミュニティは運営側にも所属側にも深刻な影響を及ぼします。企業としても個人としても、コミュニティの選び方や運営方針には十分注意が必要ですね。
悪いコミュニティはどのようにできあがってしまうか

若林:悪いコミュニティがどう形成されるのか、またどのようにそれを防ぐことができるのか教えていただきたいです。
藤田:悪いコミュニティというと、最初から悪意を持って作られたものを想像するかもしれませんが、実際には多くが善意から生まれているんですよね。
たとえば、カルト宗教でも、最初から教祖が何か悪いことをしようとしていたわけではなく、「こうすればみんなが幸せになる」と信じて始めたケースが多いと思います。ナチスドイツにしても、「ドイツを良くしたい」という前提からスタートしていて、途中で方向性が大きく変わってしまったわけです。
こういった例を見ると、悪いコミュニティが生まれる原因としては、コミュニティに参加する人を適切に選べなかったことや、世論をどのように動かすかを間違えたことが挙げられると思います。
だからこそ、そもそもの設計段階で「どんなコミュニティを作るのか」をしっかり考えることが重要なんです。それが曖昧なままだと、後から様々な人が入ってきて混乱が生じる原因になりますし、方向性がブレることにも繋がります。そして、課題が大きくなりすぎると解決できなくなり、「統制しなければならない」という状況に陥ってしまいます。そうなると、気づけば排他的な集団やカルトのような形になってしまうこともあります。
要するに、最初から明確な目標を持ち、その目標に合った人たちでコミュニティを作ることが大切だと思います。それによって、無理なく健全な方向性を維持できるのではないかと考えています。
悪いコミュニティをどう察知する?
若林: もし、個人が悪いコミュニティに所属してしまった場合、早めに気づいて離れるべきだと思いますが、どうやって早く察知すればよいでしょうか?
藤田: 以前お話しした「コミュニティの16分類」をぜひ理解していただきたいです! これを知ることで、自分がどのような環境にいるかを客観的に捉えることができます。
「コミュニティの16分類」についての記事はこちら!
藤田: また、悪いコミュニティについて知ることで、そうした環境に対する感度が上がるということもあります。
若林: 悪い環境を知ること自体が重要ということですか?
藤田: そうです。たとえば、職場体験のようなかたちで短期間でもそうした環境を経験すると、「ここはまずいな」という感覚を養うことができます。
ただし、そのままそこに居続けてしまうことが問題なので、そういった状況を避けるためには、複数のコミュニティに分散して所属することも大切です。1つのコミュニティに依存せず、他にも居場所を作ることを意識しましょう。
若林: 複数のコミュニティに入ることは、たしかに重要ですね。
私の友人の話ですが、大学院で研究室と自宅の往復だけの生活を続けていたところ、かなり精神的に追い詰められてしまったそうなんです。でも途中で気づいてフィットネスクラブに入ったところ、そこでは強い結束があるわけではないんですが、「あの人また来てるな」という程度の緩い繋がりができて、それが第3の居場所になり救われたと言っていました。
藤田: それは良い例ですね!
やはり、自分に適したコミュニティは何なのかという「コミュニティポートフォリオ」を持っておくことは非常に大事です。
最近、仕事で一緒に働いていた方が、コミュニティが合わないだけでキャリアが途絶えてしまったケースを目の当たりにしました。仕事自体は真面目に取り組んでいたのに、環境との相性が原因で結果的に職を失ってしまったんです。
若林: ええ! それは辛いですね……。
藤田: 本当にそうですよね。年収やキャリアの観点では、目標達成や課題解決を重視する良質なコミュニティに20代のうちに触れておくことも大切です。あるいは、体育会系のコミュニティに一度身を置いて経験を積むことも、有益な体験になると思います。

若林:ありがとうございます。逆に、運営者側の視点で、コミュニティが悪い方向に向かっていることを察知する方法はありますか?
藤田:そうですね。コミュニティが悪い方向に進むケースって、先ほどもお話ししましたが、やっぱり「どんなかたちのコミュニティを作りたいのか」が最初に曖昧だと起きやすいと思います。
そのかたちによって問題が変わってくるんですけど、たとえば企業の場合、売上を上げることを目指しているはずなのに雑談ばかりが増えて目標に集中できなくなる、といった状況があります。目指している方向性と逆の行動が出てきたら、それは悪い兆候だと言えます。
一方で、NPOのような団体だと、逆に「世界に行こう」とか急に革新的なことを言い始めるケースがあるんですよね。NPOとしてやるべきことに集中する必要があるのに目標とズレた方向に行ってしまうと、運営が難しくなると思います。
悪いコミュニティが生まれる原因の一つとして、設計段階で参加者を適切に選べていなかったことが挙げられます。そして運営を進めていく中で、そういうズレた方向の発言をする人が現れると、「ちょっとこの人たちは目標と違うことをし始めそうだな」という兆しが見えてくるんですよね。
ただ、これを見抜くのは難しいんです。実際、僕自身も運営していると、どうしてもその流れに引っ張られてしまうことがあるんです。だから、第三者の視点がすごく重要なんです。そういうときに僕たちのような会社に依頼してもらうことで、そのコミュニティの方向性を外部から監視できる仕組みを作れるんです。でも、それをもっと効率化したいんですよね。
今、私たちが考えているのは、たとえばコミュニティ内で目標とズレた言葉が出てきたときに、それを自動で検知する仕組みを作ることです。これをSaaSとして提供しようとしているところです。
若林:すごいですね! たとえば、Slackのようなチャットツールに導入するイメージですか?
藤田:そうです! コミュニティの会話の中で違和感のあるキーワードが出たらアラートを出す、みたいな仕組みを考えています。これができれば、運営者自身が気づきにくいズレを早い段階で検知できるので、非常に便利だと思います。
こうした仕組みがあれば、コミュニティが悪い方向に進むのを未然に防ぎやすくなるのではないかなと思っています。
悪いコミュニティほど名前を変える!?

若林: 万が一、自分が運営しているコミュニティが悪い方向に進んでしまっていると気づいた場合、どのような改善アクションが必要ですか?
藤田: そうですね。途中でコミュニティが悪い方向に進んでしまった場合、基本的には取り壊して再構築するのが最も現実的だと思います。
名前を変えるというのはよくある方法ですね。たとえば、歌舞伎町のお店などでは、看板を替えて新しい名前でスタートすることがあります。ただし、名前を変えるだけでは中身が改善されないことが多いので、本質的には内部を根本から変える必要があります。
名前を変えるのは、「悪いコミュニティが外からの見え方を変えるために行う」印象があります。一方で、良質なコミュニティの場合は名前を変えずに、内部の運営体制や仕組みを変えるケースが多いですね。
たとえば京都の例がそうで、名前はずっと「京都」のままですが、内部のコンテンツや運営方法を少しずつ改善することで良い状態を保っています。そのため、「良質なコミュニティは中身を変える」、「悪質なコミュニティは名前を変える」という傾向があるように思います。
もし良い目的で始まったコミュニティが途中で悪い方向に進んでしまった場合、中身をごっそり変える必要があります。具体的には、運営メンバーや参加しているメンバーを入れ替えることが重要です。
最初にしっかりと設計されていれば、原点に立ち返ることで良質なコミュニティに戻すことが可能です。設計がしっかりしていれば、何が問題なのかが明確にわかるので、中身だけを変えることで改善ができるんです。
つまり、最初の設計がしっかりしているかどうかが、改善可能かどうかの鍵になると思います。原点回帰が可能であれば、安心して中身を変えることができますし、それができない場合は、一度コミュニティを壊して作り直す覚悟が必要になるでしょう。
