
【COTEN RADIO まとめ】民主主義1 人類が求めた自由と平等
今回は以下の動画についてまとめています。
はじめに:複雑で興味深い「民主主義」の世界

今回の新シリーズは、「民主主義」がテーマです。いま私たちが当然のように使っている民主主義という言葉には、実は非常に複雑な背景があります。
民主主義という言葉を聞いたとき、人によって思い浮かべるものは大きく違うかもしれません。選挙制度や議会制を想像する人もいれば、革命やデモ、あるいは多数決を連想する人もいます。一方で「北朝鮮も正式名称に民主主義と入っているのに……」といった不思議な例もあり、民主主義という単語だけで多種多様なイメージが引き起こされるのです。
にもかかわらず、辞書を見ても「人民が権力を所有し行使する政治原理」とだけ書かれていたりするので、詳細まではよく分からないという方も多いのではないでしょうか。そこで、今回のシリーズでは、まず民主主義の起源や発展を歴史から見ていきます。そうすることで、私たちが当たり前だと思い込んでいる制度が実はどんな道のりをたどってきたのか、その正体に近づけるのではないでしょうか。
現代に見られる「民主主義の揺らぎ」とは

近年、さまざまな国で「民主主義の機能不全」や「危機」が取り沙汰される場面が増えました。代表的な例を挙げると、以下のようなものがあります。
ブレグジット(イギリスのEU離脱)
イギリスは国民投票でEU離脱を決めましたが、キャンペーン中には虚偽情報が流布されたり、過激な主張で大衆を煽る手法が目立ったと指摘されています。この「国民投票で重大な決定をするのは、情報操作されやすいし危ないのではないか」という声が、「ポピュリズム(大衆迎合主義)」として取り上げられました。アメリカ・トランプ政権の登場
2016年に誕生したトランプ大統領の言動も「ポピュリズム的だ」と批判されました。移民に強硬な姿勢をとる主張や、メディアを痛烈に批判する態度、さらにはSNSでのフェイクニュースが飛び交った選挙戦などが、民主主義の脆さを象徴する事態だと論じられたのです。こうした政治スタイルが、むしろ支持を集める状況をどう捉えるかが議論されました。強力な指導者が続々と誕生
ロシアのプーチン大統領や、中国の習近平国家主席など、権威主義色の強いリーダーが再選や長期政権を実現しています。民主主義の国々では「独裁的ではないか」と懸念する声がありますが、一方で「緊急時には独裁的リーダーのほうが迅速に対応しやすい」という見方もあり、効率性を称賛する意見もあるのです。
かつては「世界の国々はいずれ民主化へ向かう」と多くの人が信じていました。しかし今では、民主主義そのものに疑問を投げかける動きも増えています。興味深いのは、こうした懐疑や批判は、実は古代から繰り返し起こってきたという点です。
2600年前のペルシア帝国が示す、民主主義をめぐる議論

紀元前6世紀頃、ペルシア帝国では「どのような政治形態が国を安定させるのか」という議論が交わされた記録が残っています。カンビュセス王の跡を継いだダレイオス1世が、重臣たちとともに「民主制」「寡頭制(有力者による支配)」「独裁制」のどれが良いかを話し合ったのです。
オタネスの主張(民主制)
独裁者が責任を負わずに暴走する危険を指摘しました。民衆が自発的に政治に参加し、皆が平等に権利をもつことこそ、社会を安定させるのにふさわしいと訴えました。メガビゾスの主張(寡頭制)
大衆は無知で煽動されやすく、適切な国政ができないと反論しました。少数の優秀な貴族やエリートに権限を集める寡頭政治が最も合理的だと主張しています。ダレイオスの主張(独裁制)
民主や寡頭といった仕組みも、紛争や対立を経て結局は独裁へ収斂してしまうから、最初から「優れたただ一人」が権力を握るほうがいいと考えました。
最終的に、投票の結果、ダレイオスの言い分が採用され、ペルシア帝国は独裁体制を維持します。驚くのは、2600年前に交わされたこの3つの主張が、現代の「民主主義は愚衆政治になる」「いや、多数決で決めるべきだ」「独裁のほうが筋がいい」といった議論とほぼ同じ構図を持っていることです。
古代から続く議論は現代でも繰り返される
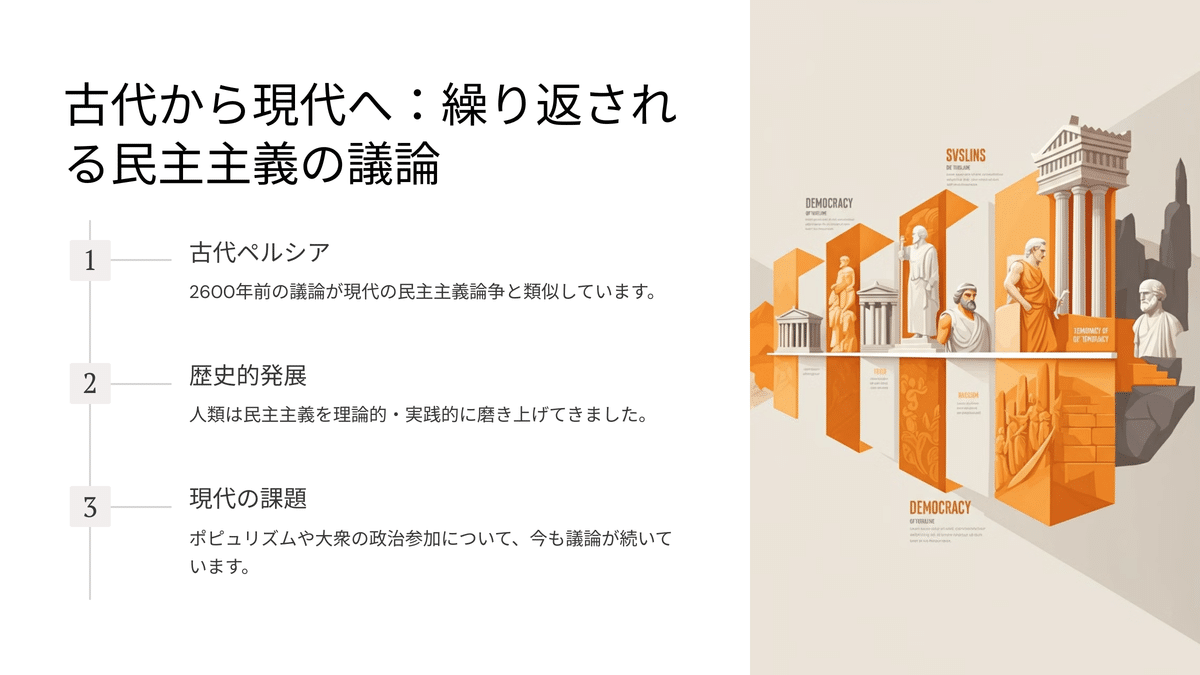
ダレイオスたちの議論は、言葉こそ古風ですが、本質的には今の私たちが抱える「民主主義のメリット・デメリット」に通じています。そして彼らは自分たちの結論として「独裁」を選びましたが、人類はその後もさまざまな時代に似たような議論を積み上げ、民主主義をどう扱うか試行錯誤してきたのです。
私たちが今もSNSや世論調査などで騒ぐ「ポピュリズムの危うさ」「専門知識をもたない大衆に国の方針を任せていいのか」という声は、まさに2600年前と同じ議題だともいえます。しかし、そのあいだに人類は圧倒的に多くの歴史を経験し、民主主義を理論的にも実践的にも複雑に磨き上げてきました。それを無視して同じレベルの結論に陥ってはもったいない、というのが今回のシリーズの出発点といえます。
次回予告:古代ギリシアの民主制
とはいえ、ペルシア帝国やメソポタミア文明にすでにあった合議制・民衆支配的な要素が、「本格的な民主制」にまで発展したのは古代ギリシアだといわれます。ギリシアで用いられた「デモクラティア(人民の力)」という言葉が、後世のヨーロッパ政治思想や現代の世界各国の制度に多大な影響を与えました。
次回は、いよいよ古代ギリシアの民主制を深く掘り下げます。私たちのイメージに近いようでいて実は大きく異なる、古代ギリシア特有の仕組みとはどういうものだったのか。そして、なぜそれが歴史の流れのなかで一旦消えたり、また復活したりするのか……民主主義の真髄を探る旅は、ここから本格的に始まります。
