
災害リスク上昇時代 自然災害に耐える住まいとは
9月の台風15号、10月の台風19号と、2つの巨大台風が日本列島を襲った2019年。災害への備えがいかに大切か、実感した方も多いはずですが、住まいの観点からは、どう備えればいいのか。数々の住宅を見てきた長嶋修さん(株式会社さくら事務所 会長)にポイントを解説していただきました。
屋根の被害が目立った台風15号
台風15号の通過後、私は千葉県館山市へと向かいました。罹災(りさい)証明書を発行する自治体の職員に同行し、判定の様子を見学するためです。
家屋の被害状況は「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」「無被害」の5段階に分けられますが、判定するのは、必ずしも建築の専門家ではありません。そのため、判定は非常に難しいようで、評価も人によって差がありそうです。
屋根の被害については、「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」に沿って施工されていたかどうかが分かれ目になったことが明らかになっています。調査をした業界団体は、ガイドラインに沿ってつくられた瓦屋根は、被害を免れていると報告しています。
また、通常、屋根が飛んだだけなら「一部損壊」として扱われます。しかし、現実的に考えれば、屋根がない住宅では暮らせません。政府が要件を緩和し、屋根が大きく破損した住宅を「半壊」とみなすことになったのは、良い判断だったといえるでしょう。
さらに、壊れた建物を補修する段階になると、不当に高額な費用を請求する業者が現れるなど、二次的な被害も発生しています。
浸水リスクが浮上した台風19号
台風19号では、河川の決壊や、処理しきれなかった雨水で市街地が浸水する被害が、首都圏や長野県で発生しました。近年、開発が進む神奈川県川崎市の武蔵小杉駅周辺では、2棟のタワーマンションで、地下の電気設備が浸水。結果、各戸の停電に加えて、エレベーターが止まり、水道のポンプが動かずトイレも使えないという状況がしばらく続きました。

武蔵小杉、あるいは多摩川の周辺は、以前からハザードマップで浸水のリスクが指摘されている地域でした。堤防の整備によってできた土地には、まず工場ができ、最近になって、タワーマンションが建ち並ぶようになりました。
土地の利用方法が変わっていくにつれ見過ごされていたリスクが、巨大な台風で改めて明らかになった、ということでしょう。
被害を受けやすい住宅とは
台風に弱い住宅を見抜く
台風で被害を受けやすい建物には、いくつか特徴があります。いくつかあげてみましょう。
●1階が半地下
住宅密集地では、土地を掘って地面よりも低い、半地下の部屋をつくっている住宅をよく見かけます。こうした住宅は、多量の雨が降ると、下水管から水が逆流したり、道路から雨水が流れ込むことになりやすいのです。浸水すると、半地下部のドアが水圧で開かない、トイレがあれば排水が逆流する、などの事態が想定されます。
●軒がない
最近は、デザイン性を高めるためだったり、敷地が狭かったりして、軒の出が少ない・まったくない、いわゆる「軒ゼロ」の住宅も増えていますが、軒の出がないと横殴りの暴風雨で雨漏りが起こる可能性が高くなります。屋根裏の点検口から雨漏りの有無を定期的にチェックしておくことをおすすめします。
●オーバーフロー管のないバルコニー
排水口がつまったり、豪雨で多量の水がたまったりしたとき、二次的な排水口として機能するのがオーバーフロー管です。室内に水があふれていかないよう、サッシよりも下に取り付けなくてはならず、後からの設置には工事方法や取り付けの位置に注意が必要です。
●雨戸がない
軒と同じように、雨戸のない住宅も増えています。外観、コストダウンなどがその理由ですが、暴風で飛んできたものを防ぐには、ガラスだけでは限度があります。シャッターを後付けしたり、ガラスの飛散を防ぐフィルムを張ることで、ある程度の効果は得られるでしょう。

●バルコニーや屋上の防水の劣化
バルコニーや、マンションの屋上には、雨漏りを防ぐための防水工事を施します。FRP(繊維強化プラスチック)防水、ウレタン防水、シート防水、アスファルト防水など、さまざまな工法がありますが、いずれの工法でも劣化が進んだり、破損部があればそこから水が流れ込みます。耐久年数は工法によってまちまちではありますが、点検と補修が欠かせません。
「水災補償」で経済的な備えも
水害にあってしまった場合の金銭的な備えとして、火災保険の「水災補償」を利用しましょう。水害、そして竜巻や台風の強風、雷やひょうによる被害が対象になります。また、雪の重みによる屋根の破損も、補償の実績があります。
水災補償は、基本的にオプション契約となります。これから保険に加入する場合も、既に加入している場合も、よく契約内容を確認しておきましょう。
気候変動による大規模な自然災害のリスクは、年々高まるばかりです。これから家を建てる方、買う方、あるいはマイホームを既に手に入れた方、それぞれポイントは異なりますが、万が一の事態を想定して、できる限り備えておきたいところですね。
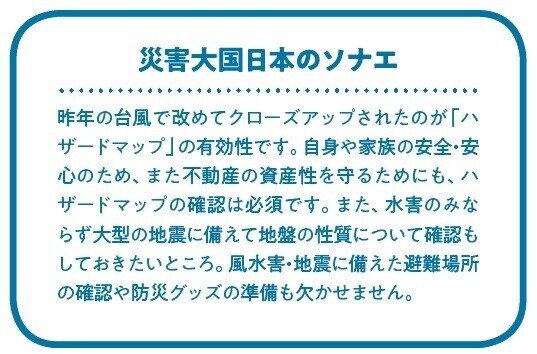
※本記事は「だん06」に掲載されています
★高断熱住宅専門誌「だん」についてはこちらをご覧ください
