
弦と弓毛の摩擦
楽譜に指示があります
ppとかffとか表現していくにはどうする?
大きな音が出れば、小さな音も出せる?
どうして音は大きくなる?
(前回の続きです)
音量は弓の圧力と速さ
ここから理屈っぽいです。
音量は周波数と弦の振幅(振れ幅)ですね。
振幅が大きいと音量は大きい。
同じ周波数で振幅が大きいということは、
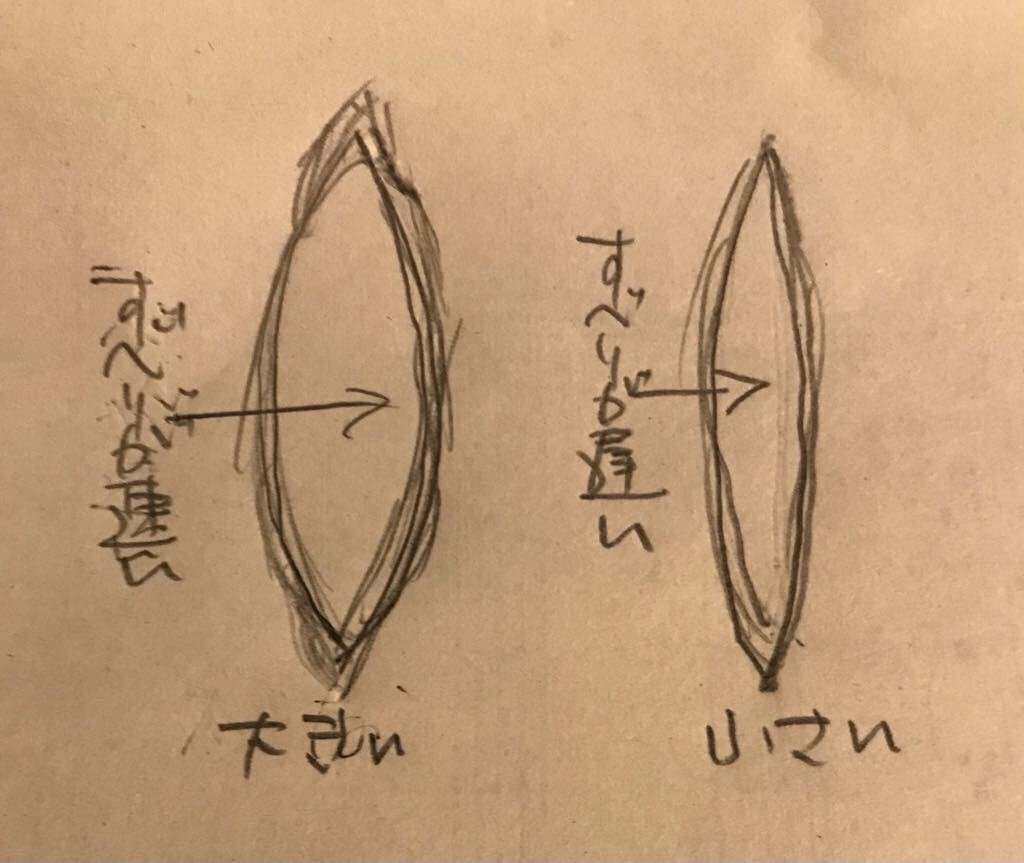
つまり、弓の速度も速くなきゃだめ!
(ついてきてくれてますか?)
次に
短い時間で弦を横にギュッて引っ張るために、
摩擦を大きくしたい。
振幅を大きくするということは、弦を横に動かす力が沢山いる。
だから、見合うだけ弓を弦に押し付けなきゃいけない。
ここが謎なんだけど、
引っ張ったら、どっかで反対方向に戻るわけで、
戻ってる間は弓と弦は滑ってなきゃいけない。
押さえつけすぎると、
戻る邪魔になって、音が こも る。

静止摩擦と動摩擦という単純な話は法則ではなくて、信用しすぎてはいけない。
でも、弦と弓の場合は静止摩擦>動摩擦
でも良さそう。振幅が最大になった時に滑り始め、
反対側まで振れると止まって
また引っ張られて振幅が最大になる
だから、
欲しい音量に見合った速度と圧力を体で覚える練習をしよう。
大きな音の時は弓が足りなくなる、
小さい音なら弓はゆっくり、
って常識ですよね。
考えるまでもない?(笑)
長々とここまでお読みくださった方々、ありがとうございます。
