
【社内研修レポート】FPと一緒に考える「マネーリテラシー研修」
こんにちは。アンバサダーのうめちゃんです。
みなさんは金融教育を受けたことがありますか?
ある調査(※金融広報中央委員会実施の金融リテラシー調査(2022年))によると、18~79歳の人のうち、「金融教育を受けたことがある」と認識している人の割合は、米国20%に対し、日本はわずか7%。
それに対し、今の子どもたちは、学校の授業で金融教育を受けています。
つまり、社会人である私たちの世代が、金融に関する基本的な知識を得るためには、自ら学ばないといけないのです。
そこで今回は、おとなの金融教育の一環として、マネーリテラシー(金融リテラシー)をテーマに社内研修を開催しました。その様子をお伝えします!
(執筆者:アンバサダーうめちゃん)
<うめちゃん 自己紹介>
・3人の子をもつ働く母、現在育休中
・趣味は時間管理、模様替え
・家族に障害をもつ者がいることから「障害者雇用」に関心があり、JPTにてボランティアとして参画中
企画のきっかけ
JPTでは新入社員に対し、金融教育を受けられる環境を用意しています。
具体的には、人事部門にて厳選したYouTube動画を視聴するように推奨しており、フルフレックス・フルリモート勤務でも均質かつ良質な情報提供ができるように工夫しているのです。
しかし、社長の阿渡さんとしては、それだけで足りているか不安でした。
その背景には、「社員の皆さんには社会人として自律しながら生活していってほしい」という想いがありました。特に、JPTの社員は障害をもちながら働く人たち。障害が原因でいつ働けなくなるかわからない。先々の見通しを立てながら、現在の収入の使い方を考えてほしい。
一方で私自身は、職業柄、FP(ファイナンシャルプランナー)資格を保有しているものの、それらの知識を誰かのために役立てた経験はありませんでした。自分の経験を活かしたい、JPTの皆さんのお役に立てたらうれしいな、という思いで、金融教育に関する研修を企画してみました。
研修の目的と概要/ねらい
①目的
社会人として必要なマネーリテラシーを学び、自律しながら、自分らしい人生を送れるようにするため。
②概要/ねらい
・約40分の講義形式
・導入:今の子どもたちが学校で金融教育を受けている現状と背景を知り、マネーリテラシーを学ぶ意義を確認する。
・(第一部)家計管理のキホン:高校向けの教育現場で活用している資料を用いながら、収入・支出・貯蓄の基本的な管理の仕方をつかむ。
・(第二部)自動車保険の見直しポイント:金融商品の一種である自動車保険に着目し、「自身の契約内容は最適化されているか」自己点検できるようになる。
研修風景(一部抜粋)
-研修内容の一部をご紹介します!
①家計管理のキホン ~支出はneedsとwantsに区別して考えよう~
支出項目については、
必要なもの(needs)と欲しいもの(wants)に分けて考えてみること
→必要なものから先にお金を使い、欲しいものはお金に余裕があるときにする、という考え方を取り上げました。
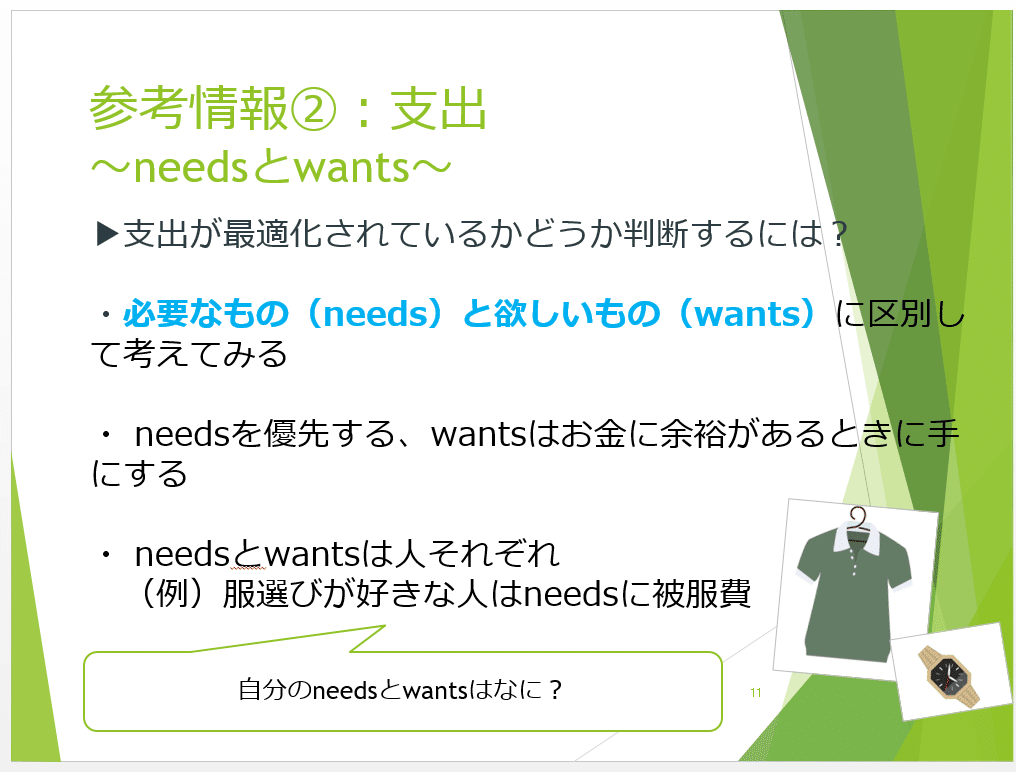
②自動車保険の見直しポイント ~運転者の年齢条件/運転者の範囲~
自動車保険には、運転者の年齢条件や範囲を限定する特約があります。
自分や家族の保険契約が自分たちに合った内容になっているか、過剰な保障により無駄な保険料を支払っていないか、確認すべきポイントを共有しました。
③お楽しみ企画 ~毎月の貯蓄額アンケート~
研修途中のブレイクタイムとして、参加者に対し、「毎月、どのくらい貯蓄している?」をテーマに緊急アンケートを行い、結果を皆さんで確認してみました!堅実に貯蓄されている方の割合が多かったのが印象的でした。

感想
-研修後、こんな感想をいただきました!
・貯蓄や保険のことなどを普段あまり考えないタイプだったので、良い機会となりました。
・needsとwants、改めて見直してみます。
・貯金はそれなりに増えていますが、「最低限の生活しか送っていない」という状況になっていることに気づくことができました。
・「年齢条件や使用目的に応じて、自動車保険の保険料が変わる」というのは初めて知りました。
・現在、貯蓄0なので、貯蓄のコツなどの話も聞いてみたかったです!
・個人的にJPT社員の毎月の貯蓄額を知れてよかったです。
研修を振り返って(うめちゃん所感)
「自分らしい暮らしとは何か?」
「支出におけるneedsとwantsは何か?」
さまざまな答えがあるこの問いに対して、皆さんで語り合う企画も面白そうだなと思いました。お互いのお金に対する価値観を通じて、相互理解が深まるよい機会となりそうだと思ったからです。また、私個人的には、自分の経験を活かし、誰かのためになった喜びが何よりも収穫でした。
参加者の皆さま、実現を後押ししてくださった人事部門の皆さま、ありがとうございました!
