
「メンデルスゾーンの手紙と回想」を翻訳してみる! 33
第4章-9.フランクフルト、1836年:メンデルスゾーンの婚約
この手紙を受けて、私はホンブルクからアクセス容易なヘーヒストでメンデルスゾーンと会う約束をしようとした。だが、下記のことから分かる通り、それは叶わなかった。
コブレンツ、1836年8月27日
親愛なる「古典戯曲」くんへ(※1)、ケルンで君の手紙を受け取りました。大急ぎでこれだけ書いています。積もる話は書くより話す方が早いので。
マインツからフランクフルト、そしてヘーヒストへ向かうのがいつになるか、はっきりと伝えることができません。
上司(外科医)の命令により、今日は僕のどんくさい足の上にヒルを載せておかなくてはならなくなりました。そして明日もここに留まり安静にせよとのことです。フランクフルトへ行きそこへ滞在するのは絶望的になりました。月曜の夜には行けるといいのですが、もしかしたら明日の朝もまだ動けないかも。いずれにせよ、不確定すぎて君との待ち合わせができないのです。
僕はヒルに従わなくてはいけません。何にしろ君に会いにホンブルクへは行けなかったでしょう。魅惑の自由都市があまりにも遠く感じます。僕がかの街をどれだけ恋い慕っているか、君はよく知っているでしょう。
すぐ返事を書いて、フランクフルトの郵便局留めで送ってください。君がいつ、どうやって戻ってくるか教えてください、君と会いたいのです。みなさんによろしく、元気で、長調で、あらゆる種類の6-4コードを君に。
君の F.M.B.
メンデルスゾーンの婚約は、私がホンブルクに滞在している間に交わされた。この素晴らしい出来事については、多くの人が語っている。
ある日の昼下がりに、彼は婚約者とその妹と共に我々を訪ねてきてくれた。しかし、彼と彼女が共にいた時間はとても短かったので、二人が恋人らしく幸せそうにしている様子を見せてくれと頼めなかった。
九月も終わりに近づくと、早急にライプツィヒの職務に戻らざるを得ず、セシルの祖父母が「サンドホフ」で開いてくれた婚約祝いの村祭り(※2)に留まることすらできなかった。
彼は、私の母から借り受けた古い馬車を駅馬に曳かせて出発した。私はイタリア行きを延期して、チェチーリア協会の指導を引き継いだ。
※注1:これまでに一、二回言及した私の最初の演奏会用序曲ニ短調には「フェルナンドの古典戯曲による序曲」というタイトルがついている。そのため、「古典戯曲」という表現が頻出する。出版時にはタイトルを省いた。今やその古典戯曲は古典になりすぎてしまったからである。
※注2:書簡集の187頁、1839年7月3日の記事を参照のこと。(https://www.gutenberg.org/files/50473/50473-h/50473-h.htm)
解説という名の蛇足(読まなくていいやつ)
前回は、ホンブルクで転地療養中のヒラーと、ようやくオランダから帰ってこれるメンデルスゾーンがどこで会えるか、という話で終わっていた。
冒頭から結論になるが、フランクフルトとマインツの間で落ち合ってフランクフルトまで一緒に戻る、というメンデルスゾーンの提案は実現に至らなかったようだ。
8月28日のゲーテの生誕日を一緒に祝いたい、と話していたのに、ここで取り上げられている手紙は8月27日付。コブレンツからホンブルクに送られた、本人も書いている通りとにかく用件だけ急いで書いた短い手紙だ。
メンデルスゾーンからヒラーへの手紙の書き出しは、ここまでたいてい「親愛なるヒラー(Dear Hiller)」あるいは「親愛なるフェルディナント(Dear Ferdinand)」だった。
だがここにきて突然「親愛なる古典戯曲くん(Dear old Drama)」というあだ名が登場した。
注釈にある通り、この頃ヒラーが力を入れて作曲していた『演奏会用序曲ニ短調』の初期タイトルからきているらしい。
ヒラーの演奏会用序曲第1番ニ短調(op.32)は、ユリウス・リーツに献呈されている。出版されたのは1844年だ。
下の画像は、ヒラーの演奏会用序曲第1番ニ短調の初版表紙。
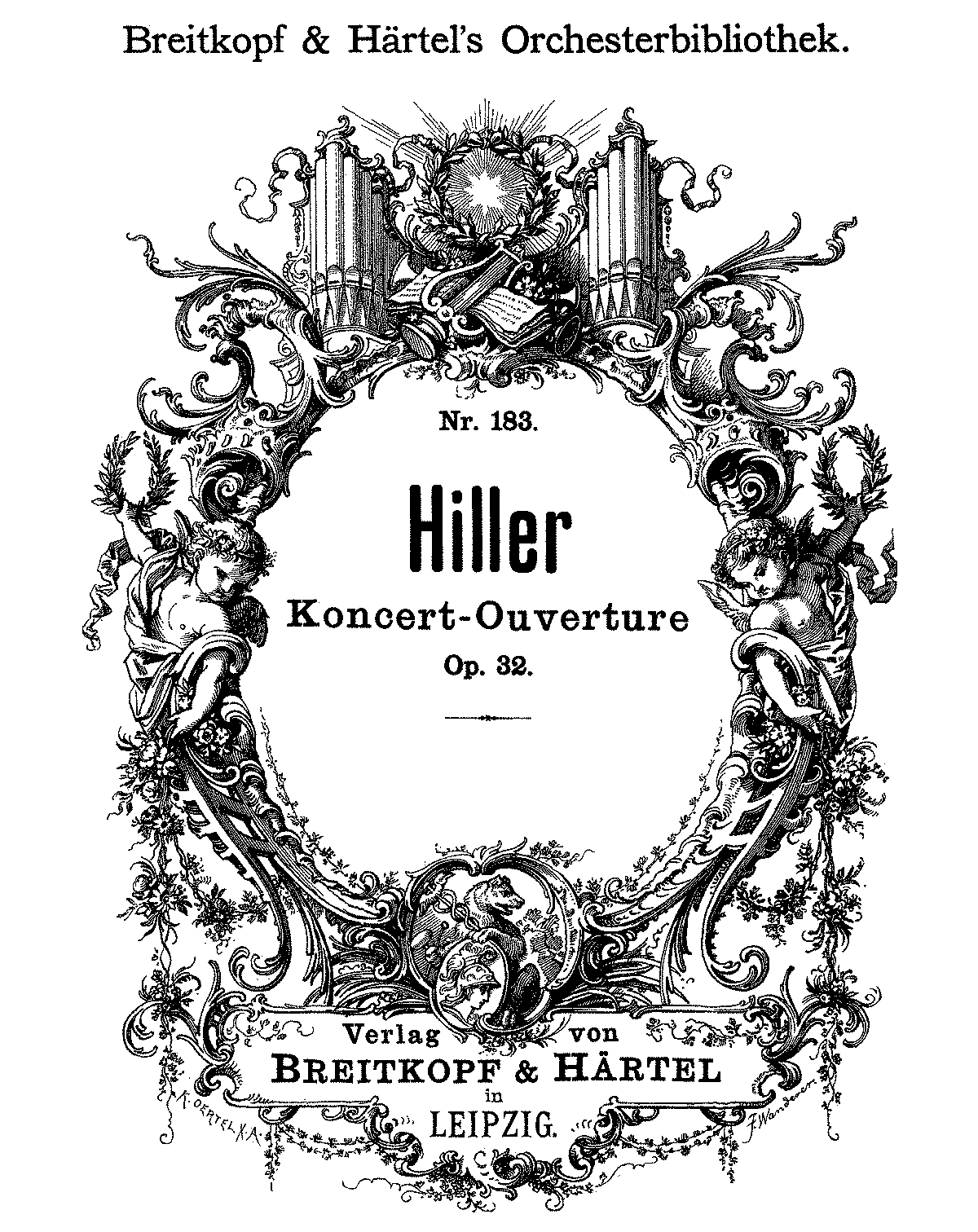
画像:IMSLP
当時の楽譜の表紙ってすごく装飾的でカッコいい。表紙だけで画集ができそう。
しかし、8年程度で古典戯曲が「古典になりすぎる」ことがあるのかはよく分からないが、当時の流行りすたりは早かったんだろうなあとも思う。
以前の記事で19世紀前半は古典劇のリバイバルが流行ったと説明したが、1844年にはもう流行りは終わっていたのかもしれない。
フェルナンドというのは、フェルナンド・デ・ローハス(Fernando de Rojas,1470-1541)のことかと思われる。
スペインの法律家・政治家だが、学生の頃に書いた唯一の戯曲「ラ・セレスティーナ(La Celestina)」が、スペインにおける中世期とルネサンス期の過渡期の作品と見なされ、歴史的に評価されているのだとか。
詩のような対話劇のような小説のような、独特のスタイルで書き上げられているとのこと(筆者は未確認)。「情熱の処女(おとめ) スペインの宝石」というタイトルで1996年に映画化もしているらしい。
ヒラーの名前フェルディナントのスペイン語読みはフェルナンドだ。
同じ名前の作家による古典戯曲をタイトルに冠した曲の楽譜を、おそらくメンデルスゾーンは草稿の頃から何度も目にしたはず。
からかい交じりに「古典戯曲くん」なんて呼び始めることも、メンデルスゾーンならやりかねないと思ってしまう。それくらい、メンデルスゾーンのおちゃめさには十分に触れてきた。
「上司(外科医)の命令により」という言い回しも、相当茶目っ気がある。
底本の英語版、ドイツ語の原著ともに「par ordre de moufti」というフランス語(風)の熟語になっているのだが、現代のフランス語ではこの熟語をあまり使わないのか、フランス語のサイトが全くヒットしなかった。
むしろドイツ語の辞書に採録されているのを見つけた。不思議な現象だ。フランス語からドイツ語に入ってきたけどフランスでは消え、流入先でだけ残った。ラ・フランスみたいだね。
意味としては「(技術的な理由でなく権力による)上からの命令」を指す皮肉表現らしい。日本語でいうと、「お上からのありがたーいお達しでねェ」という感じだろうか。
「Moufti」はイスラム法学の最高評定者のことだそうだ。ムフティの決定には誰も逆らえないとのこと。
前回の手紙で「君よりずっと軽傷だよ」と書いていたはずの足のケガが、どうやら尾を引いていたらしい。
ヒラーはメンデルスゾーンの提案に賛成し、ホンブルクから行きやすいヘーヒストで落ち合おう、と手紙を送ったようだが、今度はメンデルスゾーンの方にトラブルがあったわけだ。
「par ordre de moufti」という言い回しからは、「外科医の先生に絶対安静って言われた! 僕は大丈夫だって言ってるのに!」という行間の文句が読みとれる気がする。でも逆らえない。
コブレンツから手紙を書いているのなら、まだ伯父さんのところに滞在しているのだろうし、可愛い甥っ子の足のケガを心配した伯父さんが医者を呼んだのかもしれない。もしそうだと、さすがに断りづらい。
その外科医がメンデルスゾーンの足の捻挫に施した治療は、生きたヒルを患部に這わせ血を吸わせる、ヒル療法だった。
ヒルによる治療は、古代エジプトの時代から存在し、世界のあらゆる(ヒルが生息している)地域で行われてきた。ヨーロッパでは19世紀が最高潮と言えるほど発展かつ重要視されていた治療法だ。
病気や体調不良、なんならメンタル不調まで、「原因は悪い血が溜まっているせい」という考えのもと、その悪い血を抜くことで症状はよくなると信じられてきた。ヨーロッパが舞台の時代物によく出てくる「瀉血」というやつだ。
ある特定の症状に対して適切に行えば、効果がある療法なのかもしれない。が、歴史を見ると瀉血で助かった人よりは、瀉血で症状が悪化して死んだ人の方が多いような気がする。
モーツァルトやバイロン、ワシントンなども瀉血が死の遠因になっているように見える。みんな1週間などの短期間で数リットルもの血を抜かれたらしい。クラクラしてきた。
身体の一部に傷をつけて出血させる方法に比べれば、ヒルは抜く血の量を調整できるとも言える。また、ヒルが吸血後に分泌する唾液の中には、治癒を助ける成分が含まれているという研究もある。
ヒル療法は一度は廃れたが、現在においては再注目されてもいて、医療用ヒルの導入や、多くの医学分野研究も続けられているそうだ。効果ゼロの全くのトンデモ療法ではないのだと思う……けど大多数の人にとって、進んで受けたい療法ではないかなあ。
生理的に無理! な人も多そうなヒル療法、メンデルスゾーンはさして嫌がってもいなさそうだ。「僕はヒルに従わなければなりません」なんて、またユーモラスなことを書いている。
ヒルに足を這われるよりも、フランクフルトに戻れないことの方がずっと痛手だろう。
ゲーテの生誕日をフランクフルトでヒラー(やセシル)と共に祝うという夢は潰えてしまったが、別日でもいいから会いたい旨と、毎回書いてるのかな? と疑う返事の催促、「元気で、長調で、あらゆる種類の6-4コードを君に」という音楽家らしい結びの言葉で短い手紙は終わりだ。
この結びの言葉、音楽に詳しくない筆者には浅い推測しか出来ない。「長調で」は何となく、明るい音楽をって意味かな……と思えるのだが、「あらゆる種類の6-4コード」とは何ぞや???
ざっくり調べてみたのだが6-4コードとは三和音の第二転回形で……日本語では四六の和音と呼ぶようだ。何故逆転した。
参考サイト:作曲法サポートページ/和声読本
詳しいことは和声学に詳しい方に聞いてみてください。
参考サイトによれば、四六の和音は「れっきとした不協和音」とのことで、手紙の結びで相手に送るものとしてはどうなんだ? と思わなくもない。
四六の和音は単独で使われることはなく、協和音の間に挟むようにして使うとのことなので、ここからは完全に個人的な意見というか推理になるのだが、「あらゆる種類の6-4コード」を送ることで、すぐ後に協和音=良い事がきますように、という意味なんじゃないだろうか。
音大出身の相方にも以前、「不安定な音は安定な音に帰りたがる」といった趣旨の話を聞いた(超余談だが物理学畑や化学畑の人もだいたい同じこと言う)。
足のケガやなかなか会えないことなど、あまり良くないことが続いているけれど、ここで四六の和音鳴らしとくからね! きっとすぐ、君に良いことが起こりますように! という予祝だとしたら、なんだかホッコリする。
手紙のあと、ヒラーの回想としてメンデルスゾーンの婚約が語られる。
あっさりしすぎていて拍子抜けなのだが、ヒラー自身側にいなかったのだから仕方ない。
俺以外にもたくさんの人が、メンデルスゾーンの回想録や書簡集などで語っているからそっち読んで、ということか。
ヒラーはわりとそういうことよくする。だいたい「デフリーントの伝記読んで」とか「公開書簡集読んで」とか言ってくる。
でももしかしたら、自分のホームタウンのフランクフルトで婚約が交わされたにも関わらず、自分はその場にいられなかった悔しさとか拗ねた気持ちも少しあるのかもしれない。メンデルスゾーン風に言うと「フランクフルトにいたかった!」だ。
晴れて婚約者同士となったメンデルスゾーンとセシルは、セシルの妹と共にホンブルクまで訪ねてきてくれた。
しかし滞在時間は短く、ヒラーも「ヒューヒュー熱いね! もっとお前らのイチャイチャを見せてくれよ!」などと下世話な声をかける暇はなかったとのこと(語弊)。
メンデルスゾーン達がホンブルクを訪ねたのがいつなのかは分からないが、この手紙の日付を見る限り、9月に入ってからのことと思われる。
そして9月の終わり近くには仕事のためライプツィヒに戻らねばならず、哀れメンデルスゾーンはまたもや「フランクフルトにいられたらよかったのに!」を口癖とすることになってしまう。
滞在期間1か月弱……ノロケはうっとうしいが、さすがにちょっと可哀相になってきた。
セシルの祖父母とは、以前紹介したフランクフルトの名士・スーシェイ家当主だ。彼らが婚約祝いの席を開いてくれたとのことで、さぞ豪華なパーティーだったんだろうな~と思いながら訳したら、「婚約祝いの村祭り」と出てきて何度か辞書を引きなおした。
パーティーなんてもんじゃなかった。レベルが違う。村をあげての祭りだ。もしかしたら誤訳かもしれないが、面白かったのでこのままにした。
注釈のついている公開書簡をざっと確認したが、確かにこれは村祭りだわ、という内容だった。英語版なのでページ数などは少し違うが、ここなどで読めるので、お時間ある方はぜひ。母宛の書簡だった。
The Project Gutenberg/ EBook of Letters of Felix Mendelssohn-Bartholdy from 1833 to 1847, by Felix Mendelssohn-Bartholdy
サンドホフというのは、以前の記事に登場したガーデンレストラン・マインルストみたいなものを想像していたが、当たらずとも遠からず。
長いことドイツ騎士団の荘園だった土地で、城壁に囲まれた広大な庭とマナーハウスがあり、周辺では羊の放牧をしていた模様。これがマナーハウスなのか軍事施設なのかでちょくちょく揉めていたようだ。

画像:Wikimedia Commons
この絵画は1810年頃の、サンドホフのマナーハウスの様子。なかなかにぎわっている。
サンドホフは1809年のドイツ騎士団解散以降、裕福な銀行家ベスマン氏の持ち物になり、のちにフランクフルト市に組み込まれた。19世紀当時は娯楽やパーティによく使われたようだが、マインルストよりは客層がハイソな感じ。
フランクフルトに住む上流階級のつながりで、スーシェイ家とベスマン氏が知り合いだった可能性はある。持ち主(知り合い)に頼んでここを借り切って村祭りをしたのかもしれない。太っ腹だ。
しかしこのお祝いにメンデルスゾーンは最後まで参加できず、途中でライプツィヒに戻っている。婚約祝いなのに主役不在なんてかわいそう……セシルさんも寂しくなかったかな……と190年前の人々を心配してしまう。
病に倒れたシェルブルさんの代理としてチェチーリア協会の指導に来たメンデルスゾーンだったが、9月も短期間しか指導はできなかった。
イタリアへ行くためにパリを引き上げてきたはずのヒラーが、チェチーリア協会の指導を臨時代理として引き継ぐことになる。
この後シェルブルさんは療養の甲斐なく、翌年の1837年に48歳の若さで亡くなってしまう。シェルブルさんの死後、正式にチェチーリア協会の二代目指導者に就任したのは、フェルディナント・リースだった。
次回予告のようなもの
遠距離恋愛を乗り越えたと思ったらなんかいろいろすっ飛ばして婚約しちゃった感が否めないスピードだが、婚約おめでとうメンデルスゾーン!
次回からはまたメンデルスゾーンの「フランクフルトにいたかった」が復活する。
次回、第4章-10.真の友人とは の巻。
来週もまた読んでくれよな!
いいなと思ったら応援しよう!

