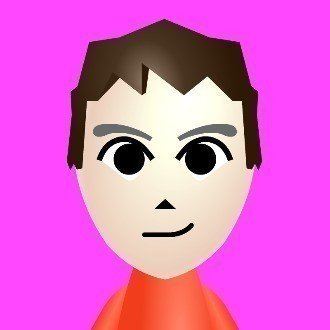ParsonsDT 夏のデザインキャンプまとめ
こんにちは。Parsons美術大学 Design & Technology Program(以下DT)に留学中のMASAです。NYに来て3週間が経ちました。
私の学部では秋学期に先駆け、生徒・教授陣全員参加による3週間の夏のBootcampいう名物コースがあり、この金曜に無事に走り抜けたので、今日はその中身や雰囲気をお伝えします。

世界中から集まった同じチームメイト・講師
日本で働いていた時より寝れなかった3週間
下がこのBootcamp3週間のスケジュールです。

毎日、各2.5hのWEB / DESIGN / CODEの3トラックの授業があり、放課後もDTの教授陣のプレゼンを聞いたり、金曜日には2nd yearの先輩のデモを見ながらPizza Partyがあります。

金曜日はFree foodで教授や先輩のデモを見るPizza Party!!
また、放課後や土日にあるソフトや技術の講座にも顔を出していたので、朝9時 - 夜9時で学校に残り、帰ってそこから3トラック分、次の日の宿題をこなす毎日で、普通に寝れませんでした。ですが久々に自分のインスピレーションの赴くまま創作制作ができ、充実感でいっぱいです。
Demo or Dieの WEB Track
各トラックの講師は2nd yearの先輩達が務めます。WEBトラックでは、各回html / CSS / js の基礎講義があり、アウトプットとしては3週間で自分のポートフォリオサイトを作ります。コーディング経験0の人も動くものを、経験者はさらに攻めたチャレンジや改善が要求されます。

ランチ時の我々のデザインスタジオ・通称D12
Demo or Die(動かないものは無価値)と言われる一方、Why / Whatの部分も毎回レビューがあり、何故このデザインなのか、コンセプトやテーマもブラッシュアップしていきます。Why / What / Howの着地点を各人の技量も踏まえて探していき、最終日に動くポートフォリオサイトをプレゼンします。
Parsonsのデザインismを感じる DESIGN Track
DESIGNトラックでは、問題発見〜問題解決の一連のいわゆるデザイン思考プロセス、ユーザー中心のデザインプロセスを課題図書・動画・クラスメートとの共創・ワークショップを通じて学びます。

Day4: Storyboard & Prototyping

Day5: User Test & Feedback
2人1組で、相手の欲しい財布をプロトするワークショップ。
財布はグローバル共通ツールだし、アイスブレイクに最適なワーク。
ユニークだと思ったのは、Research Through DesignやSpeculative Designの回が組み込まれているところです。


すなわちデザインがアウトプットするのは、直近の状況をより良くするための実現可能なソリューションだけではなく、人類のための知識や問いをアウトプットすることもできる、という視座をパーソンズは標榜しています。
特にResearch through designは自分の中で定義が曖昧だったのですが、デザインを通じた「リサーチ」なので、より先進的な分野においては、プロダクトそのものの価値よりもプロダクトを通じて得られる「知識」に価値がある、もしくは「知識」を得るためのプロダクトも存在して良い、という考え方は結構腹落ちしました。こうしたことができるデザインスクールはまだ少ないと思うので、これからの本学期で深く探求したいです。

アメリカ東海岸ではMIT Media Lab, NYU ITP, Parsons DTが
プログラムの中でデザインリサーチを標榜している。
QuestionやProblemから何かを作るCODEトラック
CODEトラックは、授業内ではProcessingによるクリエイティブコーディングの基礎を取り上げる一方、最終日には自分のインスピレーションから何か動くモデルまで制作し、プレゼンすることが求められます。
そのままProcessingで何か作ってもいいし、使用する言語・ツールは自由なので、最終日にはゲームを作った人、SonicPiでライブコーディングパフォーマンスをした人、Arduinoでリアルプロダクトを作ってきた人など様々なアウトプットが見られました。コーディング経験0の人も最終日には何かキラリと光る物を仕上げてくるあたりが、Weird集団と呼ばれるDTの文化を象徴している気がします。

授業は10人1チームで完全ハンズオン形式
自分は、人工的に創発・世代交代を繰り返すグラフィックに対して、我々は「儚い」という感情を抱くのか?というDesign Questionから、p5.jsでジェネラティブアートを制作しました。
社会人経験の名残からか、リハの時に、pptでまず制作過程をつらつら説明してから、ではこれからデモへ・・なんて進もうとしたところ、過程はいいからまずデモ出して。なんて怒られたのは美大に来た感がありました。

偶発的に生態系を形成し始めるピクセルのインスタレーション
最後はBBQで打ち上げ、そして秋学期へ・・
最後はブルックリンのProspect Parkで全員でBBQで打ち上げし、3週間のBootcampは無事終了しました。

教授自ら肉を焼いていくスタイル
ということで、何か既にやりきった感があるのですが、これからが本番です。授業の選択も非常に自由度が高く、ひたすらコーディングや制作に打ち込む過ごし方もできれば、デザインリサーチや抽象度の高いデザインプロセスの探求を行うこともできます。

個人的にやりたいのはこの辺のデザインリサーチの背景にある概念の整理。
自分は改めて、テクノロジー・デザインの両側面からスペキュラティブデザインを探求するという軸を持ち、今学期はMIT Media LabのFluid Interface Groupから来たHarpreet Sareenに師事することになったので、バイオデザインなどの分野を研究していきます。
ということでこの1週間はしばしの休息を楽しみまして、いよいよ秋学期に突入していくことになります。
長い文章にお付き合い頂きありがとうございました。
ぜひNYに旅行・留学等でいらっしゃる方がいましたら、ご連絡ください。こちらでお茶でもしましょう!
いいなと思ったら応援しよう!