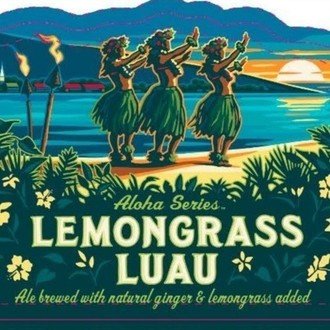「チ。」と好奇心
今年の秋クールのドラマやアニメの中で特に惹きつけられるのがNHKで放送中の「チ。——地球の運動について——」。
漫画を読む習慣がないので、テレビアニメ化された今回が初見なのだが、初回を見ただけで毎週見続ける数少ない番組の一つになった。
写真をやっていたこともあって、映像・動画の技術進歩が著しい今の世の中で、静止画がいかに脆弱になったかは身をもってわかっていたつもりだったのだが、アニメと漫画の関係においても同じ構造が顕著になってきたように感じる。
動くか、動かざるかの話はさておき(機会があれば別に書くかもしれない)、この「チ。」で描かれるモノに戻る。
魔女裁判、異端審問が盛んだった中世ヨーロッパと思しきどこかの場所で地動説の研究に携わってしまった人たちが描かれる。
大抵の人の頭に浮かぶのはおそらくガリレオ・ガリレイの異端審問だろうし、ガリレオがこっそりつぶやいたという「それでも地球は回っている」という言葉だろう。
でも地動説は表面的なテーマであって、根底にあるのは人の知識欲や好奇心、真理を追い求めてしまう習性なのは間違いない。
博覧強記の人物として僕は南方熊楠と立花隆にとても惹かれるのだけれど、彼らの根底にあったのは「知りたい」という欲で、発表する云々は2番手以下の重要度だった気がする。
番組の紹介か何かで「チ」とは「地」であると同時に「知」でも「血」でもある、みたいなことが書かれていて、なるほどなあと深く頷いた。
僕にとっても知ることと書くことを比べたら、常に圧倒的に前者に軸足が乗る。知らないことを知ることが最重要で、それをアウトプットするかどうかは正直どうでもいい。
そのことを「チ。」を見ていて再発見した。
話は飛ぶけれど、知を最優先にするというとは?ということを考えていて、ふと釈迦が頭に浮かんだ。
僕には相手がどんな神様であれ信仰心などカケラもないのだが、仏教の成り立ちには興味を惹かれる。
釈迦が悟りを開き、いわゆる「梵天勧請」で他者に教え始めるまでは悟るに至ったプロセスは誰とも共有していなかったというのが実に面白い。
自分の「知りたい」という気持ちの方が圧倒的で、誰かに教える、伝えるというのは2番手だったという事実から、釈迦の本質は立花隆らと同じだったのかもしれないと思い付いたというわけだ。
「チ。」が「知。」であれば、アニメをさらに面白く見るためには中世ヨーロッパのキリスト教(異端審問や魔女裁判の中心的な役割を担っていたローマ・カトリック)についてもう少し知った方がいいのかもと、数冊の本を読んだ。
中でも岩波新書の『ガリレオ裁判』と同じく岩波新書の『魔女狩りのヨーロッパ史』は面白かった。
(いやあ、当時のローマ・カトリックにも色々あったんですねえ、的に)
池澤夏樹の『ぼくたちが聖書について知りたかったこと』も面白かったが、こちらは現在進行形のイスラエルによるガザへの攻撃について図らずも考えさせられるものだった。
いいなと思ったら応援しよう!