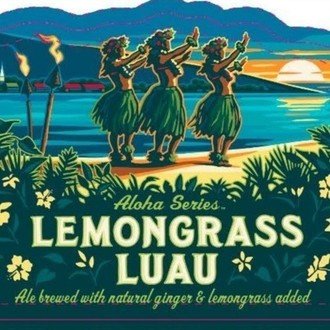暑さの前にはすべてがひれ伏す
取り立てて何も書くことがない。
いや、書きかけの小説の断片や、出かけた先で見かけたささやかなハプニングのことや、風景と記憶が突然結びついて湧き起こるフラッシュバックのことなど、頭の中には様々な「書くべきこと」が渦を巻いているのだが、とにかく暑くて取り出し口のドアノブに手をかける気にもならない。
暑さへの耐性が低いのは今に始まったことではない。
現代と比べたらいくらかマシだった30年とか40年前の東京の夏ですら、僕には十分に耐えがたいものだった。
当時はエアコンがどの家にも当たり前にあるほどではなくて、窓という窓を全部開け、扇風機程度で暑さを凌ぐのが当たり前のことだった。
今などよりはるかに気密性は低く、家のすべての窓を開けばそれなりに風が抜けて、どうにか過ごせるくらいにはなっていたのだから、やはりいまよりはいくらかマシな気候だったのだろう。
夏に、7月生まれの僕が犬みたいにヘロヘロになっているのを見ると、友達や幼馴染たちは「夏生まれのくせに」と笑うのが常だった。
夏に生まれたから暑さに強いなんてのは、何かの迷信か都合のいい思い込みでしかないと思うけれど、言い返したからと言って涼しくなるわけでもない。
僕が暑さに弱いのにはちゃんと原因がある。僕は夏の暑さを通常の人の半分も体験していないのだ。それが唯一にして最大の原因としか思えない。
夏はプールの季節である。
学校のプールでも、公営のプールでも、多くの人が水に浸かり、涼を取る。夏が水の季節なのは暑さの反動でもある。
1年中泳いでいた僕らにしてみれば、プールで遊ぶという概念そのものがすでになくなってしまっていたけれど、普段練習している屋内のプールから、強い日差しに背中を焼かれながら練習する屋外のプールは少しだけ新鮮だった。
何より屋外のプールの水温は室内よりも1〜2度低い。
練習で筋肉に熱がこもりそうになっても、普段より冷たい水が熱をとってくれる。毎度きつい練習ではあったが、頭からかぶる水の冷たさは、市民プールで遊ぶ人たちとはちょっとだけ違った角度から心地よさを感じる「季節の風物詩」でもあった。
夏休みになると強化合宿が始まり、練習は1日3回。5時半から7時までの早朝、9時半から12時半までの午前、4時から7時までの午後練。
1日のほぼ3分の1を水の中で過ごすのが毎日のルーティーンだった。
水温は24度から27度。気温より低い水の中で日中の大半を過ごすのである。体の感覚は当然そちらの低い方に慣れる。
三つ子の魂ではないけれど、そうした毎日を長く送っていれば、体の感覚もそちらに慣れてしまうのは当然で、いまになっても暑さへの耐性が低いままというわけだ。
今日の東京の予想最高気温は34度。
朝から午後の早い時間まで日の当たるベランダには、毎朝遮光ネットを吊り下げるのがその日最初の仕事になっている。
それでもすでに網戸のアルミの枠は熱で膨張して、開けにくくなっている。
これでまだ6月というのだから、今年の夏は想像するだけで怖い。
8月の半ばごろには僕自身が溶けてなくなっていたりして(溶けたアイスクリームなんて上等なもんじゃなくて、せいぜいが補修もされないまま時間がたった古いアスファルトみたいなものだろうな)。
「書くことがない」というところから始めて1400字程度までになったのも、網戸の枠と同じように暑さにやられて伸びただけなんだろうな。
いいなと思ったら応援しよう!