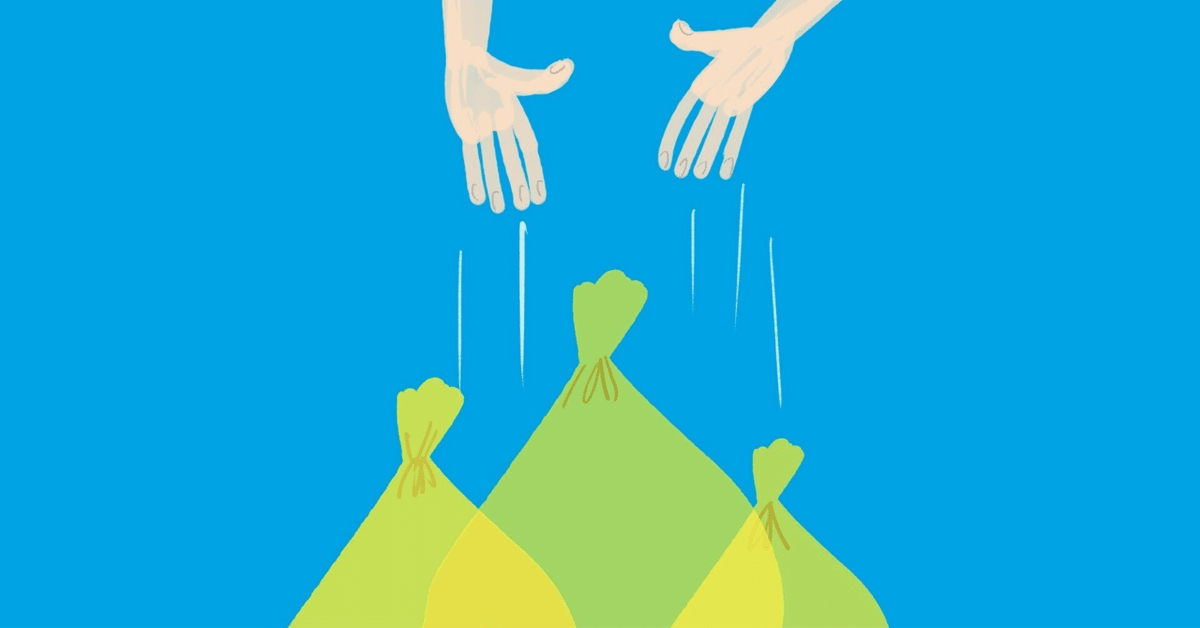
メーカーが食品廃棄物(未利用資源/残渣)を活用する難しい5つの理由
記事のきっかけはこちらのツイートまとめから。なお本稿では、以後食品廃棄物を『残渣』という言葉で統一します。
上の記事は安定供給のためには余剰が必要だという内容で、個人的には適切な論稿だと思います。
この手のロス問題は、端的に言えば
「ロスを当てにしてしまうとイレギュラーが起こった時、ロスを当てにしている人から死ぬよ」
というもの。
その通り。現実は非情である。
さて、SDGsが盛んに言われるようになる前から、フードロス問題は食品メーカーにとっては課題の一つでした。
だって、捨てるのってタダじゃないからね。

野菜を剥けば皮は出る。魚を下ろせば骨も鱗も出る。卵を割れば殻は残るし、揚げ物を揚げれば天かすが出るのです。その廃棄量は当然ながら、一般のご家庭の比ではありません。
そして、その廃棄費用も当然相応の費用がかかります。
実際には、こうした残渣の多くは例えば家畜の飼料や肥料としてそうした専門の業者や商社に買われていくこともあります。
しかし買われていくといっても、捨てるよりマシ程度。
kg単価で1円みたいな話です。
とはいえ捨てるとkg単価で数十円取られるしな、みたいな。
そして世がSDGs真っ盛りになると、こうした取り組みをすることが企業ではほぼ義務のようになります。「サステナビリティ」の名を冠した部署は今やどの会社にもあることでしょう。
残渣を価値のあるものに変える取り組みは、今やその姿勢そのものが企業のPRになる時代です。
そういうわけで、食品メーカーはこうした残渣を有効活用したいとは考えています。
成功した例もたくさんあります。
私が思うに、一番上手くいったのはホエイじゃないでしょうか。
ホエイは元々チーズを作る時に生じる廃棄物でしたが、含まれるタンパク質の吸収の速さ、体内利用効率、そしてマズくない(重要!)といった機能から、今やプロテインといえばホエイが主流になりました。プロテイン市場は伸びていますので、今後もホエイの需要は高まっていくでしょう。
このような成功例はあるのですが、じゃあ何でも上手く行くのかというと、これが意外に活用が難しかったりします。
その理由について、具体的な理由を交えて述べていきたいと思います。
1) 付加価値のある機能を見つけ出すのが難しい
当然ですが、高く売れるには高く売るための機能が必要になります。味や栄養も立派な機能ですが、それがあればそもそも廃棄されません。
ましてや、トクホがあり機能性表示食品があり栄養強化食品がある世の中、機能だけで勝負するなら結構なウリがないと価値にはなりません。
少し特定の栄養素が多いくらいでは、大体マーケの方から却下されます。
「ビタミンが多い?サプリで良くね?」のような言論ですね。
ちなみに、この「サプリで良くね?」という言葉は機能性成分を研究している研究者の1/3を殺傷することが分かっているので、2023年より国際法により使用が禁止されています。言ってる人いたら教えてください。釘バット持って向かうので。
2) 高付加価値化しようとしても、機能性成分は大抵製造しにくい
1)でボロクソに言われたあなたは、MSやマイクロアレイなどを駆使して、ついにかなり特色のある機能性成分を見つけました。
やったあ!
この成分には珍しくて有用な生理機能があるぞ!
え、作り方?
まずフリーズドライして、粉末にして、アセトンと水で勾配作って50フラクション回収したうちの14-20画分を回収して、固相抽出…
無理です。
これは大人しく細胞試験とかやって論文書いて終わりにしましょう。
研究業績にはなりますが、フードロスは救えない。
食品メーカーで化粧品や化成品を作っている会社もありますが、基本食品会社です。複雑な製法になるものはまず作れない前提でいた方が良いでしょう。フリーズドライをトン単位で実施できる会社がいくつあるのか。
こういうのは、ワンチャン化粧品原料とかで数万円/kgになればいいかなという世界です。設備がなければOEMもなくはないですが。
そもそも上記の例で言えば、廃棄物から抽出してフラクションに分けて……って、結局ごく一部しか回収できてなくない? 廃棄物の廃棄物はどうする? という命題を抱えて生きることになります。人生はままならぬ。
そんなわけで、残渣の有効活用の基本は加工度はそこまで高くなく、かつそれなりに価値のある形にしなければなりません。それも少量さばくならともかく、場合によっては数十トンの世界ですからね。
さて、ここまでは研究開発側の課題になるでしょう。
では、他の部署から見た場合はどうでしょうか?
3) プロダクトアウトの商品のジレンマ
残渣を活用した商品は、当然ながら自社の都合で製造した商品となります。ですので、出て来たものは完全にプロダクトアウトの商品となります。
実はこうした商品は、製造工場も作りにくく、営業も売りにくいのです。
残渣を使った商品に限らず、これまでのカテゴリーとは違う新規の商品というのは、
工場「いくら作れば良いかわからないものは、作りたくない
営業「どれだけ作れるかわからないものなんてお客様に紹介できない」
というダブルバインドの問題が出て来ます。
お客様が明確に決まっている・販売計画が出来上がっているのであれば生産は計画に沿って作るだけですが、得てしてプロダクトアウトの製品は、どこにハマるか分かりません。
会社の後押しのない形で進めると
「計画が作れない」→「製造出来ない」→「販売出来ない」
という死のループに陥りがちです。
回避する策としては、
・会社の大テーマとして、とにかく推進を後押ししてもらう
・最初のうちは製造はOEMにする
・社内原料として使ってもらう(営業を介さない)
などになるでしょうか。
4) 原料品質のバラつきとその保証
野菜の廃棄物を想像してみてください。どんなものが思い浮かびますか?

ニンジンのへた、キャベツの外葉や芯のような(工業的な)非可食部を思い浮かべた方。
正解です。
正解ですが、数多くの正解のうちの1つでしかありません。
規格外サイズ、何かしらの理由で破損したもの、虫食い、腐食部分……廃棄になる理由は様々なのです。そしてそれは、商品の原料として見た時に、原料として大丈夫かという品質問題があります。
野菜や果物であれば残留農薬の話なども出てくるかもしれません。
しかも、状態はロットによってまちまちです。
残渣が綺麗な時もあれば汚い時もあるでしょう。開発側はそうした影響を極力小さくするための製法を考えなければいけません。
また、季節性の問題もあります。例えば、春はキャベツの廃棄物が多く、秋はニンジンの廃棄物が多いというようなケースですね。春は作れるけど秋は作れない、だと本末転倒です。
さらに言えば、元々廃棄物と思って扱われていたものの取り扱い・保存体制をしっかり整えられるかというのもあります。
あまり詳しく書きたくないです。察してください。
この辺りは開発の段階で工場・品証と連携をしっかり整えておかないといけない内容ですが、開発ではそもそも持ちにくい視点ですし、工場や品証も既存製品ならともかく、廃棄物の管理まで目が届いているかというと、改めて調べてもらわなくてはならないことが多いです。
また前述の理由から商品も毎回同じ品質のものが出来ているかという点に注意を払わなければいけません。この辺りのハードルは廃棄物が何かにもよりますが、低くはないことを意識しておく必要があります。
5) バイプロ(副産物)なのか、主原料なのか
1)〜4)の難題をクリアしたとして、最後に残るのは、「この原料はバイプロなのか? 主原料なのか?」という問題です。
食品メーカーにおいて、残渣の有効活用は当然テーマに挙がります。ただ残渣を活用した商品が出来たとして、残渣を「原料」と設定してしまうと、商品の安定供給のために原料の残渣を切らしてはならないというジレンマが生じます。高付加価値化するほど、残渣が安定して発生するかという議論になる。 https://t.co/00rT5HQH8P
— イツキ⚗元研究職→経営 (@itsuki26_labo) February 21, 2023
上のツイートのことなのですが、実際に食品メーカーにいないと理解しにくい文章だった気がするので、補足します。具体的に示してみます。
じゃがいもの皮から抗菌成分を得られたぞ!
安定生産もできるし、お客様にも高い評価をもらった!利益もたくさん!
お客様「いやぁ、アレのおかげでウチの商品もバカ売れだよ。で、増産したいから、アレももっと発注させてもらうね!」
弊社「いえ、アレは(バイプロなので)月◯◯トンまでしか製造出来ないんです」
お客様「それは困るよ! もう広告も売ってるんだ。安定供給がメーカーの責務だろう? お金なら出すから作ってくれないか?」
供給制限含んだ売買契約にしとけよ、というのは無しとして。
例えば、じゃがいもの中身より皮から出た成分の方が利益が出たとしましょう。そうなるとどうなるでしょうか?
今度はじゃがいもの中身が残渣になるのです。
当然ですが、残渣の発生量は主原料の発生量に依存します。じゃがいもの中身がフライドポテトになっているとして、フライドポテトの製造量以上にじゃがいもの皮が発生することはありません。
しかしじゃがいもの皮に、中身以上に価値がついた場合。
主従は入れ代わり、じゃがいもの皮を取るためにじゃがいもの中身の処理を考えなければいけなくなる。
じゃがいもの皮と中身の価値が入れ替わることはおそらくないので、今のは極端な例になりますが、残渣に価値をつけるということは安定した商品とみなすことであり、商品とみなすということは供給責任が出てくるということです。
そして悲しいかな、大手企業ほど残渣の発生量は多く、一方で供給責任という社会的責任を果たさなければいけません。残渣が足りなくなったから生産停止、は余程のことでない限り認められないのです。
なので、この辺りのバランスを考慮した開発になっているのか? 逆転する恐れはないか?というのも頭の片隅には入れておいた方がよいでしょう。
長々と書いてきました。読んで頂きありがとうございます。
ここまで話してきた内容について、思いつく対策はあれど明確な回答は私は持ち合わせていません。私も何度か残渣の活用にはトライしたのですが、上記の1)〜5)のいずれかで引っ掛かって失敗に終わっています。
フードロスは一般の人にも問題がわかりやすく、ちょっとした工夫で解決出来そうな課題に見えてしまうので、企業側の動きが遅々としているように思われるかもしれません。
それでも、どの企業でも残渣の有効活用は経営的・社会的に取り組まなければならない課題であり、精一杯の努力をしているテーマです。今回はあえて光が当たりにくいかな、という角度から食品残渣の有効活用について述べてみました。
最後に以下のツイートをもって締めに代えさせていただきます。
フードロスは家庭から排出される分で半分近くなので、社会問題にしては珍しい「意識が高まればほんとに減らせる」イシューなのである。みんな、残さず食おうな!https://t.co/3sh29Kke0D
— イツキ⚗元研究職→経営 (@itsuki26_labo) February 21, 2023
