
一 夜 ”或は蛇の子を飼ふ女”
本社 菊 池 與 志 夫
一
私は水の濁らない朝のうちに海につかつてか
らひと風呂浴びた。全身に快い疲勞を覺え靑畳
の上に裸のままで横になつた。
避暑地の午前十時はもの憂い程靜かである。
その室からは前の畑がよく見えた。はす芋の大
きな葉が鮮かな綠をひろげて、冴ぇざぇと夏の
日に射返されてゐるのが、感じの鈍んだ私の眼
には痛い程である。だが私はぢつとその葉を見
つめてゐた。
畑の向ふはこの離室の持主の住んでゐる古い
母家でそこからゆるやかな坂になつて直ぐ海邊
に續いてゐた。私の室からは海は見えないが、
夏らしい紺靑の空がくつきりと畑の黑土をくぎ
つて見えた。私はそれ等の烈日の下にじつと動
かない風景を夢のやうに見つめてゐた。
蟬が山の樹で啼き出した。草むらではきりぎ
りすが鳴いてゐる。母家の座敷に泊つてゐる避
暑客も、私の從弟妹達も皆海邊へ行つて了つ
た。
私は呆然とねそべつてゐる。いつの間にか私
は眼を細めた。うとうととする氣持である。ふ
と何かきらつと光つて靑いものが動いたやうで
ある。淺い眠に堕ちやうとしてゐた私は目覺め
た。大きな葉がかすかに揺れてゐる。陽炎の立
ちのぼるのを見るやうな揺れ方である。私はそ
の葉をみつめた。
芋の葉の上の靑蛙が隣の葉へ飛び移つたので
あらう、蛙の重みで葉が傾いて、露の玉がキラ
キラ光り乍ら土にこぼれた。
遠くで汽船の笛がまのびて、かすかに聞えて
ゐる。
私はシャツ一枚着てうたた寢をした。
二
午後、私は從弟妹だちを先に海に行かせてか
らひとり裸足でとび出した。海へ出るのにはど
うしても母家の庭を横ぎつて、その庭の隅にあ
るもう一つの小さな離室の前を通らなければな
らなかつた。私はそれが妙に嫌であつた。うま
く時を見計つて行かなければ、明け放した座敷
の客から、私のやせ細つた裸をジロジロ見られ
るからである。その客が男ばかりであればさう
でもないが、そのうちにはもう大分からだの圓
みの熟した女が三人もゐたのである。
私はその女達に自分の裸を見られるのを一番
恥しく思つた。どうせ海に浸る時には見られる
のであるが、この庭先でさういふ目に會ふこと
は耐らなかつた。それで私は海へ行く時にはな
るべく母家の客達が出拂つた頃合を見計つて、
そこを驅けて通るやうにした。
が、私にはそこをことなく通つたとしても、
もう一つへんな氣のする室の前が殘つてゐる。
それは、その庭の端れにある陰氣な小さな離室
の緣側であつた。その室の後は日をさへぎるや
うに高い檜や柳が欝蒼と繁つてその室におほひ
かぶさつてゐる。その緣側には何時見ても眼の
どろんとくさつたやうにくもつた一人の女が、
ぼんやりと坐つてゐる。その女の眼は殆んど牡
蠣のみを思はせる程不氣味なものであつた。手
を膝で合せてきちんと坐つてゐる。母家の一人
娘で二十三ださうであるが、生れつきの白痴だ
から誰も結婚する男がない。幼い頃父親は大へ
ん心配して娘の育たないことをひそかに望んだ
さうであるが、今日まで大した病氣もせずに成
長して了つた。からだ丈は娘らしく發育してゆ
くのを見ると、父親は涙が出る程の愛着を感じ
るのだが、どういふものか少しも頭が働らかな
いので、どう慰めてみても娘には通じないのだ
さうである。
娘は春そろそろ菜の花が咲く頃になると、も
う緣側に坐り出して冬近い日迄それを續け、夜
明けから日の暮れきる間、そこにじつと坐つた
きりださうである。私は始めてここへ來た晩、
その娘のことを父親からさうきいてゐる。
氣が狂つてゐるのではない、根が白痴なのだ
からさう心配することもないのに、私はその娘
を見ると寒氣を感じた。
私はその室の前へ來た。やはり娘が緣側に坐
つてゐる。背のすらりとした面長な女である
が、眼や口元に打ち消すことの出來ない、病的
な歪みを見せてゐる。然し若しこれがまともな
女であつて、眼が普通であればさう大して醜い
女でもない。私のやうな偏奇なたちの男は却つ
てさういふ顔立ちを愛するかも知れない。
夏の日ざかりである。女は樹の蔭になつて涼
しさうな例の緣端に坐つて、ぢつと軒端を見上
げてゐる。大柄な浴衣を一枚着てゐるのが、却
つて女のからだを露はに匂はせるやうに感じ
た。
見ると女が見つめてゐる軒端には虫籠が一つ
吊るさがつてゐる。蔭の中には草の葉がつまつ
てゐるので、どんな虫がゐるのか分らない。
と、きりぎりすがないた。虫籠にはきりぎりす
がゐるのである。それがなくと女はにやりと笑
つた。そして不相變ぢつと籠を見上げてゐる。
時をおいて又虫が鳴いた。女は又にやりと笑つ
た。私はその笑ひ顔を見てゐるうちにへんに氣
味惡くなつた。
私は見てはならないものを見た恐怖を感じ
て、慌てて砂濱へ走つて行つた。
三
夕食が濟むと從弟妹だちは晝の疲れで直ぐ寢
て了つた。私は蒸暑い蚊帳に入るのがいやで獨
りで散歩に出かけた。月のない晩で銀河がすつ
きりと走つてゐた。私は夏の夜空ほどロマンチ
ックな神秘さを湛えてゐるものはない――とい
ふやうなことを思ひ乍ら、夜の砂濱づたひに歩
いた。私には妻はない。又こんな海邊を肩を竝
べて歩るく戀人もない。だのに濱を歩いてゐる
人びとは皆美しい話相手を持つてゐる。私は獨
りの散歩は大へん好きであるが、この避暑地の
海邊ではひけ目を感じた。私はそれを淋しく思
ひ不快であつた。
私は海と反對の路をとつた。
ふと私はここへ來る夜汽車の窓から螢がとん
でゐるのを見たことを思ひ出した。
螢を捕りに行かう――私はさう思つた。
砂濱をはづれると漁師町らしい匂のこもつて
ゐる町並がある。それを横切つて山路へかかつ
た。もう人家は一軒もないからあたりはまつ暗
である。私は廣びろとした草原を歩いた。草が
サヤサヤと鳴る。夜露に濡れた草の葉が素足に
べつとりとまつはりつく。
どうしたものか螢は一匹も光らない。あまり
海邊に近いからだと私は思つた。それに螢の好
む小さな流れがないからだとも思つた。
私はそんなことを考へ乍らただあてもなく叢
をあちこちと歩るいた。
ふと草のあひだからゆらゆらする灯が見えた
やうに思つた。へんに思つてぢつとその方を見
つめると、確に燈火である。
子供が虫でも捕るのだらう――若しさうであ
れば退屈まぎらしに私もひとつ仲間に入れても
らはうと、草を手で分けるやうにしてその方へ
近づいた。
その灯は蠟燭の火であつた。虫捕りならあん
なに灯をぢつとひとところに置くわけはないが
―私は再びへんに思つた。軈てその灯は眼の前
へはつきりと現はれた。と、その時私の姿を突
然認めて驚いたのであらう。ひとりの女が鳥が
羽ばたきするやうに跳ね上つて、ガサガサと逃
げて行つた。それは暗闇の蝙蝠を思はせた。蠟
燭の焔が激しくゆれて危く消えかかつたが、消
えはしなかつた。
あッあの女だなと直感した。例の白痴の女で
ある。私は惡るいことをしたと思ひ乍らも、あ
の女がこんな人氣のない草原で何をしてゐたの
だらうといふ興味にひきずられずに居られなか
つた。私は注意深く今迄女が坐つてゐたところ
へ行つてみた。
私はそこでなにを見たか。
若い私のまともに見るに堪えない。毒どくし
い色刷りの××を綴ぢたものであつた。
私はときめく胸を押へ乍ら、蠟燭をかざしつ
つそのへんを犬のやうに這つて、その他になに
かないかと探してみた。するとそこでもう一つ
のものをみつけたのである。それは小さな盃で
あつた。私は明かりを近づけてみた。盃には黄
色い液體がみちてゐた。酒である。私は猶ほよ
く灯で調べてみた。と驚ろくではないか、その
酒の中にはどぜう程の生きものが二三匹によき
にきよと蠢めいてゐる。
私は身ぶるいする程不氣味であつたが、その
盃をしつかりとハンカチに包んで宿へ持つて歸
つた。
四
翌朝誰も起き出さないうちに眼を覺した私
は、すぐその盃をのぞいて見た。するとその生
きものはどぜうではなかつた。蛇の子である。
それは昨夜見た通り酒液の中で動いてゐる。そ
の瞬間私はあの女の顔をまざまざと思ひ浮べ惡
寒を感じた。
その日私は海へも行かず暑い座敷に寢轉んで
終日呆んやりしてゐた。
夜、私は××を小包にし、盃のものはそつく
り畑へ埋めた。さうして小包は、明日あの離室
の女にそつと渡して呉れるやうに、從弟妹の一
人に賴んでから、獨りその夜の汽車で出立し
た。(終)(昭和十一年五月稿)
(「王友」第十二號
昭和十一年六月三十日發行より)
#怪談 #ホラー #小説 #短編小説 #グロ #グロテスク
#蛇女 #王友 #旧王子製紙


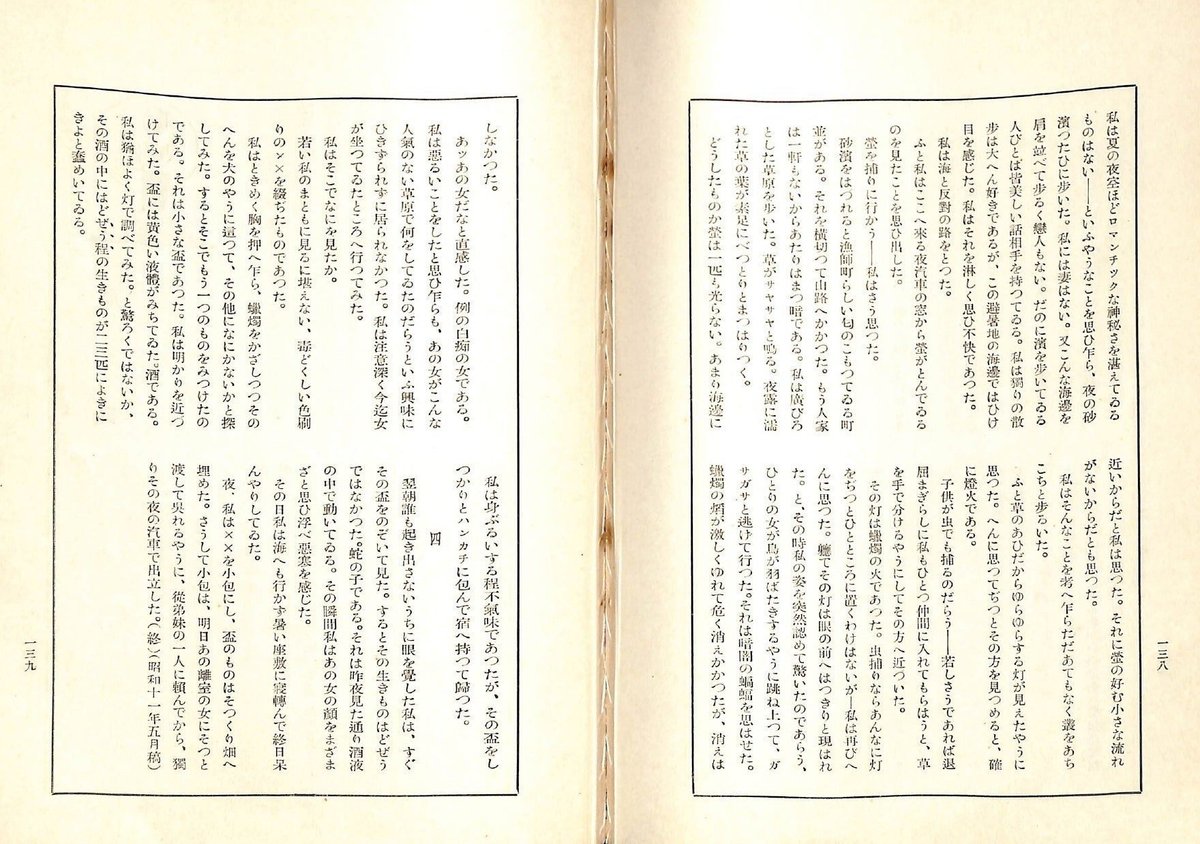
紙の博物館 図書室 所蔵
