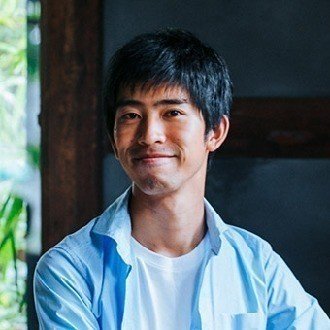文体練習のすすめ
いまマリナ油森さんが #書き手のための変奏曲 を掲げて、いろんな文体で遊ぶやつをやってるんですけど、これは万人にお勧めできる『編集稽古』です。私は大昔に松岡正剛のISIS編集学校(14守「森羅一族教室」、2006年?)で色々やりました。
作家の文体を真似る
よしもとばなな、野坂昭如、三島由紀夫の3人の中から一人を選んで文体を真似る、という演習がありました。
文体を真似るには「文体の特徴を会得するまで読み込んで分析しなきゃいけない」んでけっこう大変です。インプットがなければアウトプットができない。「ばななスタイル」を選んだ私は『TUGUMI』を手書きで筆写してみたり(途中で挫折)、うんうん唸りながら答案を書いたりしていました。このときはあまりつかめていなかったな。たとえば「四苦八苦」といった単語ひとつ取っても「ばなならしくない」みたいな指摘を受けていました(これは中級編「破」のほうのお題)。
今だったら誰の真似ができるだろう。野坂昭如はこの歳になっていいなと思うようになりました(『蛍の墓』『アメリカひじき』)。舞城王太郎? 北方謙三? クセのつよい文体の作家の方が「つかみやすい」ようでいて揃えていくのは難しいと思います。
モード編集術
ほかにも「モード」で書き分けるという演習がありました。短い新聞記事のニュースを何通りにもリライトするというお題です。
・地方雑誌のコラム風
・子どもにもわかるように
・老人の追憶風
・営業部長への報告風
・きっこの日記風(そんなワケで、ビックル一気飲みしちゃうね!)
これは楽しかった。
文体練習
こうした文体遊びの教科書となるのが、レイモン・クノーの『文体練習』です。
……え、知らない?
レイモン・クノーの『文体練習』って知ってる?https://t.co/Us8zt7OYoR
— illy / 入谷 聡 (@irritantis) July 9, 2020
https://1000ya.isis.ne.jp/0138.html
ある、ごくありきたりな風景を、100通りの文体で表現するという試み。
第2番では、わざとくどくどと書く。第3番ではたった4行にする。第4番では隠喩だけで書く、第5番では出来事の順番を逆にして倒叙法で書く、というように、次々に文体を変えてみせていくのである。
読めば分かります!
元がフランス語なので、日本語訳としてはさすがに厳しいものもあるんですけど、かなりレベル高いものもあって。お気に入りは
・10 虹の七色(七色が出てくる)
・11 以下の単語を順に用いて文章を作れ
・43 尋問
・44 コメディー(戯曲風)
・53 ソネット(14行詩)
・
あたり。
「文体」に着目して、それはつまり書き方の「ルール」を意識的に変えてみるトレーニングを積むと、けっこう表現の幅が広がると思います。純粋な「創作遊び」の方法としてもおすすめ。
ひねるアイデアに困ったらぜひ!
いいなと思ったら応援しよう!