
[自家製食品]#1牛乳からチーズを錬金する方法
❞
2つ目は、生産力の獲得である。端的に言うと、自分で作ってしまおうということだ。通常、欲しい物を獲得するには、自身の労働→賃金の獲得→商品(他人の労働)との交換、という3stepを踏む必要がある。この獲得法では、step数の多さでコストがかかるため、個々人の経済力(労働力)以上の商品を手に入れることができない。これに対し、自分で創るのであれば、自身の労働力をそのまま商品として変換することになる。ここでは、作成技術はストック資産として手元に残るため、作ればつくるほど必要なコストは下がり、成果物の質は向上する。さらに、そもそも自分専用に設計するため、その質的満足度は既製品の比ではない。だがそれでは結局、「近代以前の牧歌的生活と変わらないのではないか?」と思うかもしれない。しかし、それは大きな間違いだ。現代の最大の強みは、個人が圧倒的な生産能力を持てるようになったことにある。❞
詳しくは、思想編の記事で学んでほしいのだが、生産力とは、日々の食事にも活かすことができる。食事は人間の三大欲求の一つであることからも分かる通り、生活の中心となる行為である。わたしたちは、毎日のように食事を行うが、あくまで生きるために食うのであり、食うために生きているわけではない。一見すると、当たり前のようだが、エネルギー革命が起こるまでは、食うために生きる人間がほとんどだった。狩猟生活では一日中野山を歩かなければならないし、農業もかなりの作業量を要する。よしんば食べ物を得たとしても、解体や採取から調理が始まるので、これまた時間を要する。食物があたりまえのように手に入る現代の異常性は、これまでの歴史を振り返れば容易に理解できるのだ。スーパーやコンビニで当たり前のように食事できる我々は、食について真剣に考える機会を逃し続けている。
これまでは、それでよかったかもしれない。だが、今現在日本では、食料価格の高騰が続いている。これからも上がり続けるだろう。これは、元をたどればエネルギー掘削コスト(EROI)の上昇に端を発するのだが、まぁ、これはまた別の記事で解説しよう。ともかく、食事コストが上がれば上がるほど、我々は昔の生活に逆戻りする。自ら家庭で野菜を作り、肉を解体していくことのコスパが相対的に高くなっていくからだ。(ちなみに、アメリカでは卵の高騰で鶏飼育が流行っているらしい。)さらにメリットを挙げると、「自家製食物」は極めて栄養価が高く、新鮮で、美味しく、胃腸にも良い影響がある。なぜなら、スーパーで買える野菜や加工品は、最も美味しいモノではなく、あくまで輸送と長期保存に耐えうるモノ、という基準で選別されているからだ。例えば、小松菜などは最たる例だ。現在の小松菜はチンゲンサイの亜種のような位置づけだが、古来より食べられていた小松菜は、よりやわらかく緑が濃く、そして何より旨味が多い。だが、やわらかいが故に輸送に適さず、市場から駆逐されてしまっている。つまり、自家消費を目的とした自家製生食品は、良いことばかりなのだ。少しの手間と知識で生活を向上させる。まさに、鉄の家計簿が目指すところだ。
今回は、牛乳からチーズを作る方法を伝授しよう。
Step1.必要なもの

・牛乳
・耐熱ボウル
・ヨーグルト
・温度計
・ザル
・手ぬぐい
これだけ。牛乳の種類やヨーグルトの種類でできあがりに差があるので、いろいろ試してみると良いだろう。
Step2.ヨーグルト倍増

次に、牛乳を全部耐熱ボウルに入れ、ヨーグルトも投入する。ヨーグルトの分量は適当でいいが、今回は900mlの牛乳に対して100gほど入れた。
次に、これを電子レンジで温める。だいたい500Wで5~10分ほど。目標としては、だいたい中心部が40℃程度になるまで温める。

ここまで温めると、乳酸菌が活発になって発酵が始まるので、ふたをして一日ほど常温で放置する。
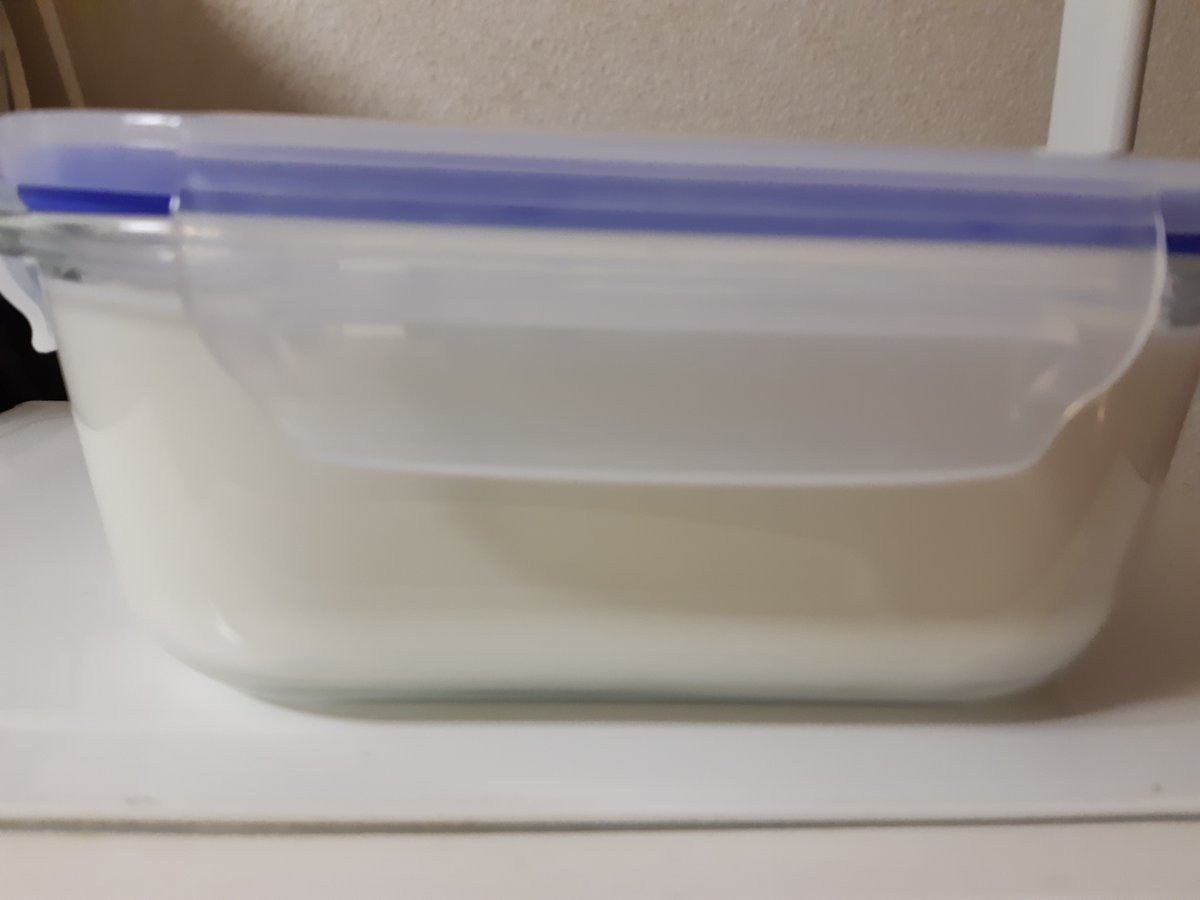
すると、このように牛乳のタンパク質が乳酸菌によって凝固して、ヨーグルトになる。

Step3.ヨーグルトをチーズ化
次に、できたヨーグルトをふきんとザルで濾す。この時出てくる液体は、ホエーといって牛乳からタンパク質が除去されただけの栄養満点の液体なので、炊飯や料理に使うとなおよし。

ある程度水分が落ちたら、少しねじって圧力をかける。

このまま二日ほど放置して、水分を抜く↓。

重さを測ると、282gとなった。ここに重量の3%の塩をふる。今回は、安全側をみて4%(12g)を加えることにした。


Step.4チーズを乾燥・熟成
正直もう味はフレッシュチーズなので、そのまま食べても美味しいし、トマトにのせて食べれば最高のワインのつまみになる。ここからは、長期保存したい or 酸味を抜いてもっとチーズっぽくしたい人向けのステップになる。
まず、より乾燥・熟成を進めるために、以下の状態で冷蔵庫に放置する。ちなみに、ふきんを外して、生のまま乾燥させても問題はない。

長期保存する場合は、水分量を30%以下にする必要がある。牛乳の固形分は全体の約12%なので、今回はだいたい固形分が1000*0.12=120gということになる。つまり、水分量30%にするためには、全体の重量が120/0.7=172g程度になればよい。塩の分量が12gだったので、目標値は184gとなる。
ここから放置すること3週間程度でだいたい目標値となった。

この後は、ラップで保存してOK。正直まだ乳酸の風味が残っているので、もっと熟成させてチーズ感を増すn、もっと水分を飛ばしてハードチーズにするもよし。筆者のおすすめは、もっとカチカチに乾燥させて、利用するときにすりおろして粉チーズとして利用することだ。粉チーズにすれば利用できる料理の幅が広がるので、かなり使いやすい。自家製の場合、水分を保ったままの熟成は運の要素が強く、途中で悪いカビが生える可能性もあるので、かなりハードルは高い。安全を考えるなら、ハードチーズ一択だ。

注意点
・言わずもがなだが、使用する食器類やボウルはすべて殺菌消毒すること。
・保存中にカビが生えてくる可能性があるので、食べる場合は自己責任で。
・長期保存はある程度リスクがあるので、不安な人は塩の量を増やしたり、水分量をもっと低下させたりした方が良い。
以上、牛乳からチーズを錬成する方法を解説してみた。材料費の割に意外と量が少ないと思うかもしれないが、市販の安いチーズはプロセスチーズなので、胃腸を活性化させる菌類はすべて死滅している。菌のないチーズはただの脂肪と塩分の塊でしかないので、いわゆるファストフードと一緒。菌のあるナチュラルチーズは200gも買えば1000円以上はするので、自家製のコスパは高いといえる。さらに、二回目以降は前回作ったチーズの乳酸菌を使用できるので、材料費は牛乳だけになる。ぜひ、日常の料理ルーティンにチーズ作りを追加してみてほしい。
今後は、他のおすすめの保存食や自家製手法についても紹介するつもりなので、乞うご期待。
>>鉄の家計簿トップはこちら
>>サイトマップはこちら
*――――*
Note: https://note.com/iron_kakeibo/
Twitter : https://twitter.com/iron_kakeibo
質問や意見は上記Twitterまで。基本的に、Note記事にて返答します。
(ペンネーム等あれば、記載ください。)
免責事項:本メディアの情報により、みなさまに発生あるいは誘発されたいかなる損害について、作者及び全ての関係者は一切その責任を負いません。本メディア作者は弁護士の資格を持っておりません。実際の法律相談、法的措置等に関しては、弁護士にお問い合わせください。
その他ポリシー:鉄の家計簿は、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラム(Amazonアソシエイト・プログラム)の参加者です。
*――――*
いいなと思ったら応援しよう!

