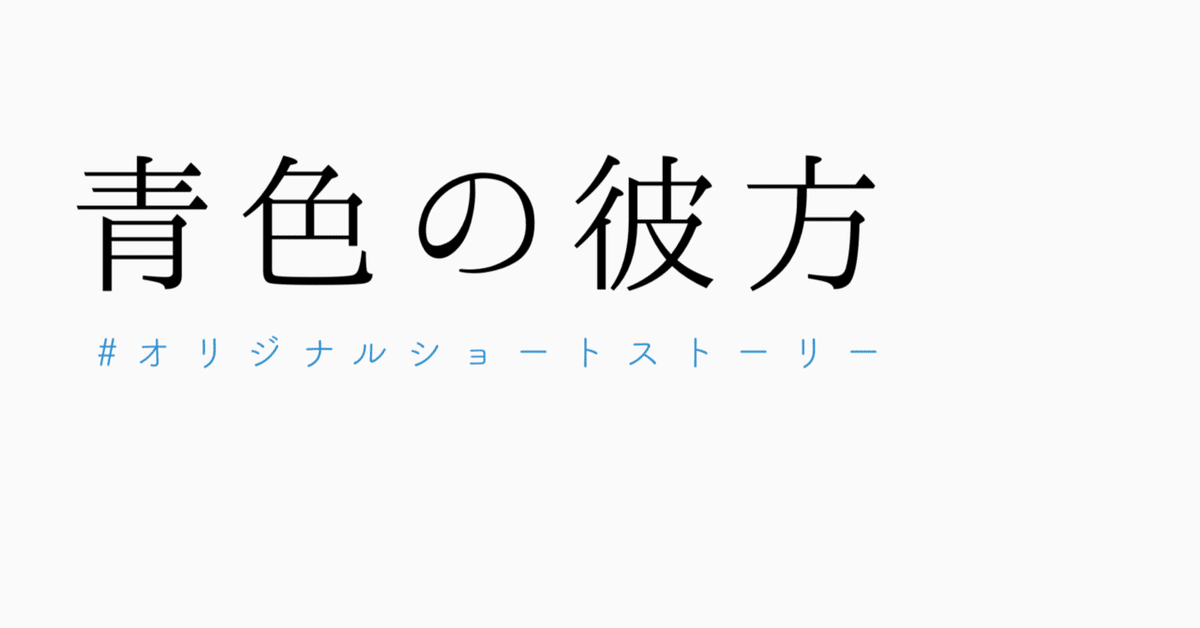
#青色の彼方
俺は誰かに対して、憧れも尊敬も昔からあまり抱くことはなかった。
決して他人を見下しているとかそういうことではない。自分にないものを持ってる人間とか、到底真似できないことを成し遂げた人間とか、単純にすごいと思う。でもそれだけだった。それ以上がなかった。
大学に入って最初に出来た友人、と言っていいのか分からないが、なんとなく一緒にいる青井は、まさに俺にないものを持っていた。俺には到底真似できないことを飄々とこなしている。と言っても良い意味の方ではない。だから、青井には何一つとして憧れることも、尊敬の念を抱くこともない。
青く光る誘蛾灯に誘われるがまま近づく鱗翅目の生き物みたいに、青井にはよく女の子が寄ってくる。近付いた子たちは漏れなく弾かれ、不可抗力のように離れていってしまう。一度離れた子たちは、なぜか二度と青井に近づこうとはしなかった。
「ごめん、お待たせ」
「お前、たまには俺より先に待ち合わせ場所にいたらどうなんだよ」
青井は今日も待ち合わせに遅れた。この間も遅れてきた。反省している様子もない。理由を聞けば「女の子に振られてきた」と、どこか寄り道でもしてきたような口振りだ。
「またかよ……そんなことばっかしてると、いつか刺されんぞ」
「あはは、怖いねそれは」
「いやいや、笑い事じゃないだろ」
喧騒に紛れる青井の笑い声。俺が鳴らした警鐘を他人事のように聞き流すばかりで真に受けることはしない。いつものことだから今に始まったことじゃないけど、最近は青井の持ち物がなくなっていたり、時々物騒なことが増え始めているのも事実だ。
「あ、もしかして俺のこと心配してくれてるの?」
「心配? 誰がするかよ」
「あれ? してくれないの?」
「俺は、客観的に一般論を述べたまでだ」
「なるほど。一般論という名の優しさね」
「なんでそうなるんだよ」
俺に女心は分からない。でも、女の子たちが青井に寄り付く理由は分からなくもない。大半はこの顔に、だろうけど。どこか掴み所のない雰囲気も相まってか、整った顔立ちはそれだけで視線を集めていた。青井はそんな自分に誰よりも無頓着だ。
「刺されて、もし運悪く死んじゃったら、天国に行きたいな」
「即地獄だろ」
どこに行くにも、なにを食べるにも「なんでもいいよ」が口癖みたいなもんで、拘りも執着もコイツからは感じたことはない。
「だったら、彼方のこと道連れにしなきゃ」
「勘弁しろよ……つーか、死ぬなよ、普通に」
本当、いつかふらっとこの地上から居なくなるんじゃないか、なんてそんな絵空事のようなことを根拠もなく思う。確かに、青井に地獄は似合わない気がした。
「ねえ、彼方」
俺の名前を呼んで、目の奥を捕まえるように視線を合わせてから、得意げに口端を釣り上げて笑うだけで、その笑みの後に言葉は続かなかった。
見透かそうとする視線で見つめてくる顔を「なんだよ」と突っぱねても「別に」と笑いながら外された視線は、新着のメッセージを受信したスマホに向けられてしまう。その横顔には感情が見つからない。
「……なあ、青井」
「ん?」
俺は、ちょっとだけ怖くなった。青井はよく「女の子に振られてきた」って言うけど、どんな顔で、それを受け止めているんだろうか。そもそも寄り付かれてる側なのに「振られてきた」ってどういうことだ?
でも、いつか、こうして隣にいる青井に、女の子の影が差す日が来てしまうのだろうか。俺はそのとき、一体何を思うんだろうか。
「なに? 名前呼んどいて、なにも言わないなんて」
「あ、いや、別に……」
「もしかして、さっきの俺の真似?」
無邪気だ。目の前の男は俺の気なんて知らない。なのに、誰もまだこの青井の表面しか知らずにいるのだと思うと、僅かな安堵が俺の心臓を薄い膜で覆っていく。俺だって、青井のことをなにも知らないのは同じなのに。
「真似じゃない、仕返しだよ」
だけど今日も俺は青井の隣にいる。俺の隣には、青井がいる。
【 青色の彼方 】
