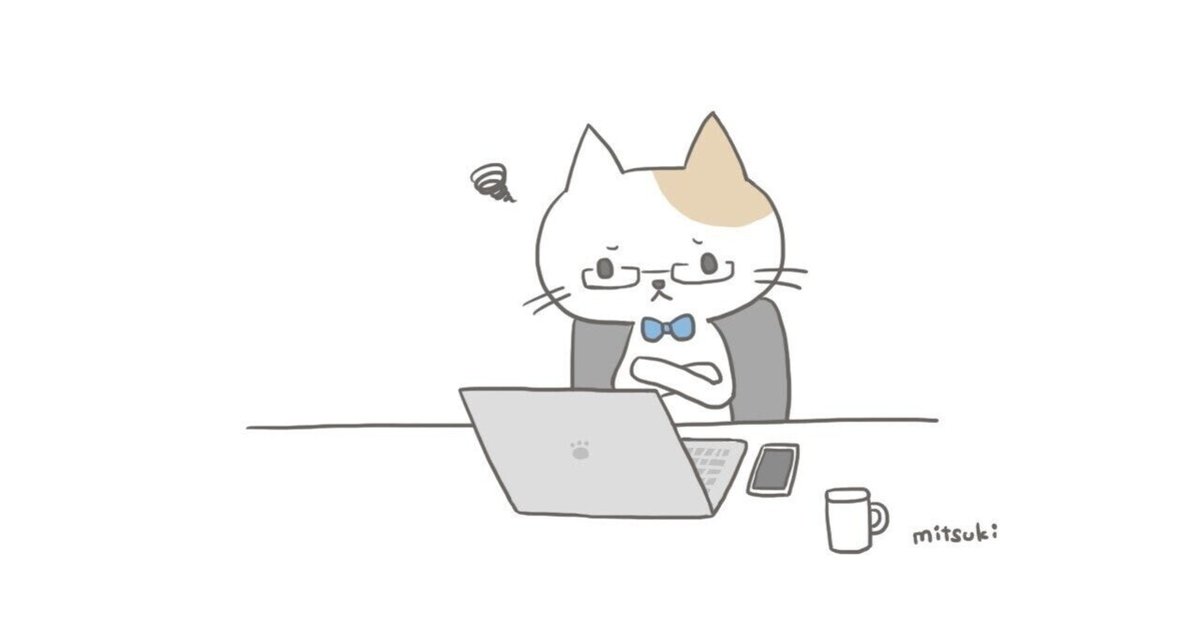
データ整理術!『10月問題』を解決!
今日から10月ですね。
パソコンやスマホのデータは整理整頓されていますか?
設定にもよりますが、表示は、たいてい「名称順」ですよね。
「あ~!!ファイルがどこにあるか分からない~!!」
皆さんのパソコンの中でも、『10月プロブレム』が発生しているかも!?
どの本だったか忘れてしまいましたが、データ整理術で学んで、僕も実践している方法についてご紹介します。
少しの工夫でキレイにデータ整理できると良いですね。
①10月プロブレムの正体
パソコンの画面に「名称順」で表示されるときには、頭文字で判断されています。
頭文字が同じ場合は、次の文字で判断します。
数字は0⇒9に順に、
ひらがなやカタカナではあいうえお順に、
アルファベットはA⇒Zに順に、並ぶように整理されますよね。
(漢字の順番の法則性は僕にはわかりません汗)
(令和に元号が変わったときも、平成の「へ」より後、「H」より後、という推測もありましたよね!)
辞書なんかと同じですね!
例えば、毎月のデータファイルがあるとして、
1月、2月、3月・・・8月、9月とあるとします。
次に『10月』というファイルを作ったとしたならば、
1月、10月、2月、3月・・・
となります。
つまり、頭文字はあくまで「1」ですから、その順番になってしまうんですね。これが僕が勝手に名付けた「10月プロブレム」の正体です!
「第〇校」、「第〇案」、「ナンバー〇」とか、わりと連番でデータ管理しているものは多いと思います。
②2桁の数字には『0』を入れよう!
日付など、2桁になるのは、必ず『0』を入れましょう!
「9月データ」ではなく、「09月データ」と書くようにすれば、
01月、02月、03月・・・08月、09月、10月
と並ぶようになります!!!
僕がよくいただくデータでは、
「2021930作成」というようなファイル名だったら、あとひと手間かかけましょう!
「20210930作成」こうすることで、キレイに並びます。
ちなみに僕は、今年なら「R03」を頭につけるように統一しています。
令和10年になったとたんに、令和元年と並んでしまうからですね。
(ウチのNPOのパソコンの中身をチラ見せ)

③データに日付を入れることのススメ
データに限ったことではありませんが、必要なときに必要なデータがパッと見つからないときは、無駄な時間・労力を使ってしまいますよね。
そのためにも日頃から整理整頓しておいた方が良いですね。
僕も色んな仕事術系の本を読んで今の方法になっていますが、大きくはジャンル分けなどして、細分化していって、最後のファイルなどは、日付を最初に書いておくことをおススメします。
なぜかというと、「あの資料どこにあるかなぁ~」と思い出すときに、頭の中で時系列を遡るからです。
最近のものならより下に、古いものなら上に並んでいます。
また、季節感なんかを覚えていることもありますよね。
対応や蓄積が順に重なって並んでいくことにもなりますので、見た目もスッキリしますよ。
また、整理整頓するには『ルール』が必要になります。
例えば、データを裸でポンと置いて、そんなやつが散乱していたら、なかなか見つかりませんよね。
また、かたや日付が書かれているファイルがあって、かたや「〇〇関係」といったような大雑把なファイルがあったりすると、もうぐちゃぐちゃです。
どういうルールで分けるか決めるとに『MECE』的な考え方が重要です。(ミーシーとかミッシーとか言います。これはまたいつかまとめたいと思います。)
要はちゃんと『すみ分けることができるルールがある』という法則です。
この場合、保存するときの「日付で分ける」という引き出しのルールさえ作っておけば、必ずどこかには収まります。
日付が決めにくいデータでも、着手する日や、ゴールの日などの日付で保存するというルールを決めると良いですね。
④まとめ
データの整理は、自分自身の検索が速くなるだけでなく、仕事であるならば、後任の人に引き継ぐときに分かりやすいものになったりします。
今日のポイント以外にも、様々なコツがありますので、またまとめてみたいと思います。
では、10月になりましたので、1~9月のファイルに0を付けましょう!
あ、来年からで良いか!(笑)
いいなと思ったら応援しよう!

