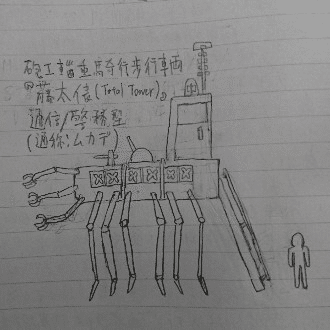随筆(2024/7/16):初期農耕がなぜ維持されていたかの我流「こうではないか」程度の粗っぽい仮説
0.ヘッダはアダム・ロジャース著『酒の科学』(白揚社)表紙であることを明記します

何か問題等ございましたら対処します。
1.初期農耕についての、よくあるがしっくりこない説明
約1万年前とされている農業革命の際に定着した農耕は、もちろん人類史ではかなりインパクトのある技術です。
かつては
「農耕は人類史を直ちに変容させるレベルでの画期的な発明だった」
とふつうに受け止められていました。
今では、様々な理由により、
「農耕が人類史で直ちに画期的な発明として受け止められたわけではなかった」
という流れになっています。
「約1万2800年前のヤンガードリアス期において寒冷化が生じ、狩猟採集民が今までの温暖な気候での生計を立てることは不可能になり、それまでに試みられていたが傍流に過ぎなかった農耕の優位性が高まった」
という説です。
しかし、当然、思う訳です。
「温暖な環境では農耕より狩猟採集に優位性があったのだろう?
わざわざ農耕を技術として確立するまで維持していた人たちは、いかなる動機でそんな不利なことをしていたのだ?」
ここについて、今まで納得のいく説明に触れたことがなかったので、首を傾げていた、というのが正直なところです。
初期農耕の時点で、何らかの維持すべき有難い値打ちがあったはずである。それは何か?
2.農業革命以前の狩猟採集民が建造した神殿
さて、トルコの有名な遺跡に、ギョベクリ・テペ遺跡というものがあります。
これは複数の層を有しており、古いところは1万年前、丁度農業革命と前後する時期であり、当然ながら研究価値が極めて高い遺跡ということになります。
ここには現時点で栽培植物や牧畜の形跡がありません。
おそらくは農業革命以前の狩猟採集民が建築した神殿と推測されています。
つまり?
宗教的動機に基づく建築作業への組織的動員があったということです。
人類は、田畑を作る前に、神殿を作っていたというのです。
聖職者階級があったかどうかは分かりません。
従来、階級の形成には、保管できる余剰食料が必要であったと言われてきました。
当時のギョベクリ・テペが保管技術や余剰食料生産技術を有していたかは分かりませんし、それは少なくとも農耕によるものではなかったはずです。
3.「単なる食料ではなく酒のためだったのではないか」説と併せて考えてみる
ギョベクリ・テペにはもう一つ、興味深い話があります。
科学啓蒙本で知られる白揚社の、下のnote記事をお読みください。
二〇一二年の論文で、さらに古い時代に人類が発酵を行っていた証拠があると主張した。ディートリッヒはトルコのギョベクリ・テペ遺跡で、台所のような部屋に巨大な桶と、モルトか大麦とおぼしき残留物があるのを発見し、これによって人類による発酵の起源はおよそ一万一〇〇〇年前までさかのぼると考えたのだ。マクガヴァンはこの結果を「示唆に富む」としながらも、化学的な証拠や植物による証拠がないとも述べる。
酒です。
ビールが作られていた可能性がある、ということです。
「何で当時非効率的でマイナーだった農耕が維持されていたのか」
という問に対して、私が思ったのが、
「例えば、ビールのために大麦が選択的に収集されていた可能性がある。
ビールはマイナー故に希少価値のある贅沢品だったことは想像に難くない。
(特にギョベクリ・テペ遺跡が神殿なら、ビールが祭祀の際に何らかの霊薬として使われたり、もっと量があれば特定の誰かたちに振舞われたりした、有用性の高い贅沢品だった可能性がある)
長期的に見れば、大麦を栽培しておいて、量を補っておこうという動機は考えやすい。
そして大麦の農耕技術は、マイナー故に希少価値のある贅沢品であるからこそ、優先的に維持されやすかったのではないか」
という答が成り立つのではないか、と思い至った訳です。
4.マイナーでも、特別感が認められれば、維持すべき優先度はむしろ高まる
つまり、
「マイナーであることは、コストをかけて何かを維持する際に、優先度を下げられるデメリットのように一見思える。
が、それがマイナーだが特別感を認められる贅沢品であった場合、維持すべき優先度はむしろ高まる」
という話がしたい訳です。
その後、今まで維持されてはいたものの、生計としては傍流だった農耕が、寒冷化による狩猟採集破綻時に、代替的な生計の主流たりえるだけの有望な生産力を既に獲得しており、主流になった。ということではないか。
当初は生計の手段としては何ら有望ではなかったはずですが、傍流でもそれをやるだけの意義が別に存在したから維持されたのだし、それを積み重ねるうちに、生産性も有望なものにまで育っていったのではないか。
農耕自体、傍流ながらも、そういうのとは関係なく価値あるものとして、苗代の如く大事に育まれた技術だったのではないか。
そういう思い付きです。(「だとしたらある程度しっくりくる」程度の思い付きであり、検証はもっと慎重になされなければならないのでしょうが)
(この記事ここでおしまい)
いいなと思ったら応援しよう!