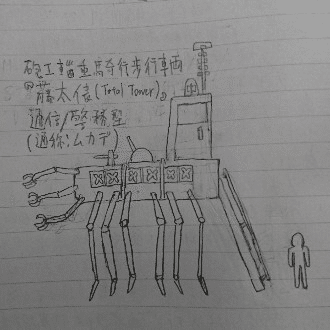随筆(2020/1/23):一対一の人間関係における地位の在り方7-8(ポイントは「妨げられない」「強いられない」という水準の「自由」にある他)
7.ポイントは「妨げられない」「強いられない」という水準の「自由」にある
「自分のやることなすことを、偉そうに、偉いから当然みたいな面で、妨げてきてほしくない」
「対等は嬉しいが、そのためのコストを同意なく突きつけられるのは嫌だ」
「公正取引をしようとする時に、盗人猛々しい人に、際限なく食い物にされて、いつか何もかも粉々にされて搾りかすみたいになって飢えて干からびて死にたくない。断固抗いたい」
「ナメてる相手を面白半分に害していいと思われたくない」
この辺を見ていると、あるパターンが見えてきます。
つまり、一対一の人間関係において、「妨げられない」「強いられない」という水準の「自由」が脅かされると、それは忌まわしくなる、ということです。
これをひっくり返すと、一対一の人間関係においては、この水準の自由は望ましいことなので、重視すべきところだ、という話になります。
8.自由のメリットを貫徹すると約束事のメリットから締め出される
しかし、自由のメリットは、いくつかの副作用をもたらします。
例えば、自由のメリットは、実は約束事のメリットと相容れません。これはかなりマズイと言えます。
約束事について言うと、
「自分が何でもかんでもやらねばならないのではなく、相手が、しかも相手の責任において、何かをやってくれる」
「この中には、コストだけではなく、能力上の理由で、自分が出来ないことも含まれている」
「特に、相手が好き勝手出来て、それで自分が迷惑を被る場合、それを誰かが制裁ないし相手が自制してくれるとなると、自分としては途方もない安全がもたらされる」
という、猛烈に有難いメリットがあります。
そう、約束事とはお互いがお互いと自分自身になにがしかの事柄を「強いる」、「拘束する」ことです。その手段が制裁であるか自制であるかはともかくとして。
拘束力のない約束事、ふつう約束事とは別の単語で呼ばれるものです(対幻想とか共同幻想という用語で、ざっくりとした近似にはなる)。
平たく言って、対幻想や共同幻想とは区別されるような約束事と、拘束力は、切り離せません。
少なくともこの時点で、「強いられない」自由には、どうしようもなく抵触してしまう訳ですね。
そういう意味では、約束事の始まりである、合意というのも、特に自由とひもづくものではない。というか、余儀なくされることも多い。
「あれをしてください、あれをしましょう」「いいよ」と言うのが、必ずしも自由という話ではなく、「嫌だけど、しゃーねーから、いいよ」というパターンもふつうに含まれているわけです。
ついでに言うと、「いいよ」という意志と「嫌だけど」という感情は別物だということは、気を付けねばなりません。
道徳や法などのレベルでは、「何かした」という実践や「どうなった」という結果は、とても重く受け止められます。
「いいよ」という意志は、実践にどれだけ寄与しているかによって、その価値を問われるものです。もちろん重たいものですが、実践に寄与しない限り、ふつうは無視されます。
「嫌だけど」という感情は、実践や意志に寄与しない限り、さらに無視されます。道徳や法のレベルでは、感情の値打ちは、その程度のものでしかない。
強いて言えば、その「結果」が相手に感情的にどう「評価」されるかは、とても重い。特に司法相手の場合は。だが、本人の感情は、かなり間接的な寄与しかしていない。
これらを区別できないと、道徳や法のレベルで何かすればするほど、果てしなく間違っていく。ですが、ここがよく取り違えられている。良くない。
(続きは、また明日)
いいなと思ったら応援しよう!