
越境な日常としっくりの変化 〜手段としてのアンラーニングを越えて〜
MIMIGURIのアドベントカレンダーDay8 記事です。
今年は、MIMIGURI代表の安斎さんの新著『冒険する組織のつくりかた「軍事的世界観」を抜け出す5つの思考法』にちなんで、みんなで #わたしたちの冒険 をテーマに書いています。
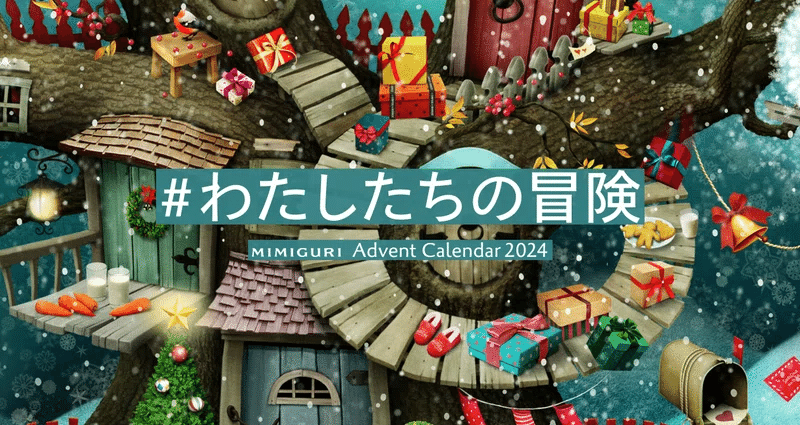
冒険ってなんだろう、と考えたときに、最初に思い浮かんだのが未知との遭遇(映画でなく、文字通り)でした。これをもう少し学習や組織領域の言葉にすると、越境学習の越境とアンラーニングのイメージがしっくりきます。
ここでは、以下の動画で話題提供くださっている法政大学の長岡健さんの考え方を足がかりにして進んでみようと思います。
越境が意識すべきプロセスであり、
アンラーニングは結果
越境は、自分を居心地の悪い(自分にとって異質な)環境にあえて身をおき、自分のあたり前に揺さぶりをかける行為。
アンラーニングは、これまでの自分の知識や価値観などのあたり前を棄てる意味で学習棄却と言われることが多いですが、人や組織のパフォーマンス向上のための手段としてのアンラーニング術ではなく、新しい価値観やライフスタイルの可能性を切り開いていく学びの姿(スタイル)として、アンラーニング論が語られています。
越境によって、自分の中に新しいしっくりがやってくるかもしれない可能性を楽しみにしてみる。そのプロセスに意識を向ける。
結果としての、アンラーニングは起こるかもしれないし、起こらないかもしれない。結果なのでどうなるかはわからないし、どちらでも良い。
漢方薬のようにじわじわと越境を日常に取り込んで、そのプロセスにドキドキしたり、ソワソワすることを楽しむ──。
漫画HUNTER×HUNTER(32巻)で、ジンが世界樹のてっぺんで似たようなことを言っていた気がします。
考え方は魅力的だし、そういう毎日を過ごしたいと思うのですが、一方でぼくには越境ってめちゃくちゃしんどくない? という気持ちがあります。
「アンラーニングってむっずかしいなあ」「越境ってエネルギーめちゃくちゃ使うよなあ」というのも、いまの僕の正直な現実。
でも、自分も気がつけばアンラーニングしてたかも?と、しっくりくるかわからないけどやってみていることもあるな、と気がついたので、残りはそれを1つずつ紹介します。
アンラーニングしていたかもしれない話
MIMIGURIに入社して2年ほどになるのですが、所属組織ではあるけれど、越境的な環境でもあったと思います。転職や異動する人にとっては少なからず越境要素がありますよね。
その中で「頭では良いと思うのだけれど、自分の中に身体感覚はない」ことの連続でした。
もしかするとこれは、軍事的世界観の経験が強く、そんな身体感覚を持ちながら、冒険的世界観に共感する多くの人が感じることなのかもしれません。

図は https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000047.000031576.html
例えば、未知との遭遇の1つは構成主義的な「現実」の捉え方と扱い方。
自分にはあまり馴染のないものの見方(レンズ)だったし、これまでビジネスの中で重要だと思ってこなかったものに思います。
もともと自分は
それぞれの捉え方はあって良い。
だけど ”そんなこと” より、やることやってこそのプロフェッショナル
という価値観がわりと強かったと思います。
だからこそ、一人ひとりがどう考えるかよりも、できるだけバイアスを排して、ファクトを直視するようにする。そしてファクトから次の手を考える。
それを上から見るか下から見るかに、あまり関心を寄せていませんでした。

でも、それぞれの人にとっての「現実」は、レンズによって、様変わりするのは理解はできます。
そして、見る対象がチームや組織の状態、流れているムードや空気感、場で生成されている意味合いの見立てとなると、それを「ありのまま」に捉えるのが難しすぎる。そもそも「ありのまま」というのは何なのだろう。意味や現実はそれぞれの人の中にあるのだから。
・対話や共通体験を通じて、集団の中で共有した現実を立ち上がらせる
・共通の現実を見られていないと各チームや個人は自律駆動できない
・だから、いま皆がいまどのような景色でいて、何が共通基盤になっているのかに気を配る
・集団に対して、情報の正しい伝達ではなく、共有された現実を立ち上がらせていくようなアプローチをとる
上記のような話題に触れたとき、越境者である自分は「そうか、なるほど!」とは思うのですが、感覚は伴っておらず、結果として例えば、会議の進め方や会議に至るまでのプロセスなどにもいちいち、わずかな異質さを感じるのです。
今までは "そんなこと"よりも、やることやろうぜと考えていたのですから。どうも場の議論の重心と自分の関心のズレがあって居心地が悪い。
※一応補足ですが、やることやるのは大事。むしろやらないと感覚が伴わないから、まずやろうの機運が高いMIMIGURIです。
そんな自分でも、2年も立つと「現実はそれぞれの人の中にあるからこそ、対話や共通体験を通じて、集団の中で共有した現実を立ち上がらせよう」というようなことを手触り感(自分にしか味わい得ない身体感覚)をもって書いたり、しゃべったりしている──。
おや、自分のしっくりが変化しているぞ。
2年たって、振り返ってみるとアンラーニングしているじゃん、と。
きっとアンラーニングってこれくらいの時間軸で、自分のしっくりやあたり前が変わっていることに気がつくのでしょうね。
上の法政大学 長岡健さんの書籍でも、「学生は卒業式で味わうくらいでいい」なんておっしゃっています。
それくらい長い時間軸だからこそ、日々アンラーニングしているかどうか(結果)を気にして日常を手段的にするよりも、少しずつ変化させてみる、越境の日常というプロセスそのものに意識を向けると良いということなのだろうと、理解が深まった感じがします。
そのうちアンラーニングするかもしれない話。
しらんけど
長くなってしまったので、続けるか迷いつつ、書いちゃいます。
疲れた方は、最後まで飛んでください!
自分がMIMIGURIで働く中で、大事そうに思うけれど、まだ「未知」で、身体が馴染んでおらず、新しいアンラーニングポイントになるかもしれないものを上記書籍の中で見つけました。
別の言い方をすれば、日々の「しっくりこなさ」を生み出しているもの。
それが「共 common」の感覚なのかもと。

地域研究に関する学問分野では、公(public)と私(private)の中間にあるスタンスを共(common)と呼んでいます。そして、個々人が私利私欲に走る殺伐とした関係を避けると同時に、社会のための自己犠牲が一律の義務となる窮屈な関係を避けながら、一人ひとりが自由意志で、相互に助け合える関係を構築していくことの重要性が指摘されています。
越境も同じです。義務感や同調圧力ではなく、個人の自由意志で、お互いに助け合おうとする共(common)のマインド。公と私のどちらにも過度に偏らない〝ほどよいマインドセット〟で結ばれている人々とのネットワークを作り続けていくことが、越境を繰り返しながら、ドキドキ感、モヤモヤ感を楽しむ〝心の自由さ〟につながっていくのです。
仕事への向き合い方として、新卒の頃の自分は、社会でなんとかやっていけるようにと「私 Private」の感覚が強かったと思います。まずは職業人としてのアイデンティティを確立しようとしていて、そんな行動原理とキャリア観でした。
ある程度経験を積んできた中で、次は「公 Public」に向いたように思います。義務感ではないのですが、社会や事業への貢献に向けて、自分をパーツ的に扱っていたイメージです。
それぞれの捉え方はあって良い。
だけど ”そんなこと”より、やることやってこそのプロフェッショナル
という感覚がまさにこれで、自分個人の感覚は “そんなこと” として切り捨てて、個人の捉え方 ”なんか” でブレずに、やることをやりきるのがプロであり、自分にとってのかっこいい姿、という感覚でした。
他人の内的動機は大切にしたいと思う一方で、自分の感覚や捉え方は割り切る傾向があった気がしますし、仕事ってそういうものだと思っていた節もあります。
そして、いまは「共 Common」を大切にしたいと思っています。
年齢や家族の病気なども経て、「私 Private」の濃度を増したくなった。
個々の衝動と社会的価値を両立する、というのはMIMIGURIの提唱しているCCM; Creative Cultivation Model の根っこのメッセージの1つですが、「私 Private」と「公 Public」の間にある「共 common」とは通じるものがあるはずです。

詳しくは https://www.cultibase.jp/articles/10109
ただ、「共 Common」のマインドセットには、自分はまだ身体的に馴染んでいないように思うのです。
いまの自分は「公 Public」な感覚が強くなるときと、「私 Private」にまで引き戻っているときと両方あり、「共 Common」を大切にしている環境やプロセスや感覚、関わり方、振る舞いなど、が自分にはまだ異質に感じられる部分がある。
でもきっと冒険的な組織にとって大切な感覚の1つだと思っているし、良いな、とは思っているのです。
そんな越境的な環境の中で、試行錯誤のをプロセスを味わって、気がつけばアンラーニングしているかもしれない日々を楽しみながら過ごしたいなと思っている──。
それが、ぼくの冒険の現在地。
これを軽やかに実践しているように感じる身近な人が、実はMIMIGURI Co-CEOの安斎勇樹さんという人に思うのですよね。
しっくりくるか結果はわかないけど、ちょっと面白そうだから、小さく試してみている。CULTIBASE RadioやVoicyではそんな話がよく聞けるので楽しみにしています(宣伝・布教)
お知らせ:冒険する組織のつくりかた
そんな安斎さんが、12月10日(火)に新著『冒険する組織のつくりかた「軍事的世界観」を抜け出す5つの思考法』に関連した無料ウェビナーを開催します。
登録しておくときっと良いことがあるので、少しでも琴線に触れるものがあれば、是非ご登録ください。
明日のMIMIGURI アドベントカレンダー
12月9日(月)のMIMIGURIアドベントカレンダーは、人見知りでひっそり生きるスタンスで、しっかり目立っているkantarockさんです!

