
本を読むのは知識を得るためだけではない〜『脳を創る読書』〜【11月読書本チャレンジ5】
今日取り上げるのは言語脳科学を専門としている酒井邦嘉氏の『脳を創る読書』です。
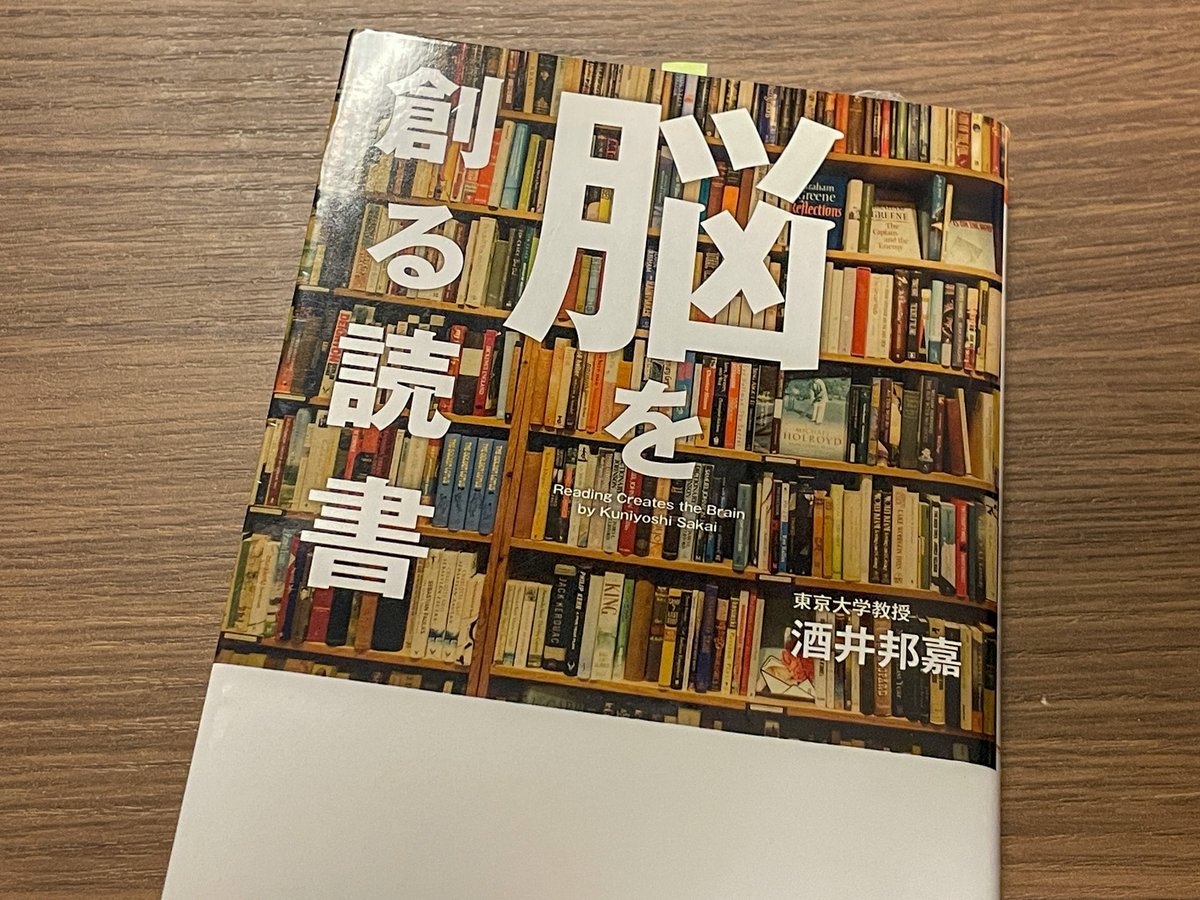
この酒井氏の本は私もいくつか読んでいて、脳科学や英語の学習の話の本でした。本書でもチョムスキーの生成文法理論や、脳の基本的なクセや反応などにもかなり時間をかけて説明されています。文字を読む、という行為がどのように脳内で処理されるか、という点については、また引用してしまいますが、ウルフ博士の『プルーストとイカ』にもある通りです。脳のどの部位がどう働いて処理されるという点については、後続の『デジタルで読む脳x紙の本で読む脳』の最初の章が特に詳しいです。
ウルフ博士の著作でも、そして本書でもある通り、「文字を読む」とは脳にとって想像力を大いに働かせなくてはならない行為なのです。
入力の情報量としては「活字→音声→映像」の順で増えていく。一報、想像力で補わなければならない情報量は、これとは逆の順番になる。
(中略)
ここで言う「想像力」とは、「心的イメージ」に加えて、「自分の言葉で考える」ことだ。
この点は実感があるのではないだろうか? 「本は読めないけど、マンガは読める」とか「YouTubeなら見るけど」というのは、情報量が少ないメディアより想像力をより必要としない、つまり「自分の言葉で考える」必要が少ないメディアの方に私たちがいかに流れてしまうか、ということを表しているのです。読字、という方法を生まれつきの能力ではなく、あくまで獲得形質として会得してきた人類が文字を読むことからどれだけの恩恵を受けてきたか、分かると思います。
SNSやメールの日常化により国民総発信者ともいえる今の時代では「言語能力を鍛える必要」など言われます。私のような一般人がこうやって発信しているのもその流れのひとつですね。
想像力には個人差があり、想像力で裏打ちされた言語能力にも個人差が生まれることになる。
(中略)
職業的な作家は、読書に紛れなく真意を伝えられる技術を持っているし、意図的に読者を誘導したり攪乱させたりすることもお手の物である。これは高度な言語能力に裏打ちされた才能であると言える。そうした言語能力を身につけるには、当然のことながら読書量が関係してくるだろう。
ここにある「想像力」は言語能力のみならず、どんな能力にも関係してくるものです。本書では数学には相当な想像力が必要だ、と書かれています。読書で想像力を養い、言語能力を培っていく必要がどんな人にでも必要、と言えるのではないでしょうか?
読書を通じて想像力を培うことができれば、言語能力も同時に鍛えられる。すると、言語能力に裏打ちされた思考力が確かなものになる。これが本書の「脳を創る」という意味である。
また本書では電子書籍と紙の書籍の違いについても触れられています。双方の利点・欠点についても述べられていますが、ここはつい最近出た新刊『デジタル脳クライシス――AI時代をどう生きるか』の方が詳しいと思われるので、そちらを読んで考えてみたいと想います。
ただひとつだけ。パソコンの画面では間違いが見つからなかったのになぜプリントアウトして紙で見ると見つかるのか、についてはなるほどと思ったので紹介しておきます。画面上ではスクロールして見るけど、紙だと文字と紙の位置関係は一定なので、注意を向けやすい、というのです。脳内で空間的な手がかりが得られる、というのですね。これは手書きでメモを取った方が効果的で記憶できる、という点にもつながる知見かと思います。もっと掘り下げてみたいと思います。
今日の本は、コチラ↓↓↓
10月英語本チャレンジとまとめたマガジンは、コチラ↓↓↓
9月実用書チャレンジをまとめたマガジンは、コチラ↓↓↓
夏休み新書チャレンジをまとめたマガジンは、コチラ↓↓↓
