
心臓病研究の第一人者・大津欣也理事長の圧倒的なキャリアに迫る
こんにちは!
心臓血管外科が舞台の医療ドラマ「ブラックペアン」をご覧になったことはありますか? 手術中の緊迫感や天才外科医の活躍がとても印象的で、視聴しているだけでも「医療の現場ってすごいな」とドキドキしてしまいますよね🫀
ドラマでは患者さんを救うシーンが多く登場しますが、その治療法や医療技術を支えているのは、実際の現場で長年積み重ねられてきた研究の成果なんです。
今回は、その「研究」の最前線で活躍し、日本を代表する医療研究者のひとりでもある 大津欣也 さんをご紹介します。現在は 国立循環器病研究センター(以下、国循) の理事長を務めており、循環器病研究と医療の発展に日々尽力されています。
医療の世界に詳しくなくても、「こんなすごい人がいるんだ!」と驚くこと間違いなし。早速、大津欣也 理事長の素晴らしいキャリアや、その研究への想いに迫ってみましょう!
理事長:大津欣也さんってどんな人?

大津欣也 理事長は、心臓・血管・脳に関する病気の専門家で、特に循環器内科の分野において世界的に活躍されている医師・研究者です。長年にわたり国内外の医療・研究活動に携わり、現在は国循の理事長として、日本の循環器病研究と治療の発展を牽引しています🏥
実際に国循の公式サイトに掲載されている大津欣也 理事長のご挨拶文や経歴を拝見すると、「医療の未来を切り開く人」という表現がぴったりだと感じました😊
ここからは、大津欣也 理事長の経歴や、特に力を入れて取り組まれている研究・医療分野についてご紹介していきます。
大津欣也さんの経歴にびっくり!
▷ 1983年(昭和58年)
大阪大学医学部卒業
▷ 1983年(昭和58年)
大阪大学医学部附属病院研修医(第一内科)
▷ 1984年(昭和59年)
米国国立保健衛生研究所国立老化研究所研究員
▷ 1988年(昭和63年)
トロント大学バンティングベスト医学研究部研究員
▷ 1991年(平成3年)
ニース大学生化学センター客員研究員
▷ 1992年(平成4年)
大阪大学医学部附属病院医員(第一内科)
▷ 1997年(平成9年)
大阪大学医学部助手 (第一内科)
▷ 2002年(平成14年)
大阪大学大学院医学系研究科講師(兼任)
▷ 2005年(平成17年)
大阪大学大学院医学系研究科助教授(循環器内科)
▷ 2008年(平成20年)
大阪大学医学部附属病院科長(循環器内科)(~H22.3)
▷ 2012年(平成24年)
英国キングスカレッジロンドン循環器科教授
英国心臓財団教授(BHF Chair of Cardiology)(兼任)
▷ 2014年(平成26年)
大阪大学未来戦略機構招へい教授(兼任)
▷ 2018年(平成30年)
大阪大学重症心不全内科治療学寄附講座特任教授(兼任)
▷ 2021年(令和3年)
国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 理事長
大津欣也 理事長が大阪大学医学部に入学した1977年は、国循が設立された年でもあります。大阪大学を卒業したあと、国内外で研究や教育、臨床に携わり、循環器内科という心臓や血管の専門分野で活躍されてきました。
大津欣也さんが注力していること

大津欣也 理事長は、心不全に関連する研究で多くの論文を発表されています。特に、細胞の「オートファジー(細胞内のリサイクルシステム)」が心臓病にどう関わるかについての研究は、世界中の研究者から注目されています🫀
現在、国循は、大津欣也 理事長のリーダーシップのもと、より多くの患者さんを助けるための「次世代医療センター」を目指しています。
① 循環器病の研究と治療の融合
国循は、脳卒中と心臓血管病の患者さんの専門的な「治療」と「研究」を行っている世界でも有数の施設です。
② 再生医療の推進
例えば、心筋細胞を再生する新しい治療法の研究が行われています。将来的には心臓病の治療が革命的に進化するかもしれません。
③ AIやICTを活用した医療
大津欣也 理事長は、AIやデジタル技術を使って診断や治療を効率化する取り組みにも注力しています。これにより、より早く正確な診断が可能になるとされています。
大津欣也 理事長は、医療の未来を切り開く存在として日本のみならず、世界中で注目されています。その活動は、私たちがより安心して生活できる社会を作るために欠かせないものです。
心臓や脳の病気に興味がある方や、医療分野で働きたいと考えている方にとって、大津欣也 理事長の研究や取り組みはとても参考になるでしょう。
英国キングス・カレッジ・ロンドン (King's College London) とは?

大津欣也 理事長の経歴を調べて、特に印象的だったのは、イギリスのキングス・カレッジ・ロンドンでも教授を務めていたこと。「世界でも認められるって、本当に一握りの人だけだよなぁ」と、単純に感心してしまいます✨
キングス・カレッジ・ロンドンの歴史
イギリスの名門大学と聞くと、オックスフォードやケンブリッジが思い浮かぶかもしれません。キングス・カレッジ・ロンドン(以下、KCL)は、これらの大学と比べると、日本ではあまり知られていないかもませんが、医学や人文学、科学の分野で世界トップクラスの評価を受けていて、イギリスの大学ランキングではトップ10にランクインしています!
(参考:Best universities in the UK 2025 - University Rankings)
KCL王室の後援を受けて設立され、イギリスの高等教育における重要な役割を果たしてきました。その特徴的な点は、伝統を守りつつ、現代的で実践的な教育を提供してきたことです。
医療、科学、人文学の分野で数多くの革新を生み出し、教育の幅を広げてきました。「単に歴史があるだけじゃなく、今でも革新を続けている」その姿勢は、まさに学びの理想形だと感じます。
ナイチンゲールとの深いつながり

KCLの歴史を語る上で欠かせないのが、「近代看護の母」と称されるフローレンス・ナイチンゲールとの関係です!
彼女は1860年にセント・トーマス病院で世界初の看護学校を設立したことで知られていますよね。この学校では、看護を「経験頼りの仕事」から「科学的知識と技術を持つ専門職」へと変革しました。
彼女の理念は、「解剖学や衛生学、公衆衛生といった知識を持ち、患者の回復を支える」こと。これが当時としては革新的で、看護師の地位を劇的に向上させるきっかけとなったのです💉✨
その後、1974年にナイチンゲール看護学校はKCLと統合され、現在の「フローレンス・ナイチンゲール看護・助産・緩和ケア学部」となりました。
ここで学ぶ学生たちは、ナイチンゲールの理念を受け継ぎながら、現代の看護や緩和ケアの最前線で活躍しています。
正直なところ、看護という分野にあまり詳しくなかった私でも、「歴史がただの過去のものではなく、形を変えながら生き続けているんだな」と感動しました。こういう取り組みが、看護や医療の未来を支えているんですよね。
KCLで得た経験が日本の医療を変える原動力に!
KCLは、大津欣也 理事長のキャリアにおいても重要な役割を果たしています。大津欣也 理事長はKCLで循環器科の教授を務め、英国心臓財団(BHF)のChair of Cardiologyとして、心不全や細胞のオートファジーに関する研究を進めてきました。この研究が世界的に評価され、国循での現在の活動にもつながっています。
このような国際的な舞台で活躍する日本人がいることにとても誇りを感じませんか😳?そして、KCLで培った知識や視野が、現在の国循の理事長として、日本の医療改革を推進する力になっていると思うと、その影響力の大きさに改めて感銘を受けます!
伝統を未来につなぐキングス・カレッジ・ロンドン
KCLについて調べるうちに、単なる「名門大学」という言葉以上の意味を感じました📚ナイチンゲールの理念を継承し、現代の看護教育と医療研究をリードするその姿勢は、世界中の学生や研究者を引きつける大きな魅力となっていることでしょう。また、大津欣也 理事長のように、この大学で培った知識や経験を活かして、日本や世界の医療に大きく貢献している方も多くいらっしゃいます。
もし、KCLやナイチンゲール、大津欣也 理事長の研究に関心があるなら、さらに調べてみると新しい発見があるかもしれません😊この大学が築いてきた歴史とその未来への挑戦は、私たちにとっても多くの学びを与えてくれるはずです!
国立循環器病研究センター(国循)とは
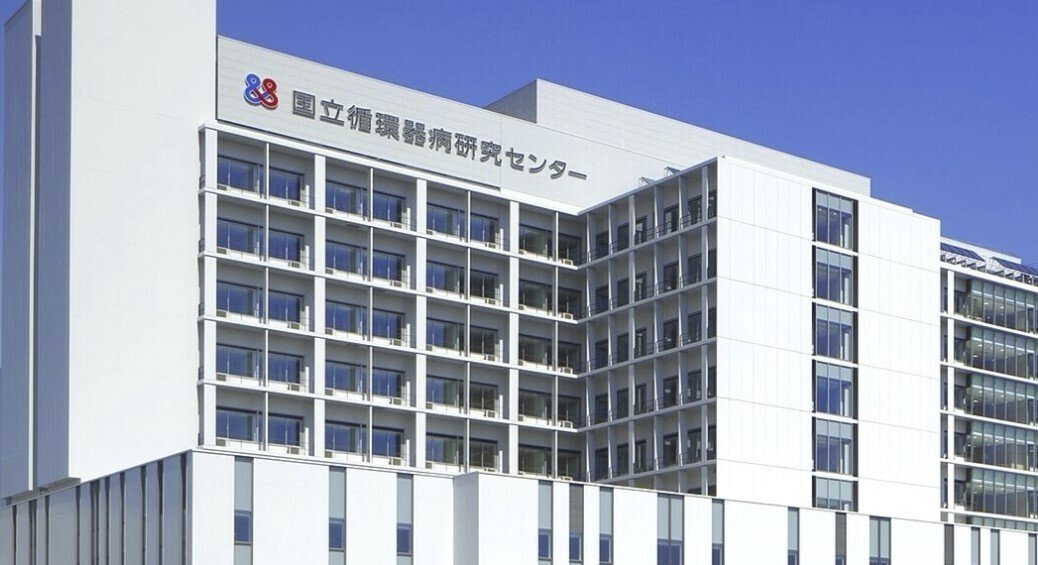
国循がどんな施設なのかについても説明しておきたいと思います!
国立循環器病研究センター(National Cerebral and Cardiovascular Center, NCVC)は、大阪府吹田市にある心臓や血管、脳の病気に特化した病院兼研究機関です。これらの病気は「循環器病」と呼ばれ、心臓発作や脳卒中のように命に関わることが多いため、専門の知識と技術が求められる分野です。
▷理念◁
私たちは、国民の健康と幸福のため、高度専門医療研究センターとして循環器疾患の究明と制圧に挑みます。
国循では、患者さんの診療(治療)はもちろん、病気を治す新しい方法を開発するための研究や、医師や看護師の教育も行っています。
まさに「循環器病のスペシャリスト集団」といえるでしょう!
どんなことをしているの?
主に次の3つが国循の役割となっています!
◍病気を防ぐ・治す
高度な医療技術を使って、患者さんを治療します。また、病気にならないための予防法を広める活動もしています。
◍新しい治療法を開発する
「どうしたら心臓や脳の病気をもっと早く、確実に治せるか」を研究する場所でもあります。これにより、未来の医療が進化していきます。
◍専門家を育てる
若いお医者さんや研究者が、ここで最先端の技術を学んでいます。
何がすごいの?
◍最先端の医療が受けられる
日本中、そして海外からも患者さんが治療を受けに来ます。たとえば、心臓の手術や脳卒中の治療において、他では受けられない特別な医療を提供しています。
◍研究と診療が一体化している
病院と研究所が一緒になっているので、研究で生まれた新しい技術がすぐに患者さんの治療に活かされます。
◍多職種が協力して治療する
医師だけでなく、看護師やリハビリ専門家、研究者がチームを組んで患者さんをサポートします。
例えば、こんな取り組みも!
◍病気を予防するための啓発
健康的な食生活や運動習慣を国民に広める活動をしています。生活習慣病を防ぐことが、心臓や脳の病気を防ぐ第一歩だからです。
◍再生医療の研究
例えば、心臓の細胞を再生させる治療法の研究など、未来の医療を目指した取り組みを行っています。
◍AI技術の活用
人工知能を使った診断支援や治療法の開発にも力を入れています。
どんな人が利用するの?
心臓や血管、脳の病気で専門的な治療が必要な人
例えば、心不全や狭心症、脳卒中といった重大な病気を抱えた方が、国循で最先端の治療を受けるために訪れています。これらの疾患は放置すると命に関わることが多く、専門的な知識と技術が必要です。国循では、それぞれの患者さんに最適な治療プランを提供しています。高血圧や動脈硬化など、将来が心配で予防したい人
「まだ病気ではないけど、このまま放っておくと心臓や血管に負担がかかるかもしれない…」そんな将来のリスクを心配される方も多く訪れます。国循では、病気を未然に防ぐための予防医療にも力を入れており、生活習慣の改善や定期的な健康チェックなどのアドバイスを受けられます。他の病院で治療が難しいと言われた人
専門的な診断が必要な難病や、治療が難しいと言われた疾患を抱える方が、最後の希望を持って国循に訪れるケースも少なくありません。国循では、国内外の研究成果を取り入れた高度な治療法を提供しており、多くの患者さんにとっての「最後の砦」としての役割を果たしています。
それだけに、もし病気になったときは「これからどうすればいいんだろう」と不安に思うことが多いですよね。
病気はいつ誰に訪れるかわかりません。だからこそ、万が一に備えて国循のような専門機関を知っておくことはとても大切です。心臓や脳の病気で不安を抱えたときに、「ここならきっと助けてくれる」という場所を知っているだけで、心の支えになるのではないでしょうか😊
心臓病の最高権威!大津欣也 理事長まとめ

大津欣也 理事長のこれまでの素晴らしい経歴や、心臓や脳の病気の治療・研究に取り組む姿勢は、医療の未来に大きな希望を与えてくれるものだと感じます。特に、世界中の研究機関で培った経験をもとに、日本の医療をさらに進化させようと尽力されているその姿勢には、深い敬意を抱かずにはいられません。
普段の生活ではあまり意識しないことかもしれませんが、こうした医療や研究の発展が、私たちの日常の安心や安全につながっているのだと思うと、なんだか心強いですよね。例えば、心臓や脳の病気に関する最先端の治療法が、いざというときに自分や家族を救うかもしれない。そんな風に考えると、こうした取り組みの重要性をより身近に感じます。
私たちの日常の陰で進められている研究や医療技術の発展が、より多くの人を救う未来へとつながることを、心から願っています!
