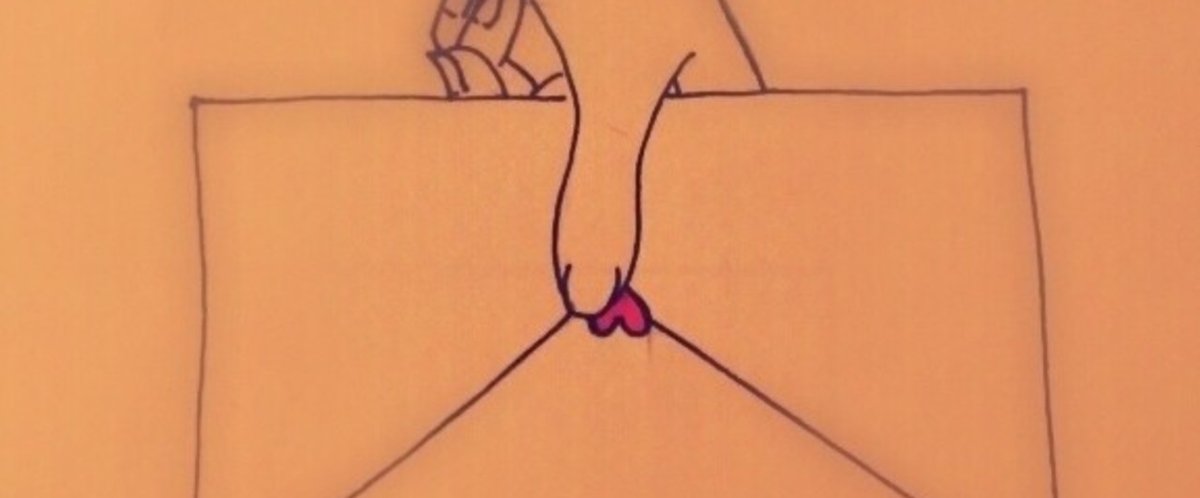
「四百四病の外とは言うが、」
「どうしよう、めっちゃ心臓どきどきしてきた。」
色素の薄い瞳に西日が当たって、きらきらと反射した。セーラー服はこの子のために作られたんじゃないの、と、思うほど良く似合う。
「大丈夫でしょ。渡すもん渡せばそれでいいんだから。」
「もー!わかってるよ、わかってるけどー…!」
伸びたセーターで半分隠れた白い手の先には、ラッピングされたチョコレートが握られている。そんなにがちがちで掴んでいたら溶けるぞ、と思ったけれど、いっぱいいっぱいの当人の前では口を噤んだ。
「ーーーじゃあ、あたし、行ってくるから!」
命でもかけてるのか、と思うほどの勇ましさでカスミが教室を出ていった。ぱたぱたと軽い上履きの音が遠のいて、教室にたった一人残される。
カスミが、恋をしたのはいつだったっけ。
机に頬杖をついたまま数ヶ月前のことを思い起こす。クラス替えをして最初のテストが終わった頃だった。たしか小雨が降っていた。紫陽花が咲く校門までの道を、カスミが校庭ばかり見て歩くようになったことに気づいたのは。
肩までの髪が頬を刺す。自分の爪先を見ると少しだけ伸びた爪が目に入る。カスミは料理が好きだから、あの子の爪はいつも驚くほど丁寧に切られて整っている。清潔感のあるあの手が、とても好きだった。家庭科部で何か作る度に、帰り道に分けてくれた。よもぎ餅も、バナナのケーキも、プリンも。カスミのお菓子を一番食べたのは自分だと思う。「瑠璃子のために甘さ控えめにしたよ」と、笑顔で言ってくれた。
けれど、チョコレートだけは。
チョコレートだけは、あたしのために作ってはくれなかった。校庭をぐるぐると走る陸上部の先輩の為にあの子は何度も試行錯誤して作ったのだ。
あたしの為じゃないお菓子は何度も口の中でどろどろと溶けて、そして少し苦かった。
世の中の病気のすべてを「四百四病」と言うらしい。恋煩いはその病気に含まれないので、「四百四病の外」と定義されるのだそうだ。
こんなに泣きそうなのに。
こんなに胸が痛いのに。
鞄の中からチョコレートの小箱を取り出した。
既製品だ。可愛らしいラッピングが施されたそれが、机の上をいっぺんに華やかにする。あの子に渡そうかと、何度も迷って迷って、結局放課後になってしまった。料理上手な人に手作りを渡すことは憚られたし、手作りすることで自分の下心が全部チョコレートに入ってしまいそうで、怖くて作れなかった。
『あたしだけのものになって。』
言えたら、どんなに楽だろうか。
窓の外の風景をぼんやりと眺める。ガラス一枚隔てた外で枯葉が舞っている。驚くほど軽やかに、音が聞こえるんじゃないかと思うほど。
ーーーするり、と、チョコレートの箱にかけられたリボンをほどいた。音もなく、何の抵抗もなくゆるやかに解かれたそれは、机の上に散らばった。
箱を開けると、トリュフが6つ並んでいる。
1つ摘んで、半分ほどかじる。中からクリームがとろりと流れた。灰色のセーターにトリュフの粉が少しつく。もうずっと、一生叶わない恋の形をあたしは知ってる。17歳のあたしは、叶わないけれど、それでも、胸を痛める恋をした。この記憶がいつか遠くなった時に、あの子の短い爪や、ひだの一つ一つ丁寧にアイロンのかけられたスカートや、セーターの裾を伸ばす癖や、手作りのお菓子のすべてを、愛しく思い出せるだろう。
誰かを好きになれるといいな。
出来るならば、好きになっても良い人を。
ぱたぱた、と、軽い足音が少しずつ近づく。駆け足で戻ってきているのを、音で先に知る。
ガラッ
音を立てて扉をあけて、カスミが教室に飛び込んできた。
「渡して、きたっ…!」
西日が彼女の輪郭を綺麗に縁どって、扉の枠の中に立つカスミが一枚の絵のように見えた。
緊張したー、と、大きく息をついたカスミが机の上に出ているチョコレートに気づく。
「あ、一人でずるい!何食べてるの?」
カスミが不思議そうに市販のチョコを眺める。もらったの?と、聞かれて、何となく「うん」と答える。
「じゃああたしも、瑠璃子に。」
いつもありがとう、と、可愛らしい袋を手渡される。
「ありがと。」
「いえいえ。トリュフいいなぁ。一粒くれてもいいんだよ?」
「だーめ。」
「えー!瑠璃子のけち。」
むくれるカスミを笑ってから、そっと箱を閉じた。
〈了〉
