
『アブラハム渓谷』、あるいは磁石女の冒険
両岸を段丘に挟まれた1本の大きな河が、特別印象的とは言えない日中の陽光によって照らし出されている。ポルトガルにおいて最も巨大な河川であるこのドウロ河周辺にはいくつもの建造物が立ち並んでおり、かなり遠くから捉えられたロングショットを通して見ても、その街の活気がひしひしと伝わってくるほどだ。この簡潔極まりないショットによってマノエル・ド・オリヴェイラの映画『アブラハム渓谷』は始まりを告げられる。現代映画最大の映画作家の、しかも渾身の一作と言われるような作品がこのように静謐で平凡なショットによって始まるとは何事か。しかし侮ってはならない。オリヴェイラの映画はいつもそうだ。『神曲』も『メフィストの誘い』も『クレーヴの奥方』も、それぞれ精神病者たちの住む屋敷、とある修道院の正門、国際的な人気歌手の楽屋を、決して動かないカメラで無機的に捉え続けるのみである。オリヴェイラはいつも、オープニングショットのあまりの簡素さに油断した観客を、次の2、3分の間に捕食してしまう。この得体の知れない、実際にあるかどうかさえ怪しい渓谷の名前を冠した映画もきっと2、3分のうちに ー189分もあるからもっと余裕を持って我々を狙ってくるかも分からないがー 私たちを捕食しにかかるだろう。そんな勘ぐりを頭の中で反芻させていたのも束の間、何やら怪しげなナレーションが画面空間に響き渡る。感情を抑えた上品で深みのある男の声が、まるで腕白な御曹司を暖かく見守りながらも先の行く末を案じる執事かの如く聞こえてくる。このナレーションを、この作品の撮影監督であるマリオ・バロッソが担当しているというのも驚きだが、何にも増して驚くべきなのはこのバロッソの声があまりにも美しいものであって、まるでこの作品のナレーションを担当するためだけに生まれてきたかのようにさえ思われてしまうということだ。それが何千人ものオーディションの中から選ばれたというならまだしも、オリヴェイラの友人であり俳優としても活躍しながらこの作品のカメラマンを務める男が偶然的にこの声を担当しているに過ぎないという事実を知ってまえば、『アブラハム渓谷』という作品の現場には「奇跡のような傑作」にありがちな“僥倖”があったのだと想像するに難くない。
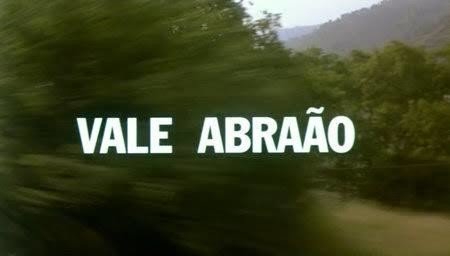
“僥倖”に導かれたその声が「アブラハム渓谷」という土地の歴史や名前の由来、登場人物たちの来歴を説明すると、カメラはドウロ河の片岸を走る列車の中に移り、動き続ける車窓の風景を捉える。瞬く間に過ぎ去っていく此岸の家々や木々と、ゆっくりと移ろい行く彼岸の急斜面との美しいコントラストの中で、“VALE ABRAÃO” という文字列に続くオープニングクレジットが始まる。『悲情城市』の寛美のナレーションに匹敵する美しさをはらんだバロッソの声と、車窓の上に記されるオリヴェイラとその幸運な仲間たちの名前のアルファベットに重なる列車の走行音に限りなく心を奪われそうになったところで、この映画を見る我々はもう現実世界に後戻りできないことを悟る。なぜならこのシークエンスに続く、14歳のエマと町の有力者であるカルロスの初めての対面シーンの官能性を見てしまえば、私たちはもはやこの映画を理性や知性を持って見ることはできず、ただ感性と本能でしか見ることができなくなると分かるからである。14歳のエマは、とても現実のものとは思えない ーしかしオリヴェイラ的世界において現実的か非現実的かといった尺度は全て無効になるー 白く淡い光に照らされながらカメラを見据えて画面の中央に収まる。舞台となる上流階級御用達のレストラン ーカルロスが経営するー の床や壁は黒を基調とした色彩を誇っているため、エマのクロースアップはフェルメールやラファエロの絵のように空間から特権化されて画面に定着している。ただこのエマ = セシル・サンス・デ・アルバのクロースアップと先に挙げた画家達の作品との大きな違いは、エマは真珠の耳飾りをつけた少女や聖母マリアとは異なり、ナレーションにもあったように悪魔のような笑い声をあげたり、邪悪な官能性を心のうちに感じさせたりするという点である。その後、カルロスはエマの父を訪ねるという名目で彼女の家に上がり込む。そこでのエマとカルロスの再会は、「美しい」という言葉が誰でも知っている形容詞であるがゆえに、美しいと形容することすら憚られるほどだ。エマの父と座って話すカルロスの後方に、フォーカスの外れたエマがフレームインする。エマの存在に気づいた父は、彼女にカルロスに挨拶するよう促す。猫を抱えたエマは、カルロスのことを覚えていないと言う。

この発言が、彼女が本当にカルロスのことを覚えていなかったがためになされたものなのか、あるいはあらゆる男を惑わしてやまないエマという女のアプリオリな性質ゆえなのかは分からないが、少なくとも映画の終盤で同じ体勢 ー猫を抱えて話し相手を見つめるー の彼女が、そのあまりの官能性からカルロスを激怒させ、猫を放り投げさせてしまったのと同じだけの艶かしさを、このとき既にエマが保持していることは確かだ。カルロスはエマの方を振り返る。2人が何も話さないまま、カメラは2人の顔の正面からのショットを2度ほど切り返す。私たちはこのシークエンスで、確実に世界に何かしらの変容があったことを感じとる。カルロスはいたいけな ーしかし邪悪なー 少女の恐ろしいほどの磁力に、彼の空間的なもののみならず時間的なもの ーつまり人生そのものー さえも狂わされてしまったのである。

映画はここまでで約9分であり、このペースで1シーン毎に述べていけば一年かけても書き終わることのないことは明らかなので、このまま書き続けることはやめにする。だが私たちは先のシーンの、エマの強力な“磁力”について考えていく必要がある。なぜならこの映画は、エマが持つ磁力によって様々な人間や事物が引き寄せられたり離れたりして推進していくドラマに他ならないからである。オリヴェイラ本人が、小津生誕100周年のシンポジウムに参加した後に蓮實重彦に送った映画理論に書いている通り、映画において運動とは時間の表象に他ならない。運動を画面に表象させることによって見る者は時間を知覚する。しかしその運動は、決して目に見えるもののみによって発生するものではない。世界を変容させることがドラマであり、それが映画的な何かであるとするならば、『アブラハム渓谷』においてそれをもたらす運動エネルギーとは決して目には見えない力なのである。
エマには強力な磁力がある。その証拠に、少女時代のエマがベランダで家の前の通りを眺めるシーンを思い出して欲しい。強力な磁石がブラウン管のテレビを故障させてしまうように、白いワンピースを着た14歳のエマがベランダに出るだけでその前を通る自動車の運転手のハンドルを狂わせてしまうのだ。初めてエマが1人で電車に乗り、隣町に住む有力者の双子の老女に挨拶に行った際、彼女は老女らが自分を舐め回すように見てきたことに憤慨する。そこでエマは悪魔のように恐ろしい笑顔を2人に振りまくことで応戦して見せるのだが、彼女の憤りは収まらない。

家に帰ったエマは父親に老女らへの怒りをぶちまける。1人娘を愛してやまない寡の父は、彼女の機嫌を治そうと真珠のネックレスをエマに贈る。鏡の前でそのネックレスをつけて見せ、嬉しそうに笑うエマの表情は隣町の老女の家で見せたものとは全く異なる可憐なものである。すっかり機嫌を直したエマは白い日傘を差して、生まれつき自由に動かすことのできない右足を引きずりながら屋敷の外の葡萄園へ行き、そこの小さな階段に腰を下ろしてネックレスをうっとりと見つめる。すると彼女の目線の先に葡萄園の水やりの仕事をしている、彼女と同い年くらいかそれより2、3歳年上と思われる少年たちがいることに気付く。少年たちはあわよくば彼女の見えそうで見えないスカートの中を見んと、チラチラと彼女の方を見やる。それに気づいたエマは、再び機嫌を損ねてすぐに葡萄園を立ち去る。その時彼女が差す白い日傘の広がり方が美しい。その後エマは気分転換にベランダへ出るのだが、そこで自動車事故が起こる。
『アブラハム渓谷』においてエマは、引き寄せるものを全て引き寄せ、拒むものを全て拒んでやまない。彼女はその魅力によってあらゆる男たちを引き寄せてしまうが、同時に彼女を愛そうとする男たちをこれでもかと拒絶し彼らを精神的に追い詰めさえする。その様はまさに強力な磁石そのものだ。エマが、”愛してもいない”カルロスと結婚する時、そこでなされる結婚の誓いや結婚式のミサそのものは幸福で華やかなものであるはずなのに、それを動かないカメラで捉え続ける画面はどこか不吉な時間を記録している。それが、あまりに美しすぎる女エマと幸か不幸か結婚することとなったカルロスの目に余る動揺具合と、それと対照的なエマの堂々とした表情の恐ろしさによるものであるのかは分からない。この時差し出されたエマの手と、その薬指に指輪をはめようとするカルロスの手とのクロースアップは、まさにラファエロの絵のように美しい。しかしただ、手の震えるカルロスが指輪をエマの薬指にはめようとする際、その指輪がただ彼が手の震えから指を滑らせただけとは到底考えられないほどの勢いで教会の床に落下していくことは確かだ。それはちょうど、同じ極を持った磁石同士を近づけたときの磁石の様子に似ている。
エマが強力な磁力を持っていることは、彼女が社交界にデビューした際に髪飾りを床に落としたり、愛について語ったセンブラノ邸での夕食会で彼女がブレスレットを落としたり、物をやたらに落とすことから明らかである。またこの仮説を裏付けるように、エマ本人がルミナレスとの会話の中で万有引力の話をしてみせさえする。しかしこの映画でエマの磁力が他の何にも増して重要であるのは、先にも述べたようにこの磁力によってこの作品の世界が変容してしまうからである。カルロスが成長したエマを初めて見たとき、それはエマの叔母の葬式であった。多くの親族や関係者が集うエマの屋敷で、彼女は棺の周りの蝋燭に火を付けている。そこにカルロスが遅れてやってくると、エマはカルロスの方を振り返り涙を見せながら軽く微笑む。”カルロスは驚いた。エマは信じられないほどに美しくなっていた。”

この時、場は決定的に変容している。大人数が集まる「公共的空間」であったその部屋はほんの一瞬のあいだ、カルロスとエマだけが知覚する「私的空間」に変貌するのである。この瞬間にカルロスはエマの恐るべき磁力に引き寄せられてしまう。彼の人生はその磁力によって大きくねじ曲がってしまうのだ。またエマの磁力は、彼女が不倫する相手であるオゾリオの屋敷に勤める使用人たちにも影響する。エマに対して密かに慕情を抱いていたカイレスは、ある日オゾリオの屋敷の玄関を掃除婦の格好 ーエメラルドグリーンのワンピースに赤いバンダナ姿ー で掃除しているエマの姿を見つける。その瞬間にカイレスの慕情はエマへの欲望に変わる。しかしエマは彼の甥であるフォルトゥナートを誘惑する。2人が2度目に逢瀬をするシーンが何よりも美しい。彼らが行く別宅は、ルノワールの絵画のように、あるいは天国のように黄色い光と感動的な植物たちの緑に包まれている。それをカイレスは段々畑の上からただ見つめることしかできない。カイレスはやがてロンドンでの事業に成功し、エマと再会する。そこで彼はエマに対して金銭的援助を申し出る代わりに自らの愛に応えることを要求する。しかしエマはそれを拒絶し、屋敷からも去っていく。こうしてカイレスはついにエマを手に入れることができなくなるのだが、結局のところそれはカルロスも同じである。エマは彼女を欲するすべての男を拒絶してやまないのである。

自宅を去り、唯一の理解者と言える洗濯女のリティーニャとも黄色いバラを贈って別れたエマは、オゾリオの屋敷であるベスビオ園へ行く。そこで彼女は少女時代のように可憐な服を着て、オレンジの実がなる木々の間を抜けて、かつて多くの男と不倫を重ねた現場であるボート乗り場に向かう。そこで彼女は、これまで自分が多くのものを地面に落下させてきたのと同じように、自らの体を河に落下させてしまう。もちろんこれはエマがボート乗り場の木が腐った部分を踏んでしまったことによる事故ではあるのだが、オレンジ農園を抜けていく彼女の姿は自らの死を予見していたかのようだ。その時の彼女の表情は恍惚としていて、自らがやがて死ぬはずの地点へ無意識のうちに引き寄せられていくように見えるのである。そこでナレーターはセンブラノ夫人がカルロスに自らが書いた小説を託したことを述べる。そして最後にセンブラノ夫人はこう言った。「たいしたことは書いてないけど、人生は美しい。そのことだけは一生懸命書いたつもりよ。」

