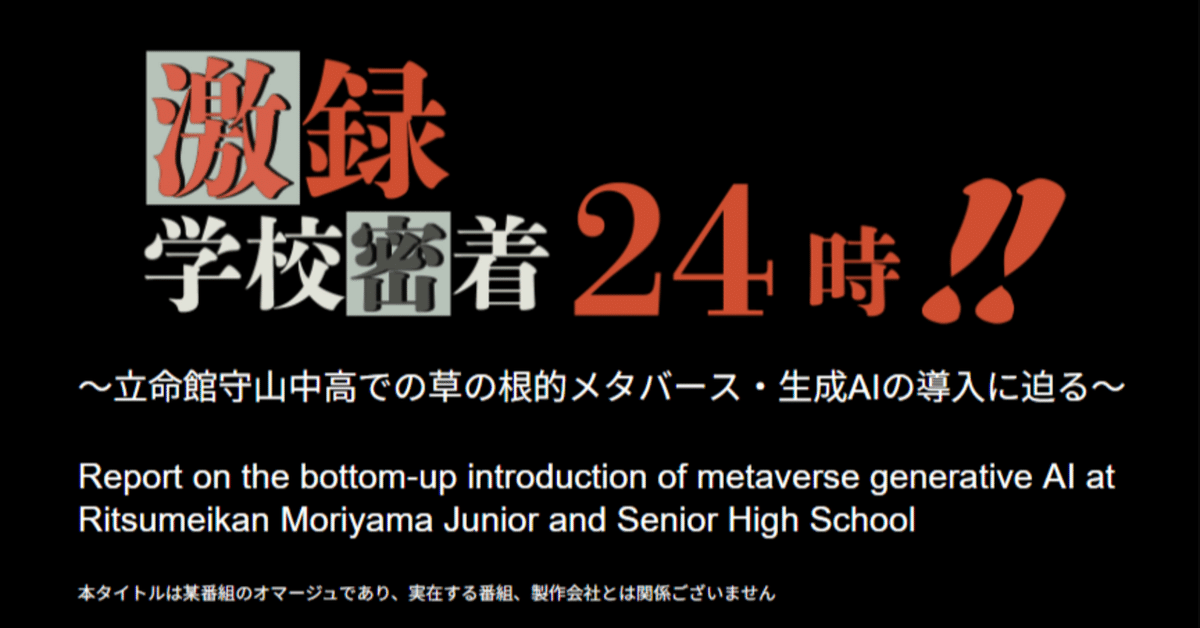
【Code for Japan Summit 2024】教育×テクノロジーの新しい可能性:立命館守山中高での56ヶ月の軌跡

私たちインパクトラボは、先日開催されたCode for Japan Summit 2024にて、立命館守山中学校・高等学校との取り組みについて共同で発表させていただきました。2020年から始まったこの挑戦は、今や56ヶ月に及びます。今回は、その歩みをご紹介したいと思います。
デジタル化が進む学校現場で見えてきた課題

「最近の生徒たちは、とても疲れているんです」
立命館守山中学校・高等学校の箭内副校長は、現代の教育現場が抱える課題をこう表現します。特にコロナ禍以降、「会話疲れ」「教室での居づらさ」「心の不調」など、これまでにない悩みを抱える生徒が増えてきました。

授業の形も大きく変化しています。かつての「先生の話を聞いて、ノートを取る」というスタイルはほぼ姿を消し、グループでの話し合いやプレゼンテーション、主体的な学びが求められる双方向型の授業へと移行しました。これは教育の質を高める一方で、生徒たちに新たな負担も生んでいます。これらの状況を「アウトプット/主体性の過剰」と箭内先生は表現します。
さらに箭内先生によると、生徒たちは毎朝、その日の授業でどう振る舞うべきかを考えながら登校しているといいます。「人前での発表が不安」「間違えたらどうしよう」—— そんな緊張感を抱えながら、一日を過ごさなければならない状況が続いているのです。
そのような状況では、自分のキャラクターを何度も変えることができるアバターになれば、テクノロジーを上手に使って不屈の闘志を鍛える必要がなくなる未来が近づいています。
デジタル保健室:新しい相談のカタチを目指して

「養護教諭は通常1人か2人。性に関する相談、家族の問題、自傷行為など、様々な悩みに一人では対応しきれません」
立命館守山中学校・高等学校の養護教諭、山村先生はそう振り返ります。この課題意識から始まった保健室の改革は、従来の枠組みを大きく超えるものとなりました。
まず取り組んだのが、保健室に隣接する「オルバ(サポートルーム)」の設置です。「カフェに立ち寄るような気軽さで来てほしい」という思いから、従来の不登校支援室とは異なるアプローチを採用。このオルバには、教員ではないスタッフを配置し、生徒たちが気兼ねなく足を運ぶことができる空間を作り上げました。さらに、保健室もカフェのようなデザインで、現在では外で生徒と話ができるオープンテラスを作りました。

そして2022年、新たな試みとしてデジタル保健室プロジェクトがスタートします。このプロジェクトでは、単に実際の保健室を再現するのではなく、生徒たちの声を設計に反映させることを重視しました。特にコロナ禍で増加した「一人の時間が欲しい」「対面でのコミュニケーションに疲れた」という声に応えるため、アバターを介したコミュニケーションの仕組みを取り入れています。

メタバース上の保健室は、実際の保健室の温かみを残しながらも、より明るく開放的な雰囲気を持つ空間として生まれ変わりました。その活用は想定以上に広がりを見せています。養護教諭が日常的にデジタル空間で生徒たちと交流を持ったり、登校が難しい生徒との遠隔カウンセリングに活用したり、さらには性教育のワークショップや文化祭での企画など、新しい取り組みの場としても機能しています。
特筆すべきは、生徒たちが自然とこの空間を活用し始めていることです。当初想定していた相談機能に加えて、生徒同士の交流の場としても発展しつつあります。

2024年からは保健室のAIによる対応の試験導入も予定しています。基本的な健康相談や一般的な質問にAIが対応することで、養護教諭がより専門的な支援に注力できる体制づくりを目指します。
「デジタル保健室は、決して既存の保健室の代替ではありません。実際の対面での関わりとデジタルでの支援、この両輪があることで、より多くの生徒たちの声に耳を傾けることができると考えています」と山村先生は語りした。
英語教育を変える:メタバースとAIの可能性

「日本語でも人前で発表することが苦手な生徒が多い中で、英語となるとさらにハードルが上がります」
立命館守山中学校・高等学校の英語科教諭、山内先生は日本の英語教育における課題をこう指摘します。特に印象的だったのは、帰国子女の生徒たちの様子だといいます。英語が堪能であるにもかかわらず、周囲の反応を気にしてわざと下手に話す。この現象は、日本の英語教育が抱える本質的な課題を表していました。
この状況を改善するため、山内先生は新しい学習環境の構築に着手しています。最初の試みとして、教員研修の場でメタバースを活用しました。約100名の教員がメタバース空間に集まり、実際にコミュニケーションを取る実験を実施。この経験を通じて、仮想空間での対話が、実際の場面でのコミュニケーションを促進する可能性を見出しました。

続いて文化祭では、小学生から高校生までを対象としたワークショップを開催。このワークショップでは、メタバースと生成AIを組み合わせた新しい英語学習の方法を提案しました。特に重視したのは、AIを「練習相手」として活用する方法です。

具体的には、生徒たちがAIやメタバースで英語でコミュニケーションを取る練習を行い、その後、リアルな教室で周りの人とコミュニケーションをとることで、教室での英語での会話を促進しようという流れです。「失敗を気にしなくていい」という環境が、生徒たちの積極性を引き出しました。
さらに、実際に山内先生が授業をされている高校3年生の英語の授業でも生成AIを活用してみました。すると生成AIを活用した生徒の英作文の量は75語から91語へと増加し、スピーキングの面でも大きな進歩が見られています。
「これは日本の英語教育における弱点を克服できる可能性を秘めている」と山内先生は手応えを感じています。生徒たちの反応も予想以上でした。先ほどの文化祭でのアンケートでは8割を超える生徒が「メタバースでの英語学習に積極的に取り組みたい」と回答。特に「もう一度挑戦したい」活動として、インタビュー形式の会話練習が高い支持を得ました。
山内先生は、生成AIやメタバースには、教室での学びをさらに豊かにする可能性があると考えています。「テクノロジーは決して従来の学習を置き換えるものではありません。むしろ、生徒たち一人一人の可能性を広げる、新しい選択肢として活用していきたい」と語ります。

テクノロジー導入で大切にしていること

「『新しい技術だから使う』のではなく、『必要だから導入する』—— この原則に至るまでには、私たちなりの試行錯誤がありました」
インパクトラボの戸簾さんは、立命館守山中学校・高等学校での取り組みをこう振り返ります。
最先端技術をまずは取り入れてみようという学校だからこそ、メタバース空間の構築では「とりあえず学校を再現してみて考えよう!」としたものの、そこからの展開が難しくなり、躓きを経験しました。技術先行で作った空間は、最初は盛り上がったものの、結局誰にも使われることなく、ただそこにあるだけの存在となってしまったのです。
この経験から、今回のサミットの「シビックテック」としての重要な気づきが得られました。教育現場へのテクノロジー導入は、単なる技術実装ではありません。感動や楽しさを重視するのか、それとも機能や管理のしやすさを重視するのか。この判断は、大学と初等中等教育では全く異なります。
例えば、大学ではカオス的な状況も許容されますが、初等中等教育の現場では、より慎重なアプローチが必要です。シビックテックとして大切なのは、その違いを理解した上で、必要な技術を必要な方法で導入すること。現場のニーズに応えていなければ、どんなに優れた技術でも意味をなさないのです。
教育機関でのテクノロジーは、人と人との関係性を豊かにするための道具に過ぎません。対面でのコミュニケーションに取って代わるものではなく、むしろそれを補完し、新しいつながり方を提供する存在として活用していく。それこそが、私たちが目指す教育現場でのシビックテックのあるべき姿だと結論づけました。
これからの展望

私たちの取り組みは、新たな段階に入ろうとしています。その一つが保健室AIの試験導入です。このAIは、定型的な健康相談や一般的な質問への対応を担当します。しかし、これは決して人による支援の代替ではありません。むしろ、養護教諭の先生方がより深い支援や緊急性の高い案件に注力できる環境づくりを目指すものです。
56ヶ月に及ぶこの取り組みを通じて、私たちは教育現場でのデジタル技術活用に確かな手応えを感じています。生徒たちの新しいコミュニケーションの形、教職員の業務効率化、そして何より、従来の教育では見えづらかった一人一人のニーズに応える可能性が見えてきました。
これからも立命館守山の先生方や生徒たちと共に、より良い教育環境の実現に向けて挑戦を続けていきたいと思います。

最後に、この取り組みにご協力いただいている立命館守山中学校・高等学校の箭内先生、山村先生、山内先生、そして生徒の皆さんに心からの感謝を申し上げます。
