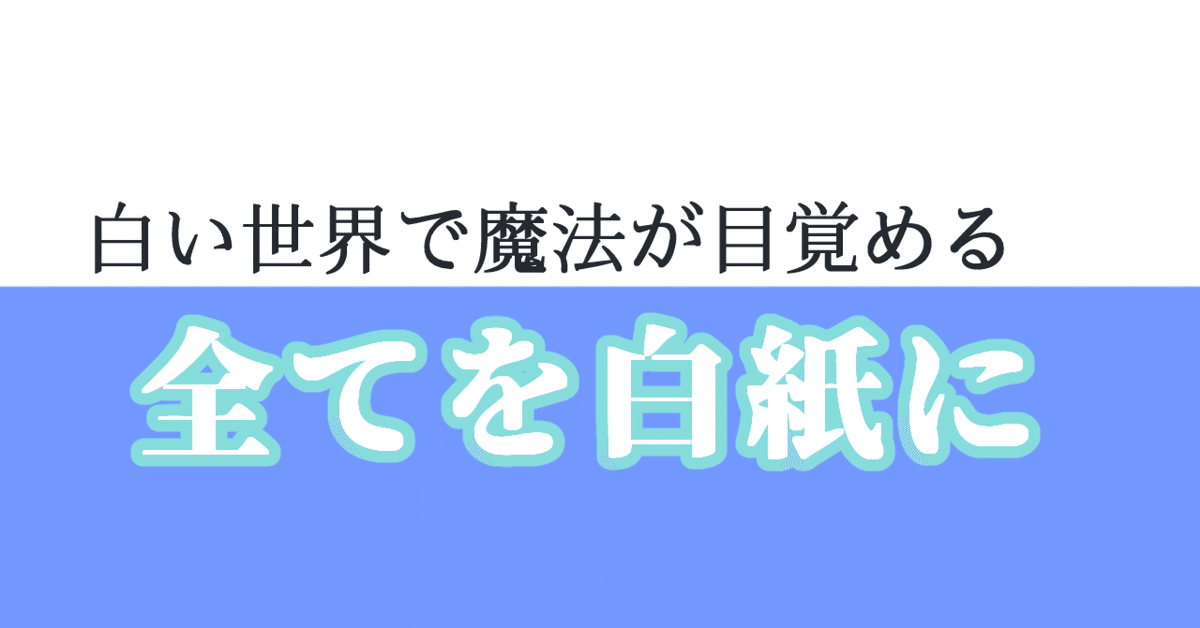
ライニア乱記 全てを白紙に 第三章 日常に帰る日 三、奇妙な団結
前の話へ
三章一話へ
序章へ
目覚めたアーウィンは、自分が白い天井の下に寝かされていると気付いた。体には布団が掛けられ、どうやらベッドの上にいるようだ。命にも等しい横笛は枕元にあったが、他の荷物は見当たらない。両隣にも寝台が並んでおり、左ではフュシャが退屈そうに正面の広い窓を眺め、右ではイムトが半身を起こしたまま呆然と固まっていた。
「ああ、やっとお前さんも起きたか。厄介なことになったよ」
フュシャがこちらを認めて笑い掛け、自分たちがいるのが警察病院だと聞かされた。イホノ湖でシランに受けた傷の治療は終わり、後は様子を見るだけだという。
結局、「虹筆」は軍に奪われてしまった。文字通り世の中を変えられると思った好機は、失われた。「野蛮人」はどこまで自分を邪魔するのか。生きている間に何度も湧き上がってきた思いに身を焦がし、アーウィンは布団の下で強く拳を握り締めた。
「お怒りはごもっともだけどさぁ……ミュスの全員に全員が、お前さんみたいに『故国奪還』とやらを望んでいるのかい?」
フュシャが顔を覗き込んでくる。それに背を向け、アーウィンは昔味わった失望を思い返した。十八から二十歳になるまで、同じ民族の人々を訪ね歩いた。そこで誰も彼もが、ライニアを再び自分たちの国にすることを諦めていたのだ。彼らは今のライニアや、遠く離れた異国での暮らしに溶け込んでいた。新しく作り上げた生活を壊したくないと言う者もいた。
計画が頓挫した今になって、アーウィンの胸にあの時以来の虚しさが込み上げてきた。先祖の悲願を果たそうと躍起になっているのは、民族の中で自分だけではないのか。同郷の仲間が広い社会に出たり、家庭を持ったりしていると思うと、今までの行動が馬鹿らしくなる。自分一人だけがその場で足踏みをして、周りに取り残されている。
そこまで考えたところで、アーウィンは首を振った。積み上げてきたものを、ここで捨てる気なのか。興味のない事柄にも触れながら、望みを叶えようとしてきたではないか。「虹筆」は少し手元を離れただけで、まだ全てが終わったわけではない。再び「虹筆」を手に入れれば、それこそすぐにでも「故国奪還」は果たせる――!
「おいおい、待ちなって。もし傷に障ったらどうするんだい?」
ベッドから下りようとしたアーウィンは、フュシャに引き留められて気を悪くした。この女も「野蛮人」だ、自分を阻もうとしているのだ。無視して床に足を付けかけた時、予想していなかった問いが動きを止めた。
「お前さんは、ライニアの血が入っている人全員が嫌いなのかい?」
フュシャが純粋なライニア人ではなかったと、アーウィンはここで初めて知った。彼女の祖母は、ライニアより南方の大陸にある国・イベテの出身だという。それでも「野蛮人」の血が入っている点に変わりはないと吐き捨てかけて、昨日まで共に旅をしていた少女を思い出した。
日常で魔術を使えない彼女は、異端であった。旅の途中でも不慣れな技に苦戦し、周りからも未熟なことで色々と言われていた。今回の騒動が起きるまでも、奇異な目で見られていたかもしれない。その姿に、同じくライニアに住みながら迫害されてきた民族の在り方が重なった。
「……『少数派』なら、同情の余地くらいはあるかもしれないな」
仮に日常が戻れば再び憂き目に遭うだろう少女を思い、アーウィンはそう呟いていた。フュシャは興味深そうにじっとこちらを見ていたが、やがて彼女自身も「少数派」に入るか尋ねてきた。彼女が唐突に明かした話に、アーウィンは首を捻った。彼女のような立場にある人がどれほどいるか分からない以上、断定は出来ない。きっと隠しているだけで、その数は意外と多そうだ。
アーウィンとフュシャが話し込む中、イムトは一向に黙ったままだった。それがふと気になったように、フュシャが彼へ声を掛ける。二回ほどの呼び掛けで、男はようやく掠れ気味の声を出した。
「おれは団長さんの役に立つどころか、迷惑を掛けちまった……」
「そりゃそうだな、頼まれてもないのにイホノ湖へ行ったんだから」
普段はこうした批判的なフュシャの言動に反発するイムトも、今日は言い返さなかった。
「団長さん、おれにはすごくかっこいい人に見えた。インディみたいに堂々と動いて世界を変える、革命者になるんじゃないかって」
イムトが意外な人物を尊敬していたと聞きながら、やはりインディに憧れていた者の姿がアーウィンの脳裏に浮かんだ。一方でフュシャは、部屋中に響くような嘆息をついている。彼女はインディに傾倒した家族に連れられ、無理やり「白紙郷」に入れさせられたのだった。十六歳の時からなかなか進展しない活動に嫌気が差し、その度に脱退しては小さなきっかけで戻ってきた。
そんな自由な動きの中で、自分は「白紙郷」に誘われたのだとアーウィンは振り返る。誰も「故国奪還」に賛同してくれず諦めかけていた中、フュシャは消却爆弾と「虹筆」の存在を教えてくれた。あれを聞いて、新しいやり方で「故国奪還」を行おうと決めたのだ。ライニア神話になぞ全く興味がなく、先日イムトと交戦した折も彼の攻撃は効かなかった。それでも最終的な目的はともかく、手段としては「白紙郷」と合致する点はあった。
「あんたがいなかったら、俺は民族の希望を捨てるしかなかっただろうな。……あの時はありがとう」
フュシャが驚いてアーウィンを一瞥し、くしゃりと表情を緩めた。対してイムトは、いかにも不満そうな顔をしている。嫌いなフュシャが感謝されている様が気に入らないのだろうか。彼と話をしようとして、アーウィンは窓枠が音を立てているのを耳にした。そして突如、部屋を激しい横揺れが襲う。扉の外で騒ぎが起こり、フュシャがベッドを下りてそっと様子を見に行った。
短い揺れが収まっても、フュシャは廊下を覗いたままだった。扉の隙間から、慌ただしい声が入り込んでくる。漏れ聞こえる情報を集めると、病院の近くが消却されたという情報にまとまった。首都を襲うのは、国土消却の最終段階だったはずだ。もうライニアの外にも、消却計画が用意されている。そこまで確かめて、アーウィンはいきなり部屋を飛び出したフュシャに肝を抜かれた。先ほどは自分を止めたくせに、何をするのか。苛立ちを覚えて笛片手にアーウィンもついて行くと、後ろからイムトの足音も迫ってきた。
「病院暮らしも飽きてきたからね! それで、どこへ行く?」
混乱する院内を走り抜けつつ、アーウィンは先を行く女の無計画性に呆れる。「虹筆」を取り戻すため、国防省に行こうか。そんなアーウィンの提案は、真っ先に却下された。あそこは警戒が厳しい上に、「虹筆」を持つ部隊には顔を知られている。納得できる理由にアーウィンが何も言えないでいると、進行を阻む人の群れが前方にあった。
さすがに走っている状態では、笛を吹くのは難しいだろうか。迷っている間にフュシャが大きく、右手を前へ突き出した。彼女の周囲に無数の光が浮かび上がり、弾幕に変じて人々を襲う。突然の攻撃に戸惑う彼らの脇を抜け、三人は病院を突破した。遠くで爆音の轟く町中を行き、イムトが声を張り上げる。
「おい、本部へ行ってもいいか? 団長さんに謝りたいんだ!」
「いいねぇ! その機転を、普段の仕事でも生かしてほしいんだけど!」
本拠地なら、軍も制圧に来るかもしれない。その隙を突いて「虹筆」を取り返せるとフュシャから聞き、アーウィンは今しがた出た候補地に行くことを了承した。どこかで自動車でも奪えれば、早く辿り着けるはずだ。最後の望みに賭け、アーウィンは笛を握り締めて走り続けた。
敵の本拠地として報告を受けた場所に向かっていたヘイズは、移動中の窓から昨日捕らえた三人が駆ける様を目撃した。部下に彼らを追うか聞かれるが、首を振る。恐らく行き先は、自分たちと同じだろう。今は事件解決を優先し、着いたところで再び捕縛するのだ。
窓から目を離し、ヘイズは手元の資料を読み返した。改めて情報を確認すると、自分の愚かさをより身に染みて思い知らされる。彼が防衛省を訪れた時点で、警戒すべきだったのだ。こちらの情報が、向こうに渡っているとも考えられる。とはいえまだ策はあるとヘイズは気を取り直す。全てが判明した今、事態収束までの距離は近い。
首都を出ると、車外は白い風景に包まれた。機械による案内がなければ、運転手も移動に困っただろう。ヘイズは助手席のカーテンを閉め、目を休ませるように瞼を下ろした。外は風の音がたまにする以外は、驚くほど静かだ。この辺りの人も、避難したか消却されたかで存在しないのだろう。
逸る鼓動に、ヘイズは手をやる。何もかもが消え去る前に、元通りにしなければならない。あの哀れな教授に、どうか考えを改めてもらいたい。その使命と同時に、教授と同じ境遇にあった青髪の少女と仲間たちは無事かという懸念が、ヘイズの胸に浮かんでいた。
