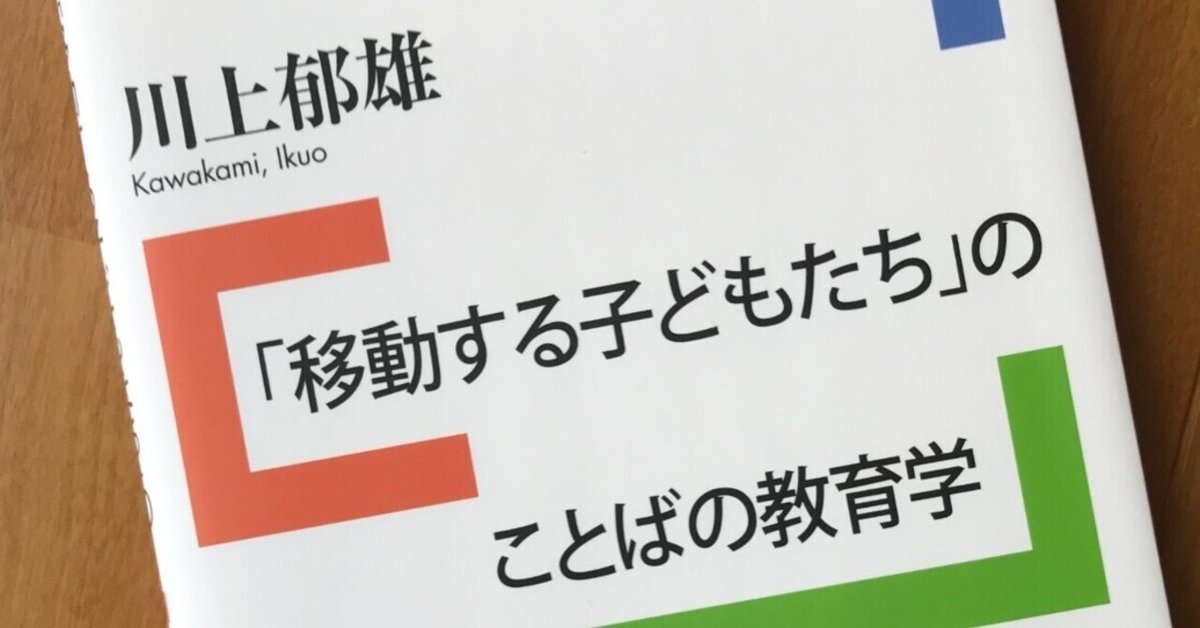
MY BOOK REVIEWS⑦「移動する子どもたち」のことばの教育学
このシリーズの7冊目にレビューする書籍は、『「移動する子どもたち」のことばの教育学』(2011, くろしお出版)。
この本は、2006年から始まった「移動する子ども」シリーズの第6弾として編んだ本である。「序 「移動する子どもたち」のことばの教育を考える」の後、以下の構成で編まれている。
「第1部 なぜ「ことばの力」の把握が大切か」(第1章、第2章、第3章)。「第2部 「移動する子どもたち」のことばの学びをどうデザインするか」(第4章、第5章、第6章)。
「第3部 「移動する子どもたち」のアイデンティティと「ことばの力」」(第7章、第8章、第9章、終章)。
ご覧の通り、本書の主題は、幼少期・成長期に複数言語環境で成長する子どもの「ことばの教育」を考えることである。第1部では、「ことばの力の捉え方が言語教育のあり方を決定する」という基本的視点から、実践者が「ことばの力」をどう捉えるかが最も重要なテーマであることが述べられる(第1章、第2章)。
「それは自明だ」と思われるかもしれないが、大人の学習者を対象にした日本語教育では実践者は自身が「ことばの力」をどう捉えるかよりも、日本語の教科書をどう教えるかということに関心を持つ人が多いのではないだろうか。というのは、大学の日本語センターや日本語学校では、実践をする前にすでに「初級クラス」「初中級クラス」「中級クラス」などと、学習者集団が「分類」されていて、さらにそのクラス用のテキストが事前に決められているケースがほとんどなので、学習者の「ことばの力」や「どのテキストを選ぶか」などについて実践者が悩むことが少ない。
しかし、子どもが対象の場合、来日時期や滞日期間、年齢・学年などがバラバラのため、指導する子ども一人ひとりの個別性が異なり、それゆえ、その個別性をどう捉えるか、どう理解するかが実践をする上で重要な「鍵」となる。そのような意味で、子どもの個別性、特に、「ことばの力」を把握するツールとして、「JSLバンドスケール」が提案されている(第3章)。
ここでも異論が来るかもしれない。つまり、子どもの「ことばの力」を把握することが必要であれば、「テスト」をすればいいのではないか、と。端的に言えば、「いいテストを作れば、ことばの力は把握できる」とテスト研究者は考えるだろうが、「JSLバンドスケール」は「テストでことばの力は把握できない」という立場である(この点の詳細な議論は、別の記事で述べることにしよう)。
では、どうするか。それは、実践者と学習者の相互の関係性のもと、実践者が実践の中で主観的に子どもの「ことばの力」を把握することになる。それが、実践の前提、つまり、基本的な視点となる。その視点から、実践をデザインすることが必要となることを論じたのが、第2部である。
第2部で中心となる議論は、「実践的教材論」である(第5章)。「ことばの力」を把握することから、実践をどうデザインするかが論じられている。さらに、「JSLバンドスケール」とその実践論を理解した専門家、「日本語教育コーディネーター」が教育支援システムに必要であることが述べられている(第6章)。この考え方は、東京都目黒区や三重県鈴鹿市で実践されることになる(これらの実践の詳細も、別の記事で述べることにしょう)。
子どもへの日本語教育は、子どもに日本語を教えればよいという単純な教育実践ではない。子どもの個別性を踏まえた上で、子どもの主体性、「ことばの力」とアイデンティティを育成することが大切である。そのことを論じたのが、第3部である。その教育を実現するための「支援」と「連携」の実質化も課題である(第9章)。
それらの議論を統合する形で、終章で「「移動する子ども」学の創発へ向けて」と展望が述べられる。この「移動する子ども」学というのは、私の造語であるが、本書の「序」で本書のテーマについて次のように説明している。
「これらの「移動する子どもたち」のことばの教育は、日本に限らず、また日本語に限らず、世界各地で大量の子どもたちが直面している教育的課題であり、グローバル・イシューであるからである。したがって、本書が最終的に目指すのは、「移動する子どもたち」のための総合的な言語教育としての「移動する子ども」学の提唱である」(p. ⅱ)。
終章でも、最後に次のように述べている。
「「移動する子どもたち」の実践研究は、子どもと実践者の双方の主体性やアイデンティティと視点の相互構成的関係にある実践研究である。それゆえ、多様な子どもたちがことばによって他者と関係性を構築し、ことばを通じて自己形成と自己実現を図りながら、21世紀の新たな社会構築に参加していく力を獲得できるような、ことばの教育の実践が、そして同様に、実践者自身の主体性と実践者としてのアイデンティティの構築を図れるような、相互構築的関係性をめざす、ことばの教育の実践が求められているのだ。「移動する子ども」学という学問が成立するとすれば、それは世界各地にいる多くの多様な子どもたちや実践者たちとともに構築する動態的で、かつ協働的実践研究の発展形と言える「学」になるのではないだろうか」(p.217)。
本書は、2002年に早稲田大学に着任し、大学院で教鞭をとりながら、日々思考を深めつつ、少しずつ書き溜めた論考を中心に編んだものであるが、当時から、「移動する子ども」学を構想していたことがわかる。それは、「実践の学」「日本、日本語に限らない、グローバルな社会的課題を探究する学」であること、さらに、学習者だけではなく、「実践者自身も変化することで成立する学」であることを述べている。
本書には、広島大学名誉教授の縫部義憲先生から以下の帯文をいただいた。
「本書は、「移動する子ども」を分析概念として年少者日本語教育学へ切り込み、子どもたちの「ことばの力」を育む実践を目指す。日本語教育学的語りと文化人類学的語りの節合という新しい視点にたった「移動する子ども」学の構築は、これからの時代にふさわしい新しい展開を予感させます」。
「日本語教育学的語りと文化人類学的語りの節合」とは何かは本書の終章で述べているので、それにゆずるとして、新しい「学」の立ち上げには多様な視点が必要であることを指摘していただいたと思う。
「これからの時代にふさわしい新しい展開の予感」とは何だったのか。
私は「序」に次のように書いた。
「難民問題に限らず、親たちの移住、ビジネス、留学、国際結婚、国際離婚などで、大人たちに随伴して移動を体験する子どもたちが、今、多数生まれてきていることを考えると、現代社会における「移動」と「ことば」の課題は極めて大きいと言わざるを得ない。この(本書の)タイトルには、そのような思いが込められている」(p. ⅱ)。
このように、2011年当時から、「移動」と「ことば」というテーマがあり、それが後に新しい書名となり、研究が発展する。それが、まさに「予感」だったのかもしれない。
本書は、2010年度の「科学研究費補助金・研究成果公開促進費」の助成により2011年2月10日に刊行できたが、1ヶ月後の3月11日の東日本大震災の際には私は仙台の自宅で被災し、それから5月半ばまで新幹線が不通になり、大学へ行くことはできなかった。
その後、「移動する子ども」学の探究は継続され、さらに展開、発展することになる。その過程は別の記事で述べたいと思う。
この本のカバーも、桂川潤さんが作ってくださった。ありがたいことに、2020年、3刷目に入った。
