
ジャズと私(17)マイルスのファンクに痺れる
【約1800字/4.5分で読めます】
▼前回の記事
前回の記事では、私が27歳の頃('10年)に NHK ではじまった『スコラ 坂本龍一 音楽の学校』でジャズのルーツを知った話を書きました。
ここまでの私の音楽遍歴を見てきてもわかるように、私の音楽的趣向の中で、「ジャズ」が中心になったことはありませんでした。
10代~20代前半までは、「テクノ」が中心で、ジャズの要素が入ったクラブミュージックも聴き、たまに本流のジャズに手を出す感じでしたね。
20代後半になってからは、テクノのルーツの一つである「ソウルミュージック」や「ファンク」に興味を持ちました。
それ以降も、やはり、ジャズの要素が入ったその手の音楽を聴いたり、たまに本流のジャズに手を出すという日々が続いていたのです。
この時代(2000年代後半~2010年くらい)の私にとって、特に気になっていたのが「ファンク」だったんですよね。
そんなこともあって、おそらく『スコラ』を観て以降のことだと思うんですが、マイルス・デイヴィスの一枚のアルバムが気になっていました。
それが『On The Corner』('72)というアルバムです。
このアルバムはジャズの作品ではあるのですが、同時代に活躍したファンクバンド、スライ&ザ・ファミリー・ストーンに強い影響を受けて手掛けたアルバムとされています。
'70年代のマイルスといえば、『Kind of Blue』('59)と並ぶほどの代表作とも言われる『Bitches Brew』('70)が有名ですよね。

『Bitches Brew』は「フュージョンの元祖」ともされており、20歳の頃にウェザー・リポートにハマった自分としては、いつか聴かなくてはと思っていたアルバムでした。
ところが、20代の頃の私はこのアルバムを聴いたものの、ハマることができなかったんです。
何年か前にも再トライしたのですが、やはり、難しく感じるんですよね。
逆に『On The Corner』の方は、すぐにおもしろさがわかりました。
なんでも、このアルバムはクラブミュージック世代にも再評価されているらしく、実際に聴いてみると、テクノに通じる感じがあるんですよね。
電子音自体は、それほどたくさん使われているわけではないんですが、やはり、スライに影響されたファンクのリズムが、テクノっぽいのです。
私はこのアルバムを聴いた時に、20歳くらいの頃に夢中になって聴いたジャーマン・ロックの『Zero Set』('83)というアルバムを思い出しました。
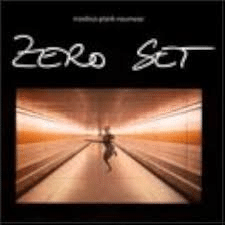
Moebius-Plank-Mani Neumeier('83)
『Zero Set』もそうですが、『On The Corner』は「編集した音」の感じがすごくするんですよね。
『On The Corner』には、ハービー・ハンコックが再登板したり、チック・コリア、ジョン・マクラフリンをはじめとする、たくさんのプレイヤーが参加しています(クレジットでマイルス以外のメンバーを数えてみると、21人!)。
しかし、そんなに「セッション」っぽくなくて、スタジオで録音して、マイルスが気に入ったサウンドを切り取って繋げたような編曲なのです。
スライも『There's a Riot Goin' On』('71)の頃は、スタジオに一人で籠って、ひたすら編集作業をしていたと言われています。
おそらく、このアルバムでも同じようなことがされたのではないでしょうか(マイルスの場合は、本人ではなく、スタッフが作業したかもしれないが、いずれにしてもマイルスの意向が強く反映されたはず)。
しかも、スライの『There's a Riot Goin' On』と比べても、このアルバムで見られるマイルスの音の切り方は、敢えて、メロディーを繋げずに、とにかく「リズム」を強調する作りです。
のちに聴いた『There's a Riot Goin' On』も、もちろん素晴らしいアルバムでした。
しかし、「ファンク」として捉えると、『On The Coner』には、一切の「甘さ」や「人懐っこさ」がなく、「過激さ」や「狂気」すら感じてしまうんですよね。
(続く)
いいなと思ったら応援しよう!

