
中絶するのは、子どものせいじゃない。
胎児に障がいがあるという理由での中絶を認めない国①
ポーランドの場合
ポーランドが胎児に障がいがあることを理由にする中絶を禁止とした。最高裁でその決定が下ったのが昨年10月22日。年が明け3ヶ月余を経て、ようやく施行される見通しとなった。公式発表があったのは1月28日だ。ここまで時間を要したのは、この最高裁の決定を不服とする反対デモがコロナ禍で猛然と繰り広げられたからである。騒乱が下火になるまで施行が見送られたかっこうだ。社会主義体制崩壊後の1993年に成立した法律によって中絶を厳しく制限するポーランドでは、レイプか近親相姦によって妊娠した場合、母体が生命の危険にさらされる場合、そして胎児に著しい異常が認められる場合のみ例外的に中絶を認めていた。その例外規定のひとつ、いわゆる「胎児条項」がこのたび除外されることになったのである。
「障がい者を差別しない」という決定に怒る人々
ポーランドで「合法的に」おこなわれる中絶は年間2000件程度というが、そのほとんどが胎児の異常を理由にしたものだ。「著しい異常」とされながら、ダウン症の子どもも中絶されていたようである。それが「胎児条項」が禁止となった今年以降は、ポーランドでは「合法中絶」はもはや極めてレアなものになるということを意味する。ポーランドから中絶がなくなった!と中絶に反対するプロライフ活動家たちは歓喜の声をあげるが、現実はまったくそんな単純な話ではないことは、反対デモの凄まじさからも窺い知れる。国民の大半が毎日曜ごとに教会に通うカトリックで温和な印象のポーランドの人たちがなんでここまで逆上するのか、日本人にはおよそ理解できないだろう。子どもに障がいがあることが中絶を認める理由にはならない、という決定である。当然そうであるべきではないのか。「胎児条項」は、明らかな障がい者差別である。困難な道のりではあるが、障がいのある子どもも「誰一人取り残さない」社会が目指されなければならない。そこに向かうためのポーランド最高裁の尊い決断が、なんでこれほどの抵抗に遭わなければならないのか。民衆の怒りが爆発する様に呆然とする。もし自分がダウン症の子を持つ親だったら目を覆いたくなる光景だ。怒りの矛先が障がいをもつ子どもに向かっているようで悲しくなる。

問題は、それが法の正義を保つために必要だったとしても、誰の益にもならない(「世間」の空気を読まない)決定だったことだ。コロナ禍で暴動まがいの反対デモが起きることを予期できていなかったとしたら国家権力が人心から乖離していると言わざるをえないが、それでもたとえ暴動が起きようと将来的にいのちが救われることになるのであればこの決定は優先されて然るべきだろう。しかし、障がいのある子どもの中絶を国が認めないことによって本当にダウン症の子どもが守られるようになるのかというと、答えは逆だ。今回の決定を受けて、「もし自分が宿した子が出生前診断でダウン症とわかったら絶対に海外に飛んで中絶してやる」と意地になった女性も少なくなかったのではないか。移動が自由なヨーロッパでは国境を越えれば選択の自由はいくらでもあるし、合法中絶を禁じれば違法中絶が増えるのは世の常だ。ポーランドで年間に中絶がおこなわれる数が公式発表で2000件だとしても、それはあくまでも国内における合法中絶の統計にすぎない。
国内で認められない(一般的な)中絶を考える女性は、隣国(ポーランド以外の欧州諸国はどこでも合法的に中絶が可能)に行って処置をするか、国内の違法中絶施設を利用する。そうして実際のところは、20万人ものポーランド女性が中絶をしているという。これは、人口がポーランドの4倍の日本の中絶件数をも上回ることになり、にわかには信じ難い数字だが、あの反対デモの広がりを見ればあり得ないことでもないと思われる。中絶を禁止する「国是」は、ほとんど何のバッファーにもなっていない。ザル法どころか悪法だと人々は憤るのだろう。女性たちを違法中絶に追い込む国家権力の無神経ぶりに腹を立てずにいられない。今回の決定によって合法中絶の件数はほぼゼロに近づくだろうが、その上辺の数字合わせに得々とする権力者たちの顔を思い浮べて人々はさらに逆上するのだろう。彼ら権力者たちは、この決定によって却って中絶実数が増えることになるだろうと予想される事態を何とも思わないのか。国は法を守るだけで、女性も子どもも守らない。デモに参加する人たちからそう非難されても反論できないほどポーランドの政治と人々との分裂は修復不能なものになっている。この国に未来はあるのだろうか。

社会に充満する教会アレルギー
人々が怒りの矛先を向ける権力者たちの中に教会も加えられていることは見逃せない。暴徒が教会の建物を攻撃したり、ミサに乱入する騒ぎが相次いだ。ポーランドは「政教分離」を原則とする国ではない。カトリック教会は政治に絶大な影響力をもつ。胎児の障がいが理由となる中絶を禁止する決定が下された10月22日は、ポーランドがうんだ聖人教皇ヨハネ・パウロ2世の記念日である。その日を期しての決定だったことは言うまでもないが、それをハッピーな知らせと受け止められなかった人々は、ヨハネ・パウロ2世を政治利用しようとする権力者と教会に対する反発をさらに増幅させることになっただろう。冷戦時代にポーランドの民主化をすすめた陰の功労者だったヨハネ・パウロ2世は、激しく中絶に反対する闘士だった。その事実を知らないポーランド人はいない。中絶が奨励されていた社会主義時代の名残りを一掃すべく中絶を原則禁止とする新しい法律が1993年に制定されたとき、バチカンに居たヨハネ・パウロ2世がどれほど大きなはたらきをしたかは推して知るべしである。ただし右派陣営からすると、93年の法律は不十分なものだった。胎児に異常がある場合だろうと、レイプによって妊娠した場合だろうと、母体の健康が危険にさらされる場合だろうと、カトリック教会の教える真理にしたがって、例外を認めることなくあらゆる中絶を禁止としなければならない。教会と結びついてそれを政治課題に掲げる確固たる勢力が、「胎児条項」を抹消した今も画策をつづけているのであり、デモに繰り出す人々のいちばんのストレスの原因となっているだろう。「胎児条項」だけでなく、レイプによって妊娠した場合も中絶は禁止とする決定が下ったと早合点してデモに参加したひともいたようだ。表面上はカトリック国のポーランドだが、水面下ではどれだけ人々の教会離れが起きているか想像を絶するものがある。いまやポーランド社会に教会アレルギーが充満している。教会が世の中を支配する中世さながらの構図に人々は辟易としているのだ。
権力に反発し立ち上がって声をあげた人々にじゅうぶん同情の余地はあると思うが、「胎児条項」を削除した今回のポーランドの決定には率直に賛辞をおくりたい。もしこんな暴動に至るほどの反発覚悟の決定だったなら、その勇気を称えたい。たとえ胎児の段階であろうと、障がいがあるという理由で差別されることが許されてはならない。それが「誰一人取り残さない」をモットーとするSDGsの掲げるグローバルスタンダードであるはずだ。各国で中絶が基本的に合法とされることに異論はないが、「胎児条項」は世界じゅうの中絶法から撤廃されなくてはならない。中絶は仕方がない。だが、子どもに問題があるからという理由は認めない。
胎児に障がいがあるという理由での中絶を認めない国②
日本の場合

日本はポーランドよりずっと早く、1996年に合法中絶から「胎児条項」を除外した国だ。子どもの異常を理由にした中絶ができなくなるという法改正に対して、とくにそのとき日本社会に何ら問題が生じることもなかったのである。もちろん日本は合法的に中絶が認められる国である。ポーランドと違って中絶を望む女性がわざわざ国外に出向いたり違法中絶の施設を探す必要はとくにない。以前のポーランドが原則的に中絶は認めないが胎児の異常を理由にした中絶は例外的に認めたのに対し、中絶は認めているのに胎児の異常を理由にした中絶は認めないのが現在の日本だ。法律のうえではそういう理屈になっている。
「優生保護法」から「母体保護法」へのコペルニクス的転回
戦後の世界で最初に合法中絶を導入し、1949年の法改正で中絶理由に「経済的理由」というマジカルワードを挿入し、1952年の法改正では事実上の中絶のオンデマンドを可能にした「優生保護法」の内実は、1996年に名称ごと「母体保護法」へと改正された後も基本的には変わらない。中絶を望むものは「胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期」であれば指定医によって合法的に処置がおこなわれるのは50年前も今も変わらない。ただし、法の建前上は「優生保護法」から「母体保護法」への移行はコペルニクス的転回と言うほどの大変革である。優生保護という建前は、劣性を切り捨てることの裏返しであって、そもそも「要らない子どもは産まれてこないようにする」ための法律である。軍国主義下の戦前から草案が練られていたものだが、不妊手術(当時の強制不妊の実態を検証した訴訟が昨今相次ぎ大きな社会問題となった)あるいは中絶手術という手段によって「優生上の見地から」産まれてこないことを認められる「不良な子孫」に当たる遺伝性疾患が条文に羅列されるがゆえに「優生保護法」なのである。その後に取って付けたように「母体の生命健康を保護することを目的とする」という名目のもと「経済的理由」の一言が接ぎ木されて一気に中絶の一般化がもたらされるのだが、それは法の位置づけとしては優生を保護するための法律におけるオマケにすぎなかったのだ。
しかしながら、優生保護という建前は人道上の見地から時代とともに非難に晒され、それに反発する障がい者団体の運動も活発になり、ついには条文から「優生上の見地」がすべて切り取られ、「取って付けた」後のほうだけが残るかたちで、歴史ある日本の中絶法は「母体保護法」へと変貌を遂げる。「産まれてこないほうがいい子ども」という規定、すなわち「胎児条項」が抹消されたのである。このたびのポーランド同様、「子どもがダウン症だとわかったので中絶します」という理由は日本では通用しないのである。もっともまあ、これもおかしな話で、日本で出生前診断でダウン症とされた子どもの90%以上が中絶されている実態は周知のとおりである。しかしこの場合の中絶も、子どものダウン症が理由になるのではない。親の「経済」が理由になるということだ。障がいがある子どもを受け入れるのは経済的に厳しいからという理由によってはじめて「合法的に」中絶手術が受けられる。所詮は建前にすぎないかもしれないが、しかし建前は重要である。法とは建前の砦である。
「経済的理由」が表向きはオマケだった「優生保護法」から、「経済的理由」がほぼ唯一の公式の中絶理由となる「母体保護法」に変わったのだ。子どもに問題があるから中絶した優生保護のための法律から、自分に問題があるから中絶する母体保護のための法律に変わったのである。中絶するのは、子どものせいではないのだ。「経済的理由」なんだから、ぜんぶ自分のせいだ。子どもに遺伝的疾患があるとかどうとか関係ない。どんな場合だろうと結果的に中絶するのは、子どものせいじゃなく、生活の多くを経済に負わなければならない自分のせいだ。子どもは何も悪くない。悪いのは自分だ。「経済的理由」という身勝手な名目にかこつけて、そう思うより他ないだろう? でも、それでいいんじゃないか、と多くの日本人は納得しているのかもしれない。「自分のせいで産んであげられなくて、ごめんね」と手を合わせるのが、中絶をめぐる日本人特有の「いのちの文化」ではないか。産んであげられなかった子どもに「ごめん」とおもう。それを水子供養という。お寺がビジネスにしているとして水子供養が槍玉に上げられることもある。だが、かたちはどうあれ、日本人なら「供養」を疎かにすることはできない。
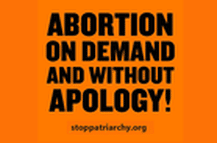
どんなに小さくて目に見えなかろうと、確かにこの世に存在したいのちを受け入れられなかったことに対する負い目。そんなものは持たなくていいと近代合理主義のエリートは鼻で笑うのかもしれないが、連中には供養するこころを育んできた日本人の感性をナメるなよと言い返してやろう。欧米の中絶推進主義者たちの掲げるありふれたスローガンの一つに「ABORTION ON DEMAND AND WITHOUT APOLOGY」というのがある。「中絶をオンデマンドで」については事実上日本がその先駆けなので何とも言い難いが、「詫びる必要なんかない」というのは違うだろう。それは供養する日本人のこころを否定することだ。オンデマンドですみやかに安全に中絶ができたとしても、負い目はある。ないわけがないだろう。当然のことをしただけと割り切ることなんてできないだろう。詫びたくなるだろう。日本人なんだから。供養することで中絶した過去を正当化したいのではない。身体を滅ぼしたとしても抹消しきれない「霊」との交わりが「ごめん」の一語に集約される。いつも、いつまでも「ごめん」とおもう。それは、今もどこかにその子の霊がいることへの期待と希望のあらわれでもある。意外にも、水子を供養する日本人の精神性をよく理解しているのが、日本人には縁遠いはずのキリスト教のリーダーだ。
中絶されたあなたの子どもは天国にいます。その子に名前をつけてあげて、あなたが歌ってあげられなかった子守唄を歌ってあげてください。
中絶を経験した女性たちのためにそんな心温まる「供養」の仕方を指南するのは、教皇フランシスコである。彼自身も天国に向かって子どもたちに子守唄を歌ってあげているのだという。中絶は社会全体の問題であると考えるなら、直接中絶を経験した者でなくても供養にあずかろうとするものだろう。道端で水子地蔵を見かければ手を合わせるだろう。水子のための慰霊は地域の祭りであり、共同体としての責務だろう。われわれの供養の本質的なところまでアルゼンチン出身の教皇様はご存知のようである(実に日本人的な感性の持ち主だと思っているのは自分だけではない気がする)。水子をめぐって宗教は垣根を越える。

中絶問題を解決に導く道理としての「経済的理由」
「経済的理由」ほぼ一択で中絶を認める日本の母体保護法は、国民の合意がもっとも得られた中絶法であると言えるだろう。世界に目を転じれば、容認するにせよ禁止するにせよ中絶について規定する法制度をめぐっては、各国でつねに紛糾する有様だ。ポーランドの騒ぎを見るまでもなく、国民の合意とは程遠いところで、政治の舞台で推進派と反対派のせめぎ合いがつづくのが中絶問題だ。だが、日本は別だ。中絶問題は政治的に無風である。現行の法制度に、「経済的理由」に、表立った不満はない。国民の大半に支持されていると見なしてよい。まだ他国が中絶は違法が当たり前だった1960年代頃までは、「経済的理由」で子殺しを認める酷い国だと日本は国際社会の非難を浴びた。一部の宗教団体などが「経済的理由」の削除を求め中絶違法を訴える運動が時折起こることもあったが、国民の関心事にはならなかった。たしかに戦後の混乱期における一時的な措置として場当たり的に導入された「経済的理由」だったが、それが図らずも、今の世にもフィットする「道理」だったのである。理由を子どものせいにしない、という道理である。子殺しに他ならない中絶に道理も何もないだろう、と言ってしまうのは身も蓋もない。頑に中絶は悪だ、人殺しだと断罪する思考は、真理かもしれないが道理ではない。中絶は不条理である。しないに越したことはないが、仕方のない場合もある。たいがいの日本人の中絶観はそういうものだろう。
できればしないに越したことはない仕方がないこと。なくしたいのはやまやまだ。しかし強制的になくそうとすることは(ポーランドのように)無理がある。誰かを責めても誰も救われない。大事なのは、「仕方のない場合」に寄り添える慈しみだ。そして、犠牲にした子どもに対する「ごめん」のおもいをみんなで共有することだ。それが中絶問題を解決に導く「道」である。日本はその道をすすんでいると思う。事実、中絶法を存置しながら、中絶率は減少の一途を辿っている。母体保護法は、名ばかりの悪法ではない。中絶が「仕方のない場合」の措置であることを明確にする一方で、子どもの人間としての尊厳を守ろうとしている。中絶を認めることと子どもの人間としての尊厳を守ることは矛盾しない。国連は「性と生殖に関する健康」という概念において中絶が女性の基本的人権であると主張するが、SDGsは「性と生殖に関する健康」の増進を目標に掲げながら、子どもの人間としての尊厳を置き去りにすることはないだろう。産まれる前の子どもも含めて。
子どものせいではなく、すべて自分が悪いと割り切るしかない「経済的理由」は、中絶を選んだ親だけでなく共同体全体に亡くした子どもに対する供養の念を促すものとなる。親が経済的に及ばなかったのであれば、それは社会の責任でもある。みんなで「ごめん」と手を合わせて、子守唄を歌ってあげよう。供養することで浮かばれる亡くなった子どもたちの霊が、未来の母と子のためにともに働いてくれると信じよう。日本がすすんできた道に間違いはない。これからも紆余曲折はあっても、いのちにとってよりよい道を行くだろう。中絶は、核兵器のようにこの世から廃絶できると願うことはできない。人間が人間である限り完全になくなることはない。法で縛っても救われない。しかし「滅多にないもの(rarelly happen)」にはできる。人々のあいだで「考えられないもの(unthinkable)」にすることはできる。現に日本はそうなりつつある。その道を世界に示そう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
