
共創で実現するデザインアプローチ〜Designship 2024 パネルディスカッションレポート〜
こんにちは!root採用広報担当です。
私たちrootは「Design Doing for More〜デザインの実践を個から組織・事業へ〜」をビジョンに、組織の右腕として、共に事業価値を創り、育むデザインパートナーです。
顧客価値とビジネス価値を踏まえ、本来あるべき「事業価値」を生み出せる組織と事業を増やすことを目指し、プロダクト開発やデザイン実践のノウハウを提供し共創しながら、事業の組成と自走できるデザイン組織の体制構築を支援しています。
rootは、先日の10月12日、13日の2日間にわたって開催された日本最大級のデザインカンファレンス「Designship 2024」に、昨年に続き2度目のPLATINUMスポンサーとして協賛しました。
今年は、スポンサー各社のブース出展に加え、2日間で80以上のトークセッションが行われ、「キーノートセッション」をはじめ、3つのデザインテーマから登壇者ならではの物語に迫る「公募セッション」、スポンサー企業各社による「スポンサーセッション」、そして「パネルディスカッション」がありました。
4回目の参加となる今回は、ブース出展に加えて、2つのスポンサーセッションとパネルディスカッションに登壇させていただきました。前回のスポンサーセッションのご紹介に続き、今回の記事では、CEO西村が登壇したパネルディスカッションの様子をお伝えしたいと思います。
前回のスポンサーセッションの記事はこちら
2024年のDesignship
今年の、Designshipは、“広がりすぎたデザインを、接続する。” がコンセプト。最前線のデザインを学び、第一線のデザイナーと語り合う、デザインの祭典であり、様々な業界から様々なデザインに携わる2,000名弱の方々が、東京ミッドタウンに集結しました。
当日のみならず、準備段階から社外も含め多くの方々と共創し、2日間のイベントを走り抜けることができました。会場でrootのブースにお越しいただいた方、登壇をご視聴いただいた方、お会いできたすべての皆さまと貴重な経験ができたことをとても嬉しく思います。
そして、Designshipを運営してくださったスタッフのみなさま、最後までサポートいただきありがとうございました。
それでは早速、パネルディスカッションの内容についてお伝えしたいと思います。
それぞれの実践から語る、デザインでの共創
rootは1日目の午後より、「共創で実現するデザインアプローチ」をテーマに、CEOの西村がパネルディスカッションに登壇しました。
ご一緒したのは、以下の御三方です。
株式会社NTTデータ Tangity Tokyo Head of Design 村岸 史隆さん
株式会社インパス 代表取締役・デザイナー 山下 一樹さん
モデレーターとして、株式会社HKSK CEO 赤木 謙太さん

本パネルディスカッションは、クライアントワークにおける「共創で実現するデザインアプローチ」において、ニーズを理解し、クライアントと”共に”つくっていくために必要な手法や事例について話し合うというもの。
各社の共創における「実践(課題と解決策)」「デザインの役割」「実現したいデザイン」という3つのテーマをもとに、登壇者がそれぞれの取り組みや考えを語り合いました。
まずは、それぞれの自己紹介の後にディスカッションに入っていきました。
1.共創の実践(課題と解決策)
一つ目のテーマは、共創の実践をしていく上で起きた課題と具体的な解決策についてです。
赤木さん(モデレーター):
ーーーよろしくお願いします。それでは早速、パネルディスカッションを進めさせていただければと思います。
一つ目のテーマは共創の実践における課題と解決策です。各社、実践していく上で起きた課題と、具体的にどんな方法で解決したのかのお話を伺えればと思います。
村岸さん、実際に共創をされている上で、課題感や解決策などがあればお伺いしてもよろしいですか?
村岸さん:
基本的にはお客様と共創、伴走するようなことをしていますが、インハウス的な形でソリューションやプロダクトを一緒に解決していくようなプロジェクトもあります。その場合、お客様のコミットメントが高いかどうかによって、課題の解決方法がかなり変わってくると実感しています。
ーーー具体的にコミットメントが高い場合や逆に低い場合、どのようにコミットメントを引き出す方法があったりしますか?
村岸さん:
言葉ざわりがいい言い方をすると、楽しく巻き込んだり、共創をするということなのですが、あまりそれでは動かないことが多いです。
自分たちが場を作ることが大事ですが、それでも動かないときは、組織としての支援や政治的な動きが必要で、依頼元や他の組織との連携がすごく重要なポイントだと思います。コミットメントは現場レベルでの連携が重要で、それをうまく進めるために楽しく巻き込める環境を作り、その上でプロセスとして進めていますね。
ーーーありがとうございます。
コミットメントの話が出ましたが、山下さんも、実際に今やられている中での課題感や解決策、特にエンジニアさんがいる組織として課題を解決されたエピソードがあれば教えていただけますか?
山下さん:
弊社では「設計が決まっているのでこのデザインを作ってください」という依頼はお請けしていません。「こういうことをしたいが一緒に考えてくれませんか?」という段階から一緒にサービスを作り上げる動きをとっています。エンジニアも早い段階で関わり、顧客とのコミュニケーションも密にします。
まず、決裁者がプロジェクトにいることを確認し、大事なことは事前にしっかり伝え、決裁者とワンチームとなり、常にコミュニケーションが取れる状態を作るようにしています。
ーーーなるほどですね。先ほど村岸さんのお話の中でも巻き込みについて上がっていましたが、村岸さんは決裁者の巻き込みについて、どのように進めていますか?
村岸さん:
決裁者の巻き込みはもちろん重要ですよね。最初に誰が決裁者で、どうコミュニケーションを取るかの計画を立てます。デザインプロセスではステークホルダーマップを作成し、必要な人を適切に巻き込み、プロジェクトを進行させています。
ーーーなるほど。西村さんは、共創の実践でどのような課題に直面され、それをどのように解決してきましたか?
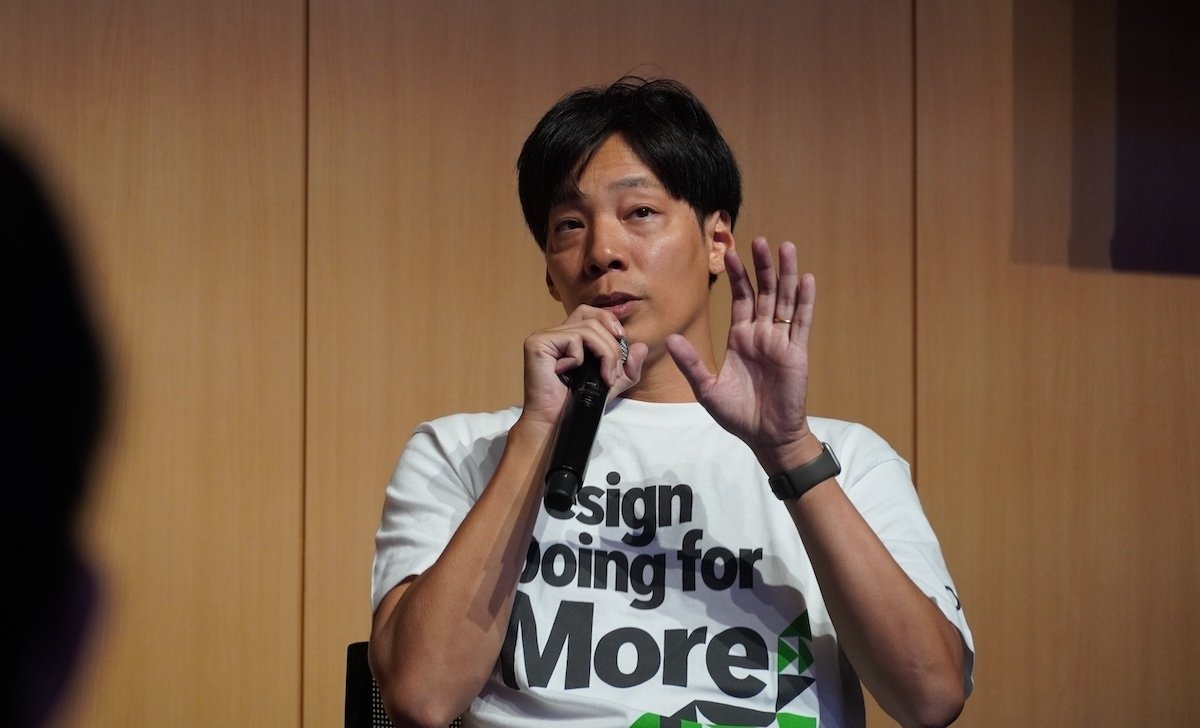
西村:
コミットメントの話ですね。rootの場合、中長期的なプロジェクトが多いので、顧客側が適切にコミットできない状況だと難しくなります。どこを推進したいのかや、事業部や組織をデザインによって変革する熱量があるかが重要です。
また、組織全体でデザインに対する期待感がばらついている場合もあります。その場合は、プロジェクトに推進力を持った人が一人でもいれば、その人をハブとして組織の中で推進力を高める支援ができると考えています。
ーーーなるほど。リーダーとなる人物が組織内でしっかり機能しているのが大事ですよね。やりやすいタイプの人や、逆に難しいタイプの人など、具体的に何か感じることはありますか?
西村:
大きな組織では、担当者がいる場合でも、新規事業に対する動機が弱いことがあります。会社から任されているだけでは、推進力が生まれにくいです。
担当者自身に事業を推進する必要性を感じさせ、しっかり接続しないと、事業に芯のない状態になってしまい、プロジェクトが進まなくなることが多いですね。
村岸さん:
とてもわかります。担当者に事業を接続していくことは本当に大切ですよね。
例えば、中期経営計画の段階で、担当者レベルが何をやっているのかが不明確になることがよくあります。そんな時、しっかり接続してサポートすることが重要です。「チェンジエージェント」を捕まえるか育てるかが大切で、その人を中心に組織を巻き込むことが大事だと思います。
ーーーなるほど。チェンジエージェントですね。山下さんは実際にそういう方と対峙されたことはありますか?
山下さん:
そうですね。今取り組んでいる新規プロジェクトを思い出しました。新規事業で何かを作らなければならないミッションがある中で進まないケースですね。これは、すでに他のコンサル会社が入っていた状況でした。
ーーー確かに、他の会社が関わっている場合もありますよね。そうした中で、例えば西村さんのケースではどのように動かれますか?
西村:
複数社が関わるプロジェクトでは、チェンジエージェントを見つけることが不可欠です。現場だけでなく、顧客側の目的や目標を理解して進めなければ、プロジェクトが本質的に動かなくなることがあります。
物事を大きく動かすためには、どう成功を作り出すかが重要で、小さなプロジェクトで成功体験を積み、それを広げていくことが必要だと考えています。
成功体験を生み出すためには推進力のあるリーダーがいるかどうかが重要であり、また、デザインに対する期待値を揃えることも大切です。純度がずれていると、組織全体の体験がうまく作れないことが起こります。
ーーー期待値を合わせるのは確かに大事ですね。村岸さんはプロジェクトを進める中で数社が関わる場合、どのように調整していますか?
村岸さん:
期待値調整は、プロジェクトが始まる前から非常に重要です。最初の成果が出た段階で、その成果が期待通りかどうかを確認するために、マイルストーンを設けて進めています。
フィンランドで共創プロジェクトに取り組んだ際、市民と一緒に図書館を作るプロセスで、楽しく巻き込むだけではなく、行政とデザイナーがしっかり介入し、アウトプットを高めていくことが重要だと感じました。
ーーーなるほど。プロセスを重視した取り組みですね。ありがとうございます。次のテーマに近いものがあるので、次に進みたいなと思います。

2.共創におけるデザインの役割
二つ目のテーマは、共創におけるデザインの役割として、実際に共創を行っていくにあたり、どのような役割が求められているのかについてです。
ーーー続いては「共創におけるデザインの役割」です。共創を進める中で、デザインがチームやプロジェクトに与える影響について、どのような役割が求められているとお考えですか?
まず、西村さんからお話を伺ってもよろしいでしょうか?
西村:
はい。事業のフェーズによってデザインに求められることは変化してくと考えていて、新規事業の立ち上げにおいて、デザインはアイデアを現実の形にする役割を果たし、ハブのような存在になります。
スタートアップのように限られた資源の中でMVPを作る際には、デザイナーが右腕となることが必要です。そこから、組織がクローズに向かう場合には、デザイナーがストーリーを作り、全体をまとめる役割を担います。
ーーーフェーズごとにデザインの役割が変わるということですが、それに伴ってチームのメンバーやファシリテーションも変わるのでしょうか?
西村:
はい、フェーズによってメンバーや進め方を変更します。立ち上げのフェーズでは、あえて属人化し、知識を一人に集約させ、スピードを維持することが大切です。これによって事業の立ち上がり確率を引き上げられます。
また、プロジェクトが進む中で、振り返りや学習サイクルを回すことも重要です。このサイクルが回らないチームは筋の良い検証を積み上げられず、動きが鈍くなり、失敗しやすくなると考えています。
ーーーなるほど。振り返りと学習のサイクルが大事ということですね。山下さん、共創におけるデザインの役割について気をつけていることはありますか?
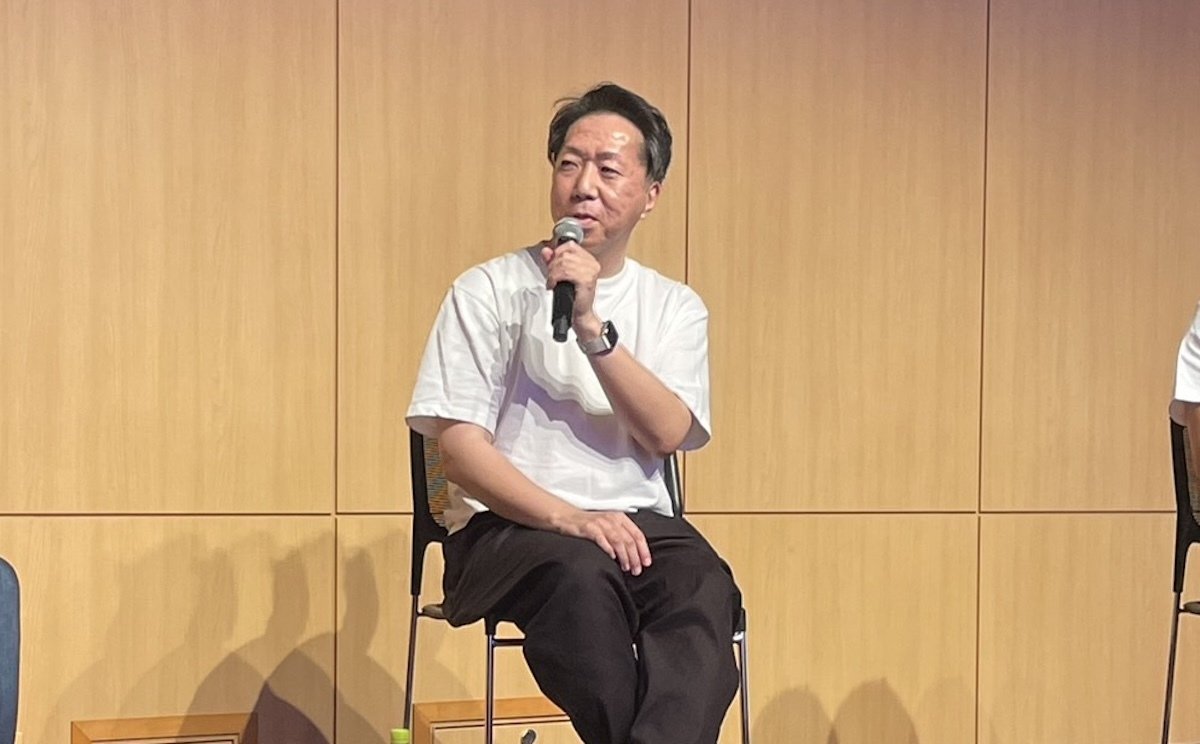
山下さん:
まず「目線の高さを合わせる」ことが大切です。例えば、クライアントからの依頼が「このアプリを改善してください」という形で来ることがありますが、本当に解決すべき問題はもっと上位のレイヤーにあることが多いです。
そのため、課題設定を見直し、率直に話し合うことが必要です。また、デザインだけでなく、リソースの調整や人間関係性の構築が重要な部分を占めることもあります。
ーーーありがとうございます。村岸さん、共創におけるデザインの役割について、具体的な例や取り組みを教えていただけますか?
村岸さん:
私たちの会社は組織の範囲が広いので、どの分野の専門家を巻き込むかが非常に重要です。顧客はやりたいことがあっても、それをどう実現するかは分からないことが多いので、技術やアライアンスをどう活用するか、デザイナーが適切に判断し、リソースを結びつける役割が求められますね。
ーーー確かに、デザイナーはプロジェクトの問題点を見つけ、どう解決していくかを主体的に動く必要がありますね。これはデザイナー特有の重要な役割だと思います。
3.共創によって実現したいデザイン
三つ目のテーマは、共創によって実現したいことについてです。技術の進化などにより、デザイナーを取り巻く環境は大きく変化することが考えられる中、関わり方や実現したい未来についてお話ししました。
ーーー最後のテーマにいきたいと思います。テーマは「共創によって実現したいこと」です。山下さんからお話を伺ってもよろしいですか?
山下さん:
共創はデザインサイド中心に考えたり作ったりしがちなのですが、まずはお客様の事業と人の成長がなければ意味がないと考えています。
最近は若い方へのスーパーバイズ、例えば稟議の通し方や人の調整の仕方について教えることが多いですね。キャリアとしてプロジェクトを回す経験は豊富ですが、コンサルティングにならないよう、コーチングとしてお客様をサポートしています。結果として、これは非常にやりがいがあると思っています。
ーーー全員で成長していくためのサポートが必要ですね。ありがとうございます。では、西村さん、共創によって実現したいデザインについてお聞かせください。
西村:
はい。2つあると思ってます。まず、クライアントは自分でできないことを支援してもらうために私たちを頼りますが、短期的な支援だけでは持続性が生まれません。ですので、共創の中で中長期的なパートナーシップにより、内製で持続性を作ることが大切だと思っています。
もう1つは、AIをはじめテクノロジーの進化を活かしたデザインです。この十年で「実現できないかも」と言われていたことが次々と実現してきました。デザインの力が問われる時代になってきたと感じていて、デザインの可能性や力を広げられると思うとワクワクするし、多くのプロジェクトに共創したいと思っています。
ーーーなるほど。デザインの可能性をさらに広げていきたいということですね。村岸さん、共創によって実現したいデザインについてお話いただけますか?
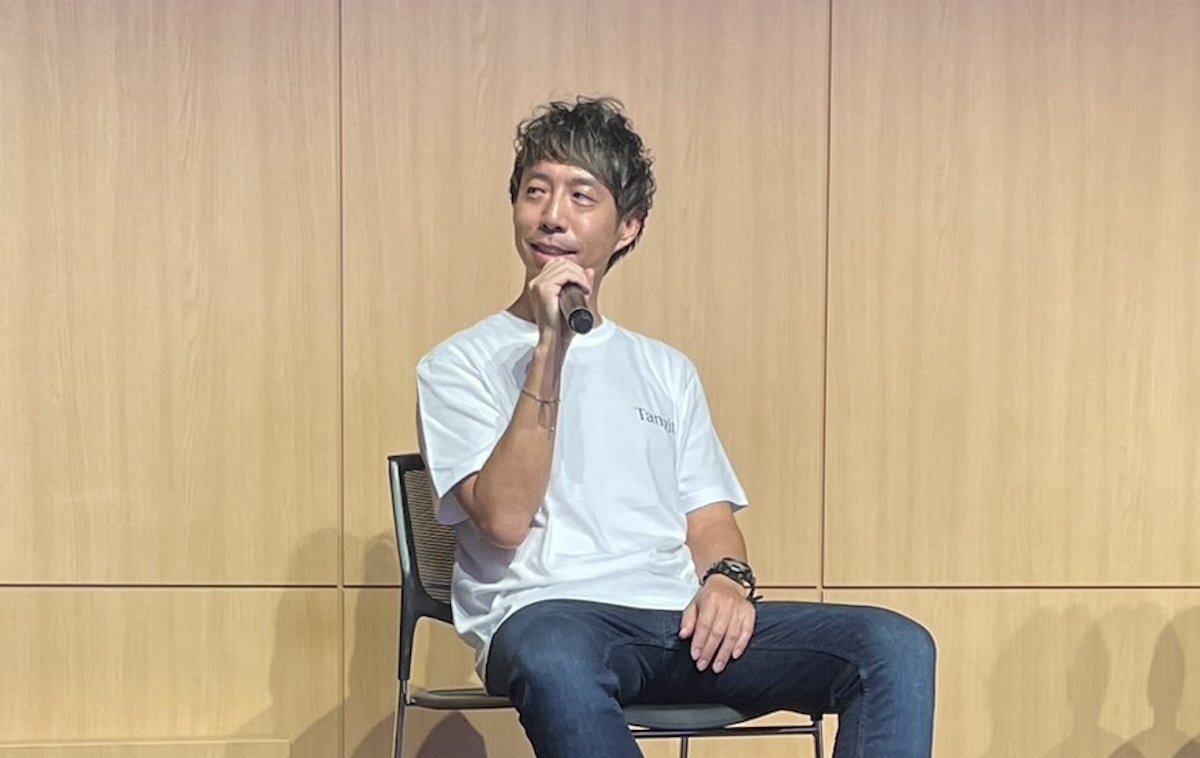
村岸さん:
技術やテクノロジーが急速に進化していますが、それに人間の理解や体験が追いついていないことが課題であり、このギャップを埋めるのがデザイナーの役割だと思っています。
また、ユーザーや顧客と共にプロセスを作り上げることも重要です。フィンエアーの事例では、カスタマーから直接フィードバックを得るための仕組みを作り、それを基にデザインを進化させていくことができました。
デザイナーがユーザーと共にニーズを拾い上げ、テクノロジーを使ってそれを実現することが、今後も重要なテーマだと思っています。
ーーーありがとうございます。まだまだお話を伺いたいところですが、時間の関係で本日のセッションはここまでとさせていただきます。最後に一言ずつ感想をお願いします。まずは西村さんから。
西村:
クライアントワークを通じ、未来を一緒に作っていくという立場で考えることで、組織の右腕として、共に事業価値を創り、育むデザインパートナーとしてあり続けたいと考えています。
よりパーソナライズされた世界では、デザインは社会に影響を与える大きな力として、求められることも多くなっていくので、デザインの力を世の中に広げ、社会に影響を与えていければと思います。
山下さん:
共創というテーマでディスカッションできて良かったです。これまでのクライアントワークの枠組みが変わりつつあり、依頼に応えるだけでなく、クライアントの立場を自分ごととして捉え、新しいやり方を模索することが求められていると感じています。
村岸さん:
共創はグローバルでのダイバーシティが大切だと思っています。
私たちは、さまざまな知見をグローバルに発信しながら、国際的なネットワークを活かし、チームとして共に成長することに挑戦していきたいですし、それがチームとしての向上につながると信じています。
ーーーありがとうございます。ご自身のエピソードを踏まえたお話、とても興味深く聞かせていただきました。改めまして、本日は皆様ご登壇いただき誠にありがとうございました。このセッションは以上となります。ご聴講いただいた皆様もありがとうございました。
10月31日に虎ノ門オフィスでイベントを開催!
「Designship 2024」はオフライン・オンラインで開催され、大盛況のうちに幕を閉じ、rootのセッションも多くの方にご視聴いただきました。ありがとうございました!
多様な事業フェーズにおける事業課題をテーマに、今回の「Designship 2024」で語りきることのできなかった、各事業フェーズにおけるrootのデザイン支援の具体的な取り組みを紹介するイベントを開催します。
ビジネス価値だけでなく、顧客価値を含めた本来あるべき事業価値を社会に届けるために、組織にデザインが浸透している状態を目指すrootのDPM支援モデルの実態や、今ある役割に縛られず、当事者として事業価値づくりを牽引する、事業フェーズごとのDPMの挑戦についてCEO西村とDPMの岸と佐藤がお話しさせていただきます。
<イベントの詳細>
タイトル 組織の右腕として事業価値を共創するデザイナーの挑戦
日時 10月31日(木)19:00〜21:00
場所 Quest虎ノ門(本社オフィス)
ご興味のある方は、ぜひ上記よりお申し込みくださいませ。ご参加お待ちしています!
※定員30名の抽選制です。
rootでは共にビジョン実現できる仲間を探しています!
私たちは、「Design Doing for More〜デザインの実践を個から組織・事業へ〜」をビジョンに、組織の右腕として、共に事業価値を創り、育むデザインパートナーです。
クライアントワークを通じて支援する組織・事業に対して共に事業価値を創り、育むための支援体系を構築しています。事業の立ち上がりや成長段階に関わることの多いrootだからこそ、事業の形がまだ定まっていないフェーズから、本来あるべき事業価値の創造を共に行い、組織と事業の成長を支援できます。
組織の右腕として、相手視点と高い当事者意識をもち、プロアクティブに変化を起こし続け、新しい価値を生み出すGiverでありたいと思われる方!
デザインパートナーとして、「事業価値の創造」に挑戦してみませんか?
共に、Design Doing for More〜デザインの実践を個から組織・事業へ〜を実現していきましょう!
ぜひ、ご興味ある方は一度カジュアルにお話しできたら嬉しいです。ご連絡お待ちしています。
👇カジュアル面談はこちら
CEO西村のカジュアル面談をご希望の方はこちらよりエントリーください。
👇rootの採用情報はこちら
Vision・Mission・Valueやカルチャー、はたらいているメンバーの紹介など、充実したコンテンツで採用情報をお届けしますので、ぜひご覧くださいませ!
👇rootの COMPANY DECK はこちら
rootをより詳しく知ってもらうため、事業内容や実績のご紹介、rootの組織やメンバーについての情報をまとめています。ぜひ、こちらもご覧くださいませ!
👇 rootの発信コンテンツ一覧はこちら
rootをより詳しく知ってもらうための発信コンテンツをカテゴリー毎にまとめたページを作成しました。
チェックいただきたいコンテンツや最新情報を集めていますので、こちらもぜひご覧くださいませ!
👇root公式Xはこちら
プロダクトデザインや組織づくり、事業成長に関する知見やイベントをはじめとしたお知らせを発信しています。
ぜひフォローをお願いします!
https://twitter.com/ic_root
