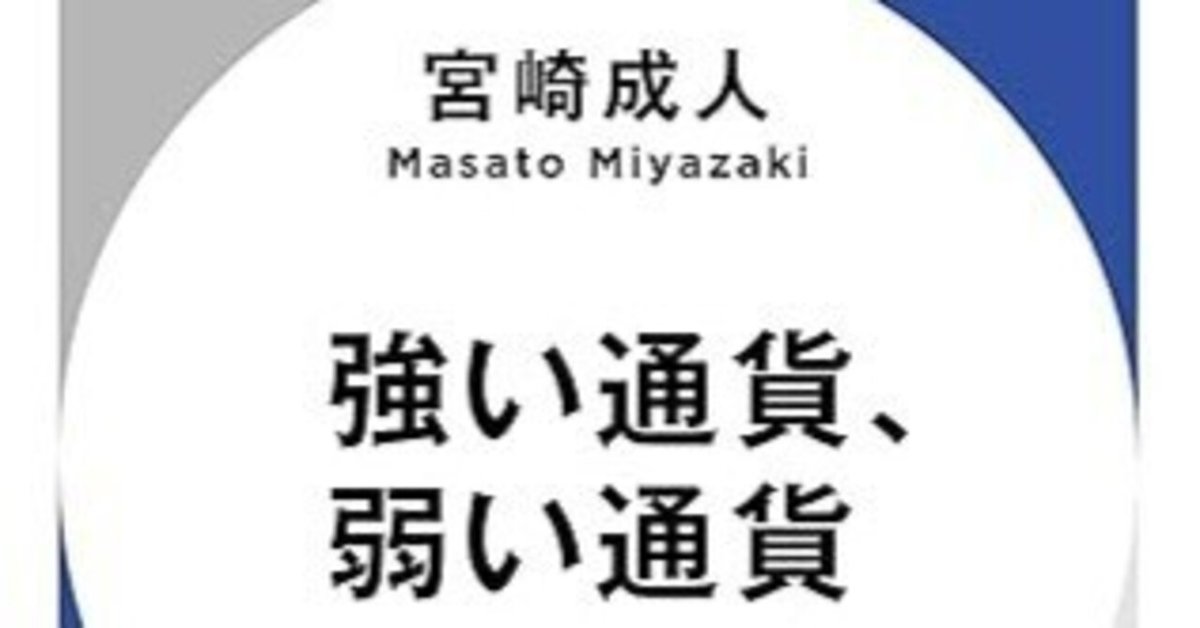
『強い通貨、弱い通貨』宮崎成人
『強い通貨、弱い通貨』宮崎成人、ハヤカワ新書
アメリカ主導のドルの基軸通貨体制がどう構築され、維持されてきたかを、独立直後のアナーキーな通貨システムから説明してくれます。日本の維新政府が藩札の整理をした上で通貨システムを構築するにあたり、米国の各州が勝手に発行していた通貨を統一する過程を参考にしたということも、実感として理解できました。
「おわりに」で《筆者は1971年のニクソン・ショックで新聞やテレビが大騒ぎしているのを眺め、「何が問題なんだろう?」と理解できなかったことを覚えています。その後大蔵省・財務省、BIS、IMFなどでの職歴を含め、ほぼ40年間にわたり通貨問題や金融危機に向き合って、少しは問題の理解が進んだかな、と願っています》(k.3062、kはkindle番号)と書いていますが、ニクソン・ショックが金というアンカーから通貨が解き放たれたことが、いかに凄いことだったか、ということが改めてよくわかります。
[アナーキーな初期の米国の通貨制度]
米国の通貨は、こんな風に始まります。
《植民地内で流通する貨幣(コイン)は数が圧倒的に不足していたため、日常の取引は物々交換か、あるいは特定の商品(小麦、タバコ、ビーバーの毛皮等)を通貨のように用いて行われていました。また、現地に先住していた人々(ネイティブ・アメリカン)が用いていた、貝殻を数珠つなぎにしたもの(ワンプン)を、入植者間でも貨幣代用品として活用していました(図1‐2)。当然不便ですし、商品価値が上下すれば通貨の価値も不安定となったでしょう(k.413)》。
《1775年の大陸会議(コンチネンタル・コングレス Continental Congress:13植民地の代表者が集まる事実上の最高意思決定機関)で、金銀や商品の裏付けのない証券の発行を決定します。第二次世界大戦中に日本軍が占領地域で発行した軍票のようなものですが、最初のドル紙幣と呼んでよいでしょう(k.453)》
1783年に合衆国の独立が正式に認められると《ドルの価値は当時流通していたスペイン・ドル硬貨と同一と定めます。そのため市場のスペイン・ドル硬貨を無作為抽出して平均を取り、1ドルは銀371グレイン(約24グラム)と決定します。また、当時の金と銀の交換比率(1:15)から、1ドルは金24グレイン(約1・6グラム)とも定められました。つまり、金と銀の双方によってドルの価値を定める「複本位制」を採用したわけです》(k.484)。
そしてリパブリカンが各州で州法に基づき民間銀行(州法銀行)が設立できるようにしたのですが、当然、不安定。《商店主などが受け取った紙幣を急いで発行元の銀行に持ち込んだことは想像に難くありません。一方銀行の側では、なるべく銀行券の償還に応じないために、わざわざ人里離れた山の中に本店を置くなどしてあえて不便にした》(k.517)というほぼ詐欺的な状況でした。
この結果《1811年の紙幣発行残高は、第一合衆国銀行と州法銀行を合わせても2810万ドルだったのが、1816年には州法銀行だけで6800万ドルも発行していました。州法銀行が次々と設立され、偽造紙幣や更には全く存在しない銀行の銀行券まで流通しますので、何が何だか分からない、という状態》(k.545)になります。さらに《1860年時点で、州法銀行券は2億700万ドル流通していましたが、銀行数は1572行で、銀行券の種類は7000種に上り、そのうち4000種が偽造ないし変造だった》(k.575)というアナーキーさ。
その後《信用力のある公認の紙幣を導入できたので、連邦は州法銀行券の排除に乗り出します。1864年の法律で、州法銀行券への税率を10%に引き上げた結果、州法銀行券の残高は1867年に400万ドルまで減少し、ようやく州法銀行券問題が事実上解消するに至りました》(k.594)というあたりは、日本の維新政府が参考にしたハズです。
[金本位制からブレトンウッズ体制]
第一次世界大戦後、疲弊した英国の経済を見た海外投資家は、ポンド資金を金に交換してイギリスから引き揚げました。金の流出に直面したイングランド銀行は、1931年9月21日に金本位制を停止します。一方、アメリカは1900年頃、世界最大の経済国となり、第二次世界大戦前夜には金の保有量は約8000トンと4倍に増加。大戦後には2万トンを超える量まで激増させますが、金本位制はとりませんでした。ブレトン・ウッズ体制は各国通貨を直接金と結びつけるのではなく、ドルを通じて間接的に金と結びつける=各国は自ら金を保有するのではなく、金と結びついたドルを外貨準備として保有するようにしました。
同時に《アメリカの考えに沿って作られたIMFの枠組みでは、経常赤字国は、外貨準備が不足する場合、一時的に外貨(ドル)をIMFから借り入れて経常赤字を埋め合わせ、同時に輸入縮小・輸出振興のための経済政策を採って、経常収支黒字化を目指すことが求められました。一方の黒字国(アメリカ)は、IMFが他国に貸し出したドルに対する利子を受け取ります》(k.1154)。
《アメリカは、貿易収支こそまだ小幅の黒字でしたが、多額の民間及び政府資金が国外に流出しており、国際収支は赤字でした。しかし、他国と違って唯一アメリカだけは、外貨獲得の努力をする必要がありません。引締め政策を採ることなく自国通貨(ドル)を刷り増すことで国際収支の赤字を穴埋めできるからです》(k.1251)
[ブレトン・ウッズ体制の崩壊]
1971年のニクソン・ショックでドルと金とのリンクが断ち切られブレトン・ウッズ体制は創設後25年強で崩壊します。戦後の混乱から回復した主要国通貨が交換可能性回復してブレトン・ウッズ体制が想定通りの機能を果たすようになってからではたった15年も持ちませんでした。これは泥沼化したベトナムで出費がかさみ、金との交換ができなくなったためですが、崩壊したとはいっても、ブレトン・ウッズ体制は金本位制よりも優れていました。金本位制下では、為替レートに下落圧力がかかると国内の景気を無視して金利が引き上げられて恐慌が起こりました。しかし第二次大戦後は、国民生活の向上や完全雇用の実現が民主主義国家の優先事項となったりして、金融政策は国内に目を向けたのになったわけです。
ブレトン・ウッズ体制崩壊直後、当コナリー財務長官は国際会議で「ドルは我々の通貨だが、お前たちの問題だ」とドルが不安定だと困るのはアメリカ以外の国だと言い放ったそうです(k.1427)。アメリカが経常収支赤字の削減に進んだら世界同時不況に陥ると困るだろう、と。
《ブレトン・ウッズ体制後の国際通貨秩序が極めて柔軟なもの(変動相場制)だったからです。ポンドは、硬直的な「現場」(金本位制)に斃れましたが、ドルは「現場」を柔軟にすることで生き延びたのです》(k.373)。
そして《アメリカが規律にとらわれない政策を行い、黒字国にも内需拡大を求めたことが、種々の歪みやバブル(及びその崩壊)を伴いながらも現在の空前の豊かさを生み出す源泉となったという意味で、これはドル秩序の特徴》(k.1567)だと。
[ユーロ、円、元は基軸通貨にはなれない]
英語で「一世代(onegeneration)」と言うと概ね25年のことを示すそうで、次の25年となる2050年までを想定しても筆者はユーロ、円、元は基軸通貨にはなれないことを説明していきますが、興味のある方はご自身でまとめてください。
[目次]
序章 鷲は舞い降りた 国際通貨覇権の淵源
第1章 幼年期の終り ドルの誕生
第2章 死にゆく者への祈り 最初の基軸通貨英ポンドの凋落
第3章 黄金三角 短命に終わった基軸通貨としてのドル
第4章 ゴッドファーザー 生き延びたドル秩序
第5章 大いなる幻影 ユーロの挑戦
第6章 ¥の悲劇 地盤沈下する円
第7章 レッド・ドラゴン 人民元の興隆
第8章 電気羊の夢 デジタル・カレンシーの登場
第9章 アクロイド殺し ドルを殺す者は誰か?
第10章 そして誰もいなくなった? 国際通貨覇権の行方
おわりに 世界はどこへ向かうのか
