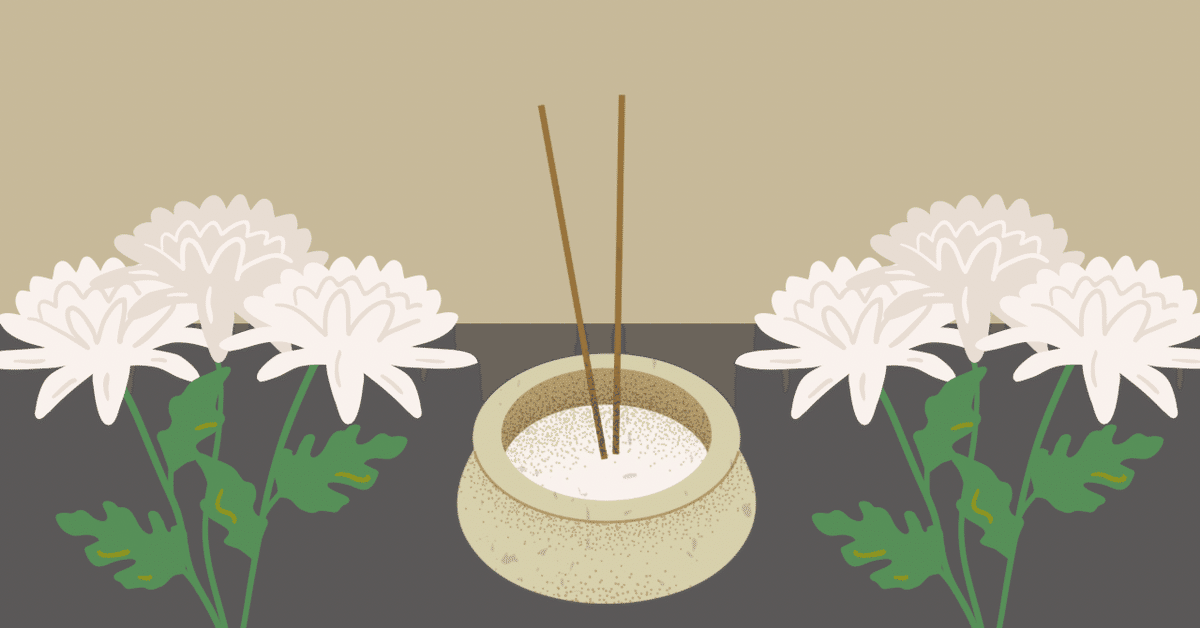
おじいちゃんが死んだ。涙は一滴も出なかった。
9月18日、敬老の日。昼まで寝る予定だったのにお父さんに叩き起こされた。入院しているおじいちゃんの体調が悪くなったらしい。
おじいちゃんは肺炎で入院したが、快方に向かっていると聞いていたので驚いた。でも、あらかた悟った。
朝食にヨーグルトだけ食べ、急いで病院に向かった。と、言っても遠い病院なので車で40分かかった。車内ではヘッドフォンを付けて音楽を聴いていた。焦りはなかった。
病院の駐車場で、先に着いた親戚に、どこにおじいちゃんがいるのか電話で尋ねた。その声は泣いていた。
迎えに来てくれたその人に連れられ、集中治療室の近くにある入院部屋まで連れられた。
そこに集まった親族は皆、泣いていた。
心電図のモニターは横一直線になっていた。でも、おじいちゃんはまだ暖かかった。
僕の家族は全員泣いた。僕だけは、涙が一滴も出なかった。病院のベッドで横たわるおじいちゃんの遺体を見た最初の感想は「こんなにちゃんとおじいちゃんの顔を見るの初めてだな」だった。おばあちゃんに「顔をよく見てあげて」と言われた。「普段は生えてないのに髭が生えてるなぁ」としか思えなかった。
その後、医者が来て、11時に死亡が確認された。
僕らは面会室で待機した。1時間はいただろう。正直暇で、スマホをいじりたかったが、周りが悲しみに暮れていてとてもそんなことができる空気ではなかった。
待ち時間の間、僕はその日にあった鬱フェスのライブ配信に間に合うかだけを心配していた。
そのまま葬儀屋が来て、遺体を運び、子供は一旦暇になったので家に帰れた。鬱フェスに間に合った。
注釈:鬱フェスはアーバンギャルド主催の心の闇を歌うアーティストを集めるフェスのこと。
勘違いされそうだが、僕はおじいちゃんを嫌っていないし、おじいちゃんんも孫思いのすごい良い人だった。近所からの信頼も厚い。
それでも涙は出なかった。次の日、登校中のスクールバスの中で自分の恩知らずさに絶望した。
思えば、去年ひいばあちゃんが亡くなった時も涙は出なかった。
いろいろあって家族を信用できなくなった時、味方してくれたのはひいばあちゃんで、絶対に死んで欲しくないと思った。でも死んだ。
僕は17年間僕という生き物と過ごしてきたが、まだまだ理解できていない。犬なら理解したうえで亡くなるぐらいの年数が経っているのにだ。
僕はあまりマイナスな感情を表に出さないようにしている気がする。
それは小学生の頃、短気で泣きながら怒るのをバカにされ、いじめられていたトラウマのせいだと思う。そこから自分の悲しみすら認識できないほど壊れてしまったのか。
人間には意識の領域と無意識の領域がある。僕の悲しみは、すべて無意識の領域に押し込められているのだろう。自分の悲しみはあまり外に出さないし、人と相談することもなかった。そうすると、心のキャパを超えてくる。だから僕は高校生になって鬱になったのだろう。無意識の容器が壊れて全部外に出てきてしまった。
だから僕は、涙以外のもので外に出す必要がある。それが僕が創作を好きになった理由だろう。塩水の涙は流せなくても、言葉の涙は流せる。
こうやって文章にすることで、僕という生き物の図鑑に少しずつ加筆できる。
僕の心が晴れることは恐らく死ぬまでない。トラウマが強すぎる。そのせいで同年代の男性とは未だに上手く話せない。だから一生創作していくし、創作で食っていけるようにする。両親は否定的だが。
追記
これは正直書くか迷った。あまりに人として思ってはダメなことだ。でも、書くしか方法がない。
言いたいことは2つある。
まず一つ目。「そこまで死を恐れていない。」
死んだら一生のお別れなんていうが、日本でメジャーな宗教では大体が、天国やら浄土やらの存在を認めていて、そこには死者がいるらしい。じゃあ一生のお別れじゃないじゃないか。時間はかかるが、そのうち会える。そう思っている。
あと生き物が死ぬのは当たり前だ。言い方があってるかはわからないが、生き物全員に通じるあるあるなんだ。「命はやがて、必ず死ぬのなんでだろ~」って感じだ。
2つ目。こちらの方が口にしたら嫌われそうだが、キーボードにしているからいいだろう。
「おじいちゃんは大切だが、人生の支えになるほどの存在かと言われたら、NOだ。」ということだ。
友達だったり家族だったり、大切な人は山ほどいる。でもその中で僕が生きる糧になっている存在はごくごく一部だ。おそらく家族にはいない気がする。
おじいちゃんには申し訳ないが、アーバンギャルドや新しい学校のリーダーズのメンバーの訃報を聞いたらすぐ泣くと思う。
これをおじいちゃんが見ていたらどう思うだろう。そう思うとキーを打つ手が重くなる。でも、これが本音なんだ。書くと決めたからには書かなきゃいけないんだ。
全編通して、おじいちゃんや家族に申し訳ない、絶対に読ませたくない文章になってしまった。でもこれが僕なんだ。自分でも理解しきれていないが、僕が考察して出てきた僕の人間性はこれだったんだ。
もし読んでた時のために、本当にごめんなさい。
