
作ったもの:Blenderで流体や破壊シミュレーション
MagicaVoxelやったあと今度はBlenderで流体シミュレーションやりたくなりました。ちっ、違いますっ!飽きっぽいのでなく変化に前向きなんですっ!
りゅーたいしみゅれーしょん?
なんかですね、動くものがやってみたくなりました。Blenderなら物理演算して液体の動きをシミュレーションできたりするみたいだったので。
なんとなく液体シミュレーションやってみたくなって #blender
— hubgry (@hubgry) March 15, 2021
クイック液体みたいなのでお手軽にできるっぽかったけど、見えないから色付けたりいろいろ慣れないと大変。
液体はドメイン内でのみ演算が行われ、フローが液体そのもの。障害物はエフェクト。日本語にしたからわかりにくくなってる感ある pic.twitter.com/0qRQqlT2ui
Blenderは言わずもがなな超有名フリーCG環境、って言うのかな。
Unityで遊んでた時にVR用に球体を作ってエクスポートしたりするくらいしか使ったことはありませんでした。
作ったものたち
ドメインという枠の中でのみ流体の演算が行われるので、コリジョンと言う衝突判定する物体を用意して、流入口って液体の入り口を作って、って言うのがスタートライン。
クイック流体っていうそれを簡単に用意できるセットがあるので、最初はそれが楽ちん。
目指したものは牛乳
— hubgry (@hubgry) March 16, 2021
ドメイン領域内だけに溜まっていく。設定わかってないからまだ荒い溶けた石膏みたいな感じ。厚みを出したけどコップは水漏れ、スカルプトモードとかいうので切り口が斜め、流体シミュレーションってムズカシイ #blender pic.twitter.com/zHjBPoKVK6
世界に光があっても光を反射する物体が無いと何も見えないって言うなぜか哲学的なことを学んでいくBlender。
ガラスのコップとミルク、のつもり
— hubgry (@hubgry) March 17, 2021
透過や反射は光だけでなく世界が無いと反射できないみたいでHDR画像が必要だった。コップはスムーズシェード(だったかな?)かけて、レンダリングの数字は64に増やしてみた。フローの流入口も少し斜めに。円ではだめで円筒使った #blender pic.twitter.com/Ur7JEewGtq
MagicaVoxelとの違いは一瞬では終わらないレンダリング。
Now baking...
— hubgry (@hubgry) March 18, 2021
Now baking...
Now baking...
#blender
動画にするならフレーム数はいくつで、何フレーム目から何フレーム目までをレンダリングするのか、あたりも設定しないといけない。
カップとお水
— hubgry (@hubgry) March 18, 2021
クイック液体はHDRを環境テクスチャで貼り付けるとデフォルト水だった。ドメインの分割の解像度は32スタートだけど、64くらいだと水が漏れるので、リアルにするなら128くらい欲しいかも #blender pic.twitter.com/WYvHxoG1DL
レンダリング中に強制終了することもあるくらいマシンパワー使うよね。万が一でもデータの復元方法があって助かった。
ついにやってしまった保存せずに強制終了。
— hubgry (@hubgry) March 19, 2021
でも自動保存から復帰できた。よかったよかった #blender
保存せずに強制終了したデータを復元する方法・データの復旧【Blender】 – 忘却まとめ https://t.co/EzbobBEApt
いくつかクイック流体を使って、色々作ってみてるところ。
あれ?クイック液体?クイック流体??
だんだん慣れてきたかもクイック液体。MagicaVoxelのobjをexportして読み込むとテクスチャ?色?一緒に読み込んでくれるからめっちゃ楽だった。 #blender pic.twitter.com/5WQ2vswqhA
— hubgry (@hubgry) March 19, 2021
簡易レンダリングでも良いからこの画面で見てるのが楽しい。MagicaVoxelもそうだったけど、作ってる最中が楽しいのって結構あるよね。旅行の下調べが楽しいとかって話でも似てる感じかな?
右上のプラスマークでドラッグする画面分割が最近のお気に入り。片方がカメラ目線のレンダリング、片方がワイヤーだったかな?立体的に楽しみながら、ハリボテ感がでないよーに工夫する感じ #blender pic.twitter.com/cqmaxCgwwU
— hubgry (@hubgry) March 19, 2021
Blenderでも英語のYouTube見ながらやり方を調べつつ。日本ではゲーム実況は多いんだけど、こういうソフトの解説とかやっぱり大変だから、そこまで多くはないよね。バージョンアップも多くって最新じゃないものの方が多かったし。
ガラスのコップと牛乳
— hubgry (@hubgry) March 20, 2021
IOR屈折率はガラスは1.5くらい、伝播1、アルファ0.5、設定でアルファブレンド
Eeveeだからか、ちょっとプラスチックっぽいコップになってるけど、やっと中が透けて見えるようになった♪ #blender
参考https://t.co/rz9rHTqnDt pic.twitter.com/0NONOmqjs6
Unityにもあったパーティクル。物理演算としては使うの初めてぱーてぃくる。
パーティクルが楽しいんだけど、コップに溜められないし、レンダリングするとなんか不安定。
— hubgry (@hubgry) March 21, 2021
パーティクル同士の衝突の計算もできてないみたいだけど、調べたらフォースフィールドとか出てきて鬼門な気がしたのでそっと離れた。 #blender pic.twitter.com/1FOij7pLFe
Unityの時も何か降って来るVR作ったのが楽しかったので
あ
— hubgry (@hubgry) March 21, 2021
やべ
綺麗になるかと思ったけど
目が
痛く
なっちゃう
これ
-
-
-#blender pic.twitter.com/WA0oSiDdfw
何事にも粘り強さは大切です。
流体から粘度をONにしてスライム。粘度を上げると液体以上にリアルさが難しそう。キーフレームの練習でフローの流入口も移動させてみた、、、って見えてるな。あと、分割の解像度の大きさが流入口より小さいとたぶん流れ出ない #blender pic.twitter.com/3nHyHcFl8e
— hubgry (@hubgry) March 22, 2021
よーやくネタっぽいのが作れた。
「喉かわいたー。なんかある?」
— hubgry (@hubgry) March 23, 2021
「溶岩でいーい?ほい冷めないうちにどーぞ」#blender
今日の先生動画https://t.co/pJ8WHC6ijH pic.twitter.com/C0S0rM9nwS
BlenderでもShaderが出てくるけど、MagicaVoxelと違って接続とかするので難しい。光り具合だけを定義したshader、変化を表したShaderなどなど。
なんかシェーダーが大量に出てきたので探すのに一苦労。名前が日本語ってだけで検索が使いにくい。。。やっぱ英語の方が良いのかなーメニュー #blender pic.twitter.com/5OZxvW3zS8
— hubgry (@hubgry) March 23, 2021
検索する時には英語の方がわかりやすいから、いっそメニュー表示とかの言語は英語にするのが良さそう。
なんか、、やたらシュールなのができた。
— hubgry (@hubgry) March 24, 2021
スモーク難しいなー。今回もクイック流体から。煙はsurfaceなしでvolumeにプリンシプル設定されると。
動画を見たらdomain heat -5、flow temp0以上で下がる煙ができるってことみたい。#blender
参考https://t.co/roAtjuGTAy pic.twitter.com/bVbTElSaIi
気体っぽいけど、扱いとしては流体だったはず。レンダリングはめっちゃ重い。
この前の煙の方がきれいだった気がしないでもないでもない #blender pic.twitter.com/7L9N5agQtt
— hubgry (@hubgry) March 26, 2021
MagicaVoxelで作ったモデルがインポートできるので、こういうことが簡単にできるの良き。
ゆるキャン△スペシャル3/29も含めて、シーズン2楽しみですねー。そろそろ録画予約もできる時期#blender
— hubgry (@hubgry) March 25, 2021
今日は火の部分:参考https://t.co/EAn6Pmclbg pic.twitter.com/VDPEunhOR4
今度は破壊だ!シミュレーション
物理演算色々あるみたいなので、破壊をば。
演算できるのはぶつかった後の移動部分なので、最初にモデルを割っておく必要があった。あと最初は割れたモデルと割れてないモデルの2つ(1つと割れた大量の方)を全部重ねておく。適当に線を引いたらそれをベースにモデルを分割してくれるshaderか何かがあったはず。
ものが割れるところ
— hubgry (@hubgry) March 21, 2021
参考動画になかったのは元のオブジェクトの消し方。元オブジェクトがないと最初からひび割れ状態なので表示しておき、ぶつかった時にスケールを0にすると良い感じ。 #blender
はどうけん!って言ってる作者さんのものを参考にhttps://t.co/80MtBbSxOL pic.twitter.com/UzdZkc7ybg
物理演算をBlenderでやる時にはどこまでリアルに近づけられるかってところが課題になってるように感じた。だけど下のものみたいに物体の性質によっても変わりそうでどれも本物に見えそうになってくる。学問というのは世界の在り方を分析した結果であって、学問に従った世界が作られているわけでないのであって・・・。
他に2つの角度で試してみた。3が最初に作ったもので当たった付近が細かく砕けるもの。他の2つは違和感出ると予想したけど、不均一な硬さの自然鉱石だったらありそうな気もしてきて現実がわかんなくなってる #blender pic.twitter.com/mB9rkSypcT
— hubgry (@hubgry) March 22, 2021
コピペで量産してたマンションを破壊っ破壊っ破壊ーーっ!!
せっかく作ったマンションがー!!
— hubgry (@hubgry) March 22, 2021
気になるところはあるけれど、今日は3カメまで用意してみた。鉄球の重さを大きくしてもどうしても押し負けちゃう。貫通すれば建物が吹っ飛ぶ勢いになるけど、正面カメラが嬉しくない感じになる #blender pic.twitter.com/uaweoCFOy0
ぶつかった球体の後処理が案外大変。
鉄球をリジッドボディの質量を計算で鉄にしたけど押し負けるからアニメオフにするのを1フレーム後ろにしてみた。もう少しおとなしい予定だったけどやっぱりそうなるか。衝突時じゃなくてほぼ貫通後に物理法則にしたがう形になるからぶつかって1フレーム分は速度そのままなわけで。。。 #blender pic.twitter.com/5Vr4l80hx3
— hubgry (@hubgry) March 23, 2021
お次は布だ!何シミュレーション?
布を使うと圧力とか含めた弾力性のあるシミュレーションができる。
布を調べてたはずが気づいたらシャボン玉みたいのができてた。圧力が使えるのは布だけみたいだけど、よくわかってない。
— hubgry (@hubgry) March 24, 2021
一回目は落ちたときに圧力増やしてジャンプさせてる #blender pic.twitter.com/E88NS4br44
たくさん組み合わせるとこんな感じ。
やっぱりゴムボールみたいなものは物理演算にcloth使うんだろな。collision付ければそれっぽく見える #blender pic.twitter.com/pbHxr88xoX
— hubgry (@hubgry) March 25, 2021
風にはためく旗とかもこの流れで行くんだと思います。あ、フォースフィールドは最初で最後だったかも。
フォースフィールド最初は風。1kgの物体に強さ100でこんなくらい #blender pic.twitter.com/nwoVfLyPra
— hubgry (@hubgry) March 25, 2021
違う意味での頭の使いどころ
前にPHPやってた時に信号が青になったら「あ、trueになった」って頭の中に浮かんだことがあったけど、たぶん同じことを続けていると脳のシナプスあーなってこーなって、思考が洗練というか狭く、鋭くなっていく感じがある。でもBlenderやUnityってそれよりは会話する時みたいにやりたいことに対しての解決策を出すことに似てる気がする。脳の使い方的に発散思考で出てきたアイディアを当てはめて解決できるか確認するって感じかな?
プログラミングって課題となるもののレイヤーによって頭の使うところが違ってる感覚はある。ロジックをゴリゴリ書いてるときは構造体や分岐条件が頭の中にある感じだったけど、実現方法で方針ががらっと変わるような時は質問されて回答したりblender/unityやってる時の感覚
— hubgry (@hubgry) March 21, 2021
こういう感じにね。
レンダリング前は消えてるはずなのに、レンダリングしたら残ってたのは、サイズ0にすれば消せるのか。ほんとアイディア勝負って感じ #blender
— hubgry (@hubgry) March 21, 2021
【Blender 2.8】 オブジェクトを途中で消えたり出現させたりするアニメーションの作成方法 | Explanatory Blogja https://t.co/K90500U6Su
Blenderでもボクセルアート
ブロックではないのかもしれないけど、ブロックベースの世界を作るのにBlenderを使うって方法もあるみたい。動画見ると結構サクサク作ってた。(同じようにできるとは言ってない)
すごい、blenderとは思えない作成速度とブロック感
— hubgry (@hubgry) March 21, 2021
"【blender初心者】10分でモデリング!ビルをつくろう【Blender2.8】【3DCG】" https://t.co/skdsU3aEsN
自分は物理演算メインでBlender使ってたけど、モデリングツールとして普通に名前があがるものだから、ありありのありなんだよね。
物理演算って見続けちゃう
スイッチがあれば押しちゃう人なので、小学校の時は非常ベルのスイッチを見ると欲望との戦いでした。でも物理演算って見続けちゃう魅力があるよね。物理演算のあるゲームも触ってみたくなるし。
Magicavoxelの時は出来上がりが静止画だけだったからパット見て次!ってyoutube見に行けたけど、blenderだと動画だし物理演算だからついつい見ちゃうの危険。情報収集ができずまったり時間が流れやすい。
— hubgry (@hubgry) March 18, 2021
見方としては、リアルに見えるかな?もうちょっと変えてもう一回、やっぱりあっちの数字をいじって、、、ってな具合なもんさ!
レンダリングとシミュレーション結果って得るのに時間がかかるわけで、「地球に隕石がぶつかるのは24時間後ですっ!」って映画とかのシミュレーションってリアルタイムかわからないけど、スパコンすっげーなってなるわけですよ。枠線だけしかないのは計算に時間がかかるから。
だけど枠線だけのシミュレーションってどこまでリアルなの?って疑問はある。荒くすれば計算は速いけど、コップから液体だだ洩れだったし。
プロジェクトPLATEAU始動っ!!
なんかBlender触ってた時にちょうど公開されたプロジェクトPLATEAU。国土交通省が災害対策などにも使えるように都市の3Dモデルを公開するっていう素晴らしい話です。
新宿南口の立体的な空間が好きなのでこれが見たかった。
お久しぶり新宿。FBXはオブジェクトというかメッシュが大量で重いけどようやくレンダリングできた。#blender #PLATEAUhttps://t.co/zad8jtXCrr pic.twitter.com/Iu3x1vbNrB
— hubgry (@hubgry) March 28, 2021
モデルの配置場所やテクスチャを探したり、モデルというかメッシュ(面)の組み合わせだったりする。レンダリングには時間がかかるからメッシュをつなげたいけど結構大変だなーって試行錯誤。
サイズ感がよくわかんないけど、デフォルトでimportすると/で注視しないと見つけられないくらい小さかった。23区モデルだからすべて読み込んで中央になるように位置づけされてるのかな。新宿は結構左の方にあった #blender #PLATEAU pic.twitter.com/c2gDsjZHkk
— hubgry (@hubgry) March 28, 2021
やっっぱりここでもこういう画面が楽しかったりする。
GoogleMapやGoogleEarthを始めて使った時のような感覚で楽しい #blender #PLATEAU pic.twitter.com/y7Z2H7cLAB
— hubgry (@hubgry) March 28, 2021
モデルデータはどうしてる?
物理演算だけをやりたいってなってもモデルが必要になるけど、自分の場合はMagicaVoxelで作ったものがそのままインポートできたので結構楽だった。ちなみに原神ではキャラクターのモデルデータ公開してまっせ。自分のツイートは無かったので恐らくテクスチャをセットするあたりでわからなくなったのかな。中国語ファイルだったか文字化けだったかあったと思うし。
その後は?
ショートムービーみたいなのができたりすれば楽しそうだったからマルチカメラは破壊のところで使ってみた。ただ、シーンの切り替えとかするならもっといくつも作る必要があるから大変そうだけどね。
マルチカメラの使い方 #blender
— hubgry (@hubgry) March 22, 2021
Blender: 複数のカメラを切り替えて使用する方法 : ReflectOrange https://t.co/8bqRkYCeNa
写真で素晴らしい一瞬を切り取るのは大変ということを聞いたことがあるけど、MagicaVoxelでは数枚撮ってお気に入りの1枚を見つける感じだった。Blenderでは動画にしてみるけど、違和感があったり納得いかないと後日また編集したりしてたので作ったものの数はそこまで多くなかったかも。
今回もこんな感じで学んだメモを良いして、それとは別にやりたいことメモを用意してまた2つのメモで学習してた感じ。
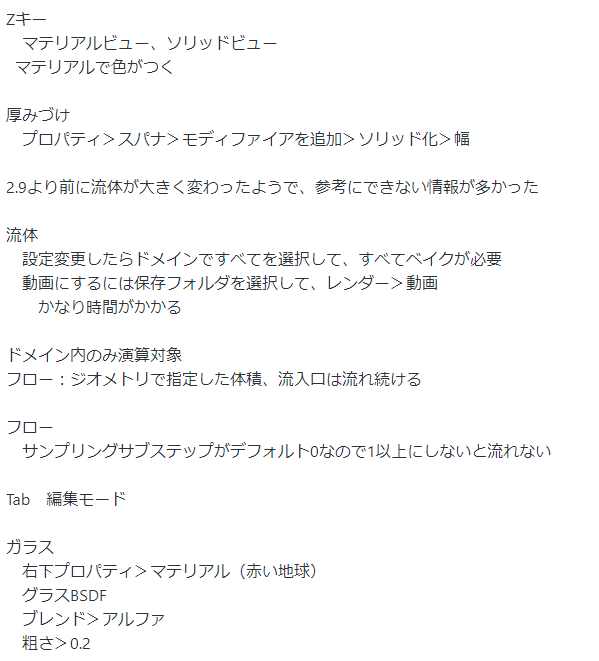
やっぱり何かを作るのってコンテンツ消費というか、他の誰かの作ったものを楽しむのとはまたちょっと違った楽しさがあるよね。
今後また作るかわかんないけど、学びながらのツイートとか参考ページのツイートなどはこちらで見られます。
https://twitter.com/search?q=from%3Ahubgry%20blender&src=typed_query&f=live
シミュレーションはいくらやってもシミュレーションだけど、世界を作ってる感を味わえちゃう。
んじゃ、ここまで読んでシミュレーションできたと思うので、次はあなたが世界をかき混ぜてくださいBlenderで。
