
【DAY 16】自分にとって思い入れのある映画 「ビッグ・フィッシュ」
DAY 16
a film that is personal to you.
自分にとって思い入れのある映画
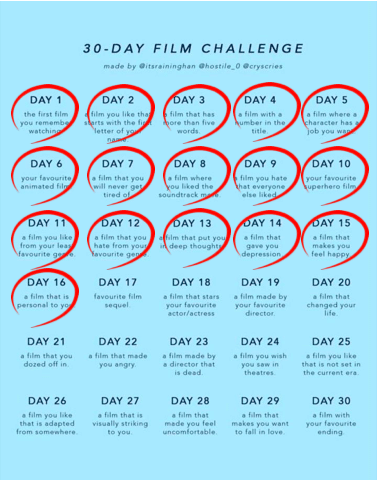
「ビッグ・フィッシュ」(2003)
ティム・バートン監督
ユアン・マクレガー、ビリー・クラダップ、アルバート・フィニー、ジェシカ・ラング、アリソン・ローマン、マリオン・コティヤール、ヘレナ・ボナム=カーター、ダニー・デヴィート
ウィル(ビリー・クラダップ)は、父・エドワード(アルバート・フィニー)が病で倒れたとの連絡を受けて、妻のジョセフィーン(マリオン・コティヤール)と一緒に帰省。父は荒唐無稽な自らの経験談を話すのが好きで、小さな頃のウィルはそれが好きだったけれど、成長していくにつれて、作り話で周りを煙に巻く姿に反発するようになった。しかし、父は病床でもおかまいなく、いつもの話を始めた。
若い頃のエドワード(ユアン・マクレガー)は、18歳になったときにはすでに街の中でも有力人物になっていた。ある日、上背が5mはある巨人が現れて街を荒らし始める。そこで彼は、街を救うために、巨人を引き連れて旅に出ることにした。その道中、「スペクター」という、全員が裸足で住むユートピアのような村に滞在。そして村を去った後は、今度はサーカス団で働いた。そこで若い頃のサンドラ(アリソン・ローマン)に一目惚れして結婚。その後、戦地へ行って勇敢に戦い、美人のシャムの双生児を味方につけて、見事に敵国から脱出して家へ帰ってきた。戦後はセールスマンとして働いていたが、スペクターで出会った詩人のノザー(スティーヴ・ブシェミ)と再会、彼のおかげで大金持ちになったということで、多額の謝礼をもらった。そんな話だった。
「全部が作り話じゃないのよ」と母・サンドラ(ジェシカ・ラング)がぽつりと言う。ウィルは父の部屋を整理しているときに気になる書類を発見。気になった彼は、証書に署名があったジェニー(ヘレナ・ボナム=カーター)の家を訪ねてみることにする。彼女は父の武勇伝の続きを話してくれた。エドワードはある日のセールスの仕事中に、偶然もういちどスペクターに立ち寄ったけれど、そこは不況のあおりを受け、かつての天国のような村ではなくなっていた。そこで彼は、各方面から資金を集めて村の再建にとりかかったそうだ。父親がたくさんの人たちから尊敬され感謝されていることを実感し始め、ウィルの心のわだかまりが溶けはじめる。
+++
大学生のとき、勉強も就活もせず、無気力に映画ばかり観ていたときに、試写会で観たんじゃなかったかな、ふつうに劇場に行ったんだっけ、とにかく劇場の大きなスクリーンで観た覚えがある。
ティム・バートンは、原画展が催されるくらいに日本でも人気の映画監督。いわゆる「ダークファンタジー」の名手で、「フランケンウィニー」(1984)「ビートルジュース」(1988)「シザーハンズ」(1990)など、世界観はおどろおどろしいけれど、語り口は暖かくてくすくす笑える、彼にしかできない独特なスタイルの映画を多数発表し、頭角を表した。
その後も、「マーズ・アタック!」(1996)「スリーピー・ホロウ」(1999)「スウィーニー・トッド フリート街の悪魔の理髪師」(2007)「ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち」(2016)などなど、粘り強く同じ系統の映画を作り続けている。
また一方で、「バットマン」(1989)「PLANET OF THE APES/猿の惑星」(2001)「ダンボ」(2019)のように、企画映画を担当しても、独自性を織り交ぜながら、きちんと丸く収めたエンタメにすることもできる。
+++
彼の映画は、どの作品でも、「異形/異質な者の迫害」というテーマが、背骨のように支えている。「フランケンウィニー」のスパーキーに始まり、「バットマン」のジョーカーもペンギンも。「アリス・イン・ワンダーランド」(2010)ではマッドハンターや赤の女王、「ダークシャドウ」(2012)のバーナバスやヴィッキーもそう。そして最新作がまさに耳の大きな奇形の象、ダンボである。そこにはおそらく、子供の頃から怪奇映画ばかり観ていて友達がいなかったバートン自身のトラウマがあるわけで、それがユニークな強みとなっている。
+++
しかし、「ビッグ・フィッシュ」は、彼の映画の中ではちょっと異質な作品である。この映画の構造は、「現実パート」と「ファンタジーパート」にきっちり分かれる。そして、その「現実パート」では、これまでの作品で行ってきた、子供のようにひたすらファンタジーのイメージの中で遊ぶ「おふざけ」をいっさい封印して、シリアスでリアリティのある演出に徹する。
+++
後半、ウィルと父の断絶は少しずつ解消していく。父親の作り話はくだらない嘘ばっかりなのかもしれない。でも、人生の後半はセールスマンとして飛び回っていた父は、複雑で姑息な現実世界で毎日あくせく働いても、家族にいっさい愚痴は言わず、その代わりに虚構の世界を語って楽しませてくれていたのだ。
ついに危篤になった父に「俺が死ぬときの話をお前が作ってくれよ」と頼まれるウィルは、初めて自分のへたくそな物語を語る。「病院を抜け出した父さんは、派手なカーチェイスをしながら、あの川に行くんだよ。そしたらそこには、巨人も、サーカス団も、双生児も、みんながいるんだ。みんな、ちっとも悲しんじゃいない、笑ってる。全員が笑顔で見送る中、川へ入った父さんはでかい魚になって泳いで行くんだ」
このウィルの話も、ちゃんとファンタジーパートで映像化する。この、それまでのキャラクターが全員登場する、「みんないるじゃん」というシーンは、感涙必須だ。
+++
しかし、ここで最後にもうひとつ仕掛けがある。そして、これがこの映画のキモである。
エドワードの実際の葬儀が行われる。ウィルは、参列者たちを見て、あることに気づく。5mとは言わないけれど、優に2mを超えた巨人がいる・・。接合してはいないけど、美人の双子もいるし、サーカスの団員もいる、あれは詩人のノザーみたいだ・・。つまり、父さんの話は、「嘘だったけど、それはそれで僕らを幸せにしてくれたからよかった」のじゃなくて、「ほんとに、嘘じゃなかった」のだ。ただちょっとだけ盛ってただけだ。
このシーンは、ウィルが創作した「みんないるじゃん」の物語が、現実パートにはらみ出てきたみたいに見えてちょっとした眩暈に襲われ、物語が持つ予言性みたいなものを感じる。
そしてさらに、その「盛り具合」に、少々複雑な気持ちになる。直前のシーンがファンタジーパートの葬儀だったので、キャラクターたちのビフォア・アフターが強調されて「じっさいはこんなもんなんだよ」ということがわかる。それが、暖かいけど寂しい、特別な気持ちにさせてくれる。
